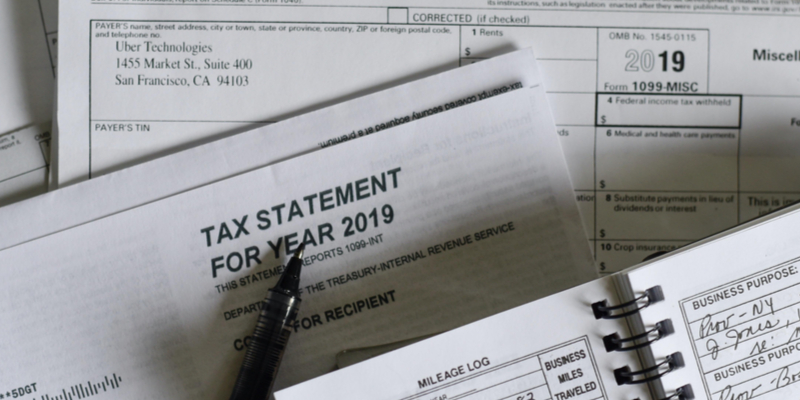書いてあること
- 主な読者:これから個人事業を起業しようとする人や不動産所得、山林所得がある人
- 課題:確定申告には、青色申告と白色申告とがあるが違いが分からない
- 解決策:税務署への届出や帳簿の記帳などを義務付ける代わりに、各種特典が与えられる
1 確定申告は色によって違う? 青色と白色の違い
所得税の確定申告には「青色申告」と「白色申告」とがあります。
- 青色申告:日々の取引を複式簿記で記録する代わりに、さまざまな特典が受けられる
- 白色申告:簡便な帳簿記録でよい代わりに、青色申告で受けられるような特典がない
近年はクラウド型の会計システムの導入が進み、会計の知識がなくても簡単に青色申告に必要な書類が作れるようになったことから、青色申告の壁はほとんどありません。そこで、この記事では、青色申告制度を受けるための手続きや特典を説明します。
なお、青色申告ができるのは、不動産所得、事業所得または山林所得が生ずる業務を行っていて、納税地の所轄税務署長の承認を受けた人です。個人事業主はもちろんですが、副収入として不動産所得のある給与所得者なども青色申告ができます。
2 青色申告の手続き
青色申告をしたい人(今まで白色申告だった事業者や、1月1~15日の間に開業した事業者)は、青色申告をしたい年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出します。例えば、2024年分の所得税を青色申告したいなら、2024年3月15日が提出期限となります。ただし、その年の1月16日以後の新規開業の場合は開業日から2カ月以内に提出すれば大丈夫です。
なお、申請書の提出後に特段の承認通知はなく、申請却下の連絡がなければ受理されたことになります。
3 青色申告者がすること
1)記帳の義務
青色申告をする人は、帳簿書類を備え付け、これに不動産所得、事業所得および山林所得の金額に係る取引を記録し、保存します。この記帳は原則として、複式簿記で行う必要があります。特例として、損益計算書が作成できる程度に簡略された簡易帳簿(現金出納帳や固定資産台帳のみなど)による記帳も認められます。しかし、青色申告の特典の1つである青色申告特別控除額が10万円に減額されます(複式簿記の場合は最高65万円)。なお、山林所得は10万円の控除のみです。
2)添付の義務
青色申告書には、貸借対照表、損益計算書その他不動産所得、事業所得または山林所得の金額の計算に関する明細書を添付しなければなりません。ただし、簡易帳簿による場合は、貸借対照表の添付は必要ありません。
4 青色申告の代表的な特典
1)青色申告特別控除
1.65万円の青色申告特別控除
次の要件を満たす青色申告者は、不動産所得または事業所得の金額の計算上、合計65万円を控除できます。この控除は、不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。なお、不動産所得または事業所得の金額が65万円より少ない場合は、原則として、その金額が限度となります。
イ.不動産所得に係る業務を事業的規模で行っていること、または事業所得を生ずべき事業を行っていること
ロ.不動産所得、事業所得に係る一切の取引の内容を詳細に帳簿に記録していること
ハ.期限内に確定申告書を提出し、かつ、貸借対照表、損益計算書その他不動産所得または事業所得の金額の計算に関する明細書を添付していること
ニ.青色申告書と決算書を、提出期限までにe-Taxにより提出していること、または仕訳帳・総勘定元帳を電子帳簿保存(税務署長へ届出が必要)していること
不動産所得を生ずべき業務については、貸付不動産が、アパートやマンションならおおむね10室以上、貸家ならおおむね5棟以上であれば事業的規模とされます。
なお、上記ニ.の要件のみを満たしていない場合の控除額は55万円です。
2.10万円の青色申告特別控除
簡易帳簿で記帳を行うなど、上記1.の要件を満たさない青色申告者は、不動産所得、事業所得または山林所得の金額の計算上、合計10万円を控除できます。この控除は、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額から順次控除します。なお、不動産所得、事業所得または山林所得の金額が10万円より少ない場合は、原則として、その金額が限度となります。
2)青色事業専従者給与額の必要経費算入
不動産所得、事業所得または山林所得の金額の計算上、青色事業専従者(事業に携わっている家族など)に支払った給与や賞与を必要経費に算入できます(退職金は算入できません)。給与を必要経費に算入すると所得が減り、納税額も減ります。
3)純損失の繰越控除・繰戻還付
その年の事業所得などが赤字(純損失)となった場合に、翌年以降3年間の繰越控除(翌年以降3年間の黒字と相殺)またはその前年への繰戻還付(前年の黒字のうち、その年の損失分の還付を受けられる)の請求ができます。
5 青色事業専従者給与額の必要経費算入の注意点
1)青色事業専従者とは
青色事業専従者とは、青色申告者と同一の生計で暮らしている15歳以上の親族で、一定期間、専ら青色申告者が営む事業に携わる人です。青色事業専従者は、支給額をその年分の給与所得に係る収入金額とされます。そのため、支給時には所得税の源泉徴収が必要です(支給額が月額8万8000円以上の場合)。
2)必要な手続き
この規定の適用を受ける場合、その年の3月15日まで(その年の1月16日以降に事業を開始した場合、または新たに青色事業専従者を有することとなった場合は、その開始した日あるいはその有することとなった日から2カ月以内)に「青色事業専従者給与に関する届出書」を、税務署に提出します。
また、その給与の金額の基準を変更する場合や新たに青色事業専従者が加わった場合は、変更届出書を遅滞なく提出しなければなりません。
3)専ら従事するかどうかの判定
まず、学生や他に職業のある人は、原則として専従者として認められません。その上で、その事業に専ら従事するかどうかの判定は、その年を通じて事業に従事している期間が6カ月を超えるか否かで行います。しかし、開業や廃業などでその年を通じて事業が営まれなかった場合や、専従者の死亡、長期にわたる病気、婚姻などによりその年を通じてその事業に従事することができなかった場合は、従事可能期間の2分の1を超える期間を従事すれば大丈夫です。
例えば、9月初めに開業した場合の従事可能期間は9~12月の4カ月なので、2カ月超をその事業に従事すればよいことになります。
以上(2024年12月更新)
(監修 エスコート税理士法人 税理士 林孝行)
pj30026
画像:unsplash