2024年11月11日、公益社団法人徳島県物産協会を発展的に改組して、「公益社団法人徳島県産業国際化支援機構」(以下「機構」)を立ち上げ、12月16日から本格稼働を始めました。機構はいわゆる「地域商社」で、会長には、葉っぱビジネスで知られる株式会社いろどりの横石知二さんが就任しています。その他のメンバーも市場の代表、県庁や金融機関からの出向者、モデルなどそうそうたる顔ぶれです。
機構は徳島県庁にオフィスを構え、「オール徳島」を旗印に、県産品を、県外はもちろん、海外にも売り出すための仕掛けづくり、場面づくりを行っています。
今回、「とくぎんサクセスクラブnavi(とくさくnavi)」では、横石さんへの単独インタビューを行い、ワクワクが止まらないこれからの徳島について、お話を伺いました。
後半には、徳島大正銀行から機構に出向している市川諭さんのインタビューも掲載しています。
お二人のインタビューの内容をまとめた動画は、こちらからご覧いただけます!
(下の画像をクリックしていただくと、YouTubeに遷移します)
―機構の概要や狙いについてお聞かせください。
これまでの組織は、縦割りになってしまいがちで、一体的・組織的に活動できていないこともありました。縦割りだと連携が難しく、徳島県内の限られた生産品を取り合ってしまうことになります。しかも、これだけ人口が減っている中、このままでは立ちいかなくなってしまいます。
ですから、県外や海外に打って出る必要があるのです。これを個人ごと、あるいは機能ごとに縦割りで進めるのは難しいですから、今回、「地域商社」という枠組みをつくり、県産品の企画やプロモーションを一体的に行うことにしました。
まさに「オール徳島」での取り組みです!

―「オール徳島」とはすてきなフレーズですね
全国に地域商社は多数ありますが、私たち機構の特徴は、「民間と行政が一体となったプロモーションを強力に展開する」ことです。バイヤー同士の連携も進めています。
今、北海道などの地域に対しても県産品をアピールしているのですが、そのときに、例えば青果など単品を売り込むだけでなく、鮮魚や肉、加工品なども幅広く売っていくことが必要です。ただ、これまではそうした事例はありませんでした。青果のバイヤー、鮮魚のバイヤーといったように担当が違うので、自分が取り扱っていない商品の販売には積極的ではないのです。そこを改善し、「オール徳島」として、青果、鮮魚、肉、加工品などの垣根なく、紹介し合えるようにしています。うまくいけば、【億単位の売上】も狙えるわけで、こうした動きは既に始まっています。
加えて、機構では文化や観光も巻き込んで、さらに徳島を盛り上げていくことが戦略の柱になっています。官民が一体となって取り組む、“「オール徳島」の渦巻き戦略”です。
―「今こそチャンス」とおっしゃっていますね。
最近、「徳島の県産品が欲しい」という問い合わせが増えていて、「潮目が変わってきた」と感じます。先日も東京の大手スーパーの方が徳島に来て、「徳島に、こんなに魅力的な商品がたくさんあるとは知りませんでした」と言っていました。問い合わせは日本だけではなく海外からも来ており、今、追い風が吹いています。

徳島には個性的な人が多く、そうした人にはこだわりがあるので、他人とは違う素晴らしいものを作ってくれるのです。ただ、売ることは苦手です。「個性的でまとまりにくいが、ものはいい。だけど売るのは苦手」というのが徳島の特徴です。
このような状況を機構が取りまとめていきます。「オール徳島」として魅力的な県産品を集約、発信していくことで、大いに可能性が広がっていきます。生産の現場に、「いよいよ、あなたの出番が来ましたよ!」と巻き込んでいくことで、活気も出てきています。
ですから、まさに「今こそ、世界に打って(売って)出なければならない」ということなのです。
これまで、徳島は観光が弱く、外の目から見て商品をブラッシュアップする機会がありませんでした。そこで、文化や観光も巻き込んで徳島ブランドをブラッシュアップして、付加価値を高めていきます。これこそが売るための「舞台」になると考えています。
―「オール徳島」をまとめる人材が重要になってきますね
はい、まさに人材が大切です。かつて、いろどりの事業で知り合ったとても有名な料理人が、「商品を作ることよりも、人を磨きなさい」と教えてくれましたが、機構にも通じるところがあります。
今、いろどりでやってきたような、「気を育てる」ことも始めています。気を育てるというのは、メンバーとの間に信頼関係を築き、「やる気を育てる」ということです。相手と接し、「この人ならこういうことができる」と一緒に取り組み、それができたら「もっと、ここまでできる」と、また一緒に取り組む。こうして丁寧に経験を積み重ねながら一緒に成長していくことが、私は好きです。できることが増え、他人から認めてもらえたら誰だってうれしいことです。自分に役割があるということは幸せなのだと思います。
ただ、少し迷っています。
私のこのやり方は時間がかかります。タイミングによっては、各分野のプロフェッショナルを集め、戦略を立てて一気呵成(かせい)に取り組んだほうがスピーディーで良いこともあります。
今は、しっかりと状況を見極めながら、一つ一つ積み上げていくことと、一気に組織をつくってアクセルを踏むことのバランスを取っています。
こうして人が育ち、取り組みが大きくなって盛り上がっていく中で、若者が「面白そうだ! 自分もやってみよう!!」と、当事者になってチャレンジしてくれたらうれしいです。
―具体的な取り組みでは、「動物的なひらめき」を大切にしていると伺いました。
用意周到に段取りをしても、想定通りにはいかないことはよくあります。ですから、私の場合、どちらかというと動物的なひらめきを大切にしています。

例えば、東京でマルシェに出展した後、徳島に帰る深夜バスの中でもいろいろと考えています。「どれくらいの人数が乗っているのか、どの年代の人が多いのか、そもそもなぜこのバスに乗っているのか?」といったことを考えながら、世の中の動きを捉え、ビジネスのヒントを探しています。
いろどりの始まりも、たまたま立ち寄った大阪・難波の『がんこ寿司』で、あるお客さんがつまもののモミジを大切そうに、きれいなハンカチの上に置いて眺めている姿を見た瞬間でした。「葉っぱが売れる!」とは、まさに動物的なひらめきで、そのアイデアにとても興奮しました。『がんこ寿司』には、1000万人のお客さまが来たそうですが、その中で葉っぱを売ろうと思ったのは私だけかもしれないですから、1000万分の1のひらめきだったわけです。
きちんと戦略を立て、しかも動物的なひらめきは逃さずに、県産品を販売する舞台を整えていきます。
―他の組織と連携する計画はありますか?
そうですね。それぞれの組織には良さがあって、その良さがどのように相乗効果を発揮するかということでしょうね。成功する連携というのは、それぞれの組織が「成長していくぞ!」と上を向いていないとダメで、一方が上を目指して成長していても、もう一方がそれについてこなかったり、マイナスだったりすると、いい連携にはなりません。
どのような組織と連携するかはこれからの課題の1つですが、成長を目指していく中で、お互いにとって良い連携先と巡り合えたらよいと思います。
―機構の目指す姿についてお聞かせください
まず売上をしっかり伸ばすことです。数字が全く上がらないのは問題ですから。
同時に「人」です。想いのある人をどれだけ集められるかということですが、そのためには、機構に関わる仕事を楽しいな、面白いなと思ってもらえるようにしなければなりません。「良かった、楽しかった、面白かった、うれしかった」。こんな言葉が次々と生まれてくるようにしたいですね。
いわゆる大手商社と違って、私たちは地域商社ですから、売上はもちろんですが、やはり徳島県の皆さまや、そこに関わってくださる方の幸せや喜びを追求していく存在でなければならないと思っています。
その結果、売上が5億円、10億円、20億円、100億円となっていけたらよいです。今は、それが実現可能なタイミングだと思います!
——–
横石さん、単独インタビューにご対応いただき、誠にありがとうございました。機構を中心に動き出す徳島の未来がとても楽しみになりました。
さて、このような横石さんを支える、頼れる機構のメンバーの1人が、徳島大正銀行から出向してきた市川さんです。機構の現状について、メンバーの立場からお話をお伺いしました。ここからは、市川さんへのインタビューをご紹介します。
―日々、どのような活動をされているのですか?
機構は2024年12月16日から本格稼働したばかりですが、改組前の徳島県物産協会から引き継いだ案件をこなしつつ、どのように“「オール徳島」の渦巻き戦略”として展開していくかを試行錯誤しています。

打ち出しやすいのは、ストーリー性がある商品です。例えば、「農薬を使っていない」などのこだわりのある商品は打ち出しやすいです。海外視察で発見した魅力的な商品が、徳島県にあるかを探すというアプローチもします。とにかく、「これは売れるかもしれない」という商品を、日々探しています。
―新しい発見はありましたか?
頻繁に現場を訪れて生産者の話を聞いたり、各市町村の役場に行ったりして情報収集をしていますが、「徳島に住んでいるからこそ気付かないことがある」と感じます。
例えば、「藍(あい)」です。徳島の人から見ると「藍」は身近な工芸品なのですが、移住してきた方は、私たちが気付かない付加価値を付けてくれていて、美術品っぽくしたり、企業ロゴを藍染めで作ったりしています。
この他にも、阿南の竹など可能性のある商材を発見しています。阿南の竹は、住民の高齢化で竹が放置されている状況なので、何とか商品化できないかアイデアを検討しています。
―今後の意気込みをお聞かせください
いわゆる地域商社には、「企画、生産、流通、販売」などの機能がありますが、機構ではこれらを一貫してサポートしていきたいと考えています。そのために、他の機関との連携もしていく必要があると思います。
横石会長はものすごい行動力のある人で、様々な情報が集まってきます。その背中を見て刺激を受け、自分の背中を押してもらいつつ活動しています。
これまでの銀行員として養ってきたノウハウも活かしつつ、「オール徳島」で徳島の魅力を広く伝えていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
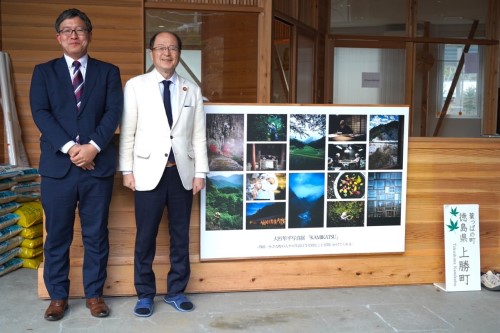
(聞き手 日本情報マート 代表取締役 松田泰敏)
ts20250407


