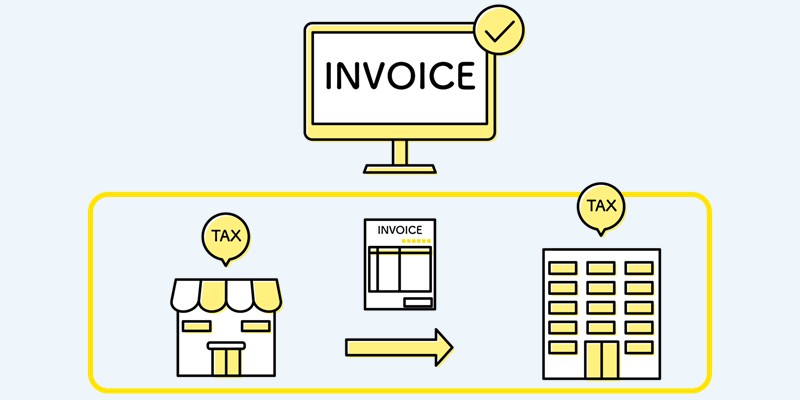1 なぜ今、インボイス制度の2026年問題を知るべきなのか
2026年10月に、インボイス制度が大きな転換期を迎えることをご存じでしょうか。具体的には、
1.仕入先に免税事業者などがある会社が影響を受ける
免税事業者などからの仕入れに係る経過措置(以下「インボイス経過措置」)の控除率が縮小
2.インボイス制度の導入を機に、課税事業者となった小規模事業者が影響を受ける
免税事業者が課税事業者を選択した場合の2割特例(以下「インボイス2割特例」)の廃止
の2つです。適切な準備を怠ると、消費税負担が増えるだけでなく、既存の取引関係にも変化が生じることになりかねません。今のうちから、このインボイス制度の2026年問題のポイントを知り、対策を講じておきましょう。
2 インボイス経過措置による控除率の縮小について
1)内容は?
インボイス制度の下では、適格請求書発行事業者として登録した事業者しか「適格請求書(インボイス)」を発行できず、買い手側(課税事業者)はインボイスを保存することで、仕入税額控除を受けられます。つまり、インボイスが発行できない免税事業者(あるいは適格請求書発行事業者の登録をしていない事業者)からの仕入れについては、原則控除が受けられません。
しかし、制度導入直後の急激な税負担の増加などの影響を避けるため、導入後の数年間は、インボイスが発行できない事業者からの仕入れでも、一定額の控除を受けられるインボイス経過措置が設けられました。一定額の控除率は段階的に縮小され、最終的にはなくなります。
- 2023年10月1日〜2026年9月30日:仕入れに係る消費税額の80%まで控除可
- 2026年10月1日〜2029年9月30日:仕入れに係る消費税額の50%まで控除可
- 2029年10月1日~:控除不可
この経過措置による控除率の第一段階の縮小(80%→50%)が、2026年10月に到来します。
2)その影響は?
1.消費税負担の増加
免税事業者から商品やサービスを仕入れている場合、これまで80%控除できていた消費税が、2026年10月からは50%しか控除できなくなります。つまり、控除できない30%分がそのまま消費税の納税負担として上乗せされるのです。免税事業者との取引が多いほど、納税額の増加は顕著になります。
納税額の増加は、会社の資金繰りに直接影響します。特に、利益率の低い事業や、運転資金がタイトな企業にとっては、予期せぬ支出増が経営を圧迫する可能性があります。
2.仕入れコストの増加と価格交渉の必要性
仕入税額控除が縮小されるということは、免税事業者からの仕入れコストは当然上がります。そのため、こうしたコスト増を加味した価格交渉や取引先の選定基準の見直しが必要になります。また、現時点では2029年10月をもって、この経過措置が終わることになっているので、第一段階(控除率の縮小)だけでなく、経過措置の完全終了も視野に入れることが大切です。
3)取るべき対策は?
1.消費税の納税シミュレーションをして、資金繰りへの影響を把握
2026年10月以降の消費税の納税額がどう変化するか、シミュレーションしましょう。現在の取引状況(免税事業者からの仕入額の見込みや前年度取引実績値など)に基づいて、経過措置の控除率が50%になった場合(余裕があれば、2029年の経過措置の完全終了の場合も併せて)の納税額を計算し、資金繰りへの影響を把握しましょう。
2.取引先との具体的な協議と、価格・取引条件の再検討
まずは、免税事業者の取引先に対し、適格請求書発行事業者への登録を促すことを検討しましょう。もし取引先が登録しない選択をした場合には、価格の見直しや取引条件の再交渉が必要になる可能性があります。ただし、その際は、
独占禁止法や下請法に違反しないよう細心の注意が必要
です。 例えば、一方的に値引きを要求したり、取引価格を据え置いたまま消費税分を負担させたりすることは、優越的地位の濫用とみなされるリスクがあります。交渉担当者は、取引先との良好な関係を維持しつつ、デリケートな交渉を誠実かつ丁寧に、そして法的なリスクを理解した上で進める必要があります。
3 インボイス2割特例の廃止について
1)内容は?
インボイス2割特例とは、免税事業者がインボイス制度の導入を機に、課税事業者を選択した場合、
納税額を、売上に係る消費税(仮受消費税)の2割とする制度
です。この特例を適用すると、売上に係る消費税額の20%だけを納税すればよいことになります。つまり、80%の消費税額が免除される計算です。例えば、売上に係る消費税が50万円であれば、納税額は10万円で済みます。この特例は、事前の届け出が不要で、複雑な消費税の納税計算の簡便さも特徴です。
この制度を適用できるのは、2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する課税期間です。最短で影響が出るのは課税期間の開始日を10月1日としている会社(事業 年度を10月~翌年9月としている会社など)です。この場合、2026年10月1日以降の取引について、特例を適用できなくなり、通常の課税事業者と同様の処理が必要になります。
2)その影響は?
1.消費税負担の大幅増、キャッシュフローの悪化、利益率の低下
インボイス2割特例の廃止により、これまで売上に係る消費税額の20%で済んでいた納税が、通常の計算方法に戻ります。納税額が大幅に増える可能性があり、特に仕入れが少ない事業や、これまで消費税を価格に含んでいながら納税していなかった事業では、影響が大きくなります 。
納税額の増加は、手元の資金(キャッシュフロー)を直接圧迫します。これまで免税事業者だった会社は、消費税の納税を考慮した資金繰り計画を新たに立てる必要が出てきますし、また価格に含んでいた消費税相当額を納税に回すことになり、実質的な利益率が低下します。
2.経理業務の複雑化
インボイス2割特例では、売上に係る消費税額に20%を掛けるだけで消費税の計算が済みましたが、廃止後は、
売上に係る消費税額から仕入にかかる消費税額を差し引く「原則課税」または、売上に係る消費税額に一定割合を乗じて計算する「簡易課税制度」
で計算しなければなりません。特に原則課税の場合は、仕入取引一つ一つのインボイスの保存、税率ごとの区分経理など経理業務が複雑化し、小規模事業者にとっては大きな負担となります。
3)取るべき対策は?
1.原価管理の徹底と価格戦略の見直し
消費税の負担が増える分、まずは仕入れや経費などのコストを見直して、削減できるところがないか確認しましょう。また、商品やサービスの価格に消費税の負担を上乗せする「価格の見直し」も大切な対応の1つです。 その際は、周りの競合や市場の動きにも注意しながら、自社の商品やサービスの魅力を保てるように、無理のない価格の付け方を考えることが大切です。
2.会計ソフト・請求書発行システムの導入・活用
インボイス2割特例廃止後の複雑な消費税計算や、インボイスの保存・管理には、会計ソフトや請求書発行システムの導入が不可欠といっても過言ではありません。これらのシステムは、請求書の作成・発行、受領したインボイスの内容チェック、税率ごとの区分経理、消費税の自動計算などを効率化し、経理業務の負担を大幅に軽減します。なお、インボイス制度に対応したシステムを導入する際は、IT導入補助金(インボイス枠)の申請も併せて検討するようにしましょう。
以上(2025年9月作成)
(監修 税理士 石田和也)
pj30226
画像:TKM-Adobe Stock