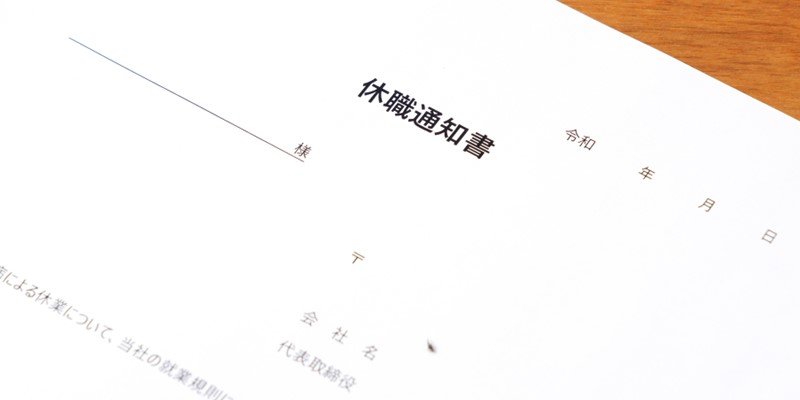目次
1 治療と仕事の両立支援が努力義務化! 休職対策は大丈夫?
社員が「休職(私傷病休職)」するのは、仕事以外の理由でケガをしたり、病気になったりしたことによって欠勤し、その欠勤が一定期間以上に及んだ場合です。
休職制度は、労働基準法や労働契約法などの法律で規制されているわけではないため、休職期間や復職の可否などをめぐってトラブルが生じます。
こうしたトラブルを避けるためには、就業規則に、
- 休職の対象
- 休職命令の発令のタイミング
- 休職期間
- 休職期間中の賃金
- 休職期間中の勤続年数の算定
- 復職の可否の判断
の6つについて定めることが非常に有益です。
2026年4月からは、
治療と仕事の両立を促進するために必要な措置を講じる努力義務が会社に課せられる(詳細は指針で定められる予定)
ことになっており、今後こうした取り組みはますます重要になってきます。
この記事では、私傷病休職を前提に、上記の6点につき、どのような点がポイントになるのか、それぞれ具体的に確認していきます。
2 休職の対象
休職制度は、社員の長期雇用を前提とするため、
適用対象は契約期間に定めのない正社員(試用期間中の社員は除く)に限定
されていることが多いですが、
短時間労働者(パートタイマー)であっても無期雇用の場合は、正社員と同様、休職制度を適用
しなければ、正社員との間で不合理な待遇差を設けるものとして、パートタイム・有期雇用労働法に違反する恐れがあります。
一方、有期雇用の場合は、その契約期間が長期間に及ぶものでなければ、適用対象にしなくても、正社員との間で不合理な待遇差を設けるものではないと考えられますが、契約期間の満了までという条件で休職を認めるケースもあります。
最近の同一労働同一賃金に関する裁判例の傾向として、
長期間雇用されている短時間労働者(パートタイマー)や有期雇用労働者に関しては、正社員と同じく休職制度の適用対象としなければ、待遇差が不合理であると判断される
可能性もあるので、休職の適用対象については、慎重に検討する必要があります。
3 休職命令の発令のタイミング
一般に、休職命令は、
- 欠勤が一定期間(1カ月など)続き、その後も療養のため働けない場合
- その他休職を命じる必要があると会社が認めた場合
に発令されます。
1.の場合は、事前に社員から主治医の診断書を提出してもらうなどして、休職が必要か否かを判断した上で、休職命令の発令します。主治医の診断書だけでは不十分な場合には、産業医などにも意見を聴くことが適切です。
2.の場合は、主に早期に社員を休職させなければならない事情がある場合、例えば、重大な傷病等に罹患している場合などが想定されます。
休職期間の起算点をめぐって、社員とトラブルにならないよう、
いつ休職命令を発令したかは、書面やメールなどで必ず記録に残す
ことが重要です。
なお、休職規定の中には、「休職事由が生じた場合には休職とする」といった規定、つまり休職事由が発生した場合には、休職命令を待つことなく当然に休職となると読める規定も見受けられます。
ただ、休職制度は、社員が私傷病によって就労できない状態になった際、一定の療養期間を与え、解雇をできるだけ回避するための制度ですので、回復の見込みがないような場合にまで休職制度を適用する(解雇できなくなる)というのは妥当ではありません。
「休職を命じる場合がある」といった具合に、会社に一定の裁量を持たせる規定にする
のが適切です。
4 休職期間
休職を開始した社員が、一定の休職期間を経過しても復職できない場合、原則として休職期間満了時に退職となります。休職期間は会社によって異なり、3カ月から6カ月程度のところもあれば、2年から3年程度と長期に設定しているところもあります。メンタル不調の社員のように、断続的に欠勤が続くこともあるため、休職命令の発令前の欠勤期間についても休職期間に通算できるような規定を就業規則に定めておくのがよいでしょう。
また、「通算規定制度」も検討すべきです。
通算規定制度とは、復職後、一定期間内に同じまたは類似の傷病で再び休職した場合は、休職期間を通算する制度
のことです。次のような規定を設けると、長期休職が何度も発生することを防げます。
復職した社員が、その後○カ月以内に、同じもしくは類似の傷病により、再度欠勤をした場合、または、通常の労務提供ができなくなった場合は、復職を取り消し、直ちに再休職とする。この場合の休職期間は復職前の休職期間の残期間とする。
なお、この通算規定を新設して、従前よりも休職可能な期間が(実質的に)短縮される場合、労働条件の不利益変更に当たることには留意が必要です。
5 休職期間中の賃金
休職期間中の賃金は、
ノーワーク・ノーペイの原則に従い無給
となるのが原則ですが、その旨は就業規則に定めておく必要があります。ちなみに、休職期間中、賃金の支払いがない場合、社員は一定の条件を満たすことで健康保険の傷病手当金を受給することが可能です。
社会保険料と住民税については、休職期間中も発生しますが、無給の場合には賃金から控除できません。この場合、次の1.から3.のいずれかの方法で対応することが考えられます。
- 社会保険料と住民税の額を社員に伝え、会社指定の口座に入金してもらう
- 会社が立て替えておき、復職後の賃金からまとめて控除する(労使協定の締結が必要)
- 傷病手当金の受取先を会社にして、社会保険料や住民税を控除した上で社員に支払う
6 休職期間中の勤続年数の算定
社員が休職する場合、
休職期間は勤続年数に含めない
のが一般的です。表彰、賞与、退職金など、会社が勤続年数を基準に評価する制度については、就業規則の規定に矛盾がないかを確認しましょう。また、年次有給休暇の付与日数を計算する際も、休職期間は勤続年数に含めないのが一般的です。
7 復職の可否の判断
復職の可否の判断はデリケートな問題です。通常、休職期間が満了する前に、社員から主治医の診断書を提出してもらって復職の可否を判断しますが、社員の主治医が仕事内容の詳細を把握しているとは限りません。また、うつ病のようなメンタルヘルス疾患の場合、症状が一進一退を繰り返すため、復職の判断が難しいケースも少なくないです。
そのため、社員の主治医だけでなく、必要に応じて会社指定の医療機関にも協力を仰ぎ、復職の可否を慎重に判断できるようにしておくことが適切です。具体的には、次のような規定を就業規則に設けることが考えられます。
- 社員は復職に当たり、所定 of 復職願に社員の主治医による診断書を添えて提出する
- 会社は復職の可否を判断するため、社員に会社指定の医療機関での受診を命じることがある
- 最終的な復職の可否は会社が判断する
特に、2.については、会社指定の医療機関として産業医の意見を聴くことが重要です。社員の主治医の意見は、会社の業務に精通していない関係で、業務との関係性があまり考慮されないケースが多いのに対し、産業医の意見は、「社員の病状に照らして会社の業務に就けるか」など、実務的な観点から述べられます。
もっとも、上記のように就業規則上のルールを定めていても、社員が主治医や会社指定の医療機関の診断を受けてくれないケースがあります。その場合は、会社としては主治医や会社指定の医療機関の診断を抜きに復職判断をせざるを得ませんが、既に休職中であることから、「回復」が明らかではない以上、復職不可という判断をすることが多いと思われます。
なお、社員が復職直後から休職前と同じように働こうとして再び体調を崩し、そのまま退職してしまうケースが少なくないため、
復職後、当面の間は、労働時間を短縮(時短勤務)するなどして、経過を見ながら徐々に従前の働き方に戻していく
ことが望ましいです。主治医や産業医の意見を聴くことなく、従前の働き方に戻した結果、社員の体調が再び悪化したような場合には、会社に安全配慮義務違反があったとして、損害賠償請求がなされる可能性も考えられます。
そのため、
復職後、会社が必要と認める場合、社員との協議の上、労働条件を変更することがある
旨の規定を就業規則に定めておくとよいでしょう。
以上(2026年1月更新)
(監修 Earth&法律事務所 弁護士 岡部健一)
pj00262
画像:PJM-Adobe Stock