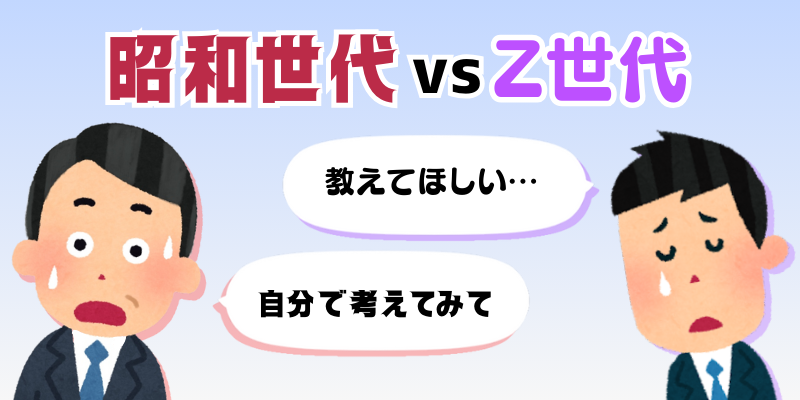1 「自分で考えてみて」と「教えてほしい」の線引きは?
2 その「自分で考えてみて」、本当に合っていますか?
3 その「教えてほしい」、本当に合っていますか?
4 それぞれの「やるべき仕事」を理解し、共有しましょう
1 「自分で考えてみて」と「教えてほしい」の線引きは?
ジェネレーションギャップは世の常……。今どきであれば、部下を持つ「昭和世代」の上司が、若手の部下である「Z世代(1990年代半ば~2010年代初頭生まれを中心とした世代)」との価値観のギャップに、戸惑うケースが多いかもしれません。例えば、仕事で昭和世代がZ世代に指導を出す際、
「自分で考えてみて」と「教えてほしい」のラインの見分け方で擦れ違いが生じる
ことがあります。
昭和世代の皆さんからすれば「少し考えれば分かる」ような質問を、部下がしてきたらどうしますか? 思わず「自分で考えなさい! 全く、若い世代はすぐに答えを聞きたがる!」と言ってしまうかもしれません。
ただ、Z世代は本当に楽をしたいから質問をしてきたのでしょうか? もし、本当に困っているのだとしたら……。こうしたときは、
お互いに自分がやるべき仕事を理解し、本当に相手に任せるべき仕事か(本当に自分ではどうにもならないのか)を見極める
ことが大切です。以降で、「自分で考えてほしい」と思っている昭和世代のAさんと、「教えてほしい」と思っているZ世代のBさんの“擦れ違い会話”を紹介します。両者の擦れ違いを解消するためのポイントを見ていきましょう。
2 その「自分で考えてみて」、本当に合っていますか?
営業職として働いている上司のAさん(昭和世代)と、部下のBさん(Z世代)。ある日、Aさんは、Bさんと定期面談をした人事部のCさんから報告を受けました。どうやら、Bさんは「Aさんに、もう少し指導してほしい、一緒に仕事をしてみたい」と思っているようです。
パワハラやモラハラ、ロジハラなど、とにかくハラスメントの問題で部下を指導しにくい時代……。自ら「指導されたい!」と申し出てくるとは見どころがあります。Aさんは「よし!」と気合を入れて、Bさんへの指導を始めました!
|
|
Bさん、クライアントに提出する、この資料のことだけれど……これはまだ、先方に提出できるレベルじゃないかもな。 |
|
|
見ていただいてありがとうございます! Aさんから見て、その資料のどんなところを修正したら、「提出できるレベル」になるのでしょうか? |
|
|
どんなところって……それを考えるのも仕事だぞ? 自分で考えてやってみてくれ。 |
|
|
ええっと……そこを、具体的に指導していただきたいんですけど……。 |
|
|
だから、自分で考えてやってみてって! 自分で何が悪いか分からないようじゃ駄目だよ! |
|
|
(そんなこと言われたって、参考資料もろくにないのに分かるはずがないよ……! 自分で考えてミスしたら、どうせまた怒るじゃないか……!) |
|
|
(自分で考えるのも仕事だろ。自分で何が悪いのか分かっていないようじゃ駄目じゃないか。全く、最近の若いモンは……) |
|
|
……。 |
|
|
(あれ……? 思った以上にへこんじゃっているぞ……? 仕事の手も止まっている……) |
|
|
(……そういえば私もついこの前、知らない専門用語ばかり使ってくる人に出会って困ったことがあったな……。何が分からないのかさえ分からないから、ぼうぜんとしちゃうんだよな。Bさんも同じ状況なのかもしれない) |
|
|
(そうか……何も分からないまま厳しく指導されても、余計に困ってしまうよね。今度指導をするときは、話しながらBさんの業務がどんな状況にあるのか、一緒に整理してみよう。もっと良い指導ができるかもしれない) |
Aさんは自分の経験を思い出したことで、Bさんが「何が分からないのかさえ分からない」状況に陥っていることを理解し、指導のための糸口を無事、つかんだようです。
3 その「教えてほしい」、本当に合っていますか?
Aさんは自分の指導方法を反省し、次からは、「Bさんが分からないことをきちんと聞き出そう!」と決意しました。
ただ、「教えてほしい」と頼む前に、Bさんが「自分で考えなければならない」ケースもあります。例えば、仕事に必要な情報がそろっていて、ちょっと頭をひねれば答えを導き出せそうなときです。
|
|
Aさん、クライアントに提出する資料ですが……事例はどのようなものを載せればいいでしょうか。 |
|
|
なるほど。何を使えばいいか、見当もつかないって感じかな? |
|
|
はい……どうすれば、うちのサービスを気に入ってもらえるのか、想像ができなくて。 |
|
|
この前の打ち合わせの感じだと、クライアントは商品の販売先を拡大したいという課題を持っている。だから、うちのサービスでそれをサポートする流れだね。Bさんならどうする? 合っていなくてもいいから、自分で考えて何個か挙げてごらん。 |
|
|
その正解が分からないから、Aさんにお聞きしているのですが……。 |
|
|
ええっ!? |
|
|
(私が教えた事例をそのまま資料にしても成長なんてできないぞ……? でも、この間、Bさんに同じようなことを言ったら落ち込んでいたしなぁ……) |
Aさんは、今度こそ本当に困ってしまいました。ここで押さえておきたいのは、Z世代は「デジタルネイティブ」であることです。物心ついた頃から当たり前にインターネットを使い、
「調べれば答えがすぐに分かる」環境で育ってきた世代
です。ですから、Bさんがすぐに答えを求めるのはある意味、自然なことですが、
仕事は、明確な「正解」があることのほうが少ない
のです。Z世代の成長のカギは、そこを理解できるかどうかにあるのかもしれません。
|
|
(何が正解なのか読めないし、的を射た質問ができないのが怖くて発言しにくい……! 分からないから聞いているんだし、教えてくれたっていいじゃないか……!) |
|
|
(社会は厳しいなあ……。怖いけど、取りあえず自分でやるしかないのか。ええと、クライアントの悩みはこれ、弊社がお薦めしたいサービスはこれ、過去の事例は……あのファイルにまとめてあるんだよな……?) |
|
|
(あれ……? よく考えたら今、分からないことって、そんなにないのでは……?) |
4 それぞれの「やるべき仕事」を理解し、共有しましょう
Bさんは、困ってしまったAさんと、もう一度話してみることにしました。
|
|
Aさん、さっきはすみません……。取りあえず自分でやってみます! |
|
|
えっ!? 急にどうしたの!? |
|
|
冷静になって考えてみれば、Aさんがおっしゃっていたように、「誰の、どのような悩みを解決したいのか」が分かっていれば、自分でも考えられるのではないかと思いまして……。それが私の「やるべき仕事」ですよね。すみません、甘えていました。 |
|
|
そうか、やってみてくれるならよかった……! 私も、この間は突き放すような言い方をしてしまって悪かったね。本当に分からないことなのであれば、これからは具体的に指導するよ。それが指導役としての「やるべき仕事」だもんな。 |
|
|
これからは、私もまず自分で考えて、頭の中を整理してから、Aさんに質問をするようにします! |
AさんとBさんが、お互いの「やるべき仕事」を理解し、共有することで、2人の擦れ違いは解消されたようです。今回は、「自分で考えてみて」と「教えてほしい」の壁をテーマにしましたが、他のテーマであっても、
自分の役割を理解した上で、「自力でできることはやる」「人に任せられることは任せる」
ようにすれば、擦れ違いは解消され、お互いの良さが引き出されていくはずです。
以上(2025年4月作成)
pj00743
画像:ChatGPT