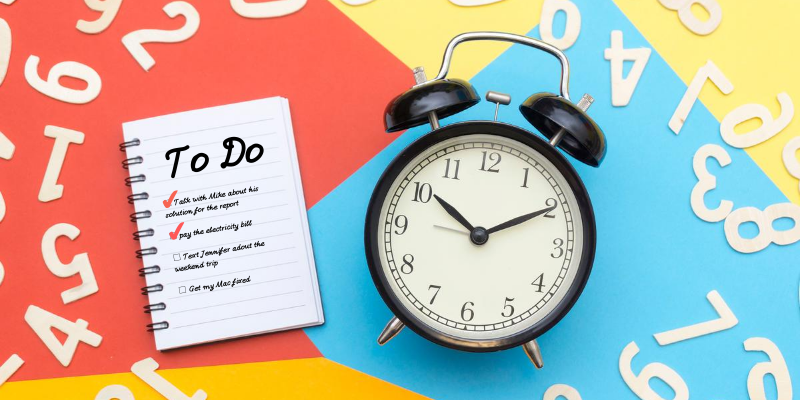1 24時間は1440分、8時間なら480分
24時間は1440分、8時間なら480分。「そのぐらい、誰でも知っている」と言われてしまいそうですが、こうして数字で表すと「時間は有限である」という実感が湧いてくるのではないでしょうか? しかも、何か予定を入れれば、その間は別のことができなくなるので、常に機会損失が発生しています。
スケジュール管理が苦手な方にとっては耳の痛い話ですが、この記事が、御社の社員に時間の大切さをいま一度、考えていただくきっかけになれば幸いです。
2 脱「他力本願」のやらされリスト
1)他人に決められるのは楽?
スケジュール管理ができない人に共通する特徴は、
働き方に主体性がないこと
です。試しに、社員にこの先1~2週間のスケジュールを登録するように指示してみてください。対応できる社員は全体の1~2割といったところでしょう。
この先の予定が決まっていないのに、なぜ社員は忙しいのでしょうか? 理由は人それぞれでしょうが、おそらく多くの人に当てはまるのは、
“他人が決めたToDoリスト”に振り回されているから
です。つまり、メールやチャットが届いた順にアポイントを入れ、仕事の納期も指定された通りに動いているのです。
しかも、上司の指示が入れば、ほぼ何も考えずにそちらを優先するので、優先順位もぐちゃぐちゃになります。「他人にスケジュールを決められるなんて、たまったものではない」と思いますが、主体性がない社員にとっては、“他人が決めたToDoリスト”に従うほうが楽なのです。
2)ToDoリストとスケジュールの違い
ToDoリストはスケジュールとは似て非なるものです。
ToDoリストは、「文字通りのやることリスト」
で、「(1)〇〇さんにメールを送る、(2)企画書を作る、(3)食事会の調整をする」などの内容が登録されます。長いToDoリストができるということは、それだけやることが多いということかもしれません。ただ、重要なのはその作られ方と中身です。“他人が決めたToDoリスト”が長くなるほど、自主性のない働き方に拘束される時間も長くなるからです。
これに対し、
スケジュールは、「目標を実現するための計画が行動ベースに落とし込まれたもの」
です。やるべきことと、それを実現するための計画が明確であれば、1~2週間先までスケジュールを登録することはたやすいはずです。
ToDoリストとスケジュールの関係は、「スケジュール→ToDoリスト」といった感じです。
スケジュールを細かく分解したものがToDoリスト
であり、ToDoリストの積み重ねがスケジュールになるわけではありません。
3)業務効率化の正しいアプローチ
「時間を大事に使おう!」となると、誰もが「同じ60分をいかに実のあるものにするか」を考えるでしょう。例えば、「順番を変えてみる」「ツールを導入してみる」「やらないことを決めてみる」といったアプローチになります。
やるべきことと向き合っているのなら、それでよいでしょう。しかし、“他人が決めたToDoリスト”をこなすための効率化だと、話は違ってきます。
重要ではないことの効率を上げるよりも先に、そもそも着手しない(断る、精度を落とす)という選択肢を持つべき
です。“他人が決めたToDoリスト”をこなすためにあれこれと苦労すると、かえって生産性の妨げになる、ということを認識しておきましょう。
また、この点は、仕事をこなす本人だけでなく、経営者や管理職も大いに反省する必要があります。社員の時間を無神経に奪ってはいけません。
3 「目標」設定から始めよう
1)「仏作って魂入れず」になる2つの理由
多くの会社では、半期ごとに人事考課面談を行い、中期経営計画に基づいた業務目標を決めているはずです。しかし、それがなかなかスケジュールに反映されません。これには、大きな理由が2つあります。
1つは、
社員が目標の達成に本気で取り組んでいないから
です。多くの社員は、すぐに中期経営計画の内容を忘れてしまいます。また、日々、“他人が決めたToDoリスト”に忙殺され、本当に大事なことを後送りにしています。
もう1つは、
社員はそれなりにやる気があっても、やるべきことを分解し、スケジュールに落とし込むことができていないから
です。目指すべきゴールは分かっているけど、ゴールにたどり着く道筋が分からないわけです。特に、受注的な事務作業が中心の社員の場合、「目標達成のためにやるべきことを分解する」というアプローチが苦手な人が多いかもしれません。
2)本気でなくても取り組む環境をつくる
この状態を打破するために、経営者が社員に「今、自分がやるべきこと」を正しく認識し、それを実行するように働き掛けなければなりません。
有効な手段は、社員に少なくとも1週間先までスケジュールを立てさせること
です。最初は多くの社員が戸惑うでしょうが、強制的にやらせます。
そうすると、“他人が決めたToDoリスト”が入り込む余地がなくなってくるので、社員はスケジュールの取捨選択をせざるを得なくなります。ここで初めて、会社にとって、チームや自分にとって、大切な仕事が何かを考えるようになります。
本気でない社員のマインドを変えるのは難しいことです。しかし、大事な仕事が後送りされない環境をつくることはできます。そして、このスケジュールをこなすことは社員の成長につながっていくのです。
3)経験と考え方の伝授
どうしても、やるべきことを分解して、スケジュールに落とし込めない社員がいたら、考え方を整理する方法を教えます。
経営者や管理職が1on1のミーティングを行い、そこでやるべきことと、それを達成するために最も効果的なことを明確にして、いつから始めるのかまで決めてしまう
のです。
後は、社員がスケジュールを意識しながら実行できる環境をつくります。前述した通り、少なくとも1週間先までスケジュールを立て、不要な仕事が入らないよう時間をブロックします。
4 学習時間をスケジュール化する
新しい仕事をするときはそれなりの準備が必要です。例えば、新しい業界に営業を展開するときは、その業界のことを勉強しなければなりません。こうした学習時間は、きちんとスケジュールに登録し、「2時間の読書、勉強会に参加」といったように記録しておきましょう。
もし、手を動かす業務でないと、「さぼっている」「他にやることがない」と勘違いする人がいるようなら、経営者がきちんと説明しなければなりません。
5 スケジュール管理のテクニック
1)基準時間を設ける
経営者や上司から見ると、「時間がかかり過ぎだ」と感じる社員がいます。しかし、その社員に「何かてこずっているの?」と聞いてみると、「いえ、計画通りです」という意外な答え。どうも釈然としないということはありませんか?
こうしたギャップは、業務の基準時間が決まっておらず、客観的に判断できないために生じます。主な業務については、「ベテランなら60分、新人なら120分」といったように、完了までの時間の目安を設けましょう。
2)基本は20分単位で取り組む
スケジュールは20分単位とします。こうすると、60分の中に3つの業務を組み込めます。また、20分の業務と10分のバッファーで30分の固まりを設定すれば、60分の中に無理なく2つの業務を組み込むことができます。20分以上かかる仕事については、まとめて固まりの時間を確保します。
最近はオンラインでの商談も増えましたが、訪問が必要な場合、アポイントの前後に「移動時間」を必ず登録します。東京都区内の場合、20分あればかなりの距離を移動できます。現地の準備時間を20分取れば40分なので、やはり20分単位だとスケジュールが組みやすくなります。
3)機会損失を意識する
今月のスケジュールを確認してみてください。既にかなり埋まっていることでしょう。では、来月のスケジュールはいかがでしょうか。まだまばらな状況で、比較的余裕があるかもしれません。
しかし、そこで来月はまだ余裕があると考え、簡単に決めてしまってはいけません。決して、今月は忙しく、来月は暇というわけではないのです。来月になれば、今と同じように忙しくなります。この点を意識していないと、
1カ月前に軽い気持ちで登録した、あまり意味のないアポイントと、とても大切なアポイントがバッティングしてしまう
のです。
同じ時間に2つのアポイントは入れられません。1つアポイントを入れた時点で、別の選択肢を排除していることを忘れてはなりません。
4)優先順位は細かな粒度で考える
業務の優先順位は、緊急度と重要度で考えます。ここにA、B、C、Dの業務があり、最も緊急度と重要度が高いのはAだとします。この場合、当然Aから着手します。ところが、正しいはずのこの着手で、なぜか問題が生じます。
それは、緊急度と重要度が2番目に高いBの業務を遂行するために必要な事前準備を、Aの業務よりも前に着手していないからです。そうすると、Aの業務が終わってBの業務を始めようと思ったときに、段取りができていないことに気付くのです。
優先順位が下であっても、全体をスムーズに進めるために先に着手すべきことがある
ということです。
5)後半こそ悲観的に考える
スケジュールが立て込んできて、いよいよギリギリの状況になると、「あれとこれがうまくいったら間に合う」と、楽観的に考える癖はありませんか。いまさらジタバタしても仕方がないと考えるのでしょうが、これは危険です。
後半になるほど関係者が増え、計画通りにいかなかった場合の影響も大きくなるから
です。それに、スケジュールがギリギリの状況になっているということは、それまでがうまくいっていないことの裏返しでもあります。スケジュール管理は、後半ほど悲観的に見積もるのが基本であり、予備日を多く設けておくべきでしょう。
6)パーキンソンの凡俗法則に立ち向かう
「パーキンソンの凡俗法則」とは、大切なことよりも、ささいなことが議論されがちな状況を指摘したものです。
例えば、原子力発電所と駐輪場の建設に関する住民の会合があったとします。原子力発電所の建設は本当に重要ですが、住民にはスケールの大き過ぎる話であり、技術的なことも分からないため議論が深まらず、比較的あっさり決まります。一方、駐輪場は原子力発電所に比べて明らかに重要度が劣るのに、住民にとって身近な問題であるため、ささいな点まで活発に議論され、決定に時間がかかるのです。
パーキンソンの凡俗法則に陥る最大の理由は、メンバーの知識や経験の不足です。
時間をかけて的外れな議論をし、本当に重要な点を見逃してしまうリスク
があります。必要に応じて、コストをかけても外部の知見を利用することを検討しましょう。
7)「ちょっといい?」は原則禁止
経営者や管理職がちょっと疑問に感じた途端、部下のスケジュールを顧みずに招集して臨時の会議を始めたりしていないでしょうか。当初は5分の予定だったのに、気付けば60分かかっていることも珍しくないでしょう。
仕事なので、経営者や管理職の疑問は解消しなければなりません。しかし、社員にスケジュール管理を徹底させている張本人(経営者や管理職)が、そのスケジュールを自ら破壊してはいけません。「ちょっといい?」にも配慮が必要な時代なのです。
【参考文献】
「1440分の使い方―成功者たちの時間管理15の秘訣」(ケビン・クルーズ(著)、木村千里(訳)、パンローリング、2017年8月)
「仕事は『段取りとスケジュール』で9割決まる!」(飯田剛弘、明日香出版社、2018年12月)
以上(2025年1月更新)
pj00288
画像:pexels