2025年7月、米国半導体大手エヌビディアの株価が時価総額4兆ドルの壁を超えたニュースは、テック業界のみならず世界経済全体に衝撃を与えました。この記録は、同社がAIインフラの王者として、新たな世界秩序を築きつつあることを示しています。
かつて2000年の時点で世界を牽引していたのは、ゼネラル・エレクトリック(GE)やインテル、エクソンモービルといった旧来の産業・金融大手でした。特にインテルは、PC時代のCPUを独占し、テクノロジーの「心臓部」としての地位を確立していました。
しかし、2007年のiPhoneの登場、翌2008年のリーマン・ショックが、すべてを変えました。GAFA(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン)はモバイルとクラウドの波に乗り、インターフェースとサービスの領域で支配的な地位を築きました。ここではデータ、ネットワーク効果、ユーザー体験が価値創造の中心となり、GAFAが市場価値を急伸させたのです。
ところが今、新たな地殻変動が起きています。それがAIとエヌビディアです。生成AIや大規模言語モデルの普及に伴い、GAFAすらも再び「インフラ」への依存を強めています。AIは、従来のCPUでは処理が困難であり、並列計算に優れたGPUが不可欠です。エヌビディアは、この需要を10年以上前から見越し、CUDAという開発プラットフォームを整備してきました。
CUDAは、単なるGPUドライバではなく、AI開発における事実上の標準インフラです。多くの開発者、研究機関がこれに対応したコードを書いており、他社への乗り換えは事実上困難です。これは、かつてマイクロソフトのWindowsがアプリ開発者を囲い込んだ構造と似ており、強力な競争優位性を形づくっています。
さらに忘れてはならないのが、台湾の半導体メーカーTSMCの存在です。エヌビディアの最先端GPUは、TSMCの3nm(ナノメートル)以下の製造プロセスなくしては成立しません。エヌビディアは設計、TSMCは製造という水平分業が、半導体を巡るグローバルな力学を決定づけているのです。この構造の中で、かつての巨人インテルは設計と製造を一体で保ち続けた結果、柔軟性を失い競争力を落としました。
2025年現在の時価総額ランキングは、エヌビディア、マイクロソフト、アップル、アマゾン、アルファベット(グーグル)といった米国企業が独占しています。その中でTSMCやブロードコムといった半導体プレーヤーも存在感を増しており、もはや経済の中核は「計算能力」そのものへと移っています。
この構図は、単なる一時の流行ではなく、構造的変化です。情報処理の高度化が進むなかで、計算基盤(コンピュート・サブストレート)を握る者が、価値の中枢を支配するようになったのです。
インテルが築いたCPU時代、GAFAが築いたクラウドとエコシステムの時代、そして今、エヌビディアとTSMCが中心となる「AIインフラの時代」。この歴史の流れを正確に理解することが、未来を切り拓く鍵となるでしょう。
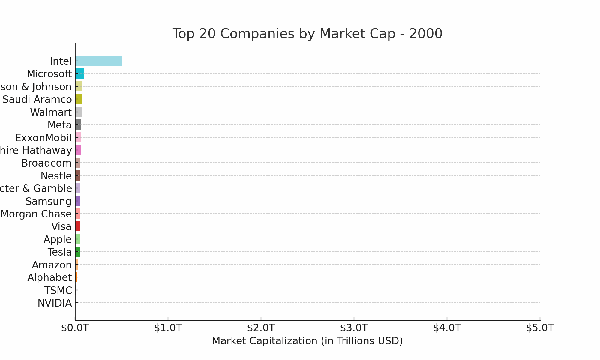
(注)このアニメーションGIFは、イメージを分かりやすく伝えるために生成AIによって作成したものですので、実際の数字等については各企業のHP等でご確認ください。
以上(2025年7月作成)
pj50558
画像:bephoto-Adobe Stock
