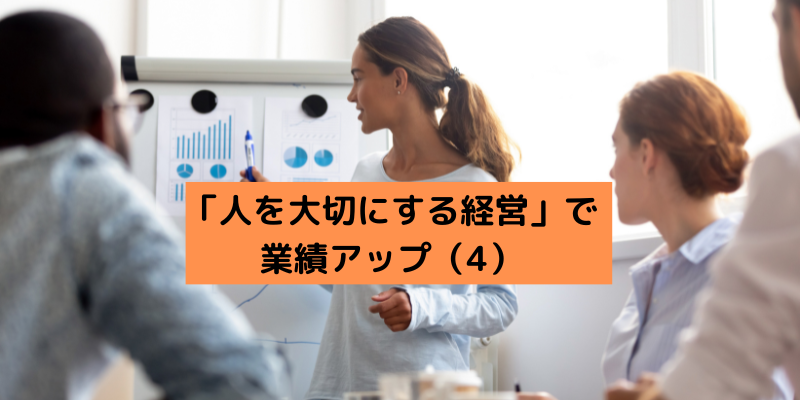書いてあること
- 主な読者:業績は上がらないし、社員は生き生きと働いていない。会社の経営指針を根本的に見直したいと考えている経営者
- 課題:社員の幸福や会社の社会的意義も大事だが、業績が悪ければそれどころではない
- 解決策:会社に関係する全ての人の幸福を最優先する「人を大切にする経営」を実践する。休暇をプラスに捉え、会社全体を見通し創造性の高い業務を行う“人財”を育てる
1 「労働時間が減る=業績が悪くなる」という大きな勘違い
前回は「経営者の意識改革」をテーマに、実践事例を交えながら、どんな有事でも一喜一憂しないために経営者が持つべき視点や、勝ち残るための非価格競争の重要性について紹介しました。
第4回となる今回は、働き方改革や“人財”育成および活用といった観点から、人を大切にする経営を進めていくための方法について、実践事例を交えつつ紹介していきたいと思います。
1)残業しないと達成できない経営計画は不要
「働き方改革で社員の労働時間が減ったら、売り上げも減った」と嘆く人たちがいます。しかし、社員の残業時間が減り、休みが増えるようになると会社の業績が悪くなるという考え方には、大きな勘違いがあります。
そもそも、
残業や休日出勤をしないと、売り上げ・利益が計画通りに達成できないという状況は異常
なことであって、
そのような経営目標・経営計画を立てたことに、もともと無理があった
ということを認識することが大切です。
誰かの犠牲の上に成り立つ経営、誰かに負荷が掛かる経営は、いずれ崩壊を招く
ことになります。
低い目標を立てろとは言いませんが、ゆっくり、着実に成長・目標達成をする計画を立てること。「急がば回れ」を意識することが求められます。
2)長野県の寒天製造販売会社が進める数値目標を掲げない「年輪経営」
第2回でもご紹介した、長野県にある寒天の製造販売会社では、「年輪経営」という経営が行われています。樹木が1年で一つずつ年輪を増加させるように、会社は急成長・急拡大を目指すことなく、地道に少しずつ成長を続けるというものです。
年輪経営を貫く同社の成長についての考え方は、「年輪は、たとえ雨が少ない年であっても、寒くても、暑くても、毎年必ず一つ増えます。毎年の成長度合いは同じでなくてもよく、前の年よりも大きくなっていることが大切」というものです。そのため、「売り上げや利益は、年輪経営の結果である」と考え、成長の数値目標を掲げていません。
むしろ、急成長には懐疑的で、「好景気や一時のブームに乗って急激に成長してしまうことに気を付けなければいけません。確実で安定した成長が、自分たちだけでなく会社を取り巻く全ての人々の幸せにつながることを実感しています」と考えているのです。
長期間にわたり増収増益を継続した同社の実績は、年輪経営の正しさを証明してくれているといえます。
3)「残業は当然」という認識は改めるべき
かつては、勤勉で残業も休日出勤も厭わずに働くことが、日本人の美徳であると思われてきました。また、自分自身の業務が終わっていても、周りの社員の業務が終わらないうちは帰らず、業務を続けるということが組織の一体感を高めることだと思われていました。
確かに、そのような考え方が機能していた時代があったことは事実かもしれません。ですが、自分自身の業務が終わったのに業務を続けているのは、残業のための残業でしかありません。なぜ、日本人は何の疑問も持たずに残業を続けてきたのでしょうか。
「お客さまが困っているから、対応せざるを得ない」ということはあるでしょう。ですが、本来、顧客満足への対応について考えるのは、社員個人ではなく、会社全体、つまり経営判断であるべきです。困っているお客さまへの対応まで所定労働時間内でやりきるのが、通常の働き方であるはずです。
それができていない理由は、会社が社員のキャパシティを超えた業務を与えているのか、またはその社員の業務の仕方に問題があるのかだと思います。
2 社員の休暇は会社にとっての「損失」ではない
1)社員の一斉10連休に取り組んだ別府市のホテル
社員が残業をせず、休みを増やすことは、本当に会社にとってマイナスなことなのでしょうか。ここでは、ある宿泊業者のケースを例に見てみることにします。
宿泊業といえば、休日が少なく営業時間が長いことの代表的な業種と思われています。しかし、ここ数年で、その業界常識の改革に挑み、実際に成果を生んでいる旅館・ホテルが現れ始めてきています。
大分県別府市にあるホテルでは、2020年の正月明けの1月14日から23日まで全館休業とし、約1000人の社員を一斉休暇としました。この取り組みは、単年ではなく2018年から3年連続で行われました。
この取り組みについて、支配人は、「この業務形態をこのままにしていいのか。働いている本人はよくても、家族はどうだろうか…」「顧客満足度にひたすらこだわってきたが、社員満足度にも力を注がないといけない。従業員の連休拡大は避けては通れなかった」「企業が有給休暇取得を推進する時勢も受け、拡大に踏み切った」と話しています。
2)社員のモチベーション向上や採用活動に大きなメリット
10日間の全館休業によって、売り上げは数億円の減収になったといいますが、それをはるかに上回る価値も生まれたといいます。まずは、社員のモチベーションの向上です。いくら好んで働いているとはいえ、やはり少なからず「満たされていない」と感じながら働き続けていると、いつか限界が来ます。一斉休暇という取り組みによって、会社は社員たちに、「会社は皆さんのことを大事にしている」ことを伝えることができます。社員たちが満たされた気持ちになると、それが仕事へのモチベーションとなり、自然と接客サービスの質につながっていくものです。
次に、採用活動への効果です。旅館業は、どうしても「厳しい労働状況」というイメージが強く、なかなか応募者が集まらないといいます。ところが、一斉休暇を始めたところ、それまで地元の九州が中心だった新卒採用応募者が関東や北海道など全国に広がり、前年の1.5倍に増えたそうです。面接では、多くの応募者から一斉休暇に関する話が出たといいます。
3 “人財”を育て、活用するための働き方改革
1)有能な社員ばかり疲弊するのは、人に仕事を付けるから
政府も推進する「働き方改革」は、思うように進んでいないように見えます。その要因の1つは、人と仕事の関係にあります。日本では、どちらかといえば、仕事に人を付けるというよりも、人に仕事を付ける方法が取られてきました。本来は、
人に仕事を付けるのでなく、仕事に人を付ける
べきです。
人に仕事を付けてしまうと、どうしても「自分はその仕事だけを任されているから、他部門が困っていても関係ない」「自分がこの仕事を任されているのだから、他の人は勝手に入ってくるな」といった気持ちが生まれてしまいます。それゆえ、その人が病気などでしばらく欠勤することにでもなれば、最悪の場合、業務が止まってしまう危険性があります。
さらに、人に仕事を付けることで、能力の高い社員に業務が集中してしまい、その社員への負荷が掛かり、結果として残業時間が増え、疲弊してしまうという悪循環も発生してしまうのです。
それを回避するためには、各業務を細分化・標準化し、誰もが業務を行えるようにしておく必要があります。業務全体では能力の高い社員と同じような結果を出せない人であっても、細分化された一部の業務であれば、繰り返し行うことで慣れ、効率が上がっていくからです。
2)ダブルアサインメントとマルチタスク
業務の標準化と併せて行うことで働き方改革に有効な手段として、ダブルアサインメントとマルチタスクの推進が挙げられます。
ダブルアサインメントとは、
ある1つの業務に対して、あえて担当者を2人割り当てる
ことです。通常は1人を割り当てればいいところを、「2人担当制」にするという働き方です。これにより、担当者のどちらかが急な休みを取っても、お客さまに迷惑を掛けるリスクは低くなります。
マルチタスクとは、
1人で複数の業務を担当する
ことです。ダブルアサインメントを導入するだけでは、人件費の増加などの問題が生じるだけで終わってしまいます。その問題解決のために併せて導入するのが、マルチタスクという働き方です。
3)中小企業が大企業に勝つには部門横断的な“人財”の育成が重要
ダブルアサインメントとマルチタスクは、働き方改革に有効なだけでなく、中小企業の“人財”育成にも欠かせないものだといえます。
東京都墨田区にある石けんなどの製造販売会社は、自社の課題として、「研究開発・営業企画・製造という各部門の壁を取り払い、いかにして一体化させるか」を常に意識しています。それは、経営者自身の経験から、中小企業の社員の基本的な知識・経験・能力は、大企業の社員と比べて低いと感じているためだといいます。
自社と大手企業とが、研究開発・営業企画・製造という各部門の「単体」で闘っても、全く勝負にならない。小さな町工場でつくる自社ブランドが大手企業に勝負を挑み、お客さまから選んでもらうようになるためには、社員が
- 製造もする営業担当
- 販促コピーが書ける研究開発担当
- セールスまでできる工場長
になってもらい、社員の「個」でなく会社の「総合力」で戦うことが必要だと考えたのです。
中小企業が一流の大手企業や海外企業と伍(ご)していくには、社員が自分の強みだけではなく、自社全体を見通せる力を備える必要があります。そのためには、社員に社内全体のオペレーションを一気通貫で経験させ、一人三役といった多能工のような“人財”を育むことが重要です。
4)機械でできることは機械に任せ、人には創造性の高い業務を任せる
社員のモチベーションと仕事の質を高める施策として、機械などでできるルーティン的な業務は機械に任せ、社員には努力が付加価値向上に直結する、創造性の高い業務に専念しやすい環境をつくることが挙げられます。これは働き方改革の成否を分ける取り組みともいえます。
京都府宇治市にある機械加工会社は、かつては大企業の下請けでしたが、機械化やDX(デジタルトランスフォーメーション)によって、働き方改革だけでなく、社員の能力が向上して高付加価値の製品が開発可能となり、飛躍的に収益力を高めることに成功しました。
同社がまず着手したのは、業務の標準化と職人的な製造技術のデータ化による、製造工程管理システムの構築でした。これにより、人力による製造工程はプログラマーがプログラムをセットするだけで、残りの業務は全て機械で行えるようになりました。
製造工程に費やす時間から解放されたことで、社員は創造性が必要な業務に専念できるようになりました。これによって社員のモチベーションは上がり、質量共に十分な人的資源が研究開発に投入されたことで高付加価値化が進んだ結果、米国のNASAなどからも発注が舞い込むまでになりました。
4 非正規社員は果たして「ローコスト」なのか
多くの会社は、人件費の削減を目的として契約社員やパート・アルバイトなどの非正規社員を活用しています。
ところが、この手法をある程度進めていくと、限界を知ることになります。社員をコストや雇用の調整弁としてしか見ない雇用形態では、社員は自分が大切にされているとは思いません。従って愛社精神や仕事に対するモチベーションが生まれるはずもなく、会社や仕事のために心底頑張ろうとは思わないのです。
愛社精神や仕事に対するモチベーションがない人は、どんなに有能であっても、会社全体を見通すことをしませんし、「こうしたら、私たちも会社もよくなる」「お客さまに対して、どのようなプラスαのサービスができるのか」という発想には至りません。指示された業務を指示された方法で処理するだけで終わってしまいます。
また、こうした人たちは自分の都合次第で、簡単に会社を辞めていきます。空いた人員はその都度補充せねばならず、新規採用者には一から教育を施す手間が掛かります。果たして、これがローコストといえるのでしょうか。
本当にローコストを目指すのであれば、原則、正社員化するべきです。少なくとも、頑張れば正社員になれるという門戸を広げておくべきでしょう。正社員化すると人件費が上がることを心配される方も多いと思いますが、正社員にすることで向上するモチベーションは、人件費以上の効果を発揮するものです。会社全体を見通して自発的に動き、計算できない価値を生み出すことができる「社員力」を人件費で割ってみると、相対的にローコストだということが分かるはずです。
次回の第5回は、経営戦略や財務戦略といった観点から、人を大切にする経営を進めていくための方法について、実践事例も交えながら解説していきます。お楽しみにしてください。
以上(2022年7月)
(執筆 人を大切にする経営学会事務局次長 坂本洋介、水沼啓幸)
【著者紹介】
坂本洋介(さかもと ようすけ)
1977年静岡県生まれ。東京経済大学大学院経営学研究科修了。株式会社アタックス「強くて愛される会社研究所」所長、コンサルタント。人を大切にする経営学会事務局次長。
主な著書に「社員にもお客様にも価値ある会社」(かんき出版)、「小さな巨人企業を創りあげた 社長の『気づき』と『決断』」(かんき出版)「実践:ポストコロナを生き抜く術!強い会社の人を大切にする経営」(PHP研究所)他、連載、執筆多数。
水沼啓幸(みずぬま ひろゆき)
1977年栃木県生まれ。法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科修了(MBA)。株式会社サクシード代表取締役。人を大切にする経営学会事務局次長。作新学院大学客員教授。中小企業診断士。地域特化型M&Aプラットフォーム「ツグナラ」運営。
主な著書に「地域一番コンサルタントになる方法」(同文舘出版)、「キャリアを活かす!地域一番コンサルタントの成長戦略」(同文舘出版)、「実践:ポストコロナを生き抜く術!強い会社の人を大切にする経営」(PHP研究所)他、「近代セールス」等連載、執筆多数。
pj98054
画像:fizkes-Adobe Stock