1 「2025年問題」を、統計データを基に考えるきっかけに
「2025年問題」は、戦後の第1次ベビーブーム(1947~1949年)に生まれた「団塊の世代」の人たちが、全て75歳以上の後期高齢者になることで、医療・介護や社会保障制度など、様々な分野に影響を及ぼすとされる社会問題です。「団塊の世代」の人たちは、出生者数で約806万人と突出して多く、その動向は雇用や消費など日本社会に大きなインパクトをもたらしてきました。
この記事では、日本の人口に関する統計データを加工し「見える化」します。“分かっているつもり”のイメージがより鮮明になることでしょう。「2025年問題」をはじめとする社会問題は、ピンチなのかチャンスなのか、違った角度から考えるきっかけになれば幸いです。
2 人口ピラミッドで見る「2025年問題」
まず「2025年問題」について、国立社会保障・人口問題研究所が5年ごとの画像データを公表している「人口ピラミッド」を基に見てみましょう。1970年までは沖縄県の人口を含まないため、ここでは1975年以降の日本の人口ピラミッドの推移を紹介します。
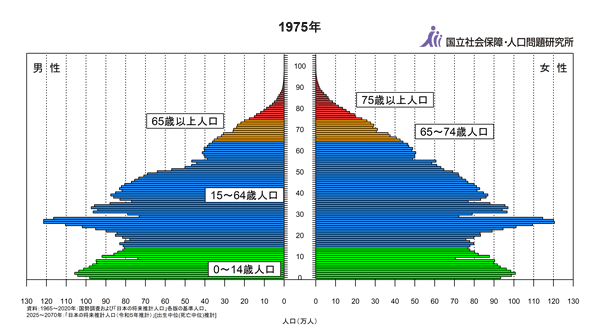
(出所:国立社会保障・人口問題研究所「人口ピラミッド画像(1975~2070年)」を加工)
(注)人口ピラミッドのデータは、1965~2020年は総務省統計局「国勢調査」および国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」各版の基準人口、2025~2070年は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)出生中位死亡中位推計」によるものです。
最初の年、1975年の人口ピラミッドで30歳の手前にある男性、女性とも横棒の長さが最も長いのが「団塊の世代」です。年を追って見ていくと、2025年の人口ピラミッドで「団塊の世代」が75歳以上(後期老齢人口)になる様子が見て取れます。
2025年の人口ピラミッドで男性、女性とも50~60歳にある山が第2次ベビーブーム(1971~1974年)に生まれた「団塊ジュニア世代」です。2040年には、「団塊ジュニア世代」の人が全て65歳以上となり、全人口に占める65歳以上の割合が35%になります。これは、人口の3人に1人以上が高齢者となる「2040年問題」として指摘されています。
なお、団塊ジュニア世代の少し上でひときわ目立つ凹みが1966年の「丙午(ひのえうま)」です。丙午生まれの女性は「気性が激しく夫の命を縮める」などといった迷信の影響で、1966年の出生数は約136万人(前年比で約46万人減)となりました。ちなみに、2026年は60年周期で巡ってくる「丙午」の年で、こうした迷信がいまだに影響し、出生数の減少に拍車をかけるのか注目されています。
3 都道府県別に見ると?
1)都道府県別に見た総人口の増減率の推移
次に、総務省統計局「社会・人口統計体系 都道府県データ 基礎データ(A 人口・世帯2025-02-21公開)」と、国土交通省「国土数値情報ダウンロードサイト」から入手した都道府県の境界データを含む日本地図のGISデータを使って、都道府県別に見た総人口の増減率の推移を、地図上にプロットして見てみましょう。
1975年を基準とした人口増減率は次のようになります。人口増を赤色、人口減を青色、色の濃淡で変化の度合いを示しています。特に、地方で人口減少が進んでいる様子が分かります。
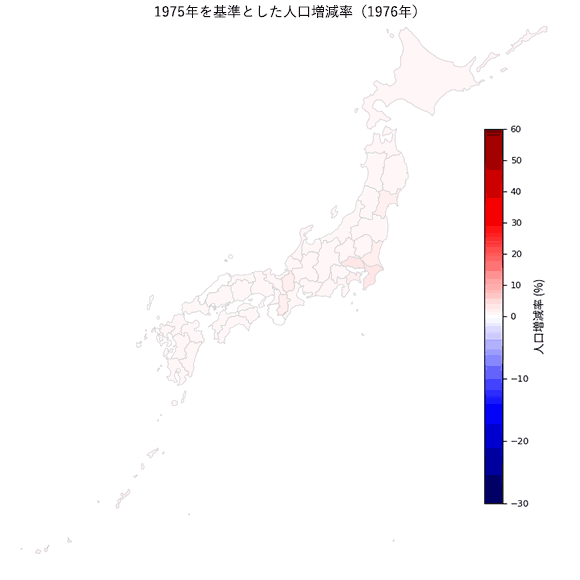
(出所:総務省統計局「社会・人口統計体系 都道府県データ 基礎データ(A 人口・世帯2025-02-21公開)」および国土交通省「国土数値情報 行政区域データ(2024年(令和6年)版)」を加工)
2)都道府県別に見た出生数の増減率の推移
続けて、都道府県別に見た出生数の増減率の推移を、地図上にプロットして見てみましょう。出生数は1980年のデータが基準となります。
出生数増を赤色、出生数減を青色、色の濃淡で変化の度合いを示しています。出生数の減少傾向は全国的なもので、徐々に濃い青のエリアが増えている様子が分かります。
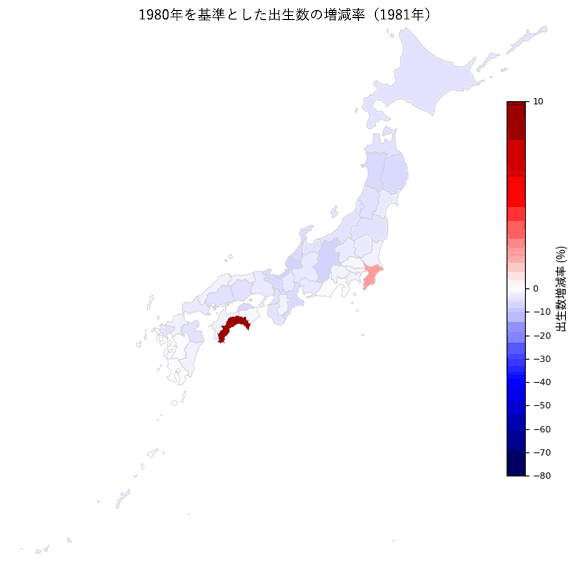
(出所:総務省統計局「社会・人口統計体系 都道府県データ 基礎データ(A 人口・世帯2025-02-21公開)」および国土交通省「国土数値情報 行政区域データ(2024年(令和6年)版)」を加工)
なお、都道府県別の総人口や出生数などの統計データは、政府統計ポータルサイト「e-Stat」から所定の手続きを経ることで、APIを利用して取得できます。
3)都道府県別に見た在留外国人人口の増減率の推移
次に、出入国在留管理庁「在留外国人統計」とエクセルの「マップグラフ」の機能を使って、都道府県別に見た在留外国人人口の増減率の推移を見てみましょう。在留外国人人口は2013年のデータが基準となります。
人口増を橙色、色の濃淡で変化の度合いを示しています。在留外国人人口は全国的に増加傾向にあり、足元で在留外国人人口増加率が高いのは南九州(大分県、宮崎県、鹿児島県)や北海道です。
なお、2024年末時点で在留外国人人口が最も多いのは、東京都の73万8946人(前年末比7万5584人増)で全国の19.6%を占め、次いで、大阪府、愛知県、神奈川県、埼玉県と続いています。
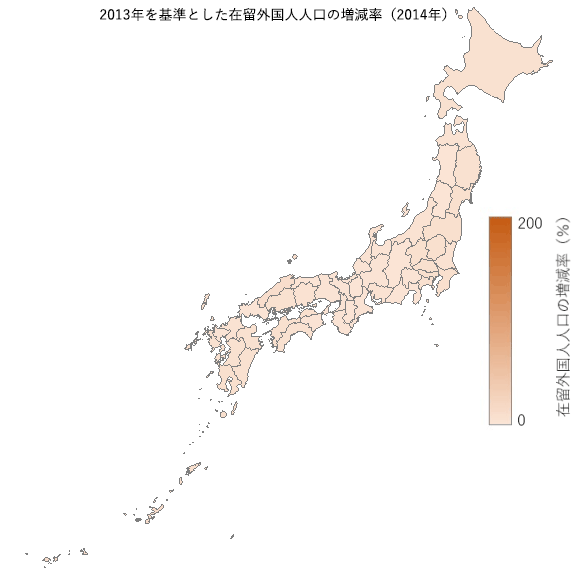
(出所:出入国在留管理庁「在留外国人統計」各年末版を加工)
(注)「未定・不詳」の数値を除いたデータを加工しています。
都道府県別の在留外国人人口の最新データは、政府統計ポータルサイト「e-Stat」からエクセルファイルのダウンロードが可能です(2025年5月20日時点で、APIを通じて提供されていることは確認できませんでした)。
4 「団塊の世代」が後期高齢者となることの影響
1)医療・介護需要の急増
75歳以上の後期高齢者になると病気やけがのリスクが高くなり、認知症の人も増え、今後、医療・介護需要が急増するといわれています。一方で、医療・介護を担う医師、看護師、介護職員などの人材不足の深刻化が懸念されています。
企業にとっては、従業員が親の介護のために仕事を辞めてしまう「介護離職」への対応も課題となります。また、経営者の高齢化や後継者不足など「事業承継」の対策も重要です。
2)社会保障費の増加
年金・医療保険制度は、支える側(現役世代)が減り、受け取る側(高齢者)が増える構図となり、財政の悪化が懸念されています。また、若年層・現役世代の社会保障費の負担が重くなるといわれています。
少子高齢化が進む中で、徐々に保険料率は上昇する可能性があります。また、社会保険の適用範囲が広がると、企業の保険料負担も従前よりも増加します。企業にとっても注視すべき課題です。
3)移動手段の確保の課題
日常の足として自らクルマを運転していた人たちが、高齢化に伴って運転免許を返納することで、買い物や通院などの移動手段を失うケースが増えることが懸念されています。
バスやタクシーなどのドライバー不足が深刻化する一方で、一部地域ではタクシー会社が運営する管理体制の下、一般ドライバーが自家用車を使って有償で送迎する「ライドシェア」が導入されています。また、地方都市などで、利用者の予約状況に応じて運行する、乗り合いの「オンデマンド交通」も普及しつつあります。
4)「多死社会」の課題
日本は、既に、死亡者数が出生者数を上回ることで人口が減少している「多死社会」です。「孤独死」「火葬場や墓地の不足」などが深刻化することが懸念されています。
葬祭関連ビジネスに注目すると、数年前の新型コロナウイルスの感染拡大によって、参列者が集まって執り行われる従来の葬儀の在り方が大きく見直され、小規模化・低価格化が進んでいます。「樹木葬」「海洋散骨」などの他、「遺品整理」「遺体の一時預かり」サービスも登場しています。
人口の減少傾向の一方で、在留外国人人口は増加傾向にあります。在留資格の申請手続きや不動産の賃貸契約サポートをはじめ、「海外送金」、日本人と外国人がコミュニケーションを取るための「語学教育」、日本語で書かれたマニュアルの「翻訳」など、在留外国人向けのサービスの動向も注目されます。
以上(2025年6月作成)
pj50554
画像:yoshitaka-Adobe Stock
