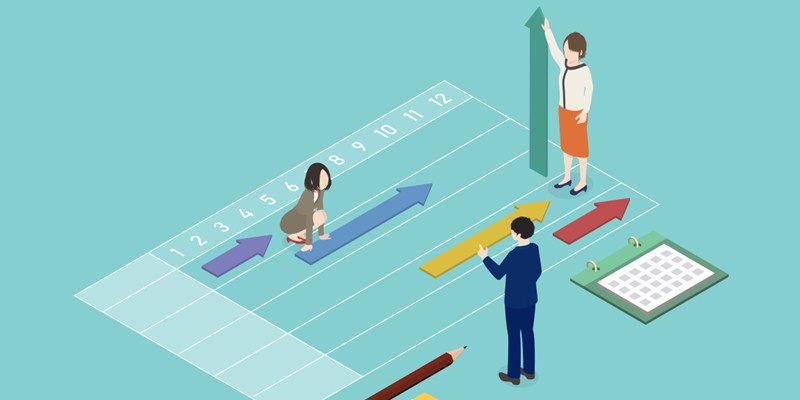1 スケジュール管理に悩んでいませんか?
あらゆる仕事には締め切りがあり、スケジュール管理は仕事の基本です。とはいえ、スケジュール管理を苦手とする人は大勢います。スケジュール管理ができない理由として、仕事の見込み時間が甘いなどが考えられますが、「先延ばしにしてしまう」というのも1つです。
産業心理学者が記した「ヒトはなぜ先延ばしをしてしまうのか」(*)によると、さまざまな調査において、「約95%の人が物事を先延ばしにすることがある」「約4人に1人が先延ばしが慢性的になっており、自分の特徴の1つである」と回答しています。
先延ばし癖は、心理学や行動経済学などの分野でも関心を集めており、
先延ばし癖の改善策の1つとして挙げられるのが、モチベーションのコントロール
です。高いモチベーションを保てれば、物事を先延ばしにすることなく、適切に対応できます。
前述した「ヒトはなぜ先延ばしをしてしまうのか」によると、モチベーションを左右するのは、「価値の大きさ」「努力が報われる大きさ」「時間の長さ(遅れの大きさ)」です。実際、日々の仕事においても、
- 自分の成長につながるとは思えない(価値が小さい)
- すぐやらなくても大丈夫(時間に余裕があるので、問題が切実に感じられない)
- 自分には難し過ぎて解決できない(努力が報われない可能性が大きい)
と感じる仕事は、先延ばしにしてしまう人が多いはずです。
そこで、以降では、「価値の大きさ」「時間の長さ(遅れの大きさ)」「努力が報われる大きさ」の各要素に注目しながら、先延ばし癖を改善するための行動として
- あえて先延ばしにする
- 具体的にイメージする
- 仕事を小分けにしてみる
を紹介します。
2 あえて先延ばしにする
組織への貢献度や緊急度が高い重要な仕事であっても、あまり自分が得意とすることでない場合、着手する気になれないものです。こうしたケースの改善策として、締め切りが目前に迫っている場合は別ですが、あえて少しだけ先延ばしにし、他の重要度の高い仕事と組み替える方法があります。こうすることで、結局何にも着手できない状態を防ぐことができます。
ただし、組み替える場合は、仕事の優先順位を正しく付けていることが前提です。組織への貢献度や緊急度が低い仕事ばかりに取り組んで達成感を得ることがないようにしましょう。
3 具体的にイメージする
「すぐやらなくても大丈夫」など、時間の余裕がある仕事は先延ばしにしがちです。しかも、余裕があることを言い訳にして、自分を甘やかしてしまいます。
これを避けるには、「週の後半頑張れば間に合うだろうから、前半は違う仕事に取り組もう」とぼんやりと先延ばしするのではなく、何時間先延ばしにするのか、着手しない間にどのような仕事に取り組むのかを、具体的にイメージします。
ある喫煙習慣に関する研究では、被験者に毎日1箱たばこを吸い続けるよう求めたところ、本数を減らす指示をしていないのに、全体的な喫煙量が徐々に減ったという結果があります。これは毎日同じ本数を吸い続けなければならないと自覚したことで、自制心が働くわけです。
何時間先延ばしにし、その間どんな仕事に取り組むのかを具体的にイメージすると、「優先度の低い仕事に取り組んで、無駄な時間を過ごしている場合ではない」と認識することができます。また、先延ばしをしたことで起こるかもしれないトラブルやミスについても具体的にイメージするとよいでしょう。
4 仕事を小分けにしてみる
「自分には難し過ぎて解決できない」など、努力が報われないと諦めを感じる仕事は、先延ばしにしがちです。これを避けるためには、仕事を小分けにして取り組みます。
1つの固まりだと難しく感じる仕事でも、小分けにしてみると、思っていたよりも簡単だったということがあります。また、小分けにして1つずつ終わらせることで、進歩を感じられ、達成感が生まれます。
この際、取り組みやすい課題から少しずつ始めてみるのがコツです。例えば、企画書の作成に着手するなら、「グラフだけでも完成させる」などの視点で取り掛かります。
5 先延ばしが良い効果を生むことも?
先延ばし癖を克服することは簡単ではなく、改善策に取り組んでも劇的にスケジュール管理がうまくいくとは限りません。効果がすぐに表れないと、モチベーションを保つのが難しいと感じるかもしれませんが、諦めてはいけません。
人は年齢を重ねるほど、先延ばしにすることが減るという研究結果があります。これは年齢を重ねて物事の因果関係が理解できるようになることで、若い頃は無意味に感じていたことにも、意味を見いだせるようになるからだと考えられています。
任せられた仕事の中には、なぜ自分が取り組まなければならないのか、その目的を理解するのが難しいものがあるかもしれません。その場合、自分で考えることに加え、上司に相談して、目的やスケジュールを組み立てる際の難所などについて確認しましょう。上司はより高い視点から仕事を捉えているため、気付きを得られるはずです。
また、上司はスケジュール管理を教えるということにとどまらず、部下により多くの経験を積ませるようにします。経験に基づく広い視点は、計画倒れにならないスケジュール管理につながるでしょう。
一方、先延ばしには、悪い効果だけでなく、良い効果もあると説く人もいます。例えば、アイデアを出すといったような、創造性を発揮する類いの仕事の場合、先延ばしによってアイデアの質を高めることができるとの研究もあるようです。
しかし、単に先延ばしをするのではなく、「3時間後に、アイデア出しの時間をつくる」といったように、課題を認識した上で、一旦その仕事から離れて、息抜きをするなど他のことをするのが効果的だとされています。
【参考文献】
(*)「ヒトはなぜ先延ばしをしてしまうのか」(ピアーズ・スティール(著)、池村千秋(訳)、阪急コミュニケーションズ、2012年7月)
「予想どおりに不合理 行動経済学が明かす『あなたがそれを選ぶわけ』」(ハヤカワ文庫 NF)(ダン・アリエリー(著)、熊谷淳子(訳)、早川書房、2013年8月)
「DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビューオンライン(2017年10月31日)」(ダイヤモンド社、2017年10月)
以上(2025年8月更新)
pj40016
画像:mayucolor-Adobe Stock