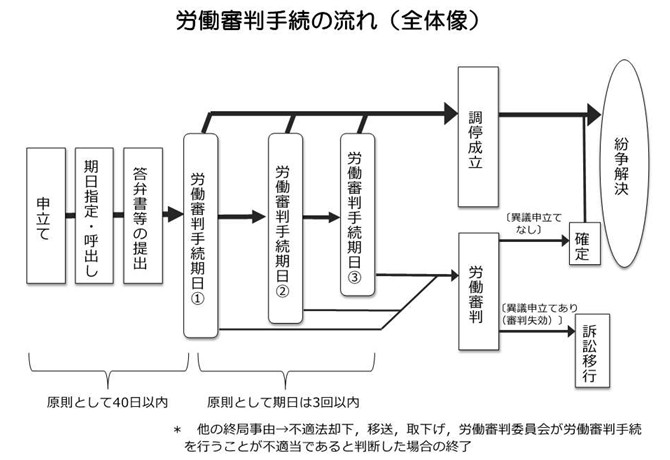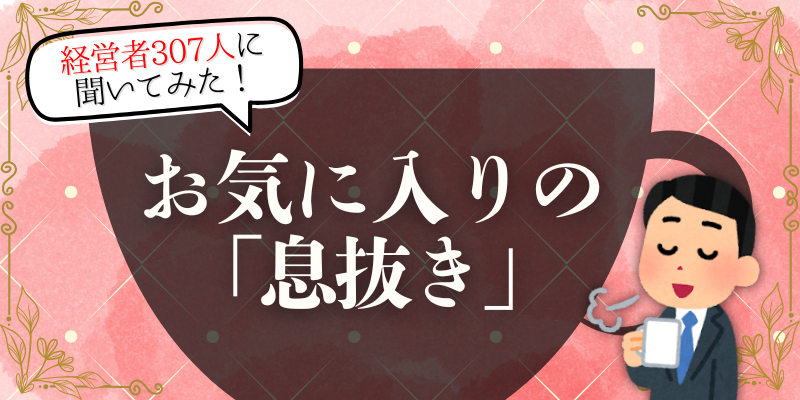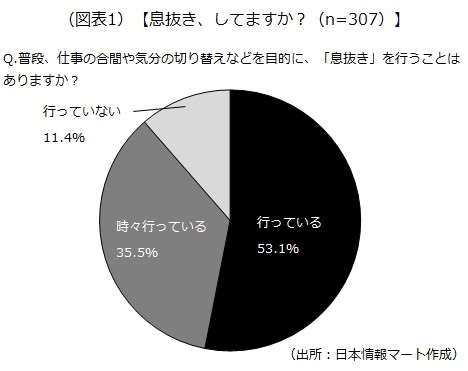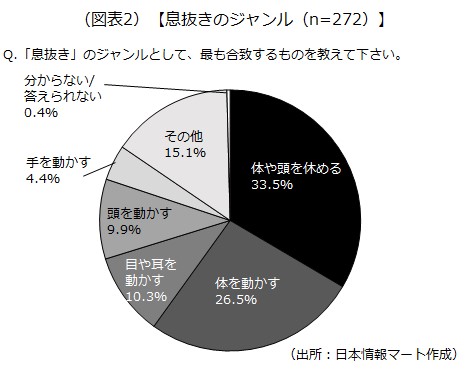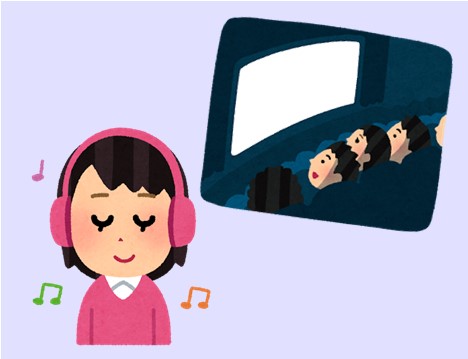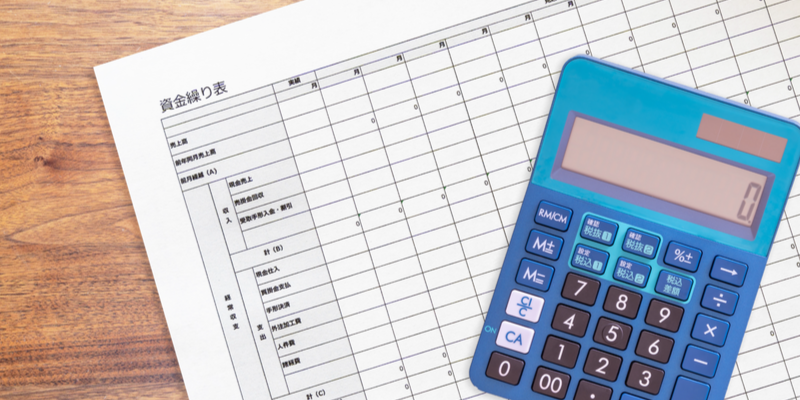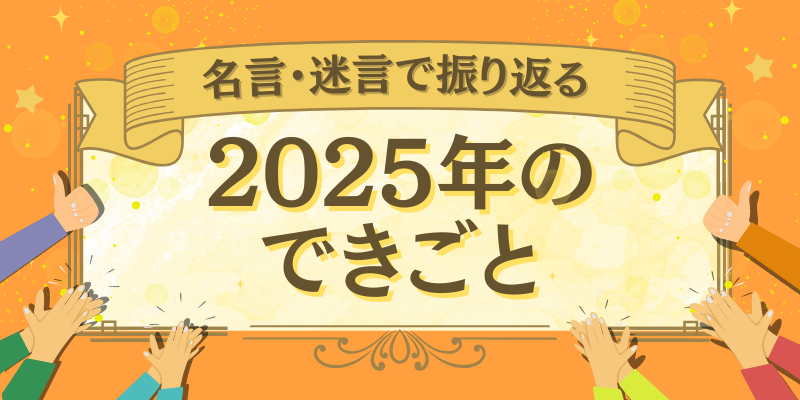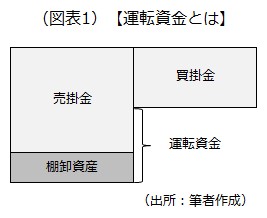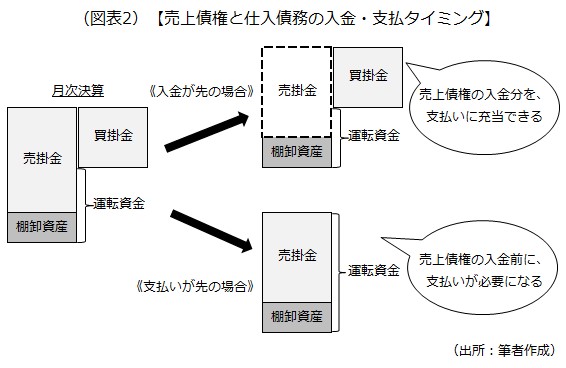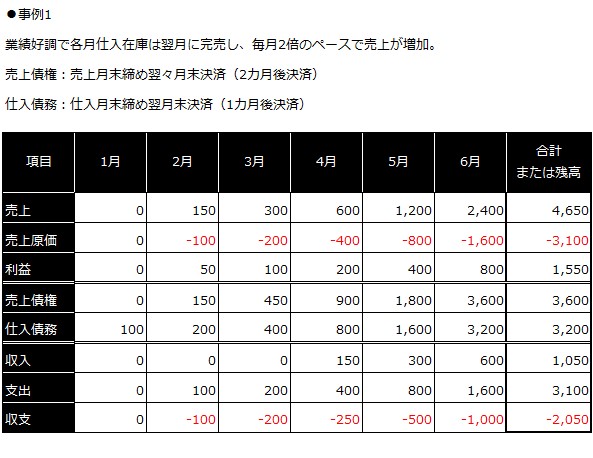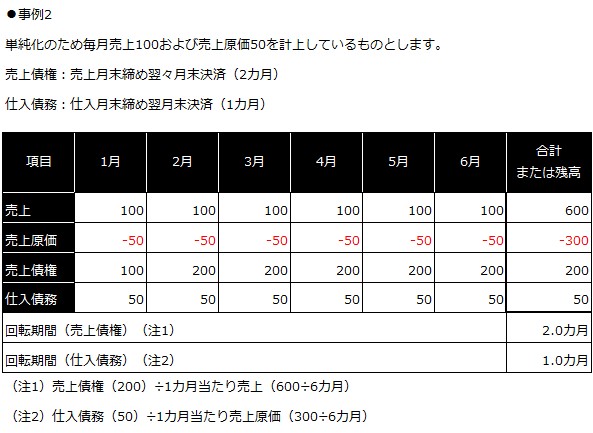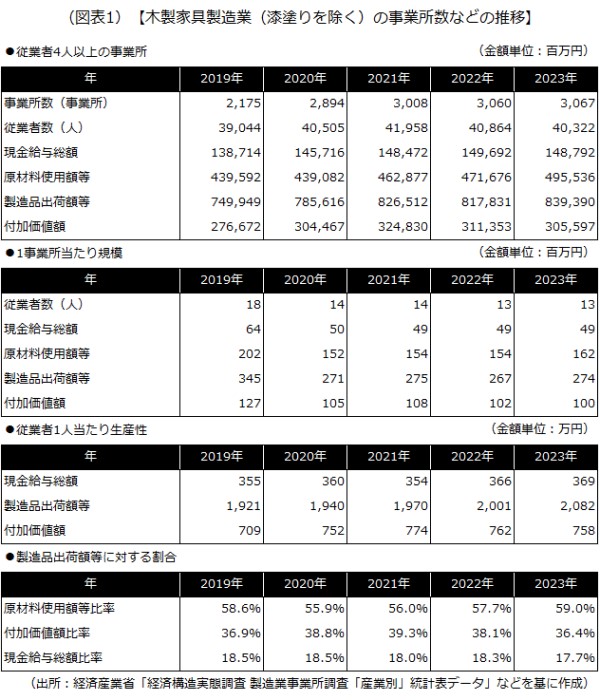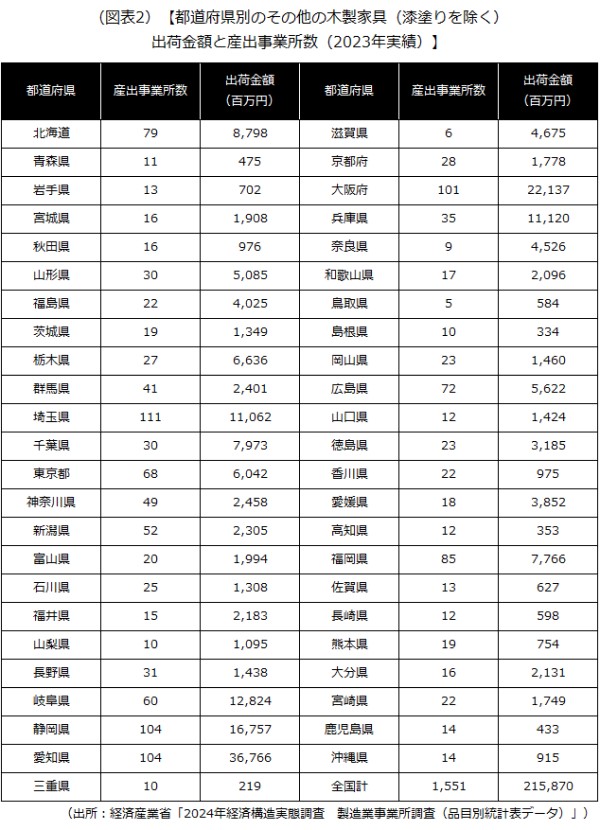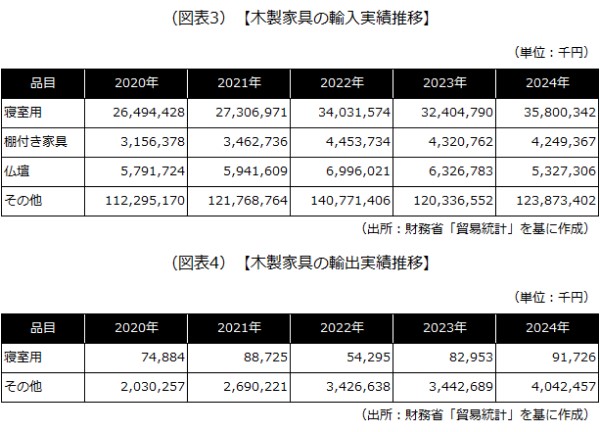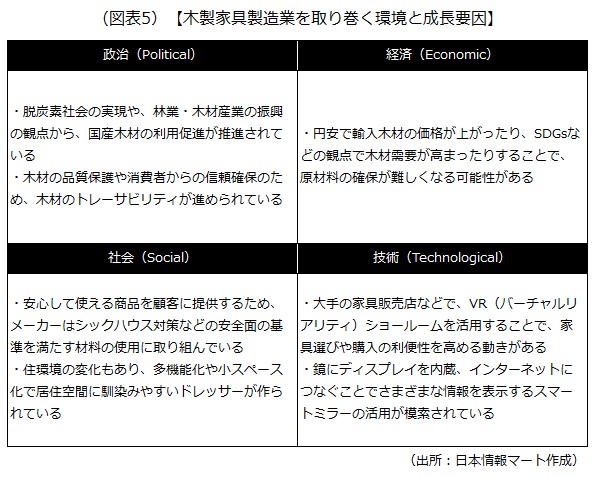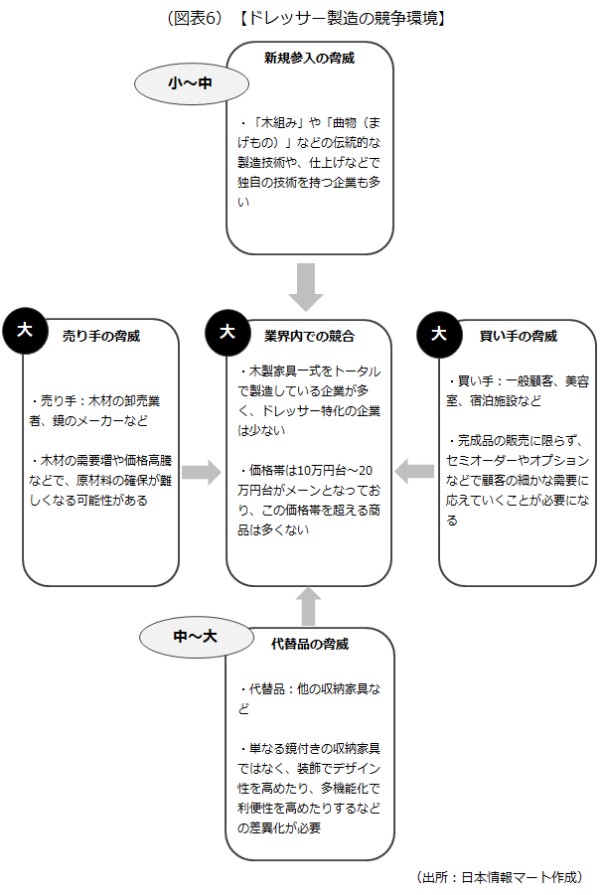早いもので、2025年もいよいよ終わりが近付いています。1月はドナルド・トランプ氏が米国大統領に再就任し、10月は高市早苗氏が日本初の女性首相に就任するなど、さまざまなニュースがありました。2025年に何が起きたのか。名言・迷言とともに振り返ってみましょう!
(1月)トランプ大統領再就任! 日米関係の今後は?
1)ドナルド・トランプ氏が第47代米大統領として再就任
「アメリカの黄金時代が今から始まる(the golden age of America begins right now)」(ドナルド・トランプ)(*)
(*)The White House「Inaugural Address」(2025年1月20日)
米国の第47代大統領に、共和党のドナルド・トランプ氏(以下「トランプ大統領」)が就任しました。就任演説で、トランプ大統領は「アメリカの黄金時代がいまから始まる」と述べ、バイデン前大統領の路線から、大幅な転換を図りました。
何かと話題のトランプ大統領。関税措置をめぐる日米交渉(7月に合意が成立)、2019年以来5年ぶりの来日(10月)なども世間を賑わせました。
2)石破茂氏が施政方針演説
「楽しい日本」(石破茂)(*)
(*)首相官邸「第217回国会における石破内閣総理大臣施政方針演説」(2025年1月24日)
当時、日本の内閣総理大臣だった石破茂氏が施政方針演説を行い、その中で、故・堺屋太一氏の「楽しい日本」という言葉を引用しました。楽しい日本とは、「今日より明日はよくなる」と実感できる国家とされています。
トランプ大統領と同様に何かと話題の石破氏でしたが、7月投開票の参議院議員選挙において、自由民主党は歴史的な大敗を喫し、10月に石破内閣は総辞職することとなりました。
(2月)OpenAIとソフトバンクが提携。AIは次のステージへ!
1)OpenAIとソフトバンクが、最先端AIの開発・販売について合意
「AGI革命は企業から始まる」(孫正義)(*)
(*)ソフトバンクニュース「OpenAIとソフトバンクグループが提携。企業向け最先端AI『クリスタル・インテリジェンス』を世界に先駆け日本で提供へ」(2025年2月5日)
ChatGPTで知られる米国のOpenAIとソフトバンクが、最先端AI「クリスタル・インテリジェンス(Crystal intelligence)」の開発・販売に関するパートナーシップを発表しました。クリスタル・インテリジェンスには、AIが学習したデータがその企業専用に最適化され、他社に利用されないという特徴があります。
ソフトバンクの孫正義氏は、近い将来訪れるAGI(汎用人工知能)やASI(人工超知能)の世界に向けて、一気に開発を進めていきたいと強調しました。驚くべきスピードで進化するAIの動向から目が離せません。
2)新宿アルタ、45年の歴史に幕
「新宿東口にまた来てくれるかな?」「いいとも~!」(末広泰之)(*)
(*)各種ニュースサイトなど
1980年の開業以来、新宿の待ち合わせスポットとして多くの人々に親しまれてきた商業施設「新宿アルタ」が2月末で閉館となり、45年の歴史に幕を閉じました。
フジテレビ系の人気番組「森田一義アワー 笑っていいとも!」の公開収録が行われていたことでも有名で、閉店セレモニーでは番組のおなじみのやり取りになぞらえて、店長の末広泰之氏が「新宿東口にまた来てくれるかな?」と呼びかけ、集まった人々が「いいとも~!」と声を上げました。
(3月)東日本大震災から14年……被災地の人々の思いは?
1)東日本大震災から14年
「自然の脅威に備えることや、安全神話は絶対ではないことを伝え続けなければなりません」(内堀雅雄)(*)
(*)福島県「福島県知事メッセージ『2025年3月11日のメッセージ』」
日本国内で観測史上最大規模、世界でも4番目の規模の地震とされる東日本大震災(2011年3月11日)から14年が経ちました。福島県知事の内堀雅雄氏は、犠牲者や遺族の人々に哀悼の意を示すとともに、福島県が2026年に150周年を迎えることに言及し、「未来図に彩りを加えながら、明るく豊かな福島県を築いていく」と述べました。
7月には、ロシア極東のカムチャツカ半島の沖合で発生した巨大地震に伴って津波注意報・警報が発表され、広範囲にわたり、多くの人が猛暑の中で避難を余儀なくされました。いざというとき、家族や従業員を守れるよう、日ごろからの備えを欠かさずにおきましょう。
2)SAMURAI BLUE(日本代表)、8大会連続でのFIFAワールドカップ出場が決定!
「厳しい戦いを乗り越えた選手たちはヒーローです」(森保一)(*)
(*)日本サッカー協会「【Match Report】SAMURAI BLUE、バーレーン代表に2-0勝利で8大会連続ワールドカップ出場決定」(2025年3月20日)
SAMURAI BLUE(日本代表)が、FIFAワールドカップ26アジア最終予選でバーレーン代表と対戦。2-0で勝利し、日本は8大会連続、8度目となるワールドカップ出場を勝ち取りました。試合後にピッチ上で開催された突破決定セレモニーでは、森保一監督が選手たちを労い、応援してくれた人たちへの感謝の言葉を述べました。
2026年北中米大会の組み合わせ抽選会は2025年12月に行われ、大会は2026年6月11日に開幕します。
(4月)大阪・関西万博が開幕! 日本での万博開催は20年ぶり
1)大阪・関西万博が開幕!
「未来社会の実験場(People’s Living Lab)」(*)
(*)大阪・関西万博ウェブサイト「EXPO PLL Talks」
大阪・関西万博(EXPO2025大阪・関西万博)が開幕しました。「未来社会の実験場(People’s Living Lab、PLL)」は、万博のテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」を実現するためのコンセプトです。
日本で万博が開かれるのは2005年の愛知万博(愛・地球博)以来、20年ぶり。最新モビリティの「空飛ぶクルマ」、新しい外食のあり方を探る「ORA外食パビリオン」など見どころ盛りだくさんのイベントとなりました。
2)フランシスコ教皇が脳卒中・心不全で死去
「核兵器のない世界が可能であり必要である(Convinced as I am that a world without nuclear weapons is possible and necessary)」(フランシスコ・ローマ教皇)(*)
(*)カトリック中央協議会「教皇の日本司牧訪問 教皇のスピーチ 核兵器についてのメッセージ 長崎・爆心地公園、11月24日」
2025年4月21日、フランシスコ・ローマ教皇が脳卒中・心不全のため亡くなりました(享年88歳)。教皇は長年平和のための活動に尽力され、2019年には来日して被爆地の広島や長崎でスピーチを行い、上記の通り核兵器の廃絶を訴える言葉を述べています。
新教皇には、米国出身のロバート・フランシス・プレボスト枢機卿が選ばれ、レオ14世と名乗ることになりました。米国出身の教皇が誕生するのは初めてのことです。時を同じくして公開されていた映画「教皇選挙」も話題となりました。
(5月)コメをめぐり、2人の大臣の迷言(?)が話題に
1)元農林水産相の庶民からは理解できない感覚?
「コメは買ったことがありません」(江藤拓)(*)
(*)各種ニュースサイトなど
当時、農林水産相だった江藤拓氏が佐賀市内で行われた政治資金パーティーにおいて「コメは買ったことがない」「売るほどある」などの発言をして物議を醸しました。
江藤氏は「消費者に(備蓄米を)玄米でも手にとってほしいと強調したかった」という旨の釈明をし、発言を撤回しましたが、批判は収まらず、農林水産相を更迭されることとなりました。米価が高騰して庶民の家計を圧迫する中での迷言(?)でした。
2)前農林水産相、やる気は伝わるけれど……
「コメはもちろん買ったことがあります」(小泉進次郎)(*)
(*)各種ニュースサイトなど
江藤氏の後任で農林水産相となったのは、小泉進次郎氏。江藤氏の失言に絡めた質問をされ、上の発言が飛び出しました。小泉氏は後任として、国民の信頼を取り戻すために言ったのですが、やる気は伝わるもののどこかズレた迷言(?)となりました。
ただ、政策面では随意契約による政府備蓄米の放出などの対策を加速させ、一時的に米価を押し下げるなど、一定の成果を示しました。10月からは、防衛相として活躍している小泉氏。防衛相としてのこれからの政策にも発言内容にも注目が集まります。
(6月)巨星墜つ ミスタープロ野球 長嶋茂雄氏
1)長嶋茂雄氏が肺炎で死去
「我が巨人軍は永久に不滅です」(長嶋茂雄)(*)
(*)読売ジャイアンツ公式ウェブサイト「長嶋茂雄終身名誉監督が死去」(2025年6月3日)
野球界の枠を超え、戦後、日本の象徴の一人として国民的な敬愛を集めた「ミスタープロ野球」こと長嶋茂雄氏が、肺炎のため亡くなりました(享年89歳)。
1974年の現役引退セレモニーの際の「我が巨人軍は永久に不滅です」は、今でも語り継がれる名言と言えるでしょう。この言葉には、読売ジャイアンツへの深い愛情、自身がその一員であったことへの誇り、そして、ファンへの感謝の念が凝縮されています。
2)日本製鉄が米国の鉄鋼大手であるUSスチールの買収を完了
「当社が世界一に復帰するためには必要かつ有効な戦略」(橋本英二)(*)
(*)各種ニュースサイトなど
日本製鉄によるUSスチールの買収がトランプ大統領によって承認され、USスチールは日本製鉄の完全子会社となりました。その記者会見で、日本製鉄の橋本英二会長兼最高経営責任者(CEO)は、今回の買収の効果を改めて強調しました。
政治問題化した同事案ですが、双方にもたらす価値を丁寧に確認していった結果、合意に至ったとされます。その後、橋本氏は各種メディアからのインタビューで、USスチールなどにおける生産を拡充し、世界での生産量を「1億トンに増やす」と話しています。
(7月)劇場版「鬼滅の刃」が公開、お前も鬼にならないか?
1)劇場版「鬼滅の刃」が公開
「お前も鬼にならないか?」(猗窩座)(*)
(*)鬼滅の刃公式サイト「アニメで聞けるかも!? 『鬼滅の刃』セリフ人気投票結果発表!」
劇場版「『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」の公開が7月から始まりました。鬼になってしまった妹を人間に戻すために、主人公・炭治郎が鬼と戦う漫画を原作としたアニメ映画です。魅力的なキャラクターやクオリティーの高いアニメーションが大人気で、11月には日本映画で初めて世界興行収入が1000億円を突破しました。
「お前も鬼にならないか?」は、劇中に登場する不老不死の鬼・猗窩座(あかざ)が、強くてもやがて老いていく人間に対して言う台詞です。SNSなどではこれをもじって、長生きしてほしい人に「鬼になろう」と投げかける「鬼になろう構文」がちょっとした人気になっています。
2)イチロー氏、米野球殿堂入り表彰式典でスピーチ
「今日は、もう味わうことはないと思っていた感情を抱いています。私は3度目のルーキーになりました」(イチロー)(*)
(*)各種ニュースサイトなど
現在、MLBのシアトル・マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー(本名:鈴木一朗)氏が、アジア人選手として初めて米野球殿堂入りを果たし、ニューヨーク州クーパーズタウンでその表彰式典が行われました。
イチロー氏は英語でスピーチを行い、1992年のオリックス入団、2001年のシアトル・マリナーズ入団に続き、今回の殿堂入りで「3度目のルーキー」になったと謙虚な気持ちを表しました。同じ日本人としてMLBを切り開いた先輩・野茂英雄氏にも言及し、「野茂さん、ありがとう」と日本語で感謝を口にしたことも話題になりました。
(8月)戦後80年、広島市長が語る平和への思い
1)広島市長の松井一實氏による「平和宣言」
「決してあきらめない『ネバーギブアップ』の精神を若い世代へ伝え続けた被爆者。こうした被爆者の体験に基づく貴重な平和への思いを伝えていくことが、ますます大切になっています」(松井一實)(*)
(*)広島市「令和7年(2025年)平和宣言」
広島市では毎年8月6日に、平和記念式典を行い、広島市長が「平和宣言」を世界に向けて発表します。今年は市長の松井一實氏が、被爆者の1人で日本原水爆被害者団体協議会の代表委員だった坪井直氏の「ネバーギブアップ」という言葉を引用したことが注目を集めました。
2025年は戦後80年の節目に当たります。世界では今なお多くの人々が戦争や紛争で苦しんでおり、平和とは何なのかを改めて考えてみる必要があるかもしれません。
2)AIの将来に言及したエヌビディア代表の発言が話題に
「新たな産業革命が始まった。AI競争は始まっている」(ジェンスン・フアン)(*)
(*)各種ニュースサイトなど
米国半導体大手エヌビディアの代表ジェンスン・フアン氏が、AIチップへの投資ブームが5年間で数兆ドル規模の市場に拡大する見通しであることを示し、上記の発言をしました。7月には株価が時価総額4兆ドルの壁を超えたエヌビディア、AIの最先端を行く代表の発言には重いものがあります。
もっとも、最近はGoogleが開発した「TPU」の台頭や、メタによるアルファベット製AI半導体の購入なども報道されており、今後のAI業界はエヌビディア一強体制ではなくなっていくのではないかという意見もあります。
(9月)アルテミス計画、前進! 人類は再び月へ
1)アルテミス計画に基づき、2026年に月を周回することが決定
「私たちは、50年以上ぶりの月への帰還という歴史的瞬間を、最前列から目撃しようとしています(We together have a front-row seat to history. We’re returning to the moon after over 50 years.)」(ラキーシャ・ホーキンス)(*)
(*)各種ニュースサイトなど
月面への有人着陸・長期滞在を通して持続的な月探査を行う「アルテミス計画」。これに基づき、米国などの宇宙飛行士が宇宙船「オリオン」で、2026年2月にも月を周回することが正式に決まりました。
宇宙飛行士による持続的な月探査は1960年代から70年代にかけて行われたアポロ計画以来で、米航空宇宙局(NASA)探査システム開発ミッション本部のラキーシャ・ホーキンス氏は、「私たちは歴史的な出来事を最前列から目撃しようとしている」と述べました。
2)NHK連続テレビ小説「あんぱん」が完結
「絶望の隣はにゃ、希望じゃ」(柳井寛)(*)
(*)各種ニュースサイトなど
3月から放送が開始されたNHK連続テレビ小説「あんぱん」が最終回を迎えました。漫画家のやなせたかし(本名:柳瀬嵩)氏をモデルにした柳井嵩が、主人公である妻「のぶ」らに支えられ、戦争や貧困を乗り越えながら「アンパンマン」にたどり着く物語です。
「絶望の隣はにゃ、希望じゃ」は嵩の伯父・寛の台詞。やなせ氏自身が2011年に「絶望の隣は希望です!」というエッセイを出しており、主人公が逆境に立ち向かう作品を象徴する言葉、やなせ氏自身の人生観の表れとして話題になりました。
(10月)日本初の女性首相、高市早苗氏! 就任時の挨拶が流行語大賞に!
1)高市早苗氏が、第104代内閣総理大臣に就任
「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」(高市早苗)(*)
(*)各種ニュースサイトなど
高市早苗氏が第29代自由民主党総裁、さらに第104代内閣総理大臣に選出されました。自由民主党総裁と内閣総理大臣、どちらも女性が就任するのは日本で初めてのこと。国内だけでなく、海外からも注目が集まりました。
総裁就任時の挨拶では、「全世代総力結集で、全員参加で頑張らなきゃ(日本は)立て直せない」として、「私自身もワークライフバランスという言葉を捨てます。働いて働いて働いて働いて働いてまいります」と発言したことが話題に。高市氏の覚悟を評価する声、時代に逆行しているという声、さまざまな意見が飛び交い、「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」は2025年の流行語大賞になりました。
2)京都大学の北川進氏、大阪大学の坂口志文氏にノーベル賞
「ノーベル賞の発表をされると、“ただのおじさん”の扱いが急に変わるんです」(北川進)(*)
(*)各種ニュースサイトなど
京都大学特別教授の北川進氏が、金属イオンと有機化合物とを結合させた「多孔性金属錯体(MOF)」の開発により、ノーベル化学賞を受賞しました。北川氏は記者会見で、「“ただのおじさん”の扱いが急に変わる」と、今回の受賞についてユーモアを交えて語りつつ、研究者を志す人たちに「ますますチャレンジ精神でやっていただきたい」とエールを送りました。
もう1人、大阪大学免疫学フロンティア研究センター特任教授の坂口志文氏もノーベル生理学・医学賞を受賞しました。坂口氏は、自己に対する異常な免疫反応やアレルギーなどの過剰な免疫反応を抑えるのに必要な「制御性T細胞」の発見・研究が認められ、受賞に至りました。
(11月)将棋の藤井聡太氏、史上最年少で「永世三冠」を達成!
1)藤井聡太氏が永世棋聖、永世王位に続き、「永世竜王」の資格を獲得
「苦しい状況でも、あきらめずに指したのが実を結んだというところも、少しはあったのかなと感じています」(藤井聡太)(*)
(*)各種ニュースサイトなど
将棋の第38期竜王戦七番勝負で藤井聡太氏(竜王)が佐々木勇気氏(八段)を下し、5連覇を達成しました。これにより、藤井氏は永世棋聖、永世王位に続き、3つ目の永世称号「永世竜王」の資格を獲得しました。
史上最年少(23歳)にして、史上3人目の「永世三冠」を達成した藤井氏。これからの活躍にますます注目が集まります。
2)ドジャースの山本由伸氏がワールドシリーズの最優秀選手(MVP)に
「もう無心で、野球少年に戻ったような、そんな気持ちでした」(山本由伸)(*)
(*)各種ニュースサイトなど
野球のMLB・ワールドシリーズで、ドジャースがブルージェイズを延長の末に5-4で下し、2連覇を達成しました。最終第7戦で投手として登板した山本由伸氏は、第6戦からの連投となる中、ブルージェイズ打線を封じ、勝利に貢献。試合後のインタビューで「野球少年に戻ったような気持ち」と発言したことが話題になりました。
山本氏は今回の功績により、日本人では松井秀喜氏以来2人目となる、ワールドシリーズの最優秀選手(MVP)に選ばれました。
(12月)2026年1月 箱根駅伝に向けて! 優勝常連校の秘策は?
1)青山学院大学、箱根駅伝に向けて「輝け大作戦」を発表!
「走る10人だけではなく、チーム全員が輝いてほしい。名付けて『輝け大作戦』です」(原晋)(*)
(*)各種ニュースサイトなど
2026年1月に行われる第102回箱根駅伝(東京箱根間往復大学駅伝競走)のチームエントリーが行われ、青山学院大学の原晋監督が、毎年恒例の「作戦名」を発表しました。今回の作戦名は「輝け大作戦」。部員一人ひとりがそれぞれの立場で一番星のように輝き、チーム一丸となって挑むというものです。
2024年は「負けてたまるか!大作戦」、2025年は「あいたいね大作戦」で優勝を勝ち取った青山学院大学。3年連続9度目の優勝を狙う選手たちが、来年1月、どのような走りを見せてくれるのか、今から期待が高まります。
2)THE MANZAI 2025! ビートたけし氏が「たけし賞」に選んだ漫才コンビは?
「俺このコンビ、凄い好きになっちゃって。凄い形ができちゃってて、安泰だなこのコンビは」(ビートたけし)(*)
(*)各種ニュースサイトなど
フジテレビで毎年12月に放送される「THE MANZAI マスターズ」は、漫才界の最前線をひた走るトップランナーが集結し、ネタを披露する人気番組です。現在は優勝を競うルールはありませんが、最高顧問であるお笑い芸人のビートたけし氏が、自身が最も面白いと感じた出演者に「たけし賞」を贈る一幕があります。
サンドウィッチマン、中川家、博多華丸・大吉、爆笑問題など、実力派の漫才師たちが次々とネタを披露する中、たけし賞が贈られたのは「ミルクボーイ」。「うちのオカンが言うには……」から始まる独特の掛け合いが人気のコンビで、2019年にはテレビ朝日の人気番組「M-1グランプリ」でも優勝を勝ち取っています。ビートたけし氏は、ミルクボーイの完成度の高い漫才を高く評価し、たけし賞と共に上記の言葉を贈りました。
以上(2025年12月更新)
pj10091
画像:日本情報マート