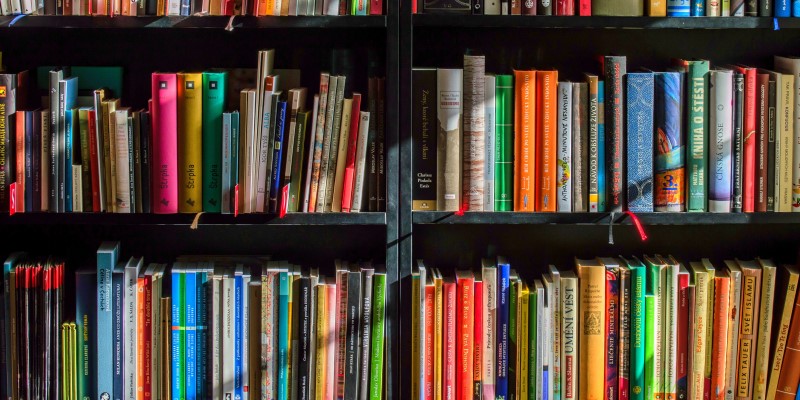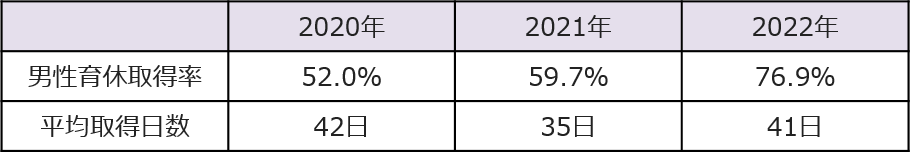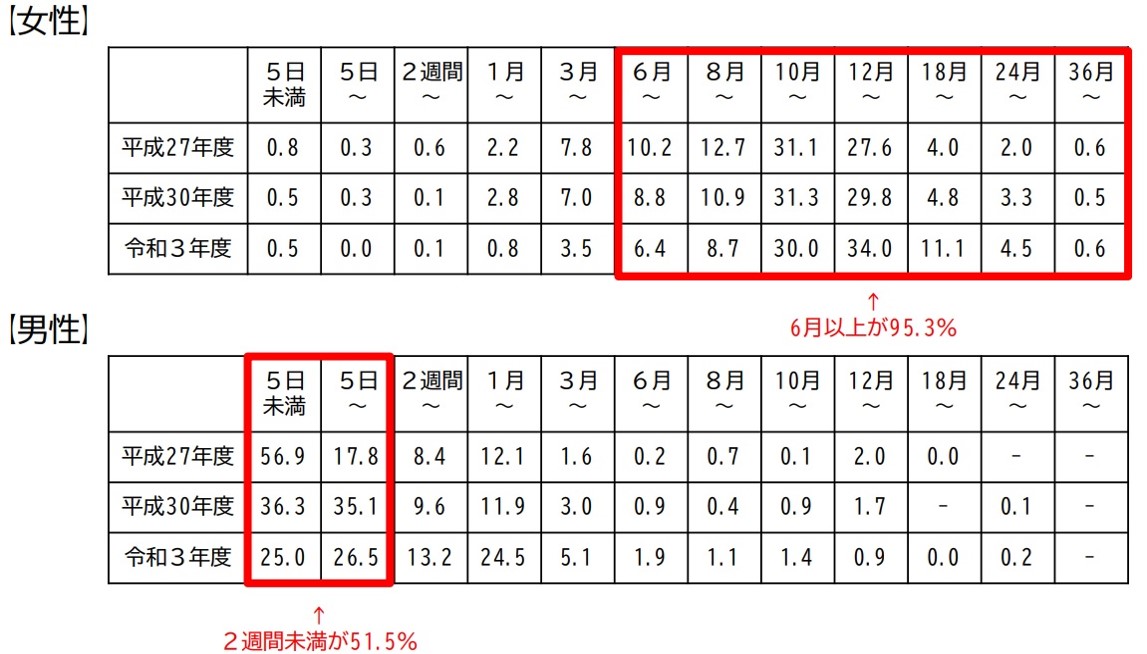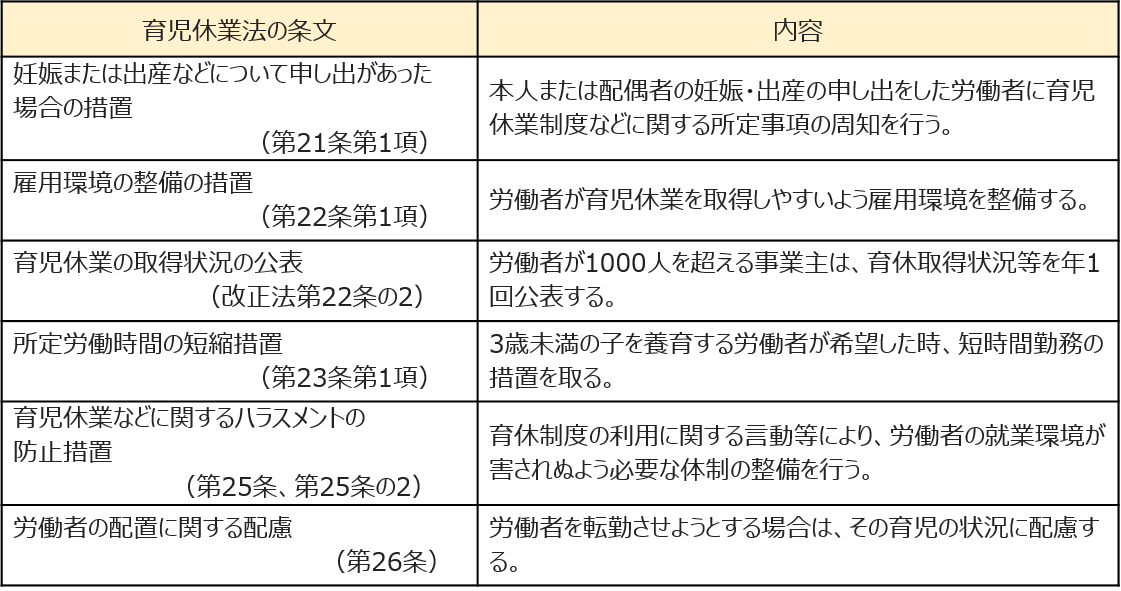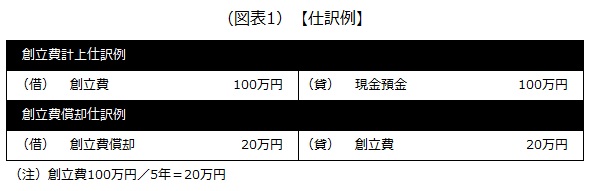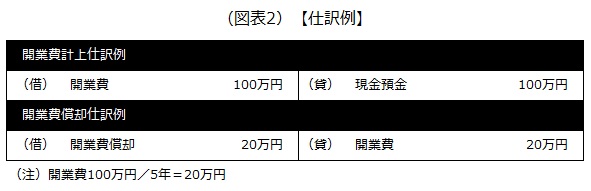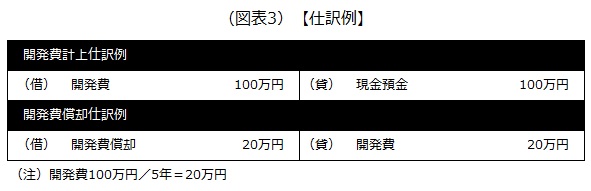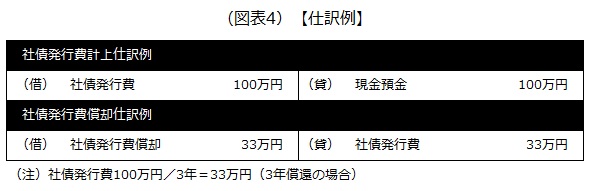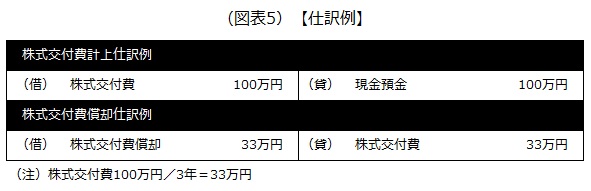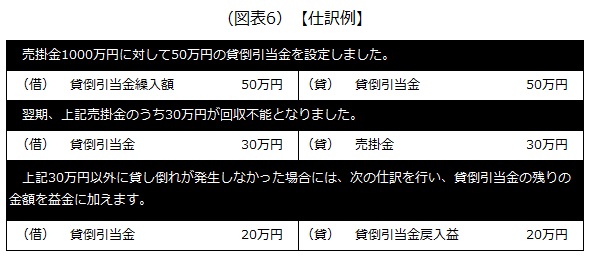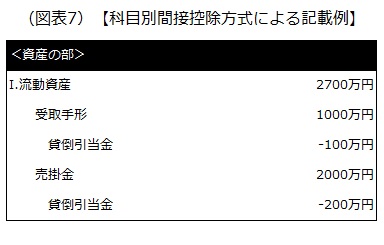書いてあること
- 主な読者:採用に悩むすべての経営者。共感型採用に興味のある中小企業の経営者、人事担当者、採用担当者
- 課題:限られた採用予算で優秀な人材を確保したいがうまくいっていない。待遇や給与面で比較されない、独自の魅力で勝負できる採用ブランディングを実現したい。自分たちの魅力、やっていることを理解し、賛同してくれる人を採用したい
- 解決策:なぜ中小企業ほど共感型採用が大切なのかを知る。共感型採用の具体的なやり方を知り、自社に活かす方法を考える。自社に隠された魅力を社員インタビューで掘り起こし、言語化する
1 共感型採用とは
共感型採用。聞き慣れない方も多いかもしれません。共感型採用とは、
待遇や給与面に焦点を当てるのではなく、企業のビジョンや理念への共感を通じて応募者を採用する手法
です。
ここ最近「求人広告に掲載しても、以前のように人が採用できなくなってきた」というお悩みを、企業様からよくお聞きするようになりました。
人材獲得競争が激化し、従来の方法では人材を採用できなくなる時代。長く活躍してくれる人材の採用に大変有効なのが、自社の事業やビジョン、思いへの共感を通じて採用を行う「共感型採用」なのです。
2 中小企業における共感型採用の重要性
中小企業は、大手企業に比べて採用予算を確保しにくく、待遇や福利厚生面でも大手企業を上回ることがなかなか難しい状況にあります。
「では、中小企業は、優秀な人材を確保できないのか」と言うと、決してそうではありません。
中小企業には、独自の技術、ユニークなサービス、経営者や社員の熱い思い、柔軟な働き方といった、その会社ならではの素晴らしい魅力がたくさんあります。そうした魅力を、自信を持って応募者に伝えることで、待遇や福利厚生面などの土俵ではなく、独自の価値で勝負できるようにする。そうすれば、自社本来の魅力や価値を理解した上で入社し、長く活躍してくれる人を採用しやすい状態を作ることができます。
待遇や福利厚生面といった「他社とも比較しやすい土俵」ではなく独自の価値で勝負。これはある意味、自分たちだけの採用スタイル、採用戦略ともいえるでしょう。
結果、中小企業でも、人材紹介や求人広告に頼り過ぎることなく、採用コストを抑え、費用対効果の高い採用手法を確立できるようになるということです。
3 共感型採用を実現するための具体策
では、具体的に「共感型採用」をどのように実現していくか、いくつかポイントを見ていきましょう。
1)自社の採用ページの文面の見直し
もし、自社の採用ページが既にあり、ある程度のアクセスがあるのならば、まずはその文章を見直してみることをオススメします。特に意識したいのは、以下の3点です。
- どのような事業をしているのか、強みは何かを、その業界ではない人にも分かりやすく伝えること
- なぜ今の事業をやっているのか、創業の思いやめざす未来を伝えること
- 実際に働くイメージが湧くように、社風や企業文化を伝えること
このあたりに重点を置いて、現在の採用ページの文章ではそれらが正しく伝わっているのかを見直し、文章を構成してみましょう。
2)採用媒体(プラットフォーム)の活用
共感型採用の実現と相性が良いのが、例えば「Wantedly(ウォンテッドリー)」などの採用媒体の活用です。
Wantedlyには、待遇や給与面は一切書かず、事業内容や思いを発信することで応募者を獲得できるという特徴があります。ユーザーは300万人、やりがいや自己実現に重きを置く、中小企業やベンチャー企業と相性の良い応募者が多い媒体でもあります。
もし、自社の採用ページが今は無かったり、そこまでアクセスが多くなかったりするようであれば、Wantedlyのように、すでにユーザーが多くいる採用プラットフォームを使うことをおすすめします。
当社(筆者の会社)のお客様もこのWantedlyを活用し、スタートアップ企業ながら、募集記事掲載から4カ月で、ベンチャーマインドの高い営業パーソン2名の採用に成功されました。
3)求人広告の内容の見直し
「現在求人広告を出しているのに、うまく採用できない」という場合は、求人広告の冒頭に書く文章の見直しをするのも一つの方法です。
- どのような事業をしていて(事業内容)
- なぜその事業をやっていて(ミッション)
- どのような未来を作りたいか(ビジョン)
を意識し、待遇よりも思いや価値に共感してもらえる文章を整えてみましょう。
4 自社の魅力の発掘は社員インタビューで
「そうは言っても、自社の魅力がなかなか分からない。言語化しにくい」という企業様も多くおられます。
そんな時にはぜひ、社員インタビューの実施をおすすめします。
社員インタビューは、文章にすることで採用ページやホームページに掲載する記事の素材にもなりますので、採用や広報担当者の方に余裕があれば、ぜひ実施してみてください。現場で働く社員の生の声を聞くことで
- 応募者は自社のどこに魅力を感じて入社するのか
- 長く活躍している社員にとって、自社のどこが魅力なのか
といった、自社独自の魅力を新たな視点から発掘することができます。インタビューでは、現場で働くからこそ分かる、具体的な仕事内容や職場の雰囲気、企業文化などを聞き出し、応募者の共感を集める採用ブランディングを実現していきましょう。
5 まとめ
人材採用難のこの時代。待遇に焦点を当てるのではなく「共感型採用」を導入することは、
限られた採用予算を効果的に活用し、自社に適した優秀な人材を確保し、企業競争力を向上させるために最も適した採用手法
です。自社独自の魅力を明確にし、他社の成功事例を参考にしながら、ぜひ、共感型採用を実践されてみてはいかがでしょうか。
以上(2023年8月)
pj00675
画像:Rawpixel.com-Adobe Stock