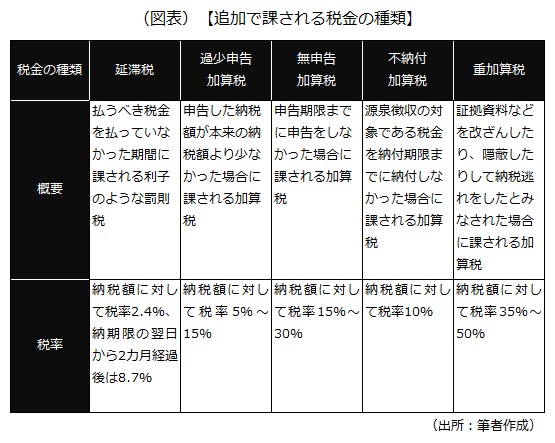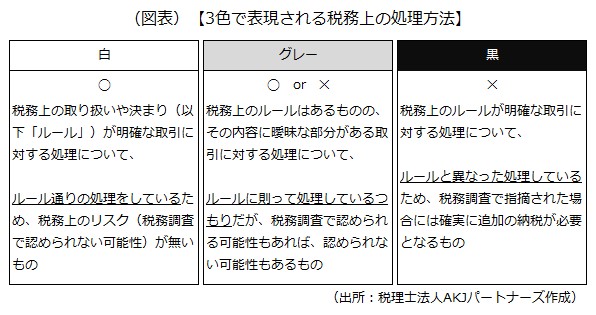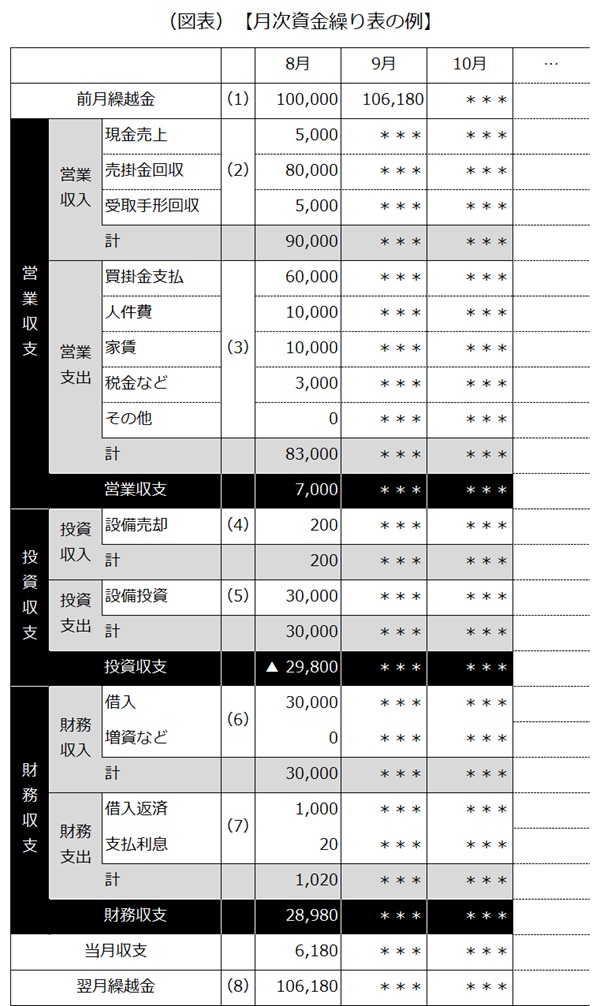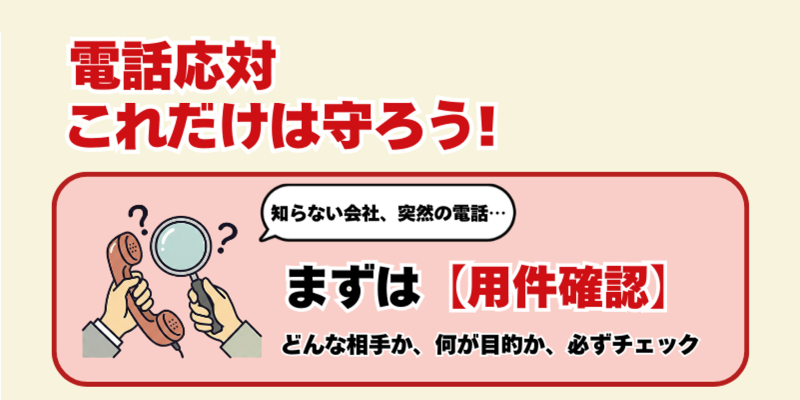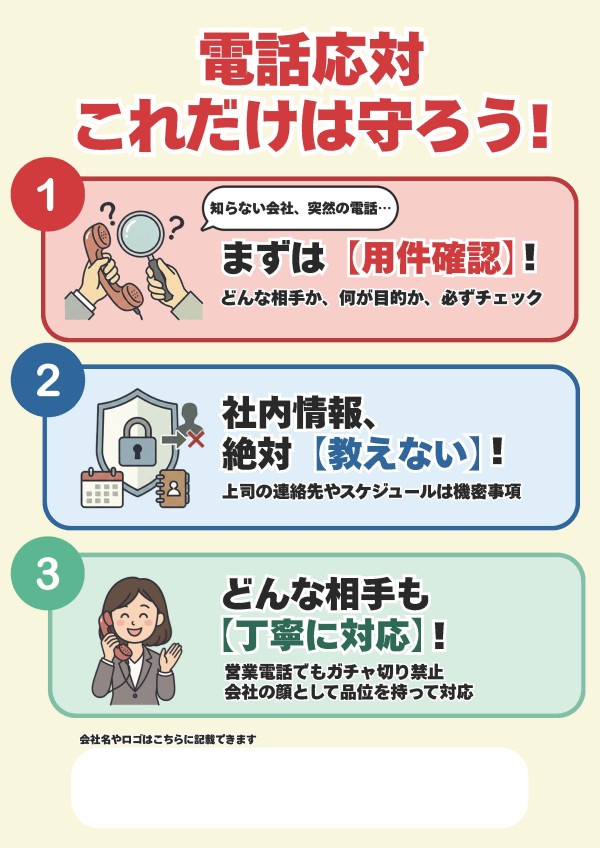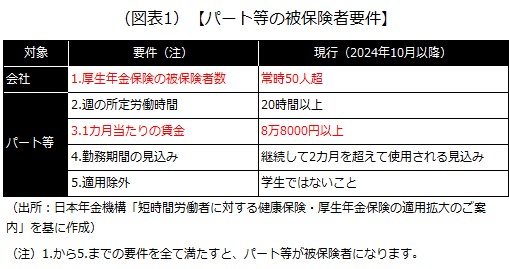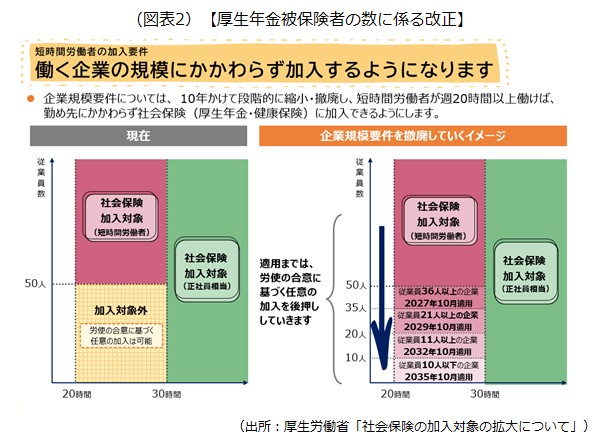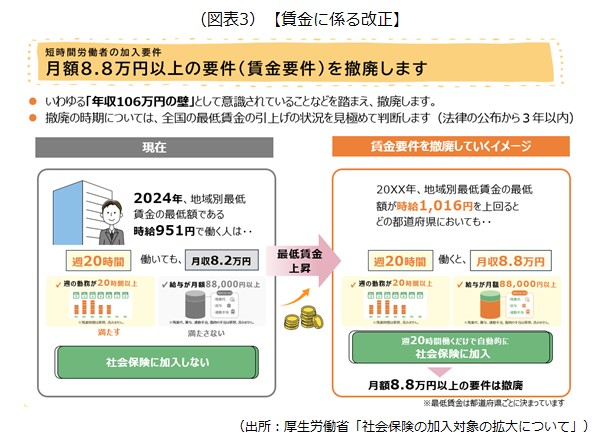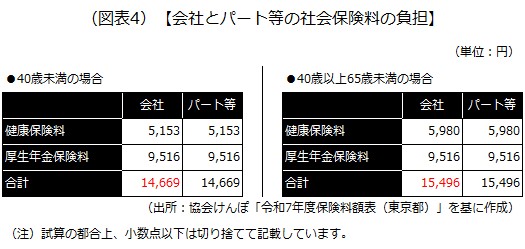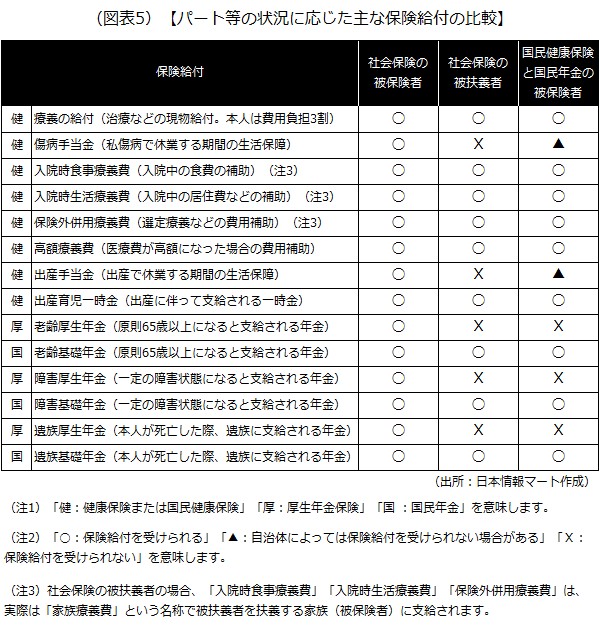目次
1 何も知らないと大ごとになるのが社長の離婚
「結婚した3組に1組が離婚する」と言われる現代、知り合いや家族から離婚をした、もしくは離婚の危機にあるという話を聞く機会もあるでしょう。
社長の離婚の場合、
離婚に際して夫婦間で決めるべき条件(別居中の婚姻費用、財産分与の対象や割合、親権者の指定、養育費など)をめぐり、長期間にわたってこじれがち
です。社長の離婚特有の「お金」に関する問題を知らないがゆえに、その都度、大ごとになってしまうからです。
例えば、財産分与は夫婦の資産を合算して(基本的に)互いに2分の1ずつ分け合うのですが、
婚姻後に築いた個人名義の資産は全て財産分与の対象となる
というルールがあります。婚姻後に購入した個人名義の土地に自社ビルなどが建っている場合などは、その評価額は高くなり、財産分与で支払う額も莫大なものになってしまいます。一方、会社名義の資産は財産分与の対象にならないので、このことを知っていれば事前に対策を講じることができます。
離婚は、社長にとっても身近なリスクです。仮に今、夫婦関係が円満であっても、先々のリスク管理の一つとしてこうした情報を知っておくに越したことはないでしょう。
この記事では、社長の離婚問題に詳しい弁護士監修の下、特にこじれがちな
別居中の婚姻費用、財産分与、親権者の指定、養育費
について分かりやすく解説し、どうすればリスクを抑えられるかも紹介します。
この記事を読むことで、自身のリスクに備えるだけでなく、離婚のリスクを抱えている社長仲間や親しい取引先に対して、有用なアドバイスをしたり、理解ある相談者になったりすることもできるでしょう。
2 財産分与……の前に別居の問題が立ちはだかる
1)別居期間中に相手の生活費を支払わなければならない
社長の離婚で大きな問題として取り上げられるのは財産分与なのですが、これはあくまで法的に婚姻関係を解消するに至った段階の問題です。実はその前、離婚に至るまでの段階で大きな問題となるのが、
別居期間中の婚姻費用の支払い
です。
婚姻費用とは夫婦がお互いに分担し合うべき生活費のことです。民法では「夫婦はお互いに扶助し合わなければならない」と定めており、それは別居期間中にも適用されます。
具体的な金額はお互いの合意の上で決められるのですが、裁判所が相場を発表しています。
■裁判所「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究 標準算定方式・算定表(令和元年版)」■
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/
例えば、子どもがいない夫婦で妻が専業主婦などで収入はゼロ、夫が役員報酬として2000万円もらっているケースだと、妻には月30万円程度の婚姻費用を支払うことになります。年間にすると360万円、別居期間が3年以上になれば1000万円を超えます。
離婚におけるお金の問題というと財産分与を真っ先にイメージしがちですが、その前に、長い別居期間中の経済的負担も大きいことを知っておく必要があります。
2)社長は別居期間が長くなりがち
弁護士へのヒアリングによると、
「協議離婚(夫婦が話し合いにより、離婚に合意する)でない場合、調停離婚や裁判離婚になる。調停離婚であれば半年から1年程度で離婚が成立することも多いが、社長の場合、調停では解決せず、離婚が成立するまで5~6年掛かるケースも珍しくない(それ以上の時間がかかることもある)」
とのことです。
ここまで長引く理由は、後述する財産分与の手続きに時間が掛かるというのもあるのですが、一番は別居期間が長くなるそうです。
「相手側からすれば、離婚時の財産分与に加え、別居期間が長ければ長いほど婚姻費用を多く受け取れる。社長が男性の場合、妻が専業主婦というケースが多く、婚姻費用も多額になりやすい。だから、妻は別居して生活費をもらい続けるほうが有利と判断し、離婚をせずに別居期間を長引かせる選択をすることが多い」
押さえておきたいのは、夫側が早く離婚したいと思っても、
簡単には離婚できない(妻が協議離婚に応じてくれない)
ということです。
基本的に、離婚はお互いの合意がないとできません。一方が離婚に応じなければ「調停」、それでも合意に至らなければ「裁判」をすることになりますが、裁判になっても、法律上に定められている離婚事由がないと認められません。
また、不貞を働いたり暴力を働いたりすると、その人は「有責配偶者」とみなされます。そうすると、有責配偶者からの離婚申し立ては基本的に認められません。
そのため、夫側に有責の疑いがある場合、探偵を雇って不貞の証拠を集めて夫を有責配偶者であることを明白にすることで夫側からの離婚申し立てをできなくさせ、別居期間を長引かせるケースも多いようです。
弁護士へのヒアリングによると、
「消極的な理由により、気が付けば結果的に長い別居を選択していたという社長も一定数いる」
とのことです。消極的な理由としては、次のようなものが挙げられるそうです。
- 離婚による財産分与で現状の資産を減少することは避けたい
- 持ち株などがあり、財産分与によって会社の経営に影響が出ることは避けたい
- 別居して婚姻費用を払い続けるほうが、離婚するよりは世間体的にいい
- 長くて面倒な調停、裁判をするぐらいなら、現状維持でいい
3)「離婚後に近い状態」を早めに作るのがポイント
2)で紹介したものの他、同居のままだったり、生活費などを全て社長が支払っていたりするために、妻が離婚後の生活をイメージできず、とりあえず現状維持(離婚しない)を選択するというケースも多いようです。
弁護士へのヒアリングによると、
「弁護士としての経験上、明確な離婚事由がない場合などは、社長に対し、まず『離婚後に近い状態』にするよう勧めることが多い」
とのことです。
「例えば、同居中はライフラインや通信費などの支払いを社長名義のクレジットカードや口座から行っていることが多いので、それをやめる。そして、すみやかに別居するとともに、婚姻費用を支払い、自分の支払いは自分でしてもらうようにする。こうすることで、離婚事由となる別居期間を稼ぐとともに、離婚を受け入れられない相手に『離婚後の状態に慣れてもらう』」
4)婚姻費用を低く抑えようとする際には注意が必要
別居期間中の婚姻費用は、社長側の収入に左右されます。そのため婚姻費用を抑えようと自身の役員報酬を下げようと考えることがあります。ですが、そういった、婚姻費用を下げる目的での収入の操作は裁判所では認められないケースがあるようです。
一方、会社の資産状況などでやむを得ないと認められるケースもあり、ここは一概にはいえない複雑な問題があります。一度税理士や弁護士に相談するのがいいでしょう。
3 財産分与で揉めないための注意点
1)会社名義の資産は財産分与の対象外
別居期間を経て、離婚の条件を詰める段階になると、いよいよ財産分与の問題が浮き彫りになります。
財産分与は、
夫婦どちらの名義の資産であっても、婚姻後に築いた個人の名義のものは合算して対象になるが、会社名義のものは対象外になる
というのが基本です。
会社名義の資産は社長個人のものとは別で会社のもの、とみなされますが、
会社名義の資産ではあるが、実質は家族のために使うなどして個人と会社の区別が曖昧
といった場合には、夫婦の共有財産であるとして財産分与の対象になる場合もあるので、迷ったらその都度弁護士に相談したほうがいいでしょう。
2)揉めがちなのは財産分与の対象の特定と評価額
財産分与の対象になるのは、預貯金や不動産(自宅の土地・建物など)の他、株、保険といった資産などです。自動車・家具・貴金属類・絵画といった動産についても婚姻中に築いたものは共有資産としてみなされるので、対象は多岐にわたります。
これらの時価などを評価した上で分与することになるのですが、この財産分与の対象物を特定し、評価するのがまず一苦労で、かなりの時間を要します。
その上で、
特に評価で時間を要するのが非上場株式
です。
上場企業の株式であれば離婚時の時価を評価額にすることができますが、非上場会社の株式の場合は市場で取引されていないので、評価自体が難航したり、評価方法をめぐって揉めたりするケースもあります。
3)自社株も2分の1を渡さないといけない?
社長が保有する自社株も、個人名義のものであれば財産分与の対象となります。そうなると財産分与によって2分の1の株式を譲渡してしまっては会社の経営権に影響が出てしまいます。
そのため、現実には、
社長が自社株を100%保有する代わりに、自社株の評価額の2分の1に相当する金銭を支払う
という合意をするケースがほとんどです。
中小企業は基本的に非上場会社なので、相手側としても、買い主を見つけるのも大変な株式よりも、現金でもらったほうがいいという判断になるからです。
相手が役員などで自社株を保有している場合も、それをすべてこちらがもらう代わりに対価を支払うということになります。
弁護士へのヒアリングによると、
「相手が妻の場合、例えば子どもが小さければ離婚後もずっと養育費をもらっていかなければならないので、夫の会社には安泰でいてほしい。また、妻自身が、離婚後に夫の会社と関わることも望まない。そのため、夫の株主比率が下がることを望む人はほとんどおらず、株式の譲渡自体で揉めることはほぼない」
とのことです。
仮に自社株の評価額が高くなり、その他の資産の評価額以上になって2分の1を現金で工面するのが難しい場合は、足りない分を分割で支払うことになります。
なお、財産分与における株式の評価額は、
別居開始日の保有株数×離婚成立日の評価額
となるので注意が必要です。
4)財産分与の割合でも揉めがち
財産分与の割合は「夫婦で2分の1ずつ」が妥当というのが原則です。
しかし、相手が専業主婦(主夫)の場合、「妻(夫)は家にいるだけで資産形成に貢献していない」といった理由で、社長が財産分与の割合を修正することを求めるケースがあります。
確かに、例えばスポーツ選手や特殊技能を持った職人など、本人の特殊な資質によって高額な所得を得て資産を築いた場合などは、相手方への財産分与の割合が減らされることもあります。
ただし、この寄与度(貢献度)については双方で揉め、調停・裁判が長引くことが多いです。また、「夫婦で2分の1ずつ」の原則により認められないケースも多々あります。この点も、迷ったら弁護士に相談するようにしましょう。
5)財産分与の対象から外すのは円満なときに
財産分与の対象となる資産を減らそうと、別居前に慌てて個人名義の資産を売却したり、会社の名義にしたりしても、その資産が財産分与の対象とされてしまうことがあります。
弁護士へのヒアリングによると、
「裁判になると、別居と財産分与を見越し、財産分与の対象となる財産から外すために財産を隠したり名義を変更したりするなどしたと評価されるものは、対象内に戻されるという例外が起こる場合がある。社長の場合、財産分与によって会社経営に影響を与えることを避ける方法を日ごろから検討、対策しておくのがベスト」
とのことです。
また、次のようなコメントもいただきました。
「別居後の稼ぎで作った財産は夫婦共有財産とはされないのが原則なので、稼ぎが多い場合、すみやかに別居して財産を増やし、それを離婚時の財産分与に上乗せする『解決金』の原資にするという考え方もできる」
4 配偶者が会社で働いている場合、離婚で解雇はできない
配偶者を役員にして役員報酬を払っていたり、事務員として雇用したりしているケースは多いでしょう。その場合、離婚を理由に解任・解雇はできません。
役員の場合、別居した時点で実質その役割を果たさないという理由で解任したいと考えても、基本的には任期があるので、任期満了を待ってそこで解任することになります。
雇用している場合でも、解雇するには会社に多大な損害を与えたり、長期にわたる無断欠勤をしたりなど、合理的な理由が必要です。どうしても解雇したい場合は、退職金を提示するなどして、合意の上で退職してもらうことになります。
5 親権問題で揉めがちなのは子どもとの面会交流
1)親権問題は妻側が有利になりやすい
夫が社長の場合、経済力の高さから子どもの親権獲得に有利に思われがちですが、実際は妻側が有利になりやすいといわれます。
裁判所は、次の点を重視してどちらが親権者にふさわしいかを判断するからです。
- これまで(同居中)どちらが主に子どもの面倒を見ていたか
- 現在(別居時)どちらが子どもの面倒を見ているか
多忙な社長は、あまり家におらず、帰りが遅いことも多いため、子と関わる時間が持てず、親権問題だと一般社員よりも認められない可能性が高いといわれます。
2)面会交流は相手が合意すれば自由にできるが……
親権者の指定については、双方で合意ができ、あまり揉めることはないようです。一方で揉めやすいのが、離婚後に子どもと非親権者が会う面会交流についてです。
離婚裁判まで進んだ場合、一般的に裁判所は「月1回数時間」程度の面会交流しか認めないといわれます。
しかし、社長の場合、
- 家族での会合が多く、そこに子どもを連れて行きたい
- 海外や国内への数泊の旅行へ一緒に行きたい
といった要望がかなり多いそうです。この場合、
親権者と子どもが合意すれば面会交流は自由
にできます。
ただし、離婚に至るほど夫婦関係が悪化し、また調停や裁判を経てさらに険悪になっている場合、親権者側が面会交流を認めなかったり、慎重になったりするケースがほとんどです。
こうしたとき、面会交流で揉めないためのポイントの一つが、養育費です。詳しくは次の章で解説します。
6 養育費は子どもの学費問題
養育費の金額は、第2章で紹介した算定表が目安になります。例えば0歳~14歳の子どもが1人いて妻の収入はゼロ、夫が役員報酬として2000万円もらっているケースだと、妻には月25万円程度の養育費を支払うことになります。
ここで揉めがちなのが、妻側がこれでは足りないと要望するケースです。主な理由として多いのが、子どもの学費です。
算定表はもともと公立学校に通わせることを念頭に算出されていますが、夫が社長の場合、妻は私学や習い事、海外留学などに年間数百万円超を掛けることも少なくありません。
弁護士へのヒアリングによると、社長の離婚ではこの学費問題で揉めるケースがかなり多いようです。
「社長が、自力でここまで来たという感覚があり、ある程度の学費は出すが後は子どもの自己判断でというマインドを持っている場合、習い事や留学など、際限なく良い教育を受けさせたいという妻側との教育観の違いが浮き彫りになり揉めてしまう」
現実としてこの養育費で揉めてしまうと、その後の面会交流の交渉で妻側が慎重になってしまう場合があります。
弁護士へのヒアリングによると、
「最終的には学費を含めて算定表よりも多めに養育費を払うというところに落ち着くことが多い」
とのことです。
学費の心配がなくなることで子どもとの関係が円満になったり、成長したときに非親権者の家から学校に通ったり、面会交流も制限なく自由にできるようになったりするケースも多いようです。
7 結婚する前なら夫婦財産契約という選択肢も
こうした社長特有の離婚リスクに備え、これから結婚する若い社長の中には夫婦財産契約(婚前契約、プレナップとも)を結ぶ人が増えています。
夫婦財産契約とは、
離婚時の財産分与で揉めることがないように資産の帰属などを決めておく契約書
です。
この契約は、「婚姻後に取得した株式も財産分与の対象外とする」といった内容を定めることもできます。
ただし、夫婦財産契約は当然、お互いの合意が必要になります。婚姻前に離婚を前提とした取り決めをするというのは、感情的に受け入れられないかもしれません。
実際に契約を結んでいるケースでは、
社長の結婚は家族だけでなく会社経営にも大きく関わる出来事なので、会社のリスク管理のためにも結んでおきたい
と切り出すことが多いようです。
なお、夫婦財産契約は婚姻後に結ぶことはできません。また、結んだ後に契約内容を変更することも基本的にはできないので、その点は留意しておきましょう。
また、夫婦財産契約は会社の規模や目的によって内容も大きく変わってくるので、結ぶ際は弁護士に相談するのがいいでしょう。
以上(2025年12月更新)
(監修 弁護士 坂東利国)
pj60248
画像:siro46-Adobe Stock