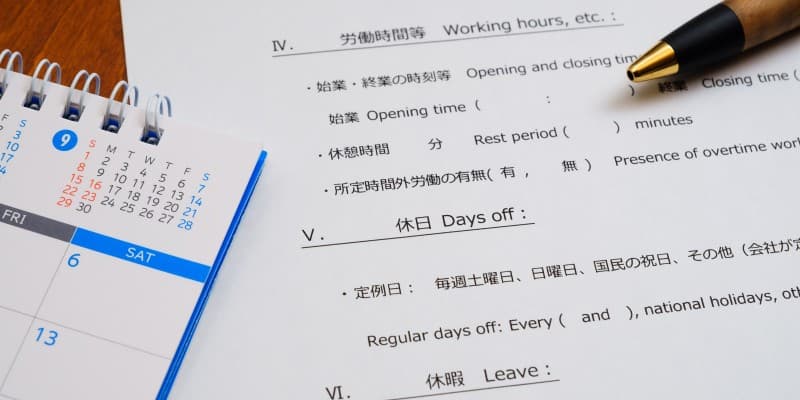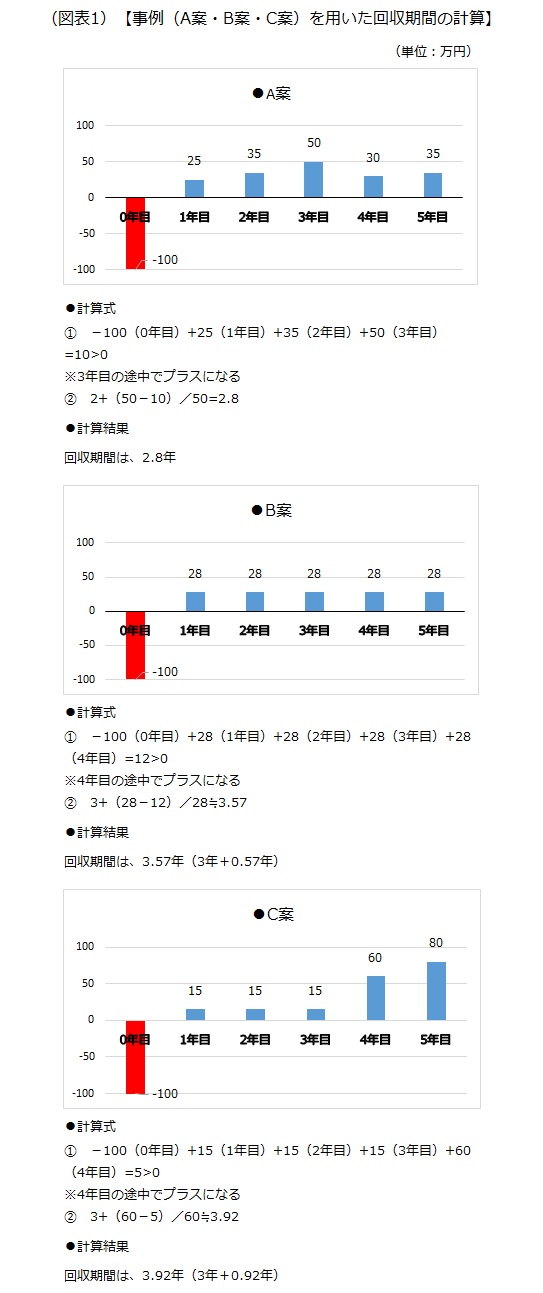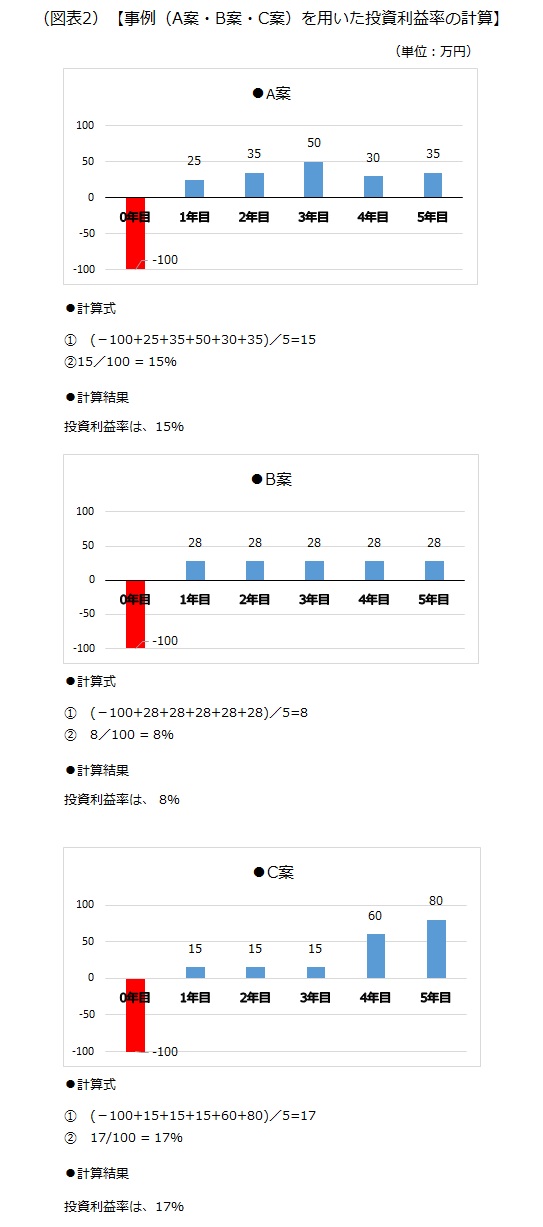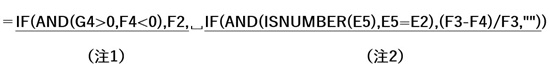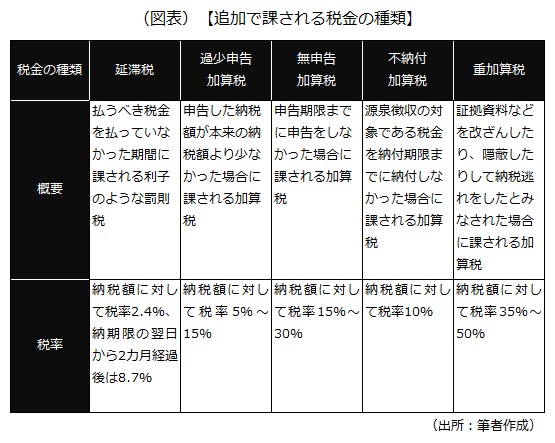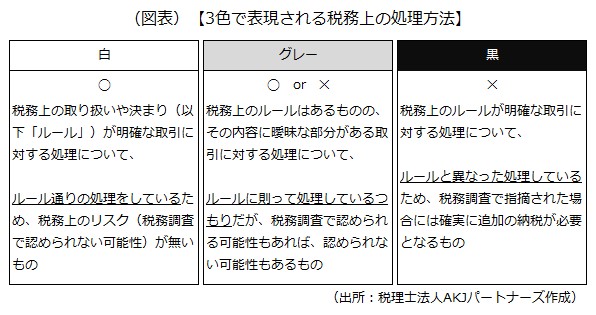目次
1 社長の愛人問題を真面目に考える
テレビやネットでは、連日のように政治家や芸能人の愛人問題など不適切な関係が報じられています。世間のコンプライアンス意識が昔より厳しくなり、当事者がそれまで積み上げてきたキャリアを一瞬で失うケースも……。人ごとであれば「またこんなくだらない話か」と流して終わりですが、もし皆さん自身が当事者になったとしたら、どうでしょう?
SNSの拡散力が増し、内部通報制度も普及した昨今。個人の不祥事は会社のリスクに直結します。特に社長は会社の“顔”であり、そのイメージが揺らげば、取引先の信頼や社内の士気、業績にも多大な影響が出ます。
この記事では、弁護士に寄せられた「社長の不適切な関係」に関する実際の相談をもとに、そこに潜む法的リスクや会社への影響、対応のポイントを解説します。紹介する事例は実情が特定されないようにしていますが、ゴシップではなく、会社防衛のための実務的な内容としてお読みいただけます。
2 社員との親密な関係が社内で噂になってしまった
社長の不適切な関係の典型的な相手は「自社の社員」です。なかには、社長が気に入った社員に片っ端から声をかけ、事実上の愛人関係を迫る(見返りとして、仕事面で便宜を図る)なんて深刻なケースも報告されています。そして、社長が特定の社員と親密になると、その噂はあっという間に社内に広がります。最初に紹介する事例は、まさにそんなケースです。
【事例1】
ある会社では、社長が特定の社員に、他の社員には任さない重要な仕事を次々に振っていました。しかも、その理由については「適任だから」という曖昧な説明しかありません。さらに、「社長とその社員が2人きりで打ち合わせを行い、他の関係部署に相談せず、物事を決めてしまう」「社長の出張には、決まってその社員だけが同行」なんてこともしばしば……。
他の社員は、次第に不信感を募らせていきます。「どうも様子がおかしい」「私的な関係があるのではないか」「業務が公平に扱われていないのではないか」といった声が広まり、ついには「愛人関係にあるのではないか」「公私混同が起きているのではないか」という通報が、内部通報窓口に寄せられる事態にまで発展してしまいました。
1)不適切な関係がもたらすリスク
このようなケースでは、次のリスクが生じます。
1.セクシュアルハラスメント(男女雇用機会均等法第11条)
「社長に逆らったら、降格や減給になるのでは……」といった不安から、社員が社長の誘いを断れないケースは多く、「社長が権力を盾に、不適切な関係を迫った(セクシュアルハラスメント)」と判断される恐れがあります。
2.パワーハラスメント(労働施策総合推進法第30条の2)
特定の社員を特別扱いし、他の社員を不当に冷遇することは、「『社長>社員』という力関係を利用した権限の濫用(パワーハラスメント)」と判断される恐れがあります。
3.善管注意義務違反(会社法第330条、民法第644条)
取締役は会社の利益のために行動する義務を負います。特定の社員を不当に優遇することは、会社の利益のために業務を行っているとは判断されず、会社の信用を損なう行為であり、取締役としての責任を追及される恐れがあります。
4.内部通報への不当な干渉(公益通報者保護法第3条、第5条、第11条、第12条)
「会社の評判に悪影響があるから」「経営陣の信用に関わるから」などと言って通報をもみ消したり、通報者に対して降格や減給などの不利益な取扱いをしたりする行為は違法です。
2)基本的な対応方針
会社が取るべき対応は次の通りです。
- 中立性、独立性を担保した社内調査の実施(人事部・コンプライアンス部門による事実調査等)
- 外部弁護士などの関与(社長が当事者であるため、公正性の確保が不可欠)
- 調査の非通知・非公表(調査対象者の介入を避けるため、調査開始を知らせないこともある)
社長が知らないうちに調査が進められることもあるわけですが、とにかく調査の結果、社員との関係が不適切と認定されれば、次の対応が取られることも想定されます。
- 社長の報酬減額(会社法第361条)
- 取締役の解任(会社法第339条)
- 当該社員の配置転換や業務の再配分
- 社内ガバナンス体制の見直し
3 SNSで不適切な言動を暴露されてしまった
近年、YouTubeチャンネルなどで、出演者の「不適切とも奇妙とも取れるLINEのやり取り」を紹介する暴露系の企画が人気を集めています。エンタメとして見ているうちはいいですが、自身が当事者になった場合を想像できますか? 次に紹介する事例は、まさに暴露されてしまった社長の話です。
【事例2】
ある会社の社長は、取引先の社員に好意を寄せていました。仕事の打ち合わせとして一緒に食事に行くこともありました。これくらいならいいのですが、社長の思いはエスカレート。ついに、相手に肉体関係を迫る内容のLINEを送るようになりました。その言葉遣いは品性や倫理観を疑われるようなものでした。
そうした不適切なLINEがなぜかSNSを通じて外部に漏洩し、瞬く間に広まってしまったのだから、さぁ大変。社内では「なぜこんなメッセージを送ったのか」「会社の代表というより、人として下品だ!」と動揺が広がり、取引先や顧客からも疑念の声が寄せられました。予想以上に早く情報が拡散し、会社は広報に社内調査、再発防止策の検討など、様々な対応に追われることになりました。
1)不適切な関係がもたらすリスク
このようなケースでは、次のリスクが生じます。
1.会社のレピュテーションリスク
SNS拡散はいわゆる「デジタルタトゥー」となり、ブランド価値を毀損し、株主や取引先に重大な影響を与えます。また、その後の採用活動などにも悪影響を及ぼします。
2.取締役の解任(会社法第339条)
社会的信用の喪失は、取締役としての適格性を欠くと判断される恐れがあります。
3.善管注意義務違反(会社法第330条、民法第644条)
不適切な私生活の行為でも、会社価値を下げられることになれば、責任問題になる場合がありえます。
2)基本的な対応方針
会社が取るべき対応は次の通りです。
- SNS事業者に対する投稿の削除請求・仮処分の申し立て
- 悪質な投稿だった場合、発信者情報請求や対象となる相手へのコンタクトを通じて、投稿者を特定した上で損害賠償請求
情報の拡散度合いや投稿内容の悪質性にもよりますが、自社ウェブサイトに会社としてのコメントを出して「火消し」をすることも検討します。ただし、事実関係を十分に調査することなく、見切り発車で対応したり、辻つまの合わない弁明をしたりすることは、かえって反感を招くので慎重に対応しましょう。
4 「同意」のはずが刑事事件になってしまった
「不同意わいせつ」などに関する報道で、加害者が「(被害者の)同意があると思った」と供述している場面をよく見かけます。人間関係における「同意」は、契約書などの書面があるわけではなく、曖昧な言動の上に成り立っています。しかも、お互いに好意があったとしても、「何を、どこまで許容できるか」は異なるので、「同意」についての認識が双方でしばしば食い違うのです。次に紹介する事例も、誤解や思い込みがトラブルに発展したケースです。
【事例3】
ある会社の社長は、いきつけのお店の店員と2人きりで食事に行く関係になりました。かねてより、その店員から好意を示すような言葉や態度があり、食事の時間はとてもムードの良いものでした(社長はそう感じていました)。“脈あり”と受け取った社長は、食事の帰りに相手にキスをし、さらにホテルで肉体関係を持ちました。
後日、思いがけない事態となります。なんと相手の店員が、キスをされたことは「不同意わいせつ」、肉体関係を持ったことは「不同意性交等」であるとして、警察に被害届を提出したのです。社長は「相手は自分に好意を持っている」と思い込んでいましたが、店員の主張は全く違っていたようです。ホテルで肉体関係まで持った相手からの被害届、それほどまでに「同意」は曖昧なものであると認識せざるを得ない事例です。
1)不適切な関係がもたらすリスク
このようなケースでは、次のリスクが生じます。
1.不同意わいせつ(刑法第176条)、不同意性交等(刑法第177条)
2023年の刑法改正で、「強制わいせつ」は「不同意わいせつ」、「強制性交等」は「不同意性交等」に名称が変わり、暴行・脅迫の有無にかかわらず、相手の自由意思による同意がなければ犯罪が成立することになりました。また、雇用関係や力関係がある場合、「自由な意思による同意かどうか」が厳しく判断されることになりました。人間関係やコミュニケーションが複雑化する現代において、「同意」はなおさら慎重に扱うべきテーマになっています。
2.会社のレピュテーションリスク
社会的な影響力を持つ社長が、刑法に抵触する行為をしていたことが明るみに出れば、組織全体の信用やブランドイメージに深刻な影響を与えるのは避けられません。
2)基本的な対応方針
会社が取るべき対応は次の通りです。
- 捜査にはできるかぎり誠実に協力する
- 会社としても事実調査を実施する
- 捜査終結前に会社としての見解を発信するのは避ける
- 逮捕されたとしても即有罪ではないため、冷静かつ慎重に対応をする
5 不倫がバレて離婚、財産分与の問題になってしまった
社長の不倫に関する相談は、想像以上に多く寄せられます。特に深刻なのは、不倫が発覚して配偶者に知られ、離婚協議へと発展した場合です。一般的な夫婦の離婚とは異なり、社長には会社の経営権という極めて重要な要素が絡んでくるからです。最後の事例、社長とその配偶者の離婚問題をご覧ください。
【事例4】
ある会社では、社長の不倫が発覚し、配偶者との離婚協議に発展しました。離婚協議の争点は「財産分与」。社長が保有している会社の株式のうち、「配偶者が受け取るべき割合」をめぐって社長と配偶者が争うことになったのです。
離婚協議の結果、社長は「株式の半数」を配偶者に分与しなければならなくなりました。それまでは株式の大半を所有するオーナー社長だったのに、株式の分与によって議決権が分散し、経営に対する主導権を維持できなくなってしまったのです。
1)不適切な関係がもたらすリスク
このようなケースでは、次のリスクが生じます。
1.財産分与(民法第768条)
財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いた財産を清算・分配することです。「婚姻中に築いた財産」なので、会社の株式も個人名義で保有していれば分与対象に含まれます。財産分与の割合は「財産の2分の1(原則)」ですので、株式が対象であればその半数を分与しなければなりません。財産形成に当たっての夫婦の貢献度によって、配偶者の財産分与の割合が下がることはありますが、一方で、婚姻関係を破綻させた責任などによって、割合が上がることもあります。
2.経営権(議決権)の分散によるガバナンス崩壊
株式が個人資産として分与対象になれば、配偶者に株式が移転します。株式の移転は単に財産の移動というだけではなく、「会社の支配権」を根本から揺るがす重大な問題です。特にオーナー社長の場合は深刻です。
2)基本的な対応方針
会社が取るべき対応は次の通りです。
- 法的にどこまで拘束できるかは分かりませんが、「株式は財産分与の対象から除外する」といった婚前または婚後契約を締結する
- 財産分与の際に株式を分与せずに、代償金(現金)で合意ができるように協議する
6 最後は社長次第
社長の不適切な関係は、私生活の問題にとどまらず、会社経営の根幹を揺るがすリスクになり得ます。この記事では4つの事例を紹介しましたが、こうした相談が寄せられることは本当に多いです。もちろん、問題の程度は社長と相手との実際の関係など事実に基づきますが、この手の問題は注目され、噂も広まりやすいです。愛人問題は私的なことだといえなくもないですが、社長は「公」の存在という一面もあり、そのことは無視できません。
そのため、社長にはトラブルを避けるための自律とリスク感覚が求められます。また、問題が起きた際には隠蔽するのではなく、覚悟を決めて、迅速で透明性の高い対応を取ることが不可欠です。
以上(2025年12月作成)
pj60378
画像:Gemini