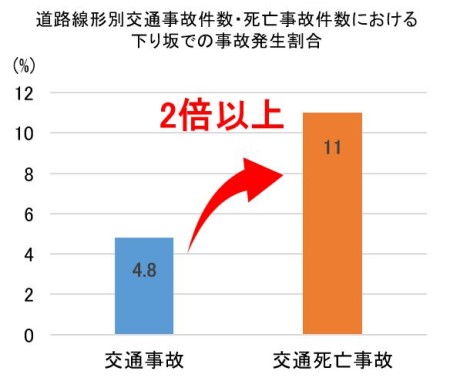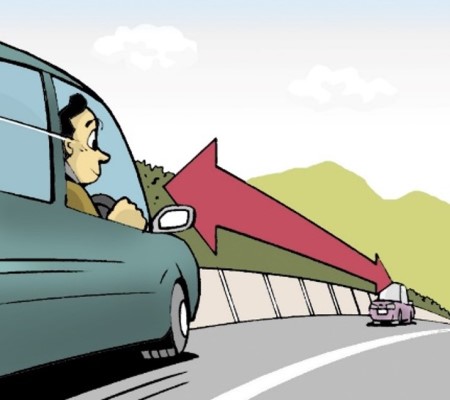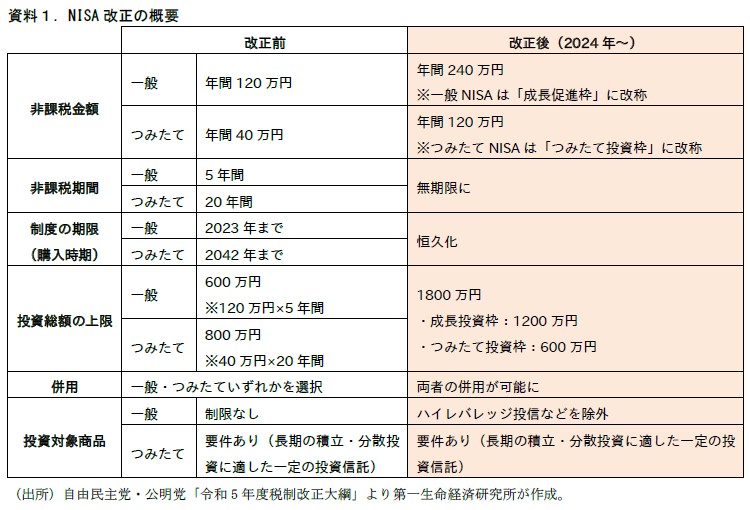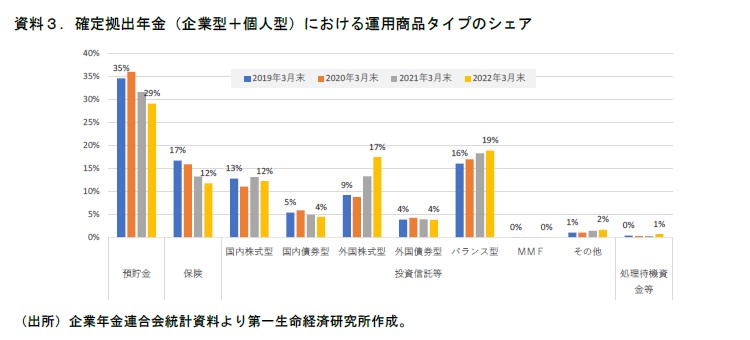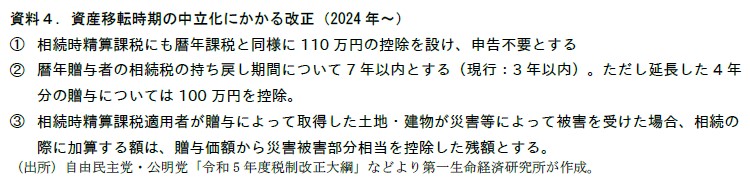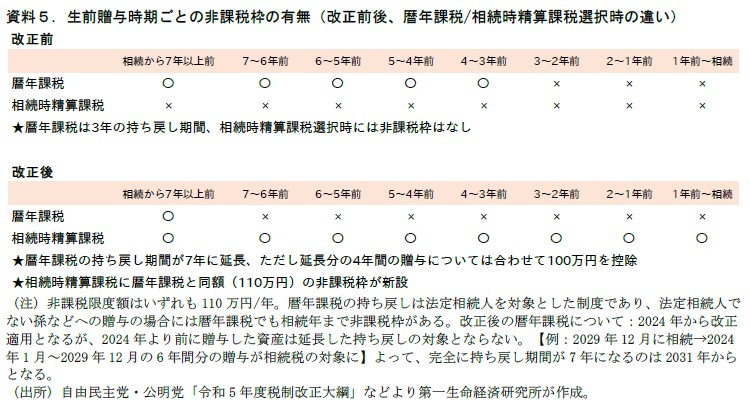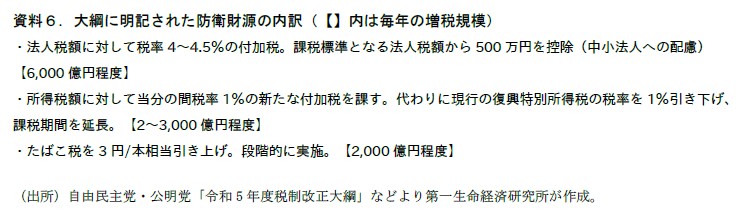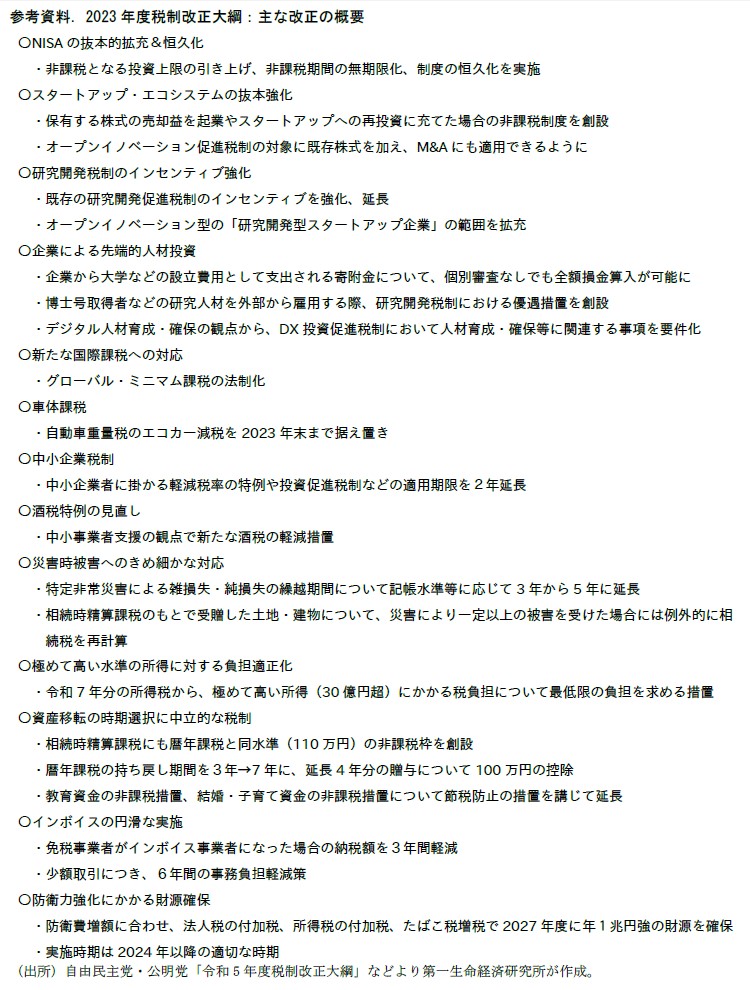書いてあること
- 主な読者:ナイトタイムエコノミーで観光客の誘致など地域活性化をしたい観光事業者や中小企業、金融機関など
- 課題:夜間のイベントで集客する方法や留意点が分からない
- 解決策:単独にこだわらず関係者と連携し、SNSも利用して告知や認知拡大を図る。夜間なので、誘導や見回りの強化などの安全対策にも注力する
1 「夜間の経済活動」で消費を拡大
ナイトタイムエコノミーとは、
主に18時から翌朝6時までの間に行われる、観光や娯楽などの経済活動
です。新型コロナウイルス感染症の影響を受けているものの、2022年10月から外国人観光客の受け入れが全面解禁されたことで、再び、注目を集めています。国外の事例ですが、観光庁「ナイトタイムエコノミー推進に向けたナレッジ集」によると、
- ロンドン:経済規模が約3.7兆円、雇用者数が72万3000人(注1)
- ニューヨーク:経済規模が約2.1兆円、雇用者数が19万6000人(注2)
といった実績もあります。
(注1)経済規模は粗付加価値額、1ポンド140円換算、2017年4月時点の数値です。
(注2)経済規模は消費額の合計、1ドル110円換算、2019年1月時点の数値です。
ナイトタイムエコノミーは地方でも十分に展開できます。実際、地方の観光地が観光資源を生かしたナイトタイムエコノミーを行って観光客を誘致している事例があります。この記事では、ナイトタイムエコノミーに取り組む国内事例と、その際に運営側が留意したことを紹介します。
なお、インバウンド向けの施策を検討する際は、こちらのコンテンツもご参照ください。
2 国内の先進事例
1)湘南藤沢活性化コンソーシアム:「江の島灯籠」
・主体
湘南藤沢活性化コンソーシアムは、神奈川県藤沢市、藤沢商工会議所、藤沢市観光協会、江ノ島電鉄などで構成される団体です。藤沢市のブランディングやイベントの主催などを手掛けています。
・ナイトコンテンツ
江の島でのライトアップイベント「江の島灯籠」に2008年から取り組んでおり、2022年は7月23日~8月31日の期間で開催しました。このイベントは夏季の地域振興を目的としたもので、江島縁起をモチーフにした大小1000基の灯籠と、江島神社のライトアップを中心に、影絵のライブ上映や影絵遊びの体験が楽しめます。
・実績
2019年度時点での来場者数は約2万2000人となっています(2020年、2021年は計測なし)。また、このイベントは、夜景観光の啓発やプロデュースを手掛ける「夜景観光コンベンション・ビューロー」の「日本夜景遺産」にも認定されています。
2)広島県立美術館:「ひろしまナイトミュージアム」
・主体
広島県立美術館は、広島県広島市内にある美術館です。広島県、施設の管理を手掛ける指定管理者のイズミテクノ・廣島緑地建設・広田造園共同事業体、観光体験のプロデュースなどを手掛けるエクスペリサスと共同で「ひろしまナイトミュージアム 第3弾」として2022年7月から取り組んでいます。「ひろしまナイトミュージアム シリーズ」は、2020年度に広島県観光連盟が始めた「魅力的なナイトタイムエコノミーコンテンツ造成事業」でエクスペリサスが企画を提案したもので、同社では、これまでに広島市内で4つのナイトコンテンツを企画・実施しています。
・ナイトコンテンツ
「ひろしまナイトミュージアムin 広島県立美術館」は、閉館後に館内の警備をしている一人の警備員に、画家のサルバドール・ダリ、菅井汲、ポーランド国王のアウグスト強王が乗り移り、美術館に展示されている自身の所蔵品の説明をしていくという全く新しい没入型アート体験です。
また、ツアー体験と併せて常設展の鑑賞、役者とのフォトセッション、ウェルカムドリンクも楽しむことができます。
・実績
2021年度は10回開催し、延べ214人が鑑賞。申し込み倍率は10倍になりました。また、2022年は7月~12月の計6回開催で延べ168人が鑑賞。申し込み倍率も回を重ねるごとに高まっているといいます。

3)長岡観光コンベンション協会:「山古志 棚田・棚池あかりのページェント」
・主体
長岡観光コンベンション協会は、新潟県内の交通・運輸会社や物産業、酒蔵・酒小売業などで構成される団体です。長岡市の観光誘客事業などを手掛けています。
・ナイトコンテンツ
長岡市役所山古志支所、JTB長岡支店、リゾートバンクと共同で「山古志 棚田・棚池あかりのページェント」というイベント名で「棚田・棚池ライトアップウオーク」と山花火の打ち上げを2020年10月30日~11月8日の期間で開催しました(2021年度、2022年度は新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて開催を中止しました)。
開催地の長岡市山古志は、錦鯉(にしきごい)発祥の地として、秋の錦鯉の品評会で世界中から錦鯉のバイヤーが訪れてにぎわいを見せる場所です。一方で、品評会が終わるとバイヤーは即時帰国することが多いため、滞在期間の延長や消費の拡大が課題になっていました。
そこで、日本農業遺産に認定された山古志特有の棚田・棚池のあぜ道や池の中、木立に明かりを照らし、来場者に散策を楽しんでもらう「棚田・棚池ライトアップウオーク」と、棚田・棚池の水鏡の水面に映る花火を鑑賞する山花火の打ち上げを行いました。「棚田・棚池ライトアップウオーク」と山花火の会場は分かれており、山花火の打ち上げ日には有料のシャトルバスを運行して会場を行き来できるようにし、警備と誘導を長岡観光コンベンション協会、山古志観光協会のスタッフで行いました。
・実績
イベントは新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、来場者を新潟県在住者限定としましたが、「棚田・棚池ライトアップウオーク」は10日間で延べ5770人、山花火は4日間で延べ1450人が来場しました。

4)MeiPAM(メイパム):「妖怪美術館」のナイトミュージアム
・主体
MeiPAM(Mei:迷路のまち P:パフォーマンス A:アート M:マルシェの略称です)は、香川県土庄町の小豆島で「妖怪美術館」や「小野川直樹美術館」を運営する団体です。
・ナイトコンテンツ
この団体では、「妖怪美術館」のナイトミュージアムを中心にした観光客の誘致に取り組んでいます。
「妖怪美術館」のナイトミュージアムは通年で開催されています。入館時に来場者がスマートフォンアプリをダウンロードすることで、妖怪が話しかけてきて館内を案内します。館内は暗闇となっており、来場者は懐中電灯で館内を照らしながら展示物を鑑賞します。
他にも、妖怪美術館に併設されている「妖怪bar」や、周辺には夜間でも立ち寄れる飲食店があるため、小豆島全体でのナイトタイム観光を楽しむことができます。
・実績
妖怪美術館の年間の来場者数は約1万人となっています。また、この取り組みは、「瀬戸内国際芸術祭2022県内周遊事業」に認定されていたり、「新しい時代に対応する観光復興ガイド2022―全国の事例48選―」に紹介されていたりします。

5)別府市産業連携・協働プラットフォームB-bizLINK:「夜の地獄めぐりと地獄の夜市」
・主体
別府市産業連携・協働プラットフォームB-bizLINKは、大分県別府商工会議所や別府市内の経営者などで構成される団体です。別府市の観光地域づくりの推進などを手掛けています。
・ナイトコンテンツ
2019年8月10日~10月20日の期間限定で「夜の地獄めぐりと地獄の夜市」を開催しました。
大分県別府市は温泉をはじめ、観光施設や神社仏閣、国立公園などの観光資源がある一方で、営業時間が日中のみで夜間は閑散としていることや、景観目当てで観光客の消費額が少なかったことが課題でした。そこで、観光スポット「別府の地獄めぐり」の開園時間を、普段は17時までとしているところを22時まで延長し、夜間イルミネーションや夜市、地獄にいそうな生き物を集めた「地獄の生き物展」などを開催して観光客の誘致を図りました。
・実績
観光スポットの地獄(白池地獄・海地獄・かまど地獄)の期間中の延べ来場者数は約3万人、お土産、屋台、周辺飲食店での売り上げ合計が約700万円になったといいます。
なお、夜間イルミネーションの「夜の海地獄」ライトアップイベントは継続して開催しており、2022年は9月17日~9月25日の期間限定で開催しました。
3 イベントを開催する際のポイント
1)来場者の安全の確保
夜間のイベントは足元が暗いので、来場者が道に迷ったり、誤って立ち入り禁止のエリアに入ったりすることがないように、誘導灯や誘導員を配置しなければなりません。
例えば、「山古志 棚田・棚池あかりのページェント」では、
来場者が歩く山道に電飾ライトを設置して誘導案内
をするだけでなく、山花火の打ち上げ日に会場を行き来するためのシャトルバスを運行する際は、
シャトルバスを斡旋したJTBとバス運行会社にも協力を依頼し、誘導員を配置
することで、来場者が道に迷わないように配慮したといいます。
また、「妖怪美術館」のナイトタイムツアーでは、
- 地元警察に依頼し、夜間の見回りを強化
- スタッフがトランシーバーで来場者を誘導
することで、安全対策に取り組んでいます。
2)ウェブサイト・SNSを利用したプロモーションによる告知、認知拡大
ウェブサイトやSNSを利用したプロモーションによる告知や認知拡大を図るケースもあります。例えば、「山古志 棚田・棚池あかりのページェント」では、次のようなキャンペーンを行い、若年層の誘致や認知拡大につなげました。
- Instagram、Twitterの両方をフォローしたら、抽選で花火観覧チケットをプレゼント
- イベントの画像にハッシュタグを付けて投稿したら、抽選で温泉ペア宿泊券やレストランでの食事券をプレゼント
3)宿泊施設・メディアなどとの連携
単独での事業展開に限らず、宿泊施設・メディアなども巻き込んでイベントの周知を図ることも大切です。例えば、「夜の地獄めぐりと地獄の夜市」では、
- 地域内のホテルや旅館が、宿泊者にイベントのチラシを渡して周知する
- 地元のテレビ局とタイアップする
ことで地域の人の集客につながったとしています。
4)来場者のけが、感染症対策も欠かさずに
検温やアルコール消毒など基本的な感染症対策は不可欠です。また、夜間の場合、来場者がけがをしたり、体調を崩したりした際に対応してくれる医療機関を確認しておきたいものです。
日本政府観光局(JNTO)のウェブサイト「日本を安心して旅していただくために 具合が悪くなったとき」などで外国人の対応が可能な医療機関や薬局などをあらかじめ調べておくようにしましょう。
外国人観光客の感染・傷病の備えについては、こちらのコンテンツもご参照ください。
4 自治体による支援策の例
自治体の中には、補助金など、ナイトタイムエコノミー推進に関連した支援策を設けている自治体があります。ここでは、一例として東京都港区と長崎県長崎市の補助金を紹介します。皆さんの地域にも支援策があるかもしれませんので、
自治体や金融機関に相談
してみるとよいでしょう。
1)東京都港区:「ナイトタイムエコノミー補助金」
東京都港区では、「ナイトタイムエコノミー補助金」を募集しました。
公共交通機関の運行外の時間を除き、日没後から早朝の間に行う、港区ならではの新規事業、または既存事業の拡充にかかる経費について、3分の2相当、もしくは、200万円の上限金額のいずれか少ないほうを補助するものです。
2022年は下記の3事業への支援が決定されました。
- 竹芝エリアマネジメント「竹芝夏ふぇす2022」
- 日本キャンドル協会「JCAA2022 ×キャンドルナイト」
- ホーン「1人外食をもっと気軽に。ソロメシパスを活用した港区飲食店の活性化」
2)長崎県長崎市:「長崎市ナイトタイムエコノミー推進事業費補助金」
長崎県長崎市では、「長崎市ナイトタイムエコノミー推進事業費補助金」を募集しました。
長崎市のナイトタイムエコノミーを推進する事業にかかる経費について、2分の1以内の金額(年間の上限金額は400万円)を補助するものです。
2022年は下記の6事業への支援が決定されました(追加募集分の3事業を含みます)。
- デュアルキーシステム:九州初!文化を伝えるナイトサップ
- 長崎サンセットマリーナ:長崎港ヨットクルーズ&ディナー
- ゼンリン:MaaSサービスを活用した次世代型ナイトライフプランパッケージ
- 長崎バスホテルズ:商館長の夜~出島で綴る音楽と演舞
- リージョナルクリエーション長崎:稲佐山ナイトフェスタ
- スリードラゴンズカンパニー:交流人口拡大のための音楽と地元食材を中心としたバーラウンジの展開『ナガサキの夜はステキ』
参考:ナイトタイムエコノミーの参考資料・関連団体
1)国土交通省 観光庁 観光資源課
ナイトタイムエコノミー推進に向けたナレッジ集として、ナイトタイムエコノミーの基礎情報や推進に当たり課題となることなどを紹介しています。
また、観光庁のウェブサイトでは、「令和2年度 夜間・早朝の活用による新たな時間市場の創出事業」として、団体・企業のナイトタイムエコノミーの取り組み例を紹介しています(ウェブサイト中段にリンクがあります)。
他にも、「訪日外国人旅行者の体験型観光コンテンツの購入促進に関するナレッジ集」を公開しており、訪日観光客が日本でのアクティビティをどのように知ったか、何に興味・関心を持ったかなど、インバウンド向け施策を検討する上で参考になるウェブアンケート結果を掲載しています(ウェブページ中段「『体験型観光コンテンツ市場の概観』世界のコト消費と海外旅行者の意識・実態の調査結果」のリンクです)。
2)東京カメラ部
SNS写真コミュニティの「東京カメラ部」の運営をはじめ、SNS運用サポートやフォトスポット開発などを手掛ける企業です。同社では、ナイトタイムエコノミーに取り組みたい自治体や企業向けの提案として、写真家の派遣や写真撮影の際のアドバイス、ライトアッププロデュース、SNSを活用したPRを手掛けています。
3)ナイトタイムエコノミー推進協議会
政府や自治体のナイトタイムエコノミー政策立案のサポートなどを手掛ける団体です。企業向けにナイトタイムエコノミーに関する勉強会、イベント、セミナーの主催や情報提供などを行っています。
以上(2023年1月)
pj70122