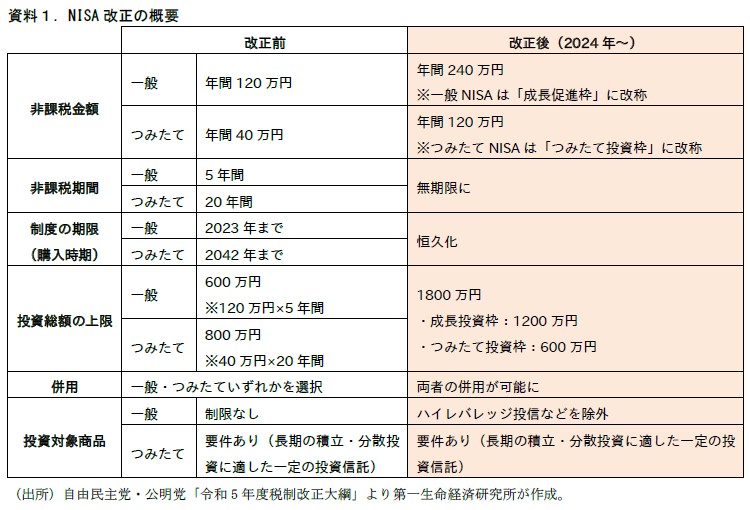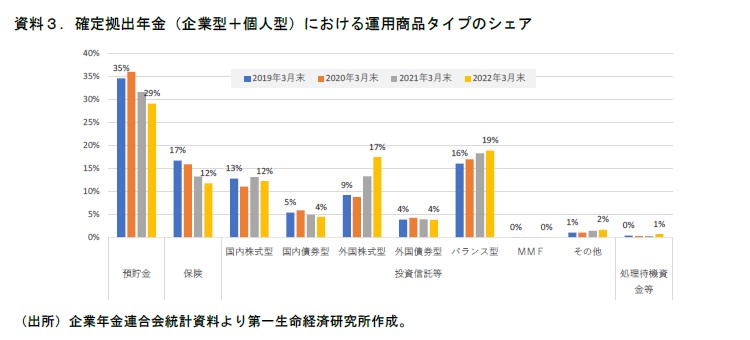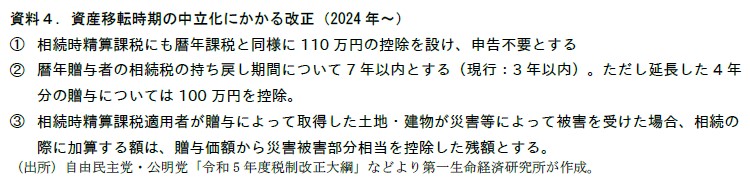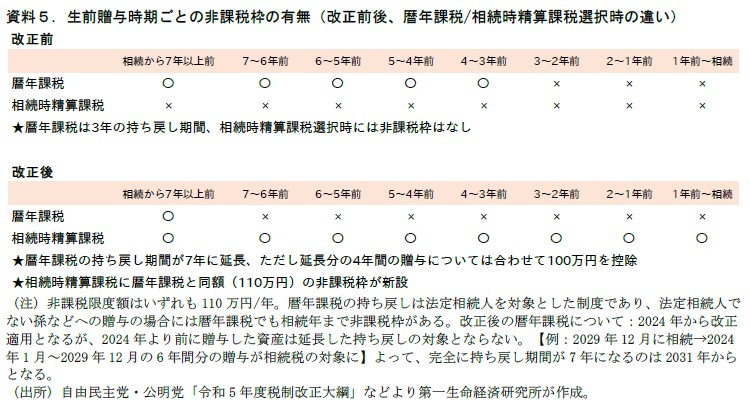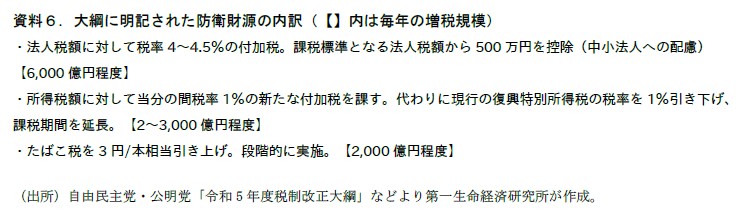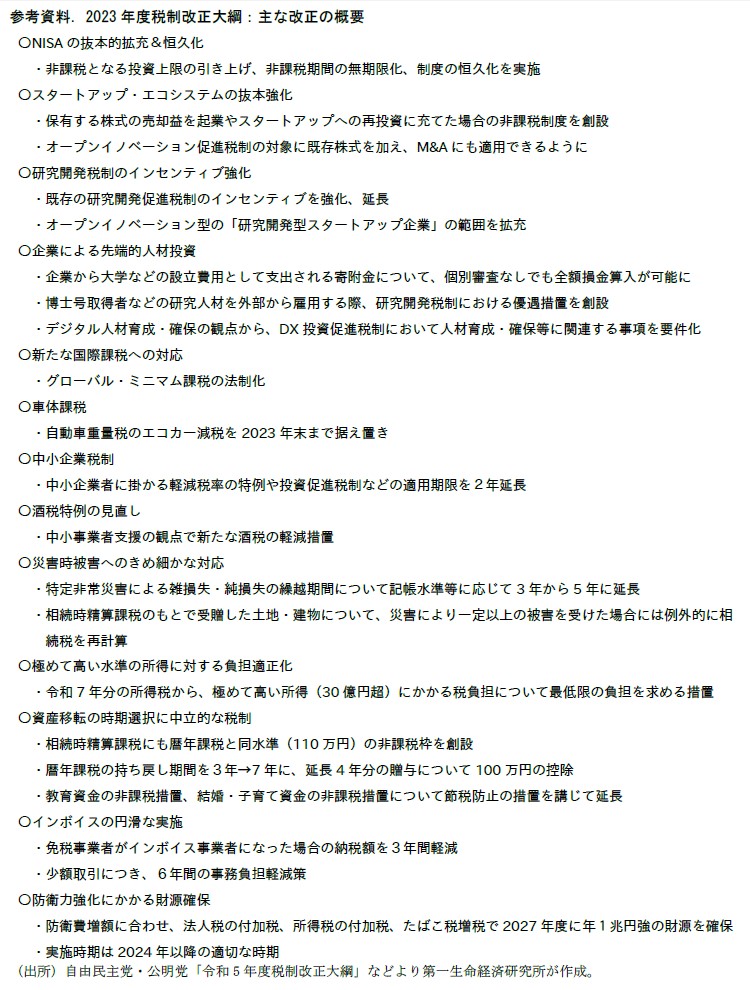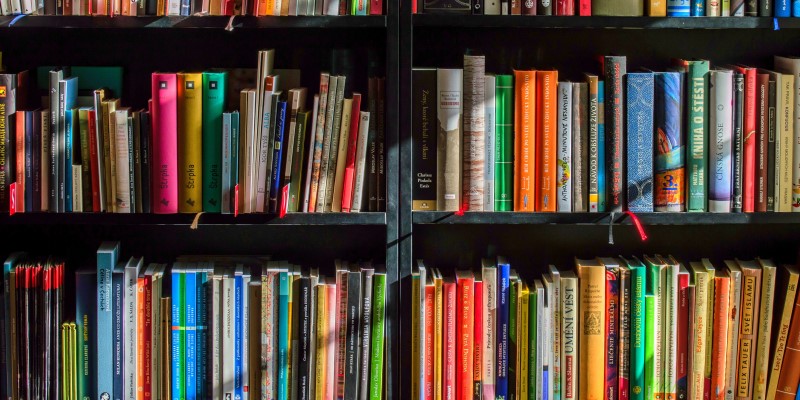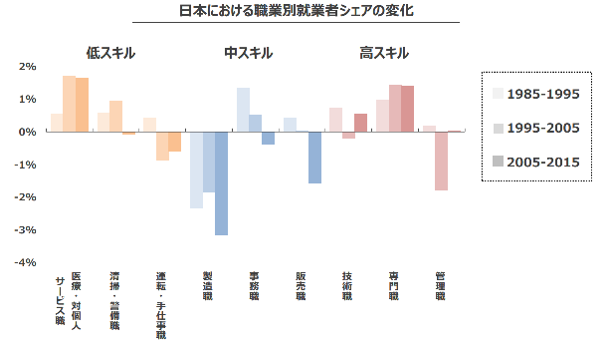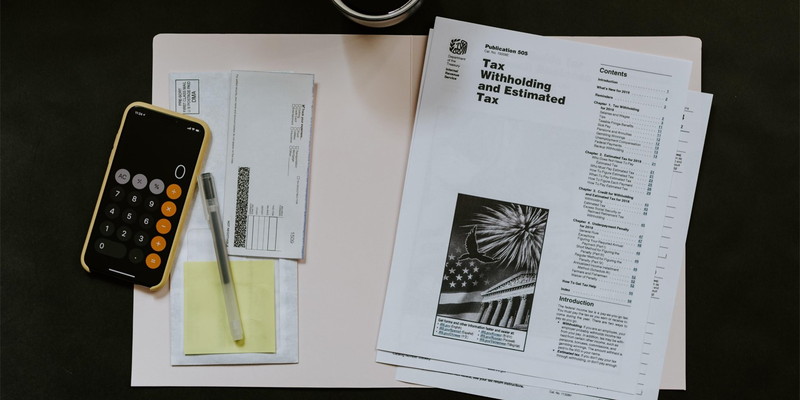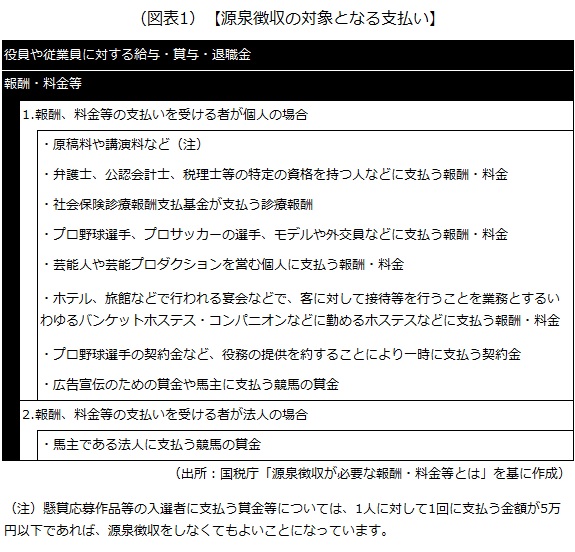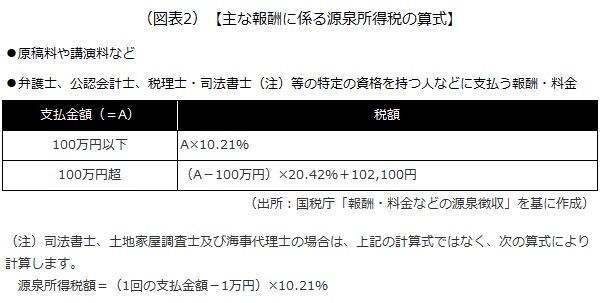書いてあること
- 主な読者:自社の立て直しに苦戦中の経営者、地域と自社を一体的に活性化させたい経営者
- 課題:自社の立て直しや、地域と自社を一体的に活性化させるための方法を知りたい
- 解決策:“地域の足”として欠かせない存在にもかかわらず、維持費が高額で採算の取りにくい地域鉄道の経営者の取り組みを参考にする
1 151年目の鉄道の進路は「金を失う道」か「鋼の道」か
1872(明治5)年に国内初となる鉄道が新橋⇔横浜で開業してから、151年目を迎えました。「鉄」の字を分解して、鉄道は「金を失う道」ともいわれるように、安全運行のために車両や施設の維持管理に多大なコストがかかります。その一方で、地域鉄道の利用者数は、クルマ社会へのシフトと少子高齢化によって減少傾向が続いています。
こうした構造的な問題を抱えながら、“地域の足”として不可欠な地域鉄道会社を守るために、さまざまなアイデアを具体化し、立て直しに取り組んでいる経営者がいます。
この記事では、地域鉄道会社の立て直しに奮闘する経営者の中でも、特に「異色」の経歴を持つ2人の社長へのインタビューを、2回にわたって紹介しています。
前編では、いすみ鉄道(千葉県大多喜町)に続き2社目の公募社長として立て直しに取り組んでいる、えちごトキめき鉄道(新潟県上越市)の鳥塚亮社長のインタビューを紹介しました。
後編となる今回は、2023年に開業100周年を迎えた銚子電気鉄道(千葉県銚子市、以降「銚電」)の竹本勝紀社長です。竹本さんは、2005年に銚電の顧問税理士に就任して以降、何度も経営破綻の危機を乗り越えてきました。「ワンポイントリリーフの予定」で2012年12月に社長に就任してからは、税理士業務と掛け持ちをしながら、報酬は実質ゼロにもかかわらず、自ら運転士の資格を取得するなど、銚電の再生に情熱を注いでいます。
次章以降で紹介するインタビューからは、“崖っぷち”状態にありながら生き残り続けている銚電の、熱い想いで鍛錬された鋼のような強さとしなやかさが見えてきます。
2 数々の破綻の危機が「絶対にあきらめない」銚電魂を鍛えた
1)路線は6.4キロメートル、売り上げの8割は食品
銚電は、銚子(銚子市)⇔外川(とかわ、銚子市)間の全長6.4キロメートルの路線で、10駅を運営しています。JR東日本・総武本線の終点である銚子駅を起点に、銚子の市街地から海岸に沿って南東に延びています。
路線は1923年に開業しましたが、運営していた「銚子鉄道」は1948年に解散し、現在の「銚子電気鉄道」が引き継ぐ形で再建されました。その後、親会社はバス会社、建設会社へと移り変わり、現在(竹本さんが筆頭株主)に至っています。
銚子市は、日本一の水揚げ量を誇る銚子漁港の他、しょうゆ醸造業や水産加工業、犬吠埼温泉の観光などで知られています。千葉県で2番目に市となり、昭和初期までは県内第2の都市でした。ただ、近年では過疎化が進んでおり、1970年代まで9万人を超えていた人口は、現在では6万人を割り込んでしまっています。
人口減に伴う銚電の利用者の減少を補っているのが、食品の製造販売です。1976年に駅に併設したたい焼き店を皮切りに、地元で古くから作られていた「ぬれ煎餅」の製造販売を1995年に始めたところ、「ぬれ煎ブーム」が起こり、自社の製造工場や、駅の併設店以外に2店舗を構えるようになりました。今ではこの「ぬれ煎餅」と、2018年の発売以来、約400万本を販売した「まずい棒」の2つの商品が売り上げをけん引しています。会社の売り上げの8割は食品製造販売で、信用調査会社での業種は「米菓製造」などに分類されています。
2)何度も経営破綻の危機を乗り越える
銚電は何度も経営破綻の危機を乗り越えてきました。私が顧問税理士になった2005年当時は、親会社であった建設会社の社長が借りた1億円超の負債を銚電が背負うこととなり、裁判所に破産を申し立てるための予納金もない状態でした。そのため、税負担を軽減するのに1億円未満に減資をし、「経営改善計画書」を作成して政府系金融機関からの借り入れを行い、急場をしのぎました。また、会計ソフトを導入したり、少しでも売り上げを伸ばそうと、私のポケットマネーでオンラインショップを立ち上げ、ぬれ煎餅を売り込んだりしました。
2006年には、国土交通省による監査の結果、老朽化した線路や踏切の改善・修理命令が出されました。運行停止にならないためには、約5000万円の修繕費が必要な上に、約1000万円かかる車両点検の期限も迫っていました。社員への給料も支払えない危機的状態に陥った中で、当時の経理課長が2006年11月、ウェブサイトに「電車運行維持のためにぬれ煎餅を買ってください!! 電車修理代を稼がなくちゃ、いけないんです」と書き込みました。すると、10日間で1万人以上の方にぬれ煎餅を買っていただき、修繕・点検費用を賄うことができました。それまで、ぬれ煎餅の売り上げは年間2億円程度だったのですが、その年は約4億2000万円に上り、「第二次ぬれ煎ブーム」となりました。このとき皆さまに助けていただいたことを、今でも私たちは「奇跡のぬれ煎餅」と呼んで、感謝し続けています。
2011年の東日本大震災の後も、観光客が激減したことなどによって、3年連続で赤字が1億円に達する危機を迎えました。2012年12月に私が社長になったときの銀行残高は50万円でした。このときは自主再建を断念し、国や千葉県、銚子市などからの支援を受けることで存続させてもらえました。
ところが、存続が決まった矢先の2014年1月に脱線事故を起こしてしまい、車両の修繕費用が捻出できなくなってしまいました。このとき救いの手を差し伸べてくれたのは、地元の高校生たちです。クラウドファンディングで約500万円を集めていただき、運行を継続できました。

3)コロナ禍はSNSの活用で乗り切る
まだ予断を許さない状況ですが、コロナ禍も本当に厳しかったです。今でも忘れられないのが、2020年4月18日、花曇りの行楽シーズンの土曜日にもかかわらず、1日の売り上げがわずか4480円だった日のことです。2020年4~6月がどん底で、四半期での赤字額が5000万円近くに上り、「もう、持たないのではないか」とも思いました。
しかも前年の秋の行楽シーズンは、相次ぐ台風に見舞われて観光客に来てもらえなかったことから、在庫の山となっていたまずい棒の賞味期限が迫っていました。
この危機を救ってくれたのが、SNSを通じた皆さまのご協力です。ツイッターで、「まずい棒、賞味期限まであとわずか、早いもの勝ち」と書き込んだところ、完売することができました。「わずか」なのは賞味期限であって、在庫は山のようにあるので、論理のすり替えというか、欺瞞(ぎまん)に満ちた言葉なのですが、それなりにバズって(SNS上で話題が拡散し注目を集めて)、多くの方に購入していただきました。
コロナ禍ではオンラインショップでの販売に注力したことで、何とか糊口(ここう)をしのぐことができました。売れ残りグッズを集めた「廃線危機救済セット」や、メガネの上からかけるタイプのサングラスを入れた「お先真っ暗セット」など、自虐ネタ商品もいろいろ企画しました。オンラインショップでは食品だけでなく、パーカーなどのアパレルからペットフードまで、「売れるためなら何でもやる」という“銚電魂”で、さまざまな商品を取り扱っています。コロナ以降のオンラインショップでの売り上げは、従来に比べて10倍近くに増えました。また、2020年7月からは、動画投稿サイトで「激辛(つら)チャンネル」を本格稼働させました。
4)「絶対にあきらめない」で「ありがとう」と言われる会社を目指す
数々の危機を乗り越えるためにご協力いただいた地元の方や鉄道ファンの皆さまには、感謝の気持ちしかありません。
2015年12月から、銚電は駅の愛称のネーミングライツを導入しています。付けていただいた愛称の中には、自社の宣伝ではなく、純粋に銚電を応援するメッセージもあります。これは結果的ではありますが、起点の銚子駅の愛称は「絶対にあきらめない」で、終点の外川駅は「ありがとう」です。これ自体が、銚電魂を示す1つのストーリーになっていると思います。
「絶対にあきらめない」というのは、どこの会社もそうかもしれませんが、銚電がここまで存続してこられた最大の理由です。あきらめないというのは、念仏にように唱えることではなく、絶対にどこかに突破口があると信じて、探し続けることです。実は銚子駅のネーミングライツの契約は終わっているのですが、「絶対にあきらめない」という愛称はそのまま残しています。
「ありがとう」というのは、当社の経営理念である、「『この町に銚子電鉄があって本当によかった。ありがとう銚子電鉄』といわれる会社を目指す」ことを示しています。これまで銚電は助けていただくばかりで、「ありがとうございます」という気持ちしかありませんが、その向きを変えて、「ありがとう」と言ってもらえるようになるのが、私たちの究極の目標です。
3 リスクを取る覚悟が「日本一のエンタメ鉄道」の根底にある
ネーミングライツで付けられている駅の愛称の1つに、ギャグが入ったものがあります。本来の駅名は「笠上黒生(かさがみくろはえ)」で、愛称は「髪毛黒生(かみのけくろはえ)」です。このギャグは、「日本一のエンタメ鉄道」を目指している銚電を象徴していると思います。絶対にあきらめずに、「ありがとう」と言ってもらえる会社になるために選んだ銚電の進路が、エンタメ鉄道です。
1)銚子に観光客を招くために日本一のエンタメ鉄道を目指す
銚電は6.4キロメートルしかなく、片道20分で終点に着いてしまいますので、はやりの「レストラン列車」をやっても前菜だけで終わってしまいます。車窓の眺めが素晴らしいわけでもありません。では、どうすれば新たな需要を喚起し、観光客に銚子に来てもらって地元におカネを落としてもらえるかを考えたときの答えが、日本一のエンタメ鉄道を目指すことでした。
駅に停車させずに運行する夏休みの「お化け屋敷電車」や、車内外をイルミネーションで飾る「イルミネーション電車」は好評で、恒例イベントになっています。いずれも高校生をはじめとする地元の方々に協力していただいています。その他、地域鉄道初の戦隊ヒーローによるアクションショー、車両内でのプロレス興行「電車内プロレス」、UFO召喚イベントなども開催してきました。2020年8月には、自主制作した映画「電車を止めるな!~のろいの6.4km~」の上映も開始しました。これは変電所の更新費用の捻出が目的だったのですが、制作費のうち500万円はクラウドファンディングで集まったものです。
エンタメには、「おもてなし」という意味もあります。銚子に来ていただいたお客さまにおもてなしをして笑顔になっていただき、また銚子に来ていただくことが、地元の皆さまからの「ありがとう」につながっていくと考えています。
2)鉄道会社の一番の強みはメディアやSNSとの親和性の高さ
銚電の平均時速は20キロに満たず、下手をすると自転車よりも遅いのですが、それでも鉄道会社の使命として、地域の足を守るということがあります。また、電車で銚子まで来られる観光客の移動手段としても、存在意義があります。
ですが、移動手段としてしか存在意義がないのであれば、地域鉄道会社は生き残れないと思っています。今、強く意識しているのは、「地域の情報発信基地」としての存在意義を果たすことです。その根底には、ただ存続するのではなく、存続するのを前提として、これまで銚電を守っていただいた地域の皆さんや鉄道ファンの皆さんのために、恩返しをしたいという思いがあります。
鉄道会社をSWOT分析すると、一番の強みはメディアとの親和性だと思います。マスメディアはもちろんですが、SNSなどのソーシャルメディアを通じて全国に向けて情報発信することの相性が良いです。これは、「奇跡のぬれ煎餅」やクラウドファンディング、コロナ禍のオンラインショップの売り上げ増などでも実証済みです。
ですので、どんな小さなことでもよいので、プレスリリースを書くようにしています。また、最近ではツイッターの書き込みを増やしています。ツイッターなどのSNS自体が、パブリック・リレーションズの役割を果たしていると思います。特にコロナ以降は、メディアに取り上げてもらうことを強く意識しています。

3)地域のPR会社になることがもう1つの存在意義
情報発信を積極的に行うのは、銚電の新商品・サービスの売り込みだけでなく、銚子の町全体のためです。
ここ数年、「×(カケル)事業」と名付けた地元の事業者とのコラボレーションを、積極的に取り組んでいます。事業がメディアに取り上げられると、コラボ先の知名度が上がるチャンスにつながるからです。
例えば、地元の農家とのコラボです。銚子といえば、銚子漁港は知られていても、キャベツの生産量が全国上位であることはあまり知られていません。そこで、2020年4月から、地元で取れたキャベツと調味料を使った餃子の製造販売を始めました。名前は、ぬれ煎餅にあやかった「ぬれ餃子」です。

その他にも、地元で取れる海産物の魅力を伝えるために、イベント列車「3843(サバヨミ)号」「鯛パニック号」「ツナ(鮪)わたり列車」を走らせたり、地元の居酒屋と「鯖威張る(サバイバル)弁当」を共同開発したりしました。
特に地域の経済の活性化に寄与できたと思っているのが、バンダイナムコエンターテインメントのソーシャルゲーム「アイドルマスター SideM」とコラボしたことです。男性アイドルをプロデュースするゲームで、多くのゲームのユーザーの方に銚子にお越しいただきました。
また、歌手のきゃりーぱみゅぱみゅさんの全国ツアーと連動した地方創生企画「LOCAL POWER JAPAN project」に選んでいただき、コラボさせてもらった企画も反響が大きかったです。
このように、銚電はある意味で、地元の魅力を発信するPR会社みたいなものになることも存在意義だと思っています。
4)営業戦略はAIDMAモデルとゲリラマーケティング
銚電の営業戦略としては、AIDMAモデルとゲリラマーケティングを重視しています。AIDMAモデルは、ちょっと普通と違ったことをやって注目されて(Attention)、銚子に関心を持っていただき(Interest)、銚子に行ってみよう、商品を買ってみようという欲を喚起して(Desire)、それを忘れてもらわないようにして(Memory)、実際に銚子に来ていただいたり、商品を購入していただいたりする(Action)ものです。
オンラインショッピングなどでは、ゲリラマーケティングを行っています。商品やサービスのネーミングは自虐ネタを多用して、インパクトが出るようにしています。自虐ネタは他人を傷つけませんし、自分たちの状況を笑い飛ばしてしまえるというメリットもあります。ですので、自虐とギャグを合わせて「自ギャグ」と呼んでいます。
普通と違ったことやインパクトのあるネーミングは、「売れるためには何でもやる」という銚電魂に基づく戦略です。銚電には失うものは何もありませんので、公序良俗に反するもの以外は、まずはやってみるという方針でいます(笑)。
5)責務を全うするためのリスクテイカーとしての覚悟
時にはお叱りを受けることもありますが、銚電の社長を引き受けた以上、責務を全うしないといけませんので、リスクテイカーとしての覚悟をしています。それは経営者の方であれば、誰でも持っていると思います。
「何もしないのが一番のリスク」といいますが、私は「リスクを取らないのが一番のリスク」だと思っています。怖がっていては、何もできません。経営判断をするのも、即断即決を心掛けています。にぎやかし的にいろいろなことをやってみることで、ぬれ煎餅やまずい棒ほどの成功はありませんが、小さな利益を生む商品を数多く生み出すことができています。
もちろん、「こんなはずではなかった」と思うこともあります。自主制作した映画は、クラウドファンディングで制作費はいただいたのですが、特殊メークやCGなどを多用するうちに、予算が5~6倍に膨らんでしまい、私自身も出資することに至りました。ですが、銚電としては上映時にぬれ煎餅やまずい棒を購入してもらえますので、売り上げ増に貢献しています。
4 車両や駅は古くても、会社の在り方は新しい?
1)会社自体がクラウドファンディング?
先ほどもお話ししたように、鉄道会社はメディアやSNSとの親和性が高いので、積極的に活用しています。「奇跡のぬれ煎餅」をはじめ、クラウドファンディングも含めて、メディアやSNSの力で何度も危機を乗り越えられてきました。
今や、銚電の存在そのものがクラウドファンディングといえるかもしれません。

2)外部の有能な人材を有効活用
私が社長になった当初は、ワンポイントという予定だったのですが、顧問税理士としてクライアントに対して全力でサポートするというポリシーもあって、銚電を放っておけなくなり、社長を続けています。私の報酬は月に10万円ですが、通勤のためのガソリン代だけでなくなってしまいます。新商品の開発や改善などは、会社に迷惑を掛けないように、ボランティアというか、自腹でやっています。
とはいっても、代表者である限り責任は免れません。税理士をしながら経営をするというのは、ある意味で邪道だと思っていますし、体が幾つあっても足りません。社員も30人いませんから、電車を安全に運行して、煎餅を焼くだけで手いっぱいです。
そこで、足りない経営資源は外部の助けを借りることにして、社外取締役や、外部の「アドバイザー」の方に業務を手伝ってもらっています。2021年に「5分で論理的思考力ドリル(安全うんこうドリル)」を販売しましたが、開発したのはソニーグループのソニー・グローバルエデュケーションで、同社の社長に銚電の社外取締役になっていただいています。銚電は本の帯だけ全力で製作しました。
外部のアドバイザーは数人いて、いろいろなご縁で出会った人の中で、これはと感じた人をスカウトしています。外部のアドバイザーの方には、まずい棒のアイデアの発案や、映画の脚本を書いてもらうなど、数々のご協力をいただいています。
5 「ミルフィーユ(=千葉)改革」で地方に活力を取り戻す
1)まずは収支トントンを目指す
銚電の財務状態は、コロナの影響で、コロナ前に3億5000万円程度だった債務が4億5000万円程度まで増えました。コロナ対策に伴う緊急融資については返済猶予がありますが、どのように手当てをするのか考えていかないといけないと思っています。公共交通機関ということで金融機関もある程度ご理解いただき、債務の償還年数は35年程度と長期ですので、それを踏まえた事業計画を考えていく必要があります。
銚電は、2018年に発売したまずい棒のヒットが、財務における転換点になっています。まずい棒の発売前は、最終赤字額が3000万円程度で、利払い・税金・減価償却費を計上する前の利益であるEBITDAはゼロでした。つまり、設備の更新や新規投資ができず、借入金は利息の返済だけで元本の返済もできませんので、いわば会社としては「死に体」だったのです。
まずい棒のヒットによって、最終赤字額は1000万円程度まで減り、2000万円のキャッシュが残るようになりました。そのため、1000万円を元本の返済に充て、残り1000万円を設備投資などに回せるようになっています。ただ、設備投資は最低限のことしかできず、新しい車両を購入するなどの大規模な投資はできません。
2021年度は21万円の最終黒字になりました。収支トントンになると、3000万円のキャッシュが手元に残るので、元本返済と設備投資以外に、1000万円を何かに使える余地が生まれます。コロナ対策の緊急融資の返済まで考えると収支トントンでも厳しいですが、まずは収支トントンを続ける必要があります。
2)「より一層」の高みを目指すミルフィーユ(=千葉)改革
銚電の立て直しは、一歩一歩だと思います。私は「ミルフィーユ改革」と呼んでいるのですが、ミルフィーユのように、パイの生地を一枚一枚重ねていくように変革を進めています。昨日より今日、今日より明日と、少しでもいいので改善していこうという姿勢が大事だと思います。経営学でいうところの、革新の積み重ねですね。そのためには、熱量を持って取り組むことと、何か問題があったときにはやりっ放しにせず、PDCAサイクルを回すことが重要です。
その際のキーワードは、「より一層」です。この言葉は現状を否定せず、肯定した上で、さらに高めていこうという意味があります。それこそがミルフィーユ改革だと思っています。
ちなみに、ミルフィーユはフランス語で「千の葉っぱ」、つまり「千葉」の意味があります。
3)地方の魅力を発信して「逆ストロー効果」を目指す
後に首相になった田中角栄氏が「日本列島改造論」を発表したのが、今から約50年前の1972年です。本来は、都市と地方が均等に発展することが狙いで、通信網や交通網が整備されていきました。ところが、新幹線網が出来上がってみると、地方の資源がどんどん都市に吸い上げられる、いわゆる「ストロー効果」が生じてしまいました。鉄道によって地方は衰退し、都市だけが発展していったのです。
私は、これから、どうすれば「逆ストロー効果」を生み出せるのかを考えています。そのためには、地方が魅力を発信して、都市からUターン、Iターンする人を呼び寄せなければなりません。
赤字の鉄道が増えて、「鉄道事業再構築」の議論が進められていますが、私は鉄道事業を「再興」させるために、地方の再興とセットにしていくべきだと考えています。町が衰退してしまえば、鉄道も存続できませんから、鉄道と地域は表裏一体です。
銚子という町の再興のために、銚電が果たせる役割は何だろうかということを模索しながら、いろいろなことにチャレンジをしています。
会計の世界では、会社という組織はゴーイングコンサーン、つまり継続性を前提としています。ですが、銚子市の人口は、2035年には4万2000人まで減るとの予測もあります。そこまでなったときに、果たして鉄道を残すべきかという議論は、また出てくると思います。いつかは銚電が地域鉄道としての使命を終えるときがくるかもしれません。ですが、今はまだそのときだとは思っていません。たとえ古びた傷だらけの電車であっても、やれることは無限にあると信じて、前向きに歩むことを胸に抱いています。
【参考文献】
「崖っぷち銚子電鉄 なんでもありの生存戦略」(竹本勝紀、寺井広樹著 イカロス出版、2019年5月)
竹本勝紀(たけもと かつのり)
銚子電気鉄道社長、竹本税務会計事務所代表。
1962年、千葉県木更津市生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業。千葉県内の税理士事務所に勤務の後、2009年4月、竹本税務会計事務所を開設。税理士として約500社のクライアント企業の税務申告や経営指導を行う。2005年に銚子電気鉄道顧問税理士、2018年同社社外取締役を経て、2012年12月から現職。千葉科学大学非常勤講師(財政学、会計学)。
以上(2023年1月)
pj80181
画像:銚子電気鉄道提供