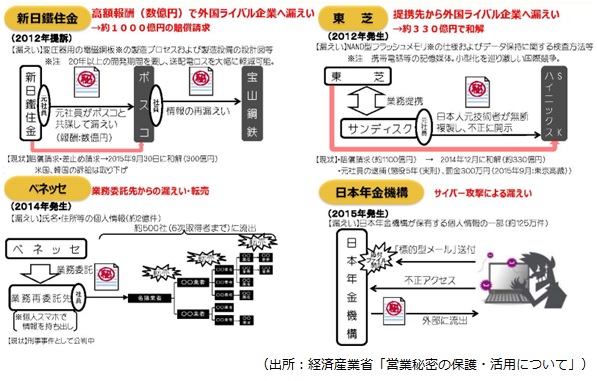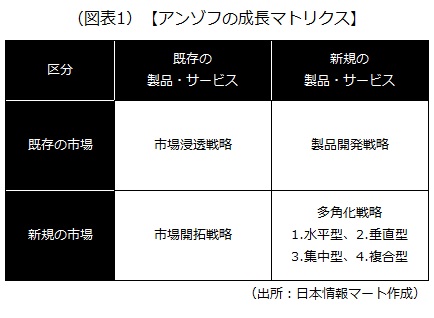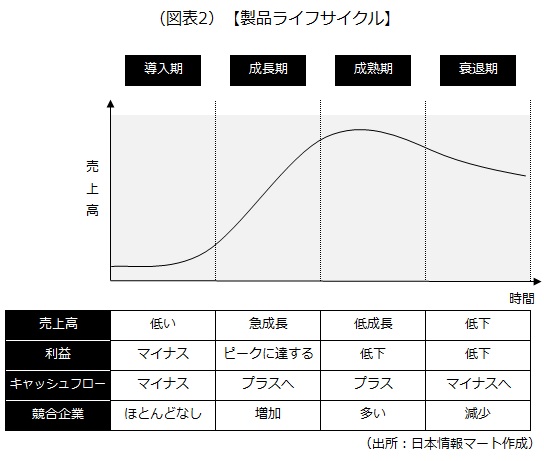書いてあること
- 主な読者:海外(特に東南アジア)の人とビジネスをしたい、海外に進出したい経営者
- 課題:現地に行ったことがなく、現地の人たちの考え方や文化もよく分からない
- 解決策:東南アジアの100以上の企業・団体との太いパイプラインを築いた日本人の、偏見を持たず壁をつくらないオープンマインドの考え方と実践方法を参考にする
1 途上国など海外の人と取引するときの秘訣
東南アジアなど海外の人と一緒にビジネスをしたい、海外に進出したい。途上国の人たちの役にも立ちたい。けれど、実は現地に行ったこともないし、人脈もない、言葉も不安……。
そんな経営者の方は、ぜひこの記事をお読みください。この記事では、ソーシャルマッチ(代表取締役社長の原畑実央さん、取締役副社長の樋口麻美さん)へのインタビューを紹介します。同社は、東南アジアの社会問題解決のために、現地の企業・団体と日本企業とのマッチング事業を行っているスタートアップです。カンボジアを中心に、東南アジアで提携する企業・団体は100を超え、現地に進出している日本企業でも届かないような、独自の太いパイプラインを多く持っています。原畑さんたちが、こうした現地との「深いつながり」を築けた秘訣は、
オープンマインドであること
です。インタビューから見えてきた具体的な実践方法をまとめたのが、次の7カ条です。
- 何よりもまず、取引相手の国を尊重する
- 語学力は気にしない。自分の情熱や思いを伝える
- 「自分だけ得する」考えを捨て、互いの目的を合致させる
- 理想は、個人同士の心でつながった関係をつくる
- 文化や商慣習などの違いを認め、受け入れる
- 自らを変えて相手に合わせることを厭(いと)わない
- 取引相手から「学ぶ」姿勢を忘れない
以降では、ソーシャルマッチの代表である原畑さんのお話をメインにご紹介します。この記事から、途上国、ひいては海外での取引を円滑にするヒントが見つかれば幸いです。
2 何よりもまず、取引相手の国を尊重する
1)カンボジア人の明るさや力強さに憧れる!
学生時代に東南アジアを旅行したときに、カンボジアでは特に、日本にはないエネルギーや“カラフルさ”を感じ、ワクワクした憧れを抱くとともに、この社会で学ばせてもらいたいと思いました。
カンボジアは東南アジアの中でも「まだこれから」と言われるのですが、たくさんの人がバイクに乗っていたり、バイクで大量の荷持を運んでいたり、路上で家族や仲間たちが集まって飲んだり食べたりする姿に、力強さと温かさを感じました。友人のアフリカ系の米国人もそうなのですが、彼らには日本人にはない、底抜けの明るさと、人としての力強さがあります。
大学卒業後は、日本の製品で東南アジアの人たちの生活に役立ちたいと考えて、アリババで1年半勤務したのですが、海外で働いている先輩の話を聞いてとても羨ましくなり、思い切ってカンボジアにある日系の人材紹介会社に転職しました。

2)カンボジアの社会問題の解決に関心を持ち起業を決意
私は学生時代から社会問題にとても関心があり、社会問題について話し合い、解決に取り組んでいる方を訪れるツアーを開催する団体を立ち上げたこともあります。
カンボジアは発展が始まったばかりで、経済格差が大きく、国の社会福祉制度も整っていません。ですから、夜間に働き学校に行けない子供や、路上で生活をする障害者など、社会問題が目に付きやすい国でもあります。
こうした社会問題を自分だけでは解決できないと思っていたのですが、カンボジアの中にも、社会問題の解決を目指す社会起業家の方がいます。国がサポートできない分、社会問題を解決するには、現地(カンボジア)の民間企業やNGOなどの団体の力がより重要になります。
彼らを応援したくて、仕事の傍ら、彼らの活動を取り上げるインタビューメディアの運営や、一緒にイベントを開催するなどの活動をしました。ちょうどこの頃、大学を休学して、カンボジアの教育支援の団体で1年間のインターンシップをしていた樋口さん(現ソーシャルマッチ取締役副社長)と出会いました。
社会問題の解決を目指している人たちの輪が広がる様子を目の当たりにして、「自分の価値を発揮できるのは、この分野ではないのか」と考えるようになりました。そして、カンボジアに移住してから3年後の2019年12月に、樋口さんとともにソーシャルマッチを起業しました。
3 語学力は気にしない。自分の情熱や思いを伝える
1)自己PRや情熱を積極的に語ることで提携先を開拓
起業して法人登記は日本で行い、カンボジアに長期出張する形で、現地の提携先探しを始めました。
提携したいと思った先には、何回もオフィスにお伺いしてお話しさせていただいたり、「現地の社会問題の解決のために取り組みたい」という情熱や思いを伝えたりしました。
日本人である私は、現地の方々とバックグラウンドが違いますし、相手から見れば「どのような人物かも分からない」ので、警戒されやすいのは当然です。そこで、まずは自分のことを分かりやすくプレゼンテーションするようにしました。海外では、自分でいかに自己主張し、自分をPRするのかが、ビジネスチャンスをつかむ上ですごく重要なことだと思います。積極的にコミュニケーションを取っていくことで、さまざまなチャンスをいただいたり、多くの企業・団体との提携に結び付いたりしました。
こうしたネットワークを活かすことで、日本企業と、1000人のカンボジア農家とのネットワークを持った現地の社会起業家とをつなぐこともできました。提携先の力を借りなければ、とてもできないことだと思います。
2)語学力よりも情熱。ただし英語力を磨く工夫は必要
カンボジアの提携先の方々は皆さん英語を話されるので、ビジネスでは英語を使っています。特に東南アジアの人たちに対しては、片言の英語であっても、自信を持って話して大丈夫だと思います。東南アジアでは英語は第二言語なので、それほど文法は気にしない人が多いですし、比較的分かりやすくゆっくりと話してくれるので、とても理解しやすいです。
こちらの話も、ちゃんと聞こうとしてくれたり、「これはこういうことだよね?」と聞いてくれたりします。ですから、間違えてもいいので、取りあえず話していくことが大事だと思います。私も、「通じていないだろうな」と思いながら話していることもあります(笑)。
英語は、話す「場」を積まないと、うまくならないものです。恥をかいた分だけ強くなり、上達もするので、取りあえずアウトプットすることが大切です。実は私自身も、英語力を磨くために、音声SNSを使って、飛び込みで知らない海外の人と英語で話すチャレンジをしてきました。ドキドキしながら話して、たくさん失敗して恥ずかしい思いをしたおかげで、生きた英語を身に付けることができたと思います。
それから、上手に話そうとするよりも、一生懸命に話している気持ちを伝えることが大事です。心から発した情熱や態度は、相手に伝わるものだと思います。言葉が未熟でも、「この人の話なら聞いてみよう」と思ってもらえることがあります。言葉は50%くらいで、後は声の大きさや表情、友好的な態度などの要素が影響するのではないでしょうか。
ただし、事前準備として、少なくとも英語でのプレゼンテーションの練習や、話をしに行く相手の事業のリサーチ、話題になりそうな業務に関する英単語のチェックなどはしておいたほうがいいと思います。
4 「自分だけ得する」考えを捨て、互いの目的を合致させる
1)目指すものが一致したとき、スムーズに協働できるようになる
私たちがマッチングさせていただく基準として、現地も日本側も、社会問題の解決やSDGsに取り組む企業・団体であることを前提としています。そのため、紹介した企業・団体は、互いの姿勢や取り組みを評価し、共感し合えることが、ソーシャルマッチの強みになっています。共感し合うことで、ビジネス上というよりも、精神的なつながりによって、「同志」のような関係を築けていると思います。

そもそも、私たちが東南アジアのこれだけの企業・団体と提携できているのも、「社会問題の解決を目指しているソーシャルマッチだから」ということがあります。例えば現地の大手商社のトップの方など、代表の方に目をかけていただくことで、トップダウンで話が進むという側面が少なくありません。それは、ご依頼いただく日本の企業も同じです。
そのような両国の企業・団体であるからこそ、チームとして同じ思いを持ち、一丸となって共同プロジェクトを進められるのだと思います。今はオンラインによる面談が多いのですが、それでもスムーズにいくのは、目指すべきもの、つくりたいものが一緒であるからだと実感しています。
2)自社の利益だけを考えていては長続きしない
長期的に見ると、例えば自社の利益だけを考えて、自然環境や現地の雇用者の労働環境をないがしろにしているような企業は、事業を継続することが困難になる可能性があると思います。
成長著しい東南アジア市場に進出してくる企業が増えています。私たちが事業領域にしている社会課題の解決をテーマとした分野では、現地の人たちと友好的な関係が築けない企業は、取引先やお客さまからの評価にも影響しますので、次第に選ばれなくなるのではないかと思っています。
逆に言うと、自社のプロダクトやブランド自体がそれほど強くない企業であっても、取引をしたい先としっかりとコミュニケーションを取り、目指している世界を共有することによって、優先的に取り組んでいただいたり、良い条件で協働できたりすることがあります。一般的な企業に広く当てはまるわけではないかもしれませんが、少なくとも社会課題の解決を重視し、取引先とともに発展したいと考える日本の中小企業にとっては、魅力的な市場環境だといえるかもしれません。
5 理想は、個人同士の心でつながった関係をつくる
私たちは、東南アジアの提携先の企業・団体の方々とは、こまめに、友人や仲間のような感覚でコミュニケーションを取っています。SNSもよく活用していて、例えば相手の誕生日や、何かの賞を受賞されたときなどには、お祝いのコメントをしています。
そのようなことをしているのは、ビジネスのことを意識してというよりも、純粋に「相手のことが好きだから」だと思います。
私たちはずっと社会問題の解決に関心があるので、自分のためでなく社会のため、未来のために活動している人たちがとても好きです。自分の人生を使って、命を懸けて社会問題を解決しようとしている人たちは本当に格好良いですし、尊敬しています。
自分の好意は相手にも伝わるもので、それは取引先やお客さまに対しても同じだと思います。心でつながっていると、「ソーシャルマッチだから」と優遇していただいたり、良い条件で協働していただいたりすることもあります。
特にカンボジアの人たちは、ある意味、日本の下町のように情に厚いところがあって、個人的なつながりをとても大切にしていると思います。私たちがカンボジアにほれ込んでいる魅力の一つかもしれません。
6 文化や商慣習などの違いを認め、受け入れる
1)納期やクオリティーに対する認識の違いを想定しておく
カンボジアの企業・団体との協働は、順調に進むことばかりではありません。気を付ける点が幾つかあります。
何よりも、現地の文化や商慣習を知っておき、それを受け入れ、尊重することが大事です。例えば、日本との大きな違いの一つは、納期が日本に比べて厳格ではないことです。これはもう仕方のないことだと思って、途中で進捗状況を確認する、実際の納期よりも余裕を持って締切日をお伝えするなどで対処するしかありません。カンボジアには長期の休みもありますし、日本人のように、納期を厳守するために休みを返上するというような意識は薄いです。これは、良いとか良くないとかの問題ではなく、もともとそういう文化なのです。そこを理解することが大事です。
また、商品のクオリティーに対する感覚も日本人とは違います。色合いや縫製など、発注時のイメージと異なる仕上がりになることが少なくありません。そのため、現物を見て確認しておく、最初は小ロットから取引を始める、サンプルをいただいて事前に改善点を伝えておくなどの対応が必要になります。クオリティーに関しては、「日本の基準や認識とは違う」ことを前提にして、その違いをどのように埋めていくか、齟齬(そご)が生じたときに、どのようにリカバリーしていくかを考えておくことが大事です。
2)口約束は厳禁
これは日本国内でのビジネスも同じですが、口頭で合意したことでも、認識が完全に一致しているとは思わないことも大切です。たとえ先方が「イエス」と言っても、認識が一致していないことがあります。取り決めは必ず文面で残し、重要な内容は契約書に残しておくようにしておきましょう。
また、日本とはインフラの整備状況が異なるということも認識しておく必要があります。カンボジアの場合、特に地方に行くと電波(通信)がつながりにくく、緊急の連絡が取れなくなることがあります。取引上の重要な時期は、相手のスケジュールを事前にチェックし、相手が地方に行く日時なども把握しておくとよいでしょう。また、停電も起きやすく、電力不足で停電になることも想定しておくべきです。
7 自らを変えて相手に合わせることを厭(いと)わない
1)意思決定や行動のスピードを上げる
日本企業と現地(カンボジア)の企業・団体のマッチングが失敗する原因の一つに、意思決定やスピード感の違いがあります。
カンボジアでは今、経済成長に勢いがあるので、チャンスがあればすぐに飛びつかないと乗り遅れてしまいます。ですので、カンボジアの社会起業家の方はかなりスピード感があります。一方で、日本の企業は「検討」「稟議(りんぎ)」といった時間が非常に長くかかります。日本企業が早く返答やリアクションをしていれば協働できたのに、リアクションが遅かったためにうまくいかなかったケースも少なくありません。「日本側の返答が遅いので、信頼感が薄れた」と言われたこともあります。先ほど、「文化として納期が厳格ではない」と言いましたが、「だから返答やリアクションが少しくらい遅くなってもいい」わけでは決してありません。途中経過を伝えるだけでもいいので、むしろ、リアクションはなるべく早いことが大事です。
日本の企業側がカンボジアの企業・団体に合わせて、スピード感を速めると、より協働がうまくいくと思います。
2)現地の起業家の意見を取り入れた商品開発を
商品のクオリティーと価格のバランスが、カンボジアの消費者の目線に合わないことも、マッチングが失敗する原因の1つです(この点はソーシャルマッチ樋口さんからのお話です)。
日本の企業は、本当に現地で展開したいのであれば、現地のニーズにフィットした商品開発をすべきです。現地の社会起業家の方々は消費者のニーズを熟知していて、「この商品はこの価格では売れない」「この価格まで下げれば売れる」ということが分かっています。日本の考え方を押し付けるのではなく、彼らの意見を取り入れ、現地に最適な商品を開発したほうがいいと思います。
3)連絡手段も現地の人たちに合わせる
カンボジアの人たちは、ビジネス上の連絡手段としてSNSを多用しており、急ぎの連絡などは、メールよりもSNSのほうが早くつながります。スピード感がとにかく大事ですので、コンタクト先とはSNSでつながっておき、リマインドなどもSNSを活用するとよいでしょう。
また、現地の祝日を把握しておくことも大切です。先ほど述べたように、カンボジアの人たちは休日はしっかり休みますので、祝日が続く間は工場の稼働がストップします。現地のカレンダーを踏まえたスケジューリングが必要になります。
8 取引相手から「学ぶ」姿勢を忘れない
先ほど述べたように、カンボジアの企業・団体には、日本の企業にはないスピード感があります。また、東南アジアを中心とした海外展開にも積極的で、ビジネスに携わる人の多くは英語を話すことができます。
カンボジアの企業・団体のトップの方々は人間的に温かい方が多く、社員や職員とファミリーのような関係を築き、一体感のある組織をつくっているケースが少なくありません。日本人より楽観的で積極的なところ、「底抜けに明るい」ところも大きな魅力です。
途上国の取引先とは上下の関係はあり得ません。オープンマインドを持って、学ぶべきところは謙虚に学ぶ、教えていただくという姿勢を持つことが大事だと思っています。
9 インタビュー後記:二人のブレない思い
原畑さん、樋口さん共に、「東南アジアの方々や日本の中小企業の役に立つことがライフワークである」という思いを持っています。

日ごろのビジネスは、もちろんキラキラしたことだけではありません。失敗や泥臭いこともたくさんありますが、それでもなお東南アジアと日本の中小企業のために前に進めるのは、そうした確固たる思いがあり、その活動が心から楽しいからでしょう。そんなソーシャルマッチは、オフィス選びにもブレがありません。古民家を改装した一軒家の一室です。なぜなら、「日本の社会課題である【空き家問題】の解決に少しでも役に立てればと思って」だそうです!
以上(2022年8月)
原畑実央(はらはた みお)
松山大学在学中に社会問題をディスカッションする団体を立ち上げる。
社会問題を解決しようとする人の講演会の主催や、活動の現場に訪れるツアーを開催する。
大学卒業後、アリババジャパンに入社。日本企業の海外販路開拓支援に携わる。その後、カンボジア移住し、カンボジアで最大手日系人材紹介会社CDLで3年間マネジャーを務める。
2019年にソーシャルマッチ株式会社を立ち上げる。
2021年度のSDGs Quest みらい甲子園首都圏大会の実行委員に就任。
樋口麻美(ひぐち あさみ)
幼少期はアメリカ、南アフリカ、オーストラリアで育ち、途上国各国でインターンシップを経験。
同志社大学在学中にカンボジアで教育支援NGOを現地の人と設立し日本支部代表として資金調達に務めた。卒業後、IT人材ベンチャーONE CAREERに入社。その後、ソーシャルマッチ株式会社の立ち上げに参画。
pj80146