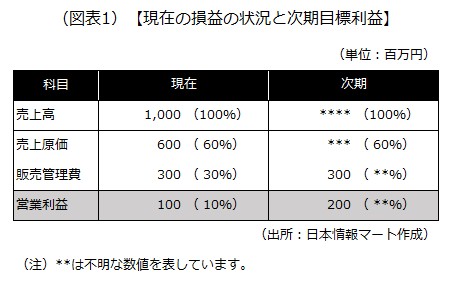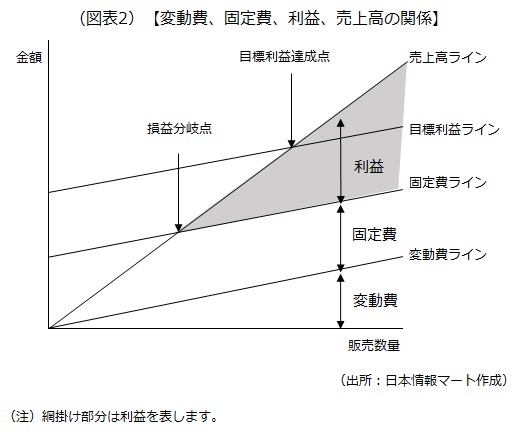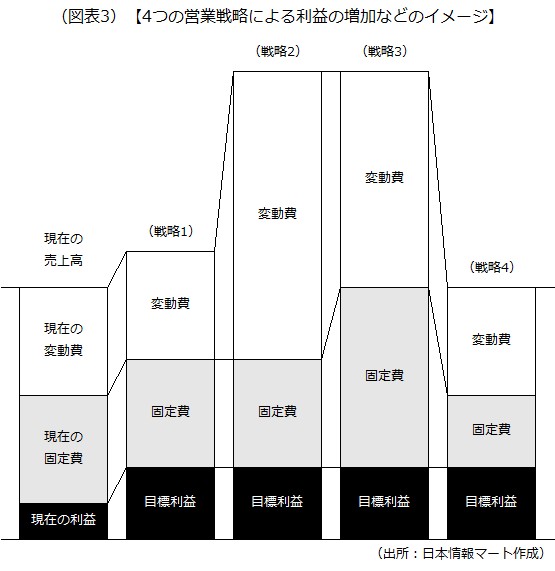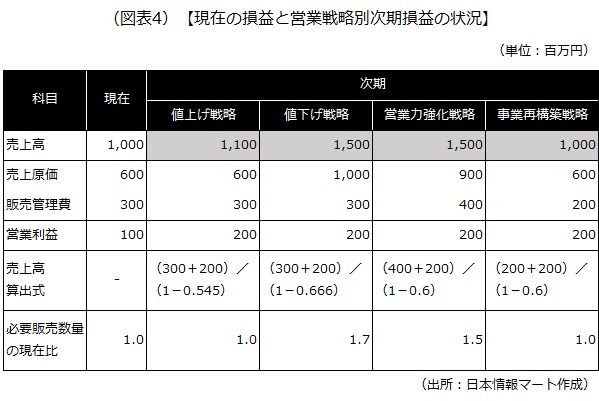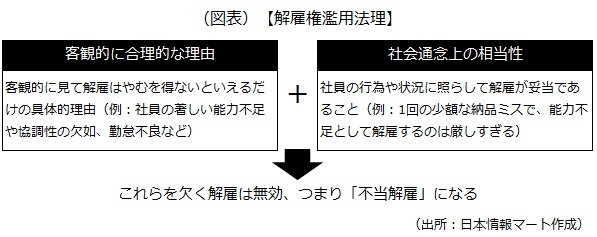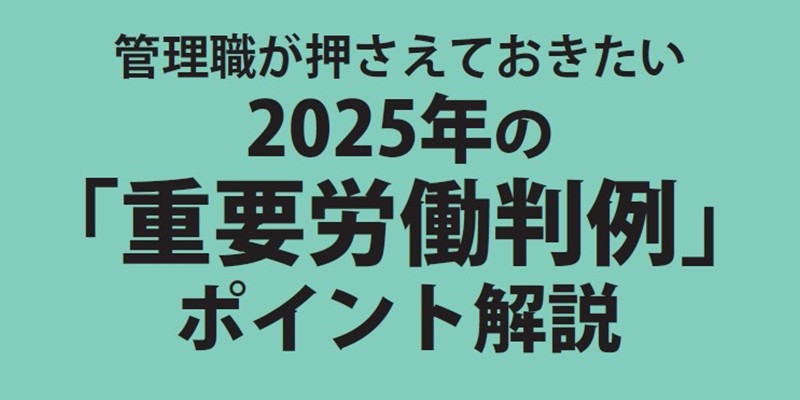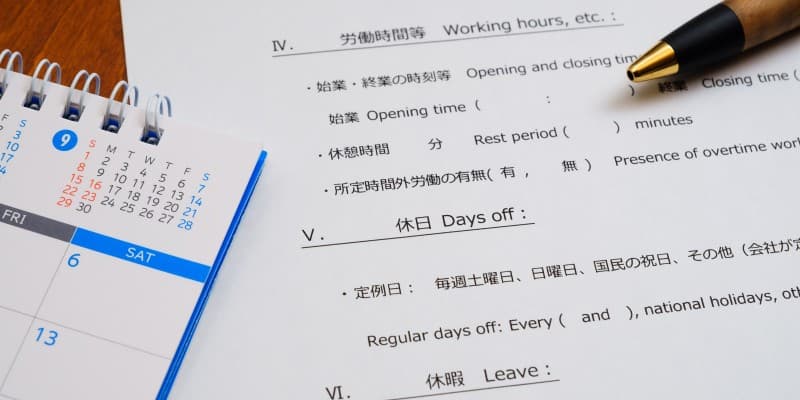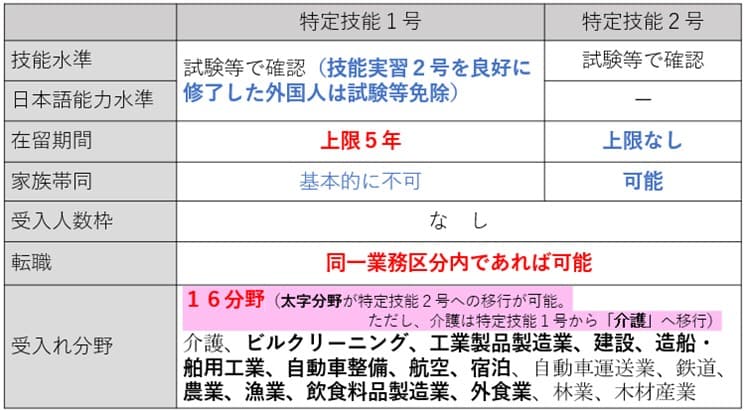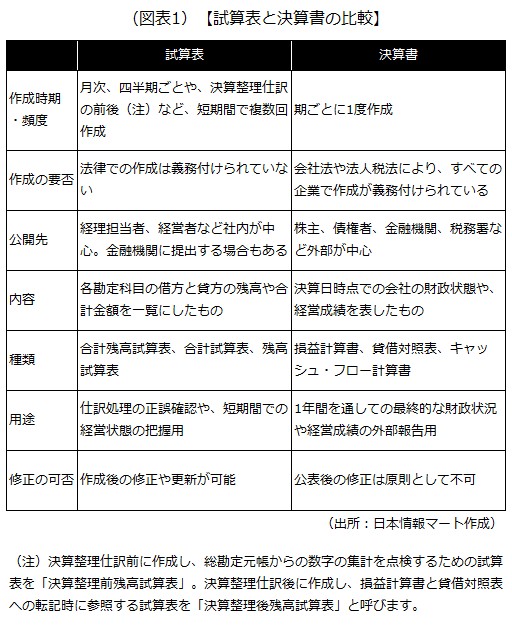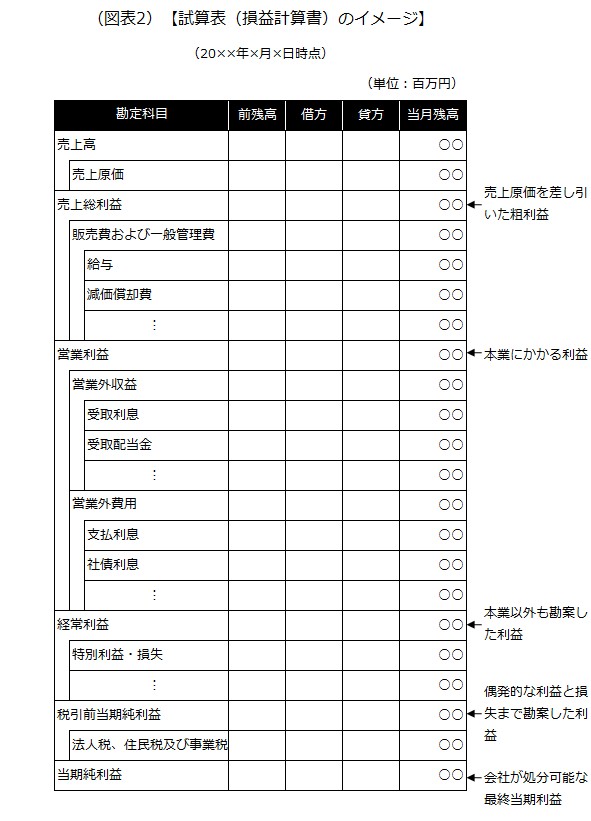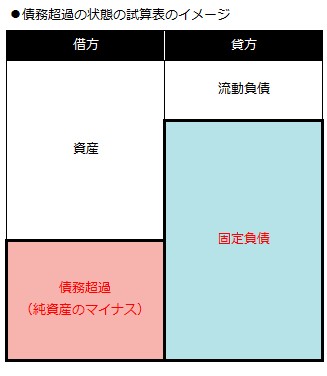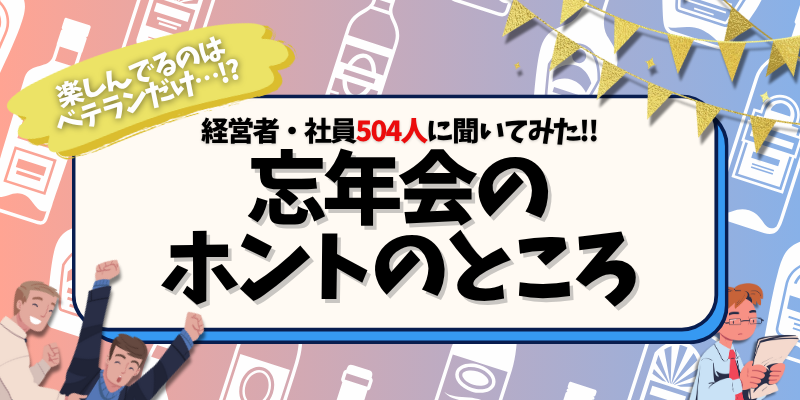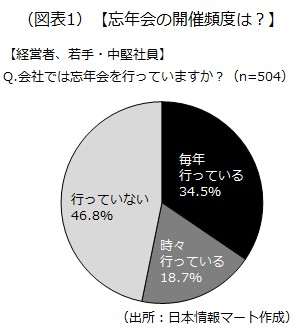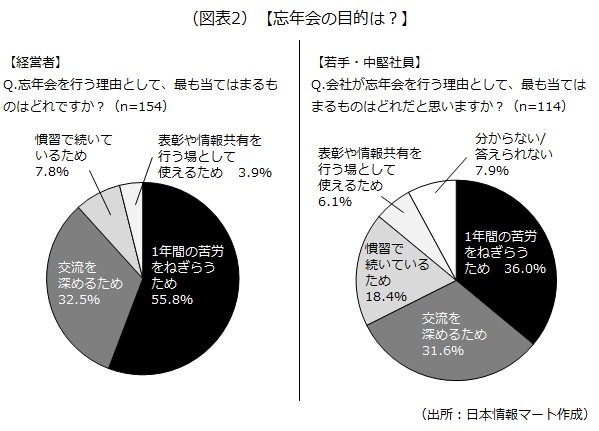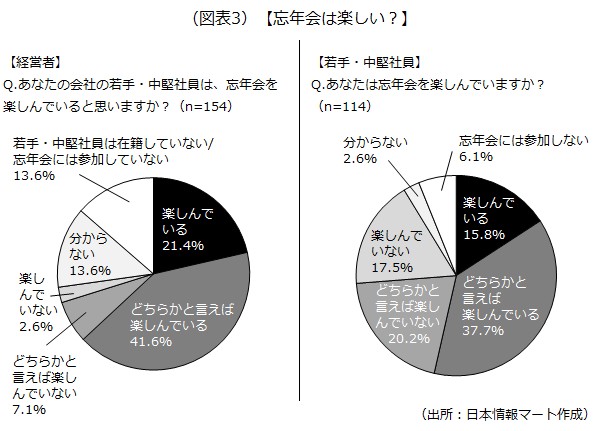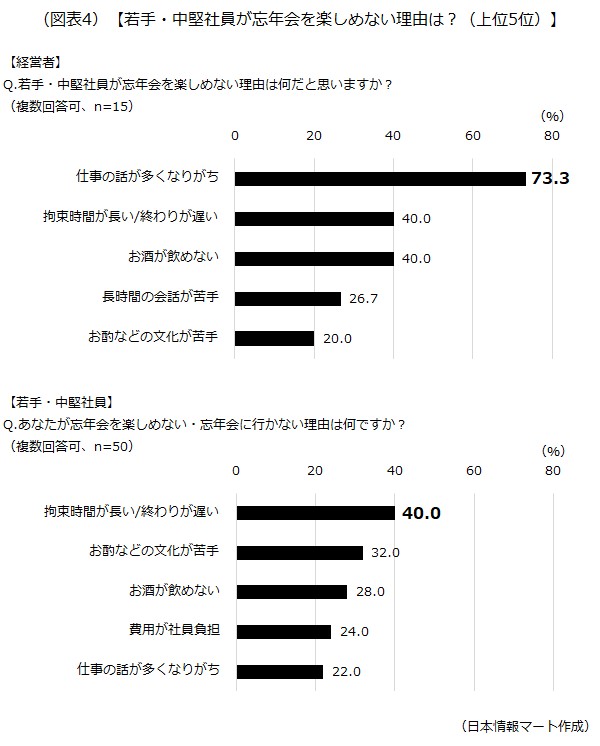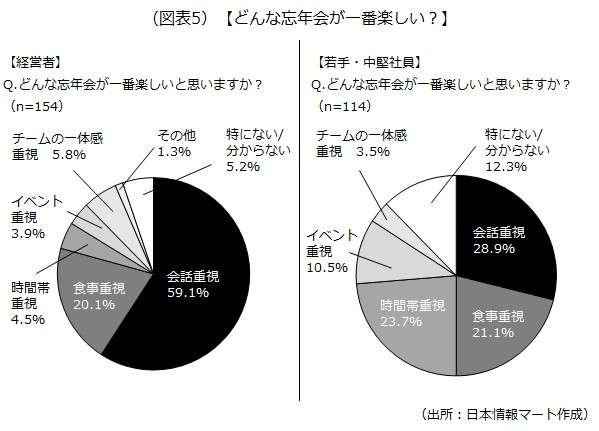目次
- 1 2025年もたくさんの白書が!
- 2 中小企業白書(中小企業庁)
- 3 経済財政白書(内閣府)
- 4 ものづくり白書(経済産業省)
- 5 情報通信白書(総務省)
- 6 科学技術・イノベーション白書(文部科学省)
- 7 エネルギー白書(資源エネルギー庁)
- 8 環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書(環境省)
- 9 食料・農業・農村白書(農林水産省)
- 10 森林・林業白書(林野庁)
- 11 水産白書(水産庁)
- 12 国土交通白書(国土交通省)
- 13 観光白書(観光庁)
- 14 厚生労働白書(厚生労働省)
- 15 男女共同参画白書(内閣府)
- 16 こども白書(こども家庭庁)
- 17 食育白書(農林水産省)
- 18 防災白書(内閣府)
- 19 交通安全白書(内閣府)
- 20 警察白書(警察庁)
- 21 防衛白書(防衛省)
1 2025年もたくさんの白書が!
白書とは、特定の分野について国が現状と課題、これからの方針を公式にまとめたレポートです。「中小企業白書」「エネルギー白書」「環境白書」、耳にはするけれど中身まではなかなか目を通せていないという人は多いでしょう。ですが、最新の統計データや業界動向、政策の方向性が整理されている白書は、経営者にとって重要な「情報の宝庫」です。
2025年もたくさんの白書が公表されました!この記事では、数ある白書の中から20種類を取り上げ、直近の内容を紹介します。世の中でどのような動きがあったのか、さまざまな分野の白書を通して見ていきましょう。
2 中小企業白書(中小企業庁)
中小企業白書は、中小企業の実態や課題、国の中小企業政策の現状と今後の方向性をまとめた白書です。直近の2025年版には、次のような内容が記載されています。
■中小企業庁「2025年版『中小企業白書』」■
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/
1)中小企業・小規模事業者の動向
中小企業・小規模事業者の課題として、円安・物価高の継続、「金利のある世界」の到来、構造的な人手不足の深刻化、過去最高水準の賃上げ圧力への対応などが挙げられています。経営者年齢も依然高い水準で推移しており、事業承継に向けた取り組みが必要とされています。
2)会社の成長・持続的発展に向けて有効な取り組み
経営力を個人特性面・戦略策定面・組織人材面の3つの視点で捉え、バランスよく強化すること、規模ごとに異なる「成長の壁(例:中小企業(成長段階)なら、経営者の一人体制の限界、スキル不足など)」の打破が求められています。
2025年版の内容については、こちらのコンテンツでも紹介しています。
3 経済財政白書(内閣府)
経済財政白書は、日本の景気や物価、雇用などの経済動向と、国の財政状況・財政運営の課題、今後の経済財政政策の方向性をまとめた白書です。直近の2025年度版には、次のような内容が記載されています。
■内閣府「令和7年度経済財政白書」■
https://www5.cao.go.jp/keizai3/whitepaper.html
1)日本経済の動向と課題
2025年半ばまでの経済の動向が記載されています。名目GDPが600兆円を超え、国内民間最終需要は1年にわたり増加を続ける一方、米国の関税措置による世界経済の下押しを通じた輸出への影響等が懸念されています。設備投資は持ち直しの動きが続いていますが、不確実性の高まりによる影響には留意が必要とされています。
2)賃金上昇の持続性と個人消費の回復に向けて
2024年度の賃金は、33年ぶりの賃上げ率となった春季労使交渉や、過去最大の上げ幅となった最低賃金の引上げ等の効果もあって、1994年以来最高の賃上げ率となりました。しかし、物価上昇との関係もあり、賃金が上昇したという実感を持つ人は、さほど増加しているわけではないようです。個人消費については、高齢層を中心に物価上昇における節約意識が働いており、消費の回復には給与所得の増加が特に重要とされています。
3)変化するグローバル経済と企業部門の課題
過去30年程度における日本の経常収支の変遷や企業行動の変化などが記載されています。また、中小企業の課題として、現預金比率が高い一方で、生産能力を高めるような前向きな設備投資が抑制されていることなどが挙げられています。
4 ものづくり白書(経済産業省)
ものづくり白書は、日本の製造業の現状や課題、生産性向上・DXなどを含む国の「ものづくり政策」の方向性をまとめた白書です。直近の2025年版には、次のような内容が記載されています。
■経済産業省「2025年版ものづくり白書」■
https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2025/index.html
1)製造業の競争力強化に向けたDX
個社単位のデジタル化・効率化は一定の成果が挙がっている一方で、「稼ぐ力」につながるだけの成果を創出できている製造事業者は少ないようです。企業間連携で産業単位の事業効率を向上させることや、ロボット・AIの開発・活用の重要性が示唆されています。
2)経済安全保障を踏まえた製造事業者の持続的成長
約6割の製造事業者が経済安全保障の取り組みを実施していないとされています。政府は、取り組みの好事例の発信等を通じて、経済安全保障の推進を後押ししていくとしています。
3)人材育成の取り組みとデジタル技術の活用
正社員以外の社員の能力開発がコロナ禍前の水準まで回復していないことなどが示唆されています。政府は、人材開発支援助成金や生産性向上支援センター、デジタル技術を含む多様な職業訓練の提供などを通じて、能力開発を支援していくとしています。
4)ものづくりを通じて社会課題の解決に貢献する人材の育成
政府は、デジタル等成長分野の人材育成(半導体人材の育成、産学協働リカレント教育モデルの確立など)、ものづくり人材を育む教育・文化芸術(学校等でのものづくり教育、技術者や伝承者の育成など)、Society5.0(注)を実現する研究開発(ものづくりに関する基盤技術の研究開発、産学官連携など)を推進していくとしています。
(注)Society 5.0:サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会のことで、情報社会(Society 4.0)に続く社会として提唱されています。
5 情報通信白書(総務省)
情報通信白書は、日本のICT(インターネット・スマホ・通信インフラ・デジタル経済など)の動向や課題、国の情報通信政策の方向性をまとめた白書です。直近の2025年版には、次のような内容が記載されています。
■総務省「情報通信白書令和7年版」■
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/index.html
1)「社会基盤」としてのデジタルの浸透・拡大と動向
社会生活、企業活動において、スマートフォン・SNS・クラウド等が浸透・拡大しています。AIについては、世界的な開発競争が激化し、日本においても大規模言語モデル(LLM)の開発が盛んに行われています。一方で、日本のAI活力ランキング(2023年)は世界総合9位と低めで、企業における生成AIの活用方針策定なども海外に比べて遅れがちです。
2)進展するデジタルがもたらす課題
デジタル分野の主要な課題として、「信頼性のあるデジタル基盤の確保」「AIによるイノベーション促進とリスク対応」「サイバーセキュリティ」などが挙げられています。
3)進展するデジタルによる社会課題解決に向けて
少子高齢化が進む地方において、デジタル技術が地方創生のカギを握ることが示唆されています。また、災害が激甚化、頻発化する中、さらなるデジタルインフラの強靱化が引き続き求められていることなどが記載されています。
6 科学技術・イノベーション白書(文部科学省)
科学技術・イノベーション白書は、日本の研究開発や技術革新(AI・宇宙・バイオなど)の動向と課題、国の科学技術・イノベーション政策の方向性をまとめた白書です。直近の2025年版には、次のような内容が記載されています。
■文部科学省「令和7年版科学技術・イノベーション白書」■
https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpaa202501/1421221_00015.html
1)科学技術基本法制定から30年とこれからの科学技術・イノベーション
2025年が科学技術基本法制定から30年の節目に当たることから、同法制定の経緯や制定後30年の歴史などが紹介されています。制定後30年間の日本の科学技術・イノベーションの振り返りとして、「基礎研究力の低下」「人材」「研究インフラ」といった重要課題も掘り下げられています。
2)科学技術・イノベーション創出の振興に関して講じた施策
ものづくり白書の章でも紹介した「Society 5.0」を具体化し、国民の安全と安心を確保しつつ、ウェルビーイングを実現するための取り組みなどが紹介されています。
7 エネルギー白書(資源エネルギー庁)
エネルギー白書は、日本のエネルギー(電気・ガス・石油など)の現状や課題、政府の今後の方針をまとめた白書です。直近の2025年版には、次のような内容が記載されています。
■資源エネルギー庁「エネルギー白書2025」■
https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/
1)福島復興の進捗
福島復興の現状として、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に向けた取り組み(燃料デブリの試験的取り出し成功など)、帰還困難区域の避難指示解除に向けた取り組み(大熊町等での復興再生計画の認定など)、新たな産業の創出に向けた取り組み(福島イノベーション・コースト構想)が紹介されています。
2)GX・2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取り組み
日本のエネルギーを取り巻く環境変化を踏まえた上で、電力インフラ・データセンター立地・通信インフラの適正な整備(ワット・ビット連携)、2050年カーボンニュートラルに向けた次世代エネルギー革新技術(光電融合、ペロブスカイトなど)に関する取り組みなどが紹介されています。
8 環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書(環境省)
環境白書は、日本や世界の環境問題の現状と施策をまとめた白書です。循環型社会白書は、ゴミ削減・リサイクルなどを通じ、資源をムダなく循環させる社会づくりの現状と施策をまとめた白書です。生物多様性白書は、絶滅危惧種や森林・海などの生き物と生態系の保護に関する現状と施策をまとめた白書です。直近の2025年版には、次のような内容が記載されています。
■環境省「令和7年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」■
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/
1)地球温暖化対策の目指す方向
2050年炭素中立(ネット・ゼロ)の実現に向け、温室効果ガスの排出量を2013年度と比べて、2035年度には60%、2045年度には73%削減する目標が設定されています。
2)循環経済(サーキュラーエコノミー)
サーキュラーエコノミーは、資源を効率的に循環させ、持続可能な社会をつくるとともに経済成長も実現するというものです。基本計画や法整備の状況、地域の特性を活かした循環資源や再生可能資源の活用事例などが記載されています。
3)自然再興(ネイチャーポジティブ)
ネイチャーポジティブは、生物多様性を維持するだけでなく、回復させるというものです。「30by30目標(2030年までに、陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全する)」の実現に向けた取り組みとして、保護地域における取り組み(国立公園の指定など)や自然共生サイト(生物多様性が保全されている区域)の認定状況などが記載されています。
4)東日本大震災からの復興に係る取り組み
帰還困難区域における取り組み(避難指示の解除など)、未来志向の取り組み(「脱炭素×復興まちづくり」推進事業の実施など)、ALPS処理水(注)の海洋放出に係るモニタリングの状況などが記載されています。
(注)ALPS処理水:東京電力福島第一原子力発電所の建屋内にある放射性物質を含む水について、トリチウム以外の放射性物質を、安全基準を満たすまで浄化した水のことです。
9 食料・農業・農村白書(農林水産省)
食料・農業・農村白書は、日本の食料供給・農業・農村の今の姿と課題、そして国の今後の方向性をまとめた白書です。直近の2024年度版には、次のような内容が記載されています。
■農林水産省「令和6年度 食料・農業・農村白書 全文」■
https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r6/zenbun.html
1)新たな食料・農業・農村基本計画の策定
2024年に改正された食料・農業・農村基本法に基づき、食料自給率の他、食料安全保障の確保に関する目標を設定し、初動5年間で農業の構造転換を集中的に推し進めるための計画が策定されています。
2)合理的な価格形成と付加価値向上
コスト高騰に伴う農産物・食品への価格転嫁が業界全体の課題であることを踏まえ、合理的な価格の形成に向けた仕組みづくりに取り組んでいることや、消費者からコストの実態への理解・支持を得るための「フェアプライスプロジェクト」を継続していることなどが記載されています。
3)スマート農業と環境戦略
ドローンやAIによる農業の生産性向上や、「みどりの食料システム戦略」に基づく環境負荷低減の取り組みを推進していることなどが記載されています。
10 森林・林業白書(林野庁)
森林・林業白書は、日本の森林や林業(木材利用や山村を含む)の現状と課題、国の森林政策の方向性をまとめた白書です。直近の2024年度版には、次のような内容が記載されています。
■林野庁「令和6年度 森林・林業白書 全文」■
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/r6hakusyo/zenbun.html
1)生物多様性の重要性と関心の高まり
「環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」の章で紹介した内容とも重なりますが、生物多様性に関する国際的な動きとしてネイチャーポジティブの進展、国内の動きとして自然共生サイトの認定状況などが記載されています。
2)日本の森林における生物多様性とこれまでの保全の取り組み
日本の植物種数は5565種と、同じ島国かつ面積も同程度の英国などを上回る生物多様性が確保されています。さまざまな生育段階や樹種から構成される森林が、モザイク状に配置されている状態を目指して、多様な森林整備が推進されています。
3)生物多様性を高める林業経営と木材利用に向けて
林野庁が2024年に「森林の生物多様性を高めるための林業経営の指針」や「建築物への木材利用に係る評価ガイダンス」を公表したことなどが記載されています。
11 水産白書(水産庁)
水産白書は、日本の水産業・漁業や水産資源の現状と課題、今後の水産政策の方向性をまとめた白書です。直近の2024年度版には、次のような内容が記載されています。
■水産庁「令和6年度 水産白書 全文」■
https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/R6/250606_1.html
1)海洋環境の変化の状況
2024年の日本近海の平均海面水温が、統計開始以降、最も高い値となっています。また、黒潮大蛇行が2017年から継続し、過去に例のない長さで発生しており、黒潮が接岸する関東沖・東海沖では海水温が上昇する傾向にあります。
2)海洋環境の変化による水産資源・水産業への影響
海水温の上昇や海流の変化が、水揚量の減少、漁場まで遠出することに伴う燃油等の費用増加、出漁の見合わせなど漁業経営に大きな影響を与えています。特に、サンマ、スルメイカ、サケの漁獲量が近年大きく減少しています。
3)海洋環境の変化に対応するための取り組み
漁業・養殖業における取り組みとして「いか釣り漁船によるスルメイカ不漁に伴うアカイカ操業の実施」などが、加工・流通・消費に向けた取り組みとして「サワラの漁獲量が増加した地域におけるブランド化の取り組み」などが、漁港・漁場における取り組みとして「藻場再生」などが紹介されています。
4)今後の海洋環境の変化への対策
気候変動への緩和策として、水産分野では、漁船の電化・水素化等に関する技術の確立により、CO2の排出削減を図ること、CO2吸収源としてのブルーカーボンを推進することなどが記載されています。
12 国土交通白書(国土交通省)
国土交通白書は、日本の国土・インフラ・交通(道路・鉄道・空港・港湾など)の現状と課題、国土づくり・交通政策の方向性をまとめた白書です。直近の2025年版には、次のような内容が記載されています。
■国土交通省「令和7年版国土交通白書」■
https://www.mlit.go.jp/statistics/file000004.html
1)国土交通分野における担い手不足等によるサービスの供給制約の現状と課題
建設業や運輸業の課題として、いわゆる「2024年問題」への対応や、就業者の高齢化・若年者の入職の減少、中長期的な担い手の確保・育成などが挙げられています。担い手不足等によるサービスの供給制約(メンテナンス不足で、水道の断水・漏水が発生するなど)についても記載されています。
2)国土交通分野における取り組みと今後の展望
業界内の人材の確保・定着に向け、「賃上げを含む処遇改善」「適切な価格転嫁」などに関する施策の状況が掲載されています。ICTスキル等により建設技術者の一部業務を代行する新職種「建設ディレクター」の活用や、人に代わり自動で鉄筋結束作業を行うロボットの導入などの事例も紹介されています。
13 観光白書(観光庁)
観光白書は、日本の観光(インバウンド・国内旅行・地域観光など)の動向や課題、国の観光政策の方向性をまとめた白書です。直近の2025年版には、次のような内容が記載されています。
■観光庁「『令和6年度観光の状況 令和7年度観光施策』(観光白書)について」■
https://www.mlit.go.jp/kankocho/news02_00041.html
1)世界の観光の動向
2023年の「外国人旅行者受入数ランキング」において、日本(2510万人)が世界15位(アジアで2位)となりました。また、2024年の国際観光客数は14億4500万人(前年比10.7%増、2019年比1.3%減、世界観光機関(UN Tourism)の統計)と、コロナ前の2019年水準まで回復しています。
2)日本の観光の動向
2024年の訪日外国人旅行者数が3687万人(2019年比15.6%増)と過去最高を記録し、2024年の日本人の国内延べ旅行者数は5.4億人(2019年比8.2%減)とコロナ前の9割程度に回復しています。
3)日本人の国内旅行の活性化に向けて
仕事より余暇を重視する割合が増加傾向にある中で、一人当たり旅行回数の増加や滞在長期化を図る必要があるとされています。地域の取り組み事例として、「何度も地域に通う旅、帰る旅等の推進」「ワーケーション・ブレジャー等の普及促進」などが記載されています。
14 厚生労働白書(厚生労働省)
厚生労働白書は、日本の暮らし(医療・年金・福祉など)と働き方(雇用・労働政策など)の現状と課題、そして厚生労働行政の今後の方向性をまとめた白書です。直近の2025年版には、次のような内容が記載されています。
■厚生労働省「令和7年版厚生労働白書」■
https://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/index.html
1)変化する社会における社会保障・労働施策の役割を知る
次世代の主役となる若者向けに、社会保障・労働施策の歴史や機能、ヤングケアラー支援の取り組みなどが紹介されています。
2)現下の政策課題への対応
本格的な「少子高齢化・人口減少時代」を迎える中で、賃上げ、非正規雇用労働者の処遇改善、女性・若者・高齢者・就職氷河期世代等の活躍促進等、医療DX等の推進といった政策課題の現状や取り組みが紹介されています。
15 男女共同参画白書(内閣府)
男女共同参画白書は、日本社会における男女平等や女性活躍、男性の家事・育児参画などの現状と課題、国の男女共同参画政策の方向性をまとめた白書です。直近の2025年版には、次のような内容が記載されています。
■内閣府「令和7年版男女共同参画白書」■
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/index.html
1)人の流れと地域における現状と課題
全ての都道府県で、家事関連時間は妻のほうが210分以上、仕事関連時間は夫のほうが180分以上長く、「男性は仕事、女性は家庭」という性別による固定的な役割分担が依然として残っていることなどが示唆されています。
2)若い世代の視点から見た地域への意識
東京圏に住んでいる人は、現在も東京圏以外に住んでいる人よりも、出身地域に「家事・育児・介護は女性の仕事」「食事の準備やお茶出しは女性の仕事」等といった固定的な性別役割分担意識が「あった」と感じている割合が顕著に高いとされています。
3)魅力ある地域づくりに向けて
個性と能力を発揮できる環境整備や魅力的な地域づくりに向け、「固定的な性別役割分担意識等を解消する」「全ての人にとって働きやすい環境をつくる」「地域における女性リーダーを増やす」「地域で学ぶ」の4つの取り組みが重要であるとされています。
16 こども白書(こども家庭庁)
こども白書は、日本のこどもや若者を取り巻く状況と、政府が進めている「こども政策」の取り組み状況を毎年まとめた白書です。直近の2025年版には、次のような内容が記載されています。
■こども家庭庁「令和7年版こども白書」■
https://www.cfa.go.jp/resources/white-paper/r07
1)全てのこども・若者が安全・安心な居場所を見つけられる社会を目指して
自殺対策や孤独・孤立対策等の観点から、全てのこども・若者が居場所を見つけることができるよう、こども家庭庁が「こどもの居場所づくりコーディネーター配置等支援事業」「こどもの居場所づくり支援体制強化事業」などを実施しています。
2)若い世代の描くライフデザインや出会いのサポート
若い世代が結婚・子育ての将来展望を描けない状況に対応するため、「若い世代の描くライフデザインや出会いを考えるワーキンググループ(WG)」が開催されています。WGに基づき、各自治体の「地域少子化対策重点推進交付金」において、若い世代の描くライフデザイン支援や官民連携の結婚支援の取り組みを重点メニューとして支援する旨などが記載されています。
3)保育政策の新たな方向性
2025年度から2028年度末を見据えた保育政策の在り方を示した「保育政策の新たな方向性」が取りまとめられています。「1.地域のニーズに対応した質の高い保育の確保・充実(職員配置基準の改善など)」「2.全てのこどもの育ちと子育て家庭を支援する取り組みの推進(こども誰でも通園制度の推進など)」「3.保育人材の確保・テクノロジーの活用等による業務改善(保育士・幼稚園教諭等の処遇改善など)」の3つが柱となっています。
4)こどもの悩みに寄り添える社会に向けて
こども・若者にとっての利益を考え、そのための取り組み・政策を社会の中心に据える「こどもまんなか社会」の実現に向けて、「こどもの悩みを受け止める場に関するプロジェクトチーム」が発足しています。
17 食育白書(農林水産省)
食育白書は、日本人の食生活や「食に関する学び(食育)」の現状と課題、国の食育推進の取り組みをまとめた白書です。直近の2024年度版には、次のような内容が記載されています。
■農林水産省「令和6年度 食育白書(令和7年6月10日公表)」■
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/wpaper/r6_index.html
1)食卓と農の現場の距離を縮める取り組みと今後の展望
食育に関心を持たない国民が増える中で、持続可能な食料システムを実現していくためには、国民が食生活を通じて農林水産業を意識する機会を作ることが大切であるとされています。食育の事例として「スポーツ選手と子どもたちによる田植えや稲刈り等の農業体験」などが記載されています。
2)消費者の行動変容を促す「大人の食育」の推進
若い世代(20~30歳代)や高齢者世代も、食に関する課題を多く抱えており、健康に生活するための「大人の食育」が大切であるとされています。食育の事例として「会社の従業員が野菜の知識を学ぶプログラム『食育マルシェ』」などが記載されています。
18 防災白書(内閣府)
防災白書は、日本で起きた地震・豪雨などの災害の状況と教訓、国や自治体の防災・減災の取り組みや今後の方針をまとめた白書です。直近の2025年版には、次のような内容が記載されています。
■内閣府「令和7年版防災白書」■
https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/r7.html
1)令和6年能登半島地震等の概要
被災者の生活と生業(なりわい)支援のためのパッケージの実施、避難生活支援コーディネーター等の育成など、支援体制の強化が進められています。「被災者による朝市の復興(出張輪島朝市)」などのコラム記事も紹介されています。
2)令和6年能登半島地震を踏まえた防災対応の見直し
デジタル技術を活用した防災情報システムの整備や、地域防災力の強化に向けた取り組みが明記され、頻発・激甚化する災害に備える体制強化が進められています。
19 交通安全白書(内閣府)
交通安全白書は、日本の交通事故の実態や原因、歩行者・自転車・自動車などへの安全対策、国の交通安全政策の方向性をまとめた白書です。直近の2025年版には、次のような内容が記載されています。
■内閣府「令和7年版交通安全白書」■
https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/index-t.html
1)交通事故の状況
2024年の交通事故の死者・重症者数は2万9948人で、2015年の4万3076人から10年間で約30.5%減少しています。特に小学生は、2015年が1185人、2024年が686人と約42.1%減少しています。一方で、小学生の飛び出しによる事故が多く発生しており、効果的な交通安全教育等の実施、自動車等の運転者に対する教育の実施の必要性などが示唆されています。
2)通学路における交通安全の確保に向けた取り組み
通学路点検や歩道整備、スクールバスの運行、地域による見守り活動が推進されています。また、最高速度30キロメートル毎時の区域規制等を実施する「ゾーン30」の整備などが進められています。
20 警察白書(警察庁)
警察白書は、日本の犯罪などの治安情勢と警察の取り組み、今後の警察行政の方向性をまとめた白書です。直近の2025年版には、次のような内容が記載されています。
■警察庁「令和7年版警察白書」■
https://www.npa.go.jp/hakusyo/r07/index.html
1)SNSを取り巻く犯罪の情勢
SNSを通じて対面することなく、恋愛感情や親近感を抱かせたりして金銭をだまし取るSNS型投資・ロマンス詐欺の被害が著しく増加しています。匿名・流動型犯罪グループが、仕事の内容を明らかにせず、「高額」「ホワイト案件」等の表現を用いるなどして実行者を募集し、こうした犯罪に及ぶケースが確認されています。
2)SNSを取り巻く犯罪に対処するための警察の取り組み
SNSを取り巻く犯罪に対処するため、デジタル・フォレンジック(犯罪の立証のための電磁的記録の解析技術・手続き)を活用した捜査、匿名・流動型犯罪グループに「雇われたふり」をして検挙するための仮装身分捜査などが進められています。
21 防衛白書(防衛省)
防衛白書は、日本や周辺地域の安全保障環境と自衛隊の活動状況、そして日本の防衛政策の考え方・方向性をまとめた白書です。直近の2025年版には、次のような内容が記載されています。
■防衛省「令和7年版防衛白書」■
https://www.mod.go.jp/j/press/wp/index.html
1)統合作戦司令部と統合作戦
2025年3月に新設された「統合作戦司令部」について記載されています。海・空自の主要部隊や、宇宙やサイバー領域などで活動する部隊の指揮が、平素から統合作戦司令部官に一元化され、各種事態に迅速に対応できる体制になっています。
2)自衛官の処遇・勤務環境の改善、新たな生涯設計の確立
2024年度に取りまとめられた、「自衛官の処遇・勤務環境の改善及び新たな生涯設計の確立に関する基本方針」の一例が紹介されています。自衛官の処遇改善(30を超える手当の新設・金額引き上げなど)、生活・勤務環境の改善(営内隊舎の居室の個室化など)、新たな生涯設計の確立(再就職先の拡充等)といった内容が記載されています。
3)防衛この一年
災害派遣や対領空侵犯措置、在外邦人等輸送任務など、2024年度に国内外で活躍した隊員の声が紹介されています。
以上(2025年12月作成)
pj80199
画像:各白書より作成