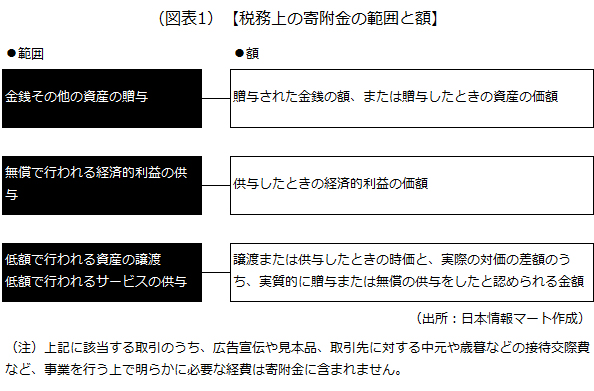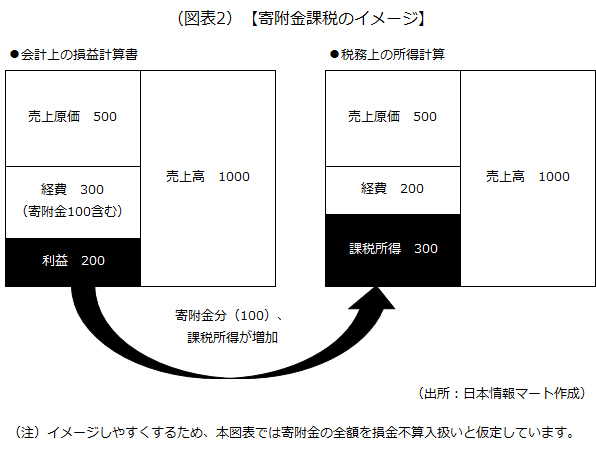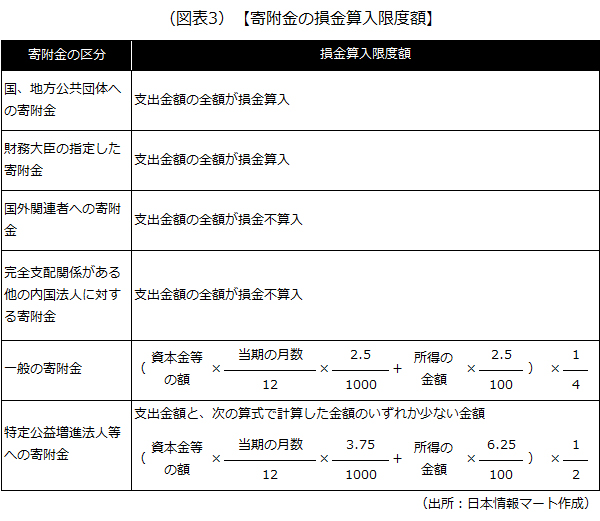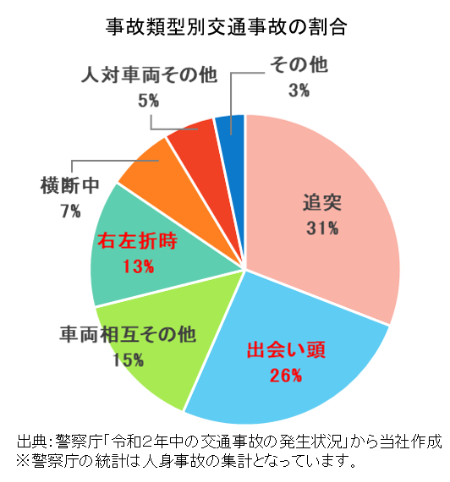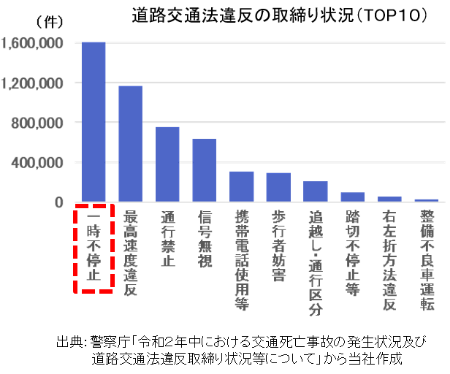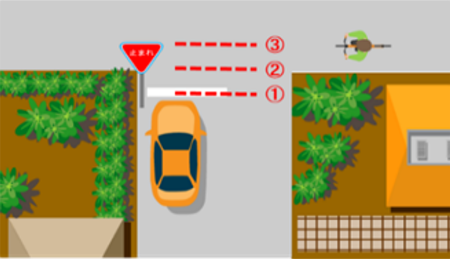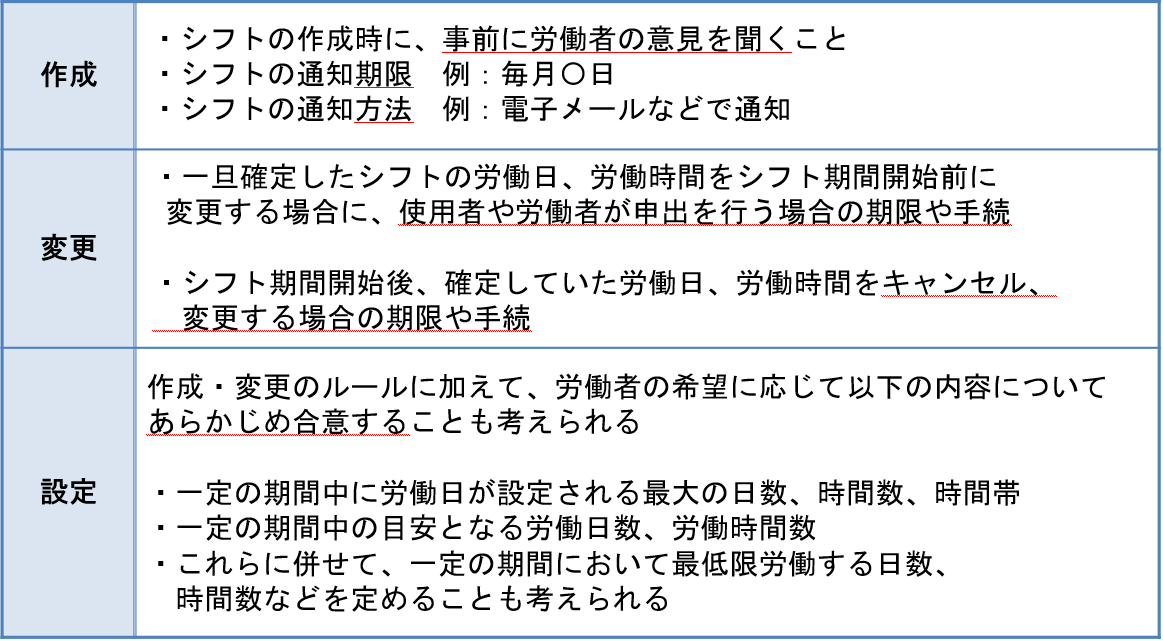書いてあること
- 主な読者:「ダイバーシティ経営」が気になっている経営者
- 課題:「ダイバーシティ経営」という言葉をよく聞くが、なぜ「ダイバーシティ経営」をしなければならないのか、本当に自分たちの会社に関係あるのかが分からない
- 解決策:4つのキーワードと「ダイバーシティインデックス」を知り、具体的な取り組みイメージをつかむ

【インタビュー相手】
佐々木かをり(ささき かをり)氏
株式会社イー・ウーマン代表取締役社長。ダイバーシティの第一人者。日本最大級のダイバーシティ会議「国際女性ビジネス会議」を26年にわたり企画・プロデュース。組織の多様性と成長性を年1回数値化する「ダイバーシティインデックス」を開発、今年第5回目を募集する。内閣府男女共同参画会議、厚生労働省など多くの政府審議会等委員、上場企業等の社外取締役を務める。世界銀行「女性起業家資金イニシアティブ(We-Fi)」日本代表。日本語・英語での講演も多くAPEC、OECDなど国内外で1700回を越える。メディア出演も多い。
1 “ダイバーシティ経営”にまつわる誤解
近年、“ダイバーシティ経営”という言葉が広がり、これを経営戦略や経営計画に掲げる企業も増えています。ダイバーシティは“多様性”を意味し、政治的背景、社会的背景、経済的背景など様々な文脈で語られていますが、企業として実践すべき“ダイバーシティ経営”として見てみると、その企業にとって都合よく偏った解釈に基づいていたり、きわめて表層的な側面だけを捉えていたり、といった状況が散見されます。
「ダイバーシティ経営の目的や効果を本質的・根本的に理解していない経営者の方々が多い」
“ダイバーシティ経営”を30年来唱え続ける、ユニカルインターナショナル、イー・ウーマンで代表を務める佐々木かをり氏はこう指摘されています。「ダイバーシティ経営を“女性活躍”と置き換えて解釈し、“女性社員を増やすことでしょう? うちのように男性中心の業界には関係ないよ”と言う方もいらっしゃいますし、“女性社員を増やしているし、管理職の女性比率も〇%だからダイバーシティ経営はできているよ”と言う方もいらっしゃいます。しかし、いずれも完全な理解ではありません。また、業界特性上、女性社員を増やすことが難しいといった固定観念も自社のためになりません。ダイバーシティ経営=女性比率だけではありませんので、ぜひ、ダイバーシティ経営がどれだけ自社にとって重要かを知ってほしいと思います」
このようにダイバーシティ経営を“女性活躍”として捉えてしまっている例の他、外国人雇用として捉えてしまっている方も多いようです。地方の建設業、製造業などでは、外国人労働者を積極的に多数雇用している企業が多く、外国人雇用者数のみを見て、ダイバーシティ経営をしているとおっしゃる経営者の方も少なくないようです。
ダイバーシティ経営に対するこれらの誤解は、日本固有の社会情勢に起因するところもあります。2000年代から少子高齢化が大きな社会問題として強く叫ばれるようになり、将来の労働力不足の懸念から、女性、外国人、さらには高齢者も含め、積極的に活用しようという流れが起こり、この流れと欧米で発展したダイバーシティ経営が紐づけて語られるようになってしまった、というのが現在の日本における“ダイバーシティ経営”です。単なる労働力MIXでしかないような場合でも、その比率をもってダイバーシティ経営をしているつもりになってしまうわけです。
また、ダイバーシティ経営という言葉が持つポジティブなイメージから、これを企業PRやマーケティングに活かすよう、看板や道具としている企業も少なくありません。この点について、佐々木かをり氏は「上場企業や大手企業では、各種の機関や団体が示す女性管理職比率や障碍(がい)者雇用比率の指標を達成してAwardや認証を取得することで安心しているように見えるケースもあります。また、IR活動として、各種の目標指標を示して、社内サーベイの結果と達成状況を市場に発信している企業もあります。こうした取り組みは第一歩に過ぎず、ダイバーシティ経営の本質を全うするためには、さらに前進が必要です」と懸念を示されています。「せっかくダイバーシティ経営に向けての組織作り、採用活動、社内セミナー等に対して真面目に取り組んでも、先述のような認識に依拠し、企業風土として全社的に浸透しない、企業活動の担い手である中間管理職層の理解が得られない、企業成長につながる形で昇華されない、という状況に陥りがちです。次の段階、すなわち本来のダイバーシティ経営の成果を得る段階に移行が必要な企業も多いことが現状です」(佐々木かをり氏)
では、ダイバーシティ経営の本質とは何なのか、その目的・意義、期待できる効果はどういったものなのか。次章で明らかにしていきます。
2 ダイバーシティ経営の本質
「ダイバーシティ経営は、多様な労働者を雇用し、その人たちの力を活かし、声を聞き、会社を変革していくことによって、社会への還元に留まらず、企業の成長、そして、もうけられる企業への転換につながること。それが目的なのです」(佐々木かをり氏)
ダイバーシティ経営が一体どうやって企業の成長につながるのでしょうか? その点についてさらにご説明いただきました。「Collective Genius、日本語では“集合天才”と訳され、“三人寄れば文殊の知恵”と言われることもありますが、多様な視点を集めてこれを経営に活かしイノベーションを起こすということ。これが企業成長の源泉になります。なぜダイバーシティ経営が必要なのか? と問われれば、人権を守りながら、持続可能な社会を作るための基本であることは間違いないですが、それが実は、企業の成長やイノベーションを起こすことに直結しているのです。こうした考えに基づき組織、制度、風土を醸成することで、長期的に成長する企業組織となっていくことがダイバーシティ経営の本質です。ダイバーシティ経営に取り組まない企業には、成長も未来もありません」(佐々木かをり氏)
ダイバーシティ経営は、人間社会としてのモラルや倫理に根差すソフトなアクションに加え、競争市場でのハードな“攻め”のアクションとしても捉える必要がありそうです。社会的要請に応えるため、あるいは市場からの批判や非難を避けるためといった消極的な目的に基づくアクションではなく、あくまでも成長戦略、競争戦略としての積極的なアクションであることを肝に銘じなければなりません。こうしたことを踏まえ、ダイバーシティ経営の本質、目的・意義、期待効果を見失うことなく、着実な取り組みにするために押さえておくべき4つのキーワードについてご説明いただきました。
1)ダイバーシティ(Diversity=多様性)
本稿のテーマが“ダイバーシティ経営”ですので、改めて掲げるまでもないかもしれませんが、先述の通り、女性や障碍(がい)者など偏った見方を持たれている方が多いのも事実です。企業の成長を見据え、「性別、年齢、国籍、経歴など多様な人材を採用し、昇格させる人事・採用戦略がダイバーシティの基礎であり重要です」(佐々木かをり氏)。多様性のある人材が長期にわたって企業の価値創造に貢献できる環境を作っていくこと自体が、企業の自力を高めていくことになります。
2)エクイティ(Equity=公平)
「今大切なキーワードは、エクイティです。イクオリティ(Equality=平等)と異なる概念です。“平等”とは、すべての人を同じように扱うことを意味します。一方で、“公平”とは、個々の状況やニーズを踏まえながら誰もが力を発揮できるように条件に揃えていくことです」(佐々木かをり氏)
言うは易く行うは難しではありますが、企業の成長という観点、すなわち個々に異なる従業員から見て有利不利がなく事業成果や付加価値を適正に図る仕組みを継続的に改善していくことが重要になります。
3)インクルージョン(Inclusion=包含)
多様な人材を採用したとしても、それらの人材が委縮し、自身の意見や考え方を示せずにいたら、新たな気付きや発見はありません。「多様な意見や考え方が気兼ねなく自由に示され、それらを広く包み込み、受け入れ、業務を進化させていく組織風土を作り上げることが重要です」(佐々木かをり氏)。そこから自由闊達な意見交換が重ねられ、イノベーションの種が見つけられるのです。最近では、製品開発や技術改革、研究開発や組織改革などにおいて、自社以外の組織や機関などが持つ知識や技術を取り込んでいく“オープンイノベーション”が度々話題に上りますが、まずは社内の多様な人材がオープンに意見交換し、互いの考え方を受け入れ、尊重する土壌を作ることが重要です。我々日本人は、比較的近しい環境で育った者同士が集まって活動している機会が多いため、特にこの点は留意する必要があります。
4)ガバナンス&イノベーション(Governance & Innovation=内部統制と革新)
ダイバーシティ経営が全社に及んでいくことにより、経営の意思決定も様々な意見交換や議論を通じて行われることになります。スピード経営が求められる昨今の競争環境においては、社長一人の意思決定のほうが速やかな対応ができ優位性があるように見え、ダイバーシティ経営では最終的な意思決定に時間と労力を要するように見えます。しかしダイバーシティ経営で生み出したイノベーションが世に出るスピードを高めて企業成長することが重要です。
「ダイバーシティ経営ではイノベーションが起きるだけでなく、役員レベルに多様な視点が入ることで内部統制が働き、社長の一存や勘に頼らない適切かつ革新的な意思決定を導く、またリスク回避にもつながります」(佐々木かをり氏)
3 中小企業にダイバーシティ経営が求められる理由
これまでに述べた通り、ダイバーシティ経営は、激しい競争に打ち勝つことを目的にした成長戦略、競争戦略としての積極的なアクションであり、このことは、中小企業にとっても何ら変わることなく当てはまることになります。とは言え、多くの中小企業にとっては、限られた経営資源(従業員)を多様化させること自体に限界があり、自分たちの課題として認識しづらい状況にあるのではないかと思われます。しかしながら、佐々木かをり氏によると、中小企業はダイバーシティ経営の実践を急務として考えねばならない状況にあるようです。以下、その状況についてご説明いただきました。
1)取引先や関係会社の変化
昨年(2021年)6月、東京証券取引所はコーポレートガバナンス・コードに係る有価証券上場規程の一部改正を公表・施行しました。改正の主なポイントの1つとして「企業の中核人材における多様性の確保」が挙げられています。これらは上場企業に求められる事項ではあるものの、新たな成長を実現する企業全般に求められる要素として受け止められています。また、「こうした事項が求められている上場企業は、共に成長する取引先企業として、ダイバーシティ経営を行っている企業のみを選ぶことがルールとなり始めています」(佐々木かをり氏)
すなわち、中小企業にとっても、ダイバーシティ経営を真剣に考えるときが来ているということです。
2)投資家、金融機関の変化
ダイバーシティ経営の本質を考えるにあたり、SDGsの文脈に若干触れましたが、それとは別の流れとして、投資家や金融機関における判断基準の変化があります。「これまでのような経営財務や事業価値の観点だけで投融資を判断するのではなく、SDGsやESGなどの非財務情報が投融資の判断となる流れになっています」(佐々木かをり氏)
換言すると、経営財務や事業価値が高く評価されたとしても、ダイバーシティ経営が十分に行われていなければ将来性に乏しいと見られ、必要な投融資を引き出せない事態もあり得る状況になりつつあります。なお、中央省庁や地方自治体による補助金事業等においては、応募資格としてダイバーシティ経営の深度が問われるような事項が含まれています。ダイバーシティ経営を含むSDGsやESGに関する取り組みが、中小企業を含む事業体の評価・判断に広く使われるようになる流れはますます進んでいくことでしょう。
3)需要サイドの多様化(供給サイドの多様化対応)
BtoC領域のみならず、BtoB領域においても、製品やサービスの需要サイドは多様化が進んでいます。以前から言われていることではありますが、需要サイドの多様化が進み、需要サイドが選ぶ側になり、供給サイドは選ばれる側になっています。需要サイドが発する様々なメッセージやニーズを的確に把握し、それに応えていくためには、供給サイドもダイバーシティ経営を推し進め、多様なプロトコルで双方向のやり取りができる体制を備え、選ばれる企業に変貌しなければなりません。「ダイバーシティ経営に取り組んでいない企業は、ダイバーシティ経営を重視する取引先や協力会社と建設的・発展的なコミュニケーションが取れなくなります。企業を取り巻く環境変化を理解し消化することができない中小企業は、ビジネス機会が減っていく可能性があるのです」(佐々木かをり氏)
4 ダイバーシティ経営“事始め”
ここまで、ダイバーシティ経営の本質は、企業成長のための戦略的・積極的な“攻め”のアクションであり、ダイバーシティ経営の実践は、中小企業を含む事業体にとって急務であることを申し述べてきました。“ダイバーシティ経営の重要性や緊急性はよく分かった。では、いったいどこから手を付ければいいのか?”。こうした問いに対して、佐々木かをり氏より助言をいただきました。
1)ダイバーシティ状況の可視化
どのような企業変革テーマであっても、まずは自社の状況や立ち位置を客観的に捉えることが重要です。単に人数やその比率を計測するのではなく、ダイバーシティの進捗状況や課題を可視化することはできないか、という問題認識の下、国内外のダイバーシティ有識者や様々な企業の協力によって作られたのが、様々な企業が年1回参加する『ダイバーシティインデックス』です。
ダイバーシティインデックスは、先述した4つのキーワード、“ダイバーシティ”、“エクイティ”、“インクルージョン”、“ガバナンス&イノベーション”の4つの角度から、自社のダイバーシティ経営とその成果を客観的に数値で把握することができます。ダイバーシティインデックスが備えているプログラムは、①企業の意識調査、②個人の認識調査、③個人テスト・セルフラーニングの3つのセクションで構成されています。年1回、非財務情報を可視化し、他社の状況をベンチマークしながら経営者や従業員に対する“気付き”の機会を与えるプログラムになっています。ダイバーシティ経営を取り組み始める初年度から記録を始め、毎年の経年変化を把握しながら取り組んでいくことが重要でしょう。「ダイバーシティインデックスは、経営戦略に使えるように作られており、ESG経営におけるS(ソーシャル)とG(ガバナンス)に相当する部分を数値化しています。社内改革のみならず、IRにも活用でき、ESG投資家などからも注目を集めています」(佐々木かをり氏)
2)業界を越えたダイバーシティ連携
先述の通り、多くの中小企業にとっては、限られた経営資源(従業員)を多様化させること自体に限界があるのも実態であり、ダイバーシティ経営への取り組みも段階的・長期的にならざるを得ないという側面があります。しかしながら、ダイバーシティ経営は、社内に限って考えなければならないものではありません。ダイバーシティ経営の本質は、企業成長のための戦略的・積極的な“攻め”のアクションですから、そうした観点から自社でできることを考えてみるべきです。そのうちの1つとして、他社とのダイバーシティ連携があります。ダイバーシティですから、同じ業界や関係会社などとではなく、まったく異なる業界の企業と、“ダイバーシティ経営”という共通の目的を持って、様々な取り組みを協働していき、お互いのイノベーションの発芽を目指していくことになります。もちろん、業界を越えた事業展開の青写真がすでにあった上で提携できればこの上ないですが、そういった青写真がなくとも、“ダイバーシティ経営“という目的のみで始めることで、想像を越えるイノベーションを生み出す可能性があります。また、企業と企業の連携に限らず、自社の顧客や利用ユーザーをメンバー化し、経営者層から従業員層まで広く展開して、仮想的・疑似的なダイバーシティ組織を組むことは、中小企業にとってもすぐに実践できる取り組みです。
3)社外取締役の戦略的登用
昨年(2021年)3月から、上場会社では社外取締役の設置が義務化されました。その理由は、取締役会の運営を健全化する観点から、会社からの独立性が高い人材を経営陣に送り込む必要があるためです。こうした流れは上場会社に限ったことではなく、事業体として取締役会の運営を健全化し、さらには有効化・高度化していきたいという考えの下で、社外取締役を戦略的に登用していこうとする企業が増えています。
“ダイバーシティ経営”の文脈で言えば、社外取締役の戦略的登用は、“はじめの一歩”になる取り組みになります。ダイバーシティ経営の4つのキーワードの1つ、“ガバナンス&イノベーション”でも触れた通り、社外取締役を戦略的に迎え入れることにより、経営の意思決定に内部統制が働き、加えて適切かつ革新的な意思決定に導くことにつながります。ダイバーシティ経営は一朝一夕にはいかず、相応の時間を要する取り組みですが、社外取締役の戦略的登用は、経営者層として取り組みやすい施策ではないでしょうか。「私自身、複数の企業の社外取締役を担わせていただいており、社外取締役の役割は、取締役会に多様な視点を持ち込み貢献することだと実感しています。成長への視点とリスク回避への視点の両方の視点を加えるダイバーシティ経営とは、ガバナンス強化そのものです。適切な社外取締役を探している企業のために、優秀な女性や外国人などの独立社外取締役を企業にご紹介するお手伝いも始めました。日本企業が社外取締役を活用し、成長することを心から期待しています」(佐々木かをり氏)
今回は、ユニカルインターナショナル、イー・ウーマンで代表を務める佐々木かをり氏へのインタビュー内容をもとに、ダイバーシティ経営についての基本的な理解から具体的な施策までを取りまとめました。今後のダイバーシティ経営の一助になれば幸いです。
- 株式会社イー・ウーマンの詳細は、こちら。
- ダイバーシティインデックスの詳細は、こちら。
- 社外取締役のご紹介に関するお問合せは、こちら。
以上(2022年2月)
(執筆 辻 佳子)
pj80147
画像:Lucky Business-shutterstock