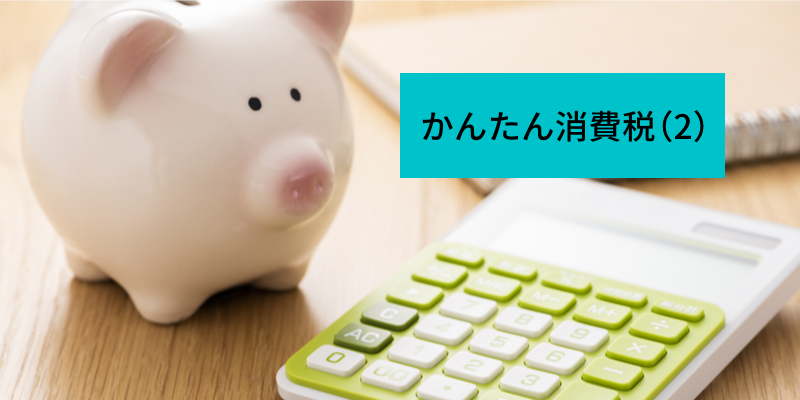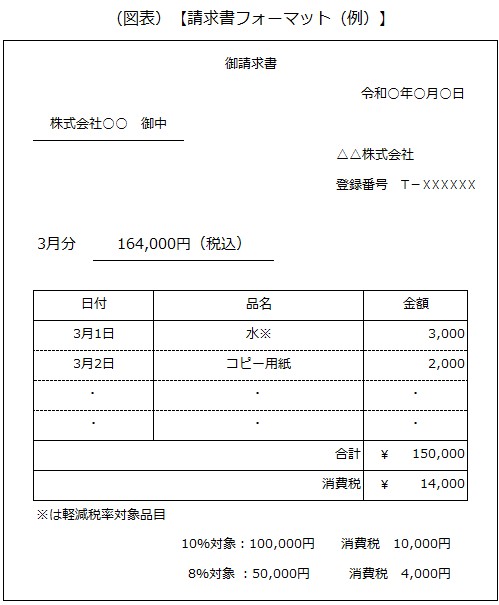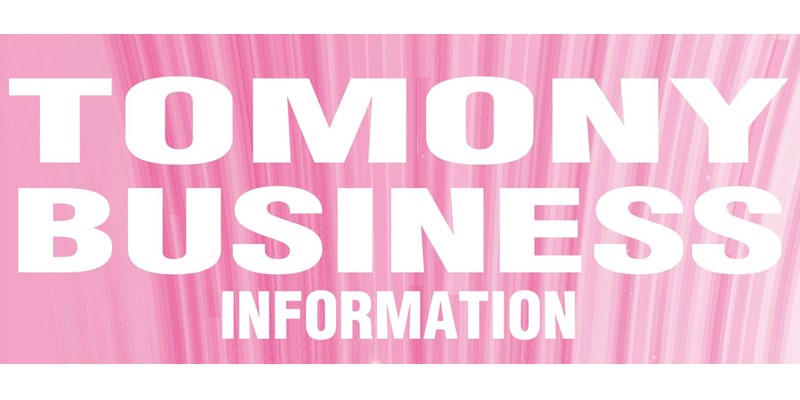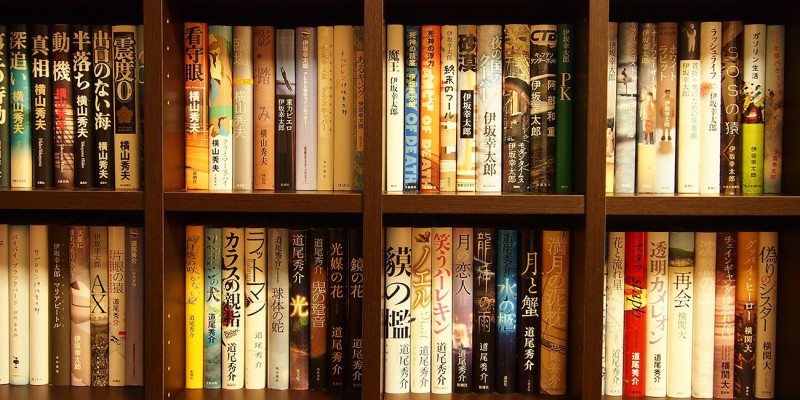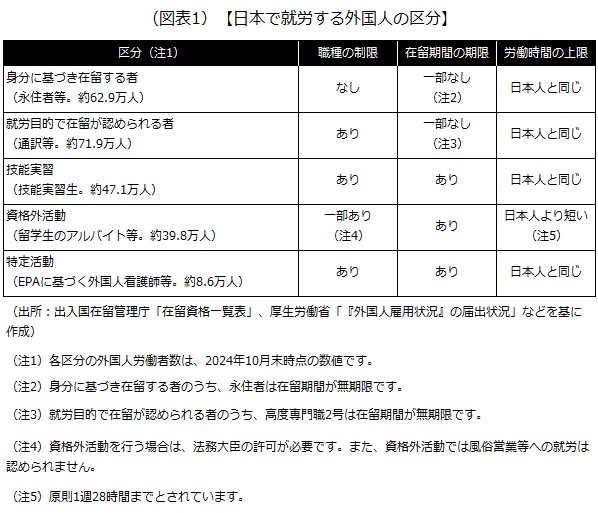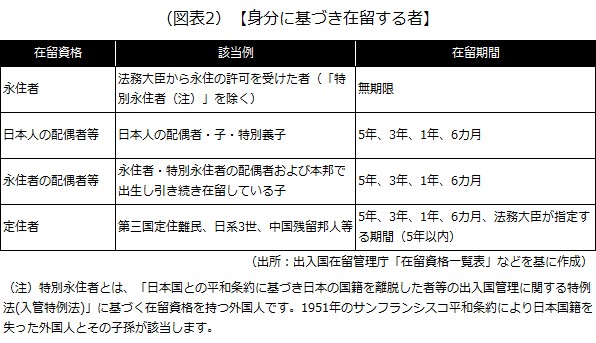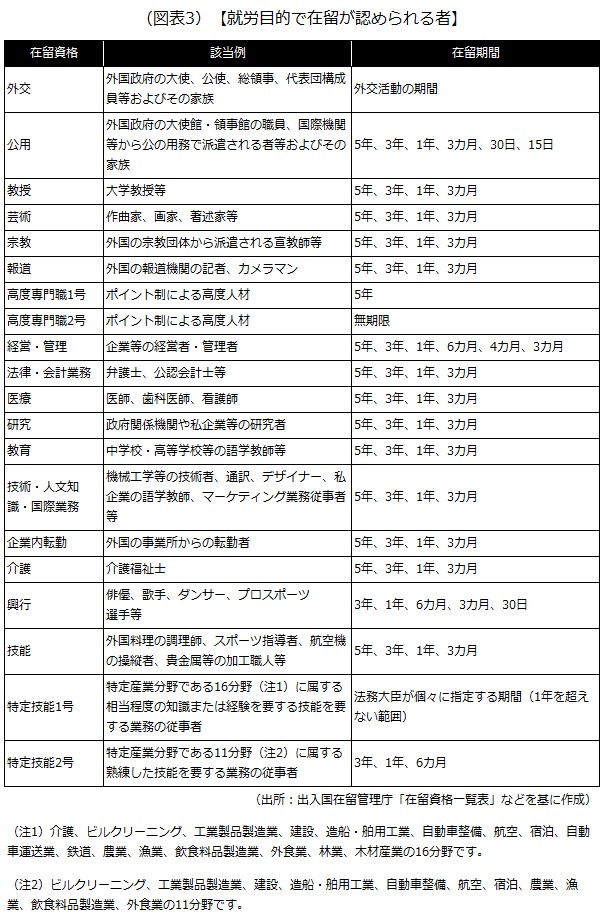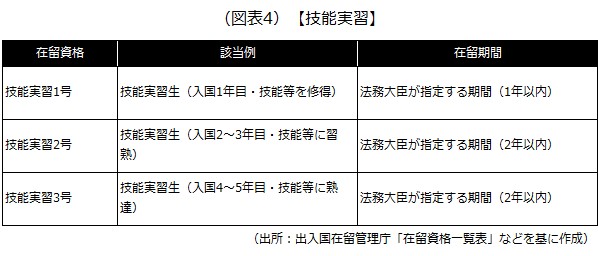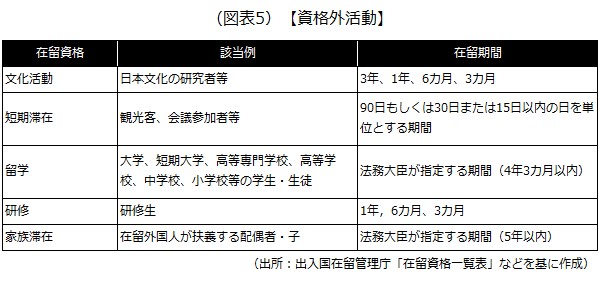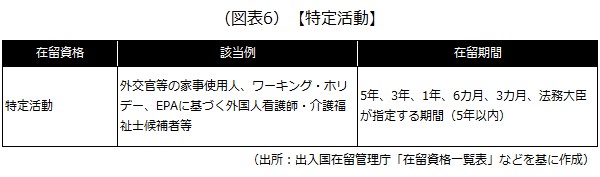1 その配慮は違法かもしれない
「女性の活躍推進」が叫ばれて久しいですが、多くの経営者がその重要性を認識し、様々な取り組みを進めていることでしょう。しかし、良かれと思って行った配慮が、実は法律に抵触し、女性のキャリアアップを阻む「落とし穴」になっているケースが少なくありません。例えば、
- 「女性は家庭との両立が大変だろう」と責任の重い業務から外す
- 「育児中の女性に転勤は酷だ」と本人の意向を確認せずに配置を決める
といった具合です。こうした一見「配慮」に見える行為が、実は差別(男女雇用機会均等法違反)と見なされるリスクをはらんでいるのです。
今回は、経営者が知らず知らずのうちに陥りがちな法的な落とし穴と、真に女性が活躍できる職場環境を構築するためのポイントを解説します。
2 男女雇用機会均等法違反のリスクと「無意識の偏見」
男女雇用機会均等法は、労働者が性別によって差別されることなく、その能力を十分に発揮できる職場環境の整備を目的としています。具体的には、募集・採用、配置、雇用形態の変更、昇進、降格、教育訓練、退職・解雇など、雇用管理のあらゆる段階で性別を理由とする差別を禁止しています。
これに違反する企業の措置は無効とされたり、不法行為として損害賠償請求の対象となったりする可能性があります。さらに、厚生労働大臣からの報告要求に虚偽の報告をすれば過料が科されます。また、厚生労働大臣からの助言・指導・勧告に従わない場合、厚生労働省ウェブサイトで企業名が公表されることもあり、そうなれば企業の社会的信用は大きく損なわれます。
問題なのは、
多くの差別が「意図せず」に行われている点です。その背景には、「無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)」
があります。例えば、
- 管理職は男性の仕事
- 女性には補助的業務が向いている
といった固定的な性別役割分担意識がそうで、こうした意識が評価や登用の機会に影響を与えているのです。実際に、コース別人事制度を導入した企業で、
総合職が全員男性、一般職が全員女性という運用実態から、女性に対する差別的な取り扱いが問題視され、裁判で違法と判断されたケース
もあります。
また、あるIT企業が開発したAI採用システムが、過去の応募者データ(ほとんどが男性)を学習した結果、女性を差別する判定を下すようになった事例があり、データに基づいた客観的な判断でさえも、元となる環境に偏りがあれば差別を生み出してしまう危険があります。
3 ハラスメント防止と「女性が辞めない職場づくり」
ハラスメントは、個人の尊厳を傷つけるだけでなく、被害者の休職や退職、職場全体の意欲や生産性の低下を招き、最終的には企業の貴重な人材の喪失と社会的信用の失墜につながる、極めて重大な経営リスクです。特に、セクシュアルハラスメントや、妊娠・出産・育児休業などを理由とするハラスメント(マタニティハラスメント等)は、女性が安心して働き続ける上で深刻な障壁となります。
セクハラ、パワハラといったハラスメントについて、法(男女雇用機会均等法、労働施策総合推進法)および厚生労働省の指針は、事業主に対し、職場におけるハラスメントを防止するため、以下の雇用管理上の措置を講じなければならないとしています。中小企業の経営者であっても、以下の対応が必要となります。
1)方針の明確化と周知・啓発
トップが「ハラスメントは断じて許さない」という明確なメッセージを発信し、社内報やポスター、研修などを通じて全社員に徹底します。経営者が直接語りかけることが、中小企業では特に高い効果を持ちます。
2)相談窓口の設置
社員が安心して相談できる窓口を設置し、その存在を周知します。プライバシー保護への配慮も必要です。
3)厳正な対処・再発防止
職場におけるハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応など、ハラスメントの相談があったときは、速やかに事実確認をし、被害者への配慮、行為者への処分等の措置を行い、改めて職場全体に対して再発防止のための措置を行います。
4)不利益な取扱いの禁止
相談者・行為者のプライバシーを保護するための必要な措置や相談したこと等を理由とする解雇その他不利益な取扱いをされない旨を就業規則等で定めます。
4 まとめ―「知らなかった」では済まされない時代に―
女性活躍を阻む差別やハラスメントは、「知らなかった」「そんなつもりはなかった」という言い訳が通用しない、重大なコンプライアンス違反です。ひとたび問題が顕在化すれば、損害賠償や行政処分といった直接的なコストだけでなく、企業の評判やブランドイメージの低下という、事業の存続を揺るがしかねない間接的な損害をもたらします。
重要なのは、制度を「作る」だけでなく、「機能させる」ことです。就業規則に立派な規定を盛り込んでも、社員が読んでいなければ意味がありません。相談窓口を設置しても、形骸化していては誰も利用しません。経営者は、制度が適切に運用されているか、現場の実態を定期的に確認する必要があります。例えば、管理職へのヒアリングを通じて実態を把握したり、ハラスメント研修を定期的に実施したりすることが有効です。また、単に「支援する」という掛け声だけでなく、育児中の社員がいる部署の人員を補充するなど、具体的な業務改善策を伴わせることが、制度を実質的なものにします。
経営トップ自らが強い意志を持って差別やハラスメントの根絶を訴え続け、制度の構築とその実効性ある運用の両輪を回していくこと。それこそが、多様な人材が定着し、企業の持続的な成長を支える「本当に強い職場」をつくるための鍵となるのです。
以上(2025年11月作成)
(執筆 法律事務所UNSEEN 弁護士 大門あゆみ)
pj60373
画像:法律事務所UNSEEN 弁護士 大門あゆみ