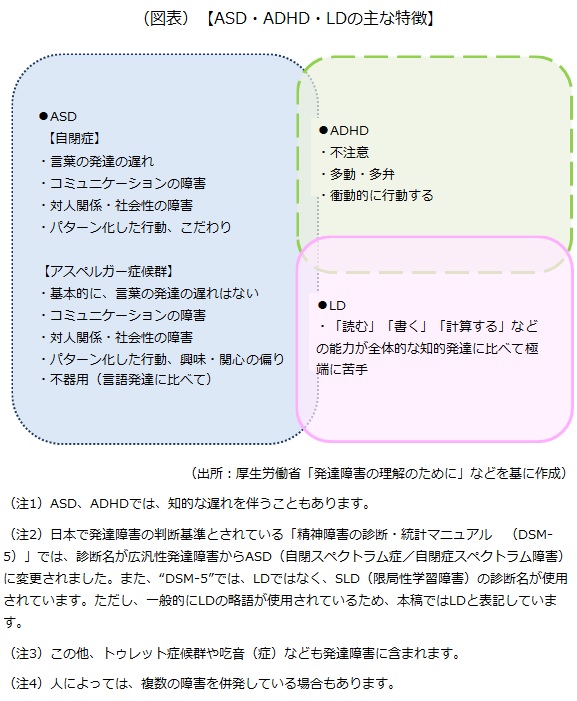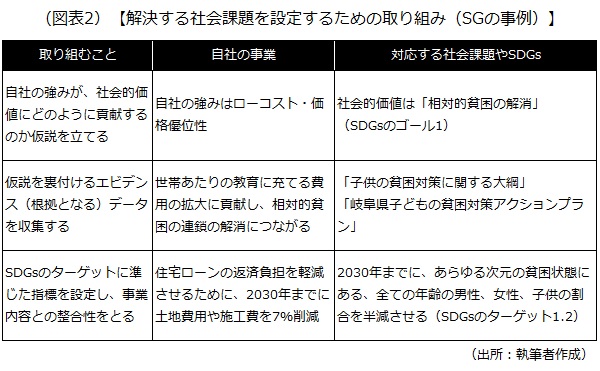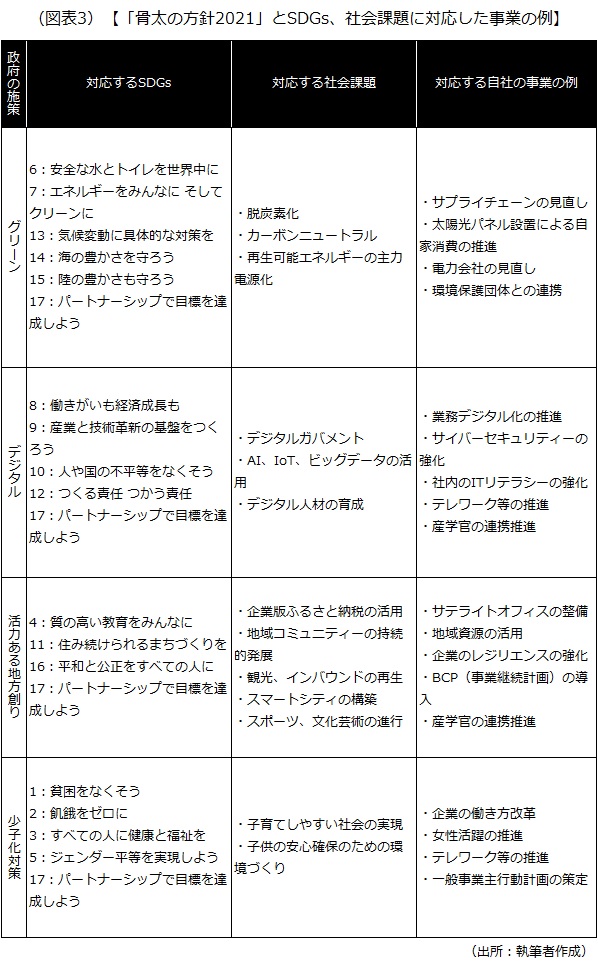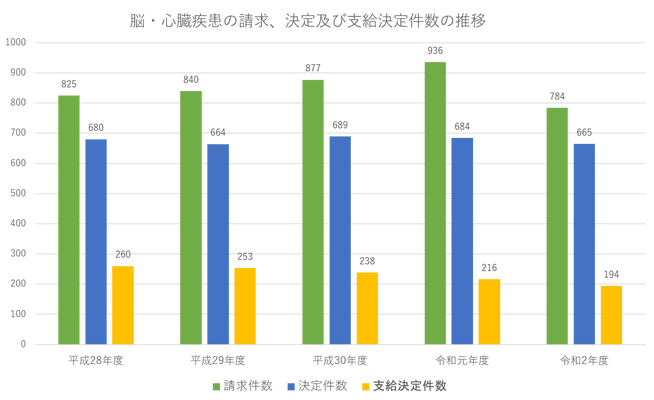書いてあること
- 主な読者:入社3〜5年目でさらに成長したい中堅社員
- 課題:率先して行動したいのだが、知らず知らずのうちに変革をストッパーになってしまう
- 解決策:まずは自身の言動が、変革を妨げる要因になっていないか見直してみる
1 場を白けさせる発言
中堅社員のAさんは、全社をあげて業務効率を進める「業務改善委員会」のメンバーとして、会議に出席しています。この委員会は社長の肝煎りで、各部門の実務を担うエース級の人材が集まり、「会社を良くするために何をすべきか」という観点から議論をしています。
今日のテーマは、古くて新しいテーマである「5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)」です。現在、会社はリモートワークの影響などもあり5Sが徹底されておらず、多くの問題が起こっています。例えば、決算時に実地棚卸しをしたら、管理がずさんで所定の場所とは違うところから商品が出てきました。他にも、営業部では本来金庫にしまうべき顧客情報が記載された書類がデスクに放置され、行方が分からなくなってしまう事態が起きました。具体的な問題にはならず「ヒヤリ・ハット」で済んだものの、紛失していてもおかしくない状況です。
そこで、委員会では5S活動を徹底させようと、早期に取り組むべき重点項目の洗い出しと、大まかなスケジュールなどについて活発な議論をしていました。そんな中、中堅社員のAさんが、ふと
リモートワークによる混乱は分かりますが、そもそも5Sの徹底はそれとは関係なく、当然のことですよね。重点項目の洗い出しよりも、全ての部門で「5S」を徹底させるべきじゃないですかね
と発言しました。その発言で、それまで活発に議論されていた場が、一気に“白けた”空気に変わってしまいました……。
2 変革の先頭に立とう
業務の仕組みや組織の文化を変えるといった組織変革は、全ての会社にとって大切なテーマです。このとき、中堅社員は変革を先導して、成功に導いていかなければならない立場です。
にもかかわらず、次に紹介するような言動で、変革の足を引っ張ってしまう人もいます。
1)「べき論」で語る人
代表的な例が、Aさんのように実現性の低い理想論を持ち出して、「こう変えていくべきだ」と語る「べき論者」です。
べき論者となる理由は、その課題について具体的に掘り下げて考えていないためです。だからこそ、実情にそぐわない理想論しか語ることができません。しかし、本人はその事実に気が付いていません。実のある議論を壊しているのにもかかわらず、本人は「5S推進についてしっかり考え、意見している」と思い込んでいます。
だからこそ、その課題について具体的に掘り下げて考えている人にとっては、べき論者の意見は場違いでしかなく、周囲は“白けた”空気になってしまうのです。
理想を模索することは大切です。しかし、変革を先導していく立場にある中堅社員は、「夢見る現実者」でなければなりません。べき論者にならないようにするためには、その課題を現実的な話として、しっかりと考えることです。
Aさんであれば、「自分が先頭に立って5Sを浸透させるために、何をどのように進めていくか」ということを現実的にイメージすることです。手順・スケジュール・必要となる予算や人員など、5W2Hで考えてみるのです。そうすれば、自分の意見が妥当なものか、それとも単なる理想論なのかは判断できるはずです。
2)「検討します」という人
「検討します」という人も、変革を妨げることがあります。新しいことに取り組む際は、さまざまな不安があります。そのため、例えば、上司から「このように変えることはできないか」と変革に関する相談を受けても、すぐには判断できないことがあります。
そのとき、つい口にしてしまうのが、「検討します」という言葉です。
しかし、単に「検討します」というだけでは、結論が出ずに終わることがほとんどです。他意はなくても、日々の仕事に忙殺される中で検討は後回しになり、うやむやになってしまいがちです。
変革が成功するか否かは、事前に判断できるものではありません。であれば「検討します」と立ち止まるのではなく、早急に行動に移す方法を考えるようにしましょう。とにかくやってみて、もし、問題があれば改善していくというスタンスで進めるのです。
なお、本当に時間をかけて検討したい事項があるのであれば、課題と期限を明確にしなければなりません。
3)失敗の原因を他のせいにする人
「5S活動の推進」のような社員の行動を変えなければ実現できない変革は、組織に定着させるのには時間がかかります。
そのため、「取り組んではみたものの、組織に定着しない」「定着したと思ったものの、時間がたつと、元に戻ってしまった」という失敗はよくあります。このようなとき、「皆、忙しくて十分な時間がなかった」「皆が言うことを聞いてくれなかった」と、失敗の原因を他のせいにする人がいます。
もちろん、こうした点も失敗した原因の1つであることは間違いないでしょう。しかし、見落としがちなのが、中堅社員などの変革を先導する人自身の「諦め」です。
重要なことであれば、忙しくても時間を確保して続けなければいけませんし、取り組みに消極的な人がいれば、繰り返し指導しなければいけません。また、問題があれば、それを解消しながら進めることが求められます。これらを実現するために何より大切なことは、中堅社員自身が改革を率先垂範していくことです。中堅社員が根負けしてしまっては、変革は成功しません。
3 変えるためには、変わること
変革というと、「会社の仕組みや社員の行動を変えなければならない」と、自分以外に視点が向きがちです。しかし、変革は一人一人の行動から始まります。まずは自身の言動が、変革を妨げる要因になっていないか見直すことから始めましょう。
以上(2021年8月)
op20301
画像:JackF-Adobe Stock