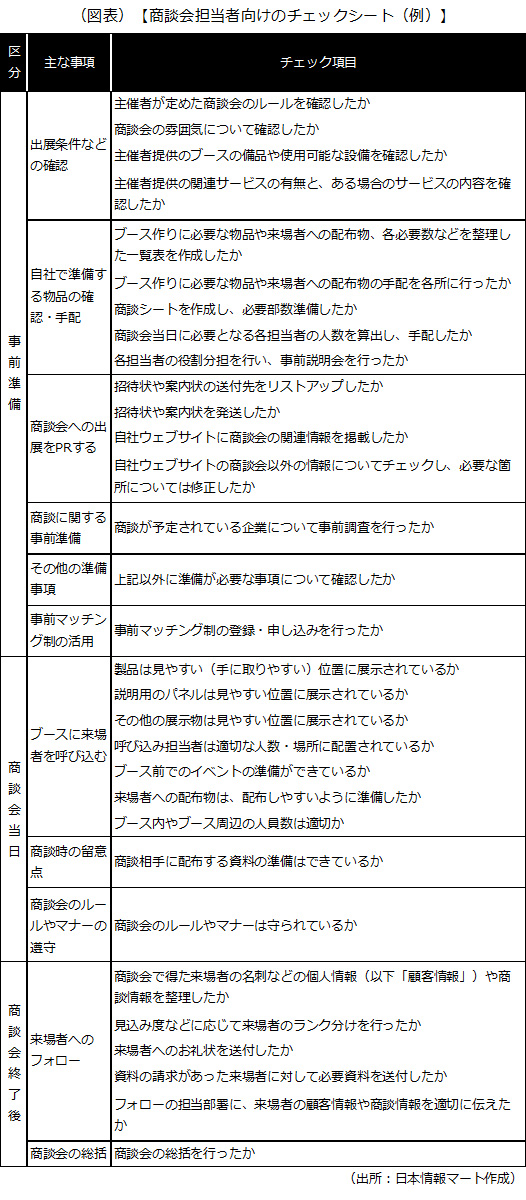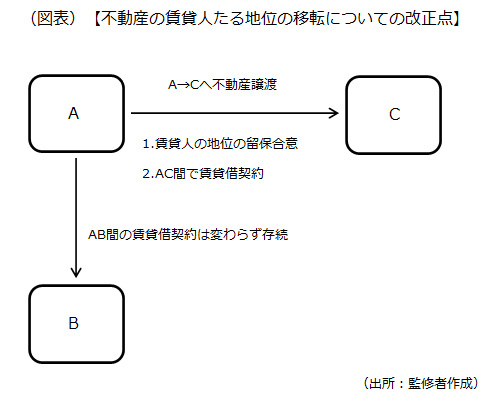書いてあること
- 主な読者:2020年4月に改正された民法のポイントを知りたい経営者
- 課題:改正の断片的な情報しか把握していないので、全体像が知りたい
- 解決策:金銭消費貸借契約のポイントを紹介(シリーズの他のコンテンツもあります)
1 諾成的消費貸借契約の新設
お金を貸し付ける契約は、民法上、消費貸借契約に該当します。これは、借りたものと同じものを、同じ数量を返却することを約束して、物や金銭を借りる契約のことです。
旧民法では、消費貸借契約は、要物契約であるとされていました(旧民法第587条)。当事者の意思表示の合致に加えて、一方の当事者からの目的物の引き渡しその他の給付があって初めて成立する契約ということです。そのため、「お金を貸します」「お金を返します」という約束だけではなく、実際にお金の引き渡しがあって初めて契約が成立します。また、お金の引き渡しがされる以前に、貸主が「やっぱり貸せません」などと断った場合、契約が成立していないことから、借主はお金を貸してもらうよう請求することもできませんでした。
ところが、実務上は、判例(最高裁昭和48年3月16日)で無名契約としての諾成的消費貸借契約が認められていました。これは、「お金を貸します」という約束の時点で契約の効力が生じることで、住宅ローンや金融機関から融資を受けることを前提とする大型の開発プロジェクトのように、諾成的消費貸借契約に対するニーズがあります。そのため、改正民法ではこれまでの判例・実務上認められていた諾成的消費貸借契約を新設し、明文化しました。
ただし、当事者の「合意のみ」によって契約上の義務が生まれると、安易に金銭を借りる約束や貸す約束をしてしまった者に酷な結果が生じかねません。そこで、改正民法では、書面または電磁的記録による諾成的消費貸借の規定が設けられました(改正民法第587条の2)。
以降では、金銭消費貸借契約を締結する際の契約書の記載例や注意点を紹介します。
2 契約書の記載例
改正民法を踏まえた契約書を作成する場合、次のような記載例が考えられるでしょう。
【金銭消費貸借契約書】
貸主(以下「甲」という。)と、借主(以下「乙」という。)は、乙が、○年○月○日に支払期限が到来する仕入れ代金の返済に充てることを目的として、以下の通り、金銭消費貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(諾成的金銭消費貸借契約)
甲は、乙に対し、金○○○○万円を貸し渡し、乙はこれを借り受けることを合意する。
第2条(金銭の授受)
甲は、乙に対し、前条の金員を、○年○月○日限り、乙の指定する口座に振り込む方法により貸し渡す。振込手数料は甲の負担とする。
第3条(返済期限・方法)
第4条(利息)
第5条(期限の利益の喪失・解除)
略
第6条(遅延損害金・損害賠償)
1)乙は、甲に対し、第3条に基づく返済を遅延した場合、遅延した日の翌日から支払い済みまで、残元金に対する年○パーセントの割合による遅延損害金を支払う。
2)甲が、本契約に基づき金銭を貸し渡す義務を怠った場合、甲は、これにより乙が被った損害を賠償する。
第7条(乙による解約)
乙は、甲から第2条記載の金員を受領する前に限り、本契約を一方的に解除することができる。ただし、甲がこれにより損害を被った場合には、当該損害について賠償する義務を負う。
第8条(一括返済)
乙は、期限の利益を放棄して、甲に対し何らの損害賠償をする義務を負うことなくいつでも一括にて返済することができる。ただし、乙は甲に対し、これにより甲が被った損害を賠償する。ただし、甲がこれにより損害を被った場合には、当該損害について賠償する義務を負う。
第9条(協議条項)
第10条(裁判管轄)
略
1)タイトル・頭書
表題(タイトル)は、通常通り、金銭消費貸借契約書でよいでしょう。
また、頭書部分については、金銭消費貸借の目的を書くとよいでしょう。改正民法では、利息付消費貸借契約においては、売買の規定が包括準用されます(改正民法第559条)。そのため、契約不適合責任が問題となります。詳細は本シリーズの第5回「債務の履行」にて解説しているため割愛しますが、旧民法の瑕疵(かし)担保責任が、改正民法では契約不適合責任となり、義務の履行が契約に適合しない場合には追完請求、契約解除、損害賠償請求などができます。
この契約不適合責任においては、合意の内容や契約書の記載だけでなく、契約をした目的や、締結に至る経緯など一切の事情が考慮されるといわれています。そこで、この点を踏まえて、契約をした動機・目的・契約締結に至る経緯を明確にすることが重要になります。
2)第1条~第2条
第1条~第2条は、改正民法では書面合意による消費貸借契約が認められたため、それを表した条項例です。
3)第3条~第5条
第3条~第5条については、現行の金銭消費貸借契約書と内容が変わらないため、記載を省略しています。
ただし、第5条の解除について若干補足します。改正民法第587条の2第3項において、書面でする消費貸借においては、借主が金銭などを受け取る前に、貸主または借主が破産手続き開始の決定を受けたときは、その効力が失われると定められました。
これは、当事者の一方が破産した場合に、貸し付けを履行させることは不合理であるためです。契約書の解除事由として当事者の一方が破産したということが記載されていない場合であっても、貸主または借主が破産手続き開始の決定を受けたときは、合意の効力が失われることに留意が必要です。
4)第6条
第6条について、諾成的消費貸借では、貸主の債務不履行に対する借主からの損害賠償が考えられます。まず、諾成的消費貸借契約においては、貸主が借主に対して貸し付けを行う義務が生じます。そして、貸主がこれを怠ることによって借主に損害が生じた場合には、貸主にはそれによる損害を賠償する義務が生じます。
ただし、何をもって損害とするか、損害をいくらと評価するかは、個々の事案における解釈・認定に委ねられ、紛争となる恐れがあります。そこで、賠償の内容を具体的に記載することも考えられます。
例えば、第6条において、次のような記載例も考えられます。
甲が本契約に違反した場合、乙は、甲に対し、損害賠償を請求することができる。この場合の損害賠償の額は、金○円とする。
甲が本契約に違反した場合、乙は、甲に対し、損害賠償を請求することができる。この場合の損害賠償の額は、乙が他で同額の資金を調達するために要した費用の額(本契約より不利な条件で借り受けたことによる経済的損失も損害と見なす)とする。
なお、これは借主側の視点になりますが、上記の記載例のように、事前に賠償額を予定する内容は、注意が必要です。賠償額が過大な場合には改正民法第90条や不当条項規制の問題から、無効となる可能性があります。
5)第7条
第7条については、改正民法第587条の2第2項の前段の内容を明記したものです。同項では、借主が目的物を受け取るまでは契約の解除ができることを定めています。これは、金銭などの引き渡し前に資金需要がなくなった借主を契約の拘束力から解放させるべきとの考えからです。
一方、改正民法第587条の2第2項の後段では、上記の場合であっても、貸主が損害を受けたときは借主に対して損害賠償請求権を有することを定めています。
もし損害賠償の話となった場合には、損害の内容や評価額で紛争になる可能性があるため、例えば、「ただし、その場合、乙は、甲に対し、違約金として金○円を支払う」のように、違約金額を定めておくことも一つの方法でしょう。
ただし、違約金額が過大である場合には改正民法第90条や不当条項規制の問題として無効となる可能性もあります。また、事業者が消費者に貸し付ける場合には、消費者契約法第9条により、一般的な損害額を超える部分については効力が否定される可能性がありますので、留意が必要です。
6)第8条
第8条について、改正民法第591条第2項、第3項では、消費貸借契約において、返還時期を定めた場合でも、借主は期限の利益を放棄して返還できること、および、借主が期限前返済をしたことで貸主に損害が生じた場合、貸主が借主に対して損害賠償請求権を有することが定められました。
旧民法においても、内容としては同様の理解がされていたものであり、契約実務上も一括返済の条項が置かれることが多いため、実務上の扱いに大きな影響を与えるものではありません。
なお、損害の内容および損害額については争いになる可能性があるため、例えば、次のような記載例とすることが考えられるでしょう。
(一括返済による賠償責任は無いとする場合)
第8条(一括返済)
乙は、期限の利益を放棄して、甲に対し何らの損害賠償をする義務を負うことなくいつでも一括にて返済することができる。この場合、乙は甲に対し、何ら損害を賠償する責めを負わない。
(一括返済による賠償責任を、甲が得られるはずだった利息を踏まえ算出する場合)
第8条(一括返済)
乙は、期限の利益を放棄して、甲に対し何らの損害賠償をする義務を負うことなくいつでも一括にて返済することができる。この場合、乙は甲に対し、当初の弁済期までの利息に相当する金員から中間利息を控除した金額を損害として賠償しなければならない。
以上(2020年11月)
(監修 リアークト法律事務所 弁護士 松下翔)
pj60202
画像:photo-ac