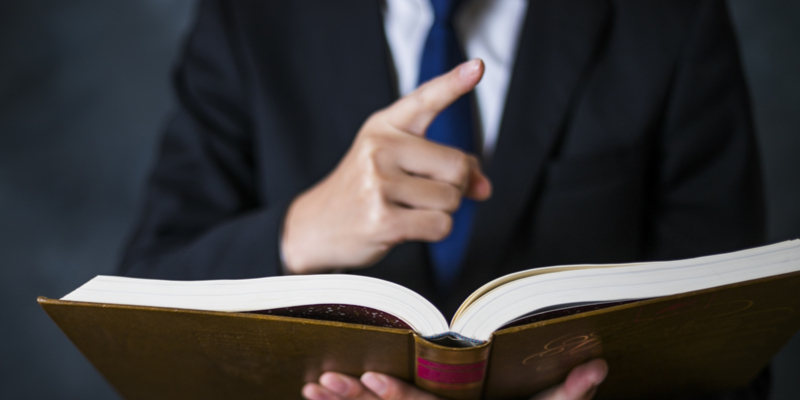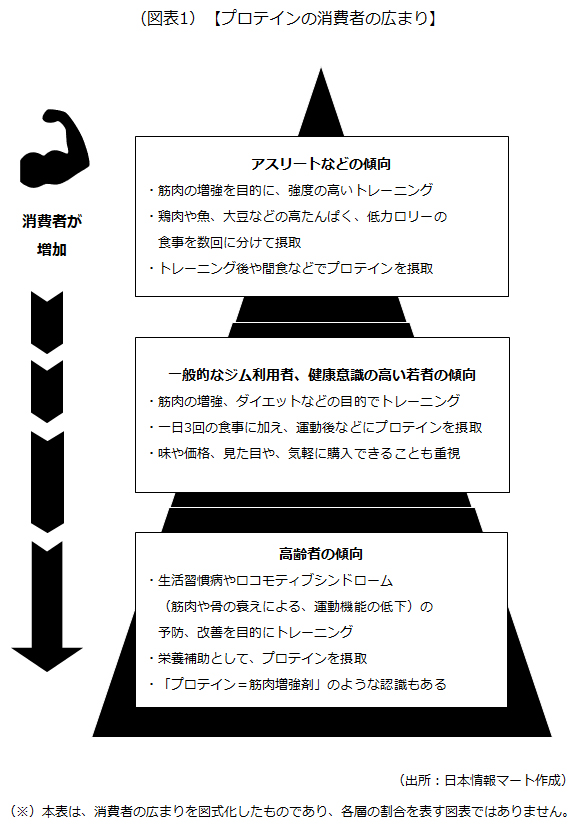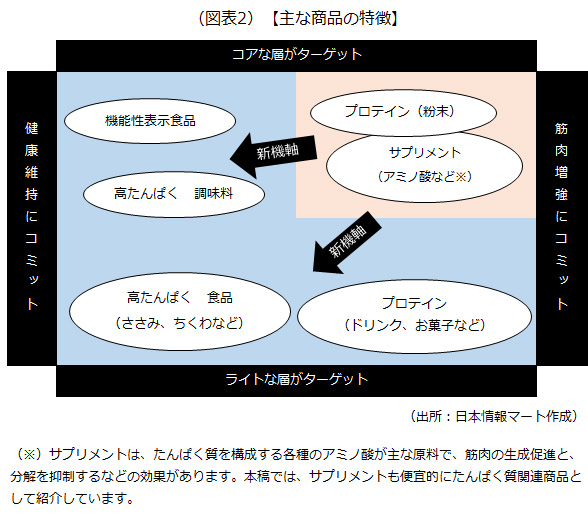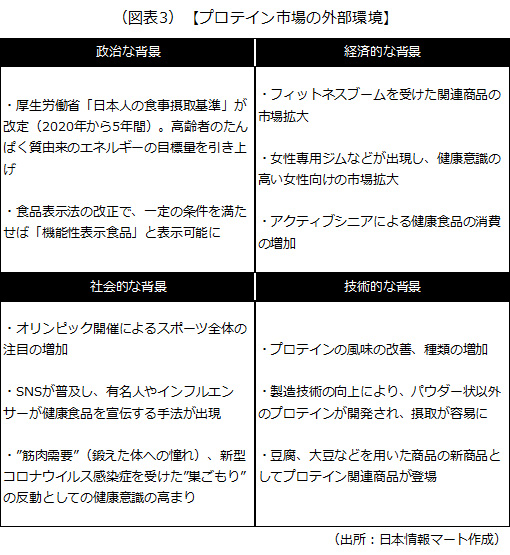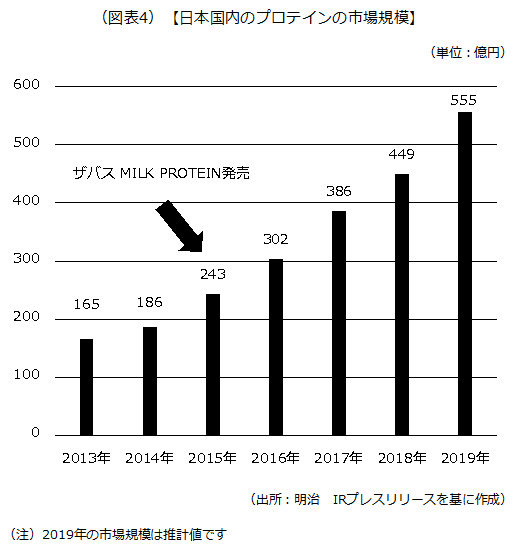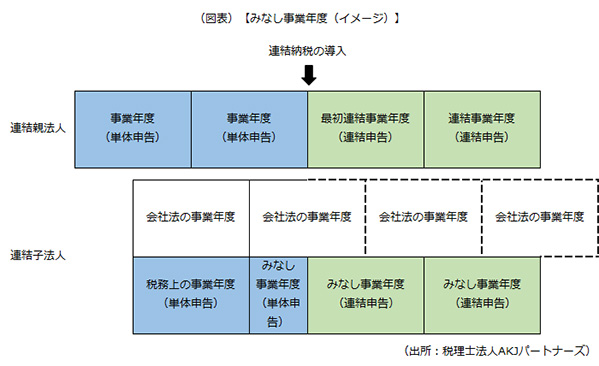書いてあること
- 主な読者:2020年4月に改正された民法のポイントを知りたい経営者
- 課題:改正の断片的な情報しか把握していないので、全体像を知りたい
- 解決策:保証、定型約款、錯誤のポイントを紹介(シリーズの他コンテンツもあります)
1 保証の改正
1)個人根保証契約とは
保証契約とは、主債務者がその債務の支払をしない場合に,主債務者に代わって支払をする義務を負うことを約束する契約です。保証契約にはいくつか種類があり、その中でも根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の債務について保証する契約をいいます。個人根保証契約とは、個人(保証人が法人ではないもの)の根保証契約のことです。根保証とは、継続的な取引から生じる不特定の債務(保証の対象となる債務、主債務のこと)を保証するものです。
旧民法第465条の2では、根保証契約のうち、個人貸金等根保証契約についてのみ、極度額を付す必要がありました。個人貸金等根保証契約とは、貸金等債務(金銭の貸し渡しまたは手形割引を受けることによって負担する債務)について個人が根保証するものです。改正民法では、これに限らず、全ての個人根保証契約で極度額を定めなければならず、これがなければ、保証の効力は生じません(改正民法第465条の2第2項)。
例えば、不動産賃貸借契約、継続的取引契約における代金支払債務などでは、個人が根保証しているケースが多いので、極度額の設定が必要になります。ただし、極度額があまりに高額だと公序良俗違反(改正民法第90条)として無効になる恐れがあるので、弁護士などの専門家のアドバイスを受けるとよいでしょう。
なお、2020年3月以前に締結された契約は旧民法が適用されますが、更新または再契約の場合は留意が必要です。このタイミングで新たな根保証契約が締結されたものと評価されるのであれば、保証の効果が失われないように極度額を定める必要があるからです。
2)事業資金の個人保証における公正証書の作成
事業のために負担した貸金等債務を個人保証する場合や、主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる個人根保証をする場合、原則として、契約締結日前1カ月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ、保証契約の効力は生じません。
この改正は、保証人の保護のために行われました。事業資金の貸付金の保証や、事業のための債務の根保証は金額が大きくなりがちですが、それを十分に認識しないまま保証を行った結果、生活の破綻を余儀なくされるケースがあります。そこで、保証債務履行の意思を厳格な手続きで確認することになったのです。
ただし、例外があります。いわゆる「経営者およびこれに準ずるもの(主債務者が法人の場合における理事や取締役等、主債務者が個人の場合における共同事業者等)」が保証人となる場合は、公正証書を作成しなくても保証契約を締結できます(経営者保証等の例外・改正民法第465条の9の各号)。
3)主債務者の情報提供
改正民法では、主債務者は、事業のために負担する債務について保証人になることを委託する場合は、相手(個人のみ)に、財産・収支・負債の状況などの事項に関する情報を提供する義務が定められました(改正民法第465条の10第1項)。提供すべき情報は次の通りです。
- 財産および収支の状況
- 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額および履行状況
- 主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときはその旨およびその内容
主債務者が情報提供をしなかったり、事実と異なる情報を提供したりしたために、委託を受けた保証人がその事項について誤認をし、それによって保証契約を締結したとします。この場合、債権者が、主債務者の情報不提供や不実情報提供の事実を知りまたは知ることができたときは、保証人による保証契約を取り消すことができます(改正民法第465条の10第2項)。
このような理由による取消しの主張を防ぐため、保証契約締結の際の手続きに注意しましょう。同時に、保証契約書の中で係る義務が履行されたことを確認する文言を入れ、手続きが正しく履行された旨を書面に残すといった対応を検討するべきでしょう。
2 定型約款の新設
1)定型約款とは
大量の定型的な取引を迅速かつ効率的に行うため、一方の契約当事者があらかじめ一定の契約条項を定めた約款を用いる取引が広く行われています。しかし、旧民法には、約款に関する規定がなく、法的拘束力を認める根拠が明らかではありませんでした。
そこで、改正民法では、一定の要件を満たす約款を「定型約款」とし、法的拘束力を認めることとしました(改正民法第548条の2ないし第548条の4)。定型約款とは、次の要件に該当するものをいいます(改正民法第548条の2第1項柱書)。
- ある特定の者が、不特定多数を相手方とし、
- 取引内容の全部または一部が画一的であることが双方にとって合理的な取引において
- 取引契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体
具体的な取引類型としては、鉄道・バス・航空機などの旅客運送、電気・ガス・水道の供給取引、保険取引、預金取引が挙げられる他、旅行、宿泊、ソフトウエア購入ライセンス、上記1、2を満たすインターネット経由の取引なども考えられます。
2)みなし合意の要件と不当条項
上記1)の1、2を満たす「定型取引」を交わすことに合意した者は、次のいずれかの要件を満たすことで、定型約款の各条項について合意があったとみなされます。
- 定型約款を契約の内容とする旨の合意をした場合(改正民法第548条の2第1項第1号)
- 定型約款を準備した者が、あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していた場合(同項第2号)
1、2のいずれかの場合は、当事者が定型約款の個別の条項を把握していなくても、定型約款の各条項について合意したものとみなされます(「みなし合意」。改正民法第548条の2)。ただし、定型約款に不当な条項があると衡平の観点から問題が生じます。そこで、改正民法では、定型約款に不当条項が含まれている場合、その条項に対するみなし合意は成立しないこととしています。具体的には、次を満たすものが不当条項に当たります(改正民法第548条の2第2項)。
- 相手方の権利を制限し、または相手方の義務を加重する条項であって、
- その定型取引の態様およびその実情並びに取引上の社会通念に照らして、
- 民法第1条第2項に規定する基本原則(信義誠実の原則)に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるもの
なお、本条と似た規制が消費者契約法第10条にもありますが、判断基準が異なります。消費者契約法では、「民法、商法、その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合と比べて」不当性が判断されますが、定型約款については上記2の通り、「その定型取引の態様およびその実情並びに取引上の社会通念に照らして」不当性が判断されます。消費者取引に約款を用いる企業としては、消費者契約法と改正民法の両方を確認する必要があります。
3)実務上の留意点
契約書と別に約款を用いている場合、約款が定型約款の要件を満たしているかを確認しましょう。定型約款に当たる場合、みなし合意の成立要件を満たしているか確認します。例えば、定型約款を契約の内容とすることをあらかじめ示しているかなど、契約手続き・手順を見直します。
具体的には、契約書に「本契約には、契約締結時点の定型約款『○○』が適用されます」という文言があるかを確認します。また、インターネット上で契約をする場合は、合意画面までの画面遷移の中で、「本契約には、契約締結時点の定型約款『○○』が適用されます」という表示をしているか確認する必要があります。約款を表示して、同意のチェックボックスのクリックを求めるほうが確実です。
4)経過措置
定型約款については、経過措置があります。附則第33条第1項により、改正民法第548条の2から4までの規定は、2020年3月以前に締結された定型取引に係る契約についても適用するとされています。ただし、例外として、契約の一方当事者により反対の意思表示が、改正民法施行日前までに書面または電磁的記録でされた場合は、改正民法は適用されません(附則第33条第2項、第3項)。
定型約款を用いる企業は、相手方の同意なく定型約款の変更ができる(改正民法第548条の4)ため、当該変更を予期していなかった相手方を保護するための決まりです。顧客から改正民法施行日前までに約款の適用反対通知が届いた場合(メールも含む)は、当該顧客との関係では改正民法が適用されず、定型約款の効力を巡って争いが生じ得る旨を認識しておきましょう。
3 錯誤(意思表示の瑕疵)の改正
改正民法では、意思表示の規定(旧民法第93条~第98条の2、心裡留保、錯誤、詐欺、強迫、遠隔者に対する意思表示)についても改正されました。「錯誤」については、法的効果が改められており、実務上影響があるので簡単に触れます。
錯誤とは、意思表示の主体が、内心と意思表示との不一致を知らない場合や、法律行為の基礎とした事情についてその認識が真実に反する場合をいいます。商品Aを買おうと思っているのに、「Bを下さい」と言ってしまう場合や、ある目的を達成するために商品Aを購入しようとしているが、実際はAの機能を全く誤解していた場合です。
このような場合、旧民法では意思表示自体が、原則「無効」とされています(旧民法第95条)。しかし、改正民法では、錯誤による意思表示の効果が、「無効」から「取消し」となりました。「無効」は、何らの行為等がなくても当然に意思表示の効力が発生しません。「取消し」は、取消しの意思表示を行うことで初めて当該意思表示の効力を否定することができます。また、取消権は期間制限(追認することができるときから5年間。改正民法第126条前段)を受けます。
以上(2020年11月)
(監修 リアークト法律事務所 弁護士 松下翔)
pj60112
画像:pixabay