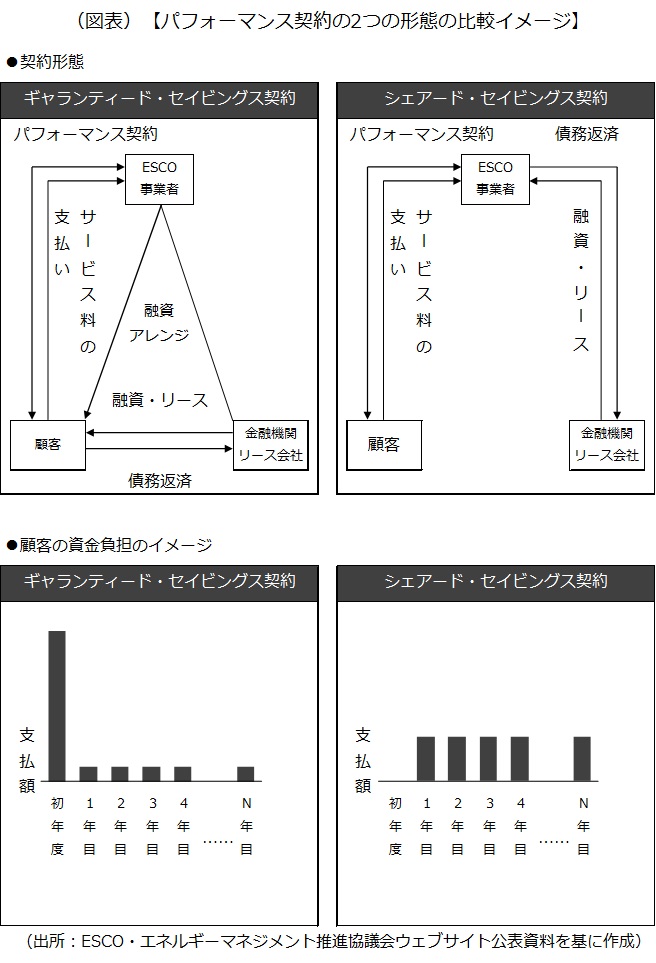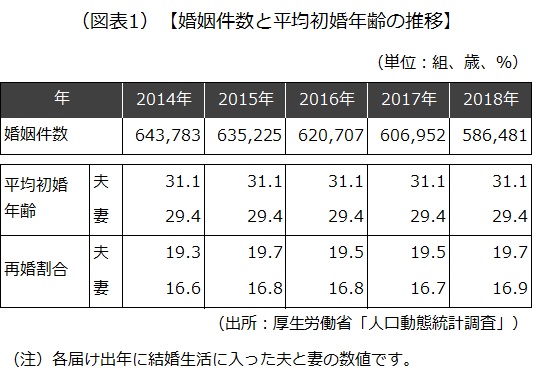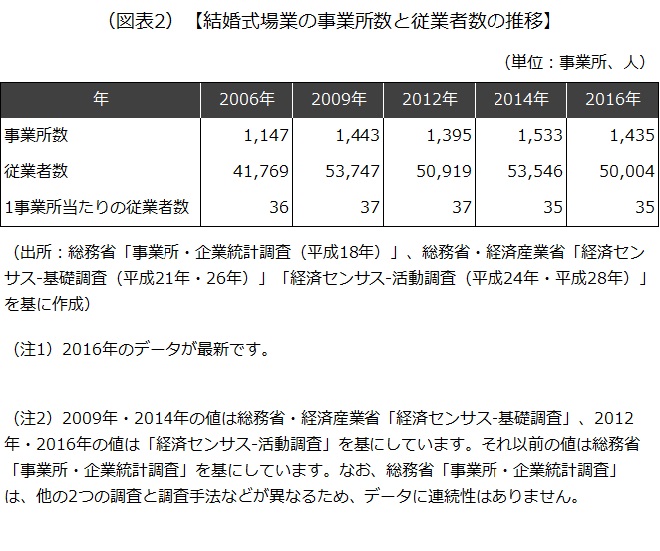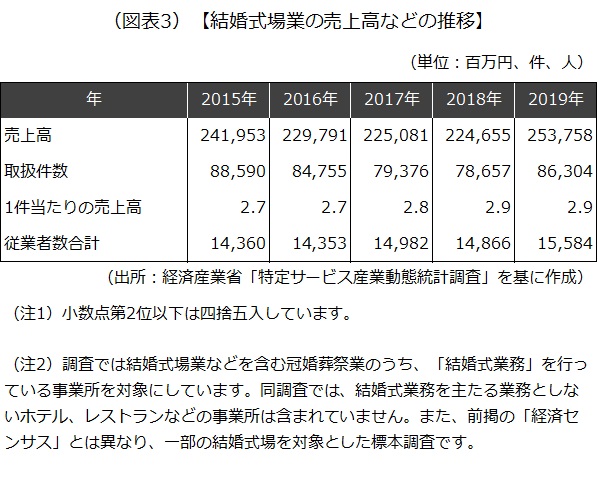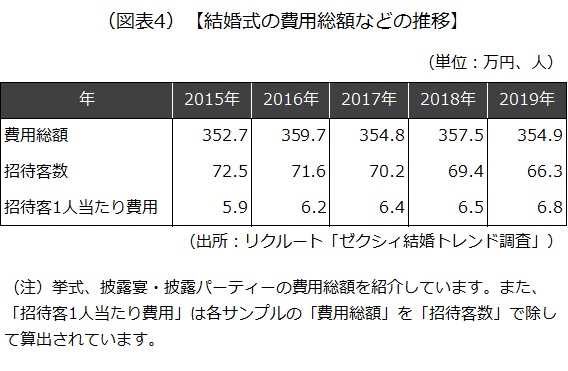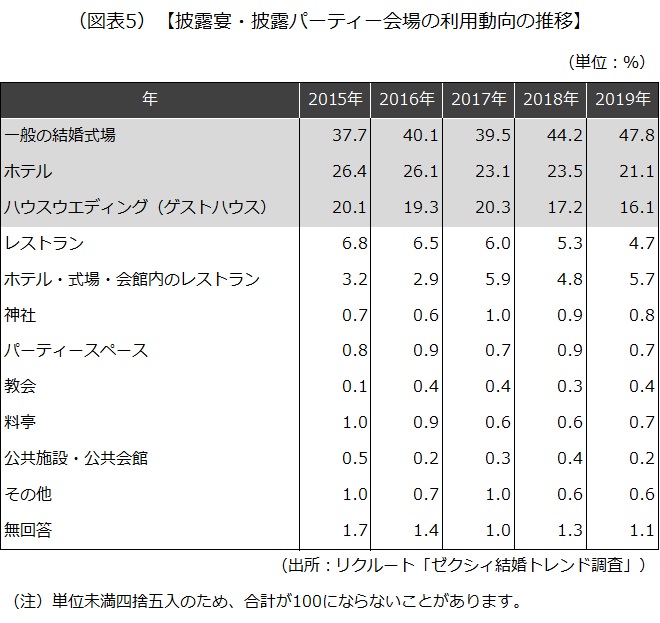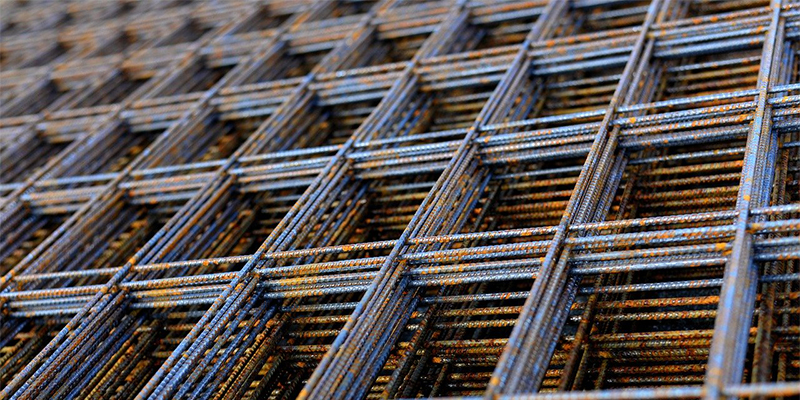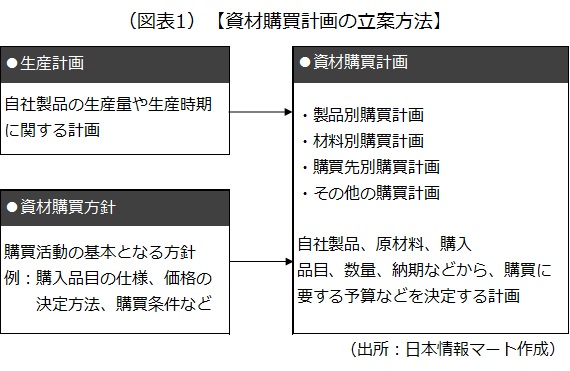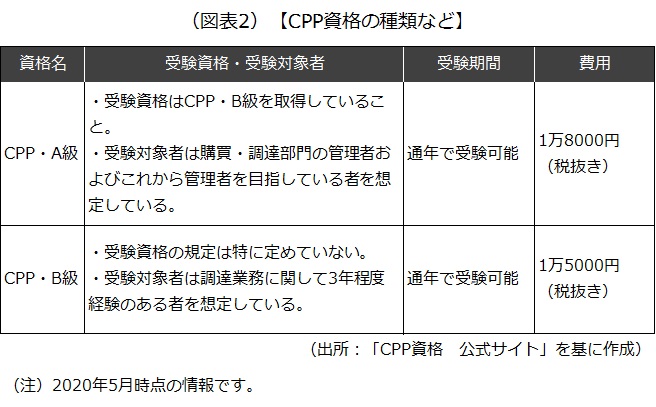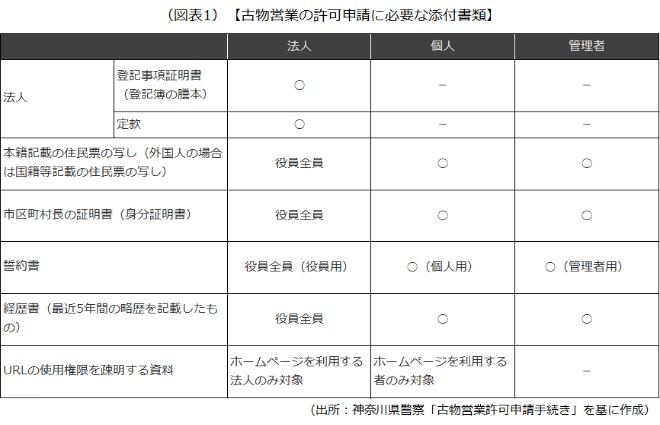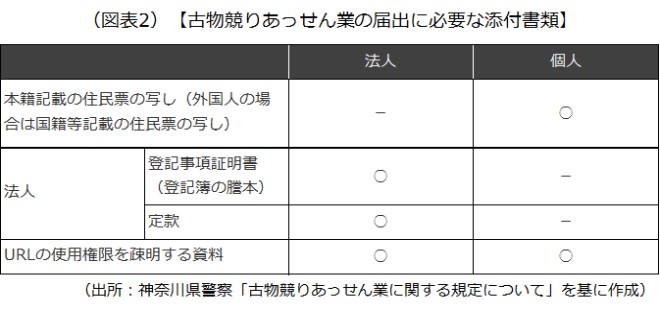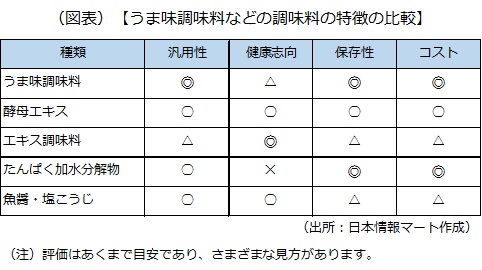書いてあること
- 主な読者:会社が岐路に立ち、大きな決断をしなければならない社長や経営幹部
- 課題:他の社長の考えを聞いてみたい
- 解決策:会社の命運を左右する重大局面で、実際に決断をした経営者の当時の心の動き、思いを参考にする。決断に一番重要なものは何か
1 事例1:「背水の陣」で製造小売りに事業転換
業績が下降していた折、追い打ちをかけるように東日本大震災が発生しました。取引先の相次ぐ廃業で売り上げの約3分の1を失う見通しにもかかわらず借り入れはできず、資金が枯渇している状態です。
約100年続くオーダースーツ製造卸会社「オーダースーツSADA」(以下「SADA」)の4代目社長である佐田展隆さんが、古巣への復帰を要請されたとき、SADAはそのような危機的状況にありました。
そこで下した「佐田さんの決断」は、従来の小売業者向けの製造卸から、製造小売り(SPA)に事業転換することでした。そのために、新たな小売店を日本最大の繁華街である東京・新宿に出店する「乾坤一擲(けんこんいってき)の戦い」に打って出ます。
1)4代目社長就任も5年で会社を去る
佐田さんが最初にSADAの社長に就任したのは、2003年12月のことでした。年商を上回る有利子負債を抱えて倒産の危機に瀕(ひん)し、当時の社長だった父の願いを聞き入れる形で、勤務先を退職して社長を引き継ぎました。佐田さんが29歳のときでした。
佐田さんは利益を重視した営業戦略を徹底し、半年で黒字転換を果たします。しかし、買掛金や給与の支払いまで先延ばししていた状況には焼け石に水でした。私的再生したSADAは2007年6月に投資ファンドに引き取られ、実家の資産も全て失いました。社長職から外され、もはや社員や工場を守ることができないと悟った佐田さんは、会社を去ることにしました。
2)震災で再び窮地に陥った中での復帰要請
東日本大震災の混乱も冷めやらぬ2011年6月、佐田さんはSADAに復帰します。投資ファンドから小売り流通大手の手に渡った後も下降線をたどり続けたSADAに、震災が追い打ちをかけました。自社工場の損壊に加え、取引先の多かった東北地方を中心とする小売り業者の相次ぐ廃業によって、売り上げの約3分の1を失う見通しに陥ったSADA。進退窮まった当時の社長が、佐田さんに復帰を要請したのです。
復帰要請とともに知らされたSADAの財政状態は、社長を離れた当時よりも悪化していました。周囲の知り合いの誰もが改善の見込みはないと口をそろえましたが、佐田さんは“火中の栗を拾う”決心をします。
復帰後の社員の反応は好意的でした。しかし、佐田さんは前回の経験も踏まえ、「社員の期待感がなくならないうちに、新たな方向に転換して成果を収める。そして、社内を『いける』という雰囲気に変えなければ、中期的には存続できない」ことを肝に銘じていました。しかも、佐田さんの復帰当初の肩書は、“社長含み”とはいえ一介の経営企画室長。部長待遇で、株式も保有しておらず、「金融機関などは『お手並み拝見』というスタンスだった」といいます。
3)製造小売りに軸足を転換
佐田さんがSADA存続の道として「これ以外にない」と示したのは、従来の製造卸から、製造小売りへの業態転換でした。
小売り事業は、前回の社長時代に、ECサイトと大都市を中心に7店舗の出店を試みていました。ただ、その目的は、小売業者に対して自社の中国工場の製品を売り込むことで、中国製品を若者に販売するパイロットケースの意味合いでしかありませんでした。
このため、佐田さんが復帰するまでの小売り事業自体は赤字が続いており、売り上げは全体の15%程度しかありませんでした。出店用の新たな借り入れが許される財務状態ではなく、既存の取引先である小売業者とは競合関係になります。
それでも佐田さんは、幹部たちを説得します。「他に策があるんですか? このまま何もせずに籠城戦をして、社員を餓死させるつもりですか? 打って出るなら今しかないじゃないですか!」
しかし、佐田さんの決断には幹部全員が猛反対。「もうオーダースーツの時代は終わったのです。持ちこたえるには節約しかない」と抵抗する幹部もいたといいます。結局、佐田さんは復帰後1年の間に、社内の主要ポストに就いていた5人の幹部全員の辞表を受理することになりました。

「背水の陣での乾坤一擲の戦い」を始めるべく、佐田さんは自らの足で店舗の物件探しから始めます。出店先は、駅の乗降客数が最も多い東京・新宿に絞りました。「震災後で空き店舗が増えており、安い条件で見つけられるはず」との見通しが当たり、ビルの4階ではありますが、新宿駅南口から徒歩3分の好物件を押さえられました。
新規出店に伴う資金繰りは、まさに薄氷を踏むような綱渡りの状態でした。注目したのは、卸と小売りの支払いサイトの違いです。卸では受注から入金までに平均75日程度掛かりますが、小売りであれば受注即日に入金されます。オープンセールでの売り上げを当て込み、店舗物件の敷金や礼金の3分の2と内装費、約100万円を掛けた山手線の窓上広告などの支払いを先延ばししてもらいました。必然的に新店舗の開店日は、冬物の注文が最も多い10月となりました。
4)今やれることを徹底してやる
新宿への出店について、幹部や社員に対しては不安のそぶりも見せなかった佐田さんですが、内心は「成功する可能性は、5割もないと思っていた」といいます。それでも決断が揺らがなかったのは、幼少の頃から祖父に何度も聞かされた「出足と手数」の教えがあったからでした。祖父は常々、「困ったときにすべきことは、今できることは何かを考えることだ。そして思いついたらすぐにやってみる。それでダメなら、また別の方法を考えればよい。それができなければ、戦場では生き残れなかった」と語っていました。祖父の言葉を胸に、佐田さんは「成功する確率が低いので意味がない、という理由をつけてやらなくなるのは、未来に翻弄されている中途半端に賢い社長がはまる落とし穴。どんなに可能性が低くても、他に道がなければ、徹底してやる」と決意を固めます。
佐田さんの決意を象徴するのが、宣伝用のティッシュ配りです。朝4時頃に起床して、新宿の店舗の看板を出し、ティッシュ配りをしてから、どの社員よりも早く出社する。新宿の店舗のオープン後の半年間、佐田さんはこのような毎日を過ごしました。「通行人に舌打ちされることもあるし、売り上げに対する効果はゼロかもしれない。でも、新宿の店舗の成功のために、他に早朝の時間にできることはなかった。私の本気を社内に示すためにも、続けることにした」といいます。
5)小売り事業は大成功
オープンセールでは、スペアのスラックス付きオーダースーツを1万9800円に設定した目玉商品が話題を呼び、約800万円の売り上げを記録。この成功で社内の雰囲気が一気に変わります。得られた利益を新規出店や店舗の移転費用に回し、さらに利益を得るという好循環も生まれ、SADAは増収増益基調に転じます。内外からその実力を認められた佐田さんは、社長復帰への道筋をつけました。
社長に復帰した佐田さんは、会社のために、自らが“広告塔”となることも厭(いと)いません。小売り事業で重要な知名度の向上と、社員に「メディアで取り上げられるほど、自分たちの会社の進む方向は正しい」と感じてもらうためだといいます。2013年からは動画マーケティングに着目し、年に1回程度、自社製のスーツ姿で富士登山やスキージャンプ、東京マラソンなどに挑戦する動画をYouTubeにアップしています。
こうした努力が実り、SADAは2017年、社員への賞与を20年ぶりに復活させることができました。そのとき工場のベテラン女性社員たちから掛けられた言葉は、佐田さんにとって今でも忘れられない一言になっています。それは、「社長を男にできた」でした。
2 事例2:「会社は社長のものにあらず」未練を残さず事業売却
皆と力を合わせて、会社はそれなりの規模にまで成長した。でも今後、社員やその家族にとって、より良い会社にしていくためにふさわしい社長は、自分ではないかもしれない――。
豆腐の移動販売フランチャイズ事業会社「豆吉郎」の創業者である宮嵜太郎さんは、10年以上掛けてグループ累計の売上高を100億円にまで成長させた後、そんな思いに至ります。
そのとき下した「宮嵜さんの決断」は、新聞社へ事業を譲渡することでした。そしてそう決断した宮嵜さんは、売却する際に自分自身に対して、「社員や金融機関に迷惑を掛けない」という条件を課していました。
1)当初のイメージの7割以下なら撤退
24歳のときから地元の福岡県でおよそ13年間にわたり、米の配達業、レンタカー事業、物干し竿(ざお)の移動販売業、造園業など約20の事業の起業と撤退を繰り返した宮嵜さん。2005年に起業した豆吉郎(当時は藤吉郎)も、開設した50事業所のうち25事業所を撤退しました。13年中、赤字だったのは8年でした。
その間、子供のための積立預金や、一人暮らしの母親が老後のために積み立ててきた生命保険を解約するなどして、資金をやり繰りしてきました。
「家族にも苦労を掛けた」という宮嵜さんですが、社員のリストラと給料の遅配、そして金融機関への返済の遅延だけは一度もしませんでした。宮嵜さんは、そうならないように「失敗したら会社そのものが潰れる、というチャレンジはしない」と自らを戒めていたためです。軽トラックによる豆腐の移動販売事業を、初期投資の回収リスクが軽減できるフランチャイズチェーン(以下「FC」)方式にした理由の1つも、その戒めがあるからでした。深手を負う前の早めの撤退も、自身の中のルールに定めていました。「売り上げを含めて、当初イメージしていた姿の7割以下だったら事業を撤退すると決めていた」といいます。

2)全国最大の移動販売組織を構築
過度なリスクを取らないとはいえ、宮嵜さんは、事業拡大のためのチャレンジには貪欲でした。客単価アップのため、豆腐以外の製品の販売を拡充していきます。また、ファン層拡大のため、月に1回、顧客が考えた豆腐を使ったオリジナルレシピなどを掲載したチラシの発行を始めました。FC事業の要である加盟店のオーナーとは頻繁に意思疎通を図り、パートナーとしての信頼関係を築くとともに、社員に対しては加盟店オーナーになることを奨励しました。
こうして広げていったFC網は、やがて西日本一帯をカバーする全国最大の移動販売組織にまで発展します。グループ累計の売上高は100億円に達しました。
3)社員とその家族の利益を考え、売却を決意
ようやく“収穫期”を迎えた豆吉郎ですが、宮嵜さんは2016年、M&A仲介会社を通じて会社そのものを売りに出します。
理由の1つは、売り上げ至上主義からの転換です。起業当初は、仕入れ面などでのスケールメリットを享受するために、売り上げの拡大に努めてきました。しかし、スケールメリットは限界に達し、「労働集約的な事業なので、これ以上売り上げが増えても、社員や加盟店の人たちの収入や休暇の増加にはつながらない。今後の売り上げ増は社長の自己満足でしかない」と考えるようになったそうです。
利益面でのネックになっていたのは採用コストでした。事業が軌道に乗り始めた頃は、リーマンショックの影響もあって1人当たりの採用コストが2万円程度でした。ところが景気が回復して人手不足となった結果、80万~90万円にまで上昇し、「利益の多くが求人のために使われ、起業当初のイメージと違ってきた」といいます。
その一方で、10年掛けて構築した事業の運営ノウハウに関しては、「すでに仕組みが出来上がっており、自分がいなくても会社が回るようになっている」と判断。このような状況を客観的に分析した宮嵜さんは、「200人の社員とその家族のことを考えると、豆吉郎が潰れない確率が高い、安心感や社会的に高い評価のある会社がオーナーになるほうがよい」との考えに至ったといいます。
4)売却先は西日本新聞社に
「そこまで黒字額が多いわけでなく、食品を移動販売で取り扱うというリスクもある。引き受けてくれるところが多くあるとは思っていなかった」という豆吉郎の売却先ですが、大手のコンビニエンスストアや飲食店チェーンを含む約100社が関心を示してくれました。
数ある選択肢の中から宮嵜さんが売却先に選んだ相手は、全くの異業種である西日本新聞社でした。決め手は、豆吉郎に対する評価額と、新聞社という社会性の高さからくる安心感でした。さらに、「西日本新聞社はなかなかリストラをしない会社だと知っていたので、雇用を守ってくれるだろうと思った」といいます。
5)情と数字のバランスを意識する
家族に苦労を掛けながら、社長・会長として13年を費やして育て上げた豆吉郎ですが、売却することに全く未練はなかったといいます。その背景には、宮嵜さんが「会社に対する愛着を50%しか持たないように心掛けてきた」ことがあります。
「起業した当初は社員を家族のように思い、社員から好かれようとしていた」宮嵜さんですが、社員の数が10人、15人と増えて“部下の部下”ができ、全社員に直接自分の思いを伝えられなくなった頃から、考えを改めるようになりました。「社員の生活を安定させ、良くしていくのが仕事」と割り切り、50%はドライなビジネス感覚で経営判断を行うようにしたといいます。起業時からいる社員や、自分の近くで働いている社員を特別に高く評価したり、頑張った出店者に同情して不振店の撤退を決められなかったりという、「正常な判断ができない」状態を避けるためでした。
ドライなビジネス感覚での経営判断は、自分自身の進退に関しても一貫していました。「ずっと未来永劫(えいごう)、(自分が)社長でいられるわけではなく、会社を渡すのが今なのか、30年後なのかという、時間の問題だけ。それならば、利益も出ており、売却するにはもったいないと言われている今のほうがよい。売却候補と有利な立場で話を進められ、社員の雇用の維持なども求められる」。それが宮嵜さんの出した結論でした。
宮嵜さんが豆吉郎の売却を終えて抱いた思いは、「誰にも迷惑を掛けず、ちゃんと辞められて、ほっとした」でした。
3 決断とは、何が一番大事なのかを選ぶこと
既存の取引先と競合関係になるリスクを負いながら、会社の危機的状況を打開するために小売り事業に参入した佐田さん。会社が大きく成長して収穫期を迎えた中で、社長やオーナーの座を譲ることにした宮嵜さん。2人の決断の内容は全く異なりますが、佐田さんは会社を存続させること、宮嵜さんは社員や金融機関に迷惑を掛けないことを一番に考えて、それぞれ決断しました。
そして、佐田さんはどの社員よりもがむしゃらに働き、宮嵜さんは会社を手放すという、ある意味で「自分が一番損な役回り」になることを厭いませんでした。
決断に迷ったとき、「何が一番大事なのか」「大事なもののためなら自分が不利になっても構わないと思えるか」を自問することが、迷いから抜け出すためのヒントになるのかもしれません。
【参考文献】
「迷ったら茨の道を行け:紳士服業界に旋風を巻き起こすオーダースーツSADAの挑戦」(佐田展隆、ダイヤモンド社、2018年12月)
「元手10万円で100億円の売上をつくった事業のコピペ術:フランチャイズ本部のつくり方」(宮嵜太郎、クロスメディア・パブリッシング、2019年11月)
以上(2020年5月)
pj10047
画像:インタビュー先より入手