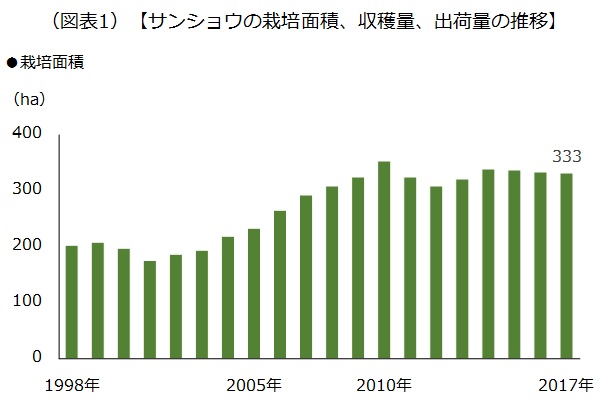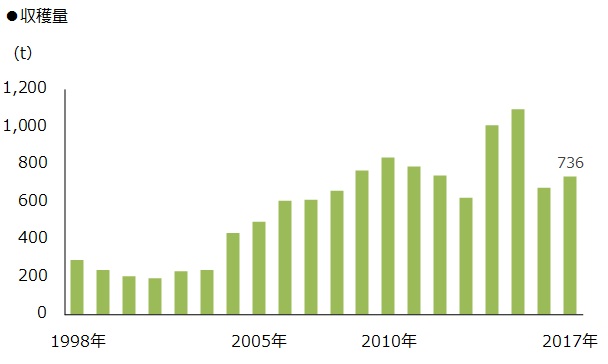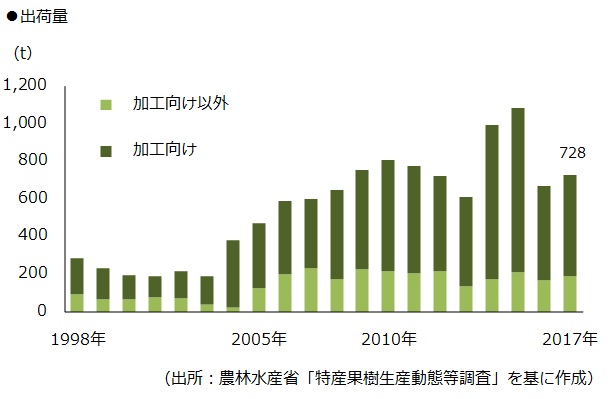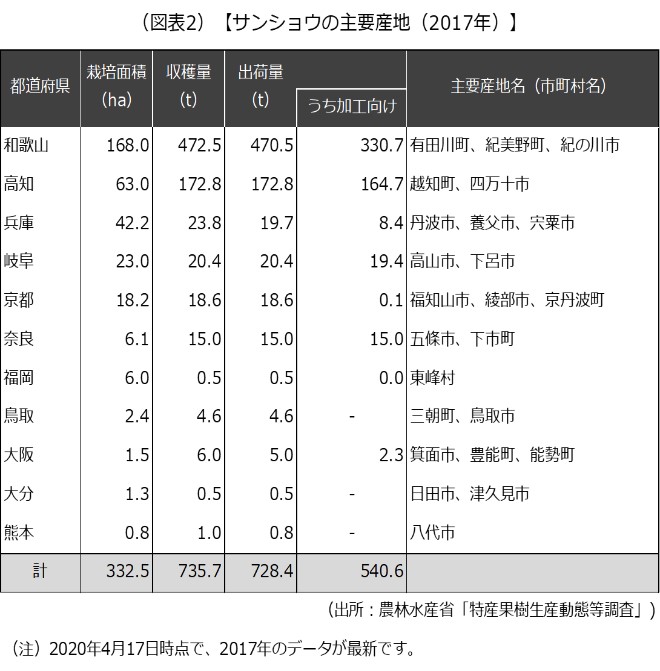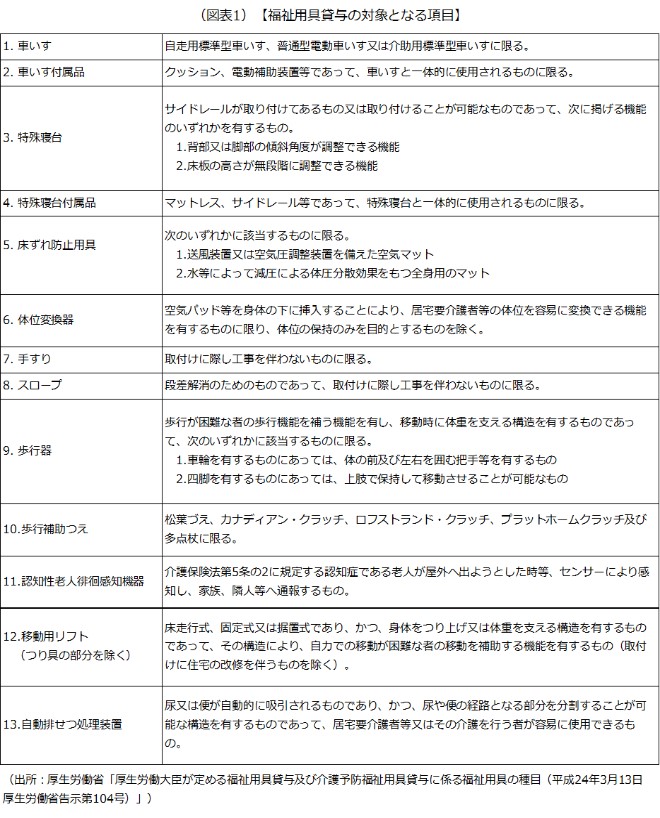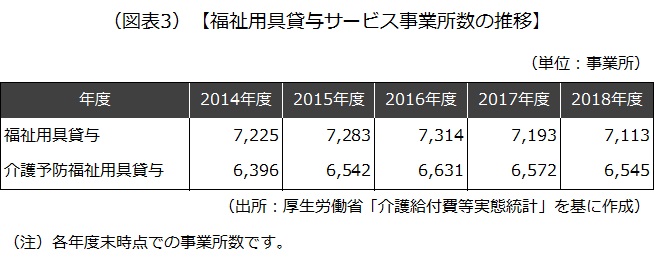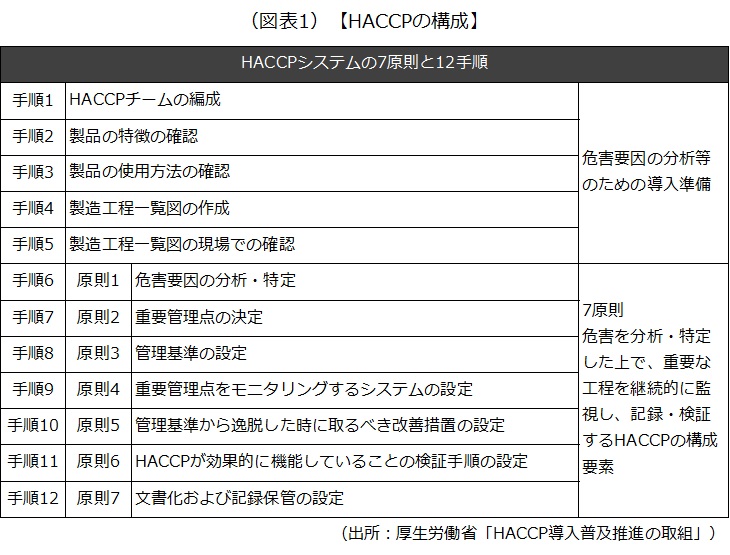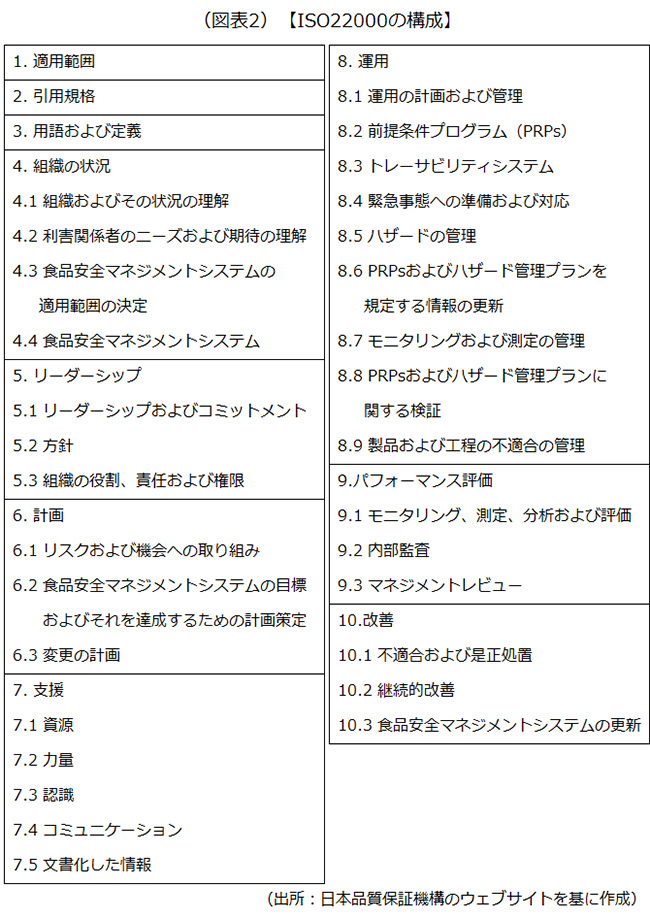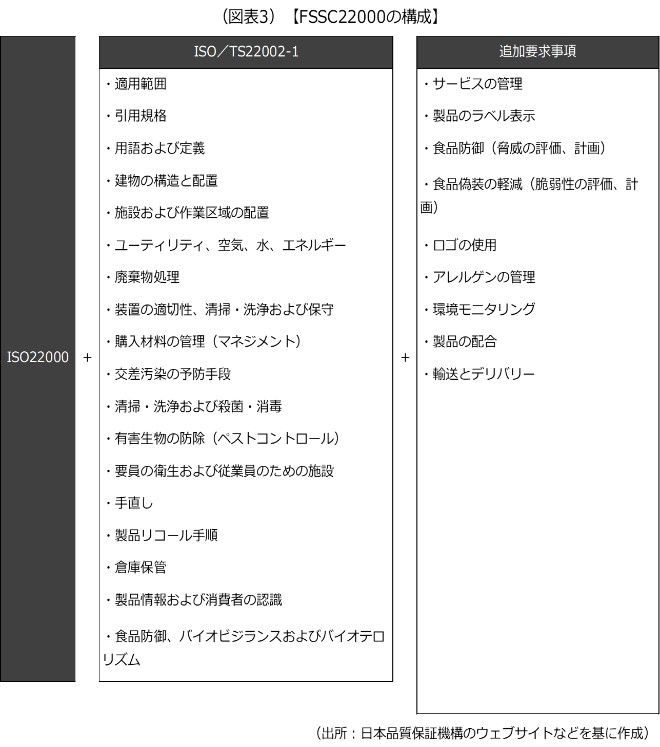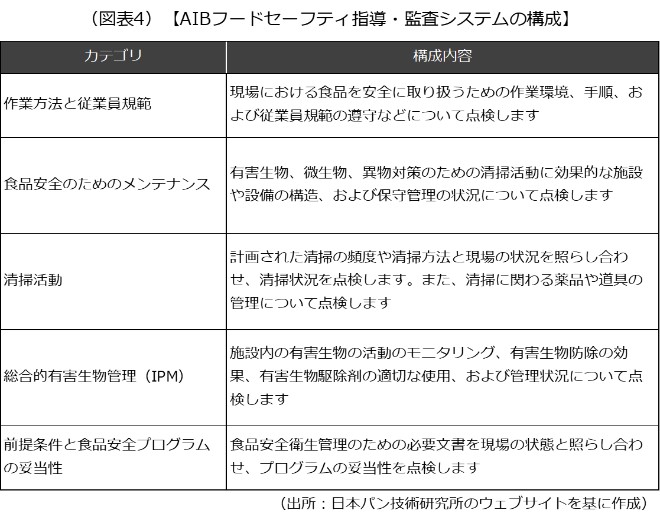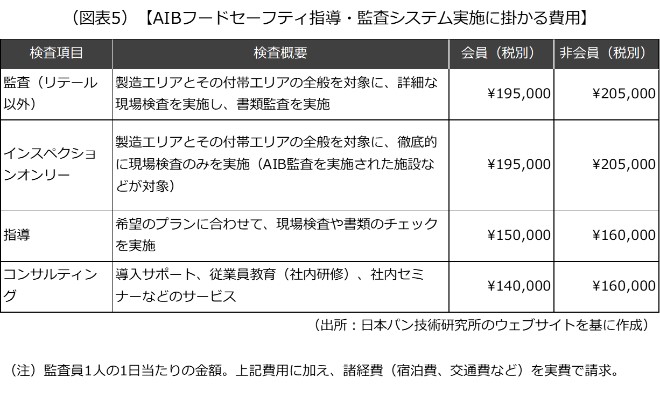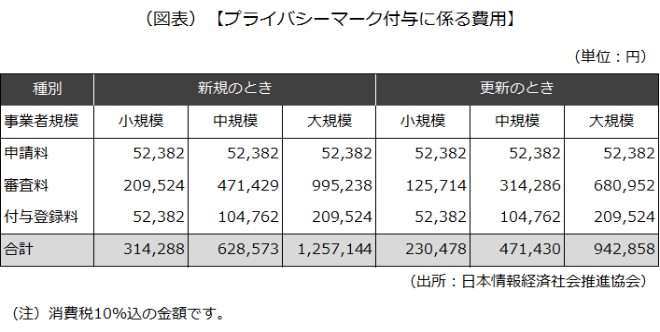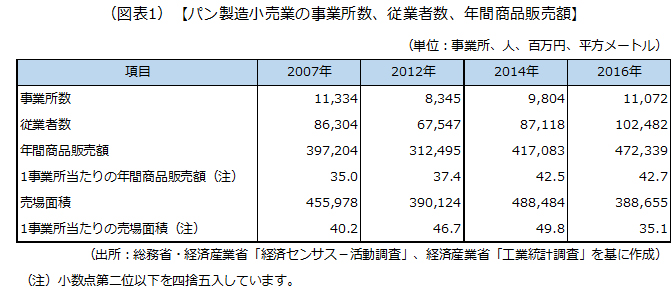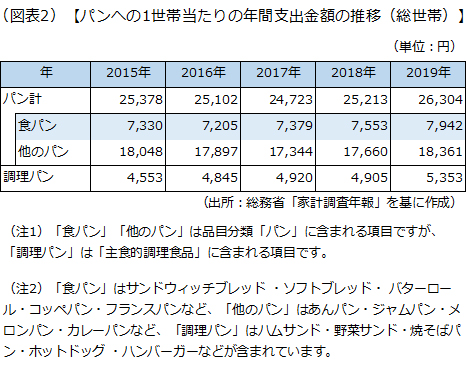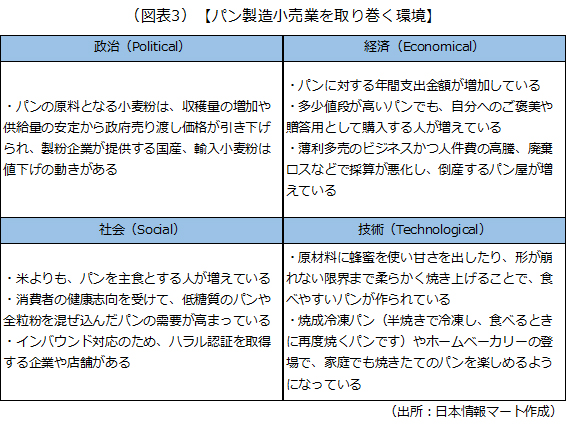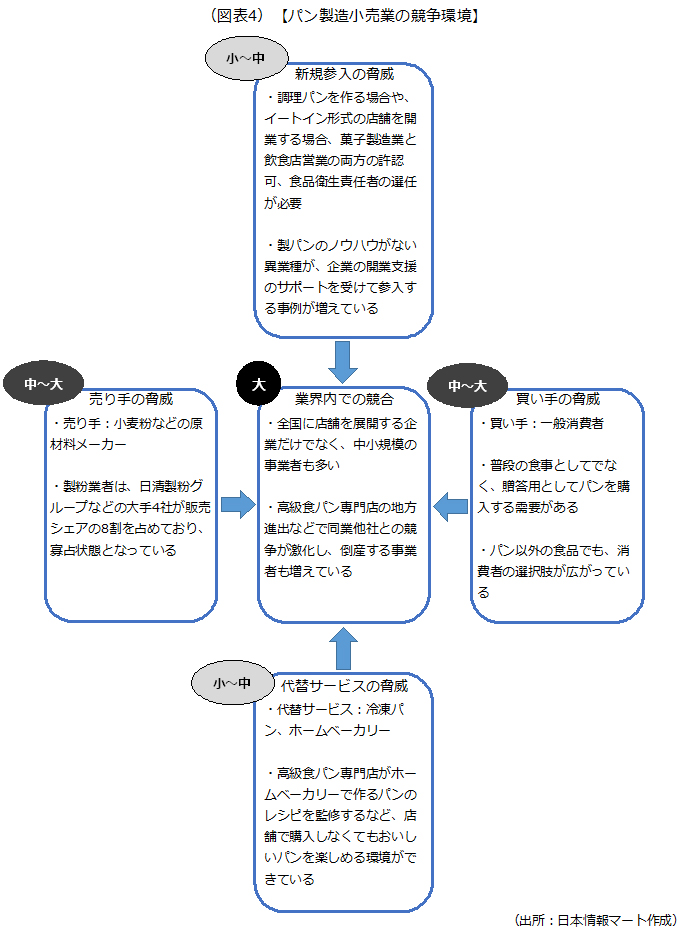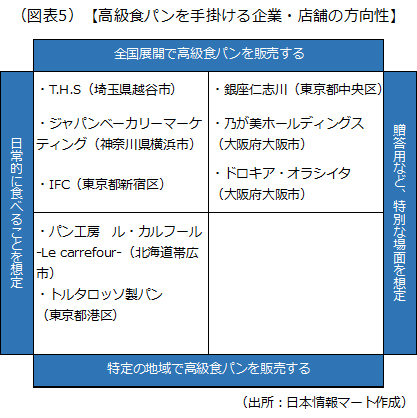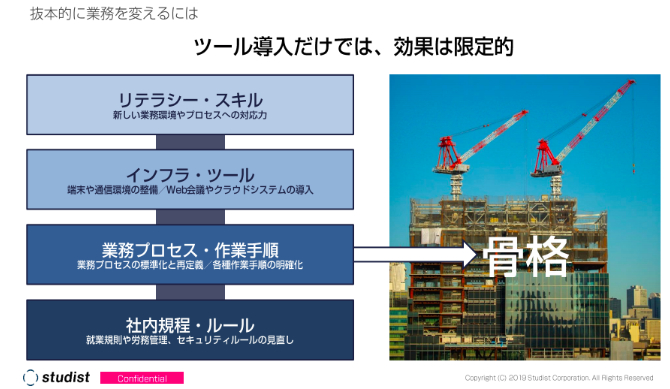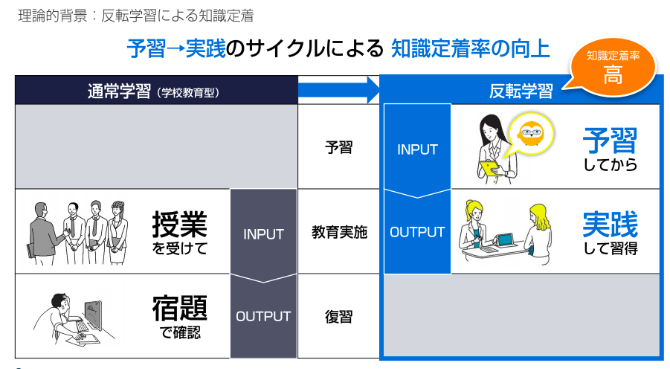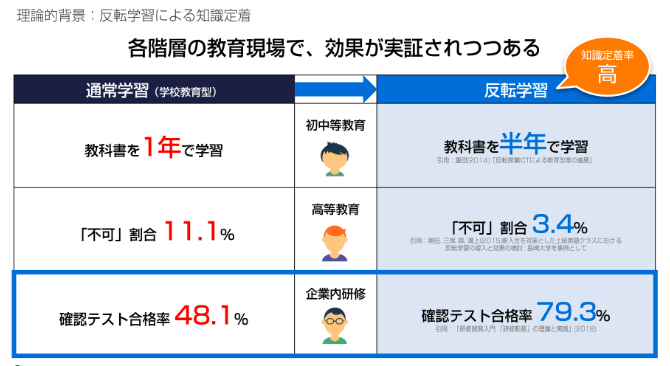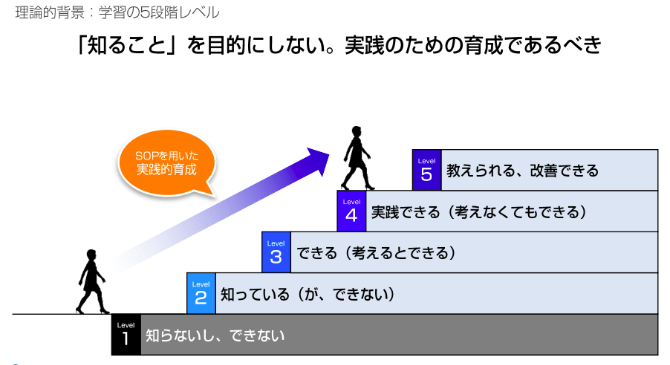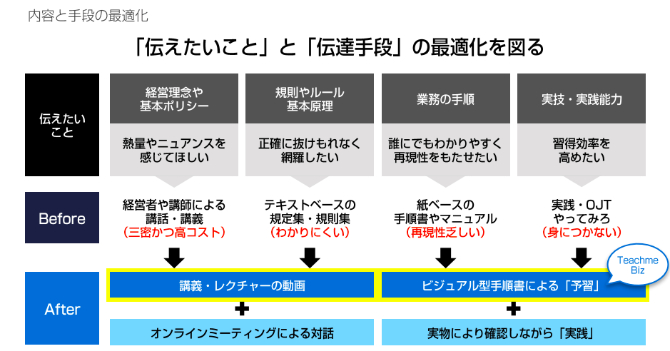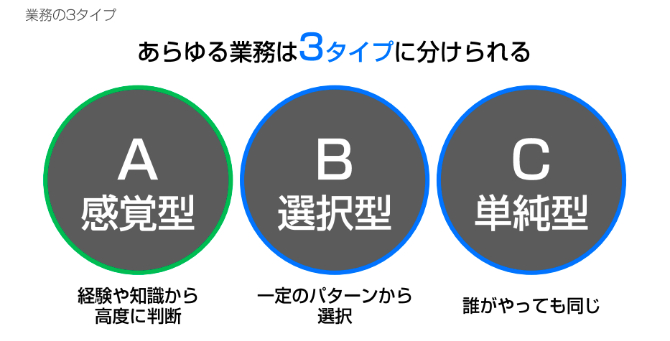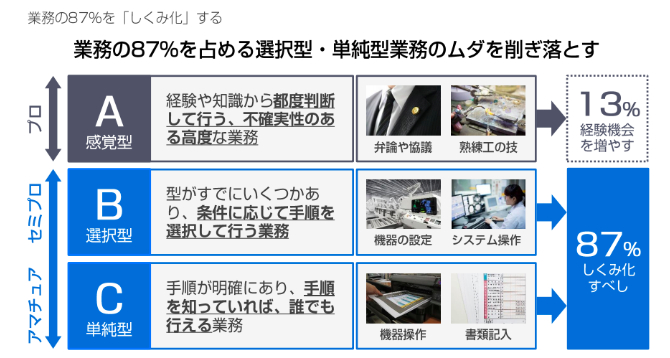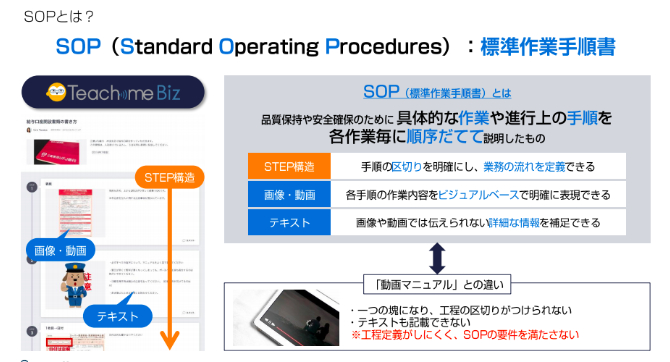書いてあること
- 主な読者:自社で管理する住宅やマンションの付加価値を高めたい不動産会社
- 課題:導入に当たって、どのような設備が良いのかが分からない
- 解決策:導入されることが多い設備として、アナウンスを流して無人で応対するインターホンや、カメラを使って来訪者を識別する顔認証システムなど、入居者のプライバシー保護や建物のセキュリティーを高めるものがある
1 スマート住宅やスマートマンションで導入される設備の主な事例
ここでは、スマート住宅やスマートマンションに導入される設備の主な事例について、「防犯・セキュリティー」「設備管理」「防災」「介護」「エネルギー管理」「その他」の分野に分けて、それぞれ紹介します。
1)防犯・セキュリティー
1.入居者のプライバシーを守るインターホン
パナソニック(大阪府門真市)が提供するマンション向けインターホン「クラウジュ」は、ロビーインターホンから自動でアナウンスを流して来訪者の用件を事前に確認することで、入居者が用件を確認した上で応対するかどうかを判断できます。
このため、セールスに応対したくない、日中の不在を知られたくないといった入居者のプライバシーを守ります。また、不在時でも来訪者の顔と用件を記録し、カレンダー形式で来訪者の履歴をインターホンの画面に表示できます。
他にも、マンション管理事務室からの連絡やアンケート、天気予報などを住戸内で確認できる機能を備えています。
同社は、戸建て住宅向けのインターホンでも、外出中にスマートフォンで来客応対をしたり、アナウンスを流して来訪者の用件を事前に確認したりできる製品を提供しています。
2.外出先からでも応対可能なインターホン
アクロディア(東京都新宿区)は、マンション向けのインターホンIoTシステムを提供しています。インターホンをインターネットに接続することで、外出先からでもスマートフォンなどの端末を経由して、来訪者との通話やオートロックの解錠ができます。
また、来訪者の顔をデータとして登録できるため、専用アプリの画面上で誰が来たのかを確認できます。
宅配会社や運送会社向けには、遠隔でインターホンを鳴らして入居者が在宅しているかどうかを確認する機能もあります。これにより、宅配会社などは、不在による再配達の手間を無くせる他、入居者は荷物の再配達時間を外出先から配達員に直接伝えることができます。
3.顔認証式の宅配ボックス
フルタイムシステム(東京都千代田区)は、宅配ボックスを使ったマンション向けセキュリティーサービス「F-ace」を提供しています。
宅配ボックスに内蔵されたカメラを使い、利用者の顔を識別する認証機能を備えているのが特徴です。
顔認証によって、入居者が鍵やICカードを使わずにマンションのエントランスやエレベーターに入れる他、子どもがエントランスを通過したときに、自動で保護者にメールを送信して、子どもの帰宅を知らせます。
4.入居希望者の内覧、民泊にも対応できるスマートロック
大崎電気工業(東京都品川区)は、集合住宅向けに既設の鍵に後付けで交換できるスマートロック「OPELO」を提供しています。
OPELOは、交通系ICカードやおサイフケータイ、シリンダー錠、暗証番号といった多様な解錠・施錠方法に対応したスマートロックです。ワンタイムパスワードを自動で発行する機能を備えているため、空室時に入居希望者が部屋を内覧するときや、外国人観光客の民泊のときに、管理人がその都度鍵の貸し出しや返却に立ち会う手間が無くなります。
5.徘徊(はいかい)防止に有効なスマートロック
エナスピレーション(静岡県藤枝市)は、戸建て住宅、集合住宅向けの徘徊対策に有効なスマートロック「ES-F700G」を提供しています。
ES-F700Gは、指紋認証、暗証番号、ICカードで解錠できるスマートロックです。既設の玄関ドアに後付けで交換可能で、オートロックのため、鍵を閉め忘れる心配も無くなります。
また、室内から解錠するときは、登録済みのICカードもしくは非常キーが必要になるため、認知症による突然の外出や徘徊の防止につながります。他にも、火災や不正解錠に対する警報機能も備えています。
2)設備管理
1.マンション掲示板のデジタル化
大京(東京都渋谷区)と、グループ会社の大京アステージ(東京都渋谷区)は、自社が手掛けるマンション「ライオンズ蒲田レジデンス」に24時間、365日対応のAI管理システム「AI INFO」を導入しています。
AI INFOはマンションの管理員が担う機能とマンションの掲示板を一体化したシステムです。管理員機能は、入居者からの問い合わせに対して、AI管理員が音声で自動応対するシステムで、入居者はスマートフォンから問い合わせができます。
また、これまでは貼り紙で掲示していた情報をデジタル化することで、管理会社からのお知らせに加えて、施設内での落とし物や地域のイベント、天気予報などのさまざまな情報を配信できるようにしています。
2.住宅設備全体のコントロール
YKK AP(東京都千代田区)は、エアコンや照明などの家電製品に加え、シャッターや玄関ドアといった住宅設備を統合管理するサービスを提供しています。
HEMS(Home Energy Management Systemの略称で、家庭内で使うエネルギーを節約するための管理システムをいいます)用の制御パネルから住宅設備を操作できるだけでなく、外出先でスマートフォンからシャッターの開閉や玄関ドアの解錠、施錠ができます。そのため、大雨や強風の際は外出先からシャッターを閉めて、ガラスが割れるのを防ぐことができます。
3.顔認証によるマンション共用部分の利用
ヨシコン(静岡県静岡市)とフルタイムシステム(東京都千代田区)は、マンションのゲストルームなどの共用部分を顔認証で利用できる「スマートマンションシステム」を2021年3月から静岡県藤枝市のマンションで導入する予定です。
スマートマンションシステムは、フルタイムシステムが手掛ける顔認証サービス「F-ace」と、パソコンや携帯電話からマンションの共用部分の利用予約ができるウェブサービス「ファンナビ」を組み合わせています。ファンナビでマンションの共用部分の利用予約をした上で、共用部分に設置されたカメラで顔認証を行うことで利用できます。共用部分を利用する際に、その都度管理室から鍵を借りなければならないといった手間や、鍵を紛失するリスクが無くなります。
3)防災
1.防災用品を格納した宅配ロッカー
穴吹興産(香川県高松市)、日本電力(香川県高松市)、エリーパワー(東京都品川区)、フルタイムシステム(東京都千代田区)は、マンションや集合住宅向けの「シェアリング防災宅配ロッカー」を共同開発し、2020年3月に発売しました。
シェアリング防災宅配ロッカーは、宅配物の受け渡しだけでなく、災害時の電力供給や防災用品を格納する機能を備えています。地震発生時には揺れを感知し、自動で扉が開いて防災用品を取り出せるようになる他、外部からの電力供給が遮断されても、内蔵のリチウムイオン電池により約3時間の電力供給が可能です。
2.BCP(Business Continuity Plan・事業継続計画)をサポートするビル管理システム
大成建設(東京都新宿区)は、東光高岳(東京都江東区)と共同で、災害発生時に館内設備を自動的にコントロールする「T-BC Controller」を2020年1月に開発しました。
T-BC Controllerは、主にオフィスビルを想定した設備管理システムです。大規模災害でライフラインの供給が止まったときに、BAS(Building Automation Systemの略称で、設備を監視・管理・制御するシステムをいいます)やBEMS(Building Energy Management Systemの略称で、設備の使用エネルギー量などを把握・管理するシステムをいいます)と連携して水や発電機燃料などの供給可能時間を可視化します。また、優先度の低い部屋の電源や設備を自動で停止させることで、施設の稼働時間の確保や、BCPの実行を支援します。
4)介護
1.急性疾患の予防
積水ハウス(大阪市北区)は、戸建て住宅向けの在宅時急性疾患早期対応ネットワークの「HED-Net」を2020年中に提供開始する予定です。
HED-Netは、入居者の心拍数などのバイタルデータを解析し、脳卒中などの急性疾患を発症する可能性を検知した際に緊急通報から安否確認、救急隊の出動要請、玄関ドアの遠隔解錠・施錠までを一貫して行う仕組みです。
同サービスは、「安否確認システム」として国内のシステム特許を取得し、国際特許も出願中です。
2.AIを活用した要介護状態の予防
ネコリコ(東京都千代田区)、日本データサイエンス研究所(東京都文京区)、東京大学は共同で、AIと電力データを用いたフレイル(健康な状態と要介護状態の中間に位置し、身体や認知機能の低下が見られる状態)の検知に関する実証実験を2020年内に三重県東員町で行うこととしています。
実験では、単身の高齢者世帯を対象に、スマートメーターから得られる電力データ、モーションセンサーやCO2センサーのデータ、AIを活用し、フレイルの簡易判定、早期発見に取り組む予定です。
5)エネルギー管理
トヨタホーム(愛知県名古屋市)が戸建て住宅向けに提供するエネルギー管理システム「HeMS」は、太陽光などの発電状況と併せて、家庭内の各部屋、機器ごとの消費電力も把握できます。
また、車のカーナビゲーションシステム、スマートフォンから玄関の鍵やエアコンなどの機器を操作できるため、鍵の掛け忘れやエアコンの消し忘れなどを防止できます。
6)その他
1.入居者の利便性を高めるマンション
長谷工コーポレーション(東京都港区)は、ICT技術を活用した学生向けの賃貸マンションを施工しています。
マンションにはHEMSをはじめ、顔認証で入館、エレベーター制御を行うシステムや、地震発生時に入居者や入居者の家族に通知する振動センサーを導入する予定です。
住宅設備から得たデジタルデータをクラウドに集積、分析することで、セキュリティーや情報サービス、見守りなどの入居者の利便性やサービスの向上につなげる計画です。
2.入居者の健康改善を図るスマートハウス
神奈川県横浜市は、IoTスマートホームを用いて入居者の健康状態を可視化、健康改善につなげる実証実験「未来の家プロジェクト」に取り組んでいます。
同プロジェクトはNTTドコモ(東京都千代田区)、and factory(東京都目黒区)と共同で2017年6月に発足した取り組みです。室内に設置したIoT機器やセンサーで入居者の健康や生活状況をスキャン・可視化することで入居者の健康改善につながる行動を促します。
同プロジェクトには20者の企業・団体が参画し、センサー付きパジャマや歯の磨き方をチェックできるIoT歯ブラシ、眠りを感知するセンサーを設置することで、入居者自身が設定した健康状態の目標と現時点の状態を可視化するなどの実証実験に取り組んでいます。
将来的には、AIを活用することで家自体が入居者の生活状況を把握し、室内を入居者にとって快適かつ健康的な状態に自動調節することを目指しています。
2 参考情報
1)IoT機器の導入に関するヒアリング結果
IoT機器の導入状況に関して、IoT事業を手掛けるユーピーアール(東京都千代田区)へのヒアリングによると「機械の遠隔操作、例えば、ネットワークカメラや外出先からでも応対が可能なインターホン、宅配ポストや宅配ロッカーに荷物が投函されると、スマートフォンに自動で通知が届くなどの仕組みについて、導入の相談を受けることが増えている」(*)とのことです。
________________________________________
(*)ユーピーアール(2020年2月5日時点)
2)スマートマンションの普及状況について
スマートマンション(MEMSを導入し、マンション全体でエネルギー管理、節電効果を高めるマンションをいいます)については、2013~2017年の期間で経済産業省が「スマートマンション導入加速化推進事業費補助金」制度を設けて、既設、新築マンションのスマートマンション化を支援してきました。
同補助金のMEMSアグリゲータ(マンションなどの集合住宅にMEMSを導入し、エネルギー管理の支援やMEMSから得た情報を活用し節電を図る事業者をいいます)に対する最終的な交付決定数は1685件(総戸数は18万3296戸)となっています。
助成制度が終了したあともスマートマンション化の拡大を図るために、現在はスマートマンション推進協議会がスマートマンションの認定制度を運用しています。
同協議会のスマートマンション認定では、MEMS機器を設置し、建物全体や各戸の電力使用量が見えることや、MEMS機器が共用部の機器を制御できる機能を持っていることなどを認定条件としています。2020年3月時点で、スマートマンション推進協議会が認定したスマートマンションは33物件あります。
以上(2020年5月)
pj59025
画像:pixabay