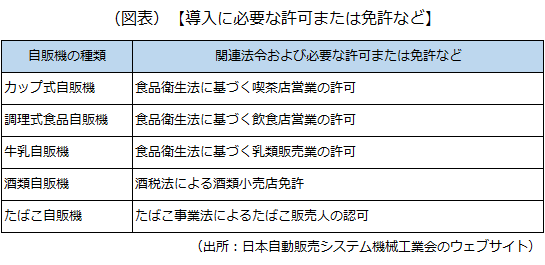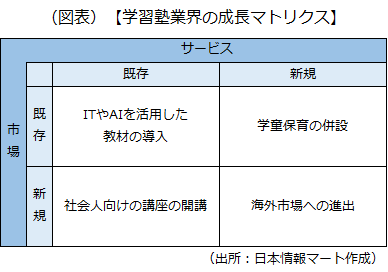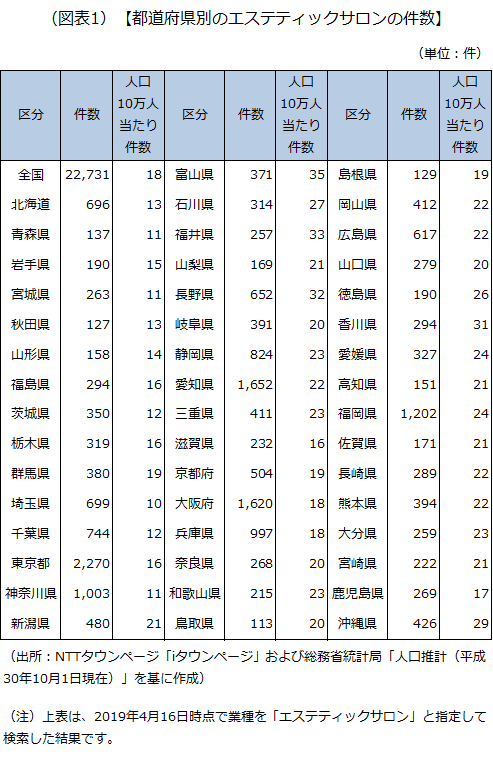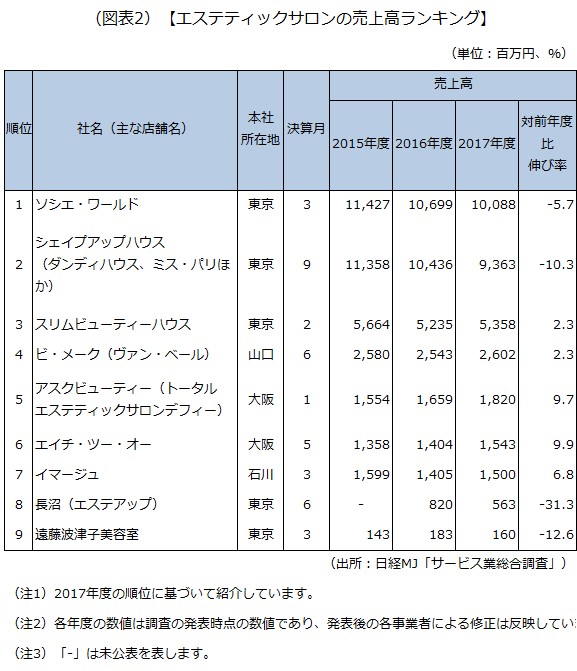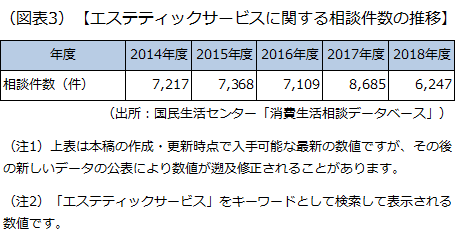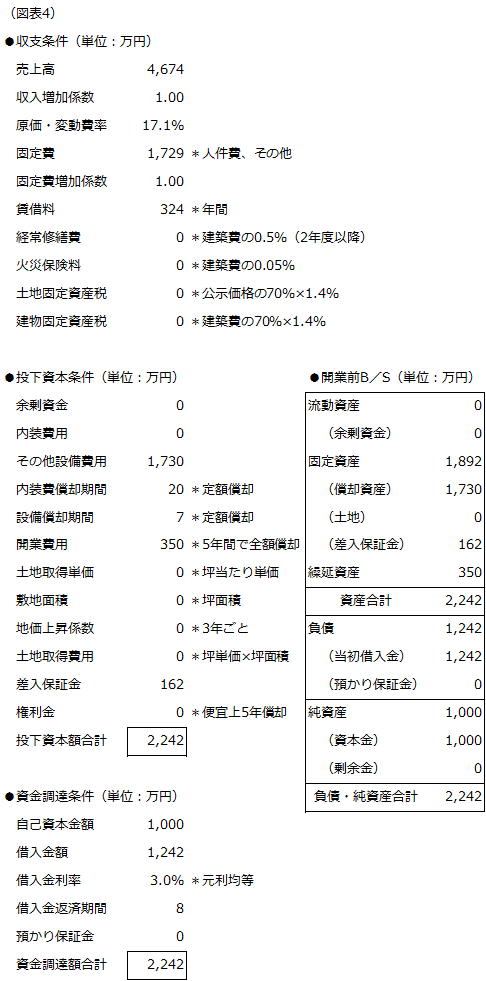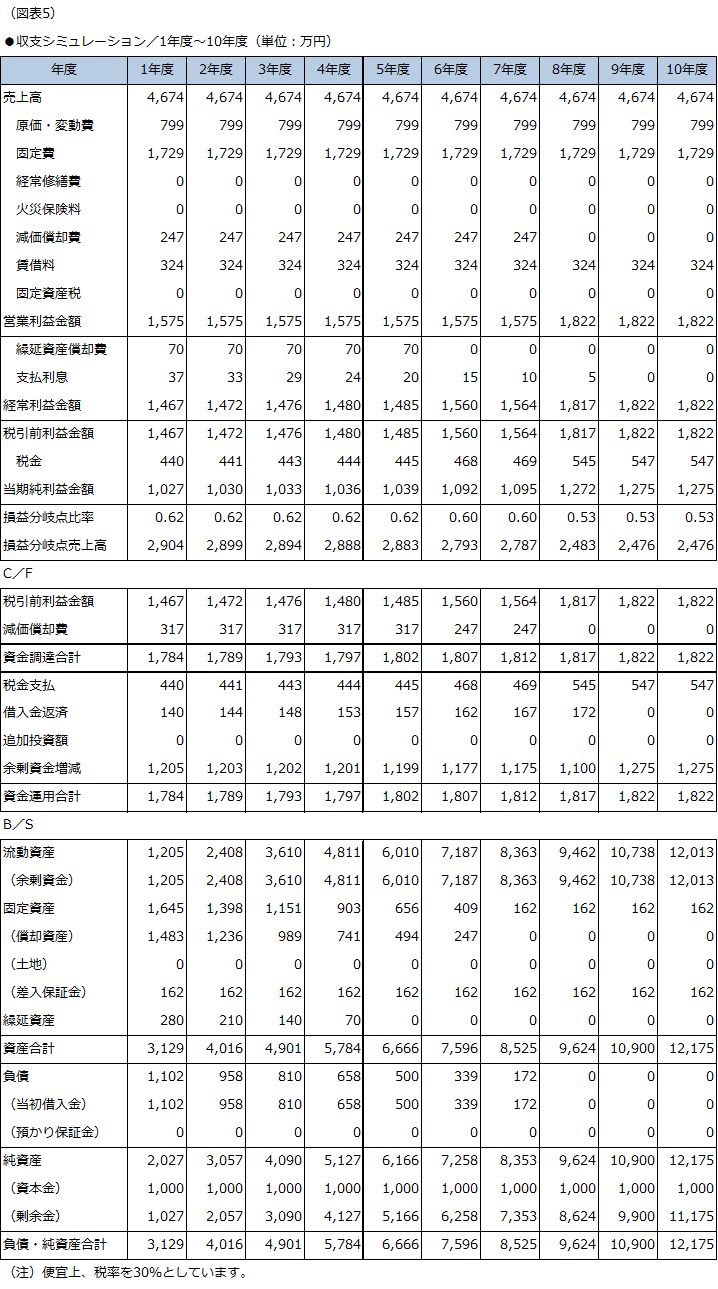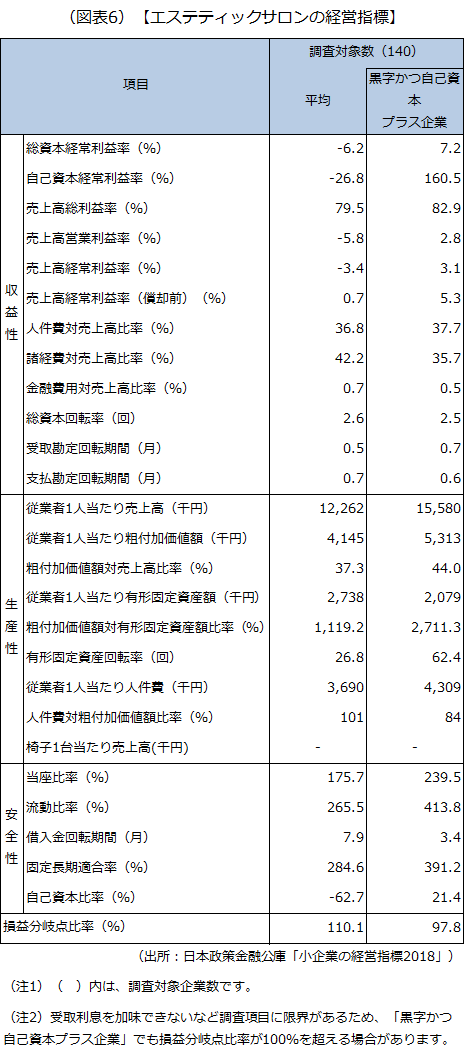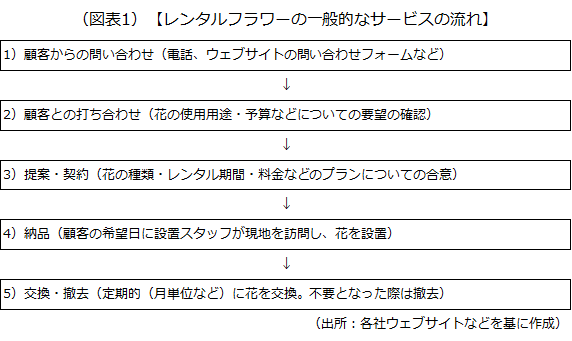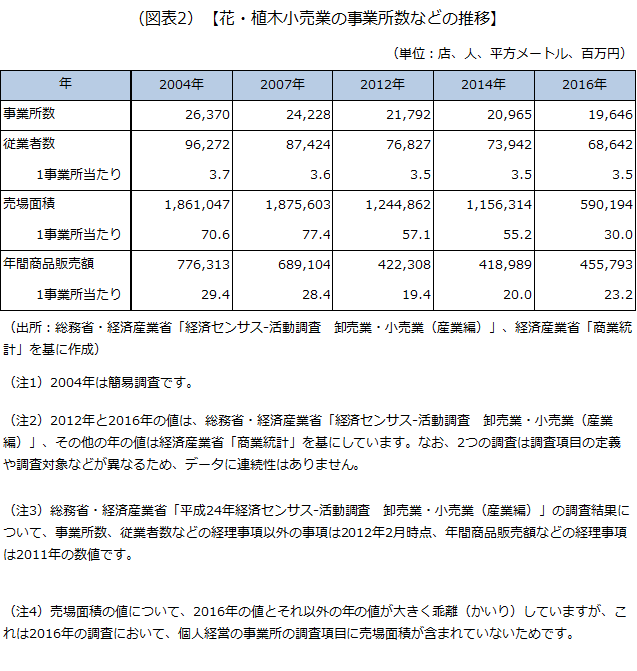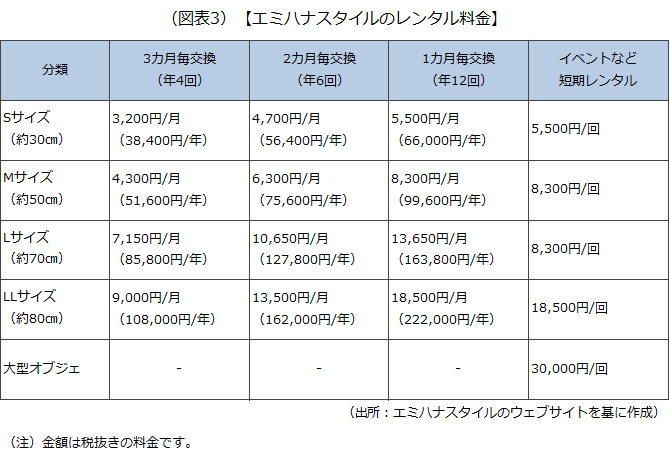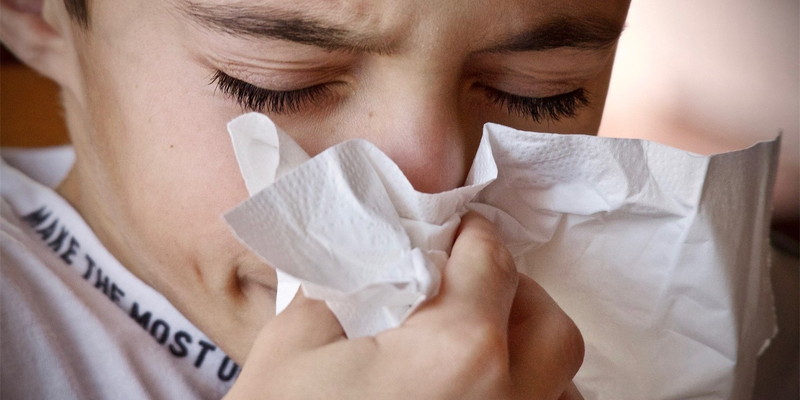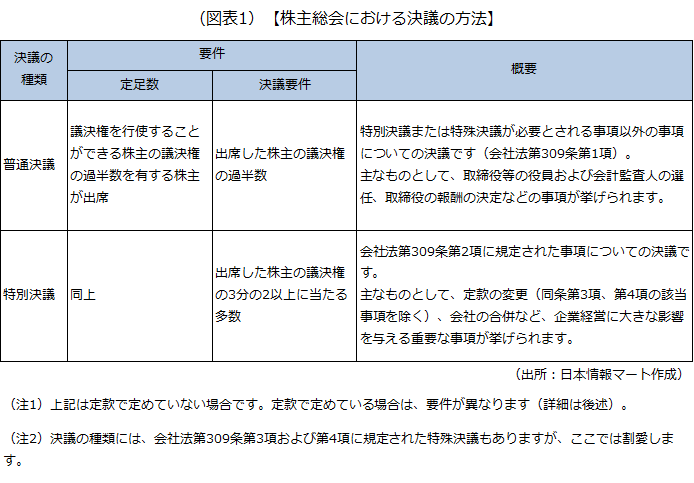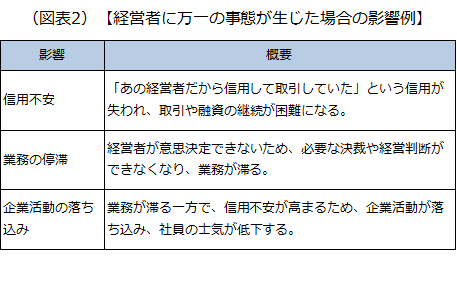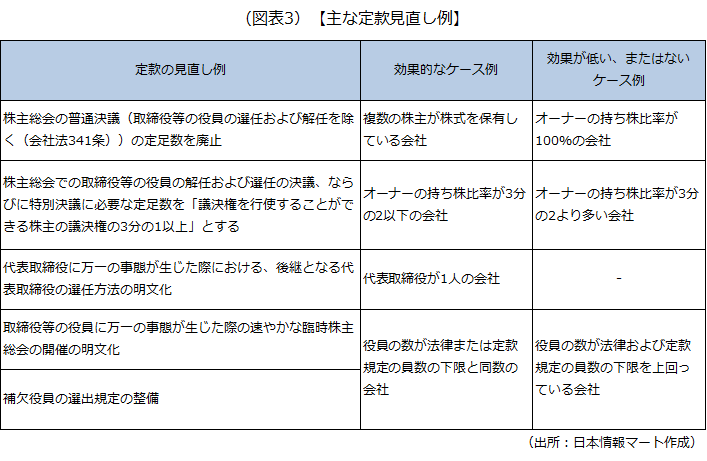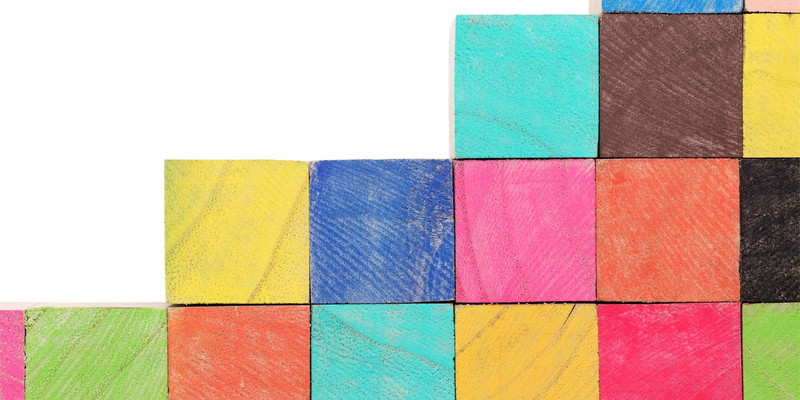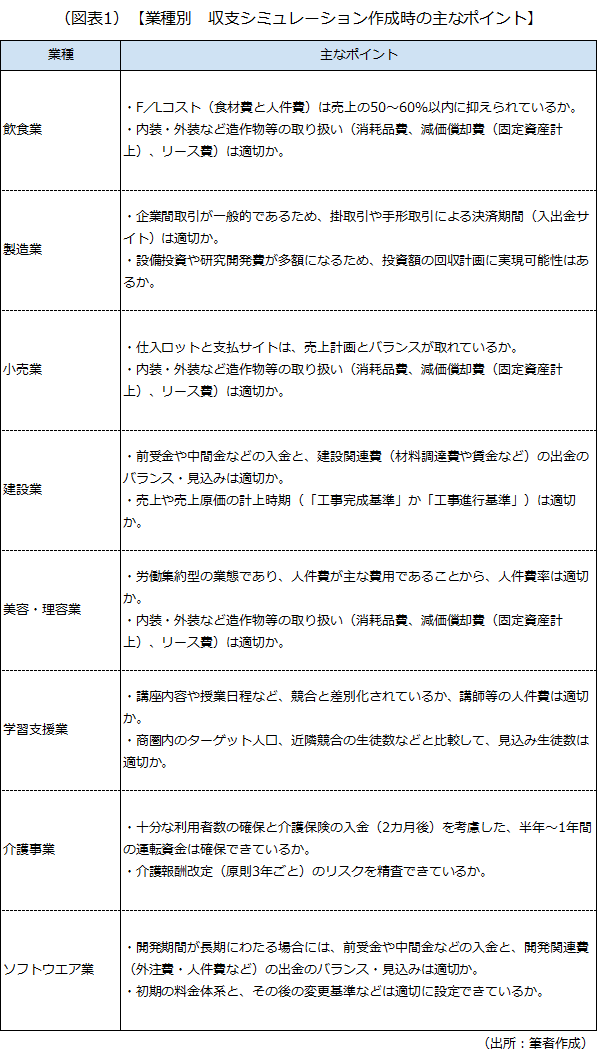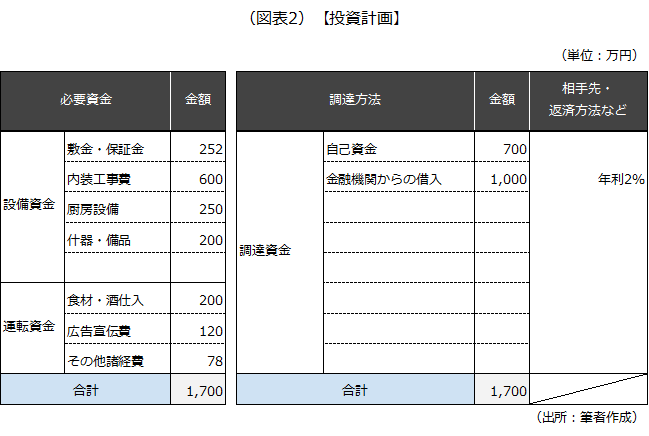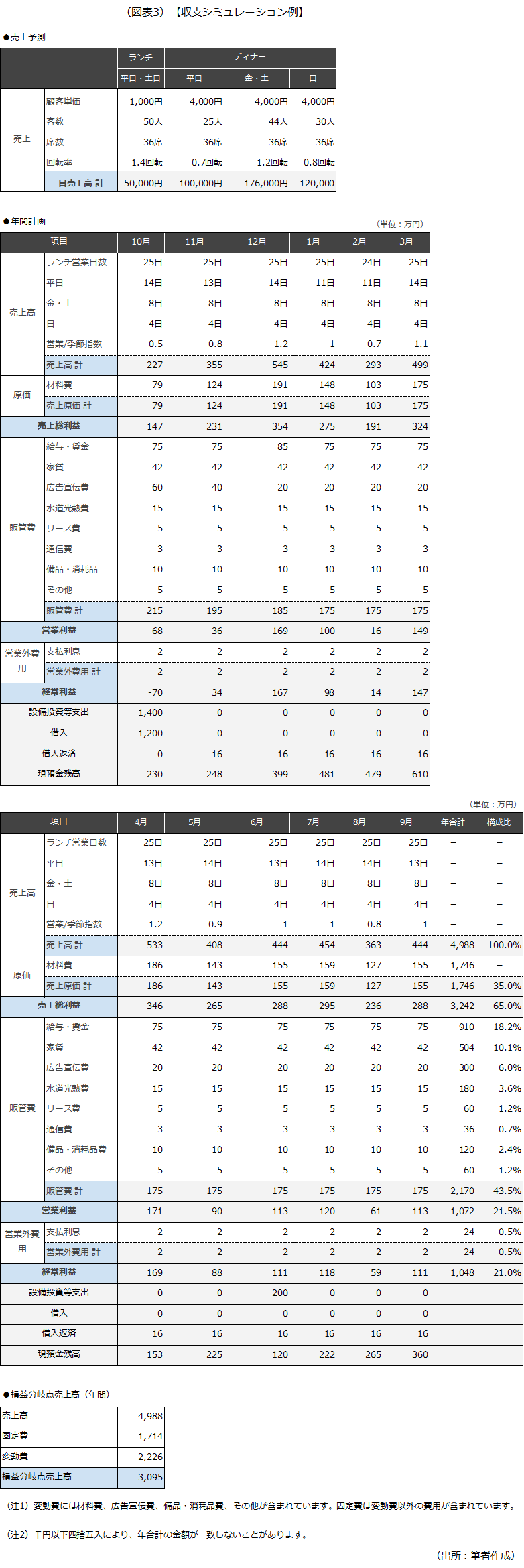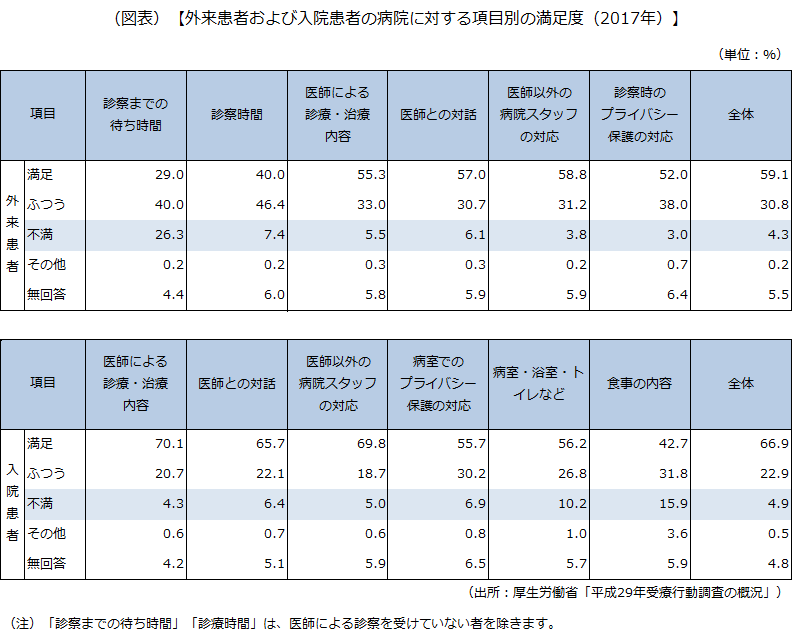書いてあること
- 主な読者:部下に「前向きに仕事に取り組んでほしい」「成長してほしい」と願う管理職
- 課題:自分と考え方や性格が違う部下のやる気を、どうやって引き出せばよいか分からない
- 解決策:「部下の本質を評価する」「まず自分が手本を示す」などの取り組みによって大業を成し遂げた戦国武将・偉人のエピソードから、部下育成のノウハウを学ぶ
1 武田信玄に学ぶ「部下を思いやり、その本質を見抜く」術
1)武田信玄のエピソード
武田信玄(たけだしんげん。本名は武田晴信(たけだはるのぶ))は、甲斐国(現山梨県)の武将です。
信玄が生まれた当時、甲斐国ではさまざまな勢力が乱立し、争いを続けていましたが、信玄の父・武田信虎(たけだのぶとら)が、これらの勢力を破り、甲斐国を統一しました。しかし、家臣の言葉に耳を貸さず専制的な政治を行う、戦費の調達のために領民に重税を課すなどの行動を問題視され、信虎は甲斐国を追放されてしまいます。
信虎の跡を継いだ信玄は、信虎とは対照的に、生涯を通じて家臣や領民を大切にしたといわれます。信玄が残した有名な言葉に、「人は城、人は石垣、人は堀、情は味方、あだは敵なり」というものがあります。
「合戦において、たとえどんなに城・石垣・堀などの守りを固めても、家臣や領民などの人心が離れてしまったら敗北は確実である。勝敗を決するのは、結局は人である。人は、用い方によっては城・石垣・堀など、合戦の際に重要なものにも成り得る」という意味です。
信玄は日ごろから家臣を大切にし、正しく評価することに努めました。そして、行政や軍事を効果的に運用するべく強固な組織をつくり上げ、合議制を採用して家臣の意見を積極的に取り入れました。
また、信玄は一軍の将でありながら、家臣たちとくつろいだ雰囲気で座談を行うことを好んだといいます。その際、信玄は自身がこれまでの経験から学んだ知恵などを家臣に説いたり、逆に家臣の意見に耳を傾けたりしました。このような場を通じて信玄の肉声に触れることで、家臣はさらに武田家に対する帰属意識を高めていったのです。
戦国時代、武田家の家臣は、その高い戦闘力と強い団結力から「武田軍団」として他国の武将たちから恐れられました。信玄の巧みな手腕が、武田家の家臣を強力にまとめ上げ、最強集団としての武田軍団をつくり上げたといえるでしょう。
2)部下のやる気を引き出す術、気持ちを引き付ける術
信玄は、家臣を見た目や表面上の言葉などではなく、本質をもって評価しました。例えば、万事において遠慮深い家臣は、合戦では「臆病者」と見られやすいものですが、信玄はこうした家臣を「思慮深い」と判断しました。「思慮深い者は常にあらゆることに対して慎重であるため、万全の態勢を整えて事に臨むだろう」と考えるのです。
このため、家臣は「信玄の下にいれば、外面ではなく本質を見抜いて判断してもらえる」と考えて発奮し、組織はより一層活性化することとなりました。後に、信玄は「人を使うのではなく、業(わざ:才能の意味)を使う」という内容の言葉を残しています。
部下の持つ長所を見抜いてそれを活用することで、部下の自発的なやる気を促し、組織のパフォーマンスを最大限に高めることができるのです。
2 織田信長に学ぶ「正当な評価によって部下のモチベーションを高める」術
1)織田信長のエピソード
織田信長(おだのぶなが)は、尾張国(現愛知県)の武将です。
織田家にはいくつかの流れがあり、信長が生まれた織田家は主流ではありませんでした。しかし、信長の父親である織田信秀(おだのぶひで)の代に大きく勢力を伸ばして織田家の主流となりました。
信秀の跡を継いだ信長は、尾張国を統一し、さらに強大な力を誇っていた駿河国・遠江国(ともに現静岡県)の今川義元(いまがわよしもと)を破り、東海道の勢力図を大きく塗り替えました。
信長が織田家を継いだ後、織田家は急速に勢力を拡大していったため、優れた人材の確保が急務となりました。信長は、家臣が優秀であると思った際には、家柄や過去の実績に関係なく登用しました。これは、家柄や過去の実績が重視されていた当時としては、画期的な人材登用でした。
特に代表的な存在は、豊臣秀吉(とよとみひでよし)でしょう。信長は、秀吉の「人心掌握に非常に長けている」という才能を見抜き、次々と重要な役職に抜てきしました。
秀吉は、その才能を遺憾なく発揮して織田家の勢力拡大に大きく貢献し、さらに信長亡き後は、天下統一を実現します。
元来は貧しい身分であったとされる秀吉が天下人にまで成長できたのには、信長の大胆かつ柔軟な人材登用が少なからず関係しているといえるでしょう。
2)部下のやる気を引き出す術、気持ちを引き付ける術
信長は、徹底した能力主義者であったといいます。このため、たとえ長年仕えてきた功臣であっても、能力がないと判断すれば、ためらわずにその任を解いたとされます。
例えば、若い頃から信長に仕え、数々の武勲を挙げてきた佐久間信盛(さくまのぶもり)は、後年、合戦における消極的な働きを叱責されて信長の下から追放されています。信長が「苛烈で家臣に対して厳しい」という印象を持たれやすいのは、こうしたエピソードがあるからかもしれません。
一方で、家柄や過去の実績などにとらわれず、家臣の能力を正しく評価しようとする信長の姿勢は見習うべきところがあります。家臣は信長の期待に応えようと努力し、努力が正しく評価されることで、さらにモチベーションが高まり、より一層仕事に励むことになるからです。
上司による正当な評価こそが、部下の、ひいては組織全体のモチベーションを高めるといえるでしょう。
3 黒田官兵衛に学ぶ「部下の意見を尊重する」術
1)黒田官兵衛のエピソード
黒田官兵衛(くろだかんべえ。本名は黒田孝高(くろだよしたか))は、播磨国(現兵庫県)の武将です。
官兵衛の生家である黒田家は、播磨国の大名・小寺家の家老でした。しかし、後に織田信長が畿内に勢力を拡大してくると、官兵衛はその将来性を確信し、信長に仕えるようになります。そこで秀吉と出会った官兵衛は、秀吉の参謀的な存在となり活躍します。
やがて、本能寺の変によって信長が明智光秀(あけちみつひで)に討たれると、官兵衛は、秀吉に「信長のあだを討つことで織田政権の後継者となり、天下統一を果たす」ことを進言するなど、秀吉の天下取りを支えました。
官兵衛は知将として知られ、官兵衛自身もその知謀を誇ったことがありました。しかし、あるとき中国地方の武将・小早川隆景(こばやかわたかかげ)から、官兵衛は鋭い頭脳を持つが故、独善的な決断を下してしまう恐れがあると忠告されました。
これ以降、官兵衛は周囲の意見に耳を傾けるよう努めたといいます。周囲の意見に耳を傾け、多面的な視点から問題を捉えることができたからこそ、官兵衛は軍師として、多数の家臣を率いる武将として、後世に名を残す功績を収めることができたのでしょう。
2)部下のやる気を引き出す術、気持ちを引き付ける術
官兵衛は、家臣の意見を尊重しただけでなく、各家臣の性格を把握し、それらをうまく組み合わせることで家中をまとめました。それは、官兵衛が「組織においては、各人が協力し合うことで、より大きな力が発揮できる」ということを理解していたからです。
このため、家臣の交遊関係を調べ「誰と誰とは性格的に合う」「誰と誰とは性格的に合わない」といったことまで勘案し、性格の合う家臣同士を組み合わせて仕事に当たらせたといいます。
このように、官兵衛は家臣に対しても細やかな配慮を欠かさず、それぞれの意見を尊重しました。自由な意見交換の場を設けることで、家臣は身分や役職に関係なく、活発に意見交換を行い、自身の頭で物事を考えるようになりました。
ただし、あくまでも最終的な決断は自身の責任の下に自身が行いました。官兵衛は、「決断はあくまでトップの仕事である」ということを認識しており、家臣の意見は尊重するものの、決断は自身が行い、決断に対する責任も自身が負う覚悟をしていました。
さまざまな意見を受け入れる柔軟性、そして決断の責任に対する上司の自覚が部下を大きく育てるのです。
4 上杉鷹山に学ぶ「自らが部下の手本となる」術
1)上杉鷹山のエピソード
上杉鷹山(うえすぎようざん。本名は上杉治憲(うえすぎはるのり))は、出羽国米沢(現山形県米沢市)の大名です。
上杉謙信(うえすぎけんしん)の活躍で有名な上杉家は、秀吉の時代には陸奥国会津(現福島県会津地方)を中心とする石高120万石を治める大大名でしたが、後に徳川家康(とくがわいえやす)と敵対して米沢藩に移され、その後、石高を15万石にまで減らされてしまいます。しかも大藩であった頃とほぼ同じ数の家臣を養っていたため、膨大な借金を抱えてしまいます。
こうした中、九州の高鍋藩(現宮崎県)から養子として米沢藩に迎えられた鷹山は、藩の財政を改革するべく自身の食事を質素なものとし、年間行事の中止や贈答の禁止を行うなど倹約に努めました。また自ら鍬(くわ)を取り、家臣にも田畑の開墾に当たらせました。鷹山は、自身が率先して取り組むことで、藩全体に改革の精神を広げようとしたのです。
しかし、保守的な家臣たちの反対や飢饉(ききん)による損害などにより改革は頓挫し、鷹山は藩主の座を退くことを余儀なくされました。その後も、米沢藩の財政は悪化の一途をたどり家臣が農民から不正に多くの年貢を徴収する、厳しい生活に耐えられなくなった農民が他国へ逃げ出すといった問題が起きました。
こうした状況を憂慮した鷹山は、隠居の身でありながら再び改革に着手することを決意します。そして、かつて性急に改革を進めようとして挫折した経緯を省みて、まずは家臣に藩の財政状況を公開し、危機を実感させることに努めました。
その後、武士だけでなく、農民や町人からも財政再建に関する意見を広く求め、集まった意見について検討を重ねた結果、産業の振興に力を入れるべく、藩全体で養蚕による生糸の生産に取り組むことを決定しました。さらに、藩内で以前から栽培されていた紅花で生糸を染めて織物を織り、藩外に販売することを考案しました。
これらの織物は「米沢織」と呼ばれ、米沢藩の名産品となって家臣の暮らしを支えることとなります。その後、米沢藩の財政は徐々に回復に向かい、鷹山の逝去後には、ついに借金のほとんどを返済することができたといいます。鷹山の現実を直視し、打開策を探り、自ら率先実行する姿勢が、家臣や領民を引き付けた結果といえるでしょう。
2)部下のやる気を引き出す術、気持ちを引き付ける術
厳しい状況に陥った藩の財政を立て直すに当たり、鷹山は、藩主の地位にありながら、自身が率先して質素な暮らしを心掛けました。家臣や領民に苦しい倹約を依頼するに当たり、まず自身が模範になろうとしたのです。
かつては120万石という大藩であった上杉家の家臣の中には、九州の小藩から養子に入った若い鷹山が進める改革を不満に思う者も少なくありませんでした。
こうした反発の中、鷹山は懸命に改革の必要性を説き、先頭に立って厳しい改革に取り組みました。このような鷹山の姿勢を目にし、当初は改革に協力的でなかった家臣の一部も次第に心を開き、その結果、藩の家臣や領民たち全員が一丸となって再建に取り組むようになりました。後に、鷹山は「してみせて、いってきかせて、させてみる」という言葉を残しています。
何かに取り組む際には、まず自身が身をもって部下に示し、指導した後に実際に挑戦させてみるという、上司の真摯かつ愛情に満ちた姿勢が、部下の心に火をともすといえるでしょう。
5 部下を1人の人間として尊重することの大切さ
戦国武将・偉人の家臣に対する姿勢にはいくつかの類型が見られます。しかし、そのいずれにも共通しているのは、「家臣を1人の人間として尊重していること」でしょう。
上司は、リーダーであると同時に、部下と同じ組織の一員でもあります。同じチームのメンバーとして、部下に対して真摯に向き合い、部下を導く姿勢こそが部下を大きく育て、強い組織づくりにつながるのです。
以上(2020年3月)
pj00259
画像:Gemini