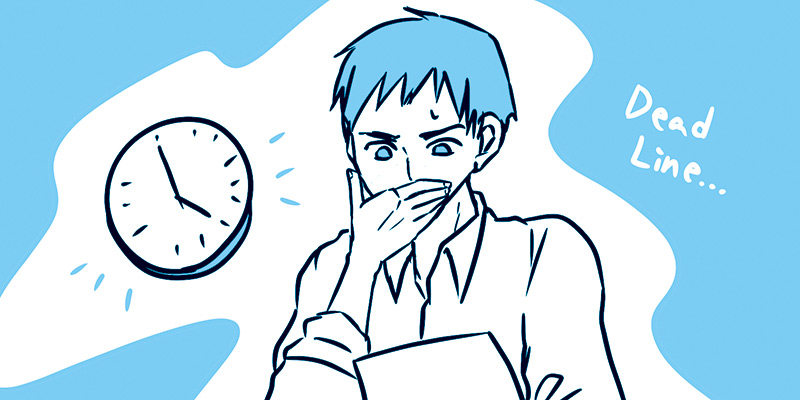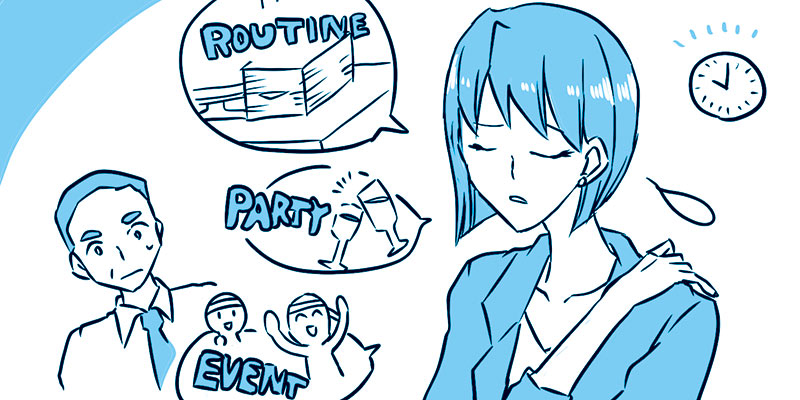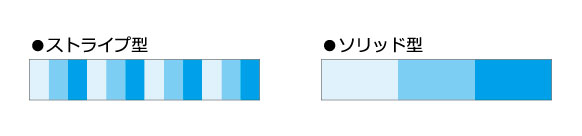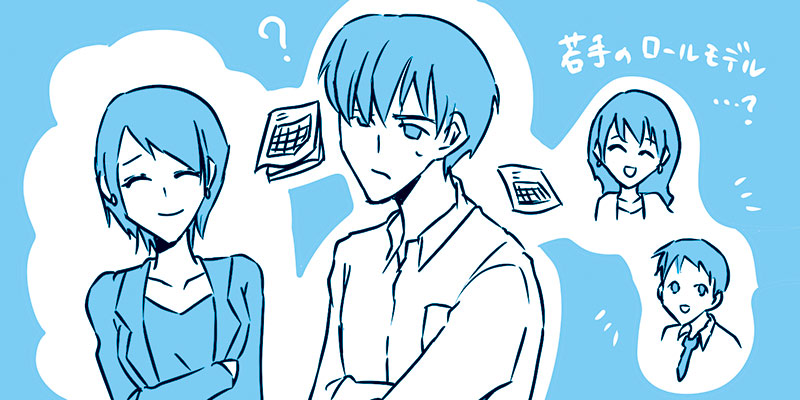メディア運営会社に勤める中堅社員のAさん。日ごろから情報収集に余念がなく、社内会議でも新しいアイデアを次々と発表し、「動画を取り入れたほうがよい、やっぱり今の時代はAI(人工知能)でしょう。いや、この際アプリ化を進めるべきではないか!」といった感じです。
アイデアを出すのはよいことですが、会社のリソースは限られています。いくらチャレンジするとはいえ、あれもこれもと手当たり次第というわけにはいきません。また、会社には事業ドメインやブランドがあります。思い付きに振り回されて事業ドメインを逸脱したり、ブランドを損なったりすることはできません。
今日の会議でも活発に発言するAさんですが、相変わらず意見が散らかり気味です。見かねた課長が指摘しました。
「Aさん、いろいろと考えるのはよいけれど、本当に重要なのはどのアイデアなの? またそのアイデアはなぜ重要なの?」
コーラとコーヒーの落とし穴
会社が成長するには新たなチャレンジが必要です。異分野に取り組むのはリスクが高いので、既存の商品やサービスに関連する分野でチャレンジするのが1つのセオリーです。
ただし、こうした考え方がリアルのビジネスで常に通用するわけではありません。例えば、皆さんは「コーラなどの炭酸飲料(以下「炭酸飲料」)とコーヒーを一緒に売る」という戦略をどう評価しますか?
清涼飲料の代表格である炭酸飲料とコーヒーを一緒に売れば、収益の拡大が期待できるかもしれません。実際、清涼飲料メーカーは炭酸飲料もコーヒーも取り扱っています。
しかし、事業戦略の視点で考えると、炭酸飲料とコーヒーを一緒に売ることに問題があるケースもあります。
- 中堅社員の皆さん、これがなぜだか分かりますか?
炭酸飲料とコーヒーは似て非なるもの
炭酸飲料とコーヒーは類似商品と思われがちですが、少し考えると想定される消費者や購入シーンが大きく異なることに気付きます。好みはありますが、一般的には炭酸飲料はスカッとしたいとき、コーヒーはホッとしたいときに飲むことが多いでしょう。
もし、会社が「炭酸飲料にかける!」という状況なら、安易にコーヒーに手を出すべきではありません。「炭酸飲料で勝負する」場合の戦略と、「炭酸飲料に加えてコーヒーも販売する」場合の戦略とでは、リソースの配分などが大きく異なります。それに、同時に2つのことに取り組むと、PDCAも2分の1以下しか回すことができなくなります。その結果、「どうなれば成功なんだっけ?」という、非常に根本的なところさえも曖昧になり、撤退の判断も鈍ってしまいます。
例えば、「炭酸飲料は好調。コーヒーは伸び悩んでいるが、足元では伸びつつある」といった場合にありがちなのは、「炭酸飲料とコーヒーを合算すれば利益が出ているし、コーヒーをもうちょっと頑張ってみようよ」という発想です。出発点は炭酸飲料で、その収益をもっと拡大するチャンスがあるのに、着手したコーヒーに愛着が湧いてきて撤退できず、機会損失が大きくなってしまうのです。
ビジネスは行動しなければ始まらないので、「取りあえずやってみる!」というのは悪くありません。しかし、思い付きに近い状態で着手してよいのは、「今すぐに低コストでできて、撤退も簡単なもの」だけです。
思い付きをビジネスプランに変える!
以上のことを踏まえた上で、中堅社員は次の“飯のタネ”を見つけなければなりません。最近は、フラットで多様性のある組織運営を目指す会社が増えています。そうした会社では、社員のアイデアに真摯に耳を傾ける雰囲気があります。
中堅社員はビジネスの仕組みが少しずつ分かってきて、新しいことにチャレンジしてみたくなる時期であり、活躍の機会が広がるでしょう。ただし、せっかくのアイデアも、「これからはAIしかない。わが社もやろう!」といった軽率なアウトプットに終わるのは残念です。このまま上司に相談したら、「もっと考えてから発言しないとダメじゃないか!」と一蹴されて終わりでしょう。
最初は思い付きのアイデアでもよいですが、ビジネスプランに落とし込む際は、少なくとも「AIを選ぶ理由、短期・中期の収益、既存事業やブランドとの関係、リソース確保と実現の可能性」は明確にしなければなりません。
アイデアを精査する目が養われていないといけないということであり、これを養うためには、常にいろいろな人と会って話す、書籍を読むなどして、ビジネスアイデアを模索することが大切です。
中小企業は一点突破?
リソースが限られた中小企業は、「これだ!」と決めた事業で一点突破を図ることが少なくありません。どんなときでも、会社が最初に着手するのは、最も効果的と思われるたった1つのアイデアです。中堅社員は、それを慎重に見極めるようにします。
ただし、大事なことなのでもう一度触れますが、「今すぐに低コストでできて、撤退も簡単なもの」は、すぐに着手してみるべきでしょう。将来大きく成長するかもしれませんし、新たな知見が得られる可能性もあるからです。
また、素晴らしいアイデアでも、小さな声で自信なさげに伝えられたら、「よし、やってみよう!」という気にはなれません。中堅社員は、自分のアイデアを魅力的に伝えるために「Show and Tell」の訓練をしましょう。「Show and Tell」とは、資料などを見せながら、論理的かつ情熱的に伝える手法で、最近は教育の現場でも注目されています。積極的にピッチイベントや交流会などに参加して、会社や自分のことなどを相手に伝える経験を積むとよいでしょう。
Point
- 「アイデア出し」は積極的に行う!
- 同時に、思い付きレベルを脱し、何が最も効果的であるかを検討できるビジネス力を養う。
以上(2019年8月)
pj00431
画像:Eriko Nonaka