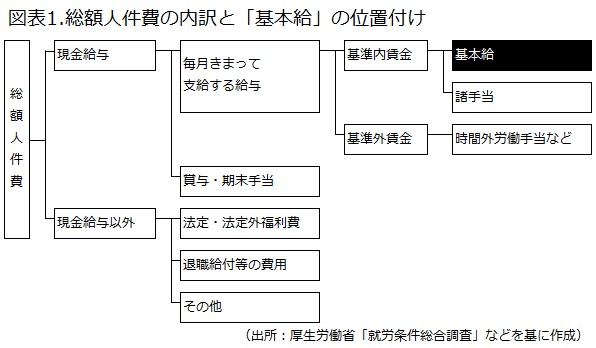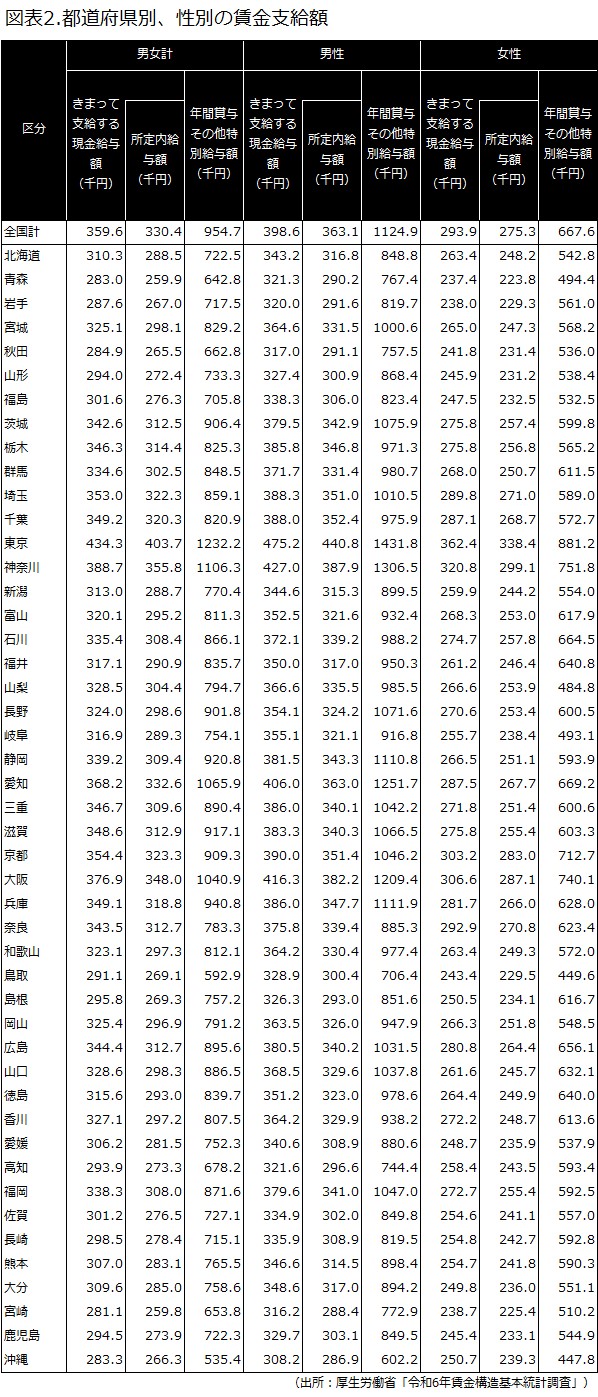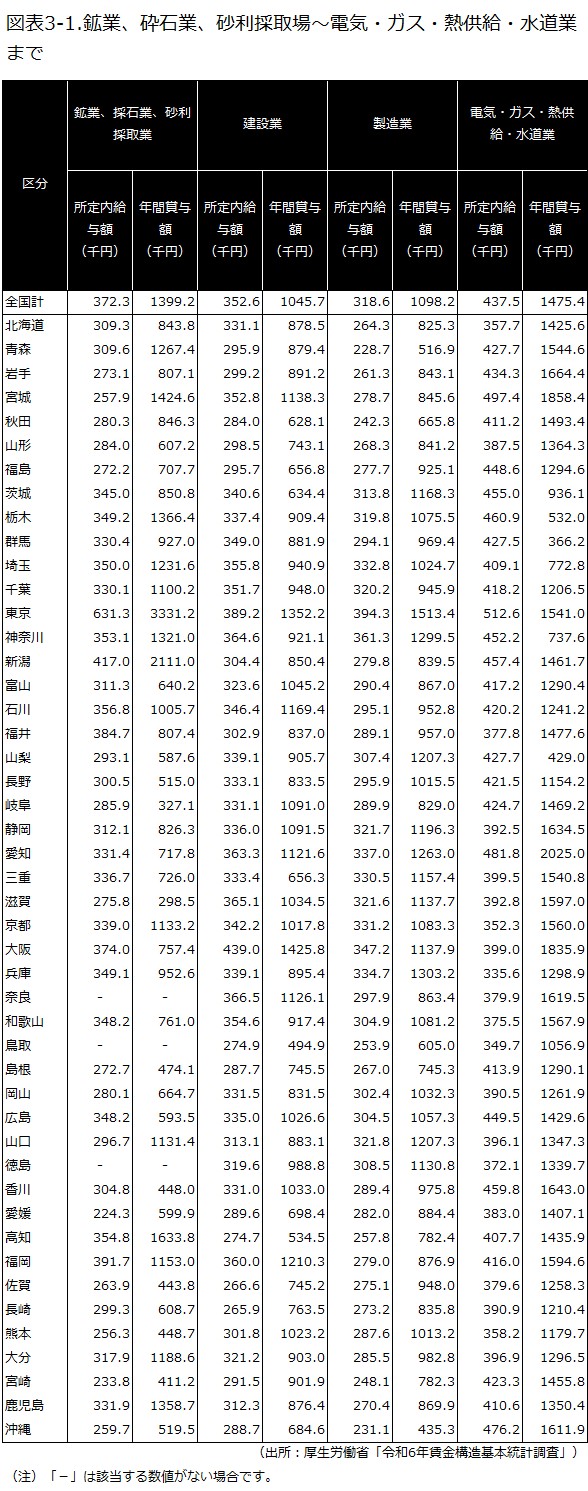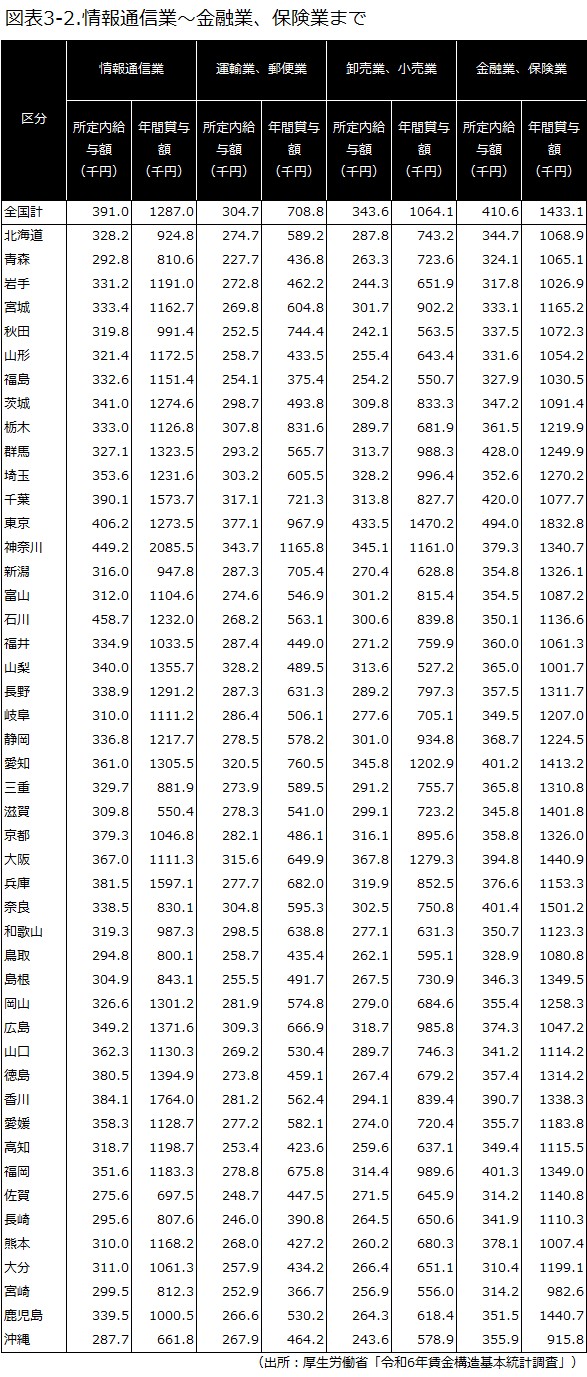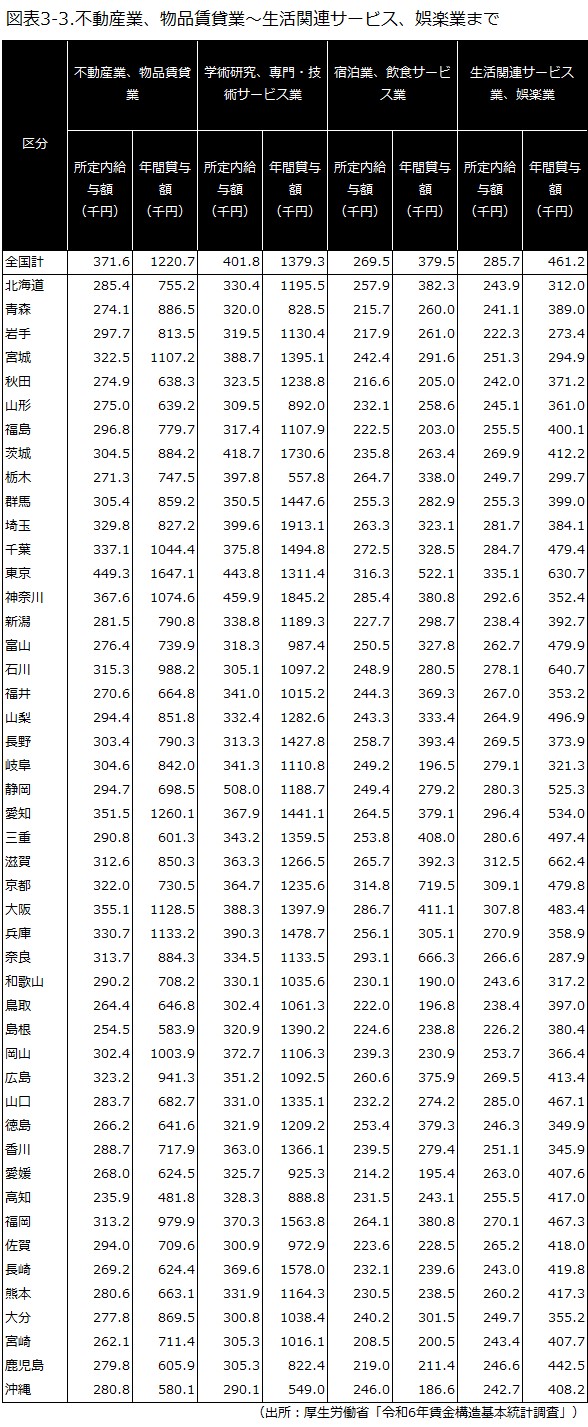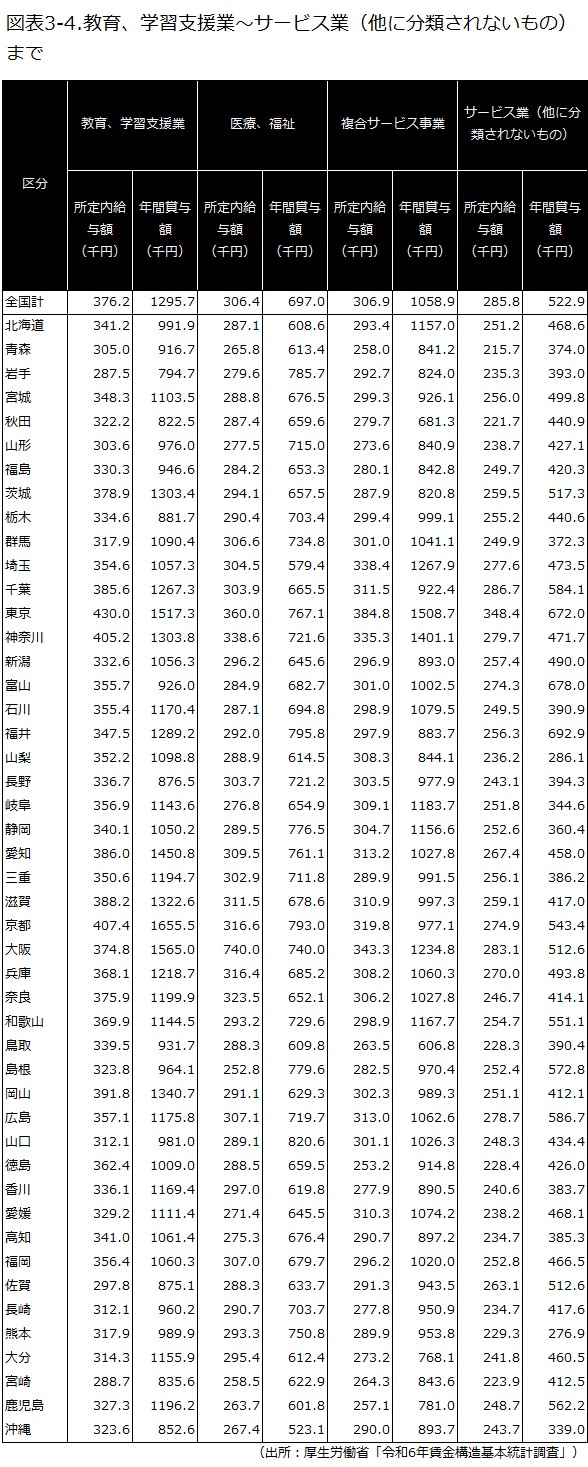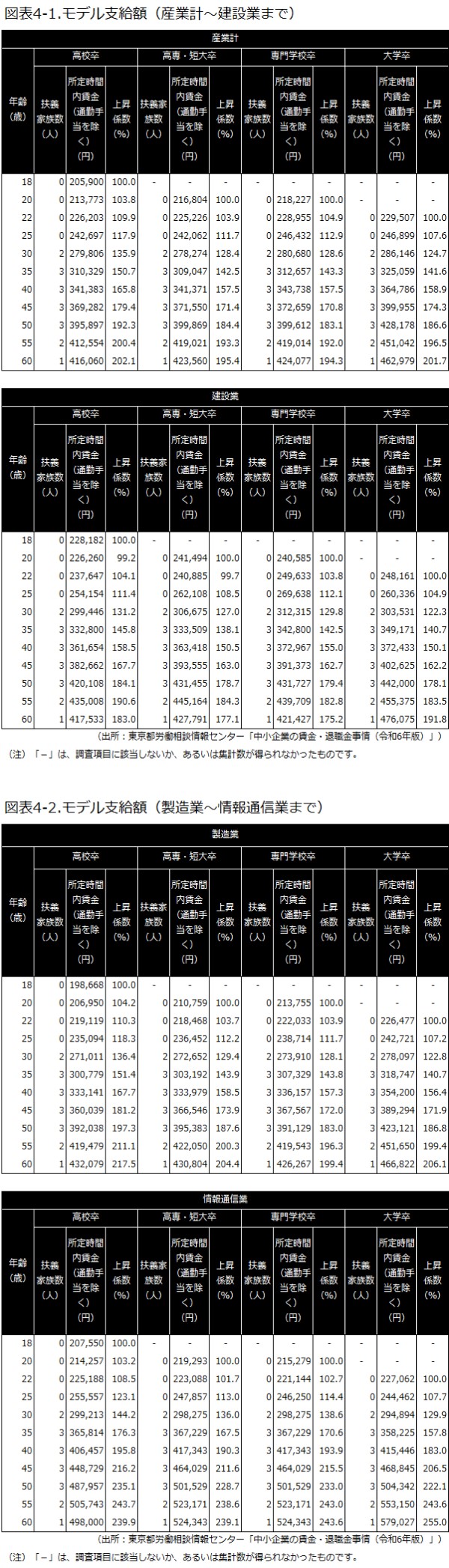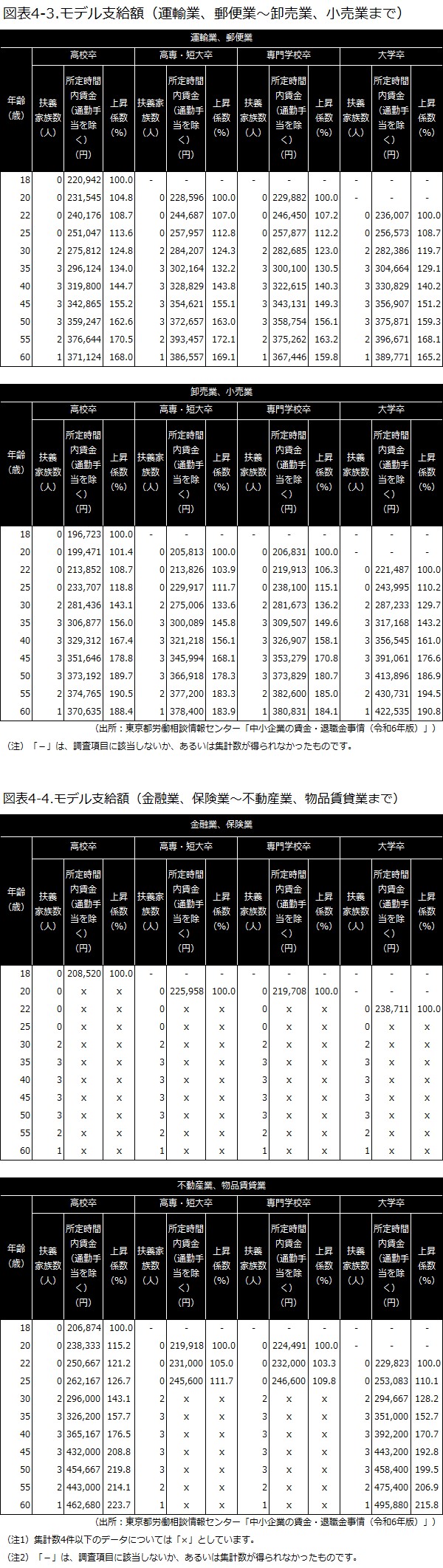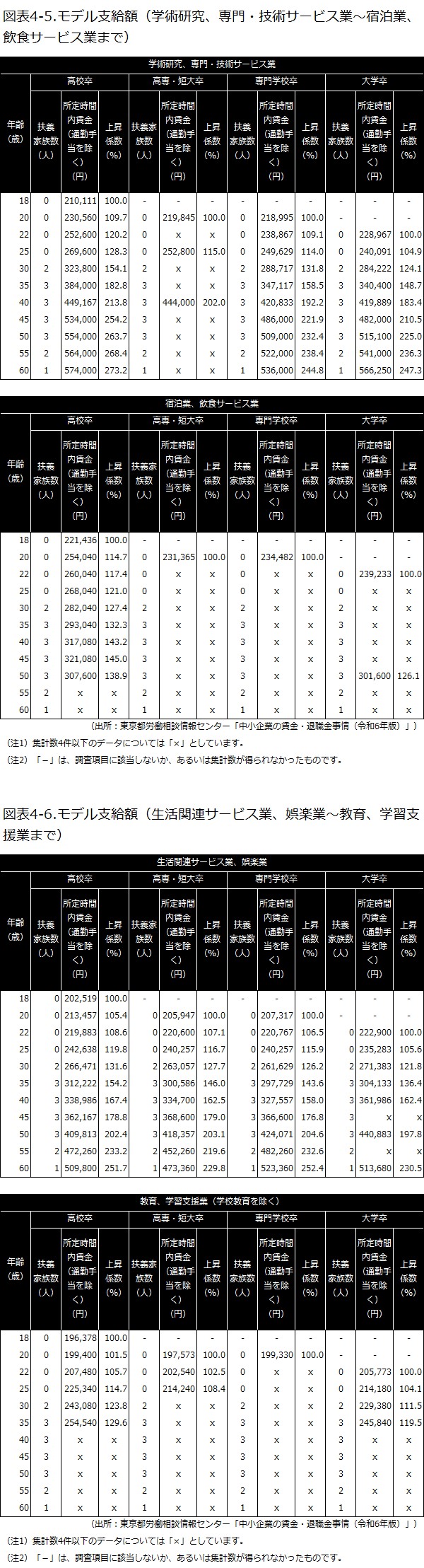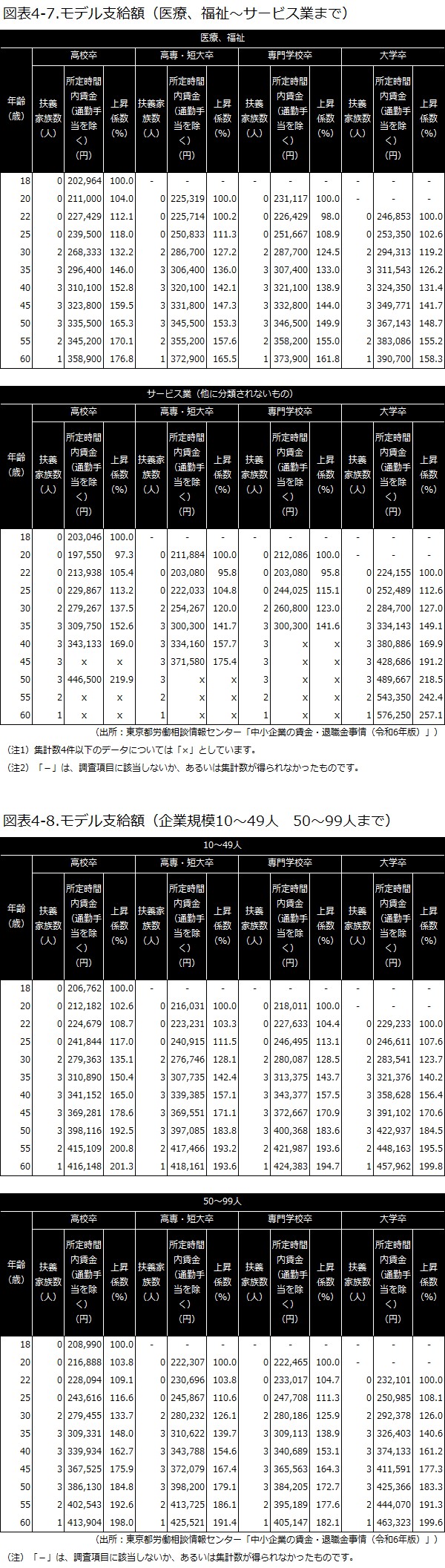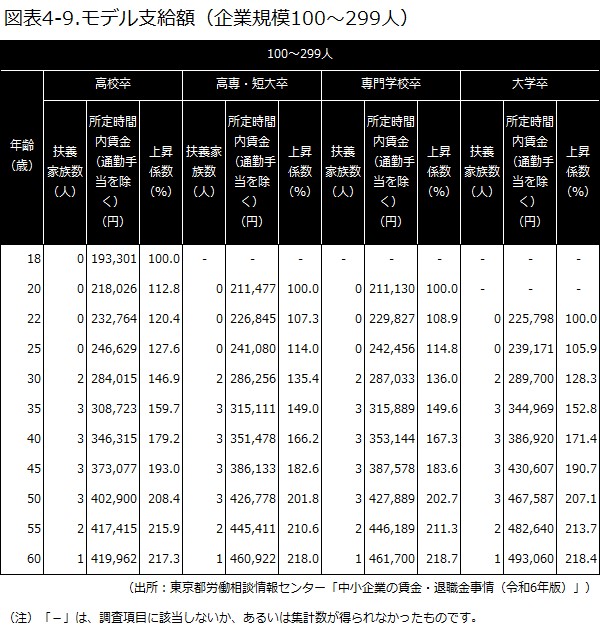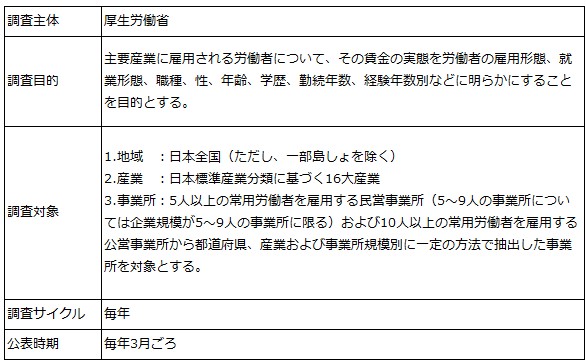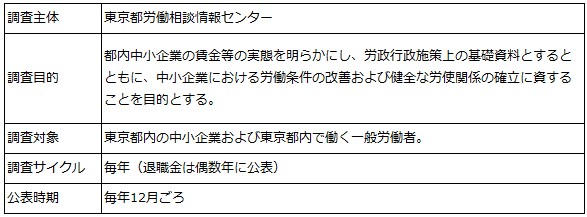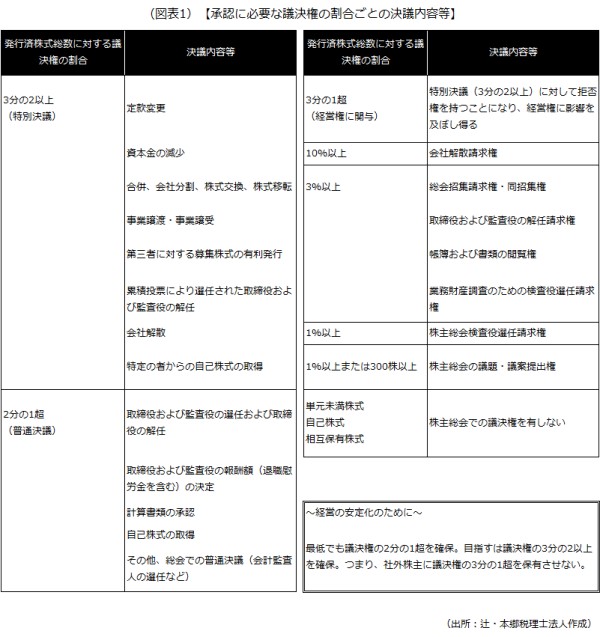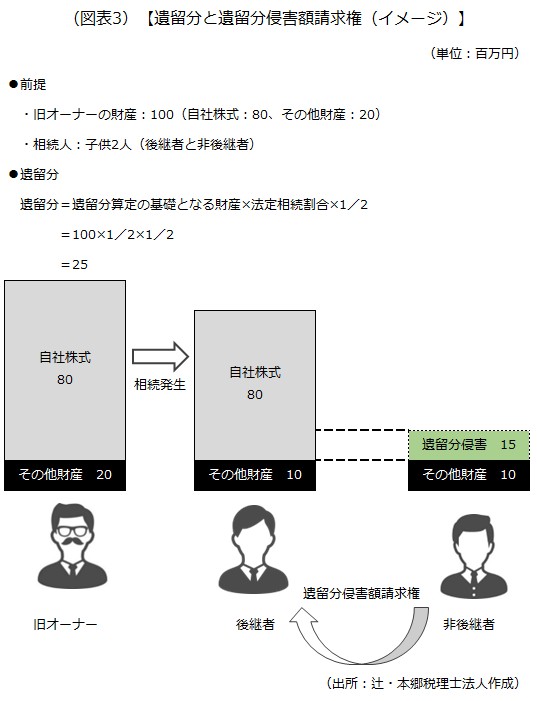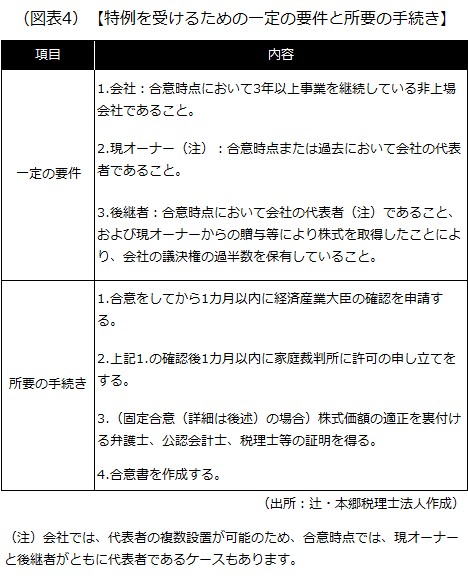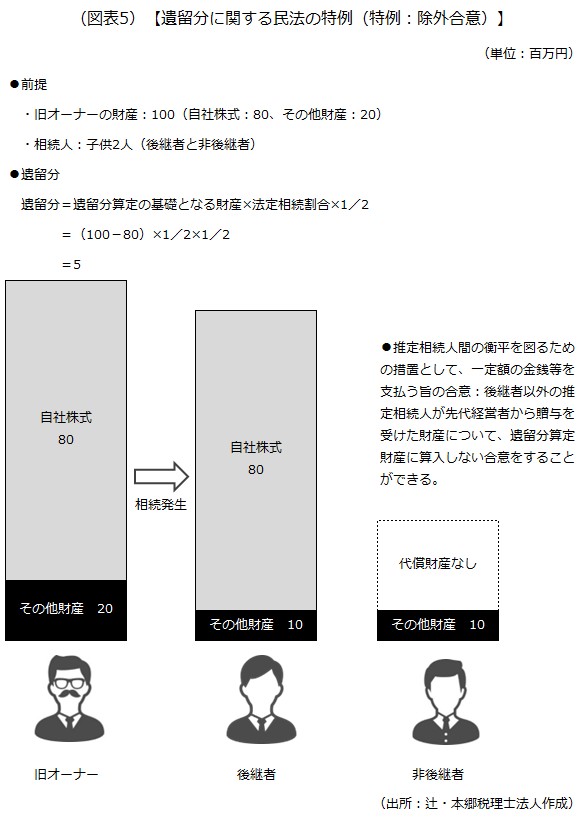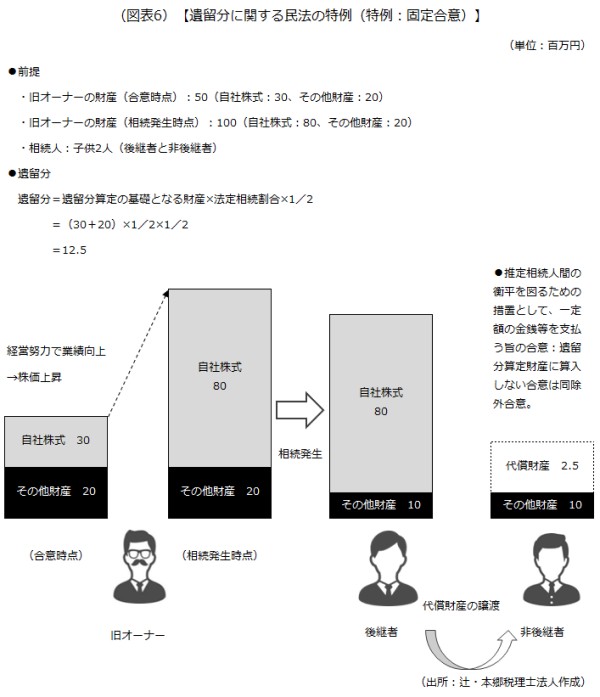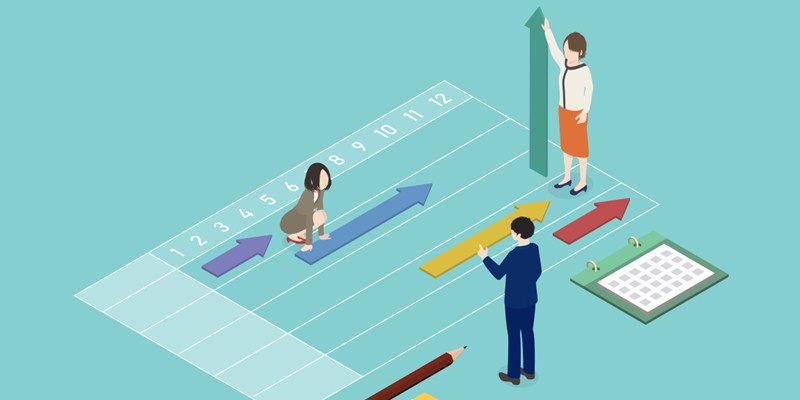1 社員本人の労働問題に、親が介入してくる?
社員本人の労働条件や処遇について、その社員の親が本人に代わり、会社に苦情を申し立ててくることがあるのをご存じでしょうか? 例えば、社員の配属先や人事評価に対する不満を会社にぶつけてきたり、社内の人間関係に口を出してきたりといった具合です。
社員本人の労働問題に介入してくる親を、この記事では「会社版モンスターペアレント」
と呼ぶことにします。
一般的に、モンスターペアレントとは、学校に対して理不尽な要求を繰り返す親を指す言葉です。少子化が進み、親が昔よりも子どもに対して過干渉になったことなどが原因といわれますが、子どもが社会人になった後もその過干渉が続き、会社版モンスターペアレントになってしまうケースがあるのです。ハラスメントに対する規制などが強化され、かつてより社員の権利が主張されやすくなったことも、こうした状況に拍車をかけているといえるでしょう。
会社版モンスターペアレントは、相手方が社員の親ということで、会社としても強く出にくい面がありますが、押さえておきたいポイントは、
労働契約は会社と社員本人との間で成立するものであるため、親は、当該労働契約に関しては第三者に他ならず、原則として労働条件に介入することはできない
ということです。社員の親の話を真摯に聞くのは大切ですが、親が何を言ってきたとしても、最終的には「会社と社員本人の問題」であるということを念頭において対応しましょう。
この記事では、会社版モンスターペアレントの具体的なケースとその対応例を3つ紹介します。
2 (事例1)残業について苦情を言ってくる親
1)ケース
新入社員のAさんは、入社して半年間が経過し、業務にも慣れてきました。Aさんの上司(課長)も頼もしく思っていましたが、あるとき、Aさんの親から、
「うちの息子のAが毎日遅くまで残業していると聞きました。同期の子は残業がないと言っているのに、Aばかり残業させるのはおかしいです!」
と電話がかかってきました。会社はどのように対応すべきでしょうか?
2)対応例
前述した通り、
労働契約は会社と社員本人との間で成立するものであるため、親は、当該労働契約に関しては第三者に他ならず、原則として労働条件に介入することはできません。
つまり、この事例の場合、Aさんの労働条件について、会社が当事者ではないAさんの親と交渉する必要はありません。ただし、
Aさん本人が会社に直接言い出せない不満や不安を、親が代弁している可能性は考慮
する必要があります。親のクレームをただ門前払いするだけでなく、Aさん本人との対話を通じて、根本的な問題(Aさん自身の不満、会社への不信感、コミュニケーション不足など)を特定し、解決に努める必要があります。具体的には次のステップで進めることが考えられます。
1.親への対応
会社としては、
「Aさんの労働条件については、Aさんご本人と会社の間の労働契約に関する事項ですので、Aさんご本人からの申し出でなければ、詳細なご説明は致しかねます。一般的に、労働時間や残業は、業務の必要性に応じて発生するもので、部署や担当業務、進行度合いによって異なります。同期の方と全く同じ時間になることはありません」
などと、労働契約の当事者がAさん本人である旨、本人からの申し出でなければ詳細な説明をすることができない旨をAさんの親に伝えます。
2.Aさん本人への対応
親からの連絡があったことをAさん本人に伝え、Aさん自身の残業に対する認識や不満等を直接ヒアリングします。Aさん自身が残業について不満を持っている場合、その内容を真摯に聞き、適切な労働時間管理が行われているか、課長からAさんに対する業務の配分が正当といえるものかを確認します。労働時間管理や業務の配分に問題がないと判断した場合、業務の必要性に応じた残業命令は会社の業務命令権の範囲内であり、不当ではないことをAさんに説明します。また、労働時間や残業に関する規定が就業規則等に明記されていることを、必要に応じてAさんに説明します。もちろん、労働時間管理や業務の配分に問題があると判断した場合は、速やかに是正する必要があります。
3.親からクレームが繰り返される場合の対応
親から会社に対し頻繁に電話があり、会社の業務に支障をきたす場合は、迷惑行為である旨を伝えます。それでも繰り返される場合は、弁護士に相談し、法的措置を検討します。
3 (事例2)給与や評価に関する不満を言ってくる親
1)ケース
新入社員Bさんの給与や評価について、Bさんの親が、
「うちのBは毎日遅くまで頑張っているのに、給料が同期より低いと聞きました。評価も納得がいかないと。正当な評価をして、もっと給料を上げるべきです!」
と、会社に苦情を申し立ててきました。会社はどのように対応すべきでしょうか?
2)対応例
給与や評価は会社の経営判断と人事裁量に属する事項ですので、まずは、労働契約の当事者であるBさん本人と会社の問題であることをBさんの親に伝えます。もっとも、Bさん本人が会社に直接言い出せない不満や不安を、Bさんの親が代弁している可能性も考慮する必要があります。具体的には次のステップで対応します。
1.親への対応
会社としては、
「一般的に、給与や評価については、当社の評価制度に基づき、業務実績や貢献度を総合的に判断して決定しております。Bさんの個別の評価内容については、Bさんご本人と会社の間の労働契約に関する事項ですので、Bさんご本人以外にはお伝えできません。Bさんご本人には、評価面談を通じてご説明しておりますので、ご不明な点があればご本人から改めてご相談いただくようお伝えください」
などと、Bさんの給与や評価に関する情報は開示できない旨をBさんの親に伝えます。
2.Bさん本人への対応
親からの連絡があったことをBさんに伝え、Bさん自身の給与や評価に対する認識・不満等を直接ヒアリングします。その上で、会社の評価制度や賃金決定の仕組みについて、Bさんに丁寧に説明し、疑問点を解消する機会を設けます。親からの給与や評価に関する苦情は、多くの場合、社員自身が会社の評価基準や自身の評価理由を十分に理解していないことが原因です。
3.給与・評価制度に問題がある場合の対応
会社の人事評価制度や賃金規定の内容が不明確な場合、不公平感が生じやすいです。社内でも、制度や規定の内容を確認し、不明確な部分があると判断した場合、改訂を検討します。また、仮にBさんが「同期と比べて不公平」と感じている場合、それが性別、年齢、雇用形態などによる不当な差別(例:賃金における男女差別)に該当しないかを確認し、該当する可能性がある場合、速やかに是正する必要があります。Bさんの業務実績や貢献度に見合わない評価や給与であると会社が判断する場合、評価の見直しや今後の成長に向けた具体的なフィードバック、目標設定など、改善策を検討し、Bさん本人に説明します。
4 (事例3)異動に関する要求をしてくる親
1)ケース
新入社員Cさんの親が、Cさんの体調不良や業務への不満を理由に、異動について、
「うちのCは今の部署での仕事が合わないようです。精神的に参ってしまっているので、すぐに部署を異動させてください! それが無理なら、もう辞めさせます!」
と、苦情を申し立ててきました。会社はどのように対応すべきでしょうか?
2)対応例
異動命令は会社の業務命令権に基づき行われるものであり、また、会社を退職するか否かは社員本人が決定する事項です。まずは、これらの事項は、労働契約の当事者であるCさん本人と会社の問題であることを伝えます。もっとも、事例1と2と同様に、Cさん本人が会社に直接言い出せない不満や不安を、Cさんの親が代弁している可能性も考慮する必要があります。具体的には次のステップで対応します。
1.親への対応
会社としては、
「異動については、Cさんご本人の意思を加味しながら、会社の人事権に基づき判断しております。また、退職についても、Cさんご本人からの正式な申し出が必要です。いずれにしましても、Cさんご本人と会社の間の労働契約に関する事項ですので、Cさんご本人と直接面談して対応を検討させていただきます」
などと、異動や退職は、親がCさんに代わって要求できるものではないことを伝えます。
2.Cさん本人への対応
親からの連絡があったことをCさん本人に伝え、Cさん自身の異動や退職についての意向を直接ヒアリングします。会社は、業務上の必要性やCさんの心身の状態・業務状況・家庭事情等を考慮して、異動を検討します。会社が異動の必要がないと判断した場合、その旨を、理由と併せてCさんに伝えます。その際に、Cさん自身が退職を希望した場合、法律(民法や労働法など)や社内規程に則り、適切な手続き(退職届の提出、退職日の調整など)を進めます。なお、Cさんに退職を促す場合(退職勧奨する場合)、強要とみなされないよう慎重に行う必要があります。不適切な退職勧奨は、不法行為として損害賠償の対象となる可能性がありますので、留意が必要です
(監修 のぞみ総合法律事務所 弁護士 曽田駿希)
pj00783
画像:友紀 寺崎-Adobe Stock