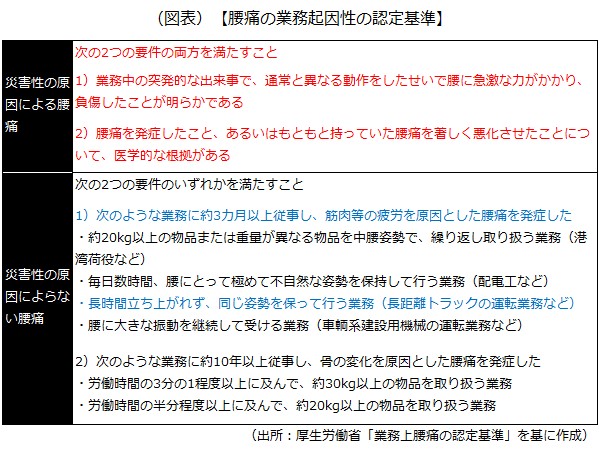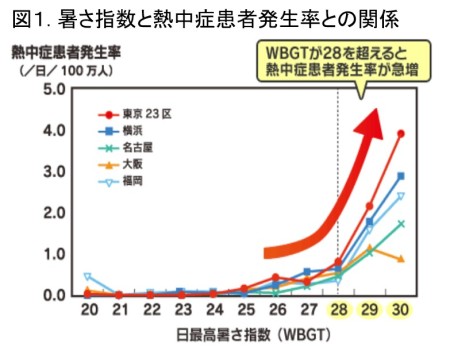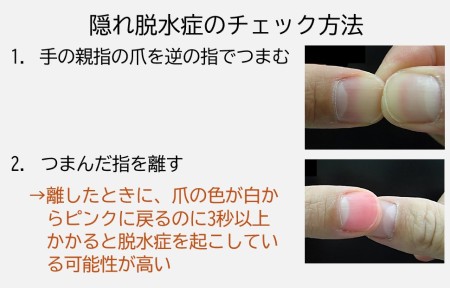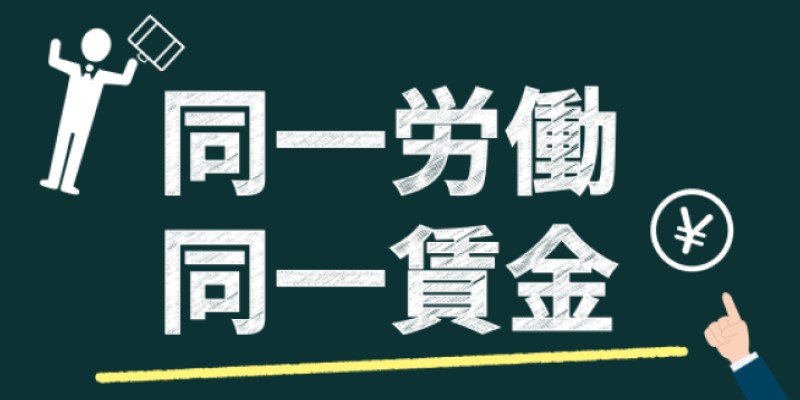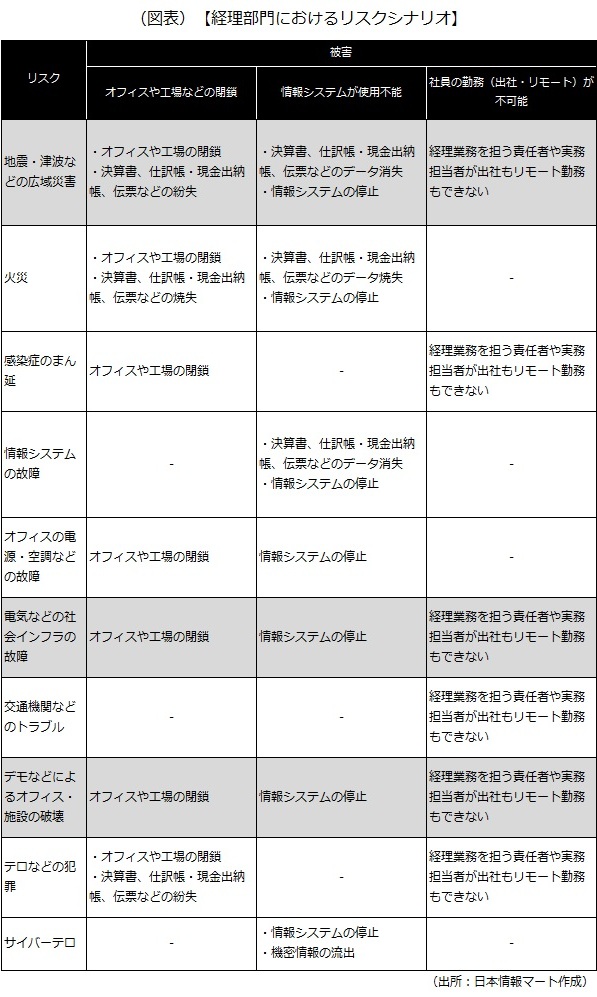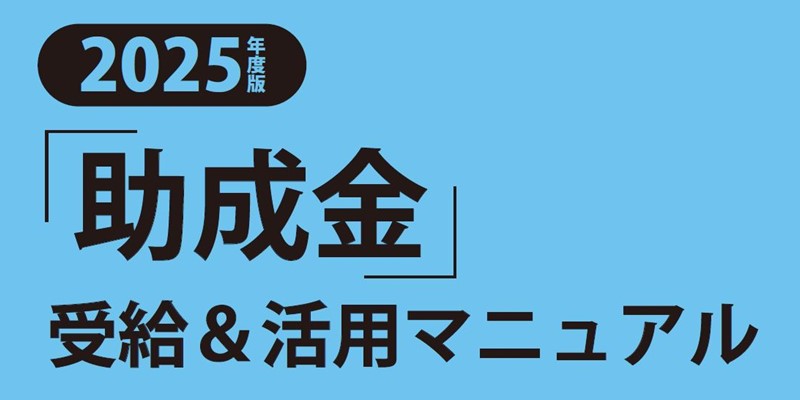1 改めて防災を考える
日本では、地震に限らず、様々な災害が発生します。万一の際、社員の安全や自社の資産を守るための拠り所となるのが防災管理規程です。もし、防災管理規程をまだ作成していないようであれば、これを機に検討してみましょう。防災対策に関する情報をまとめた行政機関のウェブサイトもあります。参考にしてください。
■内閣府「企業防災のページ(内閣府防災担当)」■
https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/
■東京都防災ホームページ「防災ブック」■
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1028036/
2 防災管理規程のひな型
以下で紹介するひな型は一般的な事項をまとめたものであり、個々の企業によって定めるべき内容は異なります。規程を作成する際は、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
【防災管理規程のひな型】
第1条(目的)
本規程は防災管理の徹底を期し、災害における人的・物的被害を最小限にとどめるために必要な事項について定める。なお、本規程でいう災害とは、火災、地震、暴風雨、洪水などに起因する災害をいい、労働災害、交通事故、テロ、ミサイル、感染症は除く。
第2条(適用範囲)
本規程は、消防法などの関連法令に基づき全社に適用する。
第3条(防災管理体制)
会社は、防災管理の推進・維持のため、次に定める管理者および会議体を置く。
- 全社防災対策本部長
- 地域防災対策責任者
- 防火管理者
- 火元責任者
- 防災対策本部
- 防災対策委員会
- 自衛消防隊
第4条(全社防災対策本部長の任命および職務)
1)全社防災対策本部長は、本社に置くものとし、総務部長がその任に当たる。
2)全社防災対策本部長は、全社的な防災対策の統括をするものとする。
第5条(地域防災対策責任者の任命および職務)
1)地域防災対策責任者は、拠点ごとに置くものとし、労働安全衛生法に基づいて選任した総括安全衛生管理者とする。ただし、総括安全衛生管理者を置かない拠点においては、労働安全衛生法に基づいて選任した安全管理者などの中から会社が個別に指名する。
2)地域防災対策責任者は、拠点における防災対策の統括をする。また、災害に際しては臨機応変な処置を講じるとともに、速やかに全社防災対策本部長に状況を報告しなければならない。
第6条(防火管理者の任命および職務)
1)防火管理者は、拠点ごとに置くものとし、法的資格者の中から全社防災対策本部長が任命する。また、防火管理者を置かない場合は、地域防災対策責任者が防火管理者の職務に準じて防火管理事項を実施・推進するものとする。
2)防火管理者は火災の予防および災害の防止を図るため、次の職務を誠実に行うものとする。
- 消防計画の作成および変更
- 建物、火気使用設備器具、危険物施設などの検査および危機管理
- 避難通路および避難設備などの維持管理
- 消防用設備などの点検および整備
- 火気の使用または取り扱いに関する監督
- 収容人員の管理
- 消火、通報および避難などの訓練の実施
- 従業員などに対する防災意識の啓発
- 火災およびその他の災害に対応できる体制、対策の維持管理
- その他、防災管理上必要な業務
3)防火管理者は前項の職務を遂行するに当たり、必要に応じて第7条に定める火元責任者および建物・諸設備などの点検を行う者(以下「設備点検員」)を任命するものとし、消防管理上必要な命令および指示をしなければならない。
第7条(火元責任者の任命および職務)
1)火元責任者は、各部門の責任者もしくはそれに準ずる従業員の中から防火管理者が任命する。
2)火元責任者は、防火管理者の命令および指示に従い、防火措置の実施、確認、その他の責任を負うものとする。
第8条(防災対策本部および活動)
会社は、重大な災害が発生した場合、本社に防災対策本部を置き、対策を決定する。また、必要に応じて、防災対策本部の決定した対策を講じるための全権を委嘱した役員を被災地に派遣する。
第9条(防災対策委員会)
1)防災対策委員会は、拠点ごとに置く。
2)防災対策委員会の委員長は、地域防災対策責任者とする。
3)防災対策委員会は、防火管理者、火元責任者、設備点検員、拠点内の各部門から任命された1名以上で構成する。
4)防災対策委員会は、原則として2カ月に1度開催する。
第10条(防災対策委員会の活動)
防災対策委員会は、主として次の事項に関する審議を行い、必要な事項を実施・推進する。
- 消防計画の立案
- 防災に関する諸規程の立案
- 防火対象物の防火構造および避難施設並びに消防用設備などの維持管理
- 消防設備の改善強化
- 消火・通報および避難訓練などの立案
- 防災意識の啓発
- 防災予防上必要な教育および消防・避難訓練の計画並びに実施
- 火災の際の隣接防火対象物の応援協定
- その他防災に関する必要事項
第11条(自衛消防隊)
1)自衛消防隊は、拠点ごとに置くものとし、火災のみならずその他の災害発生時に、人的・物的被害を最小限にとどめるための活動を行う。
2)自衛消防隊の隊長は、地域防災対策責任者とする。
3)自衛消防隊の隊長補佐は、防火管理者とする。
4)自衛消防隊には、隊長および隊長補佐の下に次の班を置く。
- 通報連絡班
- 初期消火班
- 避難誘導班
- 応急救護班
- 安全防護班
5)第4項に定める各班には、班長を置く。班長は各部門の責任者、もしくはそれに準ずる従業員の中から地域防災対策責任者が任命する。また、各班の班員は地域防災対策責任者が任命する。班員数については拠点の規模などを勘案の上、防災対策委員会が決定する。
第12条(自衛消防隊の活動)
自衛消防隊は、火災やその他の災害が発生した場合に、所有する組織力や装備を有効に活用して、人的・物的被害を最小限にとどめることを目的に、次の活動を実施する。
- 消防機関への通報
- 初期消火活動
- 人命の救助
- 関係者以外の者の立ち入り禁止処置
- 消防活動の障害となる物件の排除
- 従業員の避難誘導
- 必要な資器材の調達
- その他、人的・物的被害を最小限にとどめることに資する活動
第13条(消防計画)
防火対象物全般にわたる消防計画は防火管理者が企画・立案し、防災対策委員会で決定する。なお、消防計画については消防法など法令の定めるところによる。
第14条(防火点検)
建築物・火気・電気・危険物などにおける各施設の自主点検は、火元責任者が週1回実施し、点検結果は記録して、必要な整備事項があれば地域防災対策責任者に報告し処置するものとする。
第15条(設備管理)
1)消防用諸設備および用水については、火元責任者が管理状況を確認するものとし、防火管理者は巡回点検を定期的に行い、実施状況を監督しなければならない。
2)電気設備、警報設備、避難設備など、専門的な点検を要するものは、防火管理者が点検依頼先を指定し、社内外の専門技術者の点検を受けるとともに、点検結果を記録しなければならない。
第16条(防災訓練)
1)防災対策委員会は防火管理者が中心となり、防災訓練と防災教育の講習会を年1回開催する。
2)従業員は防災訓練並びに防災教育の講習会に参加しなければならない。
第17条(火災予防)
1)社内における指定場所以外の喫煙は厳禁とし、社内外における工事や大量の危険物取り扱いの際の喫煙場所は、事前に防火管理者の承認を受けなければならない。
2)臨時に火気を使用する場合、防火管理者並びに火元責任者の許可を得なければならない。
第18条(災害防御)
災害防御のため、該当者は次の項目に努めるものとする。
- 通報連絡
- 消火活動
- 避難誘導
災害(特に火災)発生において発見者は、所轄の消防署へ通報するとともに、地域防災対策責任者などの関係者もしくはそれに準ずる者に連絡する。連絡を受けた者は、社内放送または口頭連絡により、災害発生を知らせる。
自衛消防隊は、社内放送および連絡に基づき、直ちに消火活動に当たる。
自衛消防隊の誘導により行う。
第19条(安否確認)
従業員は各自、自身と家族の安全措置を講じた後、速やかに所属拠点へ安否情報を報告する。
第20条(災害復旧)
1)地域防災対策責任者は、事業を速やかに回復させるため、次の項目に努めるものとする。
- 勤務環境の整備
- 土地、施設および設備の復旧
- 備品などの調達および修繕
- その他、災害復旧に必要な事項
2)地域防災対策責任者は、応援要員、復旧資材、宿泊施設、食料、復旧日程などの計画を策定し、全社防災対策本部長に報告する。
3)地域防災対策責任者は、復旧計画の実施に当たって、自治体、防災関係機関などと密接な連絡を取りながら復旧を行う。
第21条(罰則)
役員および従業員が故意または重大な過失により、本規程に違反した場合、就業規則に照らして処分を決定する。
第22条(改廃)
本規程の改廃は、取締役会の承認による。
附則
本規程は、○年○月○日より実施する。
以上(2025年7月更新)
pj60033
画像:ESB Professional-shutterstock