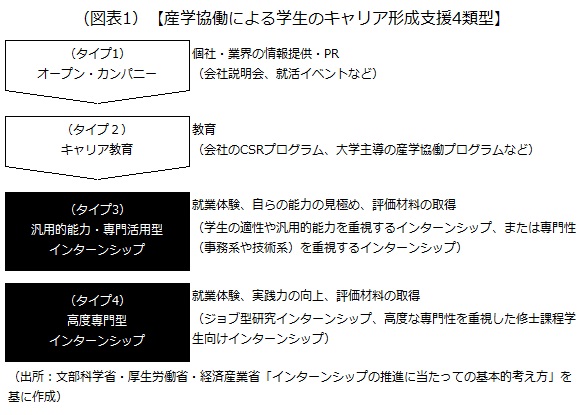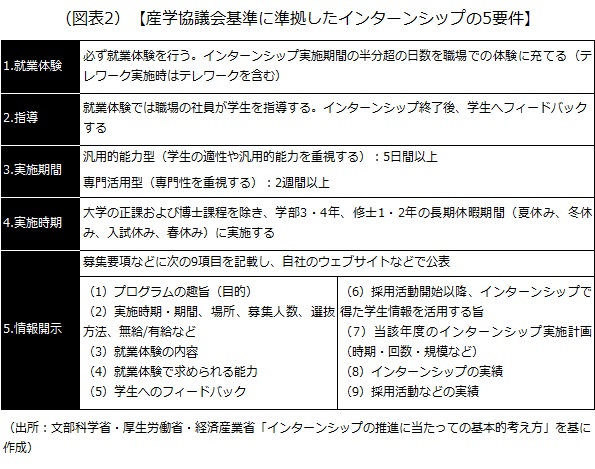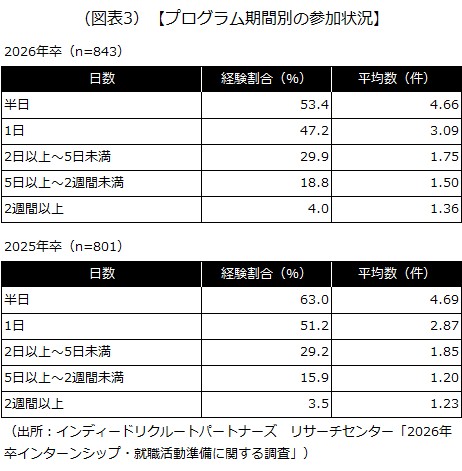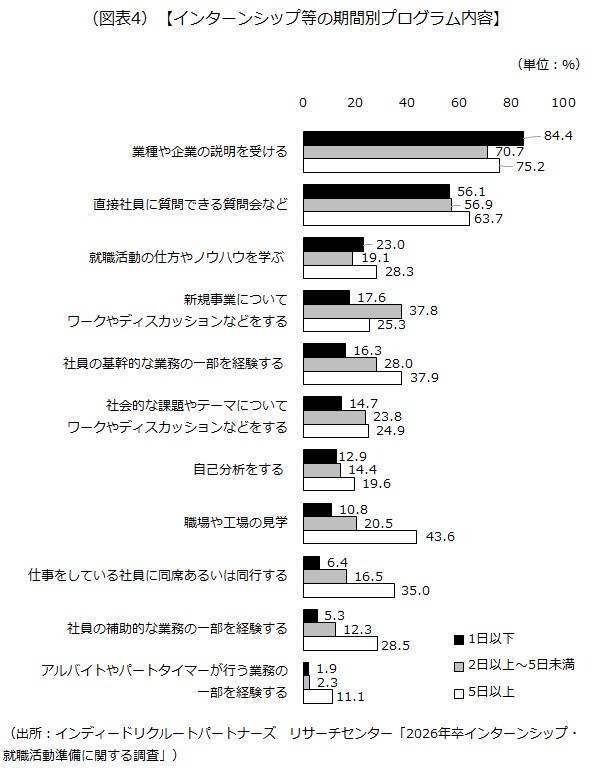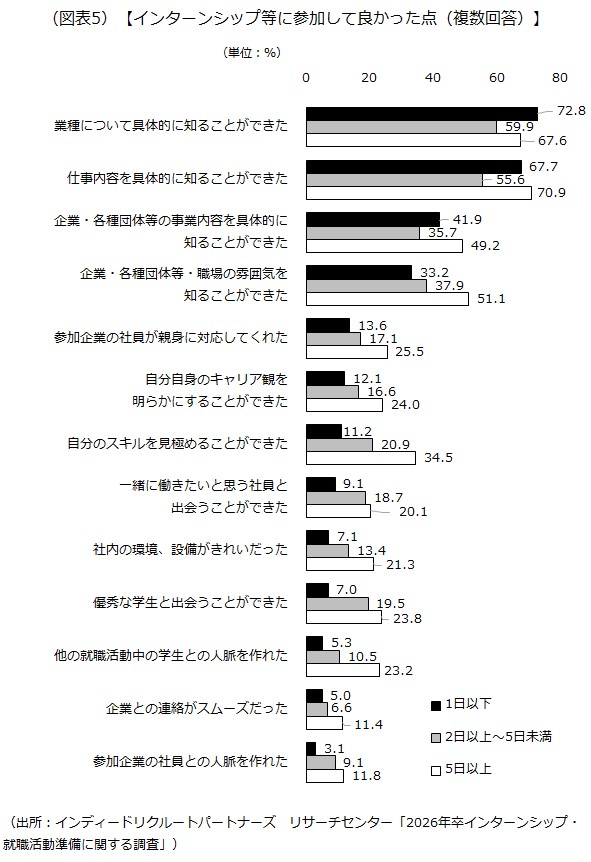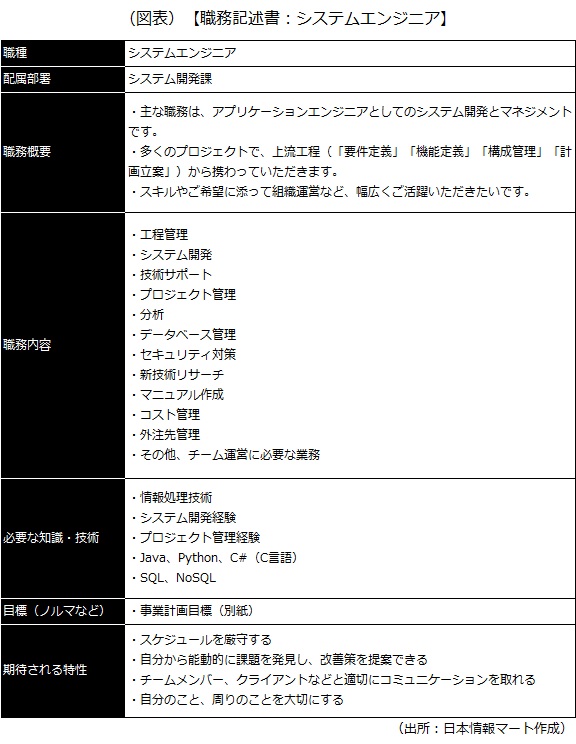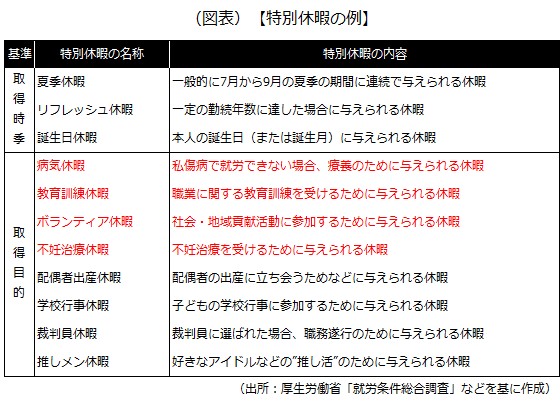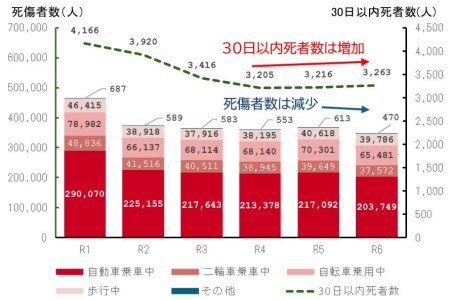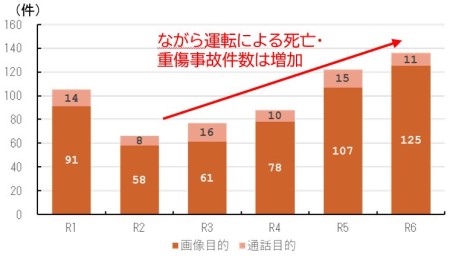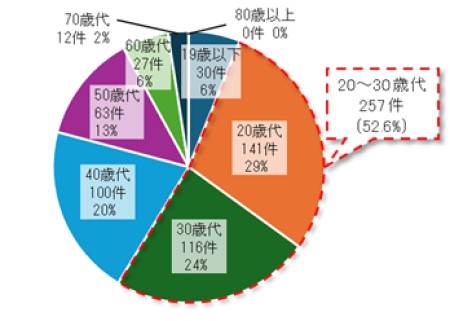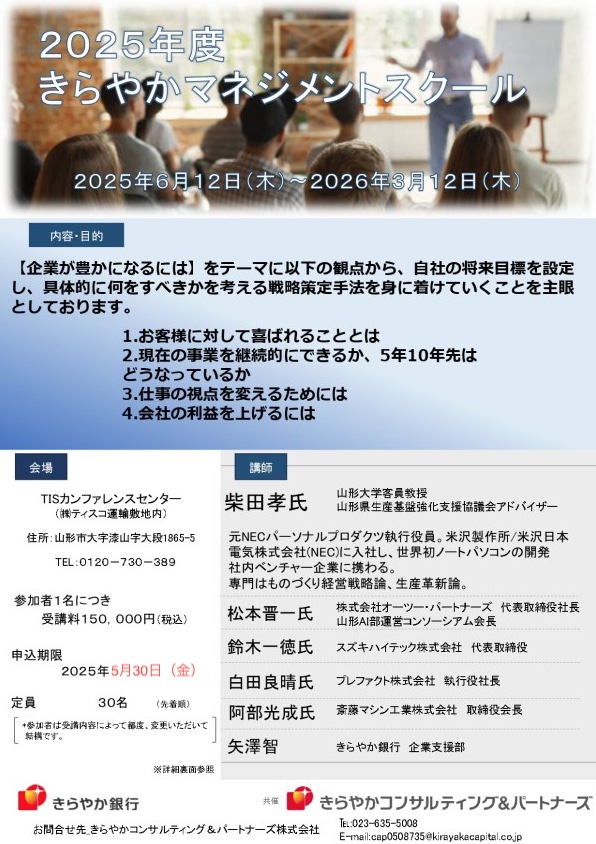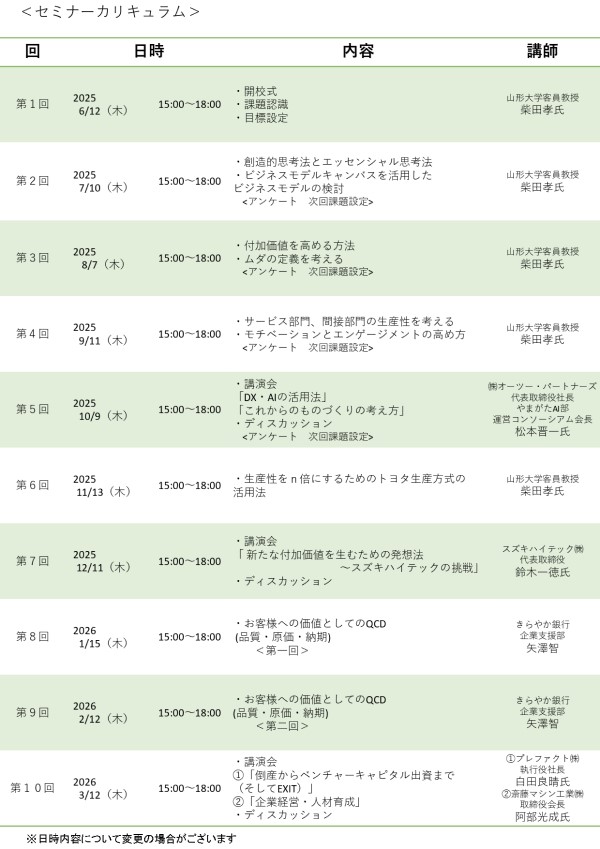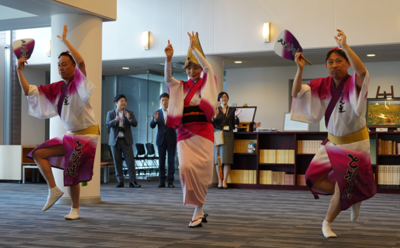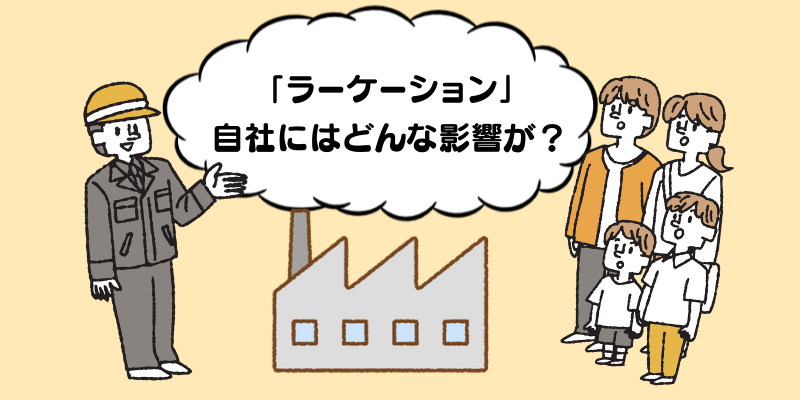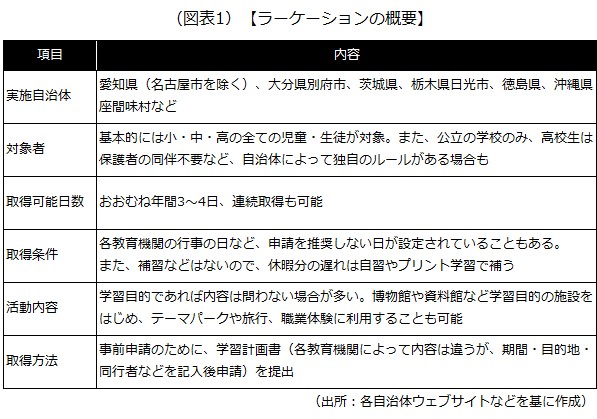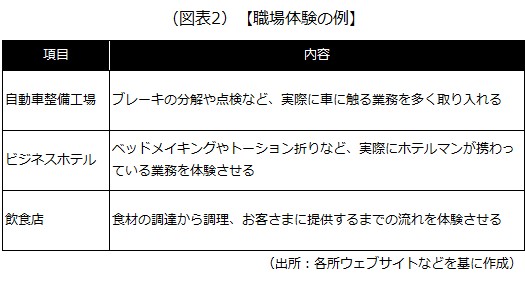書いてあること
- 主な読者:会社経営者・役員、管理職、一般社員の皆さん
- 課題:コミュニケーションに関わる知識やノウハウは、頭では理解できても、実際の場面で使いこなせるようになるまでには高いハードルがあるものです。
- 解決策:前回シリーズ『次世代リーダーに必須のコミュニケーション習慣』での知識やノウハウを聞いただけではまだ一歩を踏み出せない、あるいはトライしてみたがうまくいかないという方のために、新シリーズでは【実践編】として社内の“あるある”場面を想定した質問に対して一緒に考えながら、実践イメージを膨らませていただきます。またリーダー側の視点とは別に、若手社員側の視点による上司世代との上手な付き合い方のヒントも紹介していきます。リーダー世代と若手社員とのコミュニケーションギャップを埋めることは、世界を舞台にスピーディな成長をめざす日本企業にとっても喫緊の課題だからです。
1 若手部下Jさんが部署の業務に「タイパ悪くないですか?」、どう声をかけますか?
今シリーズは、前シリーズ『次世代リーダーに必須のコミュニケーション習慣』の実践編としてお送りしています。毎回実際にありそうなさまざまなシチュエーションを想定して、その際にどんなコミュニケーションを取るのが望ましいかを一緒に考えていきます。
前回第10回のテーマは「モチベーションの育て方」でした。部署の目標達成の締め切り日が迫る中、目標未達のメンバーの1人から突然新しい企画の提案をされた際のコミュニケーションのあり方について、上司、部下、それぞれの立場から考えてみました。
今回は最後の課題[事例10]です。以下に再掲しますので、前回皆さんが考えてみた解答を思い出してみてください。まだ考えていなかった方もぜひ考えてみてください。自ら考えないで、解説だけを読んでいても身に付きませんよ。
—————————
Q.若手部下のJさんに対して、あなたはこの後、最初にどんな声をかけますか? また、それを考える際に注意するべきポイントを3つほど挙げてください。書かれているさまざまな要素を考慮してみましょう。
[事例10]
〇若手部下のJさんは、配属から間もないこともあって、部署全体の業務の流れはもとより、自身の業務にさえ精通できていません。そんなある日、Jさんは上司のあなたに「この業務ってタイパ悪くないですか?」と問いかけてきました。
〇そればかりか「先に先輩に話してみたんですが、“つべこべ言わずに自分の仕事を早く覚えろ”と怒られました。納得いかないです」と不満そうです。
—————————
テーマは「仕事の任せ方」です。「タイパ」はご存じかと思いますが、「タイムパフォーマンス」のことです。起こっている事象を整理することから始め、現場で起こっていることの可能性を探ってみましょう。皆さんの職場でも似たようなケースはありませんか。
2 「思い込み」や「偏見」は互いの距離を遠くする
昭和世代の読者の皆さんの中に、「タイパ」と聞くと「今どきの若い連中は、二言目にはタイパ、タイパだ」と目くじらを立てている人はいませんか。
今の時代、仕事をする上で「タイパ」への意識は常に必要です。
「タイパ」とはすなわち「生産性」のこと。同じ付加価値をどれだけ短い時間で生み出せるか、あるいは同じ時間でどれだけ多くの付加価値を生み出せるかを問うています。そして日本企業の「生産性」は先進国の中でもかなり低いほうだといわれ続けています。
「働き方改革」も「タイパ」が目指す施策の1つです。社内の人材を活かし、結果として生産性と付加価値を高めていく。残業が当たり前の世界をなくし、健康な生活を維持しながら、“いかに短時間で高い成果を上げられるか”が求められているのです。
また「今どきの若い連中は」という偏見は、いつの時代にもあること。生きてきた時代や背景、常識が違う以上、世代間ギャップは生まれて当然なのです。頭ごなしに「今どきの若い連中は」と考えるのではなく、自分たちが若い頃も年配者の言葉が理解できなかったことを思い出してください。
かくいう私も心の中で「今どきの若い連中は」と全く思わないわけではありません。が、「いかんいかん、またやってる」と凝り固まりがちな思考を自戒し、「世代間のギャップなんていつの時代にもあるものだ」と思い直すようにしています。
放っておけば、組織内の世代間ギャップはますます広がり、組織としての力は落ちていくばかりです。
一呼吸おいて、「世代間ギャップなどあって当たり前」と考え、人生経験が豊富で包容力のある先輩のほうから歩み寄っていきましょう。
先ほど、“今の時代、仕事をする上で「タイパ」への意識は常に必要です”と言いましたが、全てを「タイパ」で考えてくださいと言っているのではありません。
例えば「部下からの相談や悩みを聞く」場合や「チームでキックオフミーティングや達成会を行う」場合などは、それ自体が直接付加価値を生むわけではありません。「タイパ」を意識するならば、かける時間は短ければ短いほどいいのでしょうか。
他人である上司と部下、メンバー同士が互いに分かり合うにはそれなりの時間がかかります。
一人ひとりが仕事に集中できるようにサポートし合い、協力し合って高いパフォーマンス(付加価値)を上げるには、それぞれに必要な時間があるでしょう。組織としての付加価値をより高めていきたいのであれば、そこをないがしろにしてはいけません。
今の時代の上司には、常に「タイパ」を意識しつつも、時間をかけるべきところと効率良く進めるべきところをうまく使い分けてマネジメントすることが求められています。
3 若手社員や新参社員の話の「傾聴」をお薦めする3つの理由
「今どきの若い連中は」という負の感情が首をもたげても、一呼吸おいて、世代間ギャップはあって当たり前と考え、先輩のほうから歩み寄ろうと思い直せたとしましょう。さて、次にどんな行動を取ればいいでしょうか。
皆さんに考えていただく課題も今回が最後です。「この業務ってタイパ悪くないですか?」と問いかけてきた若手部下Jさんに対して取るべき行動について、毎回読んでくださった皆さんならもうお気付きですね。そう、「傾聴」してみる、です。
シリーズでそう書いてあるからとか、若手社員のモチベーションのために必要と言われたからしょうがないなどと後ろ向きに考えないでください。
若手社員や、異動・中途入社で加わった新参社員の声を「傾聴」することは、あなたの組織に3つのメリットをもたらす可能性があります。
メリット【1】組織には常に新たな視点が必要
組織というものは、つくった瞬間から保守的になりがちです。複数の人間が集まって一緒に仕事をするには共通のルールが必要で、それを定めて動き始めます。けれども外部環境の変化によってルールは次第に古くなり、陳腐化していきます。
昔からいる人ほど、そのことに気付きません。たとえ気付いていたとしても「いったん決めたんだし、慣れているからいいじゃないか」と、重い腰を下ろしたまま変えたがらないのです。これでは変化に対応できません。
そこに入ってきた若手社員や新参社員は、“よそ者”ならではの異なる視点を持っています。あなたの組織においては常識で当たり前だと思っていたことに対して、「皆さん(王様)、裸んぼうになってますよ」と気付かせてくれる存在なのです。
メリット【2】若手社員のほうが知識・経験がありうる時代
例えば、皆さんはご自身のスマホや人気のSNS、動画などをうまく使いこなせていますか?
私の場合、パソコンやパワーポイントなら若手社員に自信をもって使い方を教えられますが、スマホやSNSを使い倒せているかと問われれば自信がありません。動画を撮影し、編集ソフトを使ってアップしたことはありますが、自在に使いこなしているとまでは言えません。
デジタルやインターネットの急速な進化と普及は、昭和世代にとっては社会に出てから仕事の一部として体験してきたものです。いまだ人生や生活と一体化するまでに至っていないでしょう。
一方で、若手社員の多くは中学生、高校生の時代からそれらが生活の一部であり、違和感なく使いこなせるのです。“年を取っているほど経験が深い”という年功の価値観が全ての時代は終わりました。ことデジタルやネットの世界では完全に崩れているのです。
昭和世代は自らもキャッチアップするべく勉強を続けながらも、追いつけないのであれば若手社員に頭を下げて任せるか、彼らから学ぶしかないのです。
メリット【3】人材育成や組織変革のチャンス
【1】の冒頭で触れたように、組織はつくった瞬間から保守的になりがちです。既存のメンバーの誰かが見直すべき点に気付いたとしても言い出しづらいでしょう。上司から提案したとしても同じやり方でやってきた仲間ですから、「まあまあ、これまでのやり方でみんな慣れてますし」と却下されそうです。
一方で、配属されたばかりの若手社員や新参社員を迎え入れるのは非日常です。既存のメンバーも、少なくとも新しいものが来たという認識があります。そこで、上司が彼らから得た新たな視点をメンバーに提示し、後押ししたらどうでしょう。
新しいやり方への理解を組織全体で共有した上で、新参メンバーをその導入のためのリーダーに据え、既存メンバーのトップをサポート役に任命してみるのです。人材育成や組織変革の良いチャンスとなるかもしれません。
4 上司が最初にかけるべき言葉とは?
部下のJさんに最初にかける言葉は次のようなイメージです。
「お、提案ですか? いいですね、大歓迎ですよ。良い提案なら私からもみんなに後押ししますから、内容を聞かせてくれますか?」
部下からの提案は、相手が新人だろうと、その社員の現状の業績が振るわなかろうと、ウェルカムで臨みましょう。それでこそ彼らは上司を信頼し、何でも相談しやすくなります。
こちらが今多忙なら「いいですね、大歓迎です」と返した上で、別に時間を設ければ済む話です。
ちなみに「いいですね」は承認であり、「褒める」の一環です。
先ほど挙げた3つのメリットをイメージしながら、Jさんの提案を「傾聴」してみましょう。「傾聴」の結果については、いくつかのパターンが考えられます。
<すでに全く同じ提案があり、検討した結果不採用となっている場合>…過去の経緯を説明した上で、「とはいえその時はその時です。今ならまた違う結論になるかもしれないとすれば、どんな可能性があると思う?」と本人に問うてもう一度考えてもらいましょう。
<すでに似た提案があり、検討した結果不採用となっている場合>…過去の経緯を説明した上で、「その時と今回の提案の共通点と違う点はどこだと思う?」「違う点を前面に押し出して提案したら、何が変えられるだろう?」と本人に問うてもう一度考えてもらいましょう。
<過去にない新しい提案だが、組織で検討するまでもなくほぼ結論が見えている場合>…「なるほど、提案は新しいと思います。ありがとう。ただ、この点はこういう結果にならないかと想像したんだがどうだろう?」と本人に問うてもう一度考えてもらいましょう。
<過去にない新しい提案で、組織で検討する価値があると判断した場合>…「なるほど、いいですね。
先輩はそこまでの話を聞いて否定したのですか?」と確認し、いずれにしても「私も後押ししますから、次回のミーティングに向けて分かりやすい発表資料にまとめてくれますか?」と本人に依頼しましょう。
資料をもとに、事前打合せをしてミーティングに臨みます。
前者3つの場合は、Jさんにした質問の答えを聞く機会を改めて作って、本人と擦り合わせてみましょう。
あなたとしては、他のメンバーに提案しても不採用になるだろうと判断すれば、その旨を正直に伝えます。それでも本人がみんなに提案したいというなら、提案すること自体の後押しはしてあげたいところです。それにより「提案自体はどんどんしていいんだ」という「前向き発想」の機運が組織に広がります。
Jさんが今回その提案をすることで、次回以降の提案がしづらくなりそうだと判断すれば、あえて今回はさせないという選択肢もあります。Jさんにはこう説明してはどうでしょう。
「従来のやり方を変えたがらない人は多いものです。特に今まで部署にいなかった人からの提案には抵抗を感じるかもしれません。提案は最初が肝心です。誰もが変えざるを得ないなと思えるくらいの提案から先にしませんか。そうすれば他の提案も通りやすくなりますよ」
5 部下からの相談や提案を、誰もが“ウェルカム”できる風土に
ポイントを整理しましょう。
【今回の3つのポイント】
1 相手が誰であろうと例外なく「提案はウェルカムである」という姿勢を示し「褒め」た上で、提案の概要を聞かせてもらう
2 部下からの提案は、「新たな視点」「若手社員からの学び」「人材育成や組織変革のチャンス」であると認識する
3 忌憚(きたん)なくJさんと話し合った上で、他のメンバーへの提案のしかたを一緒に考える。提案をすることになれば、上司として「前向き発想」で後押しする
私がかつて勤めていたリクルートでは、上司はどんな相談や提案にも耳を貸してくれました。先輩たちもしかりです。
新人のうちは慣れないので、近くの先輩に聞けば分かる内容を上司に直接聞いていました。それでも上司は私からの相談や提案を、「どうした?」「なになに?」と本当にうれしそうに聞いてくれたのです。
上司は話を「傾聴」してくれた上で「〇〇については、まず自分で考えてからもう一度相談にきて」などと質問を返されることもしばしばです。それによって「まず自分で考えてみる」という訓練も身に付きました。
やがて上司の忙しさとともに、周囲の先輩たちが「まず上司でなく自分に相談して」とやきもきしながら見ていたことに気付きます。次第にこの話なら上司を煩わせるまでもなくこの先輩に、あの話ならあの先輩に相談すればいいと分かるようになってきます。
先輩たちも上司と同様、私の相談や提案をしっかりと受け止めて、的確な質問や答えを返してくれました。もっと良い相談相手がいると思えば、「そういう話だったら〇〇部の〇〇さんに相談すればいいよ。自分から連絡入れておくから」と言ってくれるのです。
「自分に相談されたのだから自分で解決して手柄にしよう」などとは考えないのです。「あくまで相談者優先、問題が早く解決するほうがいいじゃない」と最善の方法を一緒に考えてくれました。
また同社では、基本的に「誰が誰に相談・提案してもよい」という文化が根付いていました。新人が部長や役員にいきなり相談・提案をしにいっても誰も文句を言いません。直属の上司が「何やってるんだ、まずは自分に相談するのが筋だろう」などと怒ってきません。
部長や役員はというと、やはり私の上司や先輩たちと同じようにうれしそうに話を聞いてくれるのです。新人が直接相談に来たからといって、直属の上司を叱責することも一切ありません。本人が必要と思ったからその人に相談・提案に行ったまでと判断するのです。
そうした組織で人が育たないわけがありません。私自身は「できるだけ自分で考えてみよう。でも考えても分からなかったら、まず先輩に、必要と思えば上司や上席に直接相談すればいい」と、安心して仕事に取り組めました。
困ったときに相談できる人、自分の話を真剣に聞いてくれる人が周囲にたくさんいることは、どんなに心強いことでしょう。
6 周囲への相談、提案の前にまず自分で考えよう「自分はどうしたいのか?」
最後に、逆に皆さんがJさんの立場だとして、できることを考えてみましょう。
「この業務ってタイパ悪くないですか?」とただの感想を言うだけなら誰にでもできます。それでは何も変わりませんし、あなた自身も周囲から理解されません。あなたが本気で「現状を変えたい」なら、その思いを周囲に伝えられない限り、人は動いてくれません。
ただの感想でも職場の一員=当事者として述べる以上は、「では具体的にどうすればいいか」もセットにするべきでしょう。まだ仕事に慣れていなくて具体案が的外れだったとしても構いません。他人事ではなく、当事者意識をもって真剣に考えたことが重要なのです。
たとえ適切な具体策が思いつかなかったとしても、当事者の一人として真剣に考えたのであれば、あなたの「現状を変えたい」という気持ちだけはきっと周囲に伝わります。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。「傾聴」「褒める」「前向き発想」の『新たな3つのコミュニケーション習慣』について、皆さんの現場で実践していくイメージを持っていただけたでしょうか。
次回はシリーズ最終回です。全体を振り返り、【実践編】をまとめます。お楽しみに。
<ご質問を承ります>
ご質問や疑問点などあれば以下までメールください。※個別のお問合せもこちらまで
Mail to: brightinfo@brightside.co.jp
※武田が以前上梓した書籍『新スペシャリストになろう!』および『なぜ社長の話はわかりにくいのか』(いずれもPHP研究所)が、ディスカヴァー・トゥエンティワンより電子書籍として復刻出版されました。前者はキャリア選択でお悩みの方に、後者はリーダーやトップをめざしている方にお薦めです。
『新スペシャリストになろう!』https://amzn.asia/d/e8GZwTB
『なぜ社長の話はわかりにくいのか』https://amzn.asia/d/8YUKdlx
以上(2025年5月作成)
(著作 ブライトサイド株式会社 代表取締役社長 武田斉紀)
https://www.brightside.co.jp/
pj90272
画像:PureSolution-Adobe Stock