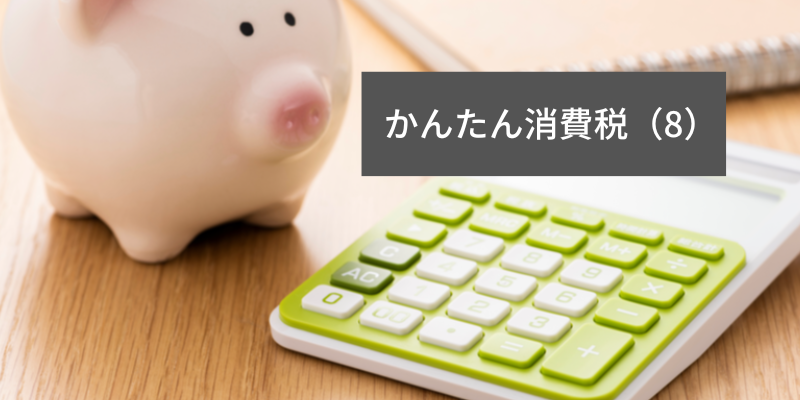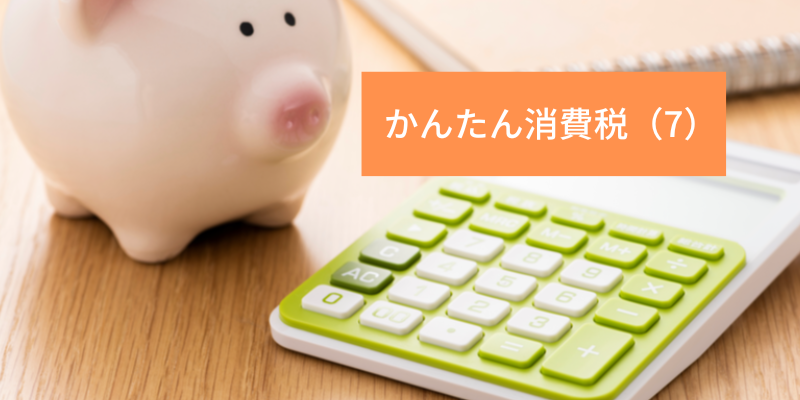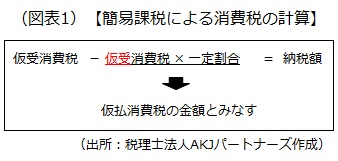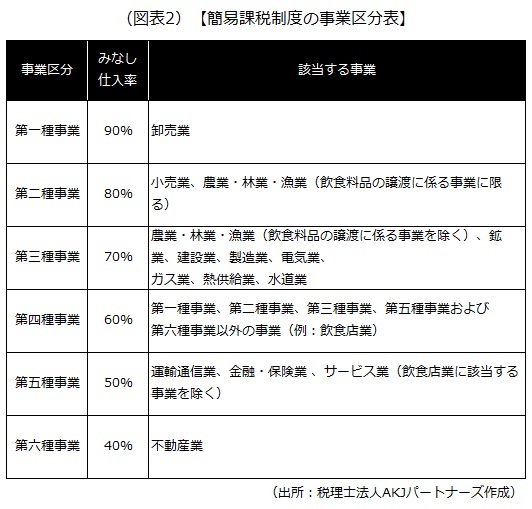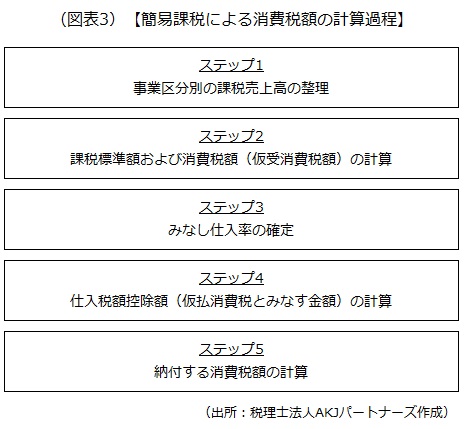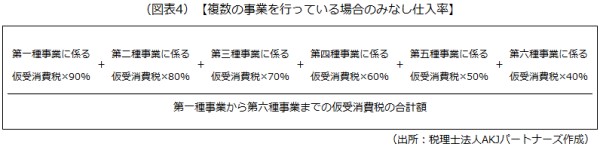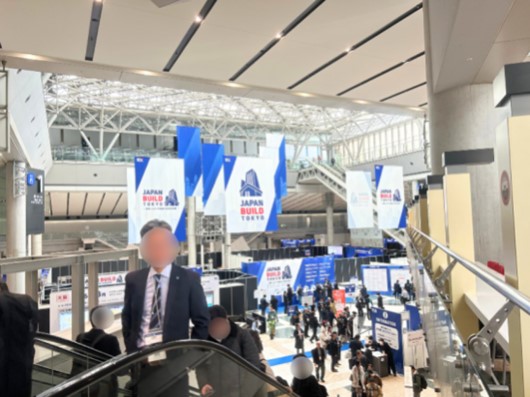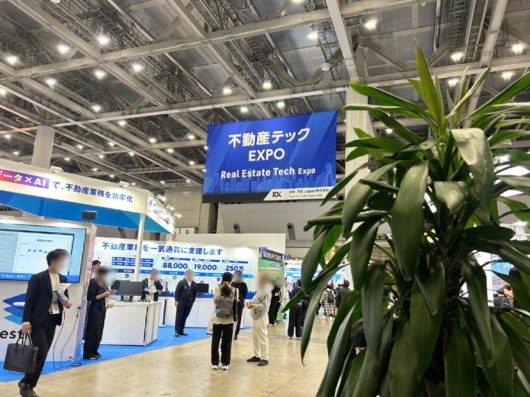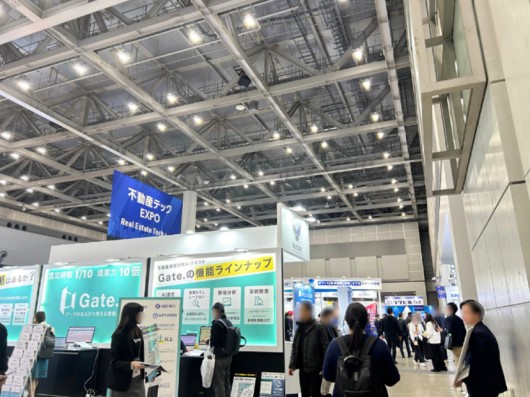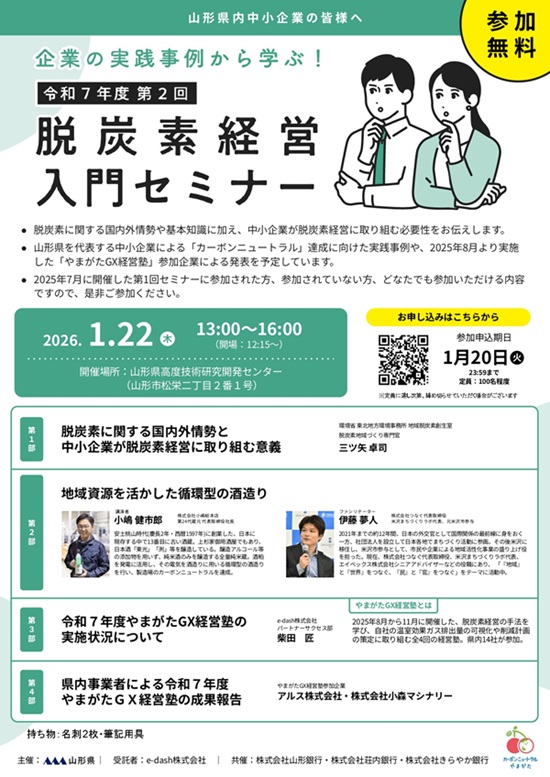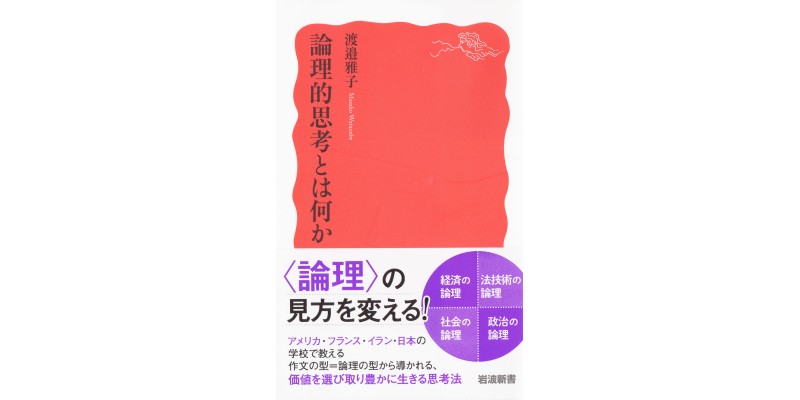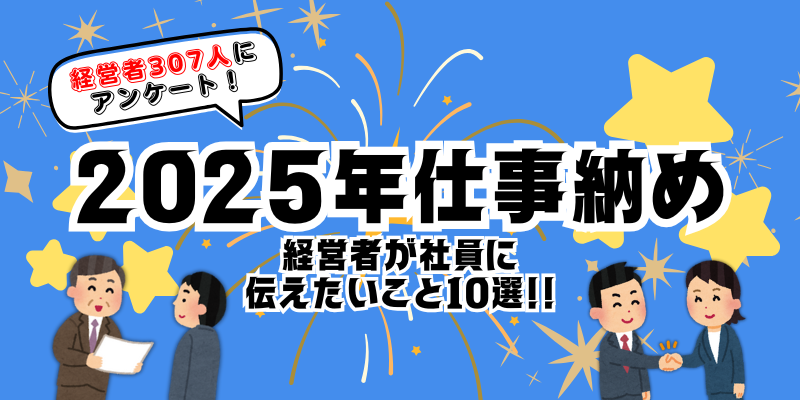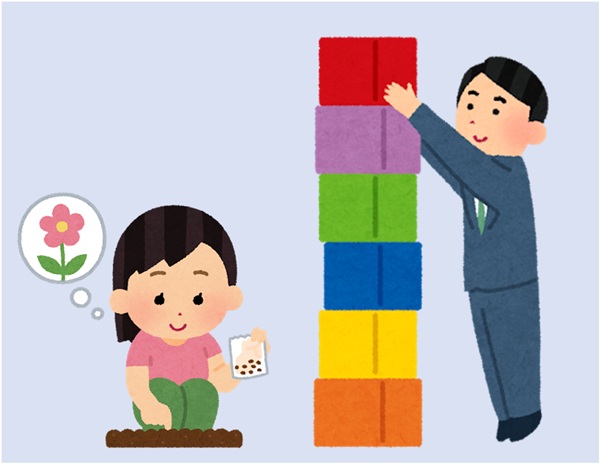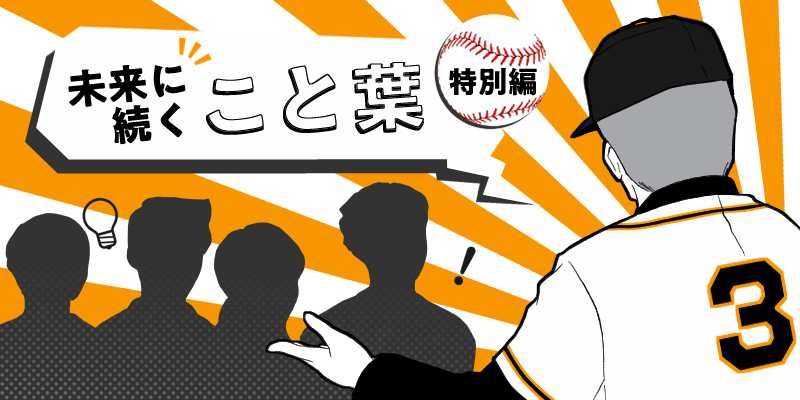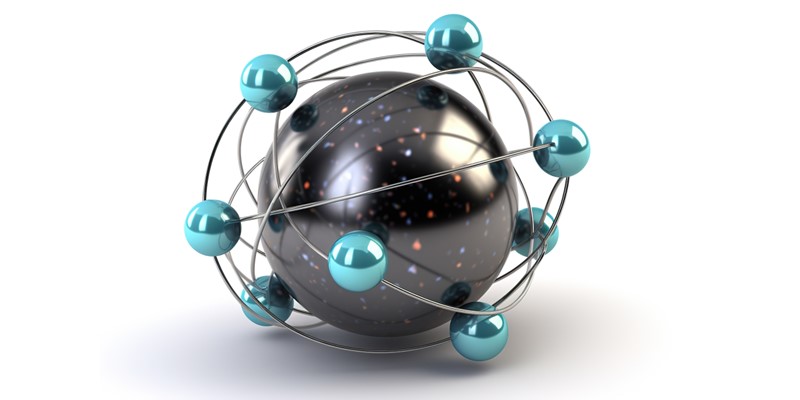不動産会社で従事している方にとって、登記簿謄本の見方は不可欠な知識です。そもそも登記簿謄本とは、不動産やその所有者に関する情報が記載された公的書類を指します。どの欄に何の情報が書かれているかポイントをあらかじめ押さえておくと、スムーズに活用できるでしょう。今回は、登記簿謄本の基本情報と表題部・権利部・共同担保目録の見方を、それぞれわかりやすく解説します。
登記簿謄本にまつわる基本情報

登記簿謄本をスムーズに読めるようになるには、登記簿謄本がどういうものか、ポイントを押さえておくことが大切です。ここでは、登記簿謄本の概要・登記事項証明書との関係・種類・構成について、基本を押さえておきましょう。
登記簿謄本とは
登記簿謄本とは、不動産やその所有者に関する情報が記載された公的書類です。具体的には、建物(家屋)や土地といった不動産の所在地・面積・構造・所有者などがわかります。また、抵当権など担保の設定状況も確認できます。
登記簿謄本を用いるのは、主に物件の購入・売却を行う場合です。不動産を購入したときや相続などで所有者が変わるときなどは、登記手続きをして記載内容を更新する必要があります。
不動産取引の安全性確保のための書類である不動産登記簿謄本は、定められた手続きをすれば、誰でも内容を閲覧できるのが特徴です。
登記簿謄本と登記事項証明書
登記簿謄本と似た名称に、登記事項証明書があります。登記所の登記情報の管理方法によって呼び方が異なるだけで、登記簿謄本と登記事項証明書は、同じ内容の公的書類です。
登記情報をデジタル管理する登記所の場合、その登記情報を印刷し、「登記事項証明書」という名称で交付します。一方、登記情報を登記用紙に直接記載し管理する登記所では、その登記用紙を複写し、「登記簿謄本」の名称で交付していました。
現在ではデジタルに移行し、書類の名称は登記事項証明書で統一されていますが、今でも登記簿謄本と呼ばれる場合があります。
登記簿謄本の種類
登記簿謄本には全部事項証明書・現在事項証明書・一部事項証明書・閉鎖事項証明書の4種類があり、それぞれ記載内容が異なります。登記簿謄本の請求時は、取得したい内容が記載された種類を選びましょう。種類ごとの記載内容は、下記の通りです。
| 種類 |
内容 |
| 全部事項証明書 |
閉鎖記録以外のすべての登記簿謄本の情報を記載 |
| 現在事項証明書 |
過去の所有者や抹消済みの権利などを除く、現在有効な情報のみ記載 |
| 一部事項証明書 |
複数の権利者のうち特定の権利者の情報など、一部の情報のみ記載 |
| 閉鎖事項証明書 |
現在は存在しない不動産情報など、閉鎖記録を記載 |
登記簿謄本の構成
登記簿謄本は、「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」「共同担保目録」の4つで構成されています。
欄ごとに記載内容は異なるので、どの欄に何の情報が書かれているのかを把握しておくことが大切です。なお、不動産によっては、表題部のみの場合や、表題部と権利部(甲区)のみの場合など、一部の欄しか記載がないケースもあります。
表題部の見方

登記簿謄本の表題部では、不動産の基本的な情報を確認できます。不動産の所在地・面積・構造・所有者などを知りたいときは、表題部を確認しましょう。
表題部は、土地・建物・マンションといった不動産の種類によって、記載内容に差があります。ここでは、種類ごとの見方を把握しておきましょう。
表題部の見方|土地の場合
登記されている不動産が土地の場合、表題部には、所在・地番・地積などの情報が記載されています。なお、土地の正確な位置は、所在と地番の2つを確認することで特定できます。表題部の記載項目と内容は、下記の通りです。
| 項目 |
内容 |
| 不動産番号 |
・法務局が割り振った管理用の番号 |
| 地図番号 |
・地図が整備されている場合は、その番号
・ない場合は空白 |
| 筆界特定 |
・筆界(土地の範囲)特定の申し出と特定が行われた場合に、その旨を記載
・ない場合は空白 |
| 所在 |
・丁目までの所在地 |
| 地番 |
・法務局が定めた土地の番号 |
| 地目 |
・宅地などの土地の用途 |
| 地積 |
・土地の面積 |
原因及びその日付
(登記の日付) |
・登記が完了した日付 |
| 所有者 |
・土地の所有者の名前と住所 |
法務省の見本からは、下記のような内容が読み取れます。
- 建物の所在地は、特別区南都町1丁目101番地
- 土地は宅地用途の地域で面積は300㎡
- 平成20年10月14日に登記
- 所有者は甲野太郎
表題部の見方|建物の場合
建物の場合、表題部には、所在・家屋番号・構造・床面積などの情報が記載されています。主となる建物に加えて付属する建物があるときは、付属の建物の情報も確認できます。建物の表題部の記載項目と内容は、下記の通りです。
| 項目 |
内容 |
| 不動産番号 |
・法務局が割り振った管理用の番号 |
| 所在図番号 |
・建物所在図が整備されている場合は、その番号
・ない場合は空白 |
| 所在 |
・番地までの建物の所在地 |
| 家屋番号 |
・法務局が定めた建物の番号 |
| 種類 |
・共同住宅、居宅、事務所などの建物の種類 |
| 構造 |
・木造など、建物の主な材料
・屋根の種類
・階層 |
| 床面積 |
・建物の各階の床面積 |
原因及びその日付
(登記の日付) |
・登記が完了した日付 |
| 所有者 |
・建物の所有者の名前と住所 |
法務省の見本からは、下記のような内容が読み取れます。
- 建物の所在地は、特別区南都町1丁目101番地
- 木造かわらぶき2階建ての構造で、1階部分は80㎡、2階部分は70㎡の床面積
- 令和1年5月1日に新築された
- 所有者は法務五郎
表題部の見方|マンションの場合
マンションの場合、同じ登記簿謄本の中に、マンション全体の情報と専有部分の情報の2種類が記載されています。一戸建てと異なり、土地・建物の両方の情報が1つの登記簿謄本で確認できるのは、マンションならではの特徴です。
マンション全体およびその土地に関する表題部には、下記のような内容が記載されています。
| 項目 |
内容 |
| 専有部分の家屋番号 |
・マンション全体の専有部分の家屋番号の一覧 |
| 所有者 |
・建物の所有者の名前と住所 |
| 所在図番号 |
・建物所在図が備えられている場合は、その番号
・ない場合は空白 |
| 所在 |
・番地までのマンションの所在地 |
| 建物の名称 |
・マンション名、ビル名 |
| 構造 |
・鉄筋コンクリート造など、建物の主な材料
・屋根の種類
・階層 |
| 床面積 |
・建物の床面積 |
原因及びその日付
(登記の日付) |
・登記が完了した日付 |
| 土地の符号 |
・土地の筆数 |
| 所在地及び地番 |
・土地の住所(一筆ごとに記載) |
| 地目 |
・宅地など、土地の用途 |
| 地積 |
・土地の面積 |
| 登記の日付 |
・登記が完了した日付 |
法務省の見本からは、下記のような内容が読み取れます。
- 建物の所在地は、特別区南都町1丁目3番地1
- マンション名は、ひばりが丘一号館
- 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建ての構造で、1階部分、2階部分ともに300㎡の床面積
- 建物が建っている土地は宅地用途の地域で面積は350㎡
また、マンション専有部分に関する記載項目と内容は下記の通りです。
| 項目 |
内容 |
| 不動産番号 |
・法務局が割り振った管理用の番号 |
| 家屋番号 |
・各専有部分の番号 |
| 建物の名称 |
・部屋番号など |
| 種類 |
・共同住宅、居宅、事務所などの建物の種類 |
| 構造 |
・鉄筋コンクリート造など、建物の主な材料
・屋根の種類
・階層 |
| 床面積 |
・建物の面積 |
原因及びその日付
(登記の日付) |
・登記が完了した日付 |
| 敷地権の種類 |
・所有権、地上権、賃借権のいずれか |
| 敷地権の割合 |
・専有部分の持ち分割合 |
| 所有者 |
・マンションの分譲業者名など |
法務省の見本からは、下記のような内容が読み取れます。
- 専有部分は鉄筋コンクリート造1階建ての1階部分で、床面積は150㎡
- 令和1年5月1日に新築された
- 敷地権は所有権で、敷地権割合は4分の1
権利部の見方

権利部には、権利部(甲区)と権利部(乙区)の2種類があります。甲区では所有権に関する内容を確認でき、乙区では所有権以外の権利に関してみることができます。ここでは、甲区と乙区に分けて、権利部の見方を確認しておきましょう。
権利部の見方|甲区
権利部(甲区)では、所有者の情報や所有権移転登記の状況などを確認できます。具体的な項目・内容は、下記の通りです。
| 項目 |
内容 |
| 順位番号 |
・登記の順番 |
| 登記の目的 |
・登記された目的(所有権の保存、移転など) |
| 受付年月日・受付番号 |
・登記を受け付けた日付と受付番号 |
| 権利者その他の事項 |
・所有者の氏名、住所 |
法務省の見本からは、下記のような内容が読み取れます。
- 現在の所有権者は法務五郎で、令和1年5月7日に売買で土地を取得
- 法務五郎の前の所有権者は甲野太郎で、最初の土地の名義人
権利部の見方|乙区
権利部(乙区)では、抵当権など所有権以外の権利の状況を確認できます。具体的な項目・内容は、下記の通りです。
| 項目 |
内容 |
| 順位番号 |
・登記の順番 |
| 登記の目的 |
・登記された目的(所有権の保存、移転など) |
| 受付年月日・受付番号 |
・登記を受け付けた日付と受付番号 |
| 権利者その他の事項 |
・所有者の氏名、住所 |
法務省の見本からは、下記のような内容が読み取れます。
- 令和1年5月7日に抵当権登記を申請
- 法務五郎の4,000万円の金銭消費貸借の担保として抵当権を設定
- 抵当権者は南北銀行
- 共同担保を設定している不動産がある
共同担保目録の見方
権利部(乙区)で記載されている抵当権について、ほかの不動産にも共同担保が設定されている場合、共同担保目録にその物件一覧が記載されます。例をあげると、土地と建物を購入するために住宅ローンを利用し、担保として土地・建物の両方に抵当権を設定した場合、共同担保目録に記載されます。
共同担保目録の具体的な項目・内容は、下記の通りです。
| 項目 |
内容 |
| 記号及び番号 |
・共同担保目録の管理上の記号や番号 |
| 番号 |
・担保のための権利の通し番号 |
| 担保の目的である権利の表示 |
・共同担保が設定されている物件の情報 |
| 順位番号 |
・抵当権の順位 |
法務省の見本からは、下記のような内容が読み取れます。
- 特別区南都町一丁目101番地の土地と建物に共同担保が設定されている
- 土地と建物どちらの抵当権順位も1位
まとめ
物件の売買などの際に必要な登記簿謄本は、「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」「共同担保目録」の4つで構成されています。欄ごとに記載内容が決まっており、表題部では不動産の情報、権利部では所有権やそれ以外の権利などについて確認できます。
とはいえ、登記簿謄本を実際に営業などで活用する際は、難解な専門用語の理解が求められる上に、抹消事項が多く、最終所有者の特定や持ち分の判読が大変です。また、差押や買戻権などの登記が入っている場合、売却活動の妨げになるため、抹消できるかの確認も必要になります。
登記簿謄本の情報を効率的に活用するなら、ホームズのスッキリ登記簿がおすすめです。スッキリ登記簿では、不要な登記を削除して登記内容を精査できます。複雑な権利関係の判読に時間をとられることがなくなり、現時点で有効な最終所有者も持ち分単位で明らかになります。業務効率化の必要性を感じている場合は、ぜひご活用ください。
(出典:ホームズメディア)