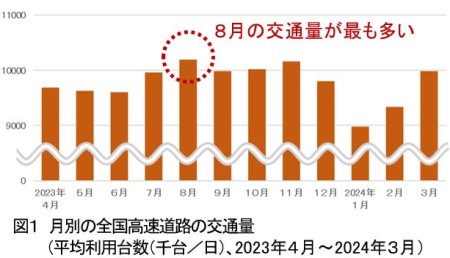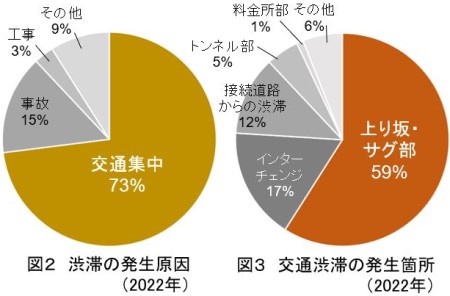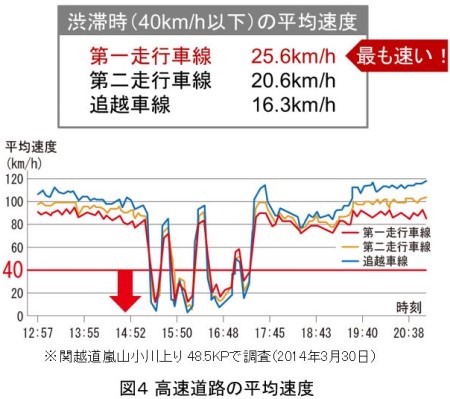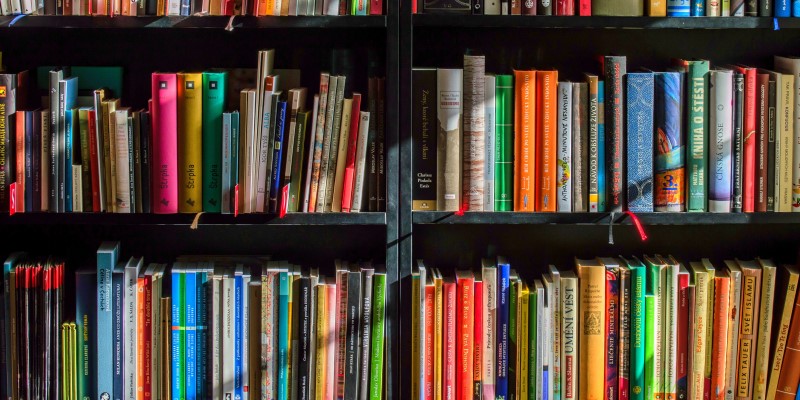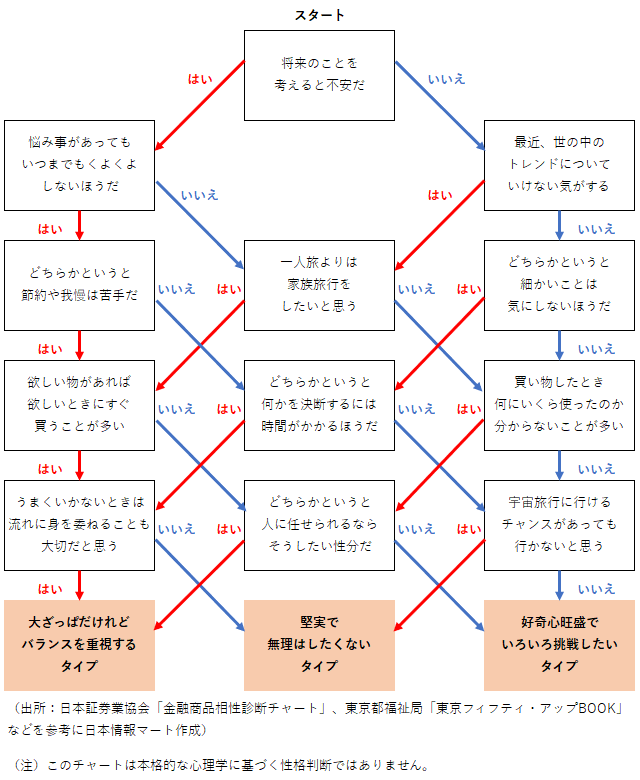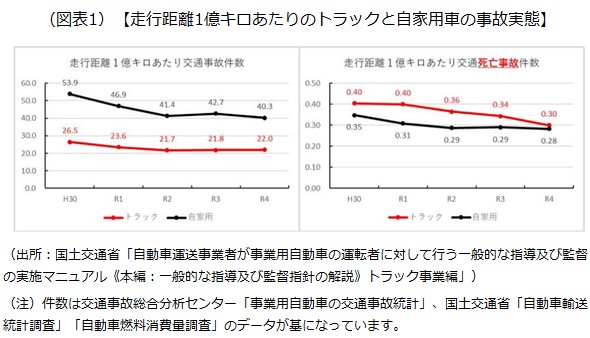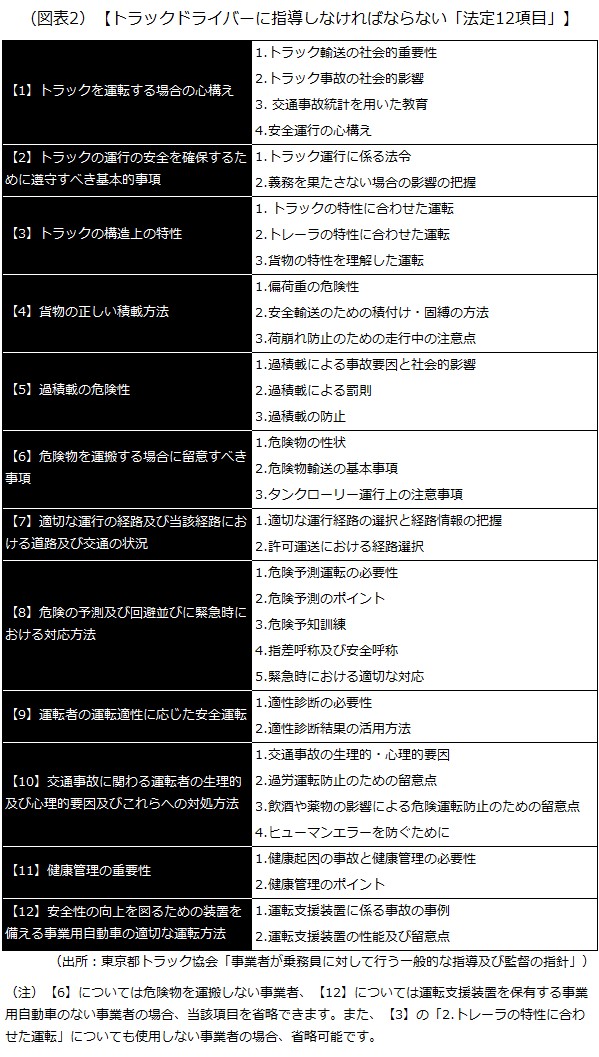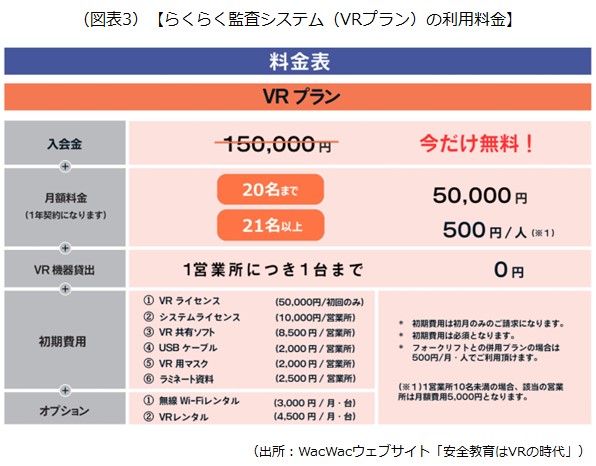書いてあること
- 主な読者:会社経営者・役員、管理職、一般社員の皆さん
- 課題:コミュニケーションに関わる知識やノウハウは、頭では理解できても、実際の場面で使いこなせるようになるまでには高いハードルがあるものです。
- 解決策:前回シリーズ『次世代リーダーに必須のコミュニケーション習慣』での知識やノウハウを聞いただけではまだ一歩を踏み出せない、あるいはトライしてみたがうまくいかないという方のために、新シリーズでは【実践編】として社内の“あるある”場面を想定した質問に対して一緒に考えながら、実践イメージを膨らませていただきます。またリーダー側の視点とは別に、若手社員側の視点による上司世代との上手な付き合い方のヒントも紹介していきます。リーダー世代と若手社員とのコミュニケーションギャップを埋めることは、世界を舞台にスピーディな成長をめざす日本企業にとっても喫緊の課題だからです。
1 笑顔のない新人Aさんを飲みに誘ったらあいまいな返事、どう声をかけますか?
今シリーズは、前回シリーズ『次世代リーダーに必須のコミュニケーション習慣』の実践編です。
知識やノウハウは分かったけれど、「現場で実践するにはまだハードルが高い」「うまく一歩を踏み出せない」という方も少なくないでしょう。そこで毎回実際にありそうなさまざまなシチュエーションを想定して、どんなコミュニケーションを取るのが望ましいかを一緒に考えていきます。
さっそく始めましょう。前回ご提示した課題[事例1]を再掲します。あなたの考えた解答を思い出してください。
—————————
Q. Aさんに対して、あなたはこの後、最初にどんな声を掛けますか? また最初の声掛けを考える際に注意するべきポイントを3つほど挙げてください。
[事例1]
〇4月に新人Aさんが加わりました(皆さんの部署に新卒配属がなければ、若手の異動をイメージしてください)。歓迎会など酒席パーティーが開かれ、部署単位での2次会も用意してひと通りの交流を無事に終えました。幸いにも部署の業績は右肩上がりで、その後はずっと部署全員が日々の業務に追われる毎日でした。
〇ところが最近Aさんの表情が心配です。「おはよう」と声を掛けても元気がなく、業務中も飲み会の時に見たような笑顔がありません。
〇そこで上司であるあなたは、Aさんと話す時間をつくってみようと考えて声を掛けました。「Aさん、最近仕事はどう? よかったら今日仕事が終わってから一杯飲みに行かないか」。するとAさんは「ええ……まあ……」とはっきりしません。
—————————
2 「相手をよく観察する」。“今の目の前の相手”と、“日常”と
前回、事例の最後にヒントを書いておきました。ヒントの1つは、「まずAさんの現在の心の状態を想像すること」です。「ええ……まあ……」という言葉の裏にはどんな心理状態があるのでしょうか。
間違っても「なんだ、こっちが心配して声をかけてやったのに断るのか」などと感情的に反応しないことです。言葉にしなくても表情や態度でAさんは気付きます。その瞬間に、これまで以上にあなたに対して心を閉ざしてしまうでしょう。「この人には絶対に分かってもらえない」と。
相手の反応に対して高ぶる気持ちがあって、一旦落ち着きましょう。そして
ポイントの1つ目「相手をよく観察する」です。こちらで勝手に思い込むことなく、相手をよく観察して事実を受け入れます。
Aさんは「ええ……まあ……」とはっきりしない返事です。つまり上司であるあなたと飲みに行きたいわけではない(恐らく行きたくないがストレートに言えない)。この事実を受け入れることから始めます。
「相手をよく観察する」のは、今声をかけた瞬間のAさんの反応についてと、同時に日常のAさんをよく観察して、深く理解しておくことの両方を意味します。観察であって、傍観ではありません。日ごろから声もかけ、必要なら時間を取り、コミュニケーションを通じて相手の反応を観察するのです。反応とは言葉だけではなく、声のトーンや顔の表情、しぐさなども含みます。
日常の観察も必要なのは、今の瞬間を観察しただけでは初対面の人に会ったときのように情報が不十分だからです。一方で、
コミュニケーションは生物(“いきもの”であり“なまもの”)です。
これまでこうだったからこうだろうではなく、今の目の前の相手が何を感じて、何を考え、何を求めているかをよく観察しないと次に取るべき対応を間違ってしまうでしょう。
例えば、Aさんがふだんから上司にストレートに意見を言えないタイプなのであれば、今回も正直な気持ちを言えずに困っているのだろうと想像できます。ふだんはストレートに意見を言えるタイプなのだとすれば、よほど困っているのだろうと私は受け止めます。
残念ながらご用意している[事例1]は、実際のコミュニケーションではなく、あくまで事例です。しかも、相手が目の前にいて観察できるわけではなく、テキストの文字情報しかありません。
そこは実際と異なる部分ですが、トレーニングとしてはもってこいのメリットもあります。文字情報なら何度も読み直せますし、観察したり考えたりする時間が十分に取れます。提供されている文字情報を丁寧に読み込んで、大事なポイントを見落とさないようにしましょう。
話を[事例1]に戻します。事実としてAさんは今夜、上司であるあなたと飲みに行きたくなさそうです。現時点で理由は分かりませんが、無理強いはいけません。
最初の一言は、「そうかごめん、今夜飲みに行くのはやめにしよう」でいいと思います。
こちらから誘った以上はこちらから取り下げましょう。上司と部下の関係では、相手は断りづらいはず、それが反応に表れています。
3 「起きている問題は何かに立ち戻る」、そして「相手の希望を尊重する」
今夜飲みに行くことをあなたから撤回したことで、Aさんはあなたに対して「自分の気持ちを分かってくれた」と思えるでしょう。少し話しやすい状態になれたかもしれません。
ポイントの2つ目は「起きている問題は何かに立ち戻る」ことです。ここでシリーズの目指す習慣の1つ「傾聴」と「褒める」のスキルを使ってみましょう。
今回、あなたはなぜAさんに声を掛けたのでしたっけ? 何が問題だと考えたのでしょうか。[事例1]の1つ目と2つ目の〇印のテキスト情報にありますね。
〇幸いにも部署の業績は右肩上がりで、その後はずっと部署全員が日々の業務に追われる毎日でした。
〇ところが最近Aさんの表情が心配です。「おはよう」と声を掛けても元気がなく、業務中も飲み会の時に見たような笑顔がありません。
「最近Aさんの表情に元気がない、業務中にあまり笑顔がない」のは事実として受け止めます。でも、そのことで現状、業務上の支障は発生しているでしょうか。
少なくとも[事例1]のテキスト内では言及されていません。なので、ここでは特に支障は発生していないと仮定しましょう。実際場面では、発生しているかどうか、もう一度確かめたほうがいいかもしれませんね。
発生していない前提で、Aさんに次のように聞いてみてはどうでしょう。
右肩上がりの業績に一生懸命対応して働いてくれているのですから、その事実を最初に「褒める」ことを忘れないでください。
「業績が右肩上がりの中、Aさんも毎日本当に頑張ってくれていますね、ありがとう。ただ、最近Aさんの表情に元気がない、業務中もあまり笑顔がないようで気になっていたんですよ。どうでしょう、正直なところを聞かせてもらえませんか?」
Aさんは、あなたが飲みに行こうと誘った理由を察するでしょう。心配してくれたことに感謝して
何かを話してくれるようでしたら「傾聴」してみましょう。こちらの言いたいことは一旦横において、ひたすら「傾聴」するのです。
もし、Aさんが
「元気がない、笑顔がないように見えていましたか。ずっと忙しくて仕事に追われていたからですよ。でも忙しいけれど倒れるほどじゃないし、仕事も楽しめていますし、大丈夫ですよ」
と答えたとすればどうでしょう。
ポイントの3つ目は「相手の希望を尊重する」ことです。
Aさんの言葉に嘘がないかは、表情を観察して慎重に判断してほしいのですが、業務上も支障がなく、Aさんもそれ以上特に相談したいこともないようであれば、一旦話を終わりにしてもいいでしょう。「相手の希望を尊重」し、しばらく様子を見るほうがいいかもしれません。
「分かりました。頼もしい限りですが、ずっと忙しいことで体調を崩すと大変ですし、様子を見ながら対応策を考えます。また状況を詳しく教えてくださいね」
上司の意向を優先して必要以上にまぜかえさないことです。どうしても心配なら、周囲のメンバーにさりげなく聞いてみましょう。Aさんは上司のあなたには知られたくないプライベートの問題を抱えているのかもしれません。業務上の支障がないのであれば静かに見守ってあげるほうが本人のためです。
[事例1]のQとして最初にどんな声をかけるか、その際に注意するべき3つのポイントについては以上です。一声掛けて、反応を確認して様子を見る。意外にシンプルでしたか?
時に最初から難しく考えすぎないことも大事です。
ところであなたは、[事例1]を通して部署の他のメンバーの様子や表情も観察してみようと考えたでしょうか。
もしかしたら部署の全員が日々の業務に追われて元気がなく、笑顔がなくなっているのかもしれません。だとすれば、事態はAさんだけの問題ではありませんね。誰かが急に倒れる、また退職などに至ることのないよう、早急に部署全体としての対応策を考える必要があります。
では最後に、もし上司からの的確な一言が期待できなかった場合、Aさんはどうすればいいでしょう。部下側の上手なコミュニケ―ション方法についても考えてみましょう。
現実問題として、日々の業務の忙しさで元気や笑顔がなかなか出せない状況下では、上司に相談している時間もないかもしれません。目の前の業務が終わるまで帰れないとなれば、業務に専念せざるを得ない状況は分かります。
であれば、
上司が声をかけてきたタイミングや面談などの機会に、ちょっとした一言でサインを出してみてはどうでしょう。
「業績がいいのは分かるんですが、それにしても毎日忙しすぎます」「私はまだ大丈夫ですけど、〇〇さんあたりはしんどそうですよ」「仕事は楽しいですし頑張りますけど、どこかで有休ください(笑)」
といった感じで。
4 異動してきたBさんが新しい取り組みを提案するも失敗、どう声をかけますか?
では、次回に向けた [事例2]を紹介します。
—————————
Q. Bさんに対して、あなたはこの後、最初にどんな声を掛けますか? またそれを考える際に注意するべきポイントを3つほど挙げてください。書かれているさまざまな要素を考慮してみましょう。
[事例2]
〇若手社員Bさんが異動してきて3カ月。はりきって新しい業務に取り組んでくれていましたが、ある日のこと、課のミーティングで提案があるというので時間を取ることにしました。内容は部署での従来のやり方を根本から見直す新しいアプローチの提案でした。
〇いきなり聞かされた他のメンバーからは「今までのやり方が間違っていたとは思わないが……」と後ろ向きな意見が出てきます。上司であるあなたは、新天地でやる気に燃えているBさんからのせっかくの提案だけに、まずは1カ月、一部業務でやってみればと受け入れ、他のメンバーにも協力を促しました。しかし、1カ月後に結果は出ませんでした。
〇Bさんはあなたに「メンバーの反対を押し切って受け入れてくれたのに、失敗に終わってすみません」と謝罪。異動したての頃の仕事への意欲をすっかり失っているようです。
—————————
ヒントとしては、今回の[事例1]の解説でお話ししたポイントも思い出しながら、[事例2]の文章を丁寧に読み返してみてください。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。実際の場面では、事例と似たようなシチュエーションであっても全く同じということはないでしょう。
今回私がご提示した声掛けや注意すべきポイントを参考にしながらも、目の前の状況に合わせてご自身で判断し、実行してみてください。
次回もお楽しみに。
<ご質問を承ります>
ご質問や疑問点などあれば以下までメールください。※個別のお問合せもこちらまで
Mail to: brightinfo@brightside.co.jp
※武田が以前上梓した書籍『新スペシャリストになろう!』および『なぜ社長の話はわかりにくいのか』(いずれもPHP研究所)が、ディスカヴァー・トゥエンティワンより電子書籍として復刻出版されました。前者はキャリア選択でお悩みの方に、後者はリーダーやトップをめざしている方にお薦めです。
『新スペシャリストになろう!』 https://amzn.asia/d/e8GZwTB
『なぜ社長の話はわかりにくいのか』 https://amzn.asia/d/8YUKdlx
以上(2024年8月作成)
(著作 ブライトサイド株式会社 代表取締役社長 武田斉紀)
https://www.brightside.co.jp/
pj90263
画像:PureSolution-Adobe Stock