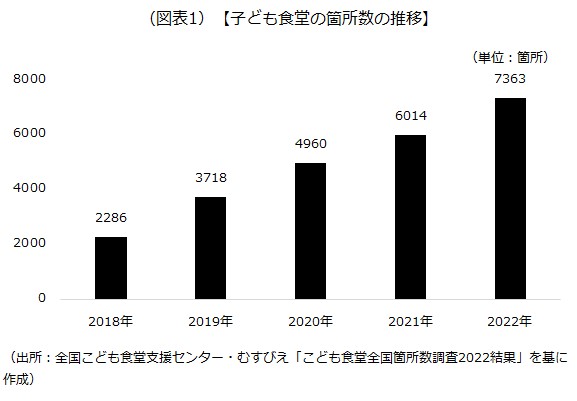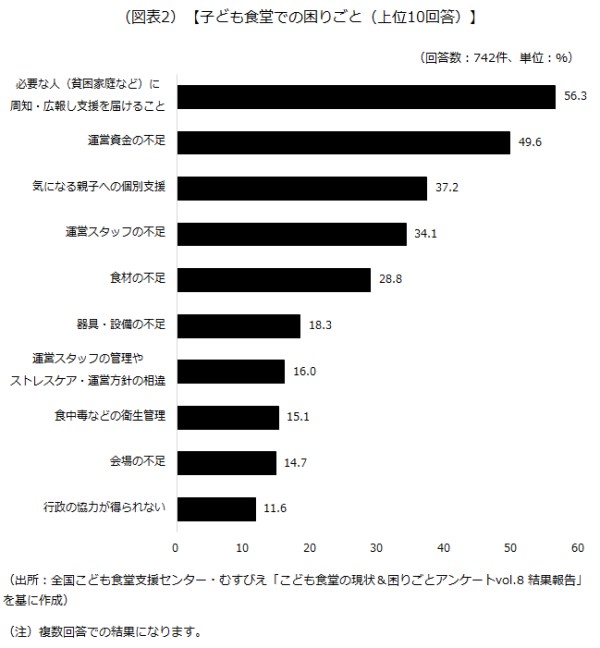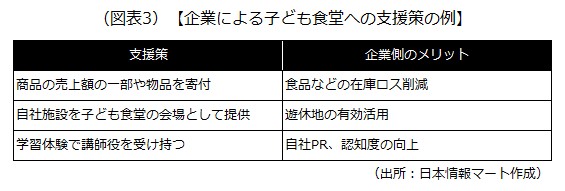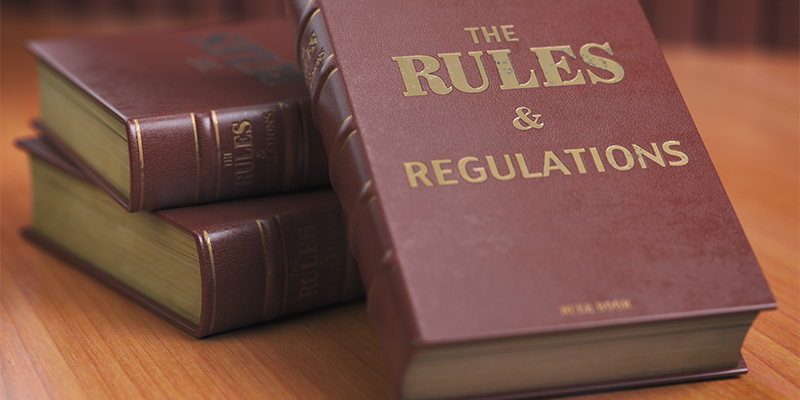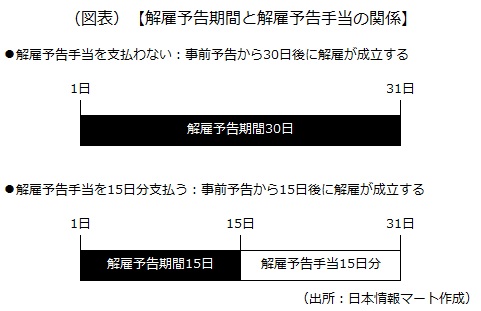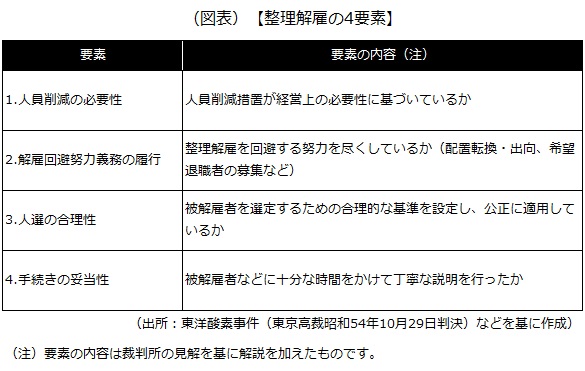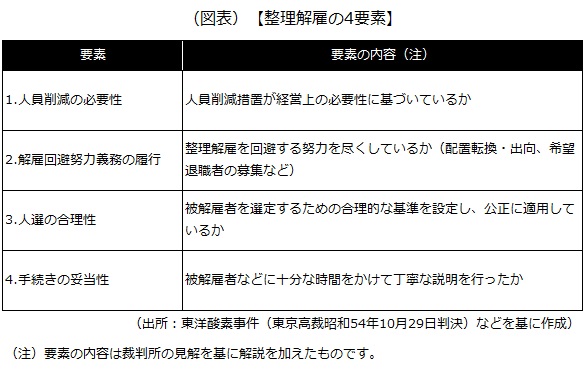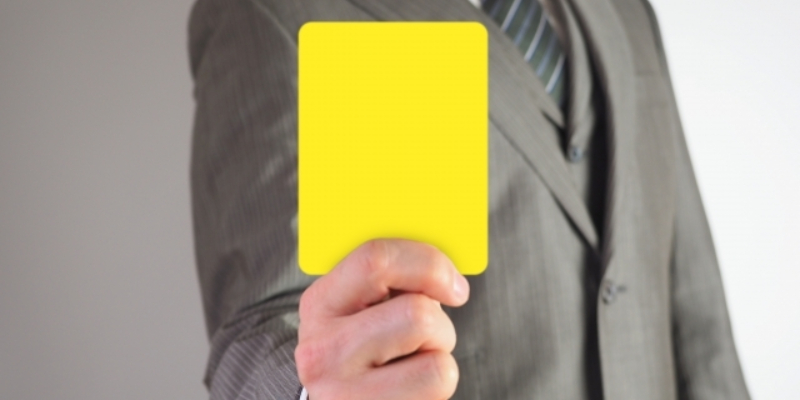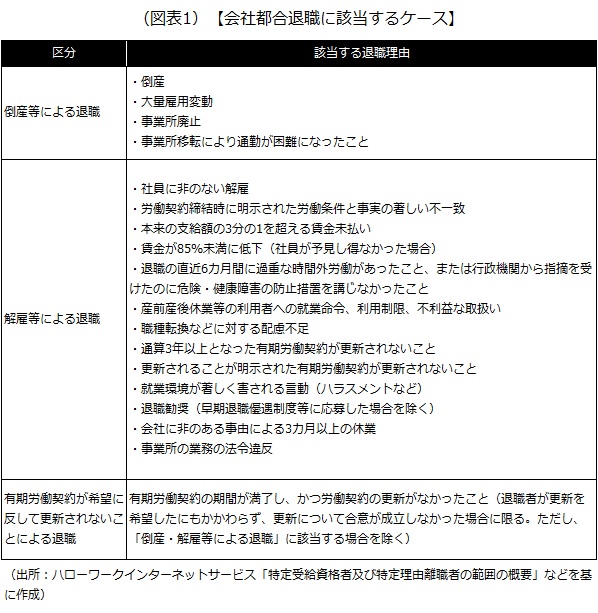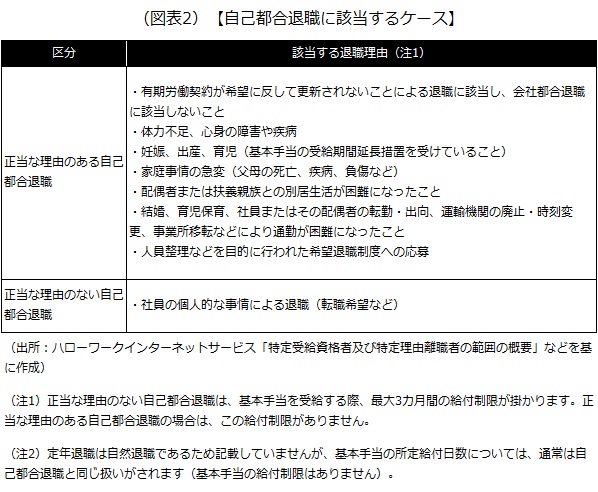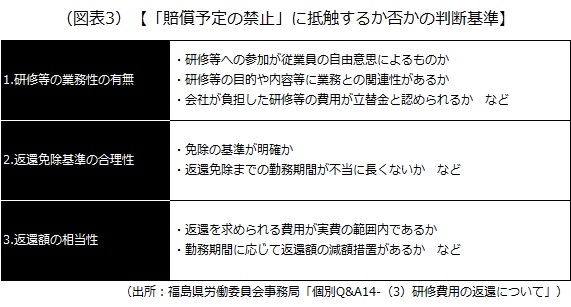書いてあること
- 主な読者:会社経営者・役員、管理職、一般社員の皆さん
- 課題:最近話題のZ世代(1990年代後半以降生まれで会社においては20代前半くらいまで)だけでなく、それ以前の平成生まれ(30代前半くらいまで)の世代と、現在経営や管理職を担っている昭和世代との世代間ギャップが注目されています。それは価値観の違いやコミュニケーションの違いとして表れ、変化や多様性が求められる昨今、日本企業において深刻な経営の足かせとなりつつあるようです。
- 解決策:まず会社においてZ世代を含む平成生まれと昭和生まれの世代背景を整理しながら、ギャップを埋めるための「価値観の変化」を明らかにします。その上で、筆者が多くの講演や企業研修で紹介してきた『次世代リーダーに必須のコミュニケーション習慣』を実践的に指南します。
1 相手を「褒める」ときに、【何を】褒めるのがベストか意識できていますか?
今シリーズでは、昭和生まれの管理職・リーダー世代と、平成生まれ、とりわけ「Z世代」との価値観に、ここ10年ほどで“真逆”といえるほどのギャップが生まれていることを取り上げています。
世界のビジネス上の価値観は、平成生まれや「Z世代」の価値観のほうに寄っており、会社の成長を今後も目指すためには管理職・リーダー側の皆さんが、価値観やコミュニケーション習慣を見直す必要に迫られているのです。
『次世代リーダーに必須のコミュニケーション習慣』その1の『傾聴』に続いて、前回第6回からは、その2『褒める』を取り上げています。
『褒める』は各社における35歳くらいから以下の平成生まれや、新人や若手の「Z世代」が育ってきた環境を象徴するキーワードの1つです。彼らは昭和生まれの『叱る』ではなく、『褒める』ことを優先した教育を経験しています。
同時に『褒める』は、『傾聴』と同様にグローバルで互いを尊重し合うDEI(=Diversity:多様性, Equity:公平性, Inclusion:包括性)にもつながっており、昭和世代にとって「人を褒めるなんて恥ずかしくて自分には無理」と逃げている場合ではなくなっているのです。
今回は、『次世代リーダーに必須のコミュニケーション習慣』その2の「褒める」について、「【何を】褒めるか」の5つのターゲットとその活用テクを伝授したいと思います。
皆さんは相手を「褒める」ときに、【何を】褒めるのがベストかを意識できていますか?
2 ①「見た目や持ち物」を褒める vs ②「内面や行動」を褒める
①「見た目や持ち物」を褒める [初対面向き]
見た目や持ち物は比較的簡単に【何を】が見つけられます。早ければ会った瞬間に見つけられるので、[初対面向き]ともいえます。
例えば、「髪形が決まっていますね。かっこいいなあ!」「素敵な時計ですね。こだわってますねー」「笑顔が素敵ですね!」といった感じ。相手は照れ臭そうですが、まんざらでもない様子でうれしそうです。
一瞬で気付けるほど目立っている見た目や持ち物は「ここを褒めて」と言っているようなものです。出会った瞬間から探すことを意識していればすぐに見つかります。
本人が普段からこだわっている可能性が高いので、そこを声に出して言うだけで、相手は「わかります?」という気持ちになって互いの距離が一気に縮まります。
なかんずく初対面同士が集う会合などで有効です
が、相手はうれしさのあまり褒めたこだわりポイントについて語り続けるかもしれません。その際はタイミングを見て「いやあ、私のほうが詳しくなくてすみません。勉強になりました、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします」と告げて、次の方との出会いに進めばいいでしょう。
社内でも新人や異動してきた社員を迎える際に有効です。ただし①「見た目や持ち物」を褒めるには、注意するべき点もあります。特に意識してほしいのはセクハラ(セクシャルハラスメント)への配慮です。セクハラか否かの判断基準は、自分側ではなく相手の中にあります。
例えば、「おしゃれだね」まではよいとしても、その後に「今日はデートなの?」と続けると、セクハラになる可能性があります。「髪切った? 何かあったの?」も同様です。仕事に関係ないプライベートは個人の自由、余計な詮索をしてはいけません。
男性が女性の服装や髪形を褒めるのは、かなり高度なテクニックが必要なのでお薦めしません。パートナーや家族を褒めるときでも失敗しがちです。「その服、素敵だね」と褒めても「2回目だけど」と返されたり、「髪切った? 似合うね」と褒めても「切ってない、まとめただけだけど」と返されたりすることはママあります。
また、相手が複数いるのに1人だけに「おしゃれですね」「髪形が似合ってますね」と褒めると、他の人は自分はそうではないのかなと不機嫌になってしまうかもしれません。
②「内面や行動」を褒める
①とは対照的に、内面や行動はすぐにはわかりません。だからこそ、②の「内面や行動」を褒めるがはまると、相手は「普段から自分のことをよく見てくれているんだな」と感じて相互の信頼関係が高まります。組織においては上司と部下の関係構築に向いています。
例えば、「〇〇さんは後輩の面倒見がいいですね、優しいんですね」「〇〇さんはいつも仕事が丁寧ですね」「〇〇さんはいつも字がきれいですね」といった感じです。
「内面や行動」を褒めるポイントの見極めは、普段から相手の良いところを見つけてあげようと意識していれば、難しいことではありません。見つかったら素直に言葉に出して届ければいいのです。「内面や行動」は何度褒めてあげても構いません。
「何度も言っちゃうけど、〇〇さんは本当に仕事が丁寧ですね」と言えば、相手はそれを強みに感じて自信になり、もっと上を目指してくれることでしょう。褒めることで一人ひとりが育っていくのです。
3 ③「変化や成長」を褒める ④「貢献」を褒める
これらは②「内面や行動」を褒めるの発展形といえるでしょう。
③「変化や成長」を褒める
②の「内面や行動」の中でも、目立った③「変化や成長」を褒めます。それには長期的な関係が前提となりますが、半年、1年と長い付き合いだからこその大きな効果を発揮します。
例えば、「今日の朝会の司会、前回より良かったですよ」「企画書の書き方がこの1年ですごく上手になりましたね」といった感じです。褒められた本人はうれしくなって、もっと上を目指そうと心に誓うのではないでしょうか。
朝会など毎週、毎月実施するものであれば、長期でなく1週間、1カ月でも可能です。とにかく本人の「変化や成長」を、つぶさに観察しておいてあげることが大切なのです。
④「貢献」を褒める
「貢献」を測るにも③と同様に長期的な関係が前提となります。期間が長ければ長いほど、“褒める”ことの効果は大きいといえるのではないでしょうか。
例えば、「今回も目標達成できたのは〇〇さんのおかげですよ」「〇〇さんの気遣いで、私は救われました」といった感じです。
個人や組織への「貢献」を褒められることは、本人にとっては「この仕事をしていてよかった」とやりがいに思えるレベルの喜びでしょう。褒める側は、本人の貢献への感謝を正直に述べたまでですが、そのことが本人の仕事や会社へのエンゲージメントを想像以上に高めるケースがあるのです。
4 ⑤「ナンバーワン」だけでなく「オンリーワン」を褒める
結果を出した「ナンバーワン」のメンバーは、ラッキーがあったとしても褒めてあげましょう。それなりの数の競争相手がいればラッキーだけで「ナンバーワン」は取れません。ラッキーだって努力の結果かもしれないのですから。
そして
「ナンバーワン」のメンバーと同時に、プロセスも含めて「オンリーワン」の貢献や成長をしたメンバーを褒めることも重要です。
人は「誰にでもできる仕事」より、「自分にしかできない仕事」にやりがいや自身の存在価値を感じるものです。
例えば、「〇〇さんの気遣いあっての△課ですよ」「〇〇さんのサポートがあったから、頑張ってこられました」と、「オンリーワン」の言葉を添えられたらこの上ない喜びでしょう。④の「貢献」を褒めるの喜びに加えて、現在の仕事を“天職”とまで思えるかもしれません。
仕事や会社へのエンゲージメントはいうに及ばず、上を目指して自らどんどん成長して、周囲や会社により良い影響を与えてくれることでしょう。
もちろん、会社としては〇〇さんが病気で急に休むことになっても十分に回る組織でなければなりませんが、一人ひとりの「オンリーワン」の個性が生きている職場こそ、輝いている職場なのだと思います。
以上、今回は「【何を】褒めるか」の5つのターゲットとその活用テクをご紹介してみました。
最後までお読みいただきありがとうございました。次回は、「相手を【どのように】褒めればいいか」をテーマにお話ししていきたいと思います。
<ご質問を承ります>ご質問や疑問点などあれば以下までメールください。※個別のお問合せもこちらまで
Mail to: brightinfo@brightside.co.jp
※武田が以前上梓した書籍『新スペシャリストになろう!』(PHP研究所)が、ディスカヴァー・トゥエンティワンより電子書籍として復刻出版されました。キャリア選択でお悩みの方にお薦めです。
以上(2024年1月作成)
(著作 ブライトサイド株式会社 代表取締役社長 武田斉紀)
https://www.brightside.co.jp/
pj90256
画像:PureSolution-Adobe Stock