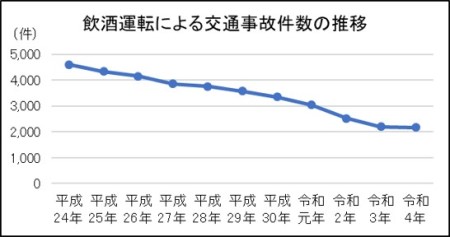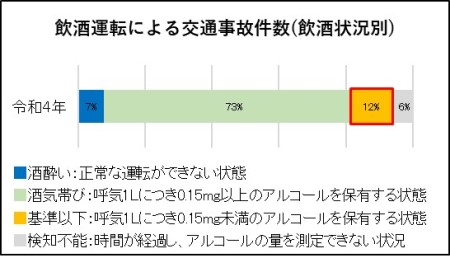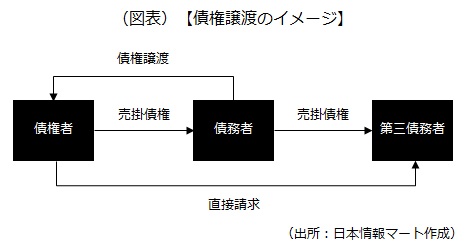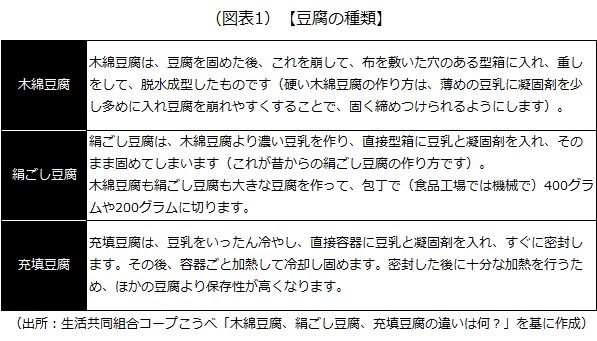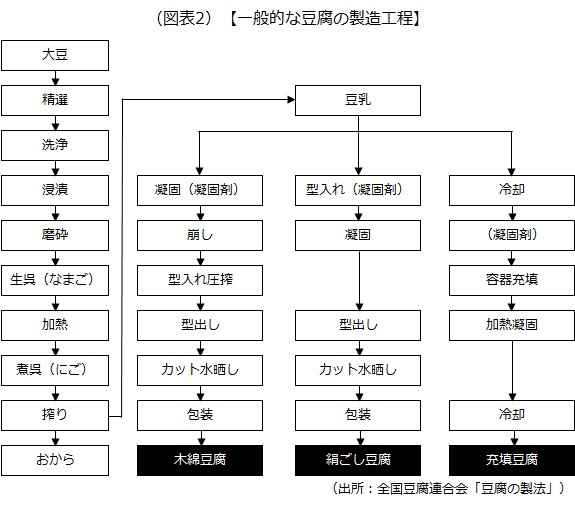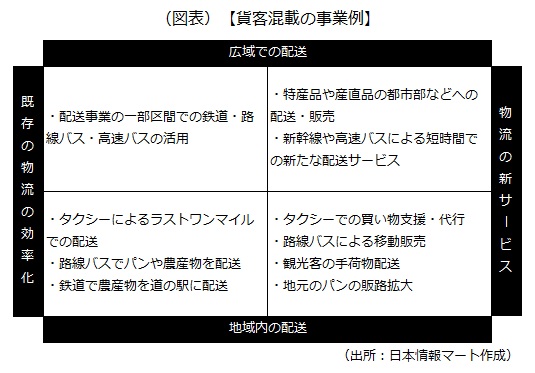書いてあること
- 主な読者:会社経営者・役員、管理職、一般社員の皆さん
- 課題:最近話題のZ世代(1990年代後半以降生まれで会社においては20代前半くらいまで)だけでなく、それ以前の平成生まれ(30代前半くらいまで)の世代と、現在経営や管理職を担っている昭和世代との世代間ギャップが注目されています。それは価値観の違いやコミュニケーションの違いとして表れ、変化や多様性が求められる昨今、日本企業において深刻な経営の足かせとなりつつあるようです。
- 解決策:まず会社においてZ世代を含む平成生まれと昭和生まれの世代背景を整理しながら、ギャップを埋めるための「価値観の変化」を明らかにします。その上で、筆者が多くの講演や企業研修で紹介してきた『次世代リーダーに必須のコミュニケーション習慣』を実践的に指南します。
1 昭和世代と「Z世代」とのギャップは、すなわち「世界とのギャップ」
前回までを簡単におさらいしておきましょう。皆さんの会社の新入社員から20代後半くらいまでの世代=「Z世代」が注目されています。理由が3つありました。
生涯価値(LTV=ライフ・タイム・バリュー)を秘めていて、他世代への影響力も含めて「主要購買層の1つ」であること。会社の次代を担う「中心的な働き手」であること。そして「昭和世代とはかなり異なる価値観を持っている」ことです。
特に最後が重要で、その価値観はここ10年ほどで“真逆”と言えるほどに変化しているようです。管理職であろう30代後半~50代の昭和生まれ世代と、現場を任されている平成生まれ、
とりわけ「Z世代」との間にはかつてないほどの価値観のギャップが生まれています。
具体的には、
「Z世代」の新入社員が理想とする上司像のキーワードは「丁寧な指導/褒める/傾聴」、同じく理想とする職場像は「個性の尊重/助け合い」など。
昭和世代の上司が育ってきた時代の「情熱/引っ張る/厳しい」「活気/鍛え合う/目標の共有」といった価値観による従来の管理・指導方法では育てられなくなっているのです。
彼らの価値観が特殊なのではありません。それらは世界の価値観の変化にも通じていて、昭和世代と「Z世代」とのギャップは、すなわち「世界とのギャップ」と言える状態です。
となれば上司たちのほうがアンラーン(既存の知識や価値観を一旦捨てて、ゼロから学び直すこと)して、新しい価値観を理解し寄り添っていくしかありません。
50代後半以降で「自分はあと数年で定年だし、何とかやり過ごせばいい」と考えている方も、いずれ自身が動けなくなった際に面倒を見てくれるのは「Z世代」以降の人だということを忘れてはいけません。
介護してくれるスタッフや、子どもやお孫さんたちに愛されながら穏やかな最後を迎えたいのであれば、やはり若い世代、「Z世代」の価値観を理解する必要がありそうです。
2 『次世代リーダーに必須のコミュニケーション習慣』その1は「傾聴」、ひたすら聴く
さて前回、若手社員とまだ十分な関係が築けていないという方は、彼らの話を「傾聴」することから始めてみてくださいと申し上げました。
「傾聴」とは文字のごとく、耳を傾けて集中してひたすら“聴く”こと、英語ではアクティブ・リスニングと呼ばれています。そしてこの「傾聴」が、今回のシリーズテーマである『次世代リーダーに必須のコミュニケーション習慣』の1つ目となります。
「傾聴」の効果を実感いただくために、私は講演や研修などでは参加者に2人ずつのペアを作ってもらい、次のようなミニワークを実施します。最近あったできごとでテーマを決めて、AさんからBさんに同じように2回話してくれるようにお願いします。一方Bさんには次のようにお願いします。
1回目はAさんが話してかけてもAさんのほうを見ないで横を向いてパソコン画面に向かったままのような姿勢で、せいぜい「ふうん」程度で一切反応しないでください。2回目はAさんのほうに体を向けてなるべく目を見て、話の内容に合わせて声や態度で大きく反応しながら「傾聴」してください。
1回目、2回目とも私がスタート、ストップと言って開始、終了してもらうのですが、本人たちには内緒で1回目より、2回目の時間を長めにして指示を出します。Aさんが2回終わったら、そのまま今度は役割を交代して、BさんからAさんに対して同じように2回、Bさんの最近あったできごとの話をしてもらいます。
1回目は当然ですが、話し手の声だけが聞こえてきます。聞き手の反応がほぼないわけですから。しかし2回目に入ると聞き手の声や互いの笑い声も聞こえてきて、会場全体が一気ににぎやかになります。
2回ずつ終えたところで、私が「実は1回目のほうが2回目より短い時間でした」と告げると、一瞬会場がざわつきますが、納得したかのように誰もがうなずいているのが分かります。
終わったところで皆さんの感想を聞くと、1回目は「壁に向かって話しているようで苦痛だった」「途中からなぜか悲しくなってきた」「ものすごく長い時間に感じた」といった声がほとんどです。
一方で2回目は「一生懸命聞いてくれているのが分かってうれしかった」「思わず、話すつもりじゃなかったことまでいっぱいしゃべってしまった」「1回目より長かったのにあっという間で、時間が足りないくらいだった」。
そして2回目を終えると一様に「いっぱい聞いてくれたので、以前よりも話しやすくなった気がした」という感想が聞かれたのです。
つまり相手が「傾聴」してくれただけで、相互の関係性が以前より近くなっていると実感できたのです。
私はまた全員に問いかけます。「皆さんはふだん忙しいことを言い訳に、1回目のような態度で部下の話を聞いたことがありませんか?」
3 「傾聴」はコーチングの基本でもある
「傾聴」はコーチングの基本でもあります。
コーチングとはティーチングのように一方的に教えたり、指示命令を出したりしません。適切な質問を投げかけることで、本人に考えてもらい、本人の中に既にある気付きを浮かび上がらせていく手法です。
変化の激しい時代を迎えて、会社組織の中で一人ひとりの社員が自律的に判断し行動できるようになるには、コーチングは有効です。
そしてコーチングで適切で効果的な質問を投げかけるためには、まず相手をよく知ることが必要で、その前提として「傾聴」が欠かせません。質の高い「傾聴」ができれば、質問を投げかけなくてもコーチングが実現することさえあります。
よく聞く買い物場面での夫婦の会話を想定してみましょう。
妻:ねえ、聞いて。洋服だけどAにしようかBにしようか迷っているのよ。Aは色が大好きだけど値段が気になるし、Bは値段がお手頃だけど、色がねえ。デザインは結構気に入っているんだけど…でもなあこっちも…
夫:(イライラしながら)で、僕に何が聞きたいの?
妻:だからね、どっちがいいのかなあって…迷っているのよ。どっちかなあ…
夫:Aでいいんじゃない?
妻:どうして?
夫:ボーナスが出たところだから、お金の心配はいいよ。だってAが気に入っているんでしょ!
妻:お金の問題じゃないのよねえ。私はどちらかといえばBがいいと思うのよねえ。
夫:なんだ、自分でもう決めているんならそっちにすればいいだろう。わざわざ僕に聞く必要ないじゃないか!
皆さんも似たような経験がないでしょうか。
4 相手の話を「傾聴」するだけで解決することも多い
先ほどの場面、妻は夫に「傾聴」してほしかっただけなのかもしれません。例えばこんな感じです。
妻:ねえ、聞いて。洋服だけどAにしようかBにしようか迷っているのよ。Aは色が大好きだけど値段が気になるし、Bは値段がお手頃だけど、色がねえ。デザインは結構気に入っているんだけど…でもなあこっちも…
夫:そっかー、迷っているんだね。AもBもそれぞれ良いところもあるし、気になるところもあるんだね。だとすると確かに迷うよね。
妻:そう、そう、そうなのよ。どっちがいいのかなあって…迷っているのよ。どっちかなあ…
夫:ところで、君自身はどう思っているの?
妻:そうねえ。どちらかといえばBかなあとは思っているんだけど…
夫:それはなぜ?
妻:デザインが気に入っているの。私はデザインにはこだわりたいから。ね、昔からそうでしょ。色はむしろ新しい色にチャレンジすればいいのかなって…
夫:なるほど。確かに昔からデザインにこだわっているよね。じゃあBなのかもね。Bの色も君に似合うと思うよ!
妻:ありがとう。やっぱりBよね。Bにするわ。あなたに相談してよかったわ。
—————————————-
いかがでしょう。できればもう一度、前者と後者の夫側の会話だけを比較しながら追ってみてください。また夫側の会話が変わったことによって、妻側の反応がどのように変化していったでしょうか。
後者の夫は、ひたすら妻の話を「傾聴」しながら、時々質問を投げかけています。
例えば「そっかー、迷っているんだね」「確かに迷うよね」「なるほど。確かに昔からデザインにこだわっているよね」などは、「傾聴」における【承認】や【共感】の手法です。
同じく後者の夫の「君自身はどう思っているの?」や「それはなぜ?」はコーチングにおける【質問】の手法の一部です。
とりあげた事例は夫婦のプライベートでの会話でしたが、同じようなことは男女にかかわらず、皆さんの職場でも日々起きているのではないでしょうか。
次回は、「傾聴」の具体的な手法やノウハウについて、より実践的にお話ししていきたいと思います。今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
<ご質問を承ります>
ご質問や疑問点などあれば以下までメールください。※個別のお問合せもこちらまで
Mail to: brightinfo@brightside.co.jp
以上(2023年9月作成)
(著作 ブライトサイド株式会社 代表取締役社長 武田斉紀)
https://www.brightside.co.jp/
pj90252
画像:PureSolution-Adobe Stock