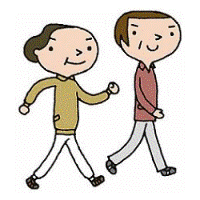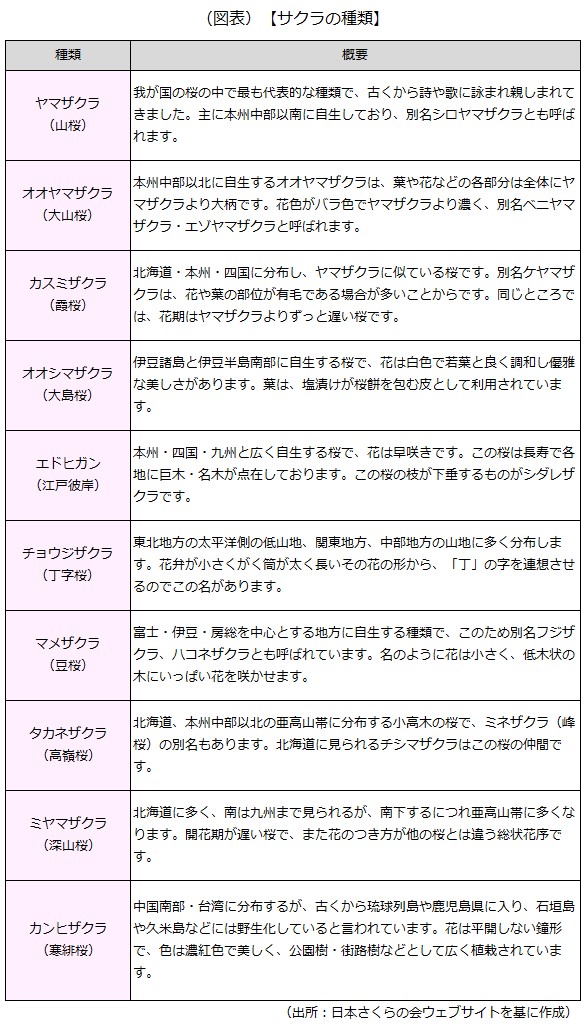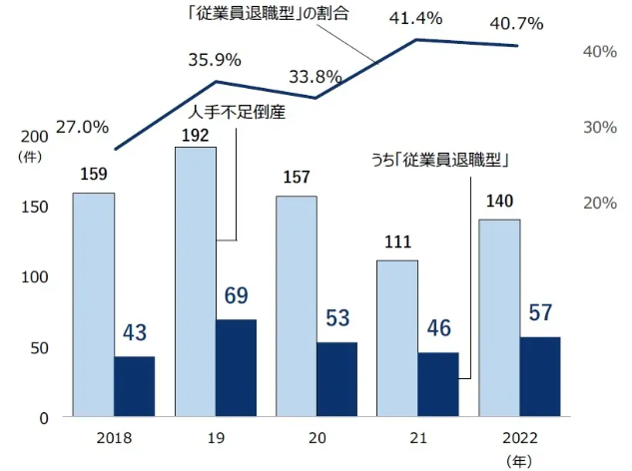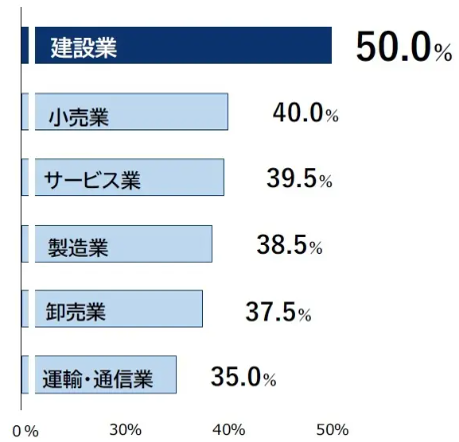1 パンのうんちく
ここでは、パンが発見されたきっかけなどについてみていきます。なお、以下で紹介するのは諸説あるうちの一説であり、異なる見解があることをご了承ください。
2 パンが発見されたきっかけ
現在の主流となっているたくさんの空気を含んだ「発酵パン」は、ちょっとした偶然から生まれたといわれています。定かではありませんが、一説には、4000年ほど前に、エジプトで単純に前日残ったパン種を翌日そのまま焼いたら発酵パンが出来上がったといわれます。空気中などに漂っている野生酵母が偶然にパンを発酵させたのでしょう。
3 ギリシャからローマへ
発酵パンはその後、イオニア(現在のエーゲ海沿岸地方)を経てギリシャへと伝わったとされています。ギリシャでは、レーズン、オレンジ、オリーブといった豊富な農産物と、ワイン造りの発酵技術がパンに応用されました。また、専門の職人によってパンが店売りされるようになります。
そして、古代ローマ時代には、パンの量産化がある程度できるようになっていたようです。ローマ市内には国営のパン焼き釜が設置され、パンの大量生産が行われていたといいます。
4 ヨーロッパ全土へ広がるパン
古代ローマ時代には、ローマ軍の遠征によって、ヨーロッパ各地にパン作りの技術が広まりました。しかし、5世紀に西ローマ帝国が滅亡すると、パン食文化は衰退していきます。パン作りは、修道院や貴族などが担うようになり、庶民は自分でパンを作ることが難しい時代となりました。
しかし、次第に庶民もパンを作ることができるようになります。14世紀ごろからイタリアで始まるルネッサンスになると、パン食文化がまた花開きます。フランスのフランスパン、東欧やロシアのライ麦パンなど、各国の素材や風土に合ったさまざまなパンが確立され、各国独自のパン文化が発達していきました。
5 長く不明だった発酵のメカニズム
それぞれの国の気候や風土に合わせたパン作りが発達し、ヨーロッパ中にパンが普及した後も、「なぜパンが発酵するか」という理由は、科学的に解明されてはいなかったようです。当時、製パンの技術は職人の経験とカンに頼る、いわば職人芸的なものだったのかもしれません。
パンが発酵するメカニズムが解明されたのは17世紀後半とされています。顕微鏡を発明したオランダのレーウェンフックが「酵母(イースト)」の存在を発見し、酵母菌を分離培養することに成功したのがきっかけとされています。
この発見によって酵母の研究は大きく進歩し、それまでの不安定な酵母から、管理された安定した酵母ができるようになったようです。長いパンの歴史の中、その原理が解明されたのはそれほど昔のことではないようです。
6 あんパンの誕生
パンが日本に伝来したのは、1543年に鉄砲がもたらされたのと同時期のようです。ポルトガルの宣教師がキリスト教の布教を行う中、パン食文化も日本に徐々に広がっていきました。しかし、その後の鎖国によって西洋風のパンは日本から姿をひそめ、長崎などで西洋人のために細々と作られていただけだったといわれています。
しかし、幕末になると、パンは「携帯食」として注目されることとなります。1840年のアヘン戦争で勝利を収めたイギリス軍が次に日本へ来襲することを恐れた幕府は、伊豆韮山の代官・江川太郎左衛門に、江戸湾の警備を命じました。この江川太郎左衛門が、携帯食としてパンに注目し、1842年4月12日にパンの試作品を焼いたのが国産パンの始まりだとされています。
明治維新を迎えると、外国人居留地のある横浜を中心に日本人経営者によるパン店も登場し始めました。また、横浜でパンの製造技術を習得した職人によるパン店も各地に少しずつ出てきたようで、文明開化の風潮につれてパン食も普及する兆しをみせ始めました。
そんな中、パンを一気に身近なものにしたのが、「あんパン」の登場でした。1869年創業の、現存するパン店で最も古い歴史を持つ銀座の老舗「木村屋」の創業者の木村安兵衛は、日本酒の酒種をパン種に使うという製造技術を考案し、この中にあんを入れた「あんパン」を売り出しました。それを明治天皇に献上したところ、非常に気に入られ、宮中で正式に取り入れられました。皇室御用達の木村屋のあんパンはあっというまに銀座名物になり、連日多くの客を集めるとともに、日本人にパンの味を伝えていきました。

7 給食で定着したパン食文化
こうして徐々に浸透してきたパンですが、日本人の食生活にパンを普及させることになった決定的な理由は、やはり第二次世界大戦だといえるでしょう。
戦後、未曽有の食料難となった日本に対して、米国は小麦の放出を行いました。この小麦を使って焼かれたパンが配給され、パンが本格的に普及し始めるようになったのです。日本が食糧難の危機をとりあえず乗り越えた後も、米国による余剰農産物の処分という思惑もあって、学校給食にパンが導入されることになりました。ほとんどの子供が食べる学校給食で、多くの子供たちがパンと牛乳という食事のスタイルを身に付け、パン食は真に普及することになったのだといえるでしょう。
その影響で、今やパンはすっかり第二の主食として定着しています。世界中のあらゆるパンが日本で手に入り、カレーパンなど日本独自の調理パンが定着し、その人気は衰えることはありません。有機栽培の小麦を使ったパンや、高級素材を厳選したパンなど、健康志向やグルメ志向に合わせたパンも数多く登場しています。
一方で、近年は国の方針から、給食でパンが出る回数が減っているといわれています。今後日本のパン食文化がどう変化していくのかを、注目してみてはいかがでしょうか。
8 世界のさまざまなパン
1)フランスパン
砂糖や牛乳などは使わず、小麦粉・イースト・塩・水だけで作られたパンです。形によってパリジャン、バゲット、バタールなどといろいろな呼び方がありますが、いずれもパリッとした皮に特徴があります。
2)ベーグル
もともとはユダヤ教徒の食事として食べられてきたといわれるパンです。今では米国のポピュラーなパンの一つで、チーズなどの具をはさんで食べるのが一般的です。ベーグルの作り方には特徴があり、焼く直前に生地を一度ゆでます。これによって、独特のもちもちした食感が生まれます。
3)フォカッチャ
イタリア語で「火で焼いたもの」という意味のパンです。イタリア北部の郷土料理で、ピザの原型ともいわれています。生地にオリーブオイルが練り込まれ、ハーブなどで風味づけされていることが多いため、そのままでも食べられます。
以上(2023年4月)
pj96521
画像:amenic181-Adobe Stock
画像:pixabay