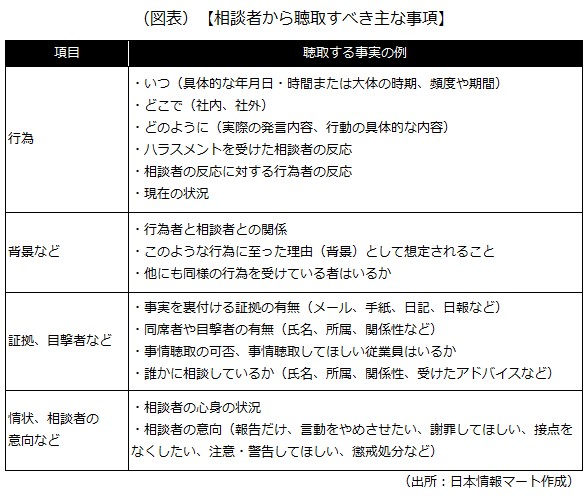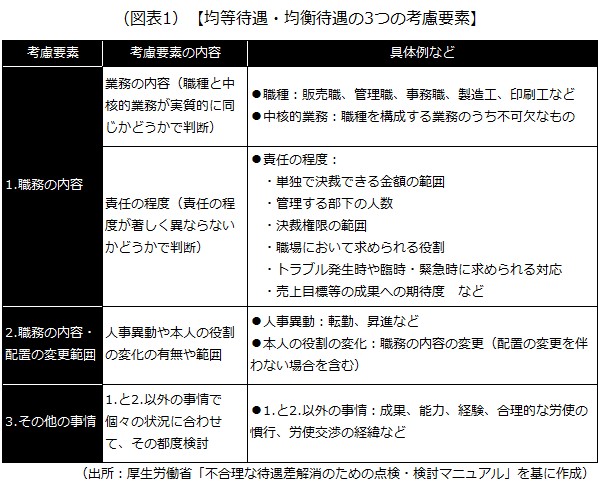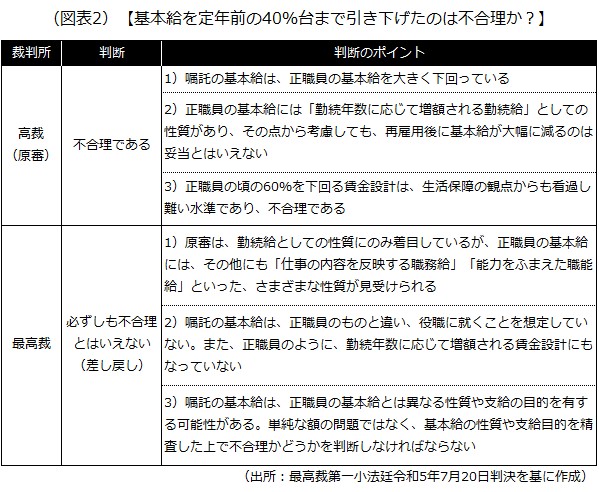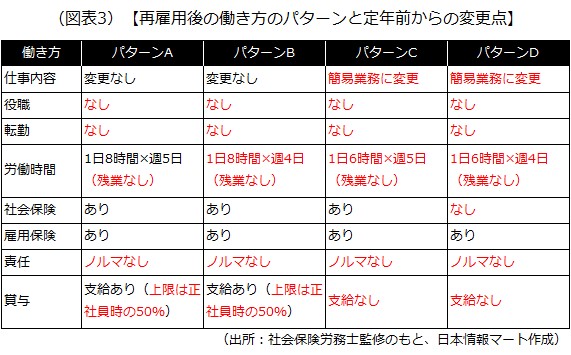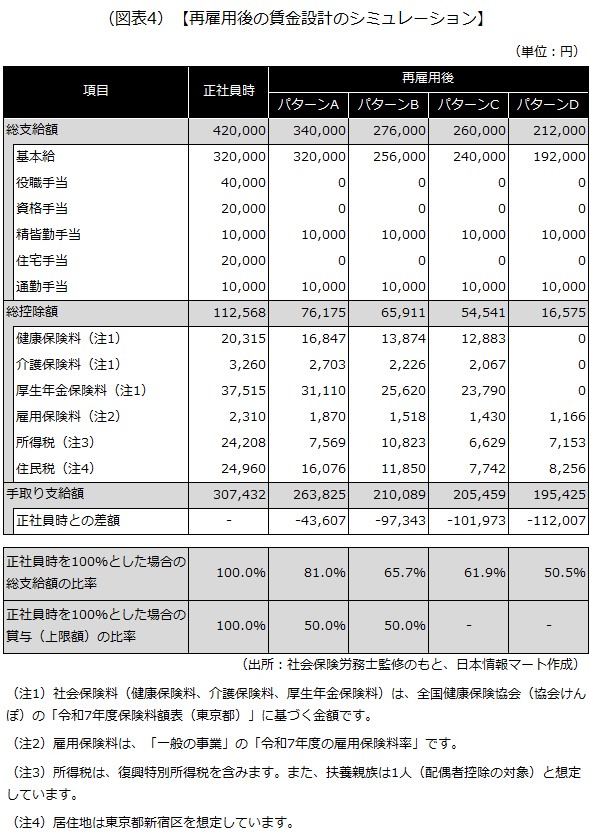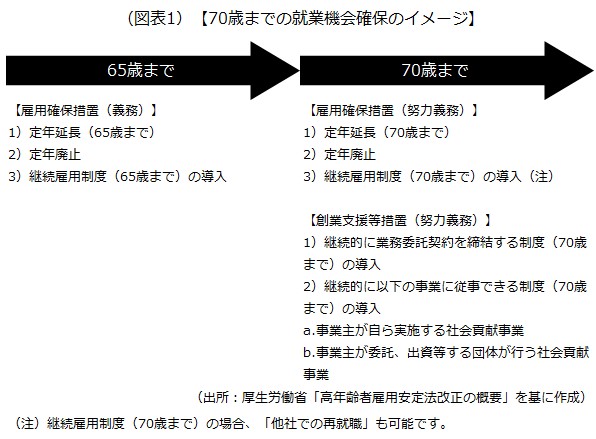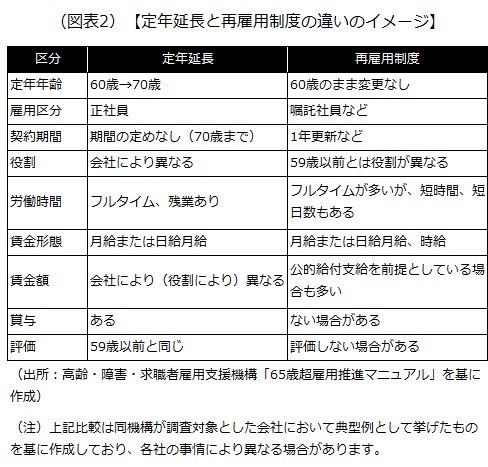1 成功するM&Aのために法的な整理も忘れずに
M&Aをする経営者が気にするのは、
M&A後の会計処理や税務上のインパクト
であることが多く、法的な整理は後回しにされがちです。しかし、M&Aのスキーム(手法)によって、
- 承継する権利関係やリスクの負担度合いが異なる
- クロージングまでのスケジュールが大きく異なる
などといった注意点があり、法的な整理をきちんと確認しないとM&Aで失敗してしまうこともあります。そうならないように、この記事では、M&Aについて最低限知っておくべき法的な注意点を、スキームごとに整理します。
2 株式譲渡を進める際の注意点
1)株券発行会社の場合は、株券の交付やこれまでの株主の異動に注意する
株式譲渡は、他のスキームに比べて譲渡手続きが簡便といえ、M&Aに慣れていない経営者でも理解しやすい手法です。ただし、株式譲渡では対象会社を包括的に譲り受けるため、その分、リスクも大きくなるので、十分に注意しましょう。
例えば、株券発行会社では、法律上、株券を交付しなければ株式譲渡の効力が生じません。特に2004年以前は株券の発行が義務付けられていました。しかし、こうした決まりを知らずに、当事者間の意思表示だけで株式を譲渡している場合が多々ありました。そのため、以下の点には十分に注意しましょう。
- 株券発行会社で、現在の株主が設立時から変更されているときは、当該株主が株券の交付を受けて、適法に株式を譲り受けているかを確認する
- 現在の株主名簿に記載されている株主が株券を所持していない場合、その理由を確認する(株券不所持に過ぎないのか、株券を紛失したのかなど)
2)会社に内在する問題を包括的に承継することを理解する
中小企業のM&Aでは、簿外債務が問題になることが少なくありません。意図せずとも、
- 正しく会計処理をしていなかった
- 未払残業代があった(みなし残業代を支払っていたが、法律上、みなし残業代とは認められない状態だった)
などのケースがあるからです。この他、必要な許認可を取得していなかったり、許認可の有効期間が切れていたりすることもあります。M&A後に飛躍的に売り上げが伸びるなどして注目を浴びるようになった際にこうした問題が露呈し、買収した親会社のレピュテーションが低下することもあります。
そのため、
デューデリジェンス(DD)をしても見つからないリスクについては、株式譲渡契約書で表明保証に関する定めや損失補償条項を設けるなどしてケアする
ことが大切です。
3 事業譲渡を進める際の注意点
1)取引先との契約は全て締結し直す必要がある
事業譲渡は、前述した株式譲渡と異なり、対象会社の全てを包括的に承継するのではなく、当事者間で合意した事業に関する権利義務だけを切り出して承継するスキームです。
一見すると大変使い勝手が良いスキームのように感じますが、
譲渡対象になった契約などが自動的に譲渡先に移転するわけではないため、全て譲渡先と新たに契約を締結し直す
必要があります。これは大変煩雑な手続きとなることもあり、それが理由で事業譲渡を断念する場合もあります。
2)譲渡対象を明確にして締結をする必要がある
事業譲渡のポイントは、当事者間で、どの事業のどの取引・権利義務・資産等を譲渡対象にするかを明確にすることです。譲渡対象によって譲渡金額も変わるため、後々、譲渡を受けたと考える譲渡先会社と、譲渡をしていないと考える譲渡会社でトラブルになることもあります。
特に中小企業の場合、個人の資産と会社の資産が明確に分かれていない場合も多いので、譲渡対象を明確にすることがより重要になります。
4 会社分割を進める際の注意点
1)手続きに時間がかかる
法律上、会社分割の進め方は決まっています。単に会社分割契約を締結するだけでなく、労働契約承継法で定められた労働者保護の手続き、会社法で定められた債権者保護の手続き(債権者保護のための公告・催告などを行う)などを経る必要があります。そのため、最短で手続きを進めようと思っても、1カ月半~2カ月程度はかかります。
また、求められる手続きも色々とあるため、会社分割を選択する場合は専門家に相談することをお勧めします。
2)債権者や労働者の理解が得られないと思わぬ落とし穴がある
会社分割は、法律上の手続きを踏むことで、取引先から個別の承諾を得ることなく、契約等を承継会社に承継させることができます。
ただし、労働者保護の手続きにより、承継会社に承継される事業に主として従事する労働者は、自分の意思で承継会社に移籍するか否かを決めることができます。また、債権者保護手続きにより債権者から異議を出された場合、当該債権者に対して、債務を弁済する、相当の担保を提供するといったことが必要になります。
以上から、会社分割においては、場合によっては、事前に労働者や債権者に根回しをしておく必要があります。
3)分割対象を明確にして締結をする必要がある
会社分割も事業譲渡と同じように、何を分割対象にするかを当事者間で決めることができます。そのため、分割内容を明確にしておかなければ、分割会社と承継会社との間で認識のずれが生じ、トラブルになることがあります。
5 合併を進める際の注意点
1)手続きに時間がかかる
会社分割と同じく、法律上、合併の進め方は決まっています。そのため、最短で手続きを進めようと思っても、1カ月半~2カ月程度はかかります。
2)債権者の理解が得られないと思わぬ落とし穴がある
会社分割と同じく、合併においても債権者保護手続きなどを経る必要があります。そのため、債権者から同意が得られないと、合併手続きを進めるにあたって影響が出てきます。
3)会社に内在する問題を包括的に承継することを理解する
合併の場合には、会社に内在する簿外債務等のリスクを全て承継することになりますので、その点に留意し、きちんとデューディリジェンスを行うなどの対策を講じることが必要になるといえるでしょう。
以上(2025年9月作成)
(執筆 リアークト法律事務所 弁護士 松下翔)
pj60362
画像:Mariko Mitsuda