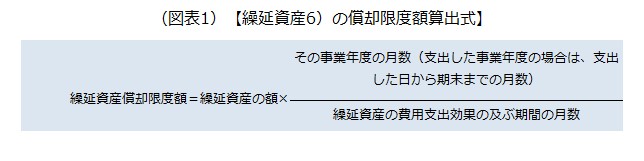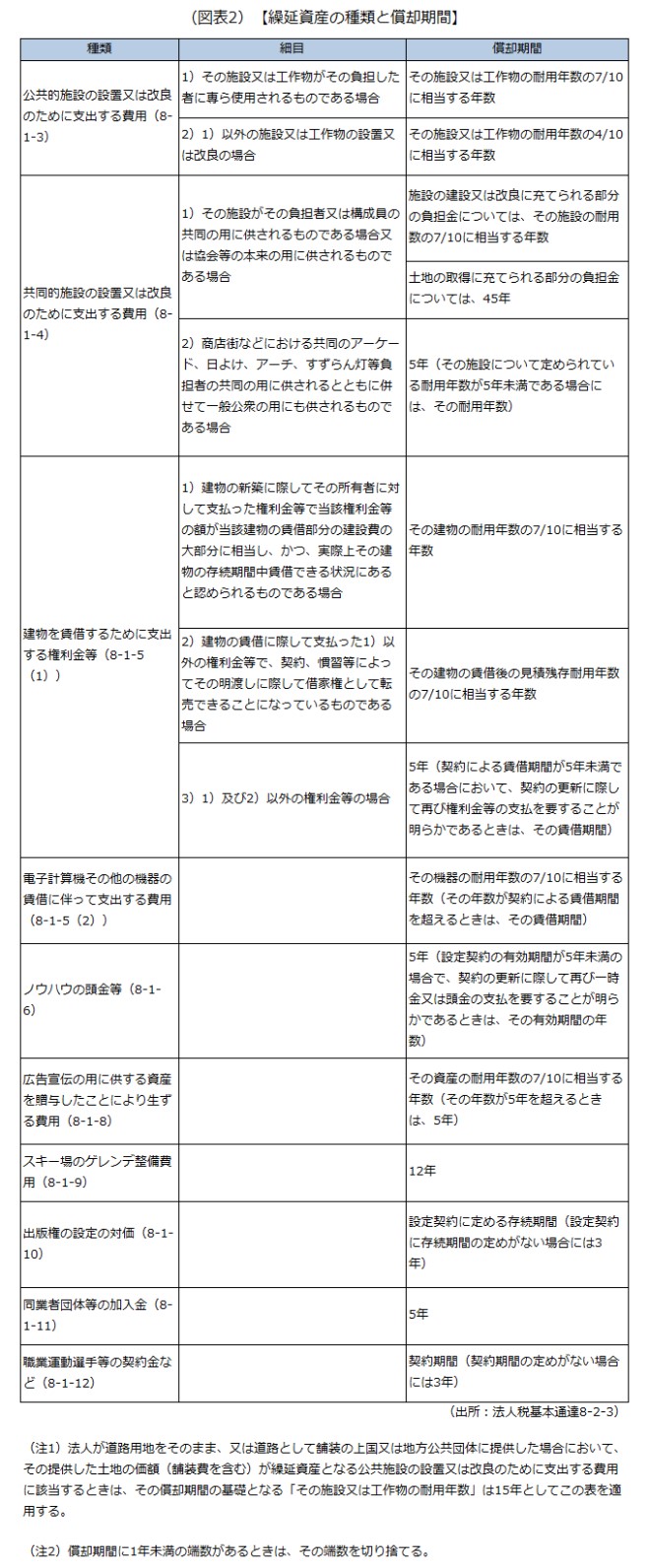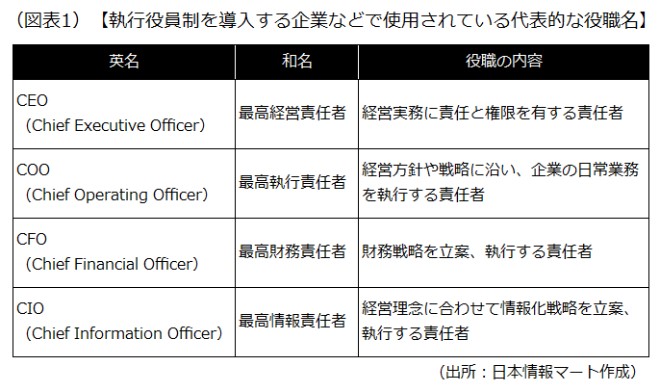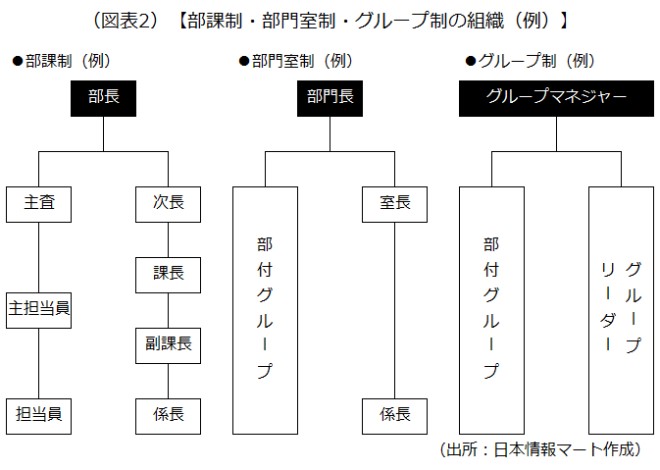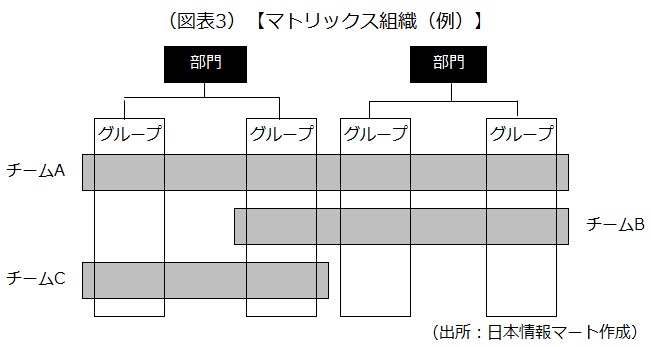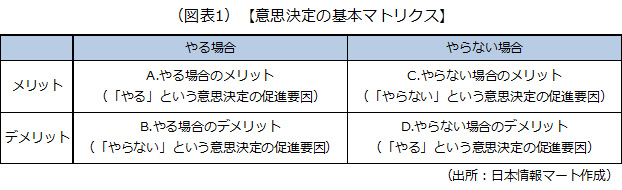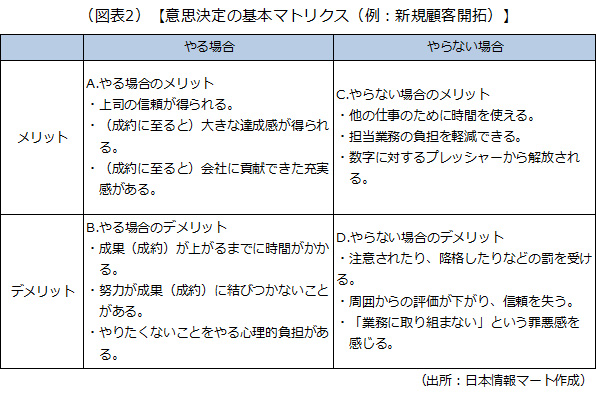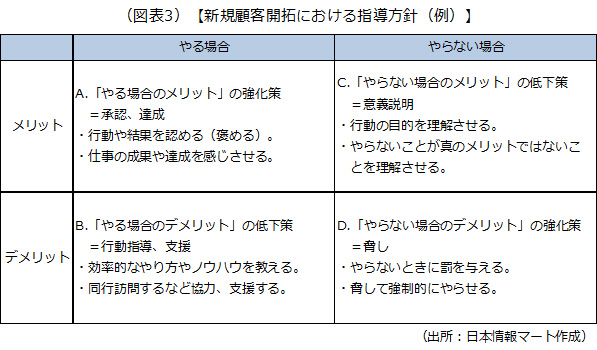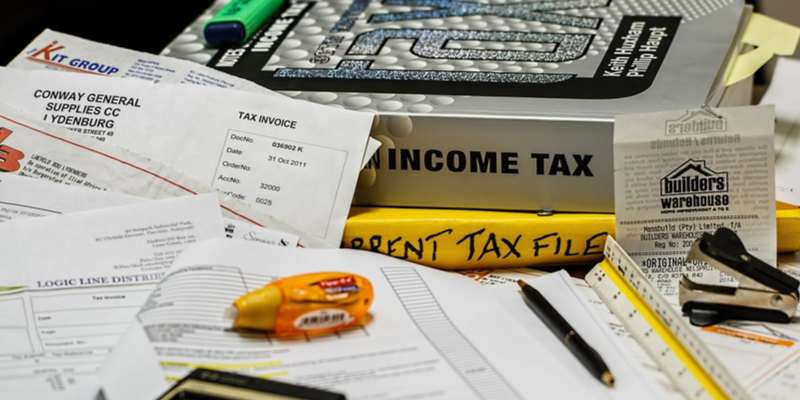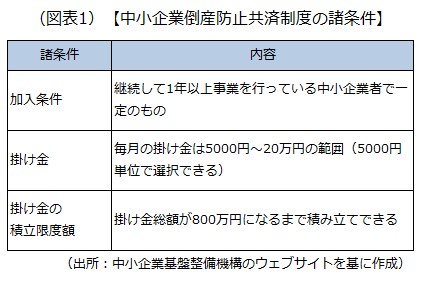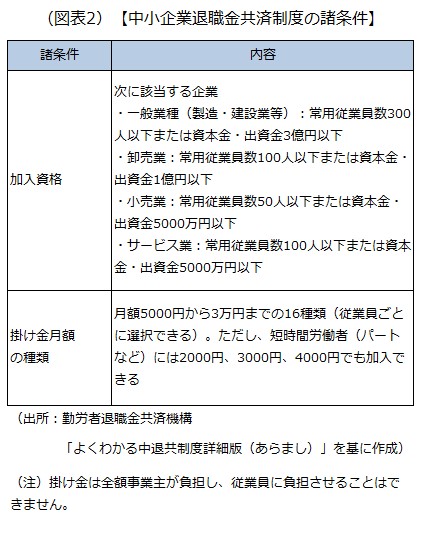書いてあること
- 主な読者:取締役、取締役就任予定の従業員
- 課題:取締役の法的な責任について知っておきたい
- 解決策:民事上、刑事上の責任を負っている。民事上では、特に不祥事が起こった場合、この責任の負担は、取締役本人のみにとどまらず、家族にまで及ぶ可能性がある。責任が大きいのは権限の大きさと比例している。取締役には企業をよい方向に導くためにその責任と権限を意識することが求められる
1 取締役の責任の厳格化の流れ
従来から日本の会社においては、長年会社に勤めてきた従業員が内部昇格して取締役になる傾向があります。このような生え抜きの取締役の場合、社内の事情に精通しているという利点がある半面、長年勤めていた会社であるが故に取締役就任に伴って、それまでとは異なる大きな責任を負うことを認識しづらいという問題があります。
近年、こうした問題点が広く認識されるようになり、投資家・消費者などを公正に保護しようとする傾向が生じていることから、取締役の責任が加重されつつあります。
その1つの例が2015年5月に施行された改正会社法です。この改正では、社外取締役などによる株式会社の経営に対する監査などの強化や、会社運営の適正化が大きな目的とされており、取締役の会社運営上の責任は一層重くなりました。
本稿では、押さえておくべき「取締役の法的責任」について、実例を用いて説明します。
2 民事上の責任1:取締役・執行役が負う責任の類型と賠償額
取締役は、経営に当たり会社に損害を与えないように注意すべきという善管注意義務を負っています(会社法第330条、民法第644条)。その義務の内容はさまざまですが、取締役の責任がよく問題となるケースとして「法令違反」「著しく不合理な経営判断」「監視監督義務違反」があります。
1)法令違反
取締役は、職務を行うに際して、法令を遵守する義務を負っています(法令順守義務、会社法第355条)。法令違反の事例としてはミスタードーナツをフランチャイズ経営していたダスキンで起こった事件(以下「ダスキン事件」)(大阪高裁平成18年6月9日判決判時1979号115頁)が有名です。ダスキン事件は、食品衛生法上使用が認められていない食品添加物を肉まんに使用して、販売したことが新聞・テレビ等で報道されて、ミスタードーナツの売上が低下する等の損害が生じたため、ダスキンは加盟店に売上減に対する補償等をするなど多額の出費をしたことについて、取締役および監査役の善管注意義務違反に起因するとして、株主代表訴訟が提起された事件です。
判決では、取締役が未認可添加物の使用および販売という事実を認識しながらも、その事実を公表せず継続して販売したことなどにより、会社の損害および信用失墜を大きくさせたことについて、隠蔽に関与した取締役だけでなく、隠蔽に関与していない11人の取締役についても責任を認め、具体的な損害賠償額は5億円以上にも上りました(ただし、取締役ごとで責任の範囲は異なっています)。
2)著しく不合理な経営判断
「法令違反」行為をした場合に責任を負わなければならないというのは、当然のことです。しかし、法令に反する行為ではなく、経営上の判断においても、取締役の責任が発生することがあります。
一般的に、会社の経営には一定程度のリスクを冒すことが不可避です。そのため、取締役の経営手腕を遺憾なく発揮できるように、経営上の判断についてはなるべく責任を負わせないようにすべきと考えられています。この考え方を経営判断原則といいます。しかし、近年、この経営判断原則を適用しつつも、取締役が経営判断に関して責任を負わされる裁判例が増えつつあります。
有名な事件としては、北海道拓殖銀行事件(最高裁平成20年1月28日判決判時1997号143頁他)が挙げられます。この事件では、取締役らが健全とは到底認められない貸付先に対して、確実な担保余力があるかどうかを慎重に検討せずに追加融資を決定したことについて、取締役の責任が問われました。最高裁は、銀行の取締役は、債権回収・保全を優先に考えるべきであるから、短期間のうちに対処方針および追加融資に応じるかどうかを決定しなければならないという時間的制約を考慮しても、その責任を免れることはできないとしました。そして、同事件では、一連の不祥事について5件の訴訟が起こされ、約101億円もの賠償金の支払いが13人の取締役に対して命じられました。
3)監視監督義務違反
取締役に就任した場合、自己の担当業務ではなくとも、他の取締役の行為について責任を取らなくてはいけないケースがあります。「代表取締役でもないのに、なぜ自分が関与していない他の取締役の行為にまで責任を負わなくてはいけないのか」と思うかもしれません。しかし、会社法第362条第2項第2号では取締役会の義務として取締役の職務執行を監督すべきことを定めています。判例でも、個々の取締役は、取締役会の構成員として、取締役会に上程された事柄についてだけ監視すればよいわけでなく、代表取締役の業務執行一般について監視する職務を有するとされています(最高裁昭和48年5月22日判決民集27巻5号655頁)。
これは、取締役が不正な行為をしないよう監督し、会社に損害を与えないようにするという取締役の善管注意義務から導かれます。複数の取締役が相互に監視監督し合うことで、会社業務の適正が確保されるのです。そのため、各取締役は取締役会のメンバーとして他の取締役の監視監督義務を負います。また、会社法第430条により、各取締役は連帯して賠償責任を負わなくてはならないため、監視監督義務違反だから責任は軽いだろうという油断は禁物です。
監視監督義務違反の有名な事件として、大和銀行事件(大阪地裁平成12年9月20日判決判時1721号3頁)があります。この概要は、大和銀行ニューヨーク支店の行員が、10年以上もの間、簿外で米国財務省証券の取引を行って約11億ドルの損失を出し、その隠蔽のため、大和銀行所有の米国財務省証券を無断で売却したというものです。同事件では、一部の取締役について監視監督義務違反が認められました。判決で認められた監視監督義務違反は次のようなものです。
まず、取締役会の招集権限を持っていた取締役会長については、代表取締役頭取の報告により簿外の無断取引行為と無断売却行為の事実を知ったのであるから、米国当局に対する届け出を行うように代表取締役に働きかけるべき義務があったとしています。
また、頭取については、一連の違法行為について認識しながら米国当局に対する届け出を行わなかったことを前提に、指揮系統の上位者であることを理由として、少なくとも未然に防止すべき義務があったとされています。
このように取締役には、行員による簿外での無断取引行為および無断売却行為を未然に防止すべき監視監督義務違反があったと認定されました。被告取締役のうち、11人に対して、総額7億7500万ドル(当時の日本円に換算して、約830億円)の損害賠償を命ずる判決が言い渡されています。
なお、この判決で注目すべきは仮執行宣言という裁判が出されたことです。通常、裁判は判決が言い渡されてから一定期間経過するまでの間、賠償金の支払義務は確定しません。ところが、仮執行宣言という裁判が出されてしまうと、直ちに支払義務(仮の支払義務)が生じることとなります。大和銀行事件では、約830億円もの賠償金の仮執行により、取締役は自宅を差し押さえられるか、それを免れる代償として約8億円もの供託金を集めるかという二者択一を迫られました。このことからも、取締役の責任がいかに重いものであるかが分かるでしょう。
また、近年では、子会社が不祥事を起こした場合に、親会社取締役の責任が追及されるケースがあります。ここでよく問題になるのは、親会社の子会社に対する監視監督義務違反です。例えば、子会社が「ぐるぐる回し取引」と呼ばれる粉飾決算の原因となる一種の架空の循環取引によって経営が破綻しかけたことをめぐる福岡魚市場株主代表訴訟事件(福岡高裁平成24年4月13日判決)が挙げられます。
この事件では、子会社がぐるぐる回し取引によって不良在庫を抱え、経営破綻しかけていたにもかかわらず、子会社に対して多額の貸付けなどを行った親会社の監視監督責任が問題となりました。福岡高裁は、親会社の取締役が子会社に不明瞭な多額の在庫があるとの報告を受け、その後も在庫や借入金が急速に増加し、状況が一向に改善しないことなどを認識していながら、何らの有効な措置を講じないまま経営破綻の事態が差し迫った状況になった後に、支援と称して貸付けなどを行ったことを指摘し、親会社取締役としての善管注意義務に違反すると判示しています。
この事件の第一審判決の中では、「公認会計士からの指摘を受けた時点で、親会社の取締役として、親会社および子会社の在庫の増加の原因を解明すべく、従前のような一般的な指示をするだけでなく、自ら、あるいは、親会社の取締役会を通じ、さらには、子会社の取締役等に働きかけるなどして、個別の契約書面等の確認、在庫の検品や担当者からの聴き取り等のより具体的かつ詳細な調査をし、またはこれを命ずべき義務があった」との指摘がなされています。現在では、子会社の株式は親会社にとっては財産であり、そのような財産の価値を維持するため、親会社の取締役は一定の範囲で子会社について監視をしなければならないと考えられています。その点から、上記裁判例は、親会社取締役の子会社に対する監督の在り方の参考になる一例といえるでしょう。
3 民事上の責任2:負担は家族にまで及ぶ
これまで見てきたように、取締役の責任は重く、特に不祥事が起こった場合の責任は甚大です。この責任の負担は、取締役本人のみにとどまらず、家族にまで及ぶ可能性があります。それは、高額な賠償額の支払いのため自宅が差し押さえられるということはもとより、取締役が亡くなった場合、その配偶者や子が高額の賠償義務を相続し、多額の負債を負う場合があり得るのです。
限定承認(注)や相続放棄という制度を用いてこの多額の債務を回避することはできますが、限定承認や相続放棄には熟慮期間という期間制限(自分のために相続があったことを知ってから3カ月以内)があり、原則としてその期間内に申立てなければならず注意が必要です(民法第915条第1項、第921条第2号)。
(注)「限定承認」とは、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務などを相続することです(民法第922条)。
4 刑事上の責任
取締役への就任に伴って生じる責任は、民事上の責任にとどまらず、刑事上の責任も生じます。実際にあった事件を参考に説明します。
1)北海道拓殖銀行事件
前述したように、北海道拓殖銀行の頭取が在職中に、実質破綻状態にあったグループ会社3社に対して十分な担保を取らず、融資した事件です。頭取と後任および融資を受けたグループ会社の実質的経営者が特別背任罪に問われ、全員実刑判決が言い渡されました(刑事事件につき札幌高裁平成18年8月31日判決刑集63巻9号1486頁)。
特別背任罪とは、会社法第960条に規定された犯罪で、刑法第247条の背任罪の特別規定で刑法上の背任罪より重く罰するものです。単なる背任罪よりも刑罰が加重されていることからしても、会社役員である取締役の責任の重さが分かるでしょう。取締役が自己や第三者の利益を図りまたは会社に損害を加える目的で、任務に違反し、会社に財産上の損害を与えた場合に成立します。法定刑は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその併科とされています。
また、実刑判決とは、一般に執行猶予が付されない懲役・禁錮刑のことを意味します。実刑判決が下されると、直ちに刑務所に入れられることになるので、執行猶予判決と異なり生活環境が大きく変わるという点で、重い処分といえるでしょう。
2)ライブドア事件
ライブドア社の粉飾決算などにより、元取締役らが旧証券取引法(現金融商品取引法)違反の罪に問われた事件(東京高裁平成20年7月25日判決判時2030号127頁、東京高裁平成20年9月12日判決)です。財務等に関する業務を統括していた元取締役に対して、懲役1年2カ月の実刑判決が言い渡されました。
3)ミートホープ事件
食肉製造加工会社のミートホープ社が、実際には豚肉や鶏肉などを混入した牛ひき肉を、牛肉のみを原料とするかのような表示をして製造・販売したとして、詐欺罪、不正競争防止法違反(虚偽表示)の罪に問われた食肉偽装事件(札幌地裁平成20年3月19日判決)で、同社元社長に、懲役4年の実刑判決が言い渡されました。
5 会社における対策
1)不祥事を防ぐ施策
まずは、会社の不祥事を未然に防ぐ策を施すこと、つまり不祥事を予防するためにリスク管理体制を徹底することが大切になります。会社法も、大会社(会社法第2条第6号)と指名委員会等設置会社(会社法第2条第12号)において、「内部統制システム」と呼ばれるリスク管理体制の構築・運用を、取締役会の義務として定めています(大会社については会社法第362条第5項および第4項第6号、指名委員会等設置会社については第416条第1項第1号ホおよび第2項)。
前述したように、取締役はその職責として、会社業務の適正を確保しなくてはなりません。しかし、事業が複雑化した大会社や指名委員会等設置会社では、体制としてリスク管理のシステムを構築しなければ、会社業務の適正を確保することは困難です。そこで、会社法では大会社や指名委員会等設置会社について、会社業務の適正確保という取締役の義務が全うされるよう、内部統制システムの構築を求められているわけです。
もっとも、法律上は、不正な行為を防止するために具体的にどのような内部統制システムを採用すべきかについてまでは規定されておらず(会社法施行規則第100条第1項各号参照)、各社の判断に委ねられています。これは、内部統制システムが、その会社の業務において想定されるリスク、想定リスクの現実化による事件・事故といった経験の蓄積、各社内でのリスク管理に関する研究の進展などといった、会社ごとの事情により充実していくシステムであるとされているからです。
従って、内部統制システム構築義務を負わない会社の取締役であれば、極端な話、内部統制システムを構築する必要がないと判断することも、それがその会社の実態に即した判断である限り許されるわけです。確かに、内部統制システムは、構築して運用するにはコストが掛かり、自由な組織風土を損ねる恐れもあります。内部統制システムを構築するかどうかも含め、自身の会社が置かれている状況やさまざまなバランスを考慮し、より良いリスク管理体制を模索していくことは、経営のプロフェッショナルである取締役の判断に委ねられているのです。
ここで内部統制システムの例としては、内部通報制度に関する規定や、担当窓口を設けるという方法があります。会社で不正な行為があった場合、やはり最初に気付くのは内部の人間であることが多くなります。内部通報制度が機能していれば、会社における不正行為によって、会社に甚大な損害が生じる前に食い止められる可能性が高まります。
また、不正防止委員会や担当者を置くという方法、コンプライアンス規定を定めて定期的に取締役や従業員に研修を行うという方法も考えられます。取締役は、予算や会社の組織風土などを考慮した上で、会社の実態に沿った内部統制システムを構築することになります。
昨今、個人情報や企業秘密の流出による不祥事が問題に上がることが多いですが、そのようなケースでは、現場の従業員を情報セキュリティー管理責任者に任命する、管理体制について第三者からのアドバイスを受けられるように諮問委員会を設置する、全ての派遣会社および従業員に対して集合教育・eラーニングテストなどによる個人情報保護教育を実施するなどといった措置が、内部統制システムの例として考えられます。
ただし、取締役は「他社もやっているから自社も」というのではなく、あくまで「自社にはこのやり方が合う」という見方で判断する必要があります。
2)顕在化した責任を軽減する施策
次に、実際に顕在化したリスクを軽減する策を施すことが考えられます。株式会社の取締役は会社との委任契約に基づいて会社に対する責任を負うため、不祥事が起きると会社から損害賠償を請求されてしまいます(会社法第423条)。
これに対しては、法律上の対策と事実上の対策が考えられます。まず法律上の対策として挙げられるのが、会社法第424条から第427条までに定められている責任免除ないし限定措置です。会社法第424条は、責任の全部免除について定めていますが、それには総株主の同意を得る必要があるとされており、現実的にはほとんど不可能と言わざるを得ません。
一方、会社法第425条および第426条は、責任の一部免除について定めており、株主総会特別決議または定款の定めに基づく取締役会決議を要する点で、決して容易な手段ではありませんが、全部免除よりは現実的な方法で、実際に利用されることもあります。なお、会社法第427条は、非業務執行取締役等の責任を限定する契約について規定しており、非業務執行取締役等はこの責任限定契約を事前に結ぶことで、多額の損害賠償債務を圧縮することができます。
また、実際に訴訟を提起されてしまった場合の対策としては、あらかじめ会社役員賠償責任保険(D&O保険)に加入しておくことや、請求額よりも低額による和解をすることなどが考えられます。会社役員賠償責任保険への加入は、米国のような訴訟社会では一般的のようですが、日本ではまだそれほど普及はしていません。しかし、最近の取締役の責任厳格化の傾向からすると、日本でも会社役員賠償責任保険への加入を真剣に考えるべき段階に至っているといえるでしょう。
6 まとめ
取締役の責任の重さは、権限の大きさの裏返しでもあります。前述した経営判断原則が一般的に承認されているのは、取締役にはその権限をフル活用し、時にはリスクを冒して、より良い経営を行うことが求められているからに他なりません。近年の取締役の責任厳格化の流れの中では、不祥事を起こさない十分なリスク管理体制の構築と、不祥事が起こってしまったとしても責任をなるべく軽減できるよう、対策をしっかり取って、取締役が萎縮することなく経営を行う環境を整えることが求められているといえるでしょう。
以上(2019年4月)
(監修 弁護士法人 法律事務所オーセンス 弁護士 佐藤駿介)
pj60069
画像:unsplash