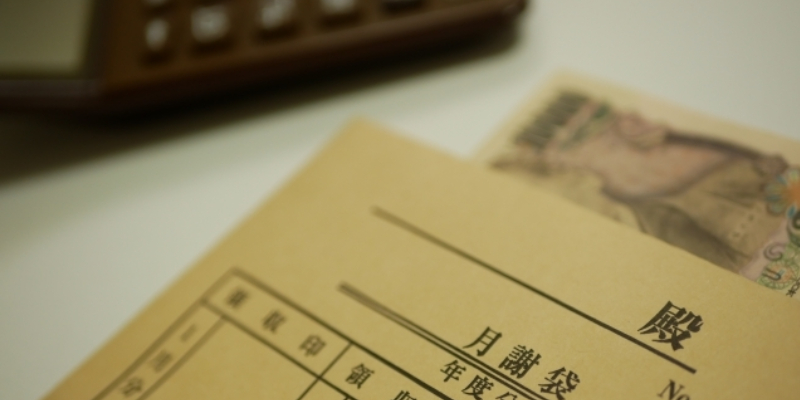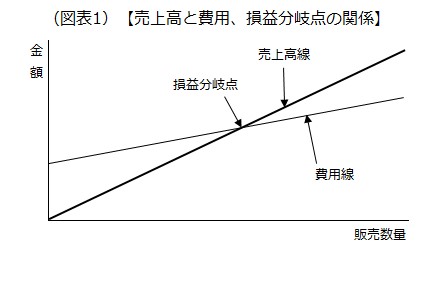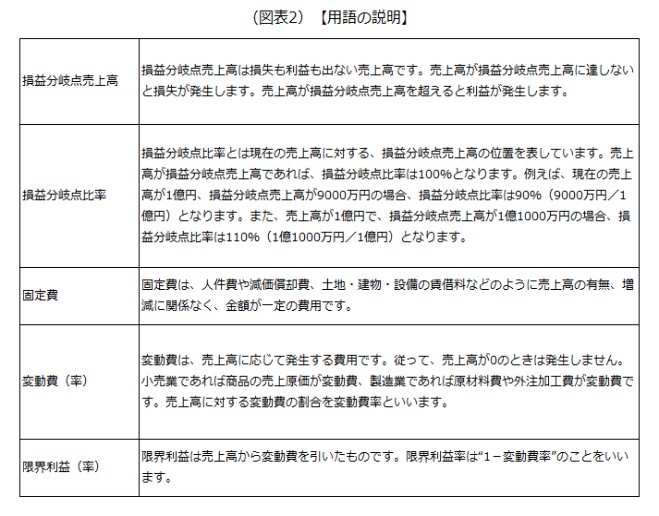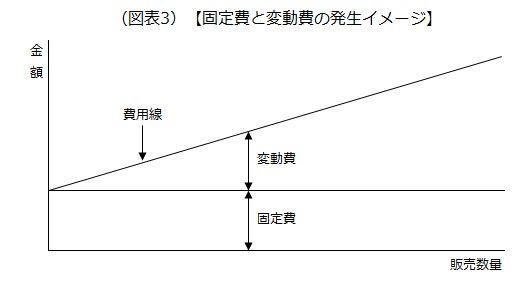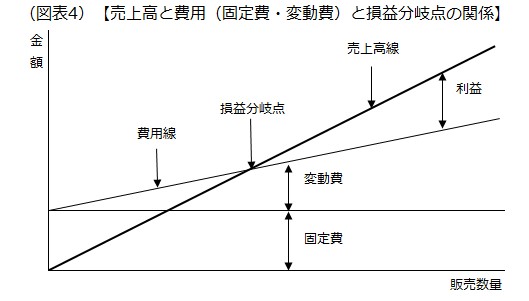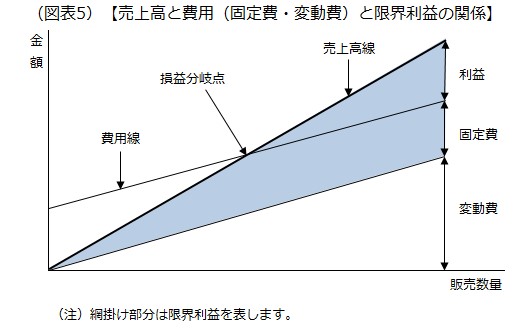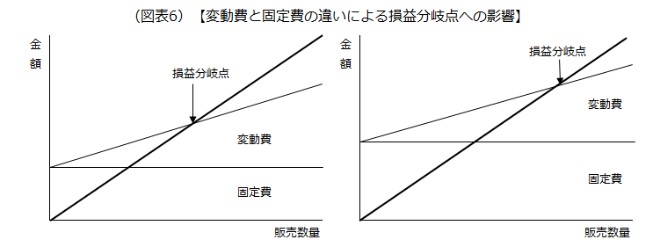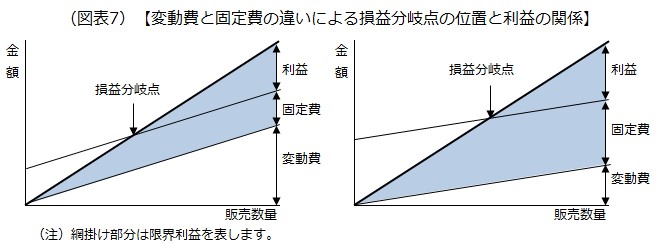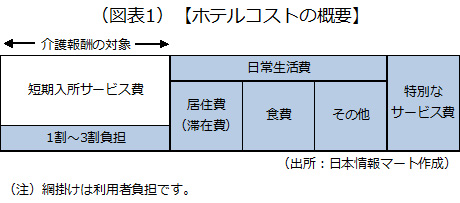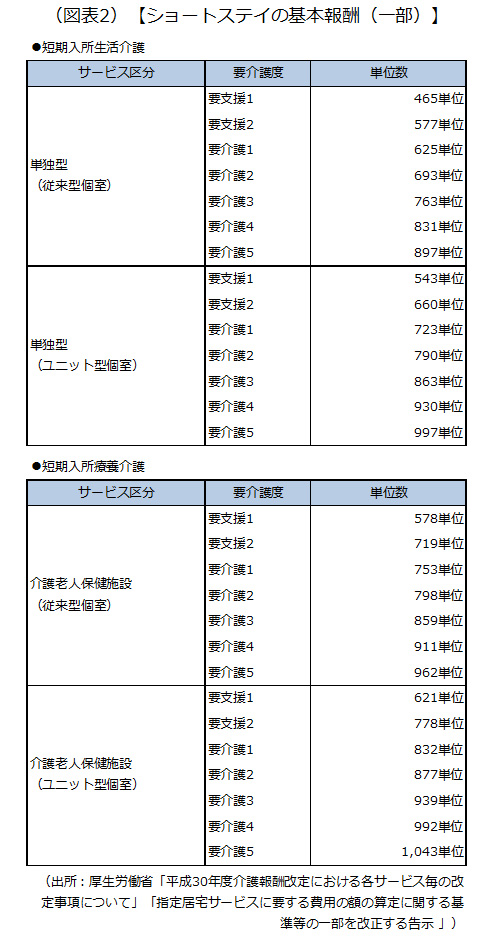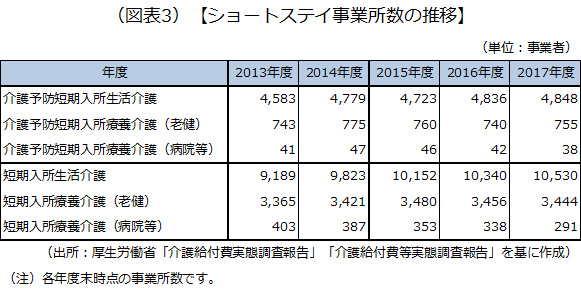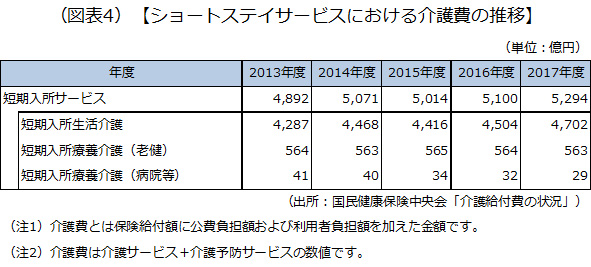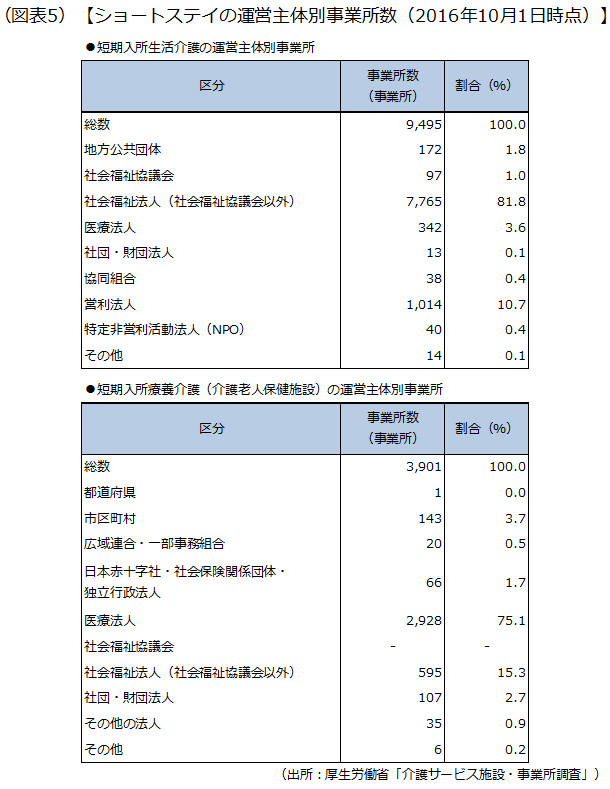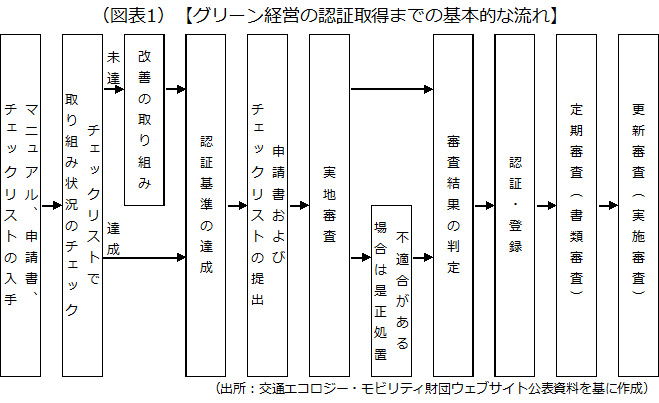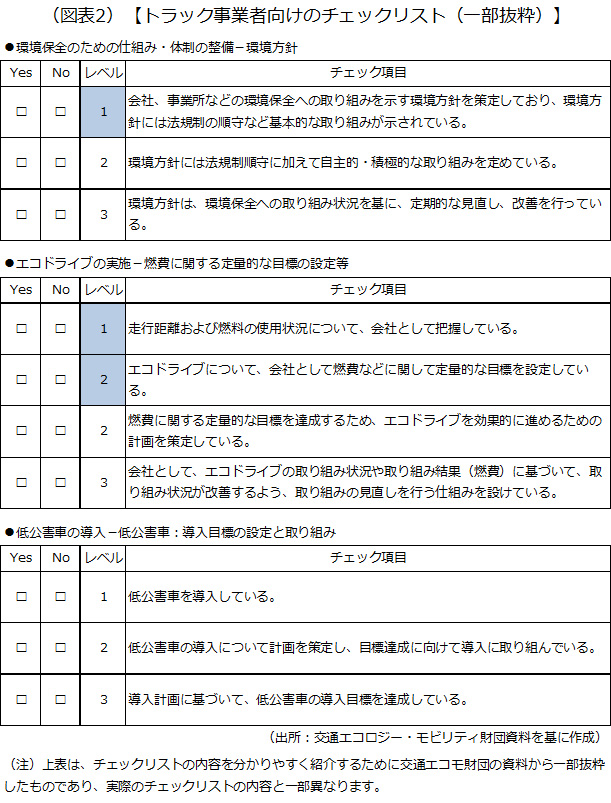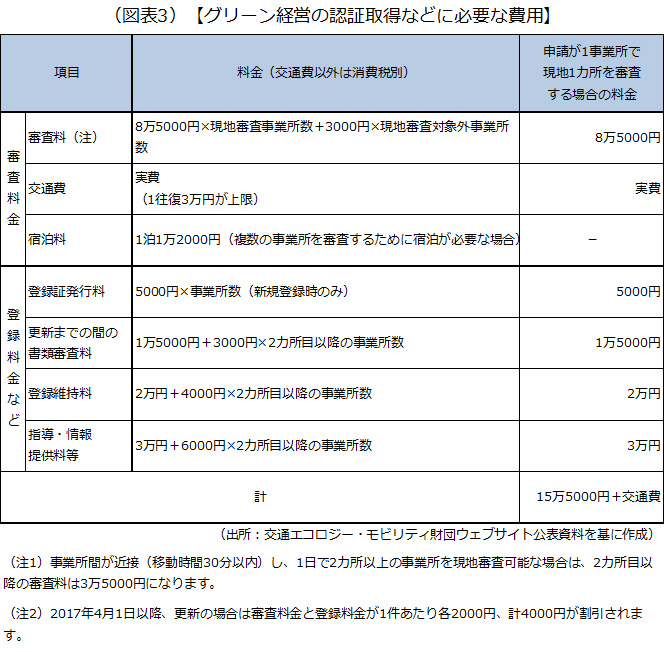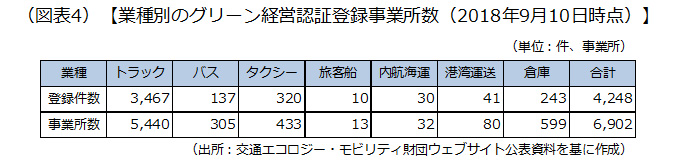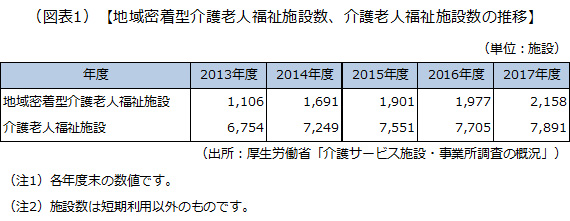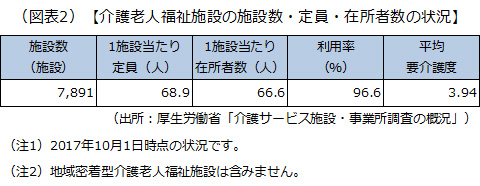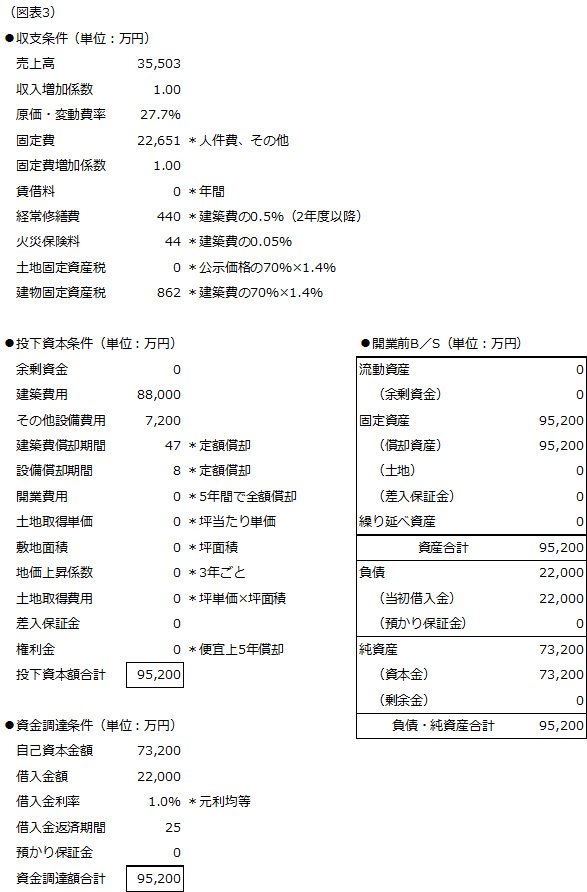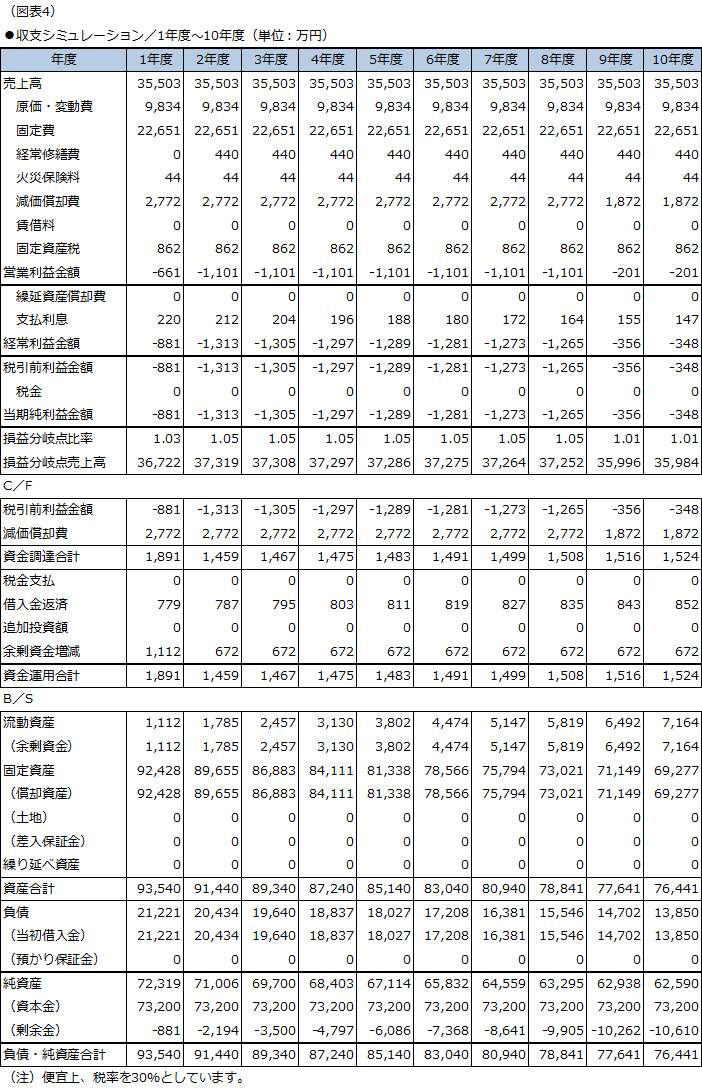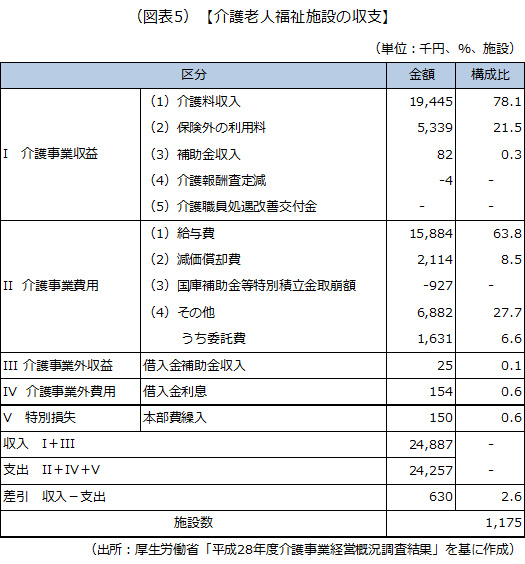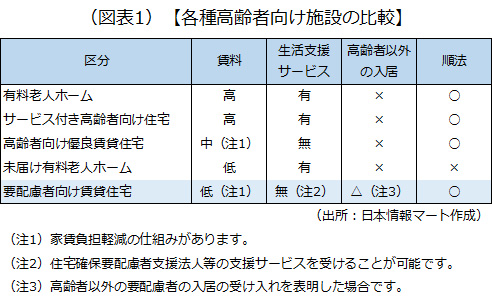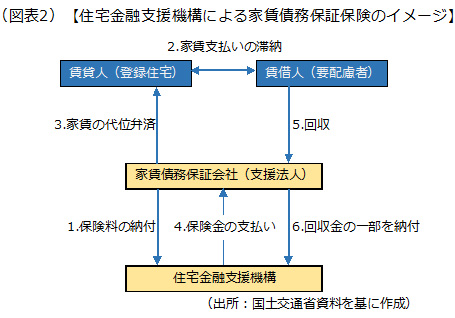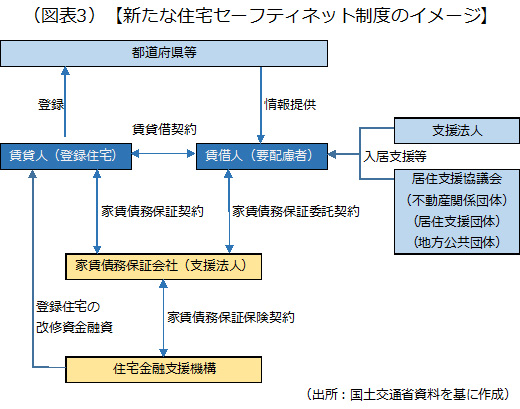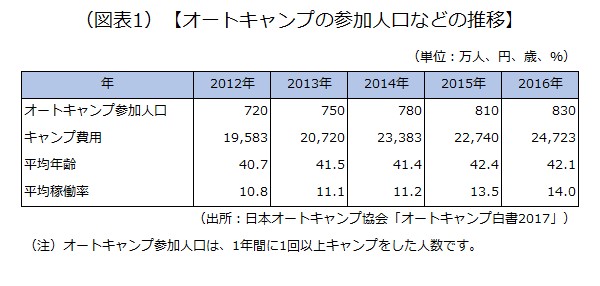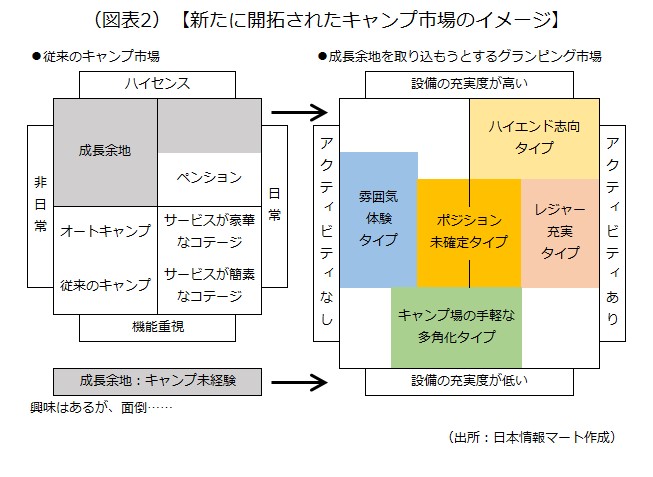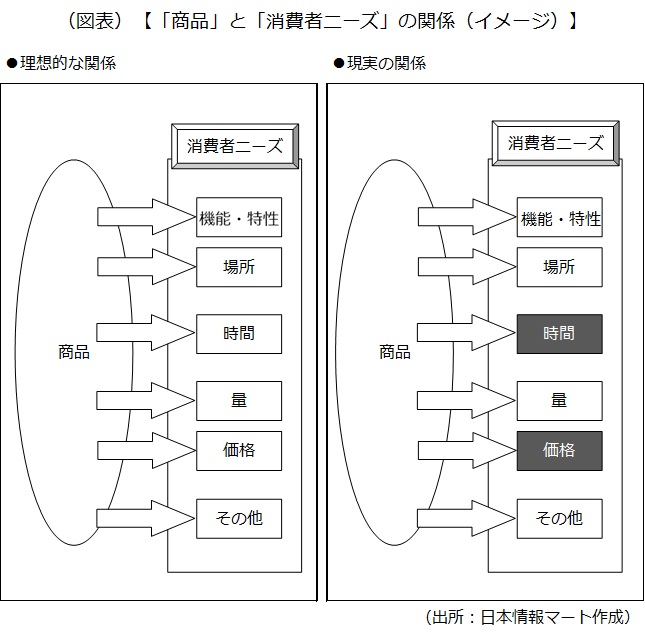書いてあること
- 主な読者:適正な税務処理を徹底したい経営者・税務担当者
- 課題:入会金や会費は内容によっては、税務上役員報酬や給与とみなされることがある
- 解決策:ゴルフクラブの入会金や同業団体の会費など、会社で発生する主な入会金や会費を抜粋して、税務上の取り扱いを解説
1 ゴルフクラブの入会金など
1)ゴルフクラブの入会金
法人がゴルフクラブに対して支出した入会金については、次のいずれかの場合に応じて処理します(法人税基本通達9-7-11)。
1.法人会員としてゴルフクラブに入会するケース
法人会員として入会する場合、入会金は資産として計上します。
ただし、記名式の法人会員で名義人として特定の役員または使用人が法人の業務に関係なく利用するため、これらの者が負担すべきものであると認められるときは、当該入会金に相当する金額は、これらの者に対する給与とします。
2.個人会員としてゴルフクラブに入会するケース
個人会員として入会する場合、入会金は個人会員たる特定の役員または使用人に対する給与とします。
ただし、無記名式の法人会員制度が無いため個人会員として入会し、その入会金を法人が資産に計上した場合、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人の負担すべきものであると認められるときは、その会計処理を認めます。
入会金はゴルフクラブに入会するために支出する費用なので、他人の有する会員権を購入した場合、その購入代価の他、他人の名義を変更するためにゴルフクラブに支出する費用も含まれます。
2)資産に計上した入会金の処理
法人が資産に計上した入会金は償却を認められていません。しかし、ゴルフクラブを脱退してもその返還を受けることができない場合、当該入会金に相当する金額およびその入会金に係る譲渡損失に相当する金額は、脱退または譲渡をした日の属する事業年度の損金の額に算入します(法人税基本通達9-7-12)。
3)年会費その他の費用
法人がゴルフクラブに支出する年会費、年決めロッカー料その他の費用(その名義人を変更するために支出する名義書換料を含み、プレーする場合に直接要する費用を除く)については、「入会金が資産として計上されている場合には交際費」とし、「入会金が給与とされている場合には会員たる特定の役員または使用人に対する給与」とします(法人税基本通達9-7-13)。
プレーする場合に直接要する費用については、入会金を資産に計上しているかどうかにかかわらず、その費用が法人の業務の遂行上必要なものであると認められる場合には交際費とし、その他の場合には当該役員または使用人に対する給与とします。
4)レジャークラブの入会金
前述の「ゴルフクラブの入会金」および「資産に計上した入会金の処理」の取り扱いは、法人がレジャークラブに対して支出した入会金について準用します。
ただし、レジャークラブ会員としての有効期間が定められており、かつ、その脱退に際して入会金相当額の返還を受けることができないものとされているレジャークラブに対して支出する入会金(役員または使用人に対する給与とされるものを除きます)については、繰延資産として償却することができます(法人税基本通達9-7-13の2)。
レジャークラブとは、宿泊施設、体育施設、遊技施設その他のレジャー施設を会員に利用させることを目的とするクラブで、ゴルフクラブ以外のものをいいます。
年会費その他の費用は、その使途に応じて交際費または福利厚生費もしくは給与となることに留意を要します。
施設を利用する人が特定の役員や社員だけの場合は、入会金も年会費も給与になります。また、特定の社員の他に取引先の接待などに使えば、年会費は交際費になります。そして、施設を従業員全員が平等に使えるのならば、年会費は福利厚生費になります。
2 社交団体の入会金など
1)社交団体の入会金
法人が社交団体(ゴルフクラブおよびレジャークラブを除きます)に対して支出する入会金については、次の各場合に応じて処理します(法人税基本通達9-7-14)。
1.法人会員として入会する場合
法人会員として入会する場合、入会金は支出の日の属する事業年度の交際費とします。
2.個人会員として入会する場合
個人会員として入会する場合、入会金は個人会員たる特定の役員または使用人に対する給与とします。ただし、法人会員制度がないため個人会員として入会した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であると認められるときは、その入会金は支出の日に属する事業年度の交際費とします。
2)社交団体の会費など
法人がその入会している社交団体に対して支出した会費その他の費用については、次の区分に応じて処理します(法人税基本通達9-7-15)。
1.経常会費
経常会費については、その入会金が交際費に該当する場合には交際費とし、その入会金が給与に該当する場合には会員たる特定の役員または使用人に対する給与とします。
2.経常会費以外の費用
経常会費以外の費用については、その費用が法人の業務の遂行上必要なものであると認められる場合には交際費とし、会員たる特定の役員または使用人の負担すべきものであると認められる場合には当該役員または使用人に対する給与とします。
3)ロータリークラブおよびライオンズクラブの入会金など
法人がロータリークラブまたはライオンズクラブに対する入会金または会費などを負担した場合には、次によります(法人税基本通達9-7-15の2)。
1.入会金または経常会費として負担した金額
入会金または経常会費として負担した金額は、その支出をした日の属する事業年度の交際費とします。
2.それ以外に負担した金額
それ以外に負担した金額は、その支出の目的に応じて寄附金または交際費とします。
ただし、会員たる特定の役員または使用人の負担すべきものであると認められる場合には、当該負担した金額に相当する金額は、当該役員または使用人に対する給与とします。
3 同業団体の会費など
1)同業団体などの会費
法人がその所属する協会、連盟その他の同業団体などに対して支出した会費の取り扱いについては次によります(法人税基本通達9-7-15の3)。
1.通常会費
同業団体などがその構成員のために行う広報活動、調査研究、研修指導、福利厚生その他同業団体としての通常の業務運営のために、経常的に要する費用の分担額として支出する通常会費については、支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入します。
ただし、当該同業団体などにおいてその受け入れた通常会費につき不相当に多額の剰余金が生じていると認められる場合には、当該剰余金が生じたとき以後に支出する通常会費については、当該剰余金の額が適正な額になるまでは、前払費用として損金の額に算入しないものとします。
同業団体などの役員または使用人に対する賞与または退職給与の支給に充てるために引き当てられた金額で適正と認められるものは、剰余金の額に含めないことができます。
2.その他の会費
同業団体などが次に掲げるような目的のために支出する費用の分担額として支出する会費については、前払費用とし、当該同業団体などがこれらの支出をした日にその使途に応じて当該法人がその支出をしたものとします。
- 会館その他特別な施設の取得または改良
- 会員相互の共済
- 会員相互または業界の関係先などとの懇親など
- 政治献金その他の寄附
通常会費として支出したものであっても、その全部または一部が当該同業団体などにおいて上記のような目的のための支出に充てられた場合には、その会費の額のうちその充てられた部分に対応する金額については、その他の会費に該当します。
ただし、その同業団体などにおける支出が当該同業団体などの業務運営の一環として通常要すると認められる程度のものである場合には、この限りでありません。
2)災害見舞金に充てるために同業団体などへ拠出する分担金など
法人が、その所属する協会、連盟その他の同業団体などの構成員の有する事業用資産について災害により損失が生じた場合に、その損失の補てんを目的とする構成員相互の扶助等に係る規約など(災害の発生を機に新たに定めたものを含む)に基づき、合理的な基準に従って当該災害発生後に当該同業団体などから賦課され、拠出した分担金などは、支出した日の属する事業年度の損金の額に算入します(法人税基本通達9-7-15の4)。
以上(2019年4月)
(監修 税理士法人コレド会計 石田和也)
pj30016
画像:photo-ac