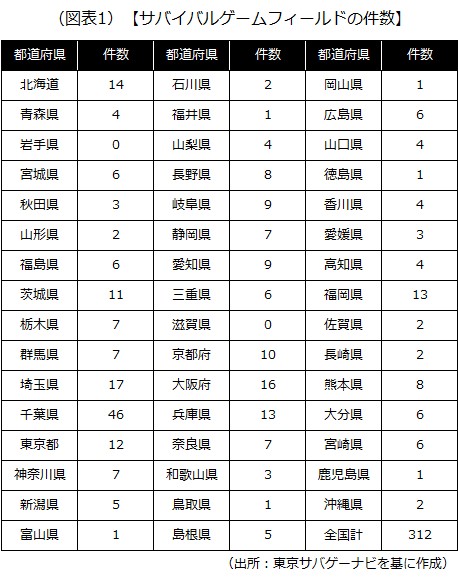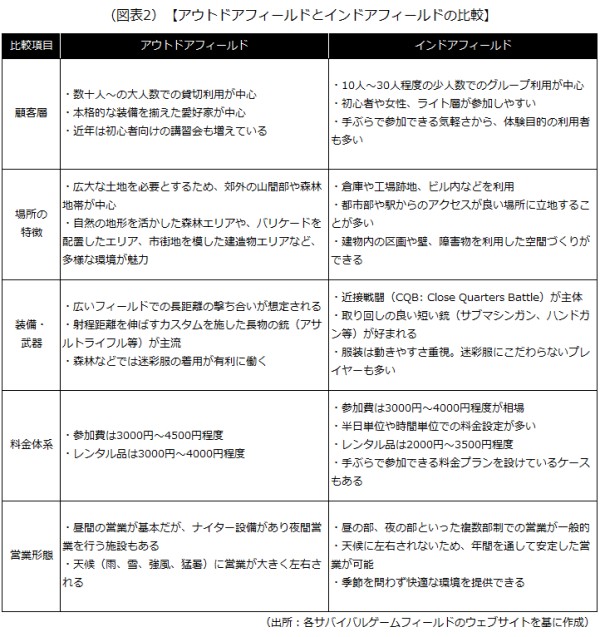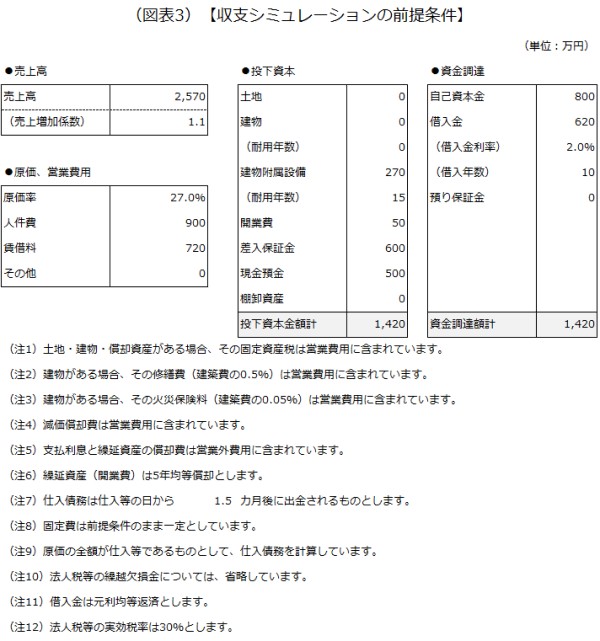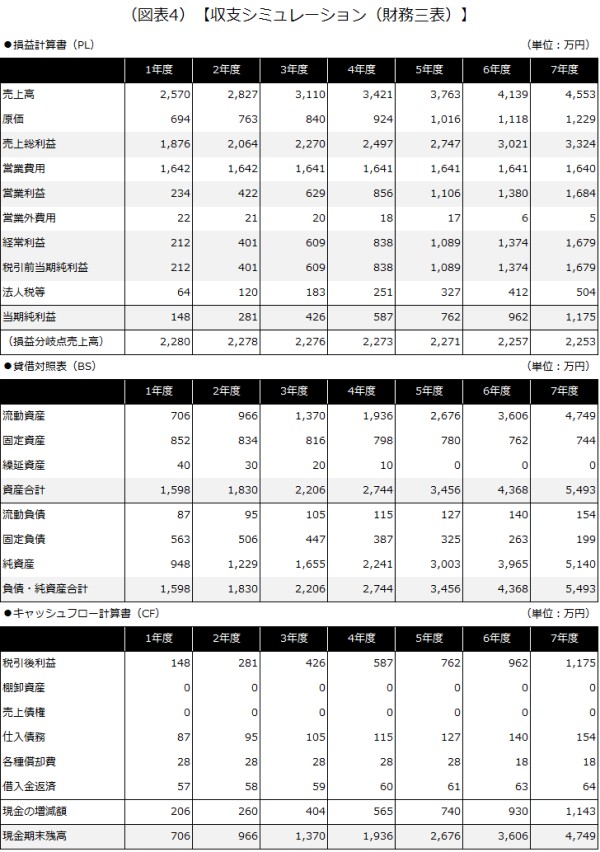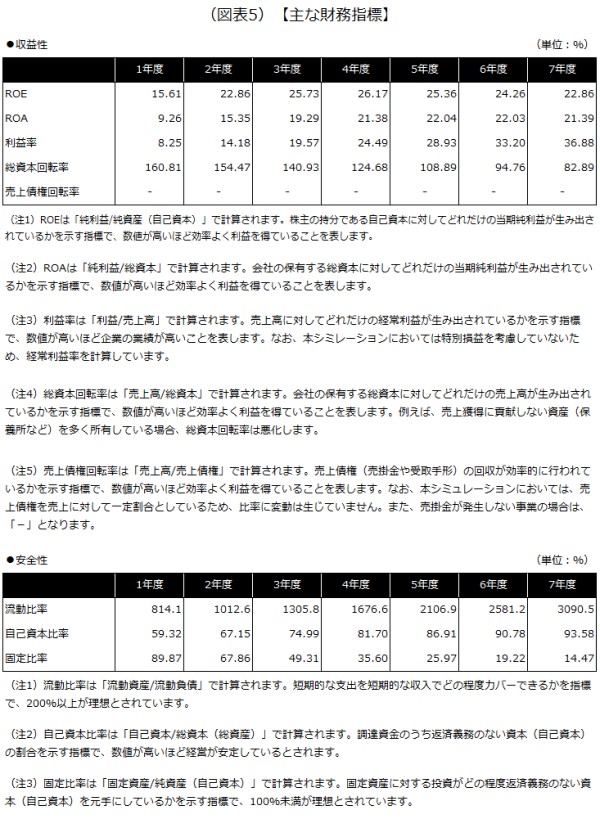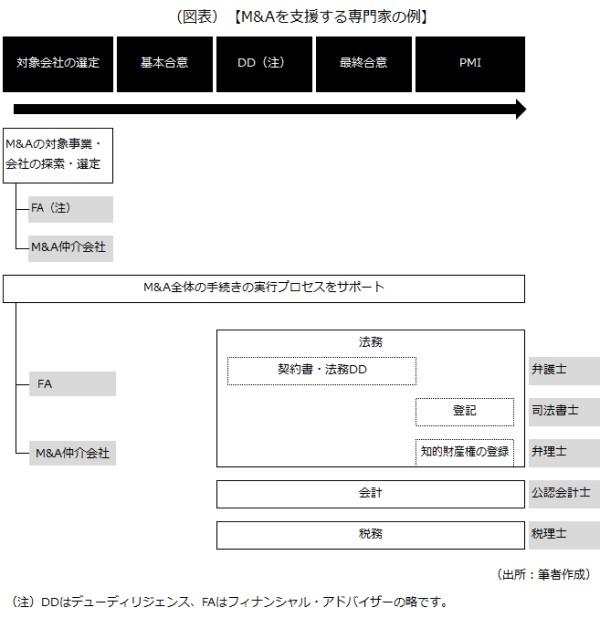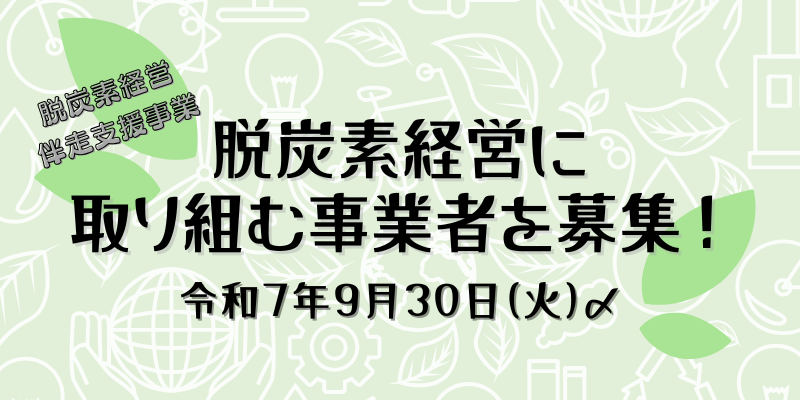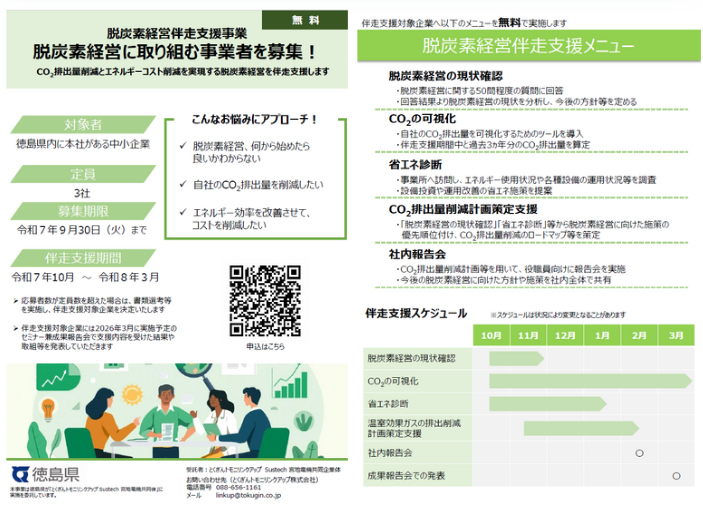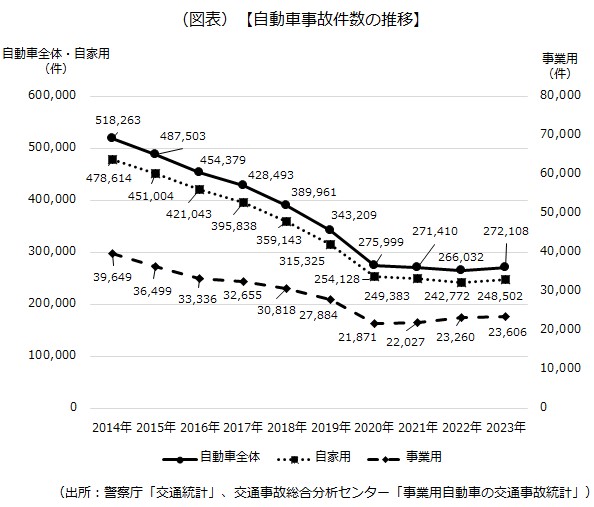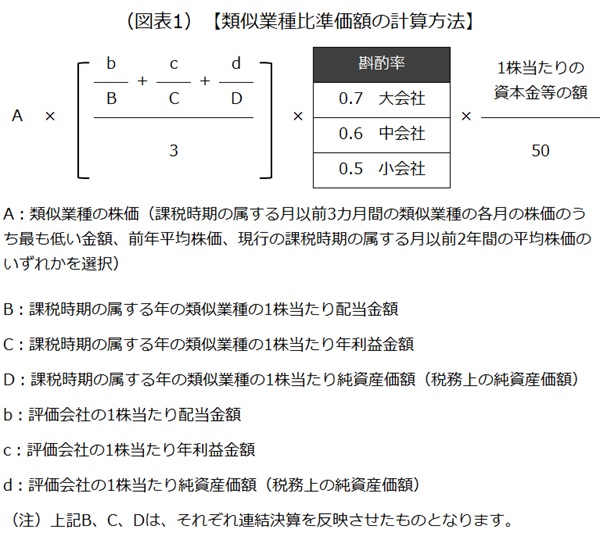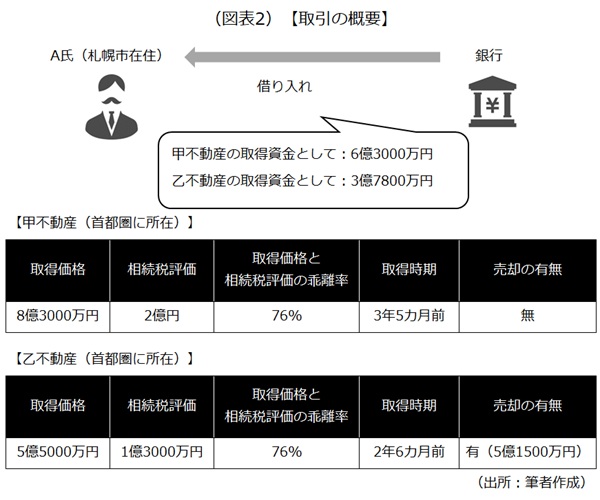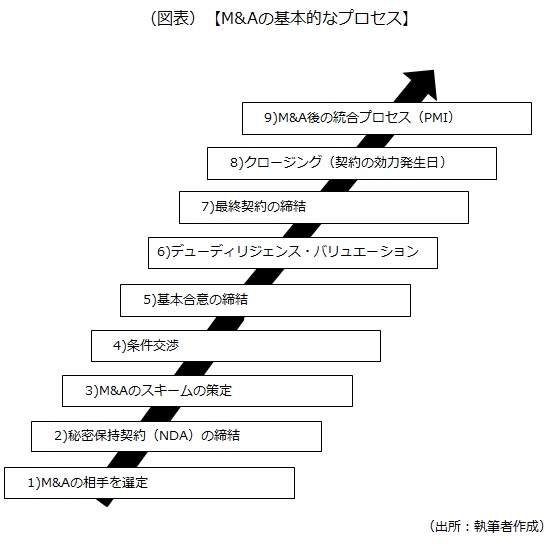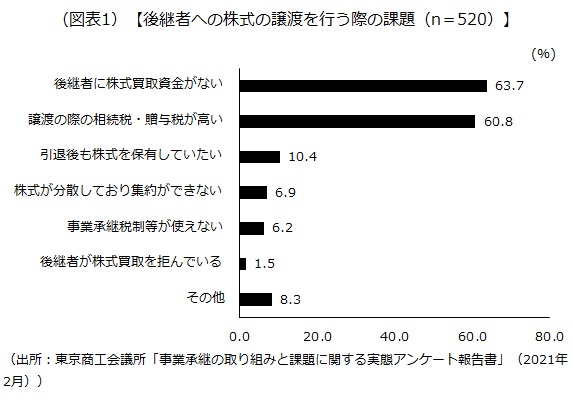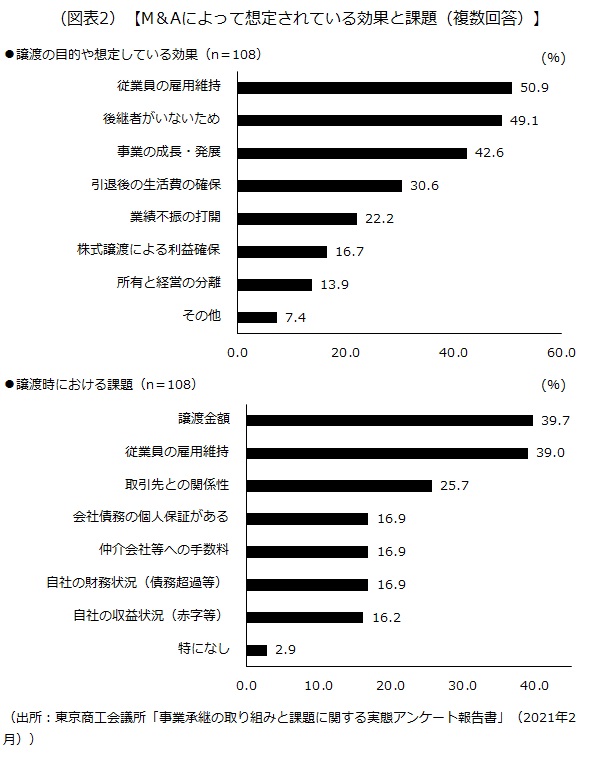1 建設業の担い手確保に向けて
建設業者は、地域のインフラや住居・オフィス・商業施設の建設を担う重要な存在でありながら、他の産業よりも賃金が低く、就労時間も長いという課題があります。
一方で、2024年4月1日から労働基準法の「時間外労働の上限規制」が建設業にも適用されるようになったこと(いわゆる「2024年問題」)等を受けて、これまでのような長時間労働に依存した働き方も難しくなり、建設業の担い手を一刻も早く確保する必要が出てきています。
そんな中、建設業の担い手確保に向けて、2024年6月14日に改正建設業法・入契法が公布され、2025年12月13日までに全面施行されることとなりました(2025年9月現在、すでに施行済みの内容もあります)。ポイントは大きく次の3つに分けられます。
- (ポイント1)処遇改善
- (ポイント2)資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止
- (ポイント3)働き方改革・生産性向上
以降で簡単にポイントを紹介します。より詳しく知りたい場合は、国土交通省のウェブサイトをご確認ください。
■国土交通省「建設業法・入契法改正(令和6年法律第49号)について」■
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk1_000001_00033.html
2 (ポイント1)処遇改善
1)労働者の処遇確保の努力義務化
建設業者に対し、労働者の処遇を確保する「努力義務」が課せられます。具体的には、
- 労働者の能力(知識や技能)を公正に評価して、適切な賃金を支払うこと
- その他、労働者の処遇を確保するための措置を効果的に実施すること
が求められるようになります。
2)不当に金額の低い見積もり提出・見積もり依頼の禁止
また、労務費(賃金原資)について、国土交通省の中央建設業審議会が「労務費の基準」を作成・勧告することになりました。そして、この基準に照らして、
著しく低い材料費等による見積もり提出・見積もり依頼が禁止
されるようになります。
この規定に違反した場合、発注者は国土交通大臣による勧告・公表の対象、受注者は指導・監督の対象となります。特に重要なのが「公表」です。従来の規制下では、不適切な契約が結ばれても、受注者側が泣き寝入りするケースが多くありました。しかし、今回の改正により、不当に低い労務費の見積りを依頼した発注者の名称が公表されることになります。
3)原価割れ契約の禁止
この他、建設工事の請負契約について、
建設業者がその地位を利用して、原価に満たない金額で契約を締結することが禁止
されます。ただし、自ら保有する安価な資材を工事に用いることができる等、正当な理由がある場合を除きます。
3 (ポイント2)資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止
1)契約締結前のルールの追加
請負契約の締結前のルールとして、
受注者が注文者に、資材高騰等の請負金額に影響を及ぼすリスクの情報(おそれ情報)を通知すること
が義務付けられます。おそれ情報には、必要な資材の供給不足や価格高騰、特定の建設工事における労働者不足等が含まれます。また、
おそれ情報と併せて、状況把握のために必要な情報(根拠情報)を通知すること
も求められます。根拠情報は、メディアの記事、資材業者の記者発表、公的機関による統計資料等一定の客観性を有するものである必要があります。
さらに、契約締結後に予期せぬ事態が発生した際の協議を円滑に進めるためのルールとして、
資材が高騰した際の請負代金等の「変更方法」を、契約書記載事項として明確に定めること
が義務付けられます。
2)契約締結後のルールの追加
請負契約の締結後のルールとして、
- 実際に資材の価格高騰等が起きた場合、受注者が注文者に、請負代金等変更について協議を申し出ることができること
- 注文者は、受注者から協議の申し出があったら、誠実に応じる努力義務を負うこと
が定められます。協議すること自体を正当な理由なく拒絶したり、協議の開始をあえて著しく遅らせたり、受注者の主張を一方的に否定したり、十分に聞き取らずに協議を打ち切ったりすると、「誠実」に協議に応じていないと判断されます。
4 (ポイント3)働き方改革・生産性向上
1)働き方改革
いわゆる工期ダンピング(建設工事を施工するために通常必要とされる期間よりも著しく短い工期を設定する請負契約)への規制が強化されます。
もともと注文者については、工期が著しく短い請負契約を締結することが禁止されていますが、このルールが受注者側にも適用
されるようになります。受注者自らが無理な工期設定を提案することを抑制し、長時間労働の温床を根本から絶つのが狙いです。
また、
- 受注者が注文者に、資材が入手困難になる等工期に影響を及ぼすリスクの情報を通知する義務を負うこと
- 通知を受けた注文者は、工期の調整について誠実に協議に応じる努力義務を負うこと
が定められます。
2)生産性向上
本来、公共性があったり、多くの人が利用したりする建物の建設工事では、専任の監理技術者等を置くことが義務付けられていますが、
ICT(情報通信技術)を活用することを条件に、専任者の設置義務が緩和
されます。ICTの活用例としては、
- タブレット端末を通じた設計図面や現場写真等の共有
- ウェアラブルカメラ等による現場のリアルタイム映像・音声の共有
等が挙げられます。ただし、ICTの活用と併せて「現場間の移動時間が概ね2時間以内であること」等の要件も満たす必要があります。
以上(2025年9月作成)
pj50566
画像:metamorworks-Adobe Stock