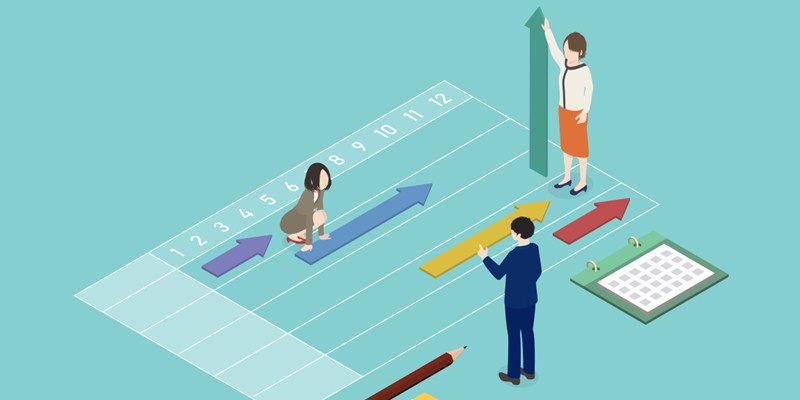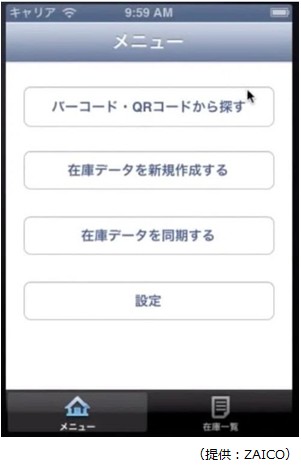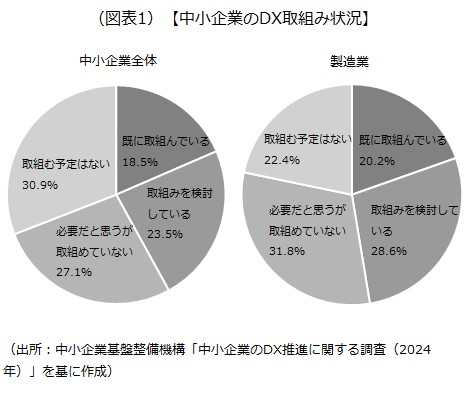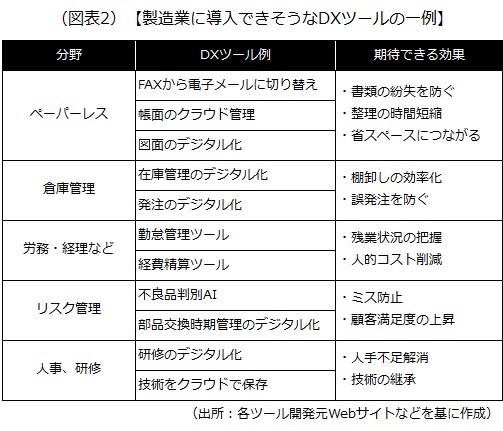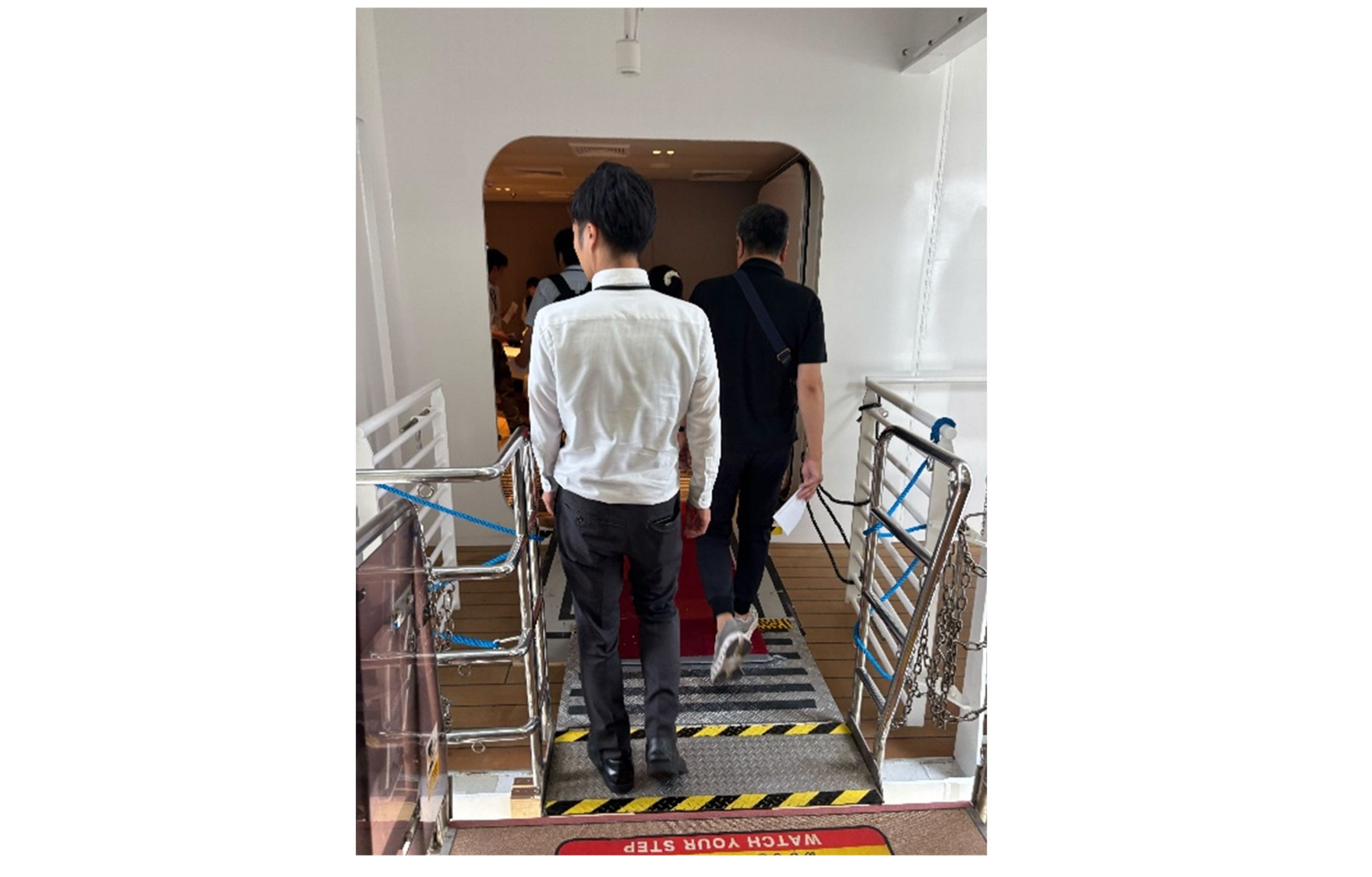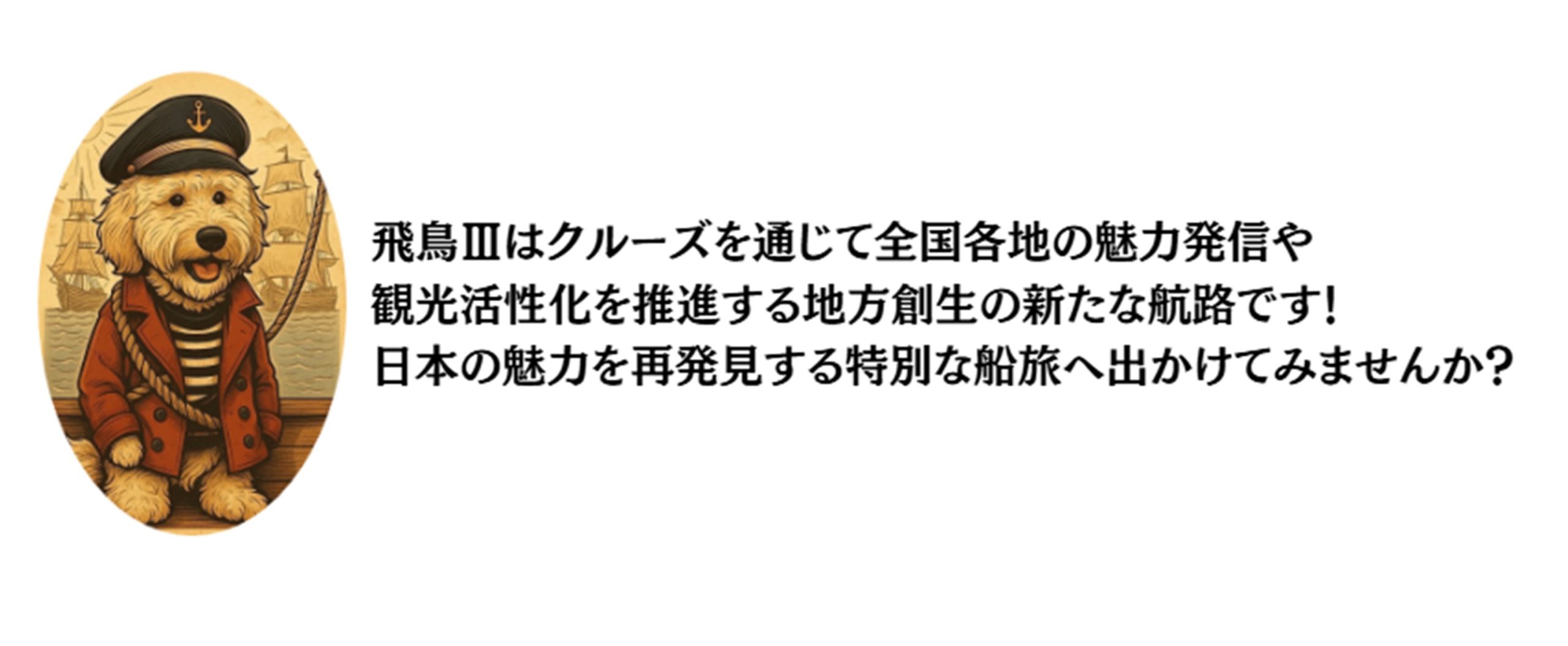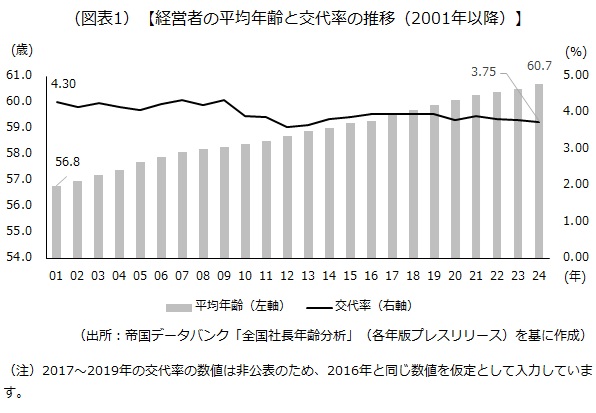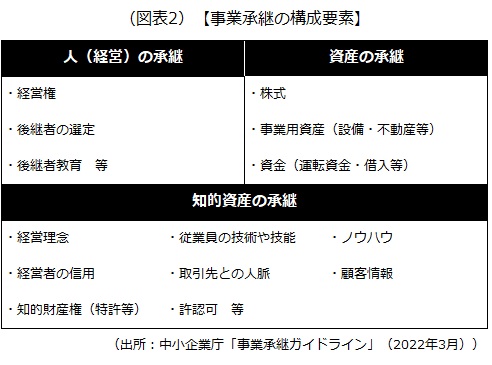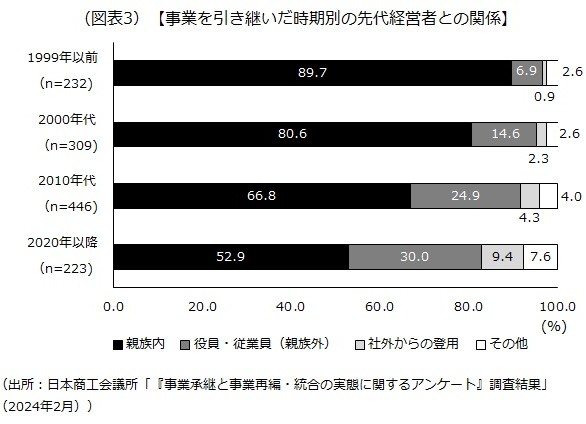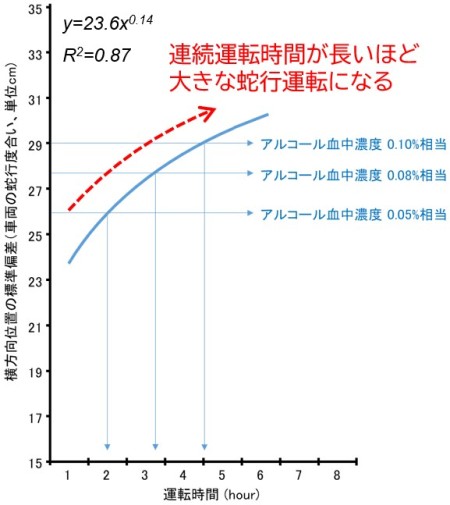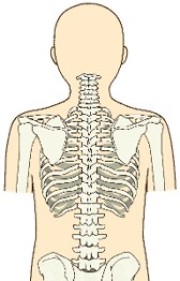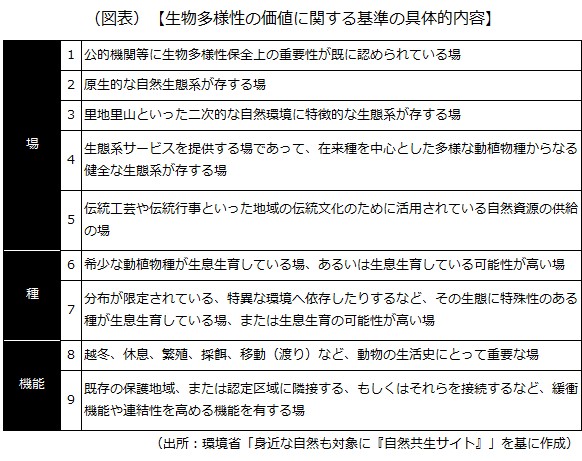1 10のヒントは、自社を「辞める理由」または「辞めない理由」
今回から、「社員を採ってもすぐに辞めてしまう上に、そもそも採れない」という経営者、人事担当者、現場のお悩みを解決するためのヒントを、毎回1つずつご紹介していきます。
第1回でお話ししたように、
解決策は会社や職場によってさまざまだと思います。が、簡潔に言えば退職する一人ひとりの「辞める理由」を解消し、働いている一人ひとりの「辞めない理由」を高めていくことです。
毎回ご紹介していく10のヒントは、裏返せば多くの場合、「辞める理由」あるいは「辞めない理由」になっています。それぞれが自社にとっては採用や早期退職問題を解決するための“課題”なのか“強み”なのかを見極めていきましょう。
さて、『人が辞めない会社、10のヒント』を、どの順番でお話ししていくといいでしょうか。「多くの会社が抱えていそうな原因」を優先するか、「比較的取り組みやすそうな原因」から始めるべきか。
ここは「時系列」でお話ししていくことにします。つまり、人材が会社の門をたたき、出て行くまでの流れに沿ってという意味です。入社してからは、退職につながるいろいろな原因が同時に発生することも多いので、項目を整理しながら取り上げるようにします。
あらかじめご注意いただきたい点があります。時系列で毎回1つずつお話ししていくので、当初のヒントが皆さんの会社の抱える問題の原因に当てはまらない可能性もあります。
ですが、そこで「役に立たない」と読むのをやめないでください。ヒントの1~9までが該当しなくても、10が当てはまるかもしれません。
原因が1つだけというケースは少ないので、何回分か読んでいただければ「これはうちにも当てはまるな」というものが見つかるだろうと思います。
逆に「今回は該当しないようだ」ということでしたら、それはそれで1つの気付きです。その回は途中で読み飛ばしていただいて構いません。
10のヒントの初回となるヒント1は、会社と人材との出会いの場面から始めます。それは、“出会いがそもそも間違っているかもしれませんよ”というお話です。
2 本当に「採用したい人」が応募してくれていますか?
会社と人材との出会い、すなわち「採用活動」は、「応募者を集める」、そこから「候補者を絞り込む」、最終的に「採用予定者に内定を出して入社してもらう」という流れになります。
ここで会社や人事が意外に見落としがちなことがあります。それは「そもそも応募者が、会社にとって本当に採用したい人なのか」という点です。
各社の採用を支援していると、例えば新卒では「今年は去年よりたくさん応募者が集まった」とか「今年はいい大学からたくさん応募があった」と喜んでいる採用担当者の声を聞きます。
私からすればちょっと心配になります。人数が多かろうと、東大生が10人応募してこようと、彼らが自社の採用したい人かどうかは分からないからです。
最悪の場合、人数も有名大学からの学生も多いのに、採用したい人が一人もいなかったなんてこともあり得ます。
担当者は心の中では「ちっとも採用したい人がいないなあ」と思いながらも内定を出して、上司や会社に「今年はたくさん採れました」「今年は〇〇大と〇〇大が〇人もいます」と報告するのでしょうか。
採用したい人ではないけれど採用するのは、例えて言えば「好きじゃない相手と結婚する」のに似ています。こちらが好きじゃないのは相手にすぐに伝わります。一緒になったとて、相手はこの人と末永く一緒にいたいと思ってくれるでしょうか。
会社にとっての「採用したい人か」と同じように、応募者にとっても本当に「入りたい会社か(やりたい仕事か)」という問題があります。
「本当は入りたい会社(やりたい仕事)ではなかったけれど、いろいろな理由で決めてしまった」とすればどうでしょう。それはいずれ会社にも伝わりますし、仕事にも表れてくるでしょう。
新卒採用の場合は、応募者である学生がまだ社会との接点が少ないため「入ってみたら自分に合っていた」というケースはあります。また、社内の教育制度を通して「慣れたし、この会社(仕事)でよかった」というケースもありますが、かなり偶然の世界です。
このようにお話しすると、「では採用したい人が含まれているかどうかを、どうやって判断すればいいのだ」と質問されそうです。私に言わせれば、それは募集の仕方でも分かりますし、応募者と会って少し話せばすぐに分かります。
はたして応募者に「採用したい人」がたくさん含まれるようにするにはどうすればいいのでしょうか。
3 自社を必要以上に大きく見せない
自社が「採用したい人」が応募者にたくさん含まれるようにするには、2つのポイントがあります。1つは「自社の魅力と、どんな人を求めているか(求める人物像)を明確に示すこと」。これについては次回以降で詳しくお話しします。
もう1つは「自社を必要以上に大きく見せないこと」です。“必要以上に大きく見せているかどうか”の分かりやすい判断方法をお教えしましょう。社員に自社の募集広告を見せて、忖度なしの感想を聞けばいいのです。
そこで「自社を大きく見せすぎている」という声が上がれば、恐らく採用で失敗しています。
本当に「採用したい人」が集まっていない、あるいは応募者にとって本当に「入りたい会社(やりたい仕事)」ではない可能性が高いでしょう。
すると、ご支援している会社の採用担当者はこう言います。「だって、うちのような中小企業だと(あるいは不人気の業種だと)少しくらい大きく見せないと、だれも応募してくれないじゃないですか」と。
本当にそうでしょうか。
中小や不人気業種の企業であっても、自社を必要以上に大きく見せずに欲しい人材をしっかりと獲得できた例は、私が関わったケース、そうでないケースも含めていくつも存在します。
自社を必要以上に大きく見せて採用できたとしても、数年以内に退職してしまうのでは、互いにとって不幸でしかありません。応募者からすれば「話が違う」わけで、辞めた会社に対して感謝どころか恨んでさえいる可能性が高いのです。
時間と手間をかけて取り組んできた採用担当者としても、虚しいばかりでしょう。
かといって「うちは中小企業(不人気な業界)ですけれど、よかったらきてください」と訴えかければ、「採用したい人」が応募してくれるのかというと、そうではありません。
応募者に「自分は100社応募しても1社も声がかからなかったのですが、よかったら採用してください」と正直に言われても、採用側が「分かりました、採用です」とはならないのと同じです。
現状は中小企業であることや、一般に不人気業界といわれる業界の1社であることは認めた上で、「ただ、うちにはこんな事実(歴史・社風・仕事の魅力・制度など)があります」あるいは「うちはこういうことを大事にしています、こんなことを本気で目指しています」という情報があればどうでしょうか。
「それがないから困っているんだよ」と言われるでしょうか。私からすれば「自社の魅力やアピールポイントを見つけられていない」だけだと思います。原因は見つける努力が足りないのか、見つける努力はしているけれど正しい努力の仕方が分からないだけなのか。
4 理想を信じて脱サラ起業したスタートアップ、初めて新卒募集した結果は……
以前採用に関わるシリーズでもお話したことがありますが、都内某所に私が採用をご支援した従業員10名足らずの土木コンサルティングの会社がありました。
都内といってもターミナル駅から各駅停車でいくつも行った町はずれの駅、そこから10分以上歩いた古いマンションの1階の1室がオフィスでした。丸の内や新宿のきれいなオフィスに入る企業を回ってきた学生なら、道の途中で引き返すか、ドアの前にたどり着いても入るのをためらうような佇(ただず)まいです。
初回訪問でドアを開けると、寒い時期で中央にストーブが置かれ、雑然とした中、デスクが壁際に並んでいました。社長が待ってくれていて、さっそく募集の背景を伺いました。
「仕事はあるけど人がいない。思い切って初めて新卒採用にチャレンジしてみようと思ってね。採用は1名程度、できれば土木系がいいけれど、入ってから教えるから理系の学生ならいい、一人でも多く集めてほしい」
私は正直に言いました。「現時点では残念ながら、この売り手市場で応募してくれる理系学生はたぶんいないと思います」。ただ、その後にこう続けました。「なので、もっと詳しいお話を聞かせてください」
社長は大学で土木系を専攻し、日本を代表する大手土木コンサルの会社に就職して第一線で活躍していたそうです。主に河川事業を担当したものの、治水のためとはいえ自然の草が生い茂り、虫や動物が生息していた場所をコンクリートで固めてしまうことに疑問を感じるようになったといいます。
社長は元々東京の郊外のご出身。「昔はあの辺りにも、夏は普通にホタルが飛んでてさあ、それはきれいだったんだよ。そういう川を東京にも蘇(よみがえ)らせたいなって思ったら会社を辞めて、今の会社を始めてたんです」
大雨や洪水に備えて、河川周辺住民の命と暮らしを守らなければいけない。そのためにはコンクリートの護岸は必要だけれど、子どもたちが安全に遊べる自然の水場を少しでも残すような設計ができないか。お金が余計にかかる提案にはなるけれど、それが社長の目指す理想でした。
河川事業は国や自治体の管轄、中小企業が直接請けられる可能性は低く、大手からの下請けとなればそんな理想は言っていられないのも分かっています。「それでも10件に1件でもいいから、自然を残せる提案をしたいんだよね」
「そしていつかは東京にホタルのすむ川を蘇らせたいんですね」と、私は続けました。社長ははにかんだ優しい笑顔を返しました。「じゃあ、その思いを募集に書きましょう。きっと共感してくれる理系学生が現れるはずです!」
確信はありませんでしたが、自信はありました。理系学生は全国に十万人単位で存在する。その中で社長の思いに共感してくれる人は必ずいるはずだと。
大手にはできないこととして、初回訪問から社長に直接会ってもらうことにしました。応募者数が少ない中小だからできることです。もちろん最寄り駅までのアクセスや、駅からの詳しい道順も添えました。「もし道に迷ったら電話ください、迎えに行きます」
結果は数名の応募があり、社長は全員と直接会って話をしてくれました。皆が自分の思いに興味を持って来てくれたと知って本当にうれしかったそうです。わずか数名とはいえ、全員が「採用したい人」だったと聞きました。
最終的には1名を内定としました。決めた理由は、その人が社長の思いに強く共感してくれて「いつかホタルの川を作りましょう!」と言ってくれたからだと。彼はたまたまですが東大の大学院生でした。
社長は「うちみたいな小さい会社に入ると言ったら、ご両親に反対されない?」と心配しましたが、本人が説得し理解してもらえたそうです。彼の専攻は土木ではなく、会社としては新たな専門分野に広がる可能性も感じられたと聞きました。
5 働き続けている人がいる以上、全ての会社に“他社にない魅力”がある
中小企業での成功事例をご紹介しましたが、この会社が特別なわけではありません。働き続けている人がいる全ての会社に、必ず何かの“魅力”があるのです。
人手不足の日本は、働く側にとって売り手市場です。にもかかわらず皆さんの会社で働き続けている人がいるのです。なぜだと思いますか?
中には「今さら転職するのも面倒くさいから」とか、「そこそこ働いていれば、そこそこの給料をもらえるから」という人もいるかもしれません。でも全員がそうでしょうか。
経営者や採用担当の皆さんは、改めて「他社にない魅力って何だろう」と自問自答してみてください。どうしても思いつかなかったら、仕事への意欲が高くて自社で働き続けてくれている社員を一人ひとり呼んで、本音を聞いてみてください。
人間は正直です。今の会社に魅力を感じなくなったら誰もが去ることを考えるでしょう。けれども他社にない何らかの魅力を感じていて、待遇などの諸条件を含めても自分にとってプラスだと判断するから転職しないのです。
その魅力が何かを見つけてみてください。少なくともその“他社にない魅力”は、人をひきつける力があるのです。
今後もその“他社にない魅力”を大事にしたいのであれば、それを募集時に誇張せず分かりやすく提示するだけで、自社が「採用したい人」が集まります。
同時に、自社を必要以上に大きく見せることが、いかに無駄で虚しい行為か分かるはずです。
第2回を最後までお読みいただきありがとうございました。次回は『人が辞めない会社、10のヒント』のヒント2として、“自社ならではの魅力”の見つけ方もご紹介します。
このコラムをヒントに、自社を退職する一人ひとりの「辞める理由」と、働いている一人ひとりの「辞めない理由」の2つを丁寧に拾っていきながら、自社ならではの“課題”を解消し、“強み”を活かしていきましょう。
<ご質問を承ります>
ご質問や疑問点などあれば以下までメールください。※個別のお問合せもこちらまで
※武田が以前上梓した書籍『新スペシャリストになろう!』および『なぜ社長の話はわかりにくいのか』(いずれもPHP研究所)が、ディスカヴァー・トゥエンティワンより電子書籍として復刻出版されました。前者はキャリア選択でお悩みの方に、後者はリーダーやトップをめざしている方にお薦めです。
以上(2025年8月作成)
(著作 ブライトサイド株式会社 代表取締役社長 武田斉紀)
https://www.brightside.co.jp/
pj90275
画像:VectorMine-Adobe Stock