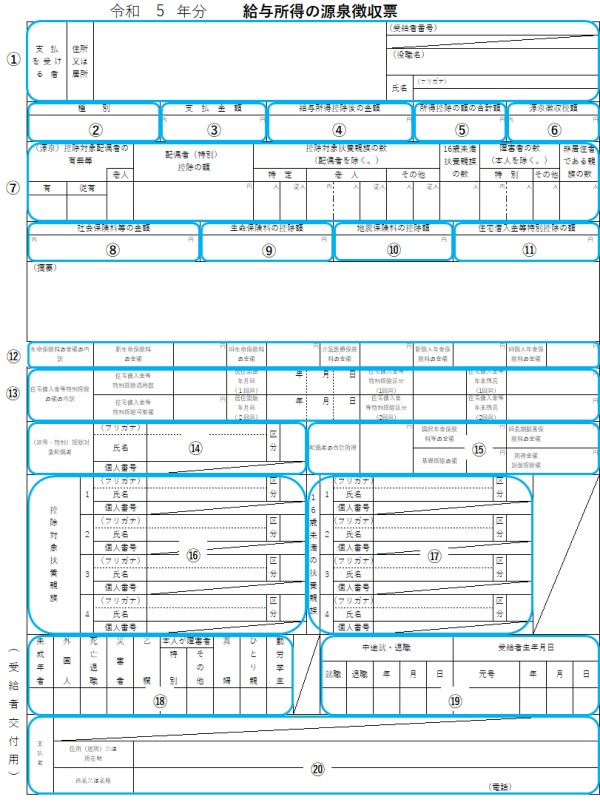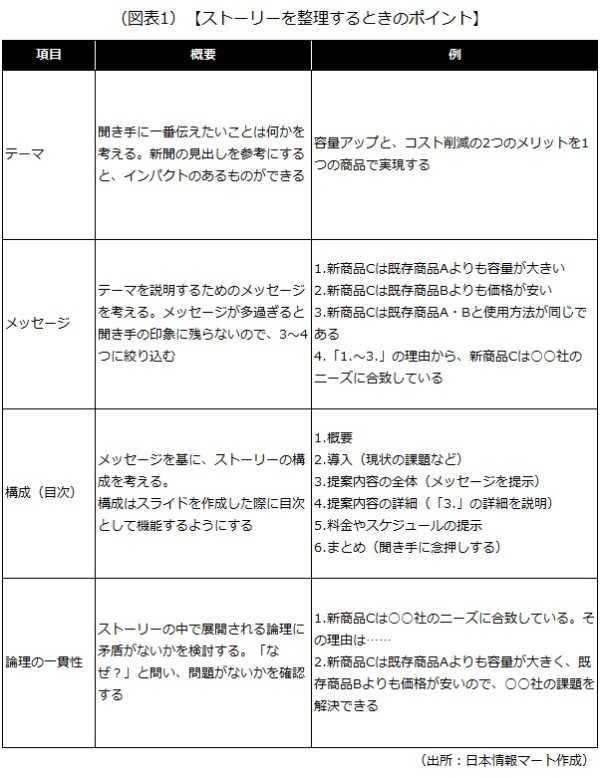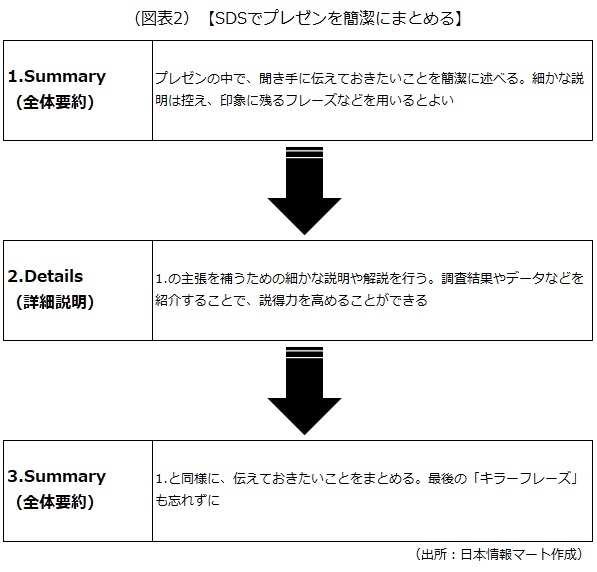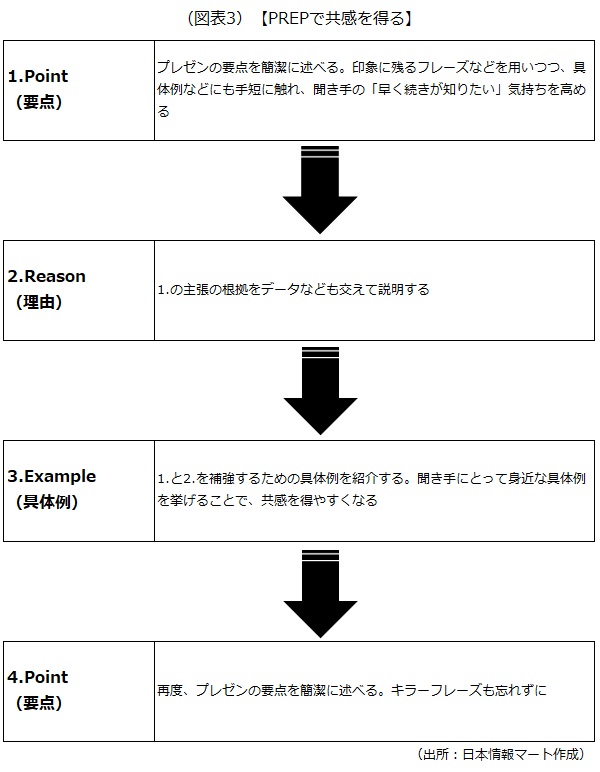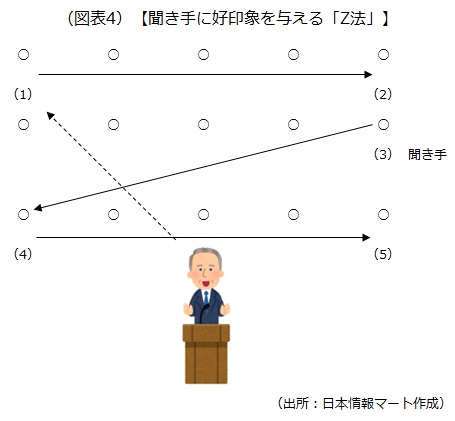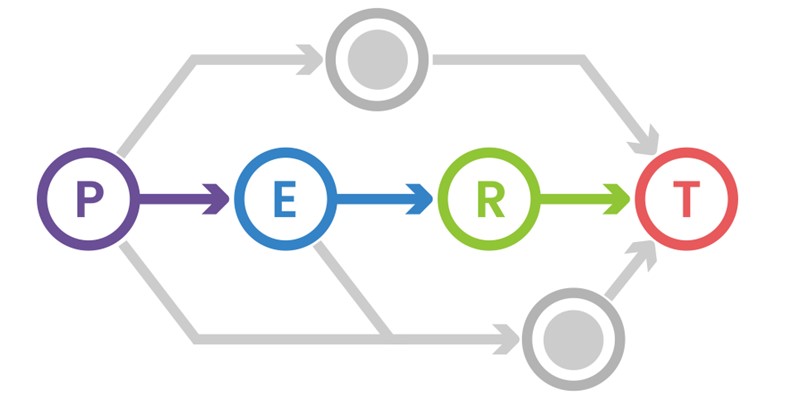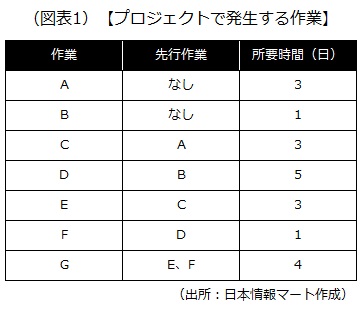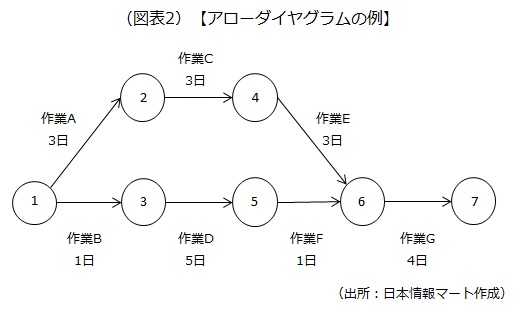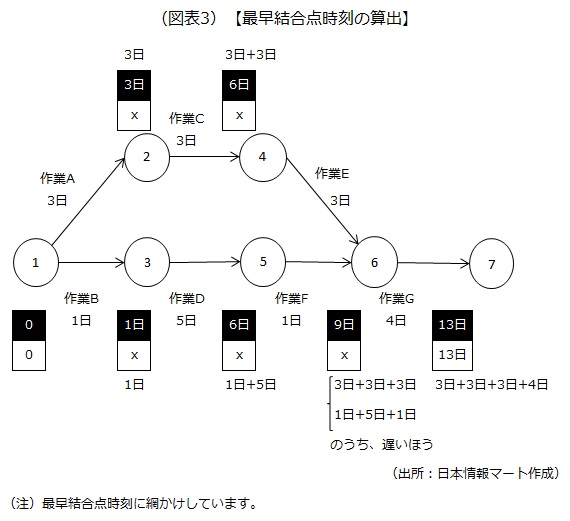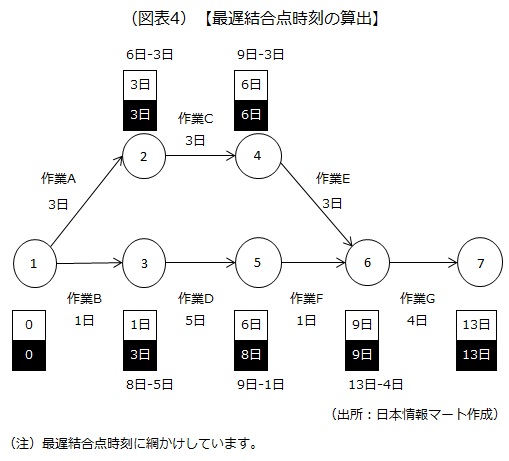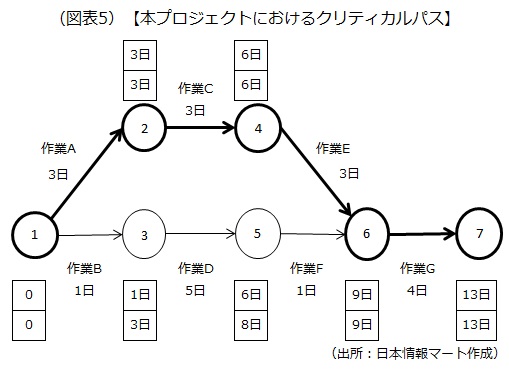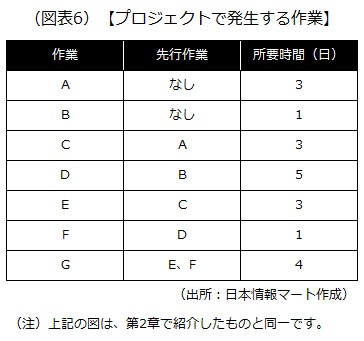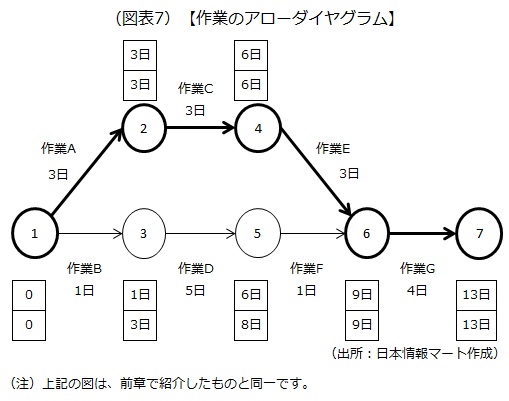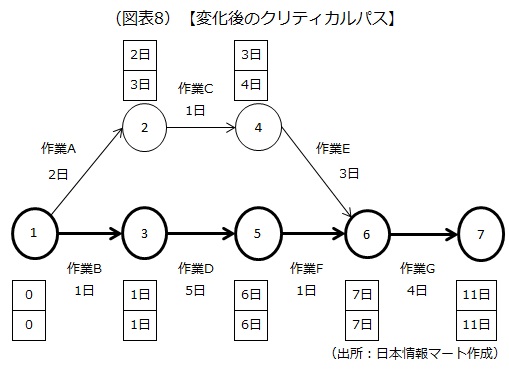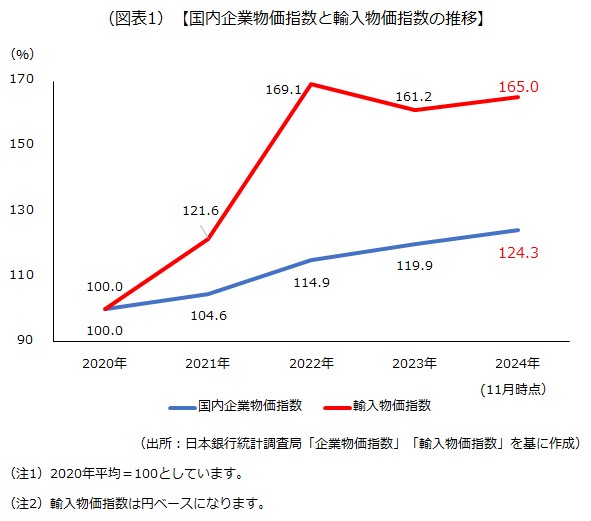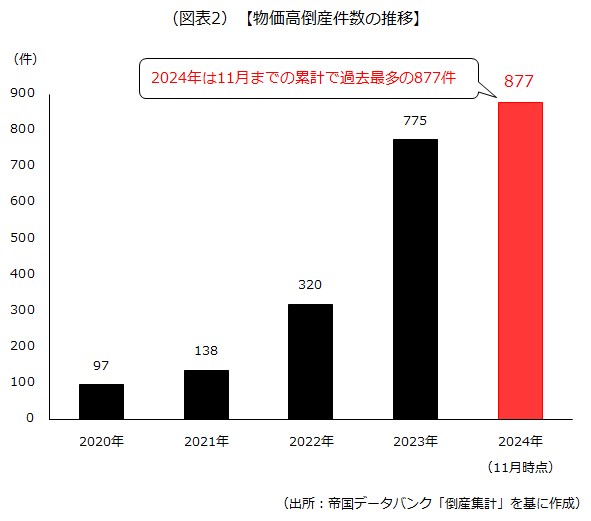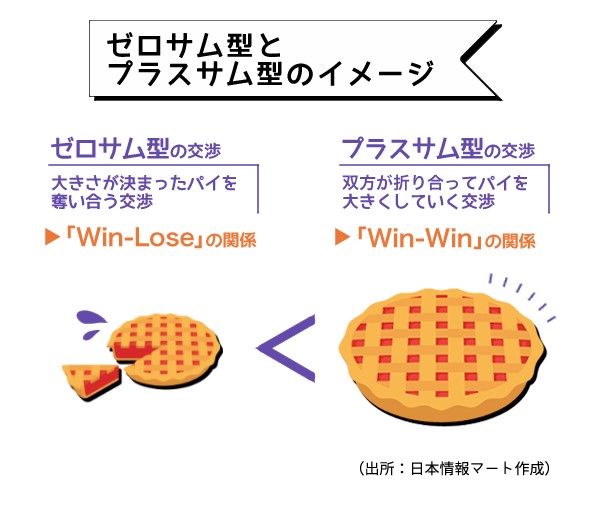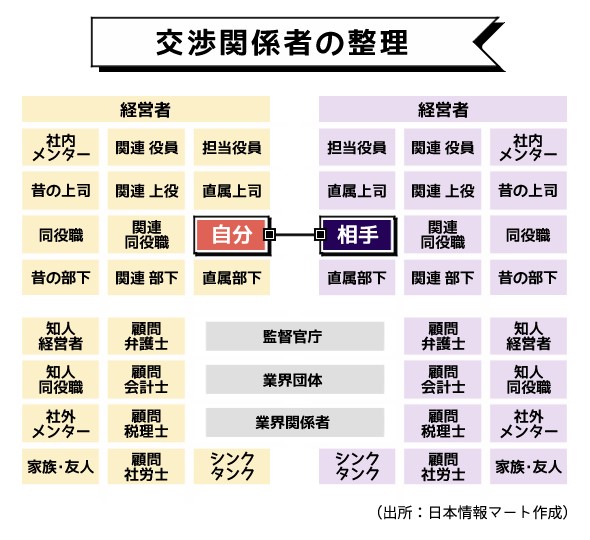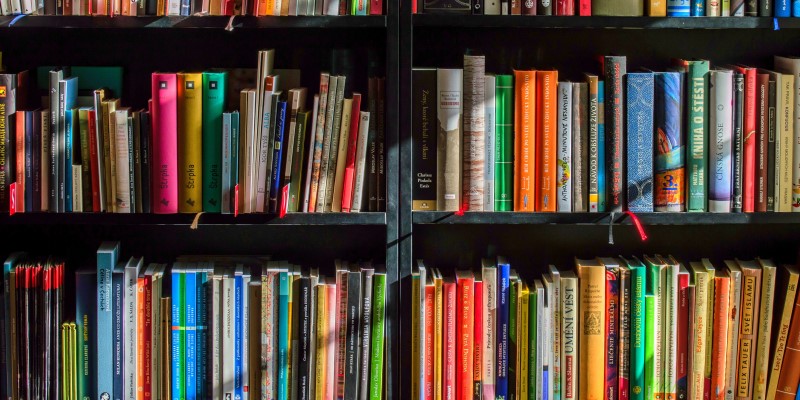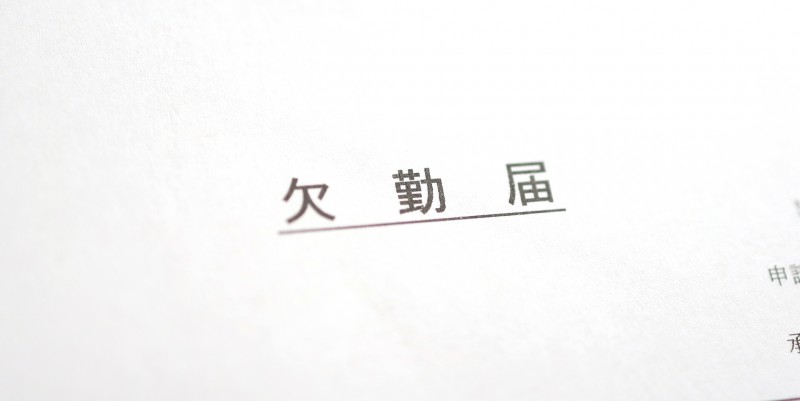1 誰と、いくらの値上げ交渉をするか?
実際の値上げ交渉では、
その値上げ交渉に失敗したら、大きな損失が出る
といったケースがあり、誰でも緊張します。
どのような交渉も軽んじてはいけませんが、難しさはそれぞれ違います。また、企業間の取引では、交渉相手によって提示する条件も変わります。こうした、ある意味でレベル感がバラバラの値上げ交渉について、組織としての勝率を高めるために経営者がすべきことは、
「誰と、いくらの値上げ交渉をするか?」を明確にすること
です。この絶対的な基準によって交渉担当者は安心と自信を得て、不要な譲歩をすることもなくなるのです。
2 誰と交渉をするか?
1)交渉する相手を決める
早速ですが、交渉相手となり得る先をリストアップしてみましょう。この記事は、値上げ交渉について紹介していますが、仕入れ先との「値下げ交渉」も視野に入れてください。
仮に100件がリストアップされたとします。ここで、「よし! 上から順番に値上げ交渉をしよう」という経営者がいたら、ちょっとお待ちください。このリストで最初に行うべきことは、
交渉しない相手を決めること
だからです。例えば、
- 交渉決裂の際のリスクがかなり大きい相手
- 収支は厳しいが、取引することで業界に影響を与えられる相手
などとは、あえて交渉しなくても問題ありません。一斉値上げなどをせず、他との取引条件を知られることなく、しかるべき相手と値上げ交渉をすればよいのです。
2)交渉する順番を決める
値上げ交渉をする相手を決めた後は、交渉する順番を決めます。値上げ交渉に限らず、交渉は情報が多く経験が豊富なほど有利になりますから、
簡単な先から交渉をして相手の出方や感触を確かめ、そこで学んだことを次の交渉に活かしていくことの繰り返し
が基本になります。
値上げ交渉の難易度を整理する参考として、縦軸を「交渉への依存度」、横軸を「交渉の論点(価格以外の納期や品質などの交渉余地)」とするポジションマップを紹介します。交渉への依存度とは、「その交渉に必ず勝たなければならない」といったように、文字通り、依存度が高い交渉を指します。
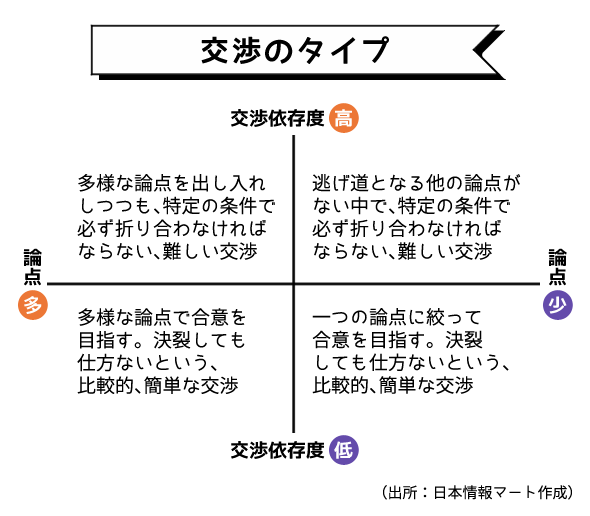
上段は依存度が高く、難しい交渉になりそうですから、最初は下段にある決裂しても仕方がないと判断した相手から、値上げ交渉を始めるとよいでしょう。
左右の「論点が多いか少ないか」は状況次第で有利、不利が変わりますが、交渉担当者には、それぞれ次のような性質が求められます。
- 論点が多い:相手のことをよく知っており、的確な状況判断ができる
- 論点が少ない:タフな場面でも感情的にならず、突破することができる
3 いくらの値上げ交渉をするか?
1)相手によって条件を変える
値上げ交渉をする相手を決めたら、相手ごとに、
- 値上げ額
- 留保価値(それを下回ったら交渉を打ち切る水準)
を設定します。値上げ額と留保価値は同じ場合もありますし、次のように違う場合もあります。
できれば100万円の値上げをしたいが(値上げ額)、80万円までなら譲歩できる。ただし、80万円を下回るのはあり得ない(留保価値)
最もシンプルな考え方は、
値上げ額=仕入れ額の増加分以上
とすることです。仕入れ額が80万円増加したら、販売価格も80万円上げればよいですし、これまで無理してきた分も取り返したければ、100万円の値上げをするということです。現実には、
- 取引の規模(自社の収益に与えるインパクト)
- その相手と取引に至った背景や取引年数
- その相手と取引することによる宣伝効果
といった事情も考慮することになりますから、
- 販売先であるA社とは、100万円の値上げ交渉
- 販売先であるB社とは、60万円の値上げ交渉
- 販売先であるC社とは、値上げをしない代わりに、取引量の増加交渉
といったように対応が分かれていくでしょう。もちろん、
仕入先であるD社とは、10%の値下げ交渉
といったように、仕入れ額の減額交渉も行います。結果として、自社の取引全体から適正な収益が生まれればよいわけです。
2)変動損益分岐点を用いた値上げ額の設定
具体的な値上げ額を決める際に使うのが「損益分岐点」です。詳細は割愛しますが、損益分岐点は固定費と限界利益が同じになる水準です。限界利益は「売上高-変動費」で求められ、売上高に占める限界利益の割合を限界利益率と呼びます。
損益分岐点は、
固定費÷限界利益率(売上高に占める限界利益の割合)
で出します。目標利益がある場合は、固定費に目標利益を足して計算します。例えば、固定費が400万円、営業利益が100万円の取引で、限界利益率が50%から40%に下がった場合、損益分岐点売上高は次のように変化します。
- 限界利益率が50%の場合:(400万円+100万円)÷0.5=1000万円
- 限界利益率が40%の場合:(400万円+100万円)÷0.4=1250万円
今の仕入れ額を受け入れつつ、同じ営業利益を確保したければ25%の値上げが必要になります。こうした計算をするには、自社の収益構造を正しく把握する必要があるので、「変動損益計算書」を作成してみるとよいでしょう。変動損益計算書とは、
費用を変動費と固定費に分けて作成する損益計算書
であり、財務会計上の損益計算書とは次のように違います。
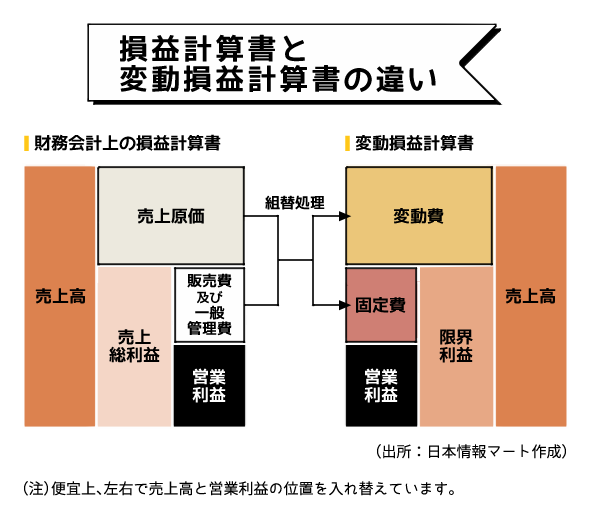
変動損益計算書を見ると、企業全体と取引先ごとの収益構造が把握しやすくなります。もとの状態からの変化を、
- 変動費(仕入れ)の上昇で赤字転落
- 値上げによって利益を確保
- 変動費(仕入れ)削減で赤字を回避
- 固定費の削減で赤字を回避
の例を示すと、次のようになります。
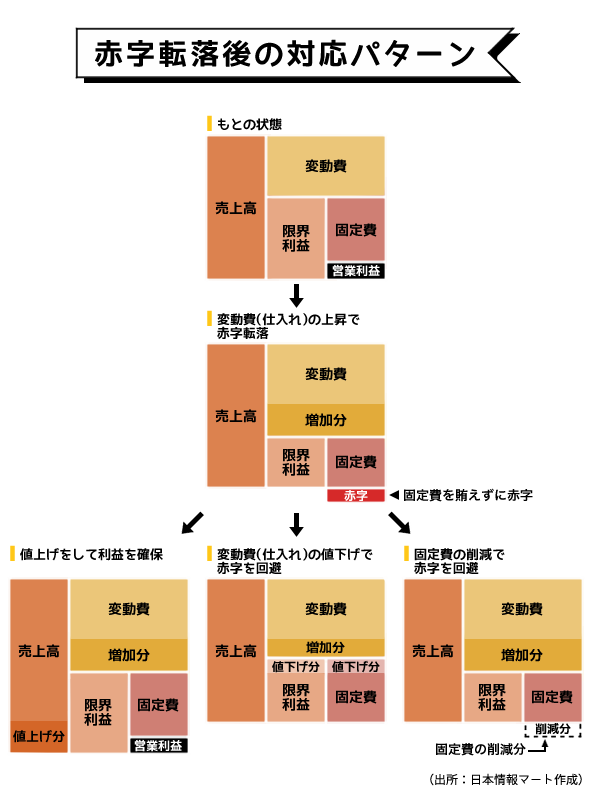
仮に、企業全体で10%の値上げを目標とするなら、
- 大手取引先と交渉して、1社で10%分を値上げする
- 小口取引先と交渉して、10社で10%分を値上げする
といった方法があります。変動損益計算書で収益構造を把握しつつ、交渉条件の方針を決めましょう。
4 現場に情報を伝える
方針が決まったら、現場の社員に伝えます。値上げをする企業が増える中で、現場の社員が、取引先の担当者から、
「御社との取引価格は今のままで大丈夫ですよね? 上司から確認するように指示されていまして……」
などと確認を受けることもあるでしょう。そうしたときに、
- 申し訳ありませんが、変更したいと考えています。上司より改めて取引条件についてご相談させていただく予定です
- はい、大丈夫です。御社との取引条件は当面、今のままで変わりません
などと明確に答えられるようにしてあげることで、現場の社員と取引先とのコミュニケーションが図れるようになります。
以上(2025年2月更新)
pj80171
画像:Mariko Mitsuda