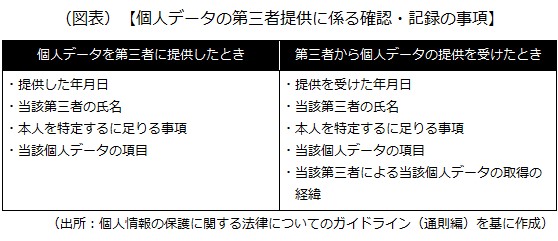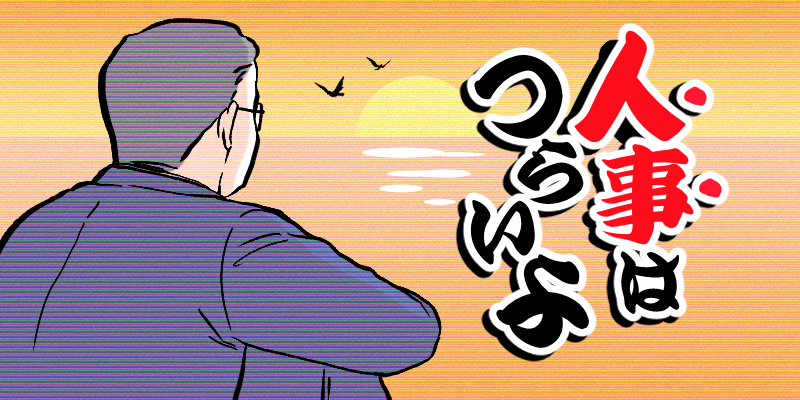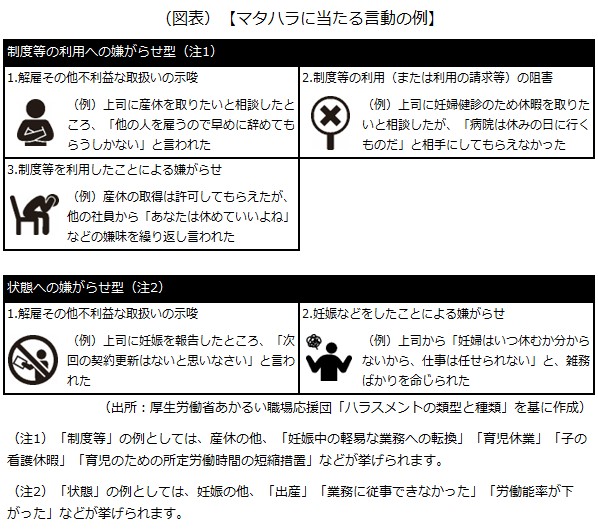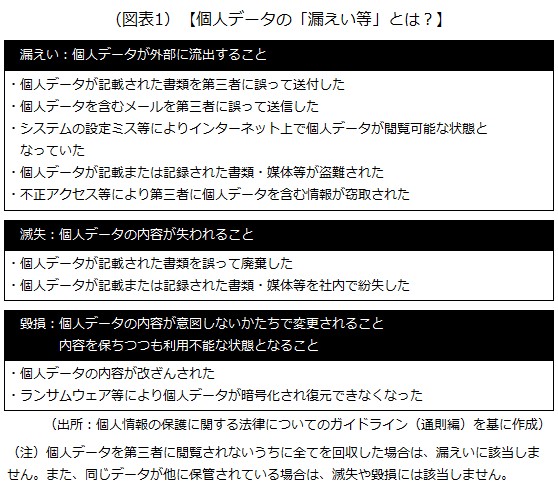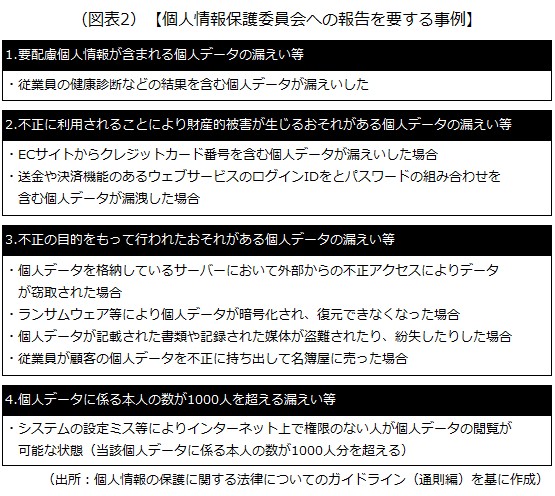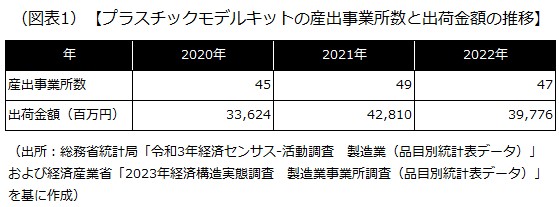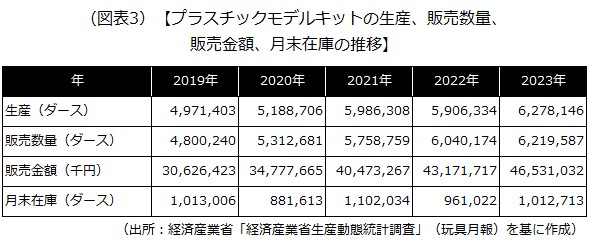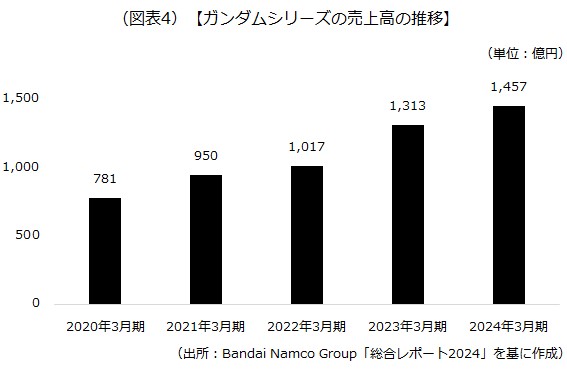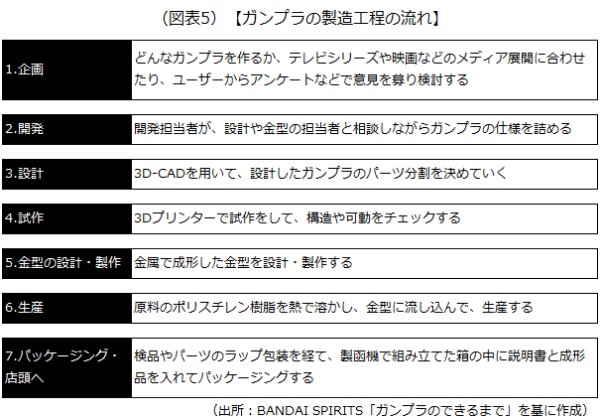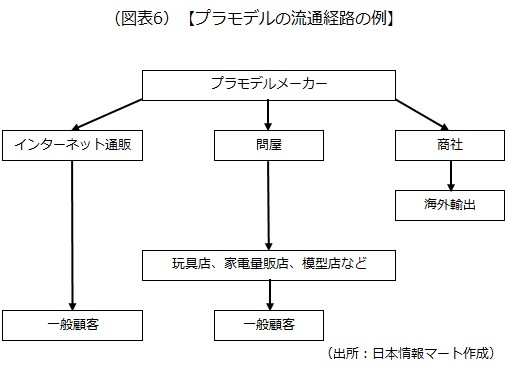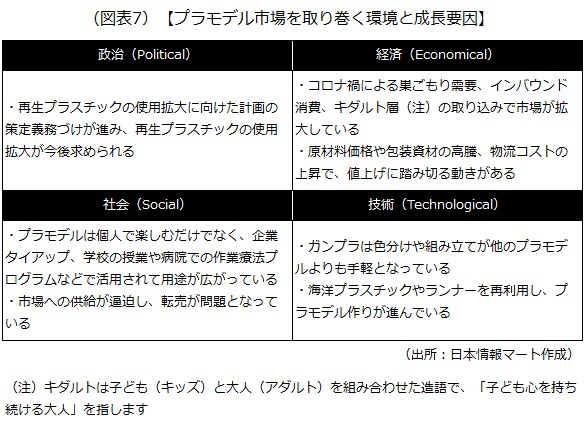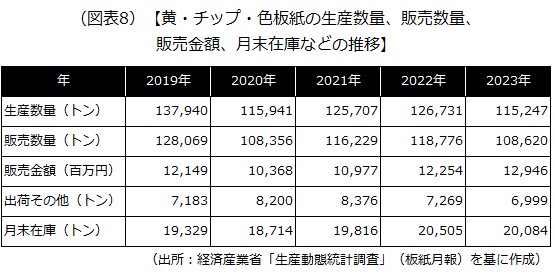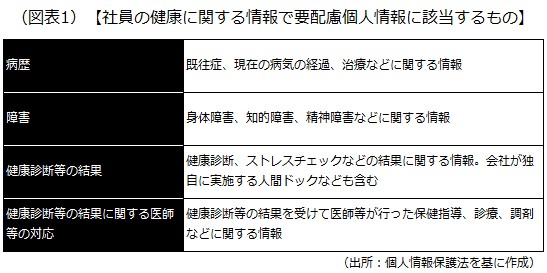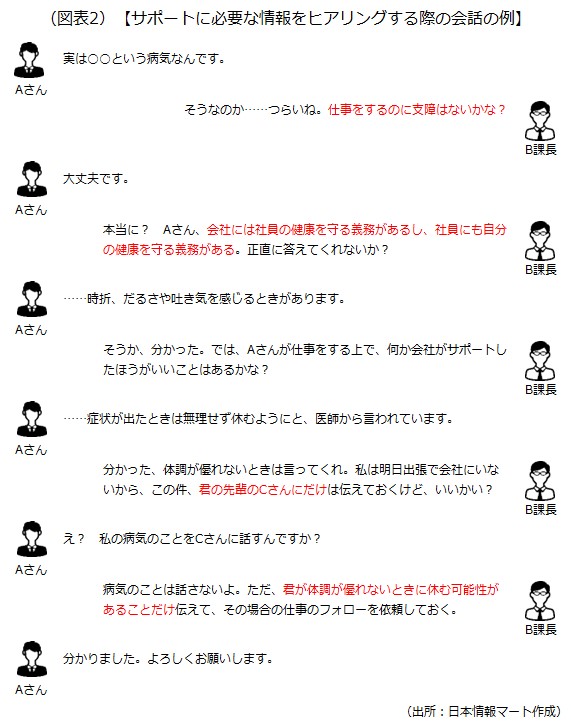1 ギャンブル依存症は誰でもなり得る?
大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手の口座から巨額の預金を不正送金し、銀行詐欺罪などで訴追された元通訳が、自ら告白したことで注目される「ギャンブル依存症」。
ギャンブル依存症は、ギャンブルにのめり込み、自分ではコントロールができなくなってしまう精神疾患の1つ
で、世界保健機関(WHO)では「病的賭博」、米・精神医学会では「ギャンブル障害」として診断基準が定められています。
日本でも「ギャンブル等依存症対策基本法」により、ギャンブル等(公営競技である競馬・競輪・競艇・オートレース、その他パチンコ・パチスロといった射幸行為)にのめり込むことで、日常生活・社会生活に支障が生じている状態を「ギャンブル等依存症」と定義しています。
健全な娯楽のレベルで楽しむぶんには個人の自由ですが、仕事も手につかなくなるほどギャンブルにのめり込んでしまう社員がいたら、とても困りますよね。ただ、会社として社員の趣味にどこまで口を出してよいのかは悩むところもあります。
そこで、この記事では、
- ギャンブル依存症について、会社が介入(懲戒処分など)できるケースを押さえること
- ギャンブル依存症を生まない職場をつくること
- ギャンブル依存症が疑われるときの参考情報、相談先を知っておくこと
をご提案します。
なお、ギャンブルは、広義には「金銭等を賭けて、より価値あるものを手に入れる行為」を指します。その意味では、FXや商品先物などの金融取引、宝くじやスポーツくじ、ゲームセンターのクレーンゲーム、スマホゲームやソーシャルゲームの「ガチャ」などもギャンブルといえるでしょう。また、違法ですが、海外のオンラインカジノや友人同士の賭け麻雀などの賭博もギャンブルです。この記事では便宜上、違法なものも含めて「ギャンブル」として扱います。
2 ギャンブル依存症の社員を解雇できるのか?
前提として、健全な娯楽として社員が個人的に行っているギャンブルを会社が規制することはできません。プライベートな時間をどう過ごすかは、基本的に労働者(=社員)の自由だからです。
ここでは、会社として判断が求められる次の3つの場合を考えてみましょう。
- 社員が行っているギャンブルが違法な賭博だった場合
- 合法でも勤務中に社員がギャンブルを行った場合
- ギャンブルに起因して社員が借金問題を抱えている場合
なお、判断の基になるのは、就業規則にどのように定めているかです。例えば、
就業規則にギャンブルに関する懲戒事由を定めていなければ、そもそも懲戒処分は不可
です。自社の就業規則が厚生労働省「モデル就業規則(令和5年7月版)」を参考に策定したものであれば、不足がないか確認の上、規定を見直して労働基準監督署に届け出るようにしましょう。
■厚生労働省「モデル就業規則(令和5年7月版)」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/
1)社員が行っているギャンブルが違法な賭博だった場合
多くの会社では、
「会社の名誉や信用を損なう行為をしないこと」
を服務規律の遵守事項として定めています。賭博は、刑法が定める犯罪類型の1つで、単純賭博の場合は50万円以下の罰金または科料、常習賭博の場合は3年以下の懲役が科されます。社員が賭博を行ったことが明るみに出れば、会社の名誉や信用を損なう恐れがあります。つまり、
賭博をすること自体が服務規律違反(懲戒事由)
になるというわけです。
懲戒処分の種類(懲戒解雇、出勤停止、減給など)は、事案の大きさなどに応じて決めることになります。ただし、解雇の判断は慎重に行わなければなりません。たとえ、社員が単純賭博の容疑で現行犯逮捕されたとしても、それをもって直ちに解雇することはNGです。逮捕された時点では、社員が本当に有罪なのかは分からないからです。
また、逮捕された社員の家族や弁護人から「会社に迷惑をかけられない」といった理由で退職の申し入れがあるかもしれませんが、承認するかどうかは、事案の重大さや捜査状況を見ながら検討するべきでしょう。
なお、逮捕された場合、社員は身柄を拘束され働けない状態になります(検察官が起訴・不起訴といった終局処分を決定するまでに、最長23日間(72時間+20日間)身柄を拘束される恐れがあります)。そのフォローをどうするかなどは検討する必要があります。
2)合法でも勤務中に社員がギャンブルを行った場合
同じく服務規律の遵守事項として、
「勤務中は職務に専念し、正当な理由なく勤務場所を離れないこと」
という定めもよく見受けられます。この定めにのっとると、
社員が勤務中に正当な理由なく店に行ってパチンコを打つのは服務規律違反(懲戒事由)
となります。
とはいえ、勤務場所を離れなくても、スマホがあれば、オンラインで競馬、競輪、競艇、オートレースに賭けることはできてしまいます。こうした行為を防ぐために、服務規律の遵守事項に「勤務中は職務に専念し、正当な理由なく私用で携帯電話他、通信機器での通話・メール等通信を行わない」旨を定めることも1つの手です。
なお、休憩時間は、労働者(=社員)に自由に利用させなければなりませんが、一定の制限を加えるのは可能です。服務規律の遵守事項に「休憩時間中のギャンブルを禁止する」旨を定めることも検討の余地があります。
このように「ギャンブルを禁止する」旨を定める場合、少なくとも会社のネットワーク環境からは、競馬、競輪、競艇、オートレース関連のウェブサイトに接続できないように設定するなど(Webフィルタリング)、技術的な対応も併せて行い、ルールと実態の整合性を保つように努めるとよいでしょう。
3)ギャンブルに起因して社員が借金問題を抱えている場合
社員がギャンブルに起因する借金問題を抱えていても、
職務遂行に影響を及ぼさない限り、会社が介入する余地はない
というのが原則です。とはいえ、社員が隠そうとしても、消費者金融業者などから督促の電話が会社にかかってきたり、裁判所から給与の差し押さえ命令が会社に送られてきたりすることで、借金問題は露呈します。
社員の借金問題が露呈したときには、本人としっかり話し合い、対応を決める必要があります。例えば、
社員が経理業務やレジ業務の担当の場合、直接お金を扱う職種を避けて配置転換をする
といった対応もあり得るでしょう。
また、現実には、社員が同僚から借金を重ねた挙げ句に、返済が滞りトラブルに発展することも起きています。こうしたトラブルを避けるためには、服務規律の遵守事項に
「社員間の金銭の貸借を禁止する」
といった定めを設けるとよいでしょう。
3 ギャンブル依存症を生まない職場づくりを
1)ギャンブル依存症の人は日本に何人いる?
ギャンブル等依存症対策基本法に基づいて2021年に行われた国立病院機構久里浜医療センターによる調査では、調査対象者の過去1年以内のギャンブル等の経験の評価結果から、「ギャンブル等依存が疑われる者」の割合を、成人の2.2%と推計しています(松下幸生、新田千枝、遠山朋海「令和2年度 依存症に関する調査研究事業 ギャンブル障害およびギャンブル関連問題の実態調査」、2021年)。
単純計算すると、社員数50人規模の会社では、ギャンブル依存症の社員が1人くらいいても不思議ではないということになります。
2)ギャンブル依存のメカニズムを知る
依存症の原因は、脳内の「報酬系」などの機能異常と考えられています。ギャンブルで勝ったときなどに、脳内では快楽物質であるドーパミンが放出され、多幸感や高揚感が得られます。そして、それを繰り返すうちに脳が刺激に慣れてしまい、より強い刺激を求めるようになります。その結果、行動がコントロールできなくなってしまうのがギャンブル依存のメカニズムと考えられています。
3)ギャンブル依存に至る変化を見過ごさない
最初は、興味本位で、友人や知り合いから教えてもらってギャンブルに手を出し、勝ったことに味をしめて、次第にのめり込んでしまうという人が少なからずいます。ギャンブル依存症になると、自らギャンブルをやめたくてもやめられない状態に陥り、泥沼から抜け出せなくなってしまいます。
例えば、職場で「パチスロで〇万円勝った」「週末に万馬券とった」「万舟きた」などと自慢気に吹聴している社員がいたら、度が過ぎていないか、それとなく言動に気をつけておきましょう。勤務中にギャンブルの話ばかりしているようであれば、口頭で注意することも必要です。
再三にわたって注意を聞かず、他の社員から苦情まで出てくるような場合などには、服務規律の遵守事項に照らして、けん責などの処分対象にすることも検討しましょう。
4 ギャンブル依存症が疑われるときの参考情報、相談先
1)ギャンブル等依存症対策推進本部
首相官邸に設けられたギャンブル等依存症対策推進本部では、ギャンブル等依存症を克服した人やその家族などからの体験談を公開しています。また、後述する「ギャンブル依存症問題を考える会」をはじめとする、相談先などを紹介しています。
■ギャンブル等依存症対策推進本部「ギャンブル等依存症を克服された方の体験談」■
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gamble/
2)依存症対策全国センター
国立病院機構久里浜医療センターは、アルコール健康障害、薬物依存症、ギャンブル等依存症、ゲーム依存症の全国拠点機関(依存症対策全国センター)に指定され、依存症の治療や回復支援に携わる専門家の育成、依存症相談事業の拡充、依存に関する情報発信の向上など各種事業を実施しています。
ギャンブル依存症を含む依存症に関する基礎的な知識を紹介しているほか、全国の依存症専門相談窓口と医療機関が検索できます。
■依存症対策全国センター■
https://www.ncasa-japan.jp/
3)ギャンブル依存症問題を考える会
ギャンブル依存症問題を考える会は、ギャンブル依存症当事者・家族の支援に力を入れ、そこから派生する各地域の支援者との連携や啓発活動を行っています。
考える会の代表・田中紀子氏らは、2018年、病的ギャンブラーとギャンブル愛好家を分ける重要4項目を抽出し、その頭文字から「LOST」と名付けた、ギャンブル依存症自己診断ツールを開発しました。
- Limitless:ギャンブルをするときには予算や時間の制限を決めない、決めても守れない
- Once again:ギャンブルに勝ったとき「次のギャンブルに使おう」と考える
- Secret:ギャンブルをしたことを誰かに隠す
- Take money back:ギャンブルに負けたときすぐに取り返したいと思う
直近1年間のギャンブル経験にあてはめ、上記4項目のうち2つ以上が「はい」という回答の場合、ギャンブル依存症の危険度が高いと考えられます(田中紀子、松本俊彦、森田展彰、木村智和「病的ギャンブラーとギャンブル愛好家とを峻別するものは何か:LINEアプリ・セルフスクリーニングテストを用いた病的ギャンブラーの臨床的特徴に関する研究」日本アルコール・薬物医学会雑誌 53 (6) 264-282、2018年)。
■ギャンブル依存症問題を考える会■
https://www.scga.jp/
以上(2024年12月作成)
(監修 弁護士 田島直明)
pj00720
画像:ChatGPT