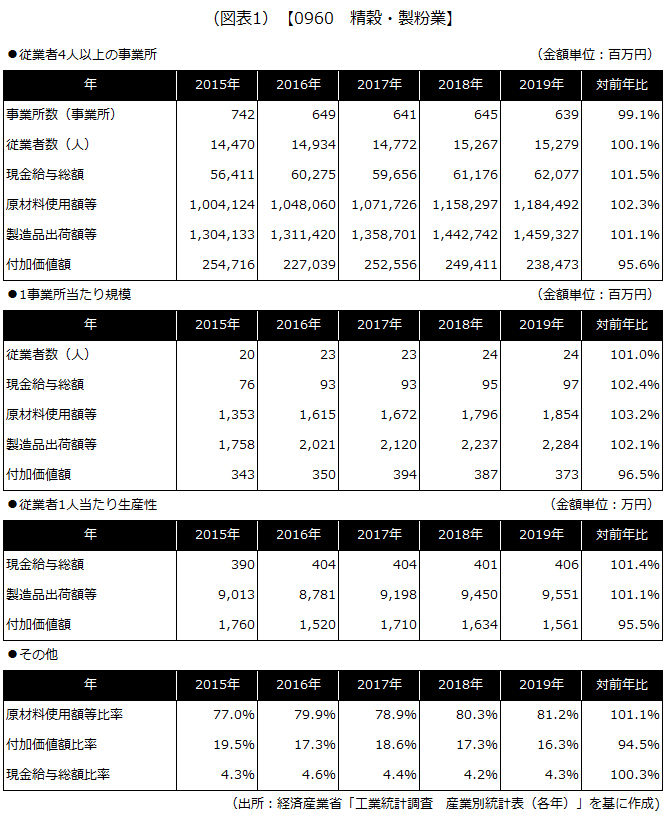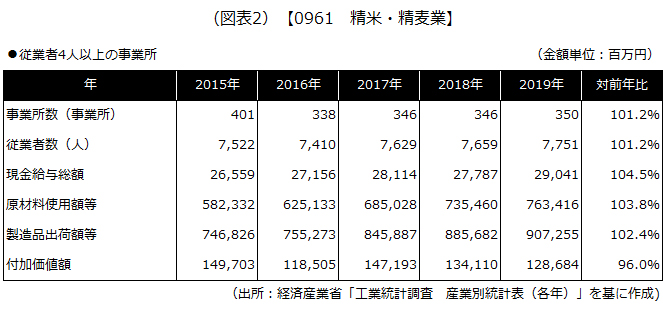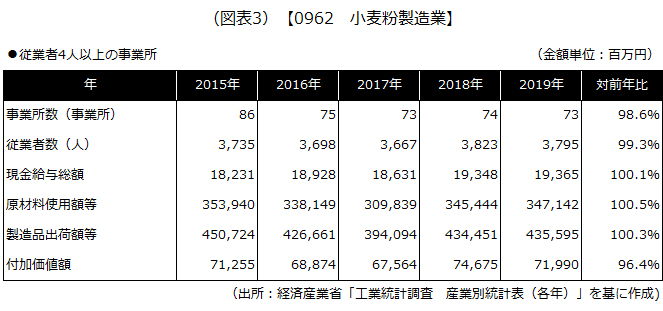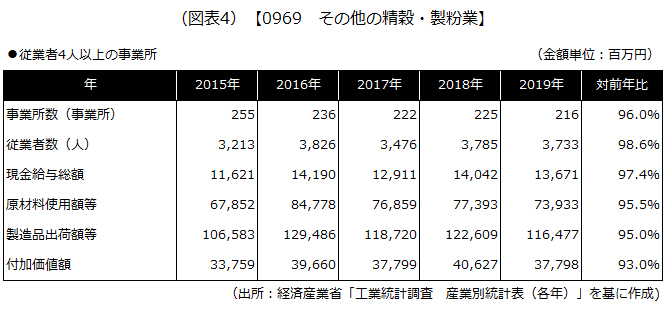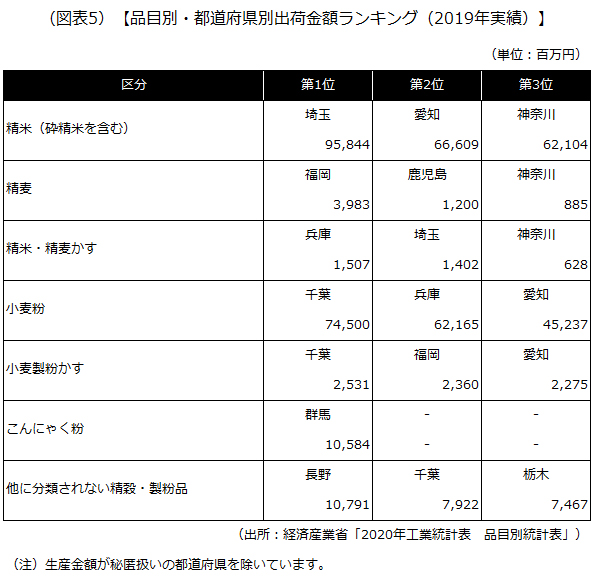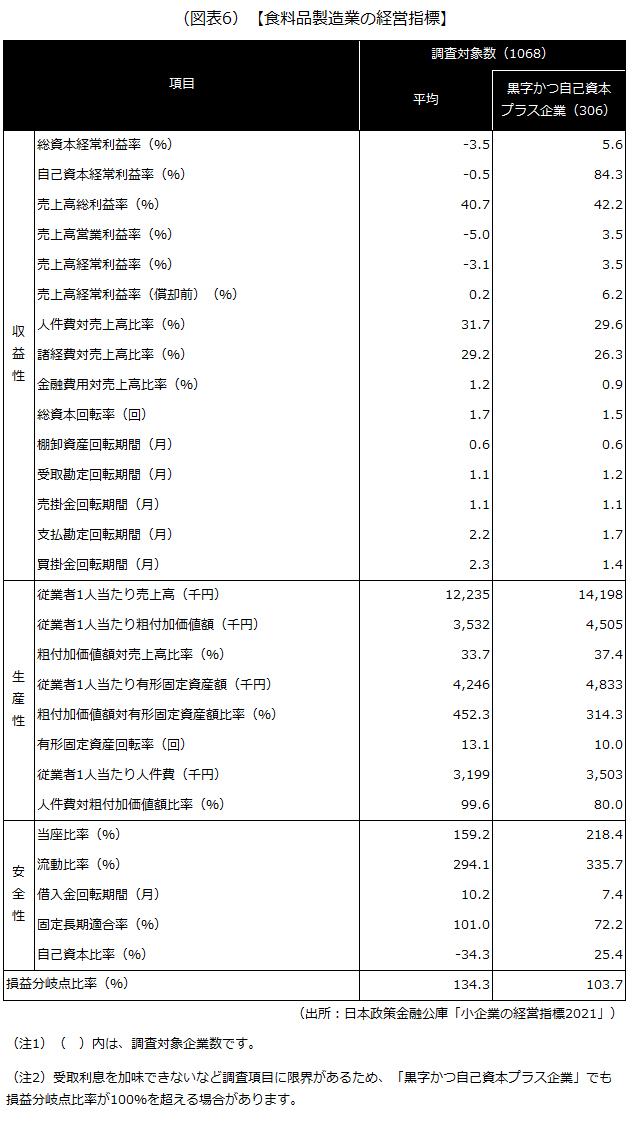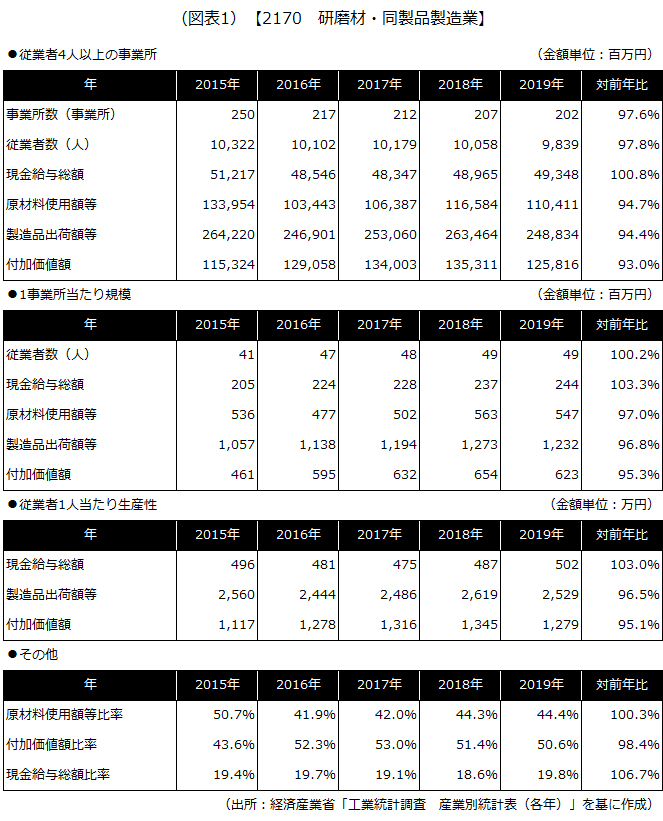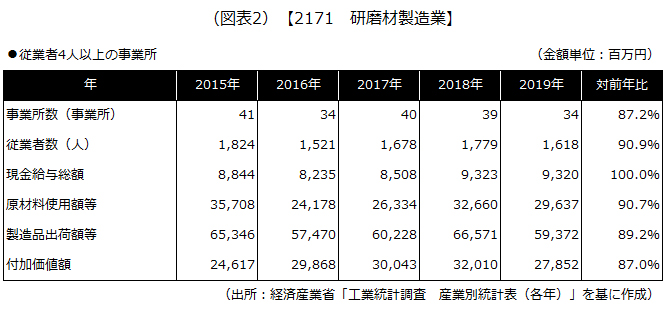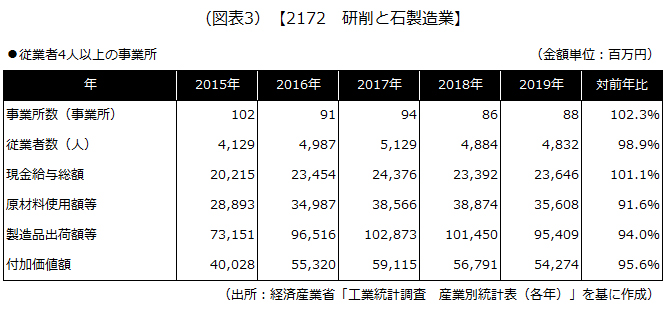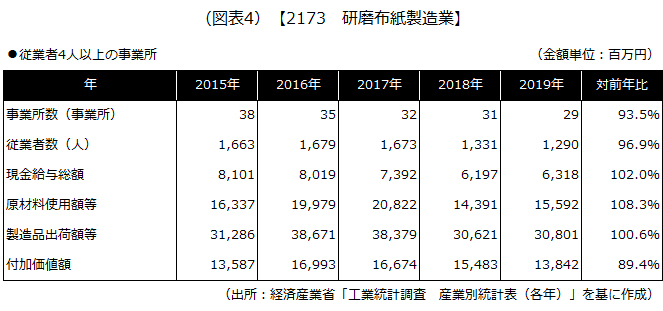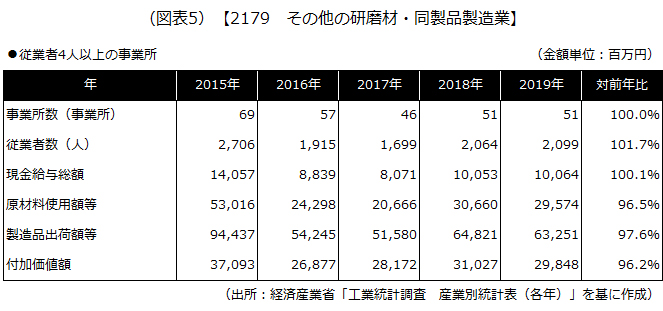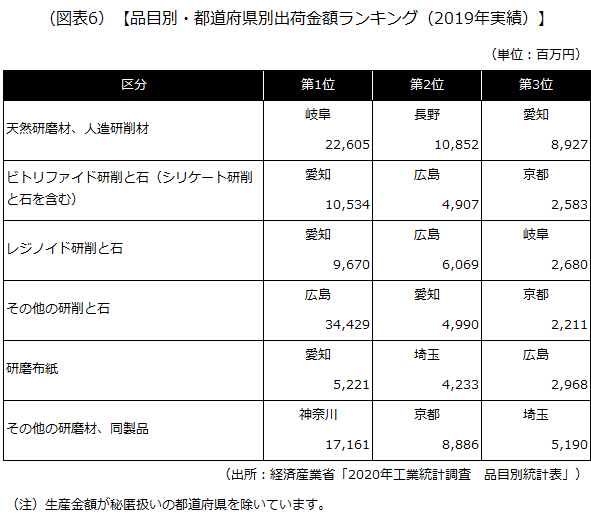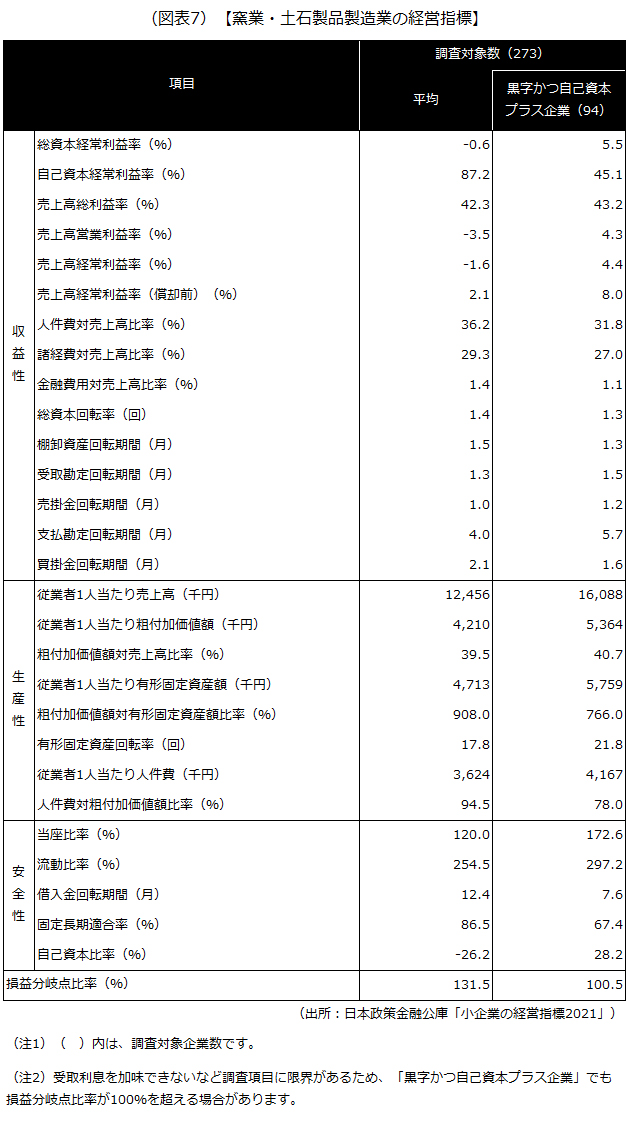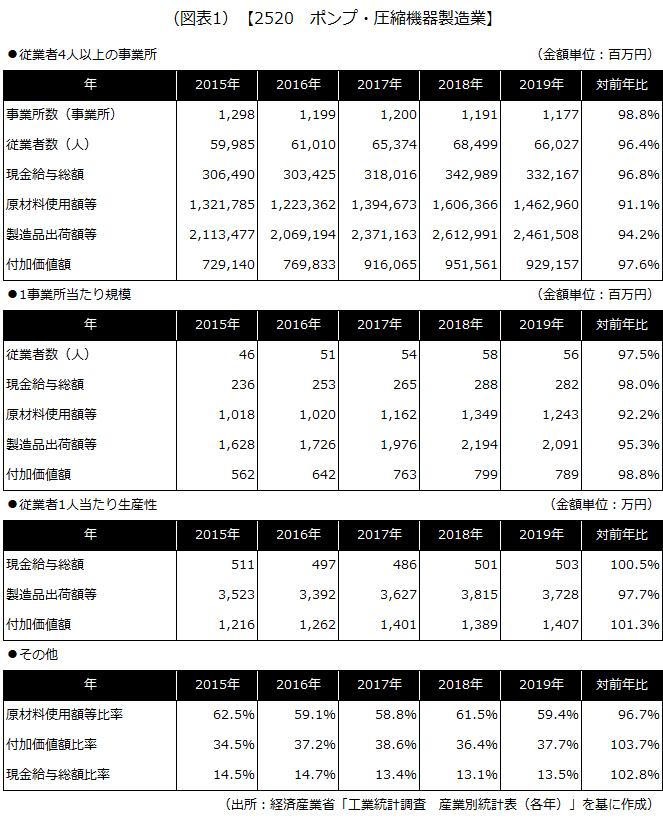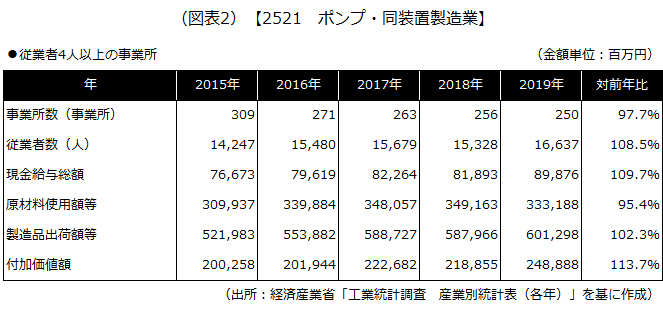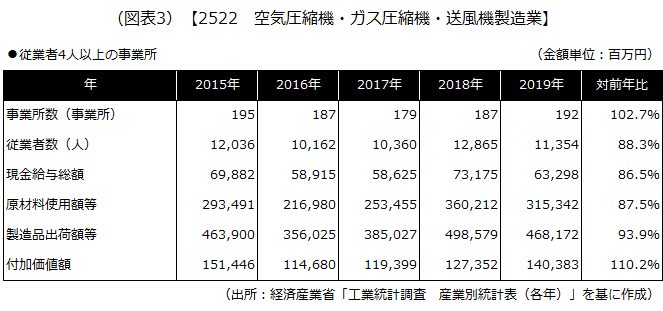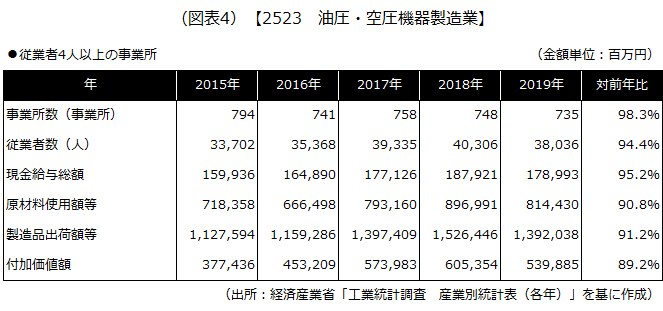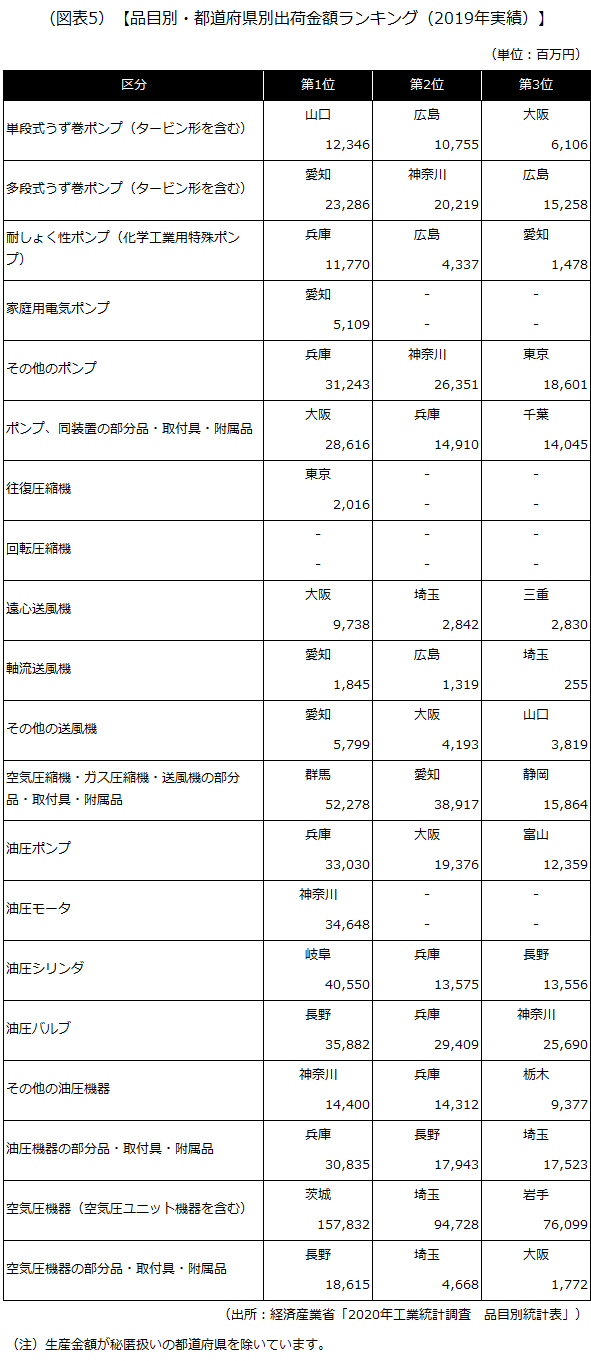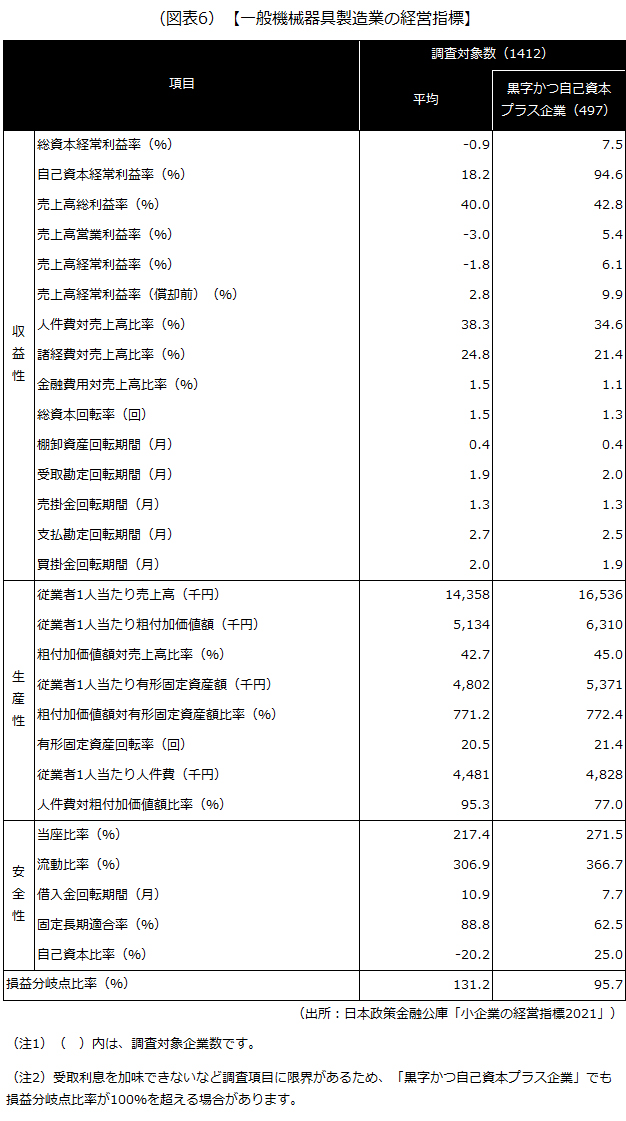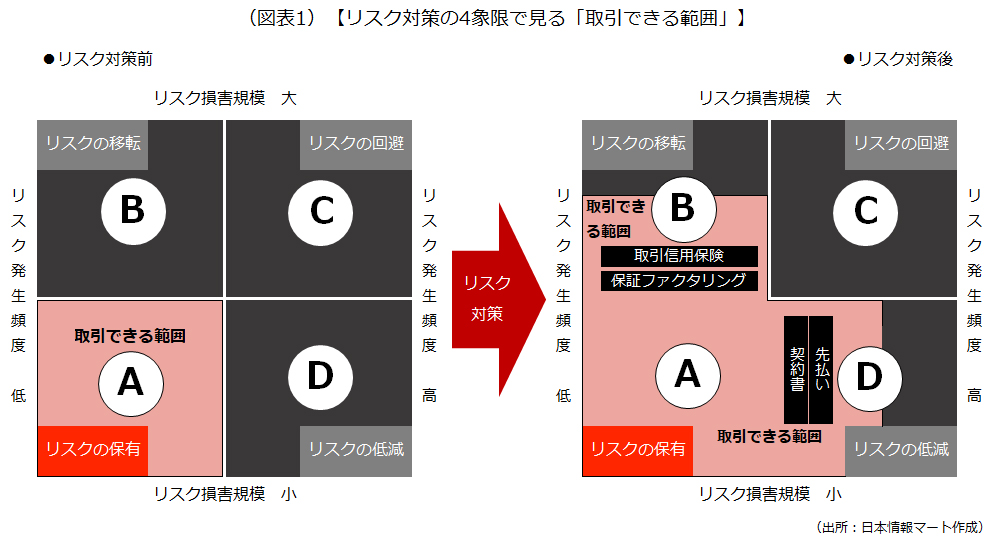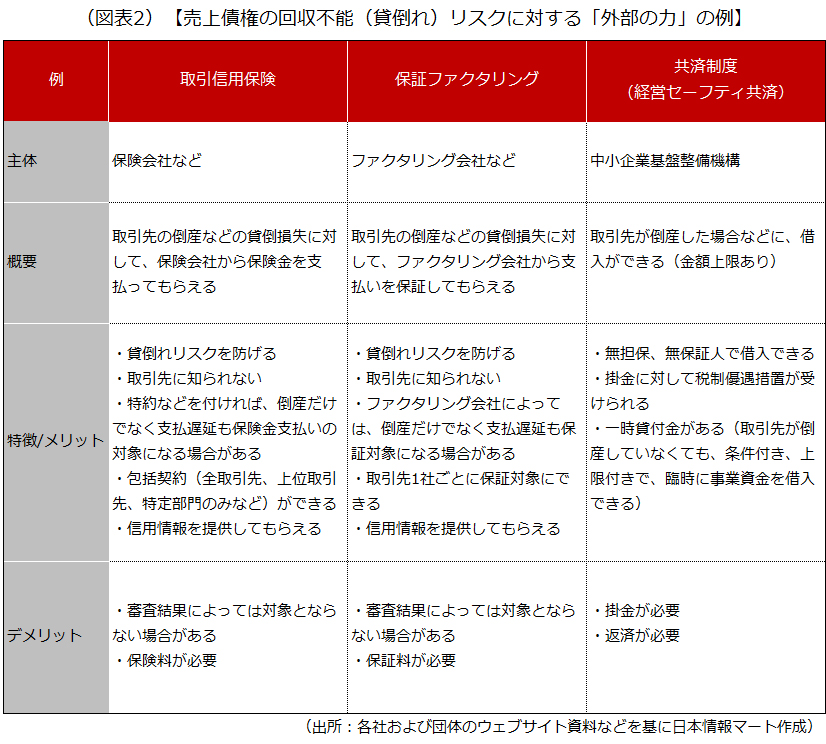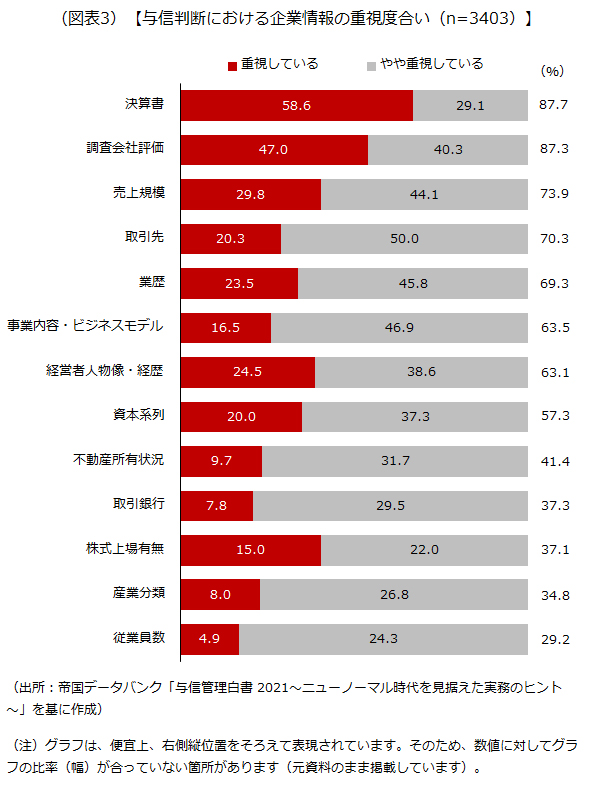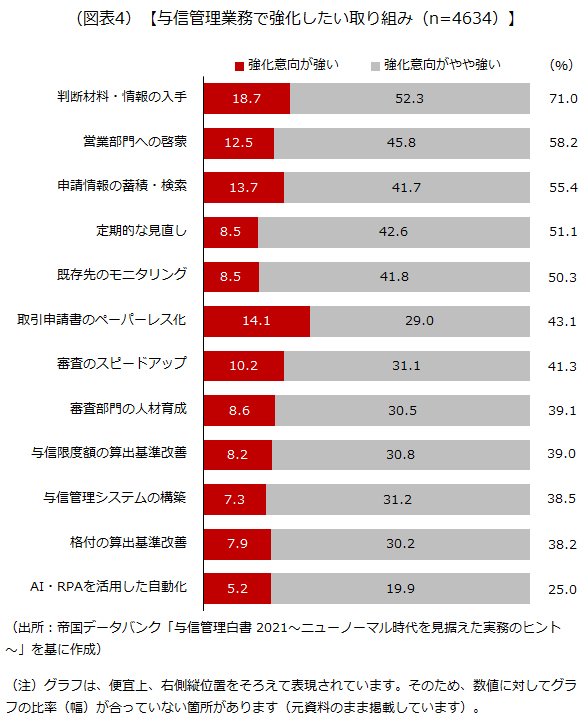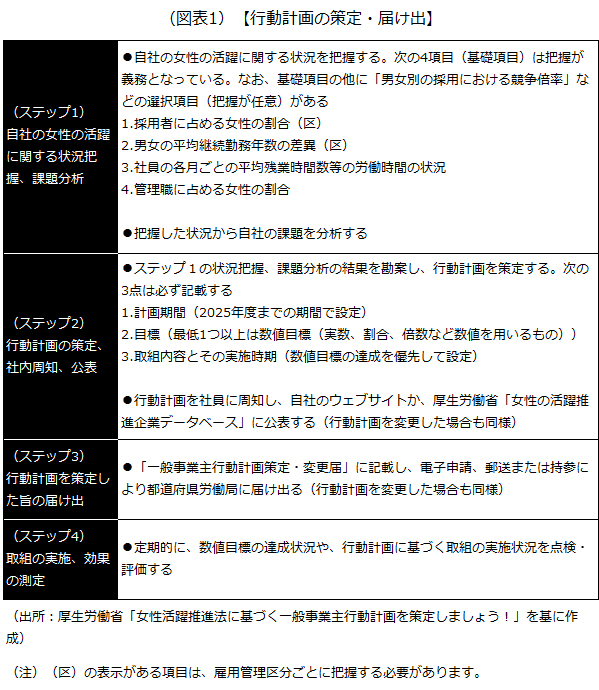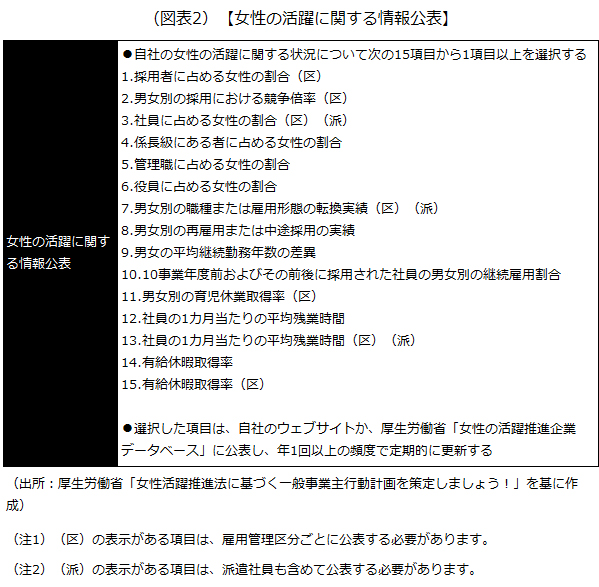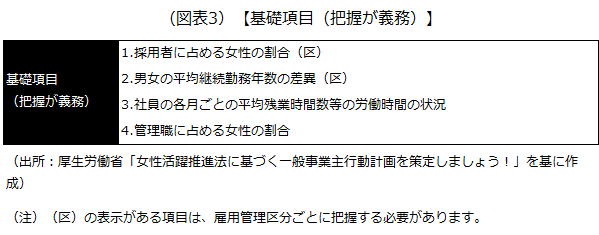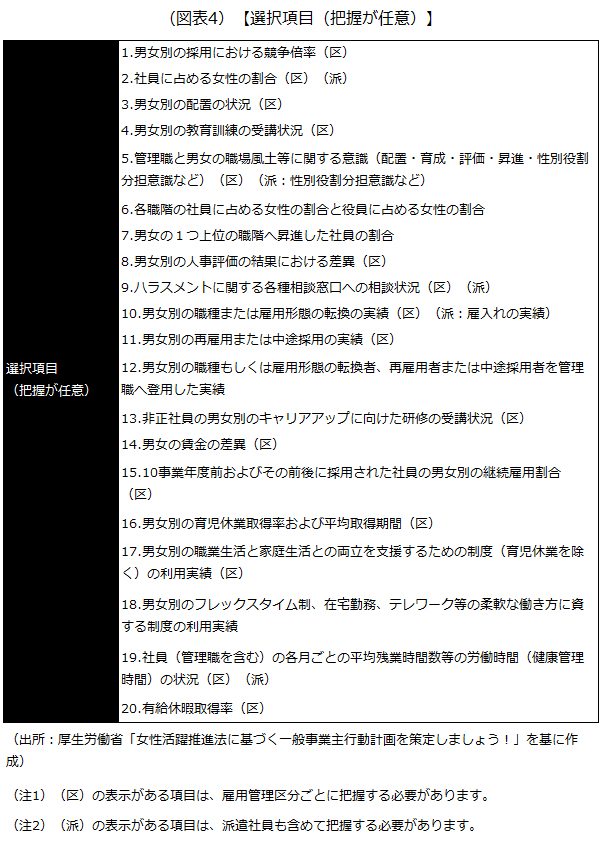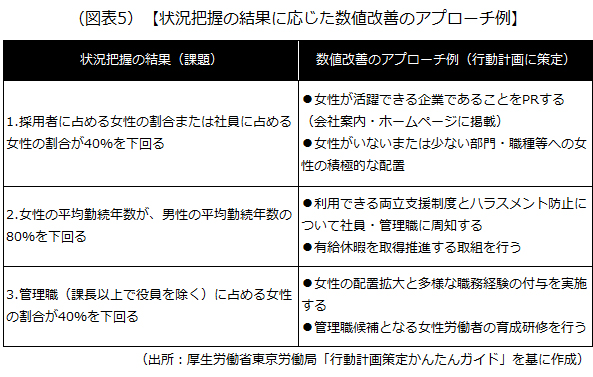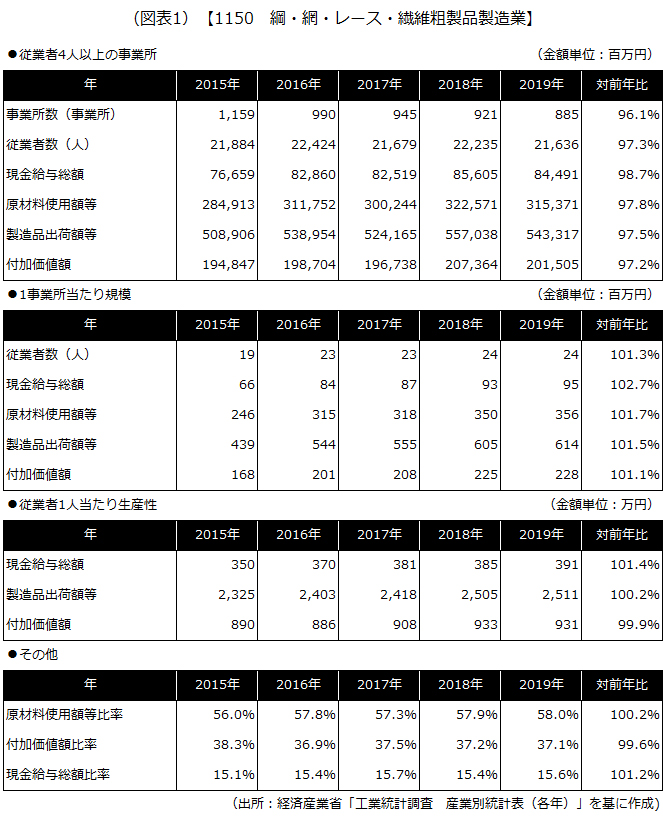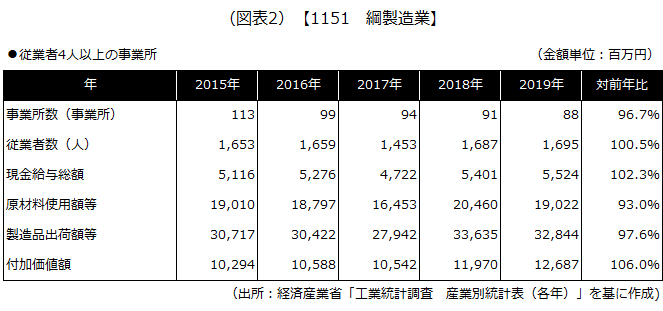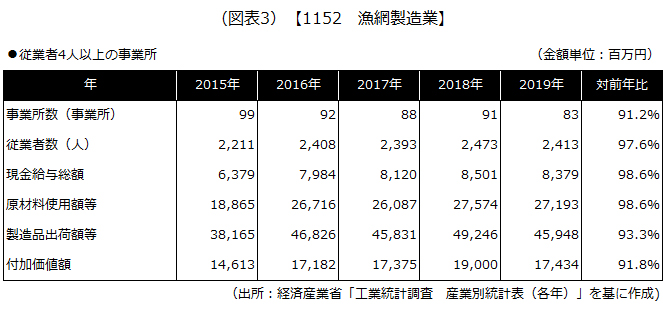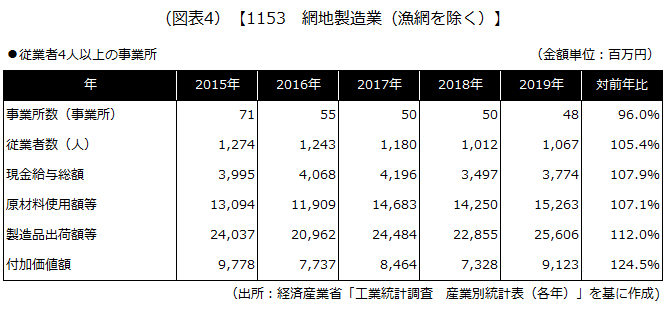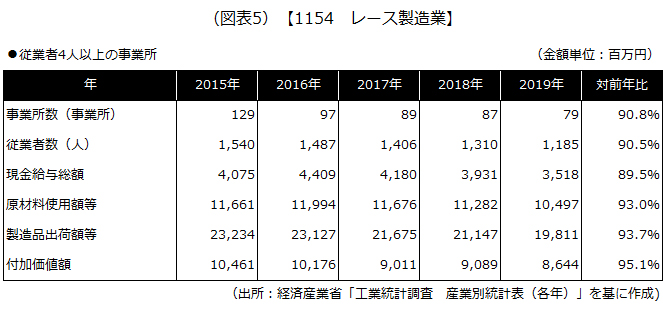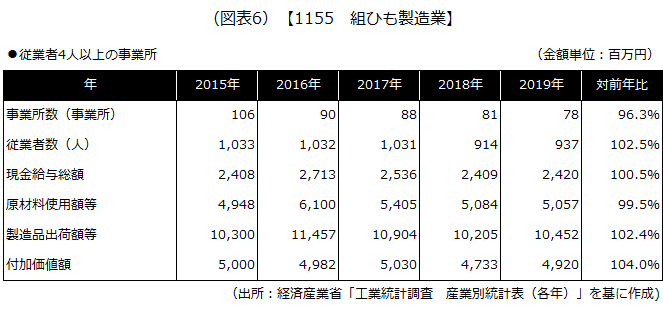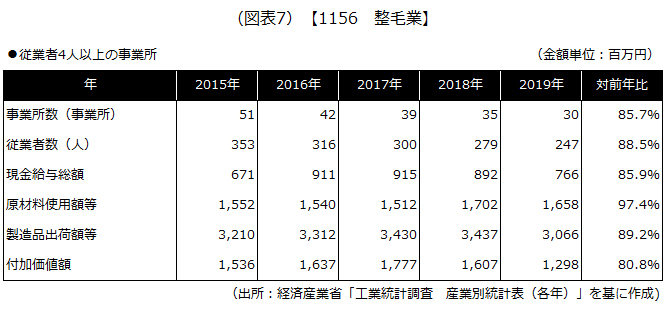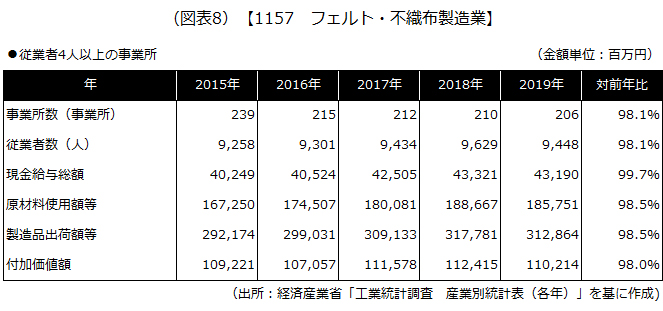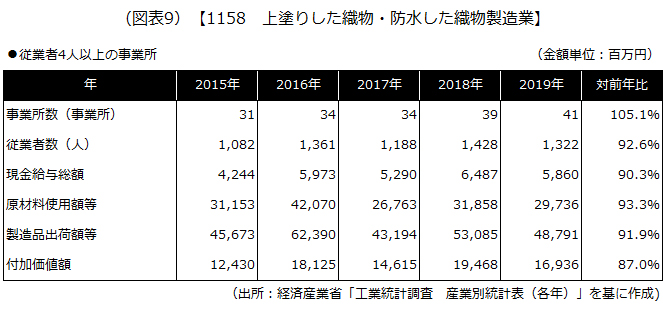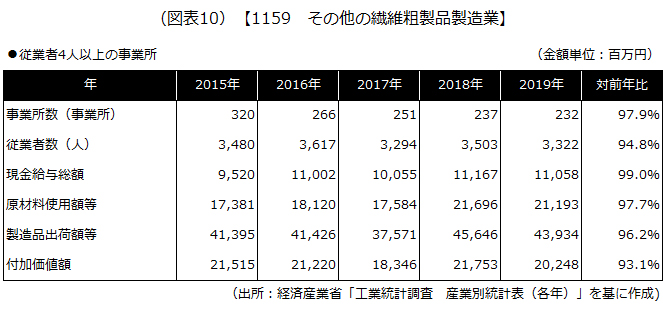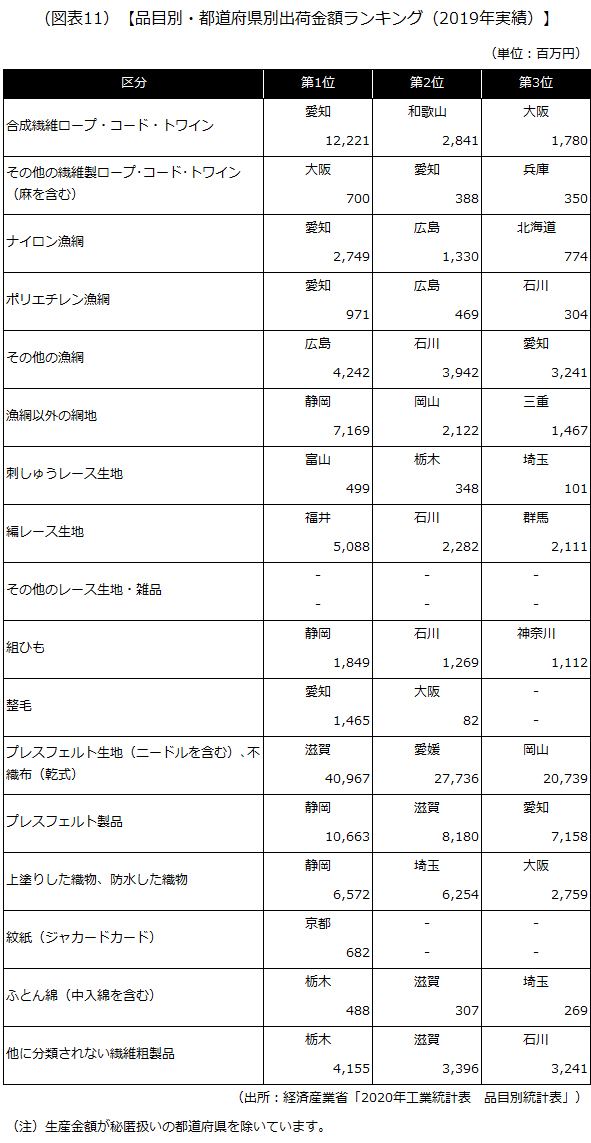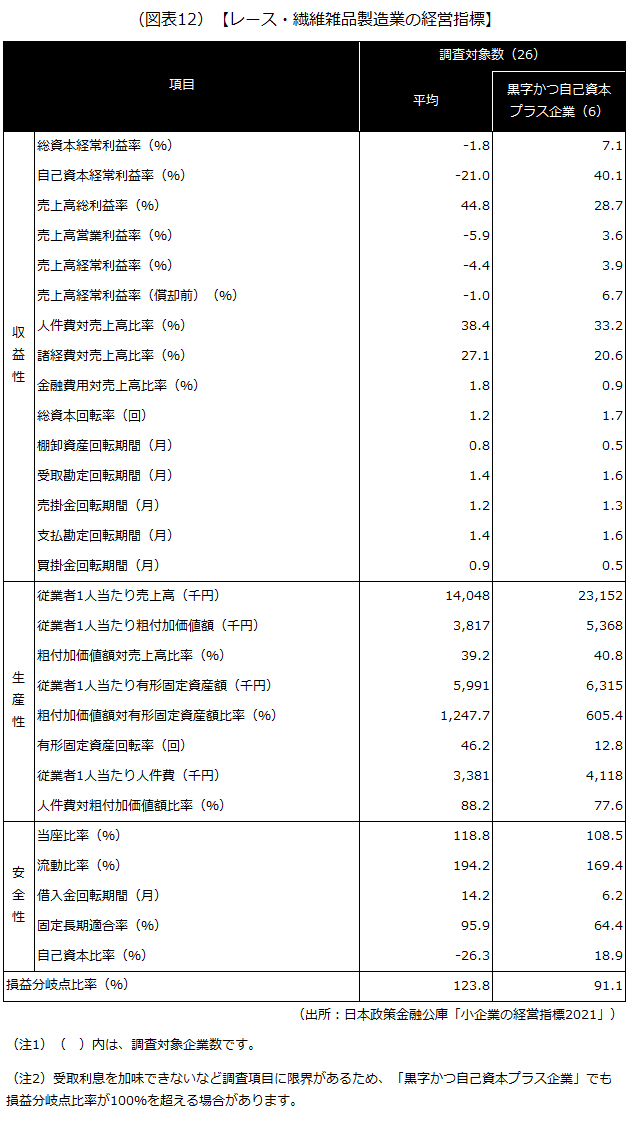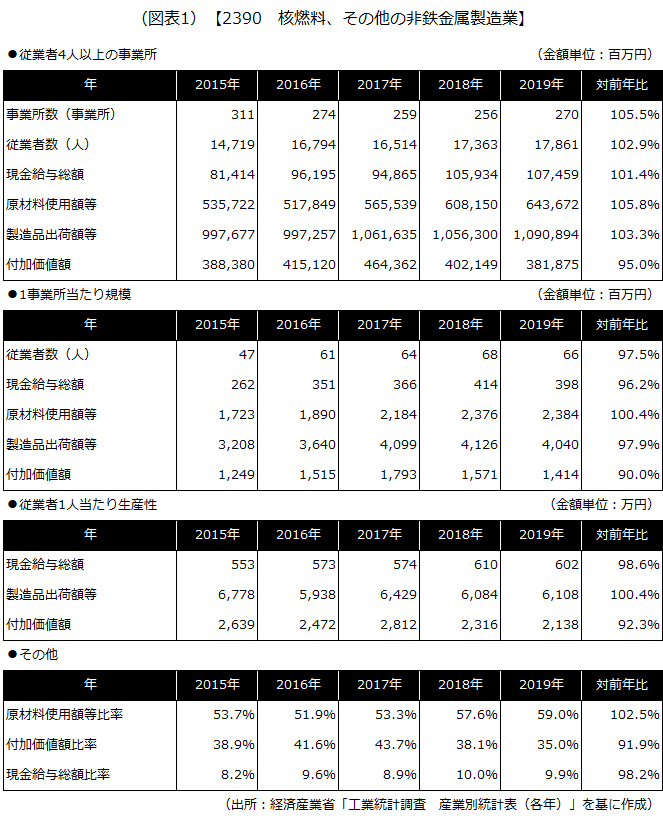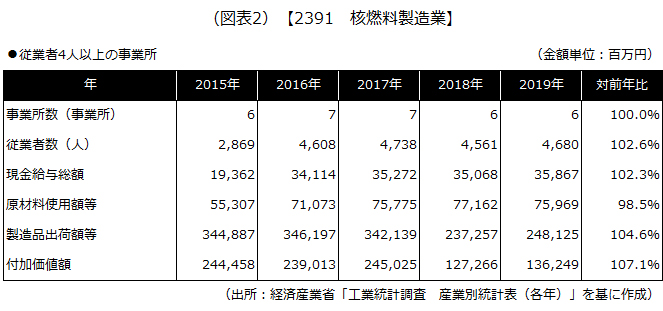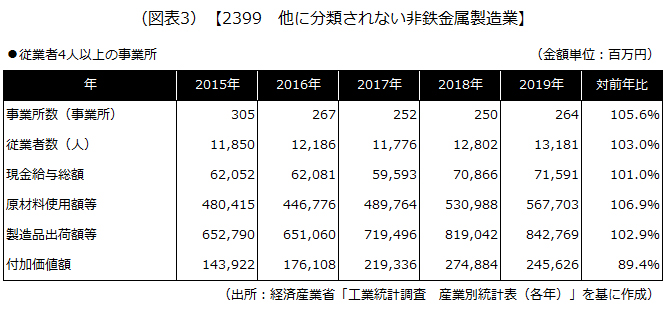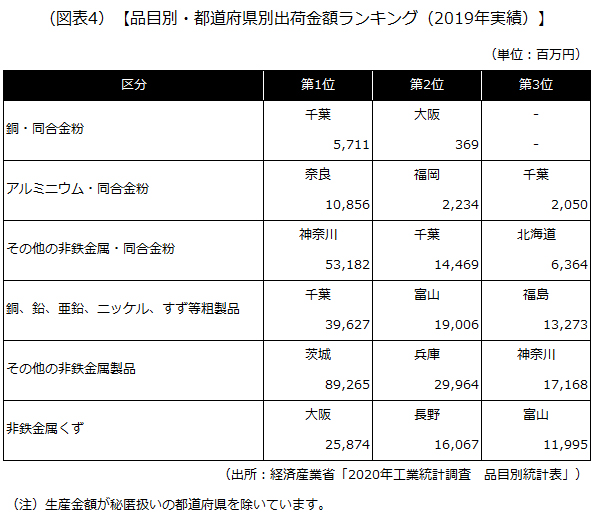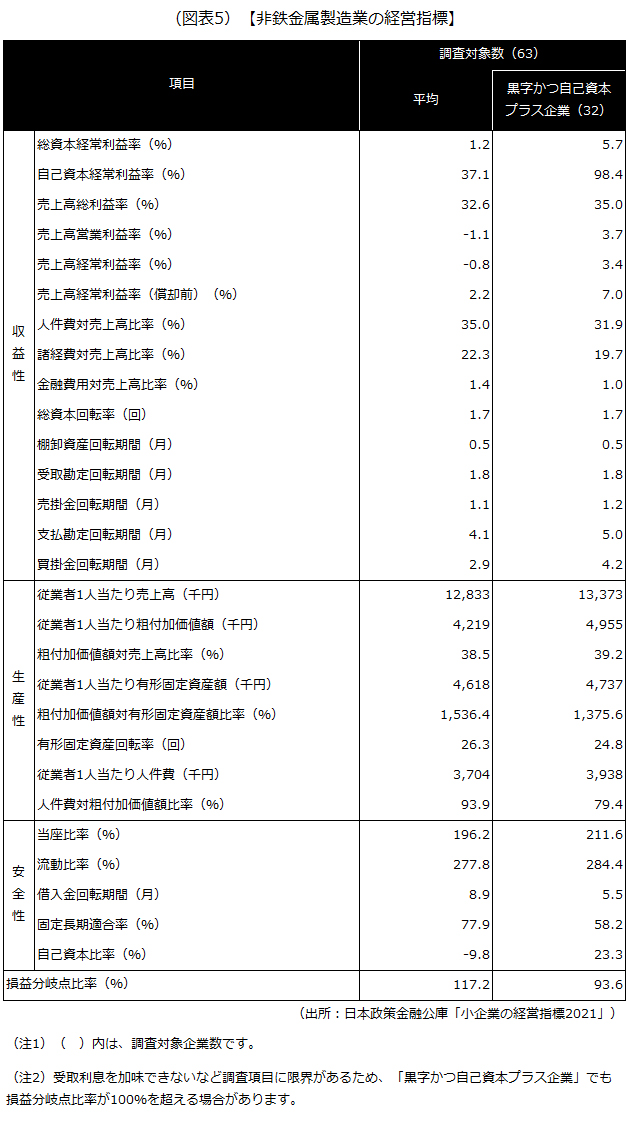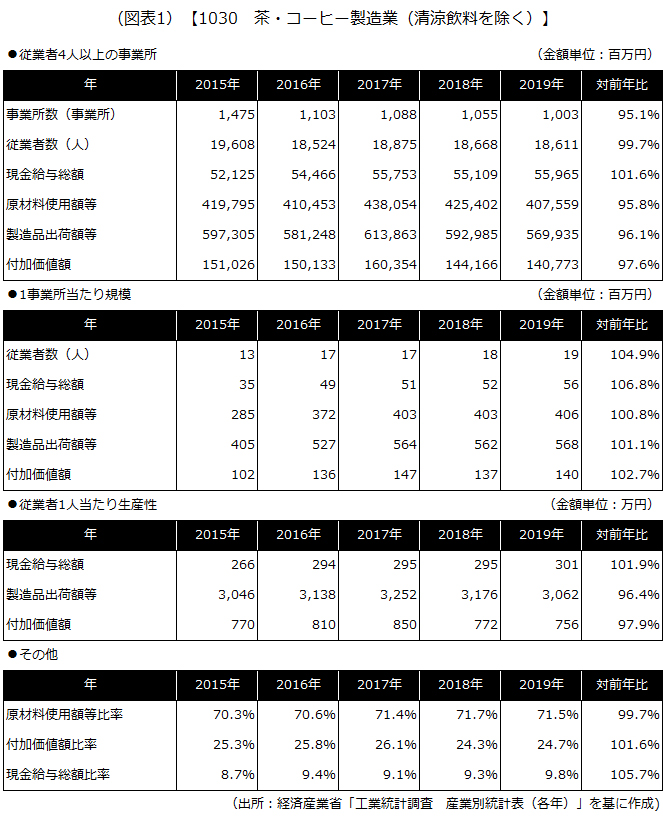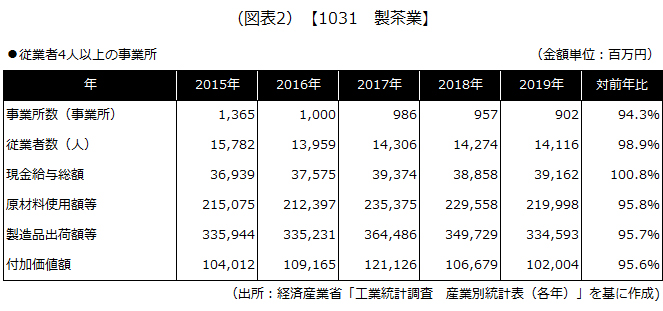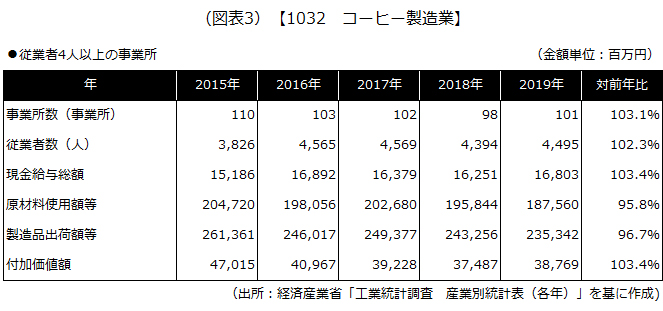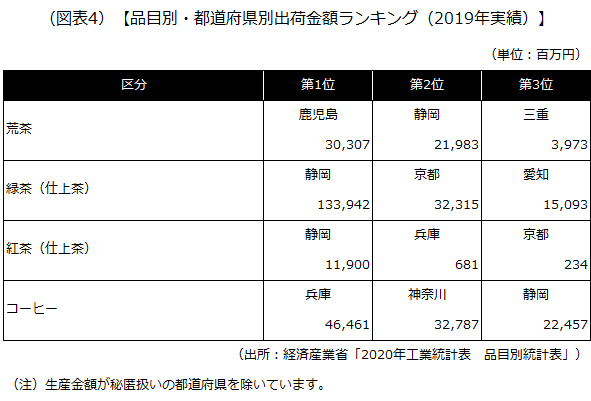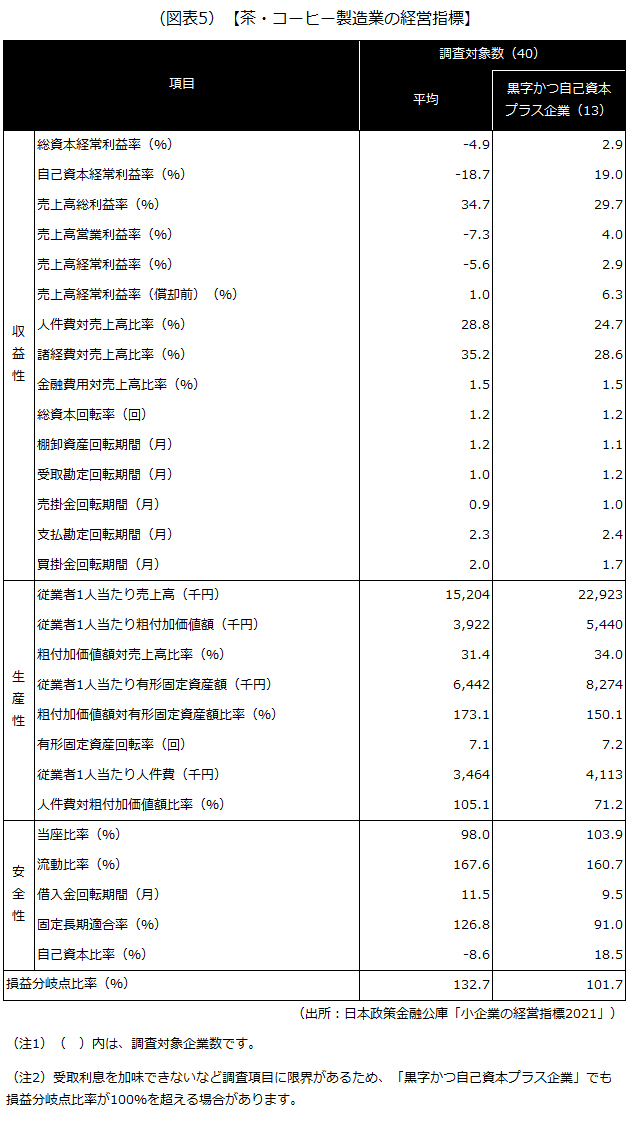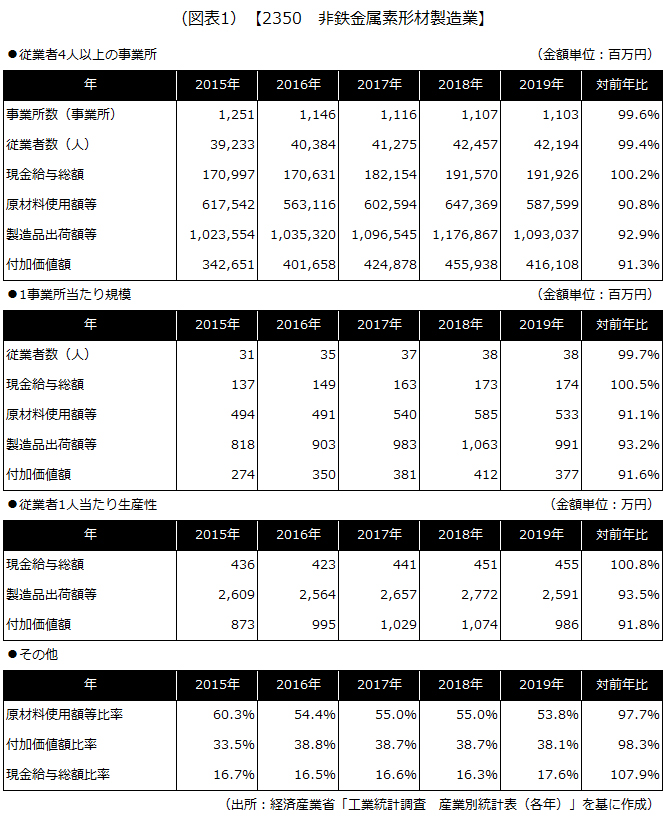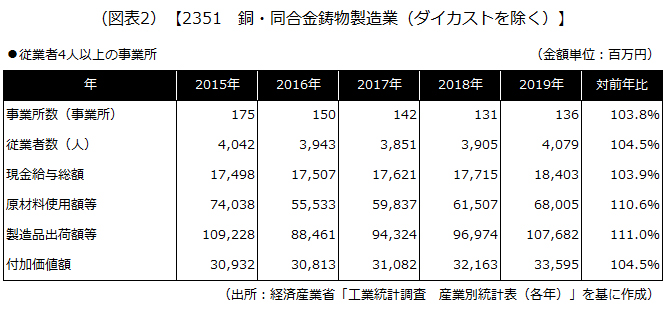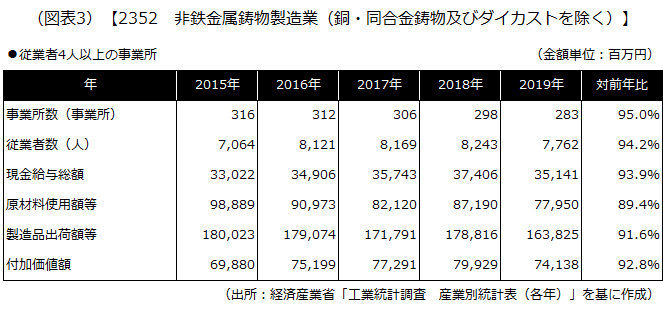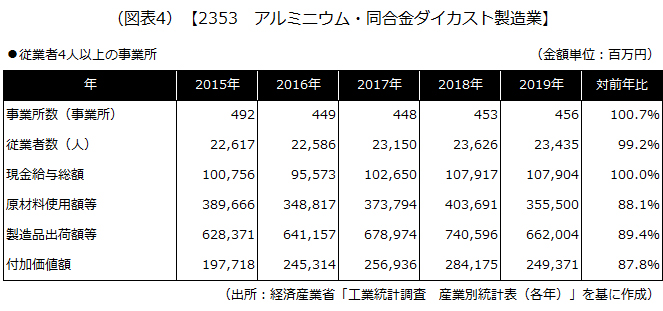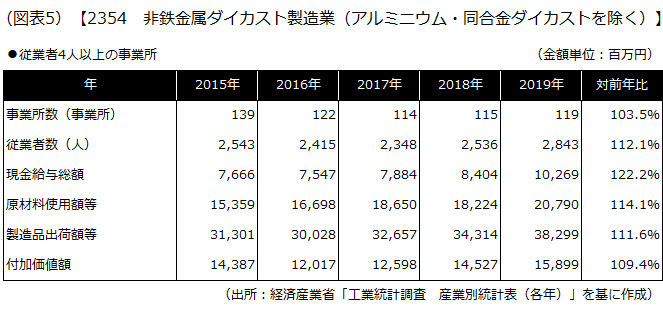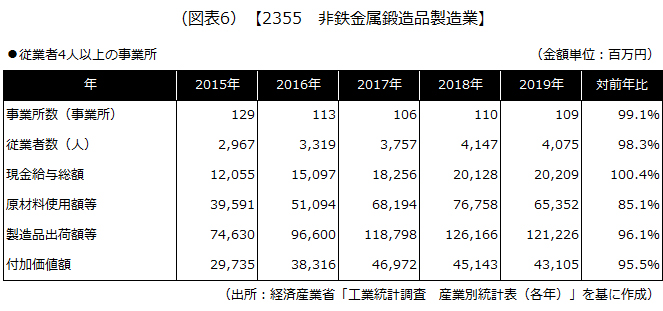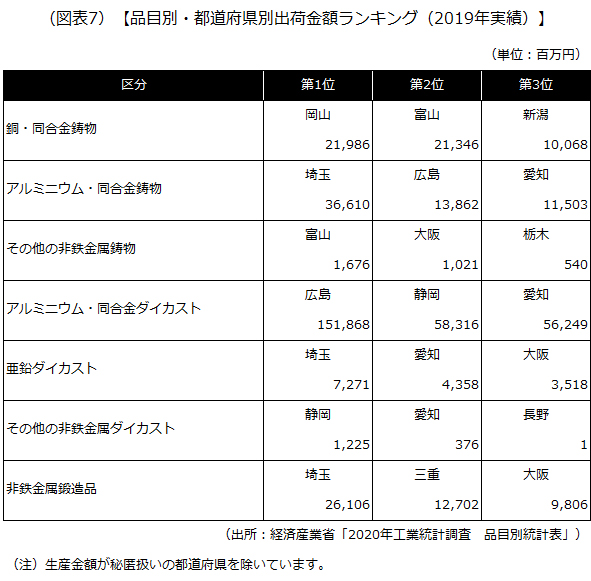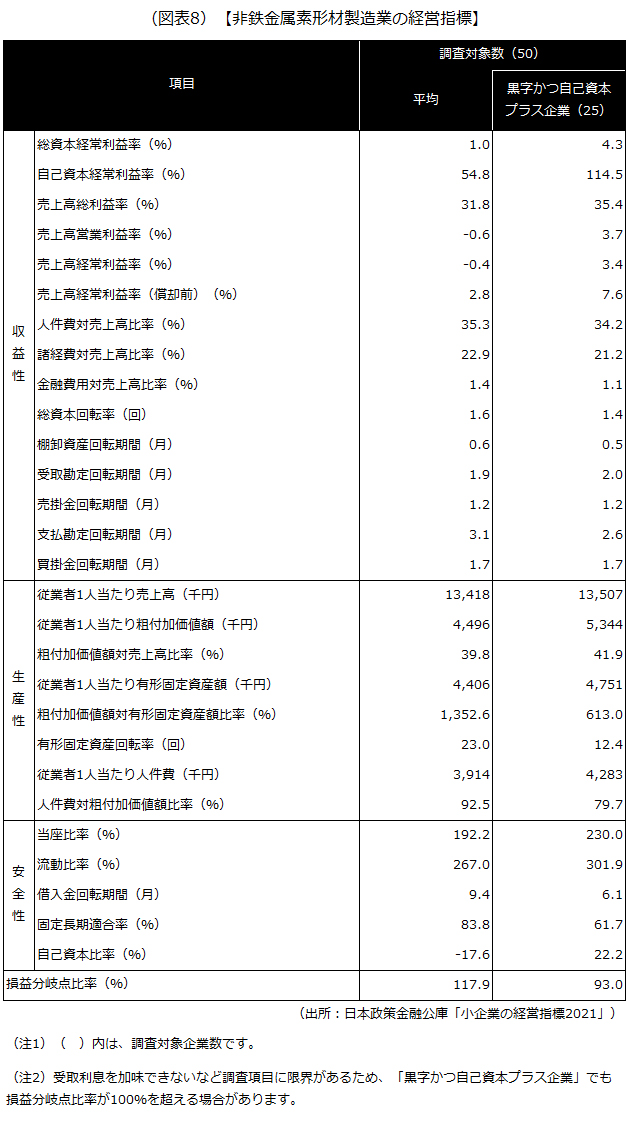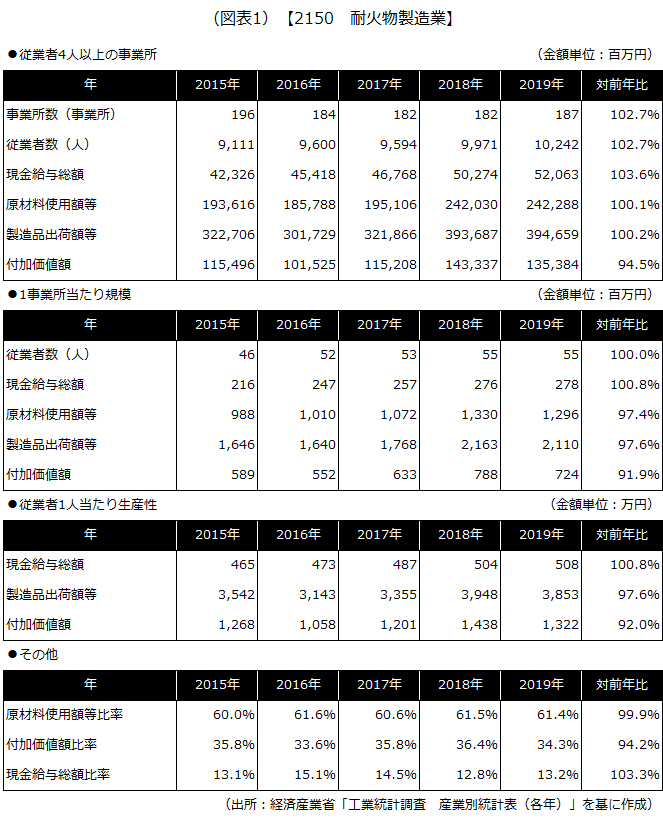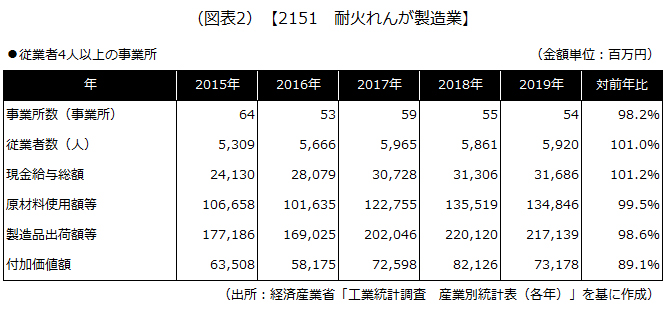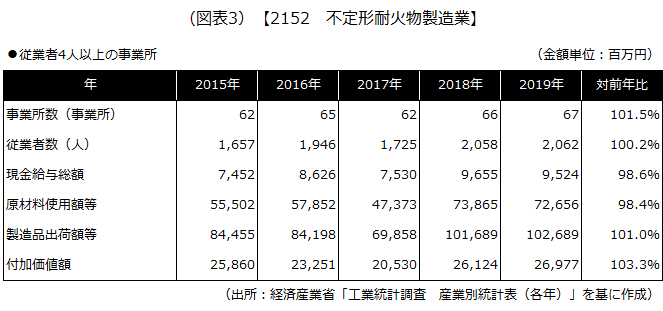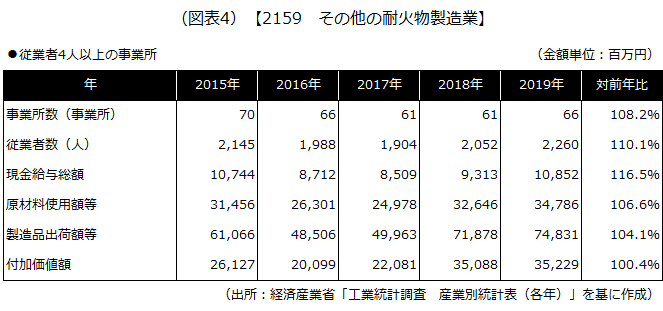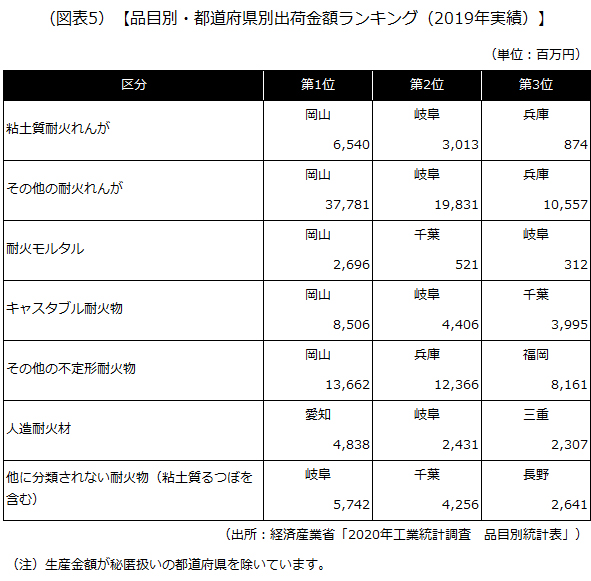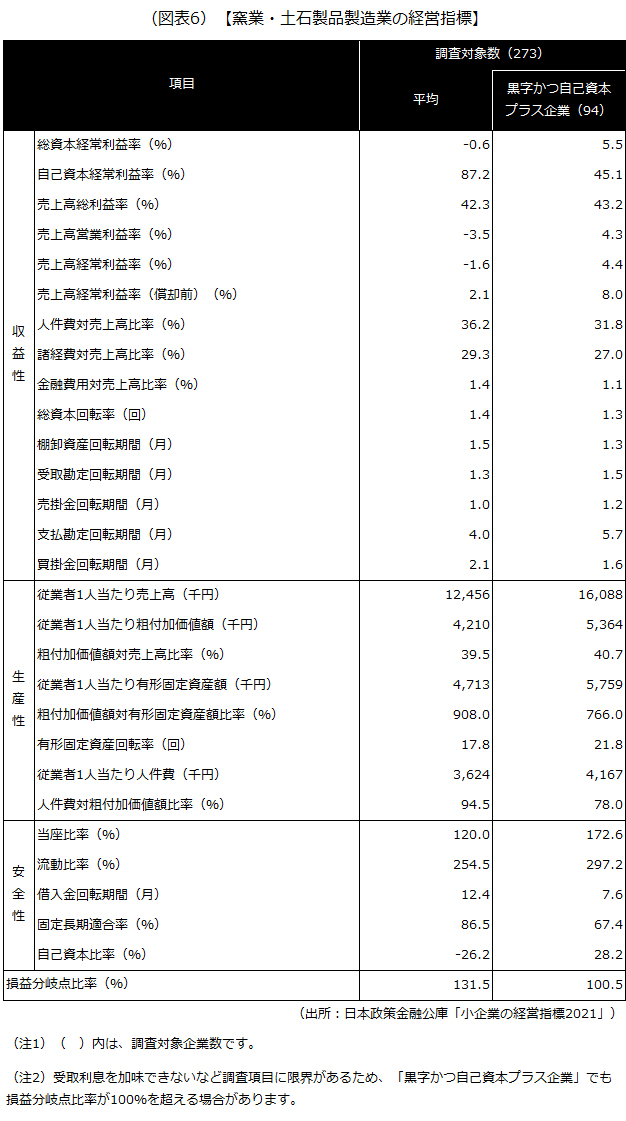書いてあること
- 主な読者:社員101人以上の会社の経営者
- 課題:女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」の策定義務が生じる
- 解決策:女性活躍は経営者と現場のギャップが生じがちなので注意。計画の策定・実行で助成金の対象となるので受給を検討する
1 2022年4月1日より「行動計画」に関する義務の対象が拡大
女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」(以下「行動計画」)とは、
会社が女性の活躍に関する課題を解決するための計画であり、社員数が常時301人以上の会社に策定などが義務付けられている
状況です。これが、
2022年4月1日より、社員数が常時101人以上の会社にも義務付けられる
ことになります。
経営者は「当社では女性が十分に活躍している」と思っていても、実際は、
- 育児休業から復帰した女性へのサポートが不十分で、その後のキャリアが限定される
- 女性の管理職登用に注力しているが、そもそも管理職に与えられている権限が小さい
といったケースがあります。行動計画を策定する場合、その過程で「採用者に占める女性の割合」「管理職に占める女性の割合」などを確認するので、こうした課題が明らかになる可能性があります。また、行動計画を策定すると、一定の要件を満たすことで、
- 最大60万円の「両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)」を受給できる
- 会社PRなどに使える「えるぼし認定」「プラチナえるぼし認定」を取得できる
といったメリットがあります。
2 まずは行動計画の策定などの全体像を押さえよう
2022年4月1日より、社員数が常時101人以上の会社に義務付けられるのは、
- 行動計画の策定・届け出
- 女性の活躍に関する情報公表
です。
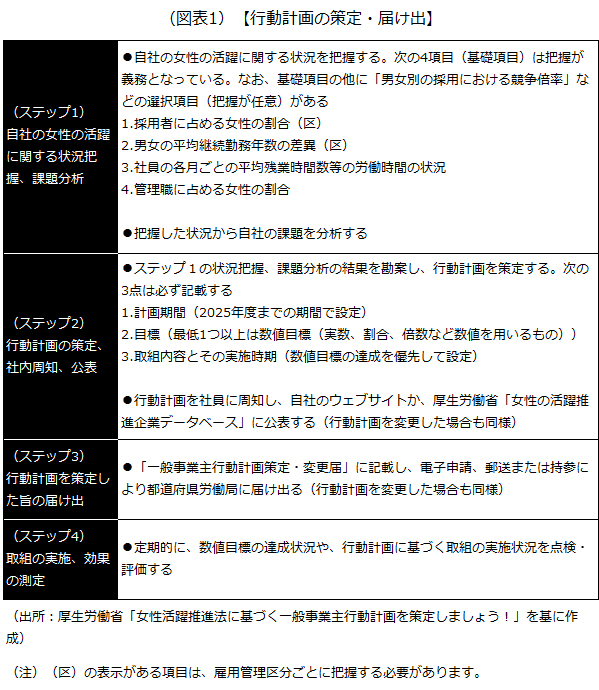
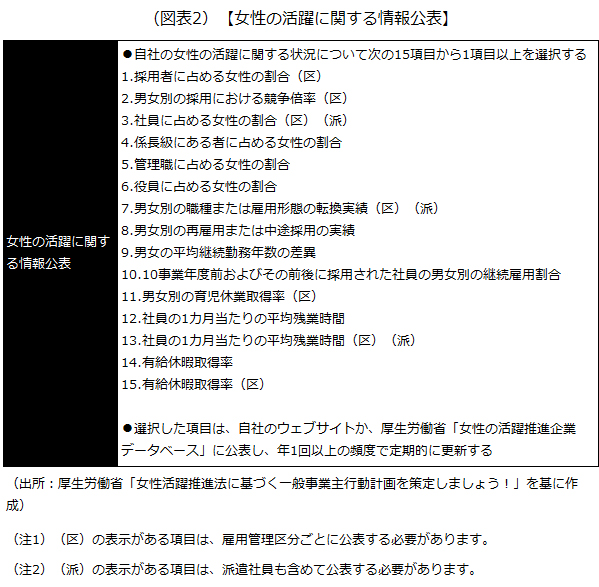
「1.行動計画の策定・届け出」「2.女性の活躍に関する情報公表」に違反しても罰則はありませんが、次のペナルティーを受けることがあります。
都道府県労働局からの報告徴収、助言、指導、勧告、会社名の公表
ここから先は、「1.行動計画の策定・届け出」の「(ステップ1)自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析」に焦点を当てて、ポイントを紹介します。行動計画の策定例、届け出の様式、女性の活躍に関する情報公表のイメージなどについては、こちらをご確認ください。
3 女性の活躍に関する課題を明らかにする
1)「基礎項目」と「選択項目」を押さえる
女性の活躍に関する状況を把握する場合、まずは「基礎項目」の状況を全て調査し、次に「選択項目」の状況を可能な限り調査します。
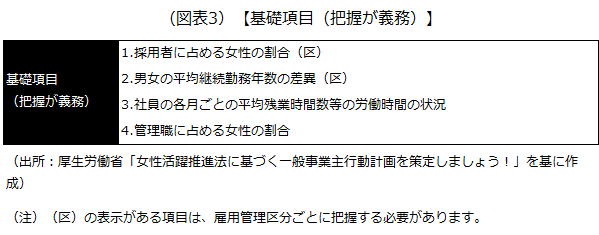
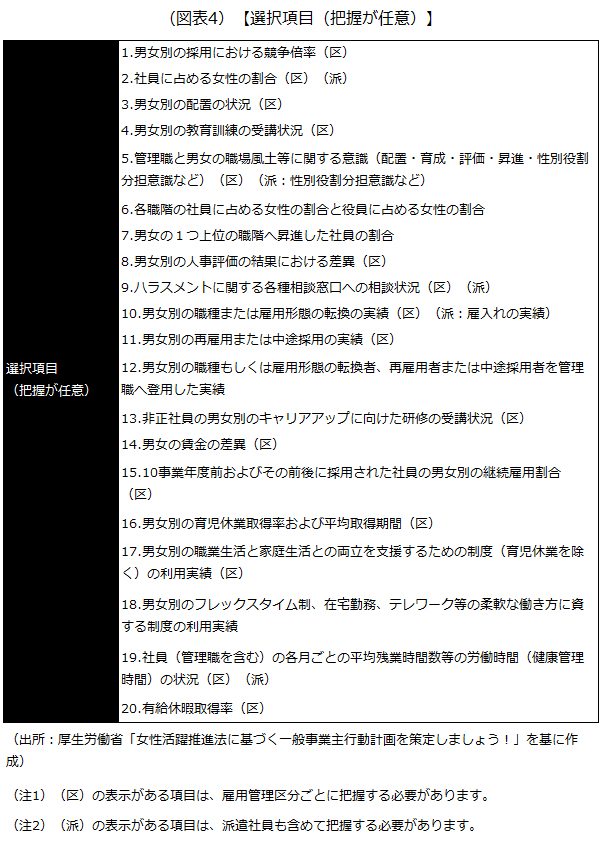
2)数値だけではなく本質も見る
把握した状況を基に自社の課題を分析し、解決のためのアプローチを行動計画に落とし込みます。厚生労働省東京労働局では、状況把握の結果に応じた数値改善のアプローチ例として、次のようなものを紹介しています。
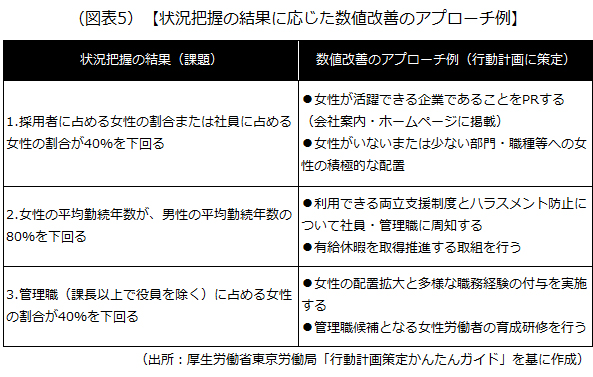
基本的には基礎項目と選択項目のうち、数値が低い項目に注目することになりますが、注意しなければならないのは、
「数値が低い項目=解決すべき課題」とは限らない
ことです。例えば、管理職に占める女性の割合が低い場合、
そもそも管理職になることが、本当に女性の活躍につながるのか
という問題があります。中小企業では個々の社員一人一人の裁量が大きいため、管理職がマネジメントできる範囲が限られます。つまり、「管理職になったら女性が活躍できる」とは言いにくく、管理職の権限を見直すことが先決となります。
こうした課題を見つけるには、
経営者自身が「女性が活躍しているとは、どのような状態なのか」を掘り下げる
ことが重要です。活躍のイメージは、
- 新しい仕事に積極的に挑戦する女性が多い
- 育児休業や時短勤務などの両立支援制度を、積極的に利用する女性が多い
- 特別な成果などを上げるわけではないが、活気にあふれている女性が多い
などさまざま考えられます。
3)解決のためのアプローチに注意する
解決のためのアプローチも慎重に判断します。例えば、女性の育児休業取得率を高めたい場合、育児休業取得率が低い理由によってアプローチが異なります。
- 管理職の理解が乏しい:マタニティーハラスメント研修などを受講させる
- 長期休業が取得しにくい:多能工化を進めつつ、業務委託なども利用する
- 復帰に不安を覚える:休業中、定期的に仕事に関する情報を共有する
- 復帰後の両立支援が不安:時短勤務など自社の両立支援制度を再度周知する
この辺りは、社内アンケートなどで、
自社の仕事や両立支援制度で改善が必要だと思う項目は何ですか(理由も)
といった質問を、女性にぶつけてみるとよいでしょう。
4 行動計画を策定・実行すると助成金の対象になる
1)両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)
両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)とは、
- 社員数が常時300人以下の会社が、行動計画に盛り込んだ取組内容を実施し、3年以内に数値目標を達成した場合、
- 47万5000円(生産性に関する要件を満たした場合は60万円)が支給される
というものです。申請先は管轄の都道府県労働局で、支給は1社につき1回限りです。詳細はこちらをご確認ください。
2)えるぼし認定・プラチナえるぼし認定
「えるぼし認定」は女性の活躍が推進されている証しといえます。行動計画の策定・届け出、女性の活躍に関する情報公表を行った会社は、えるぼし認定の申請ができます。取得のメリットは次の通りです。
- 自社のウェブサイトや商品などに認定マークを貼布してPRできる
- 公共調達で加点評価を受けられる
- 日本政策金融公庫「働き方改革推進支援資金(企業活力強化貸付)」を、通常より低金利で利用できる
えるぼし認定は3段階に分かれています。また、えるぼし認定を取得した会社のうち、「女性の活躍推進に関する状況が優良である」など一定の要件を満たした会社は、さらに上位の「プラチナえるぼし認定」を取得できます。

えるぼし認定・プラチナえるぼし認定の詳細は、こちらをご確認ください。
以上(2021年11月)
op80138
画像:peshkova-Adobe Stock