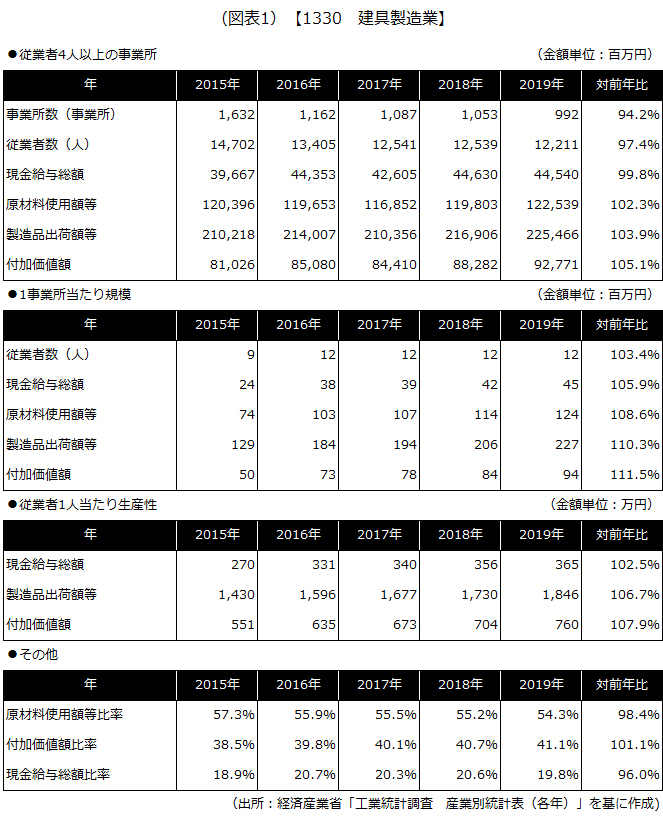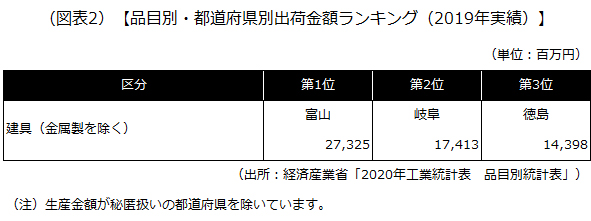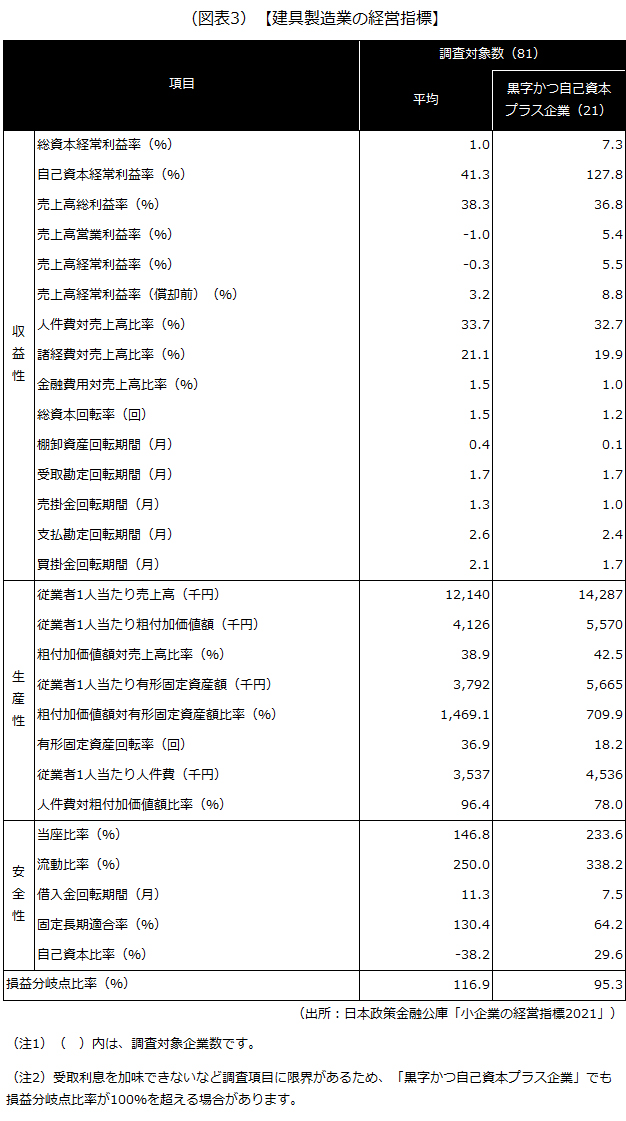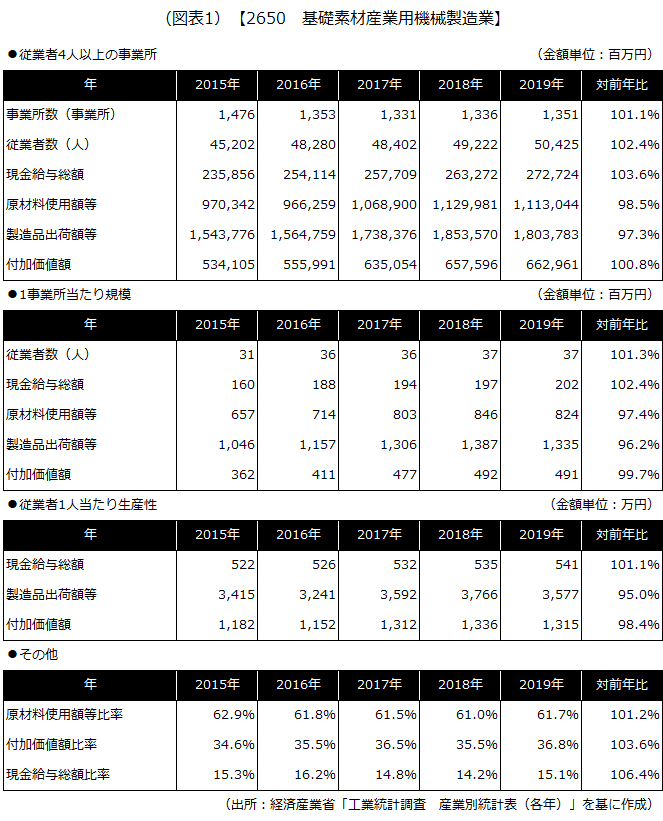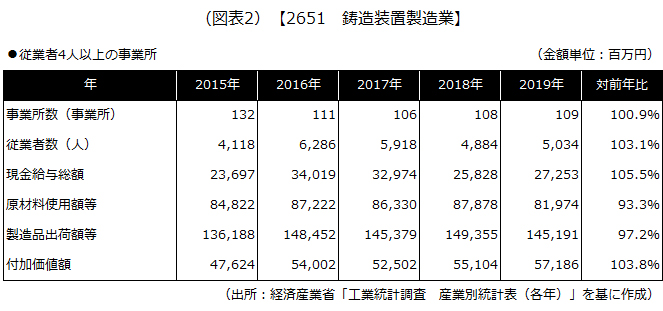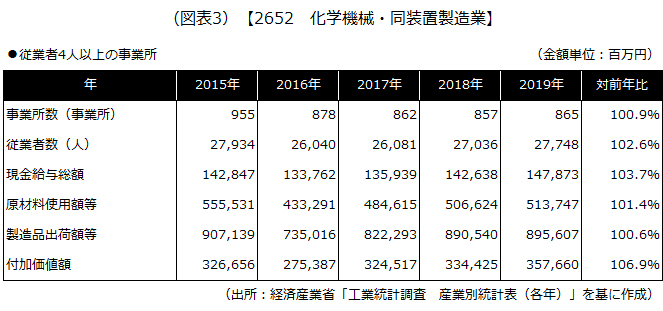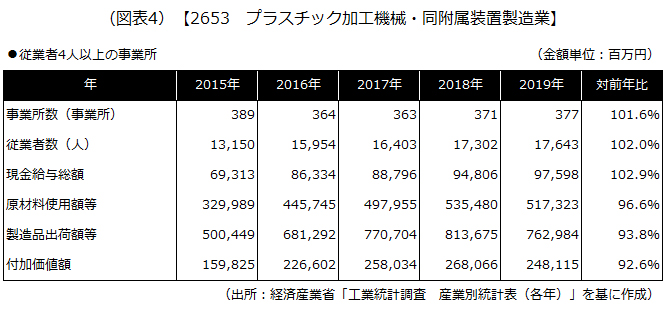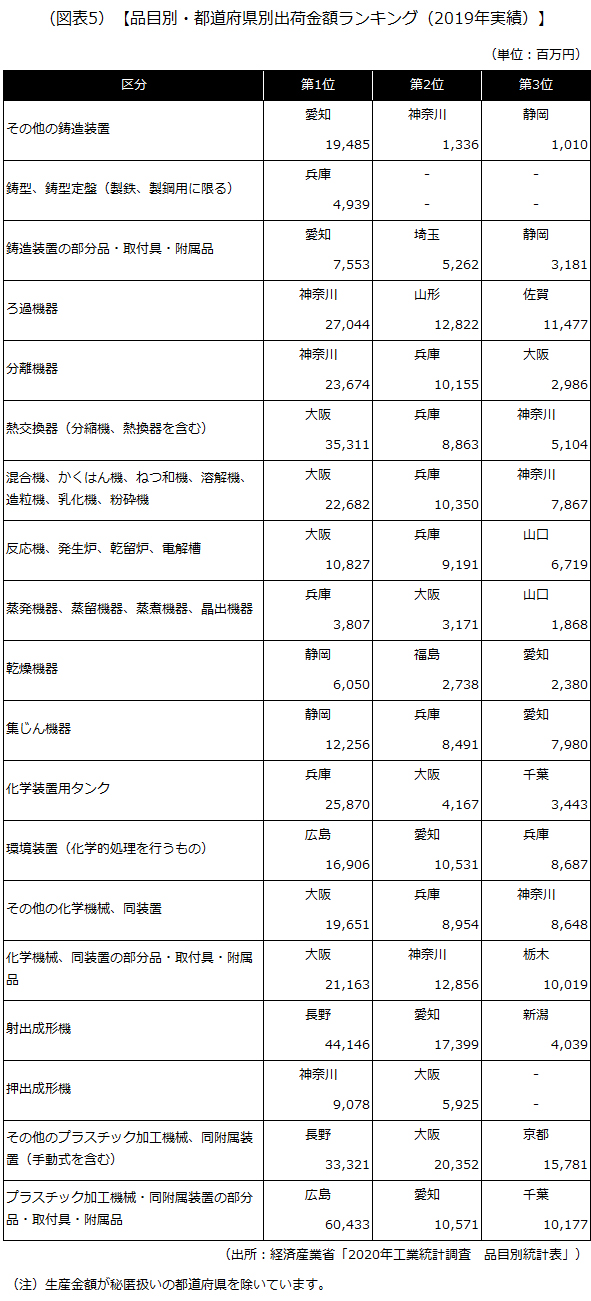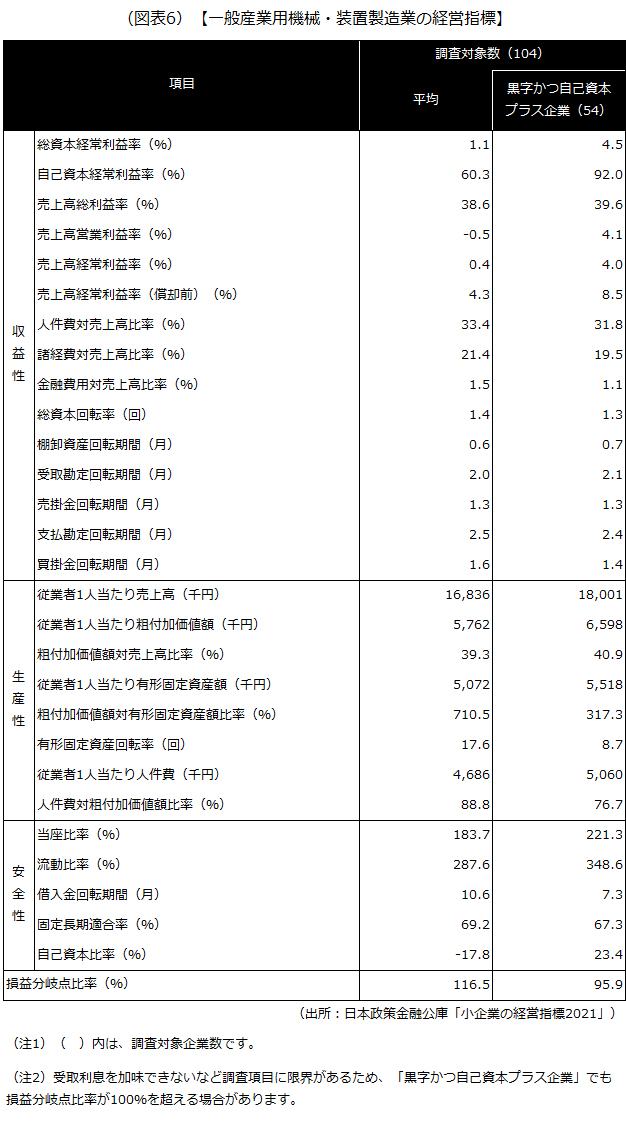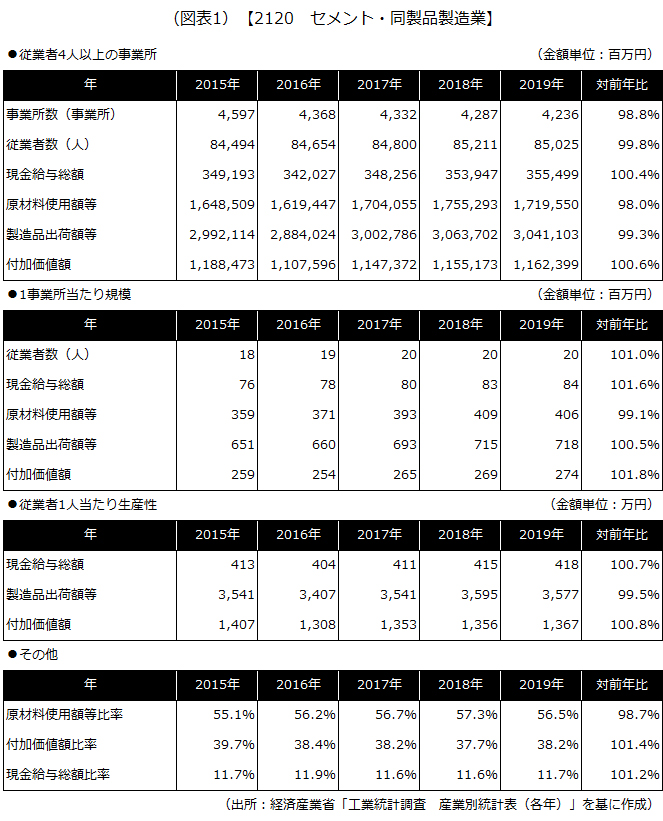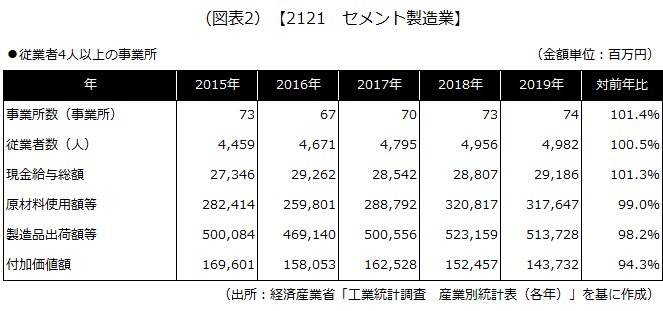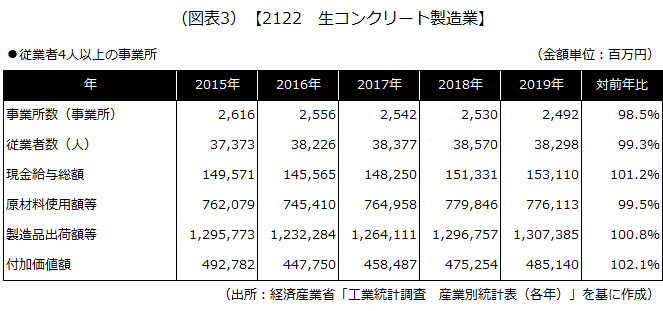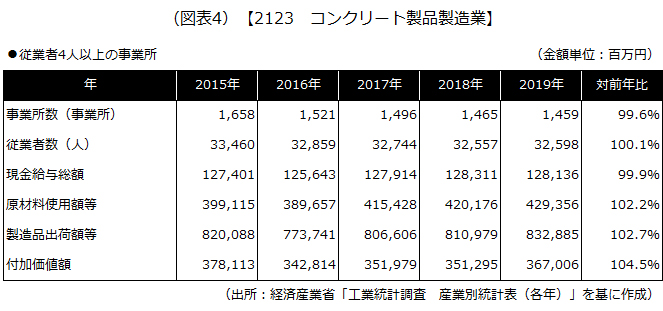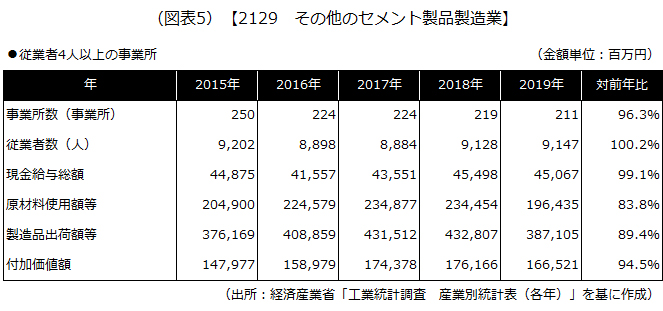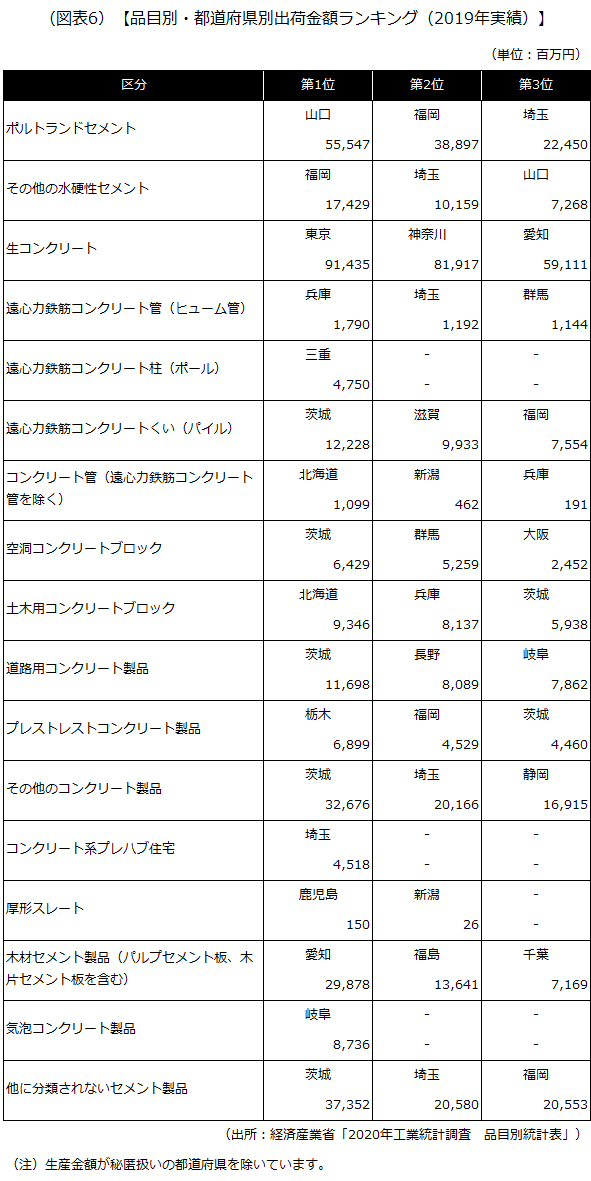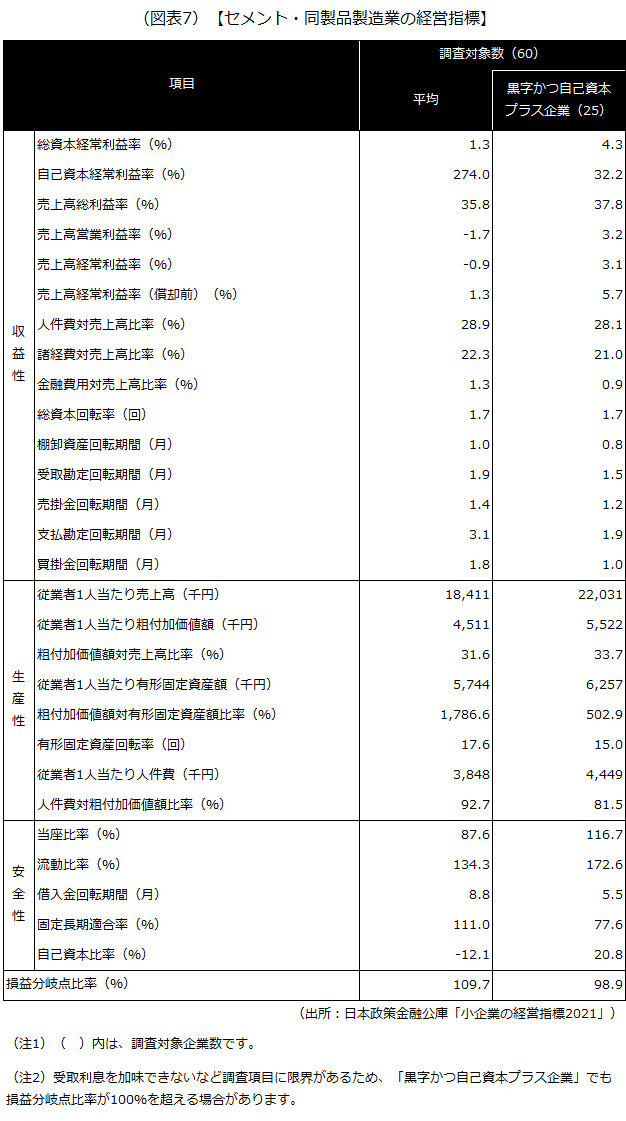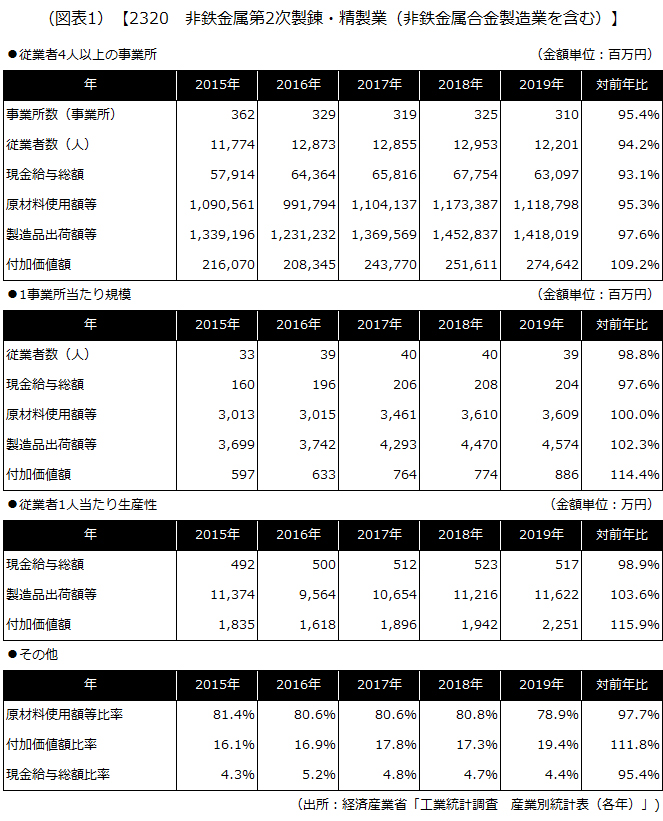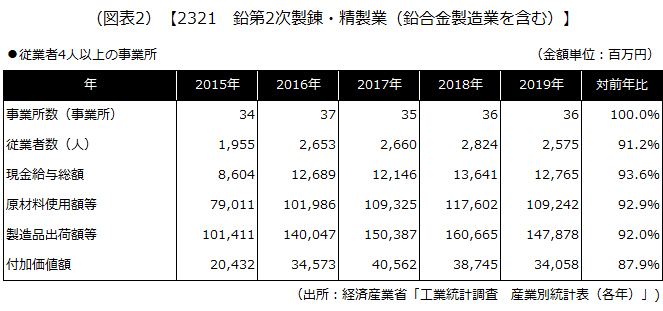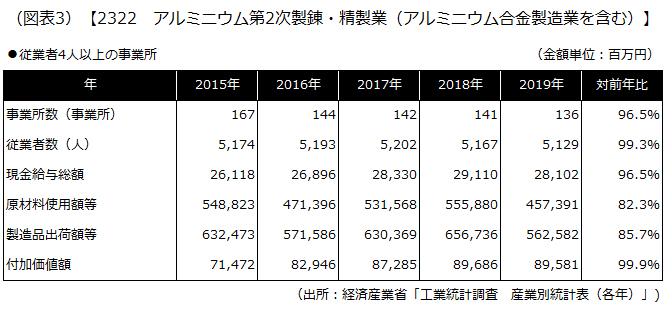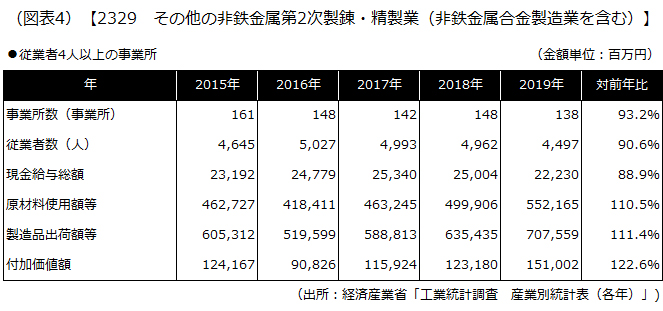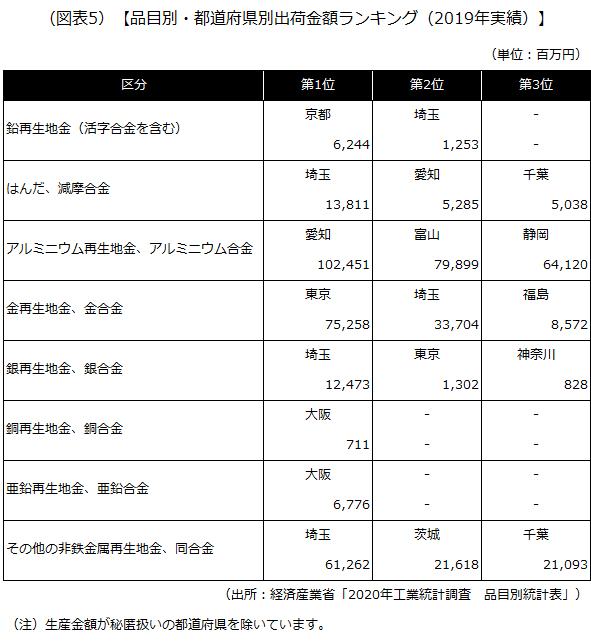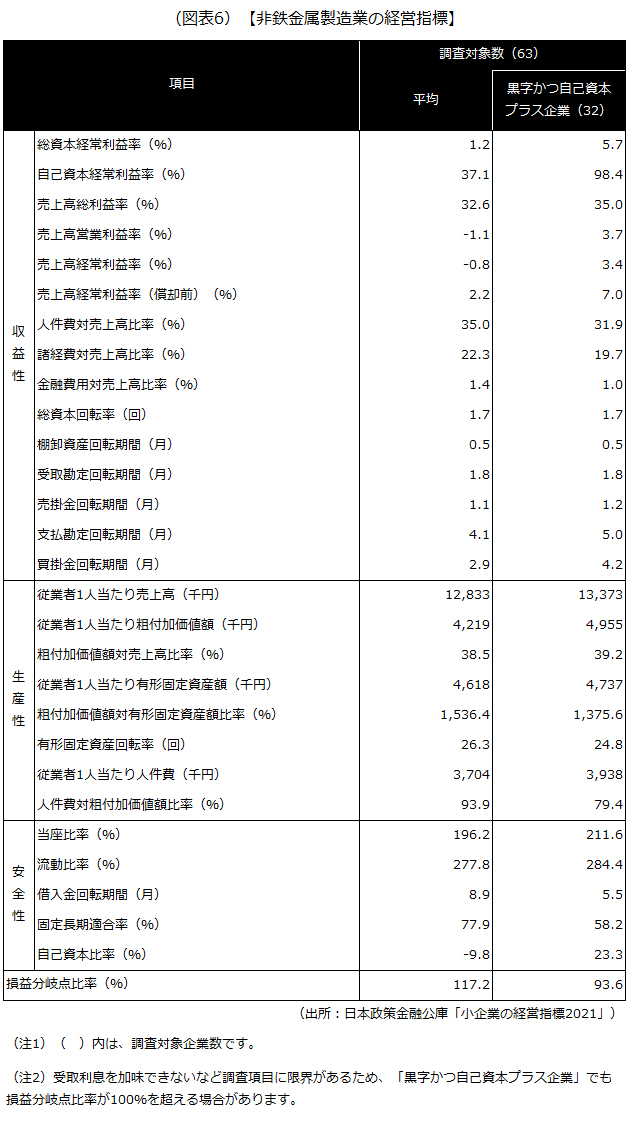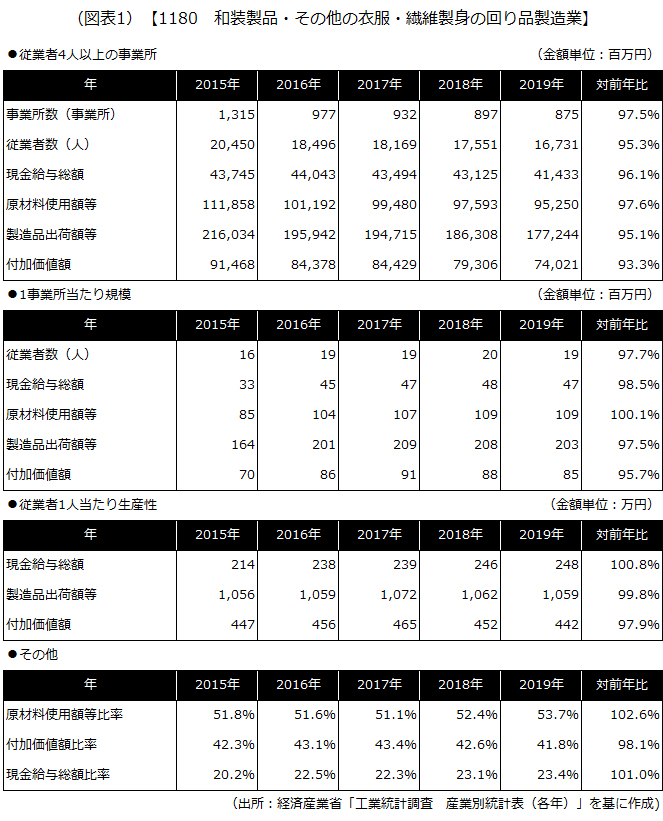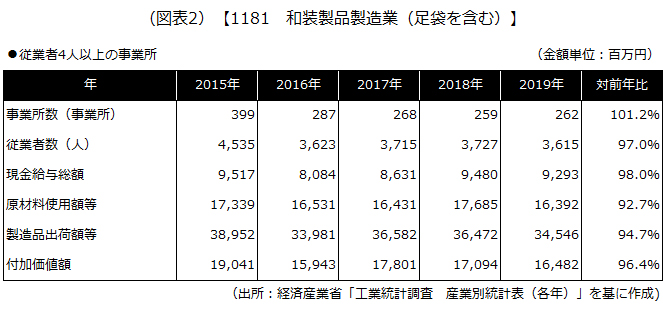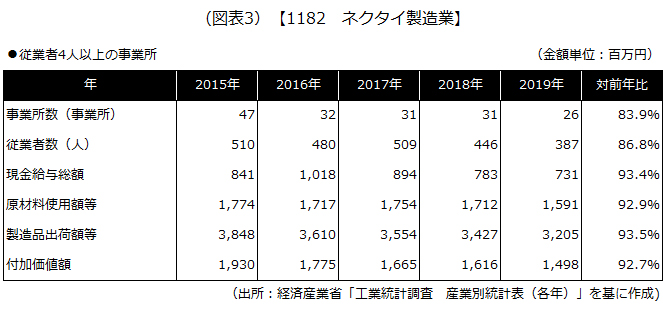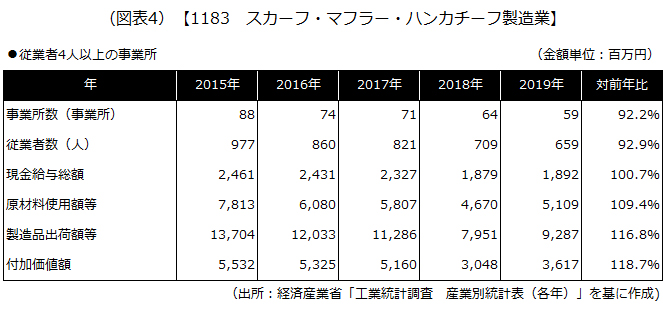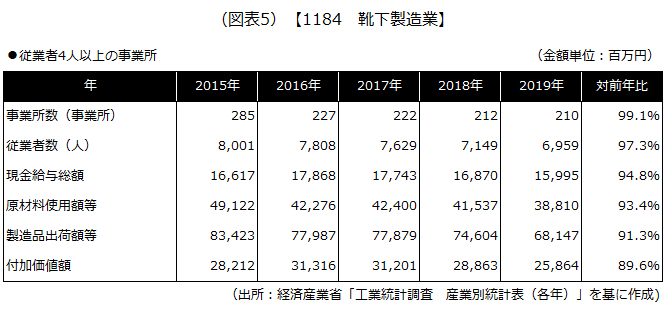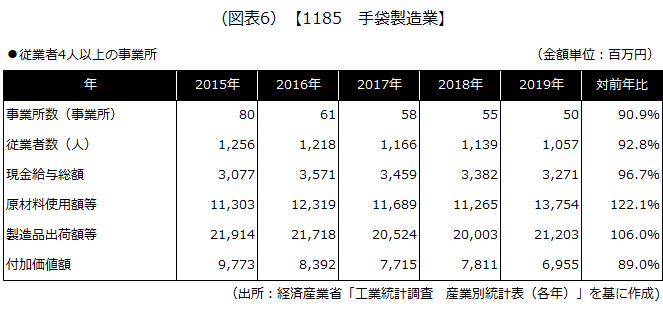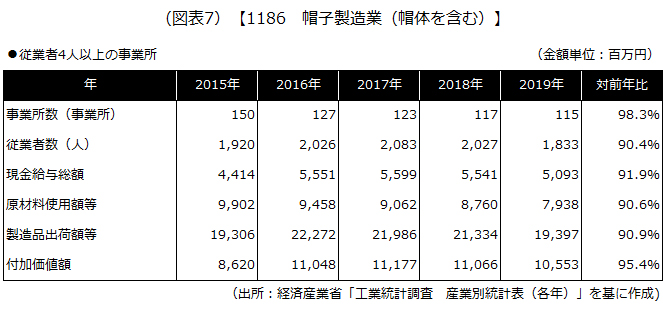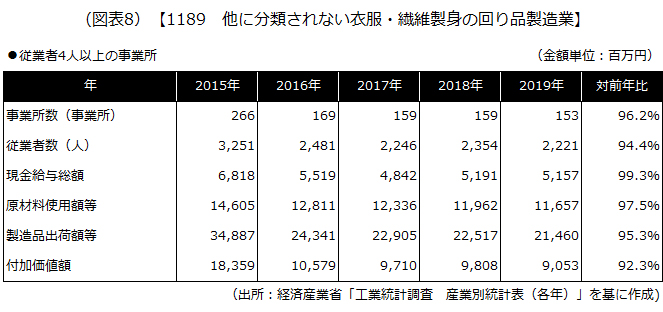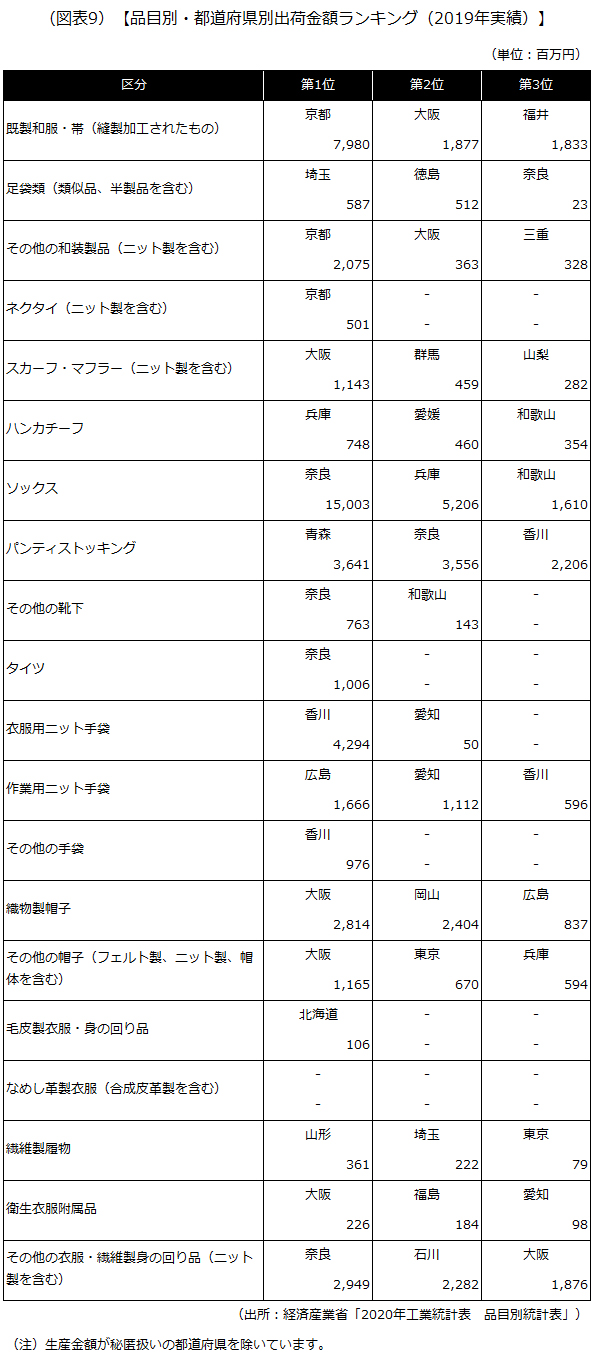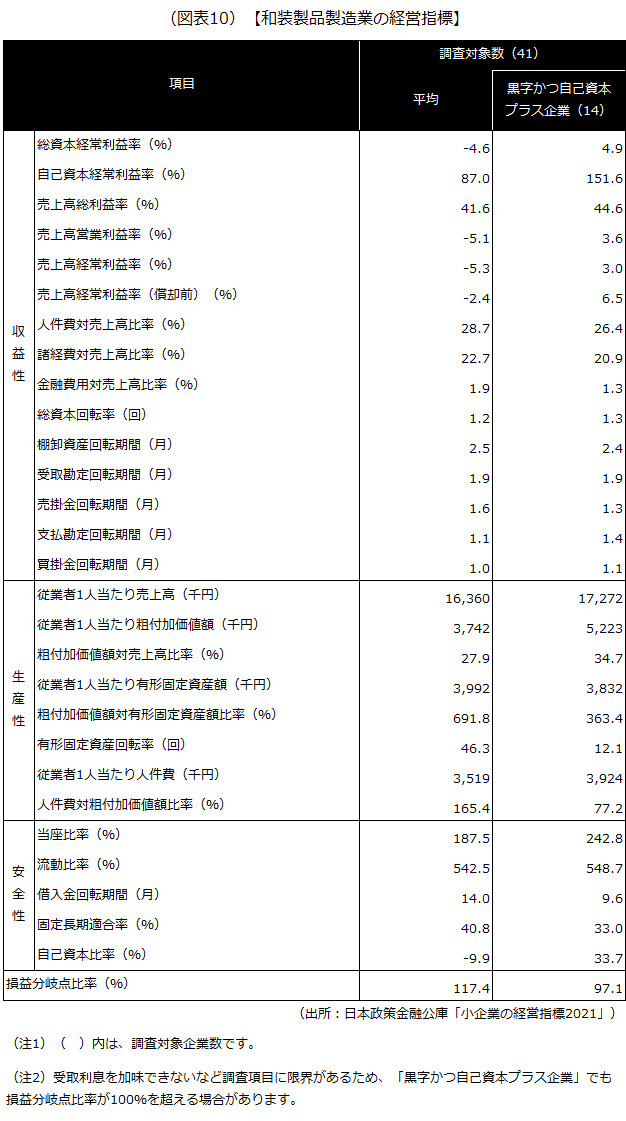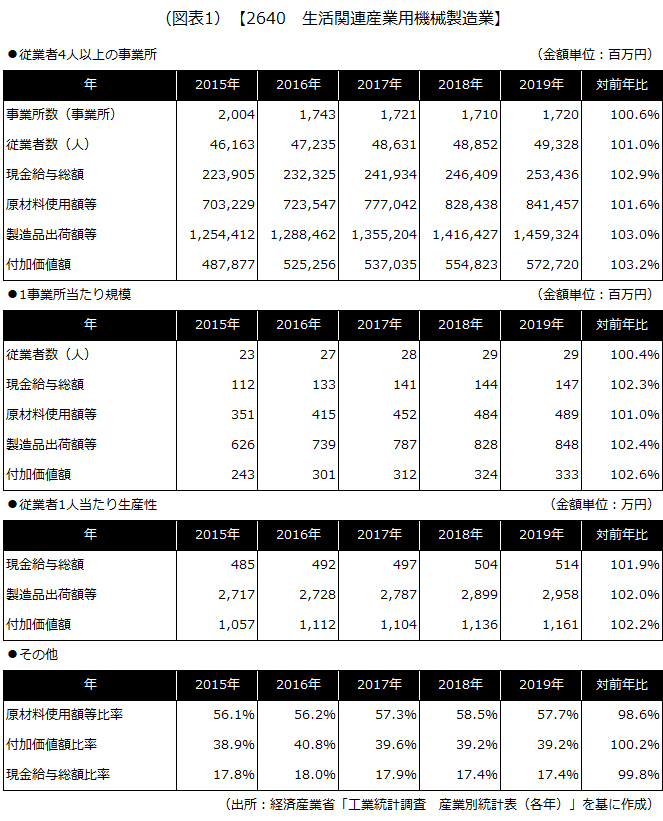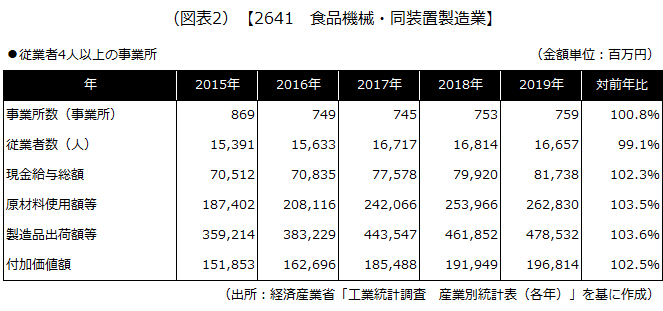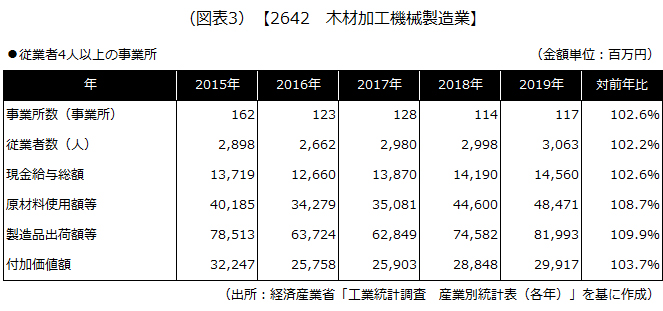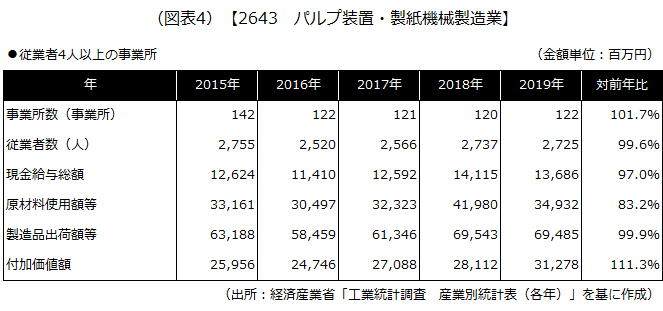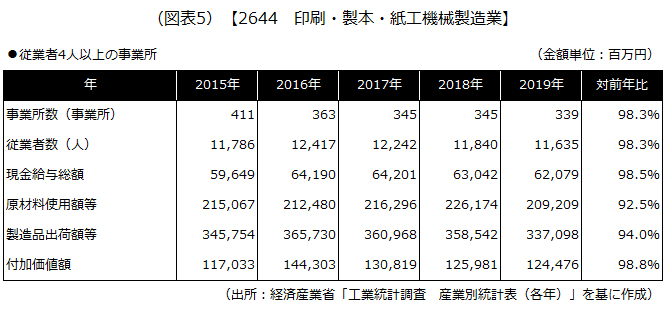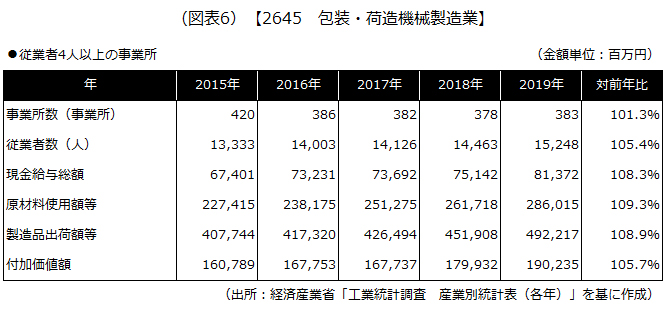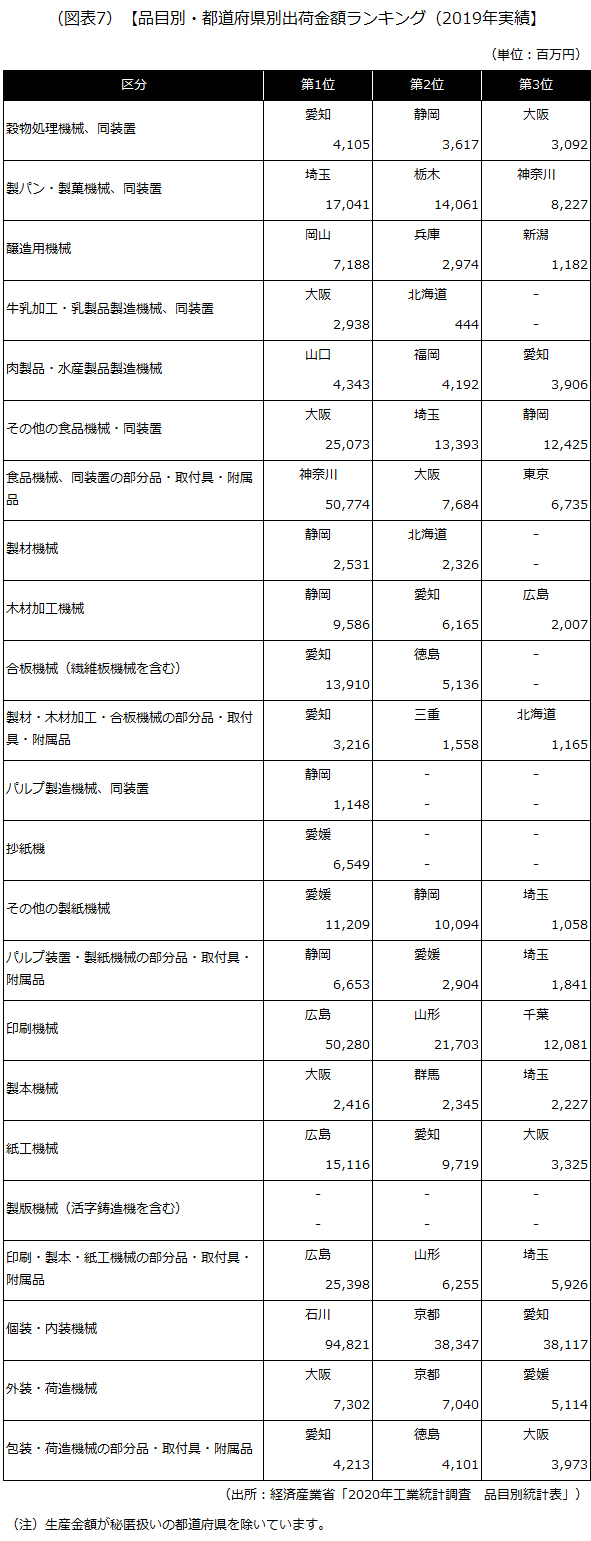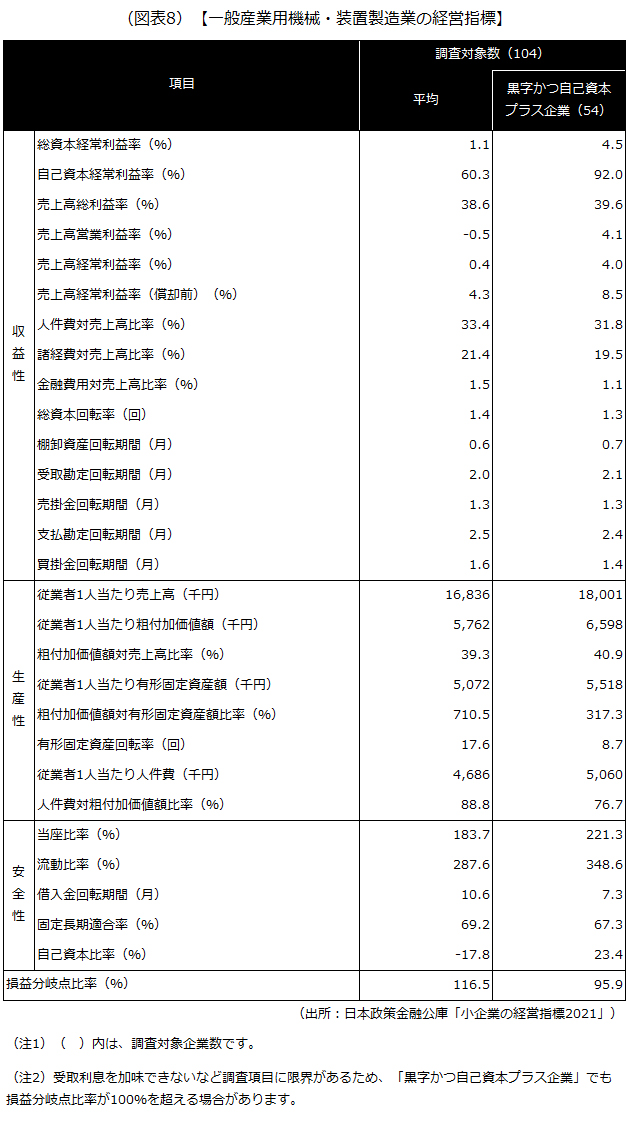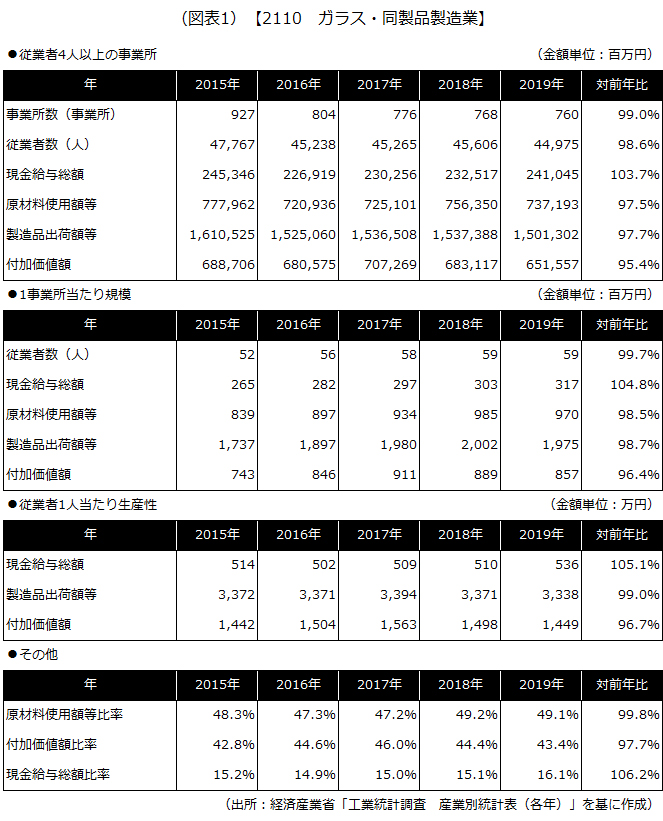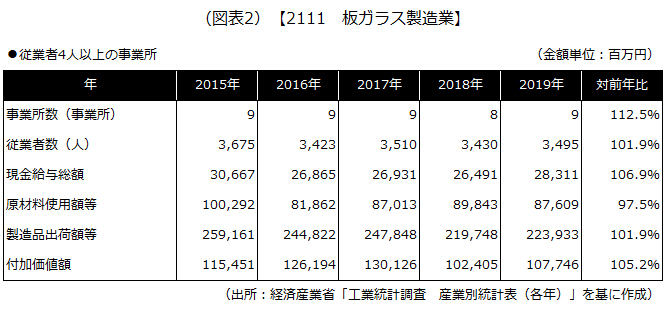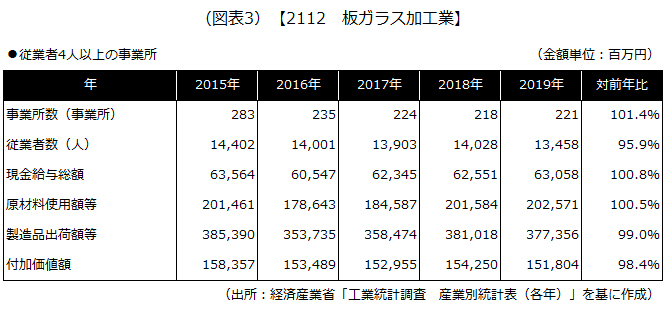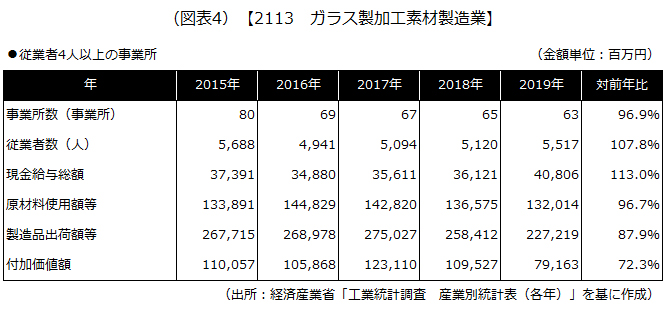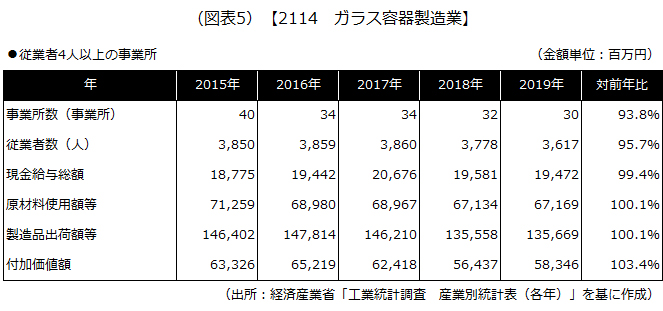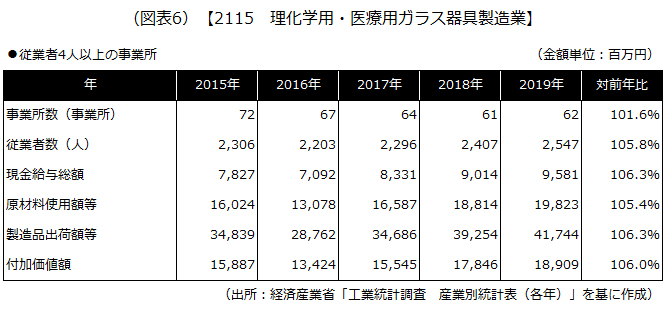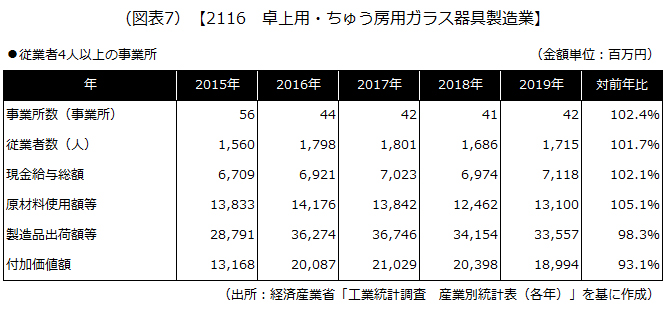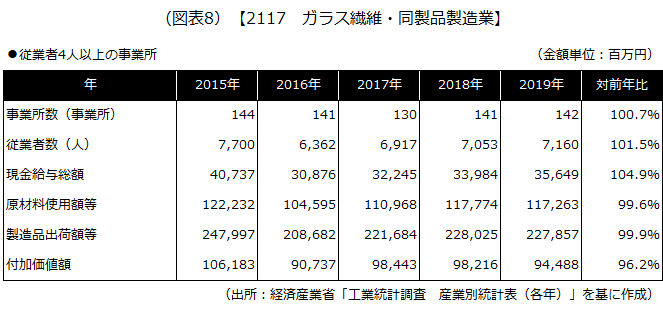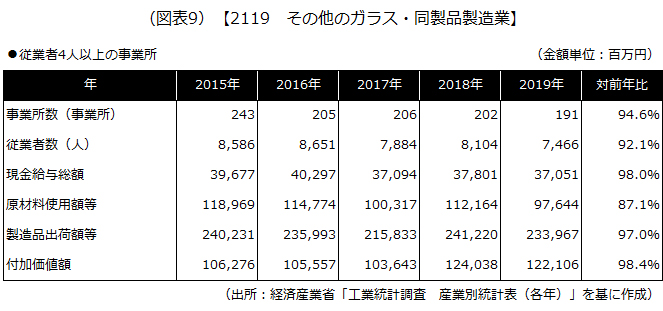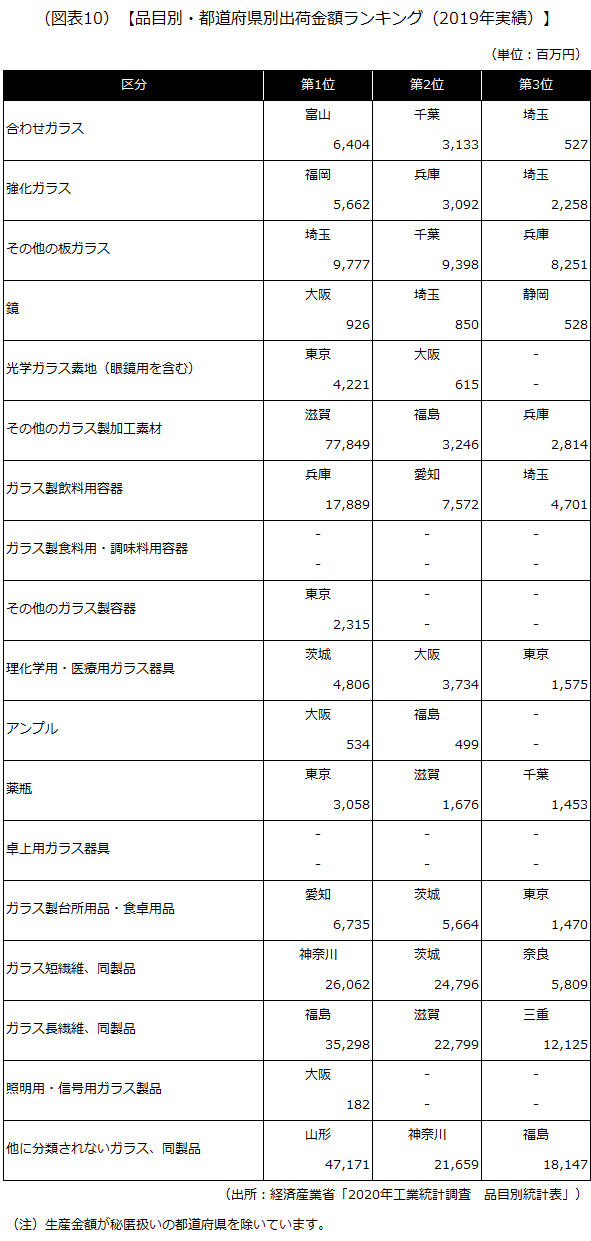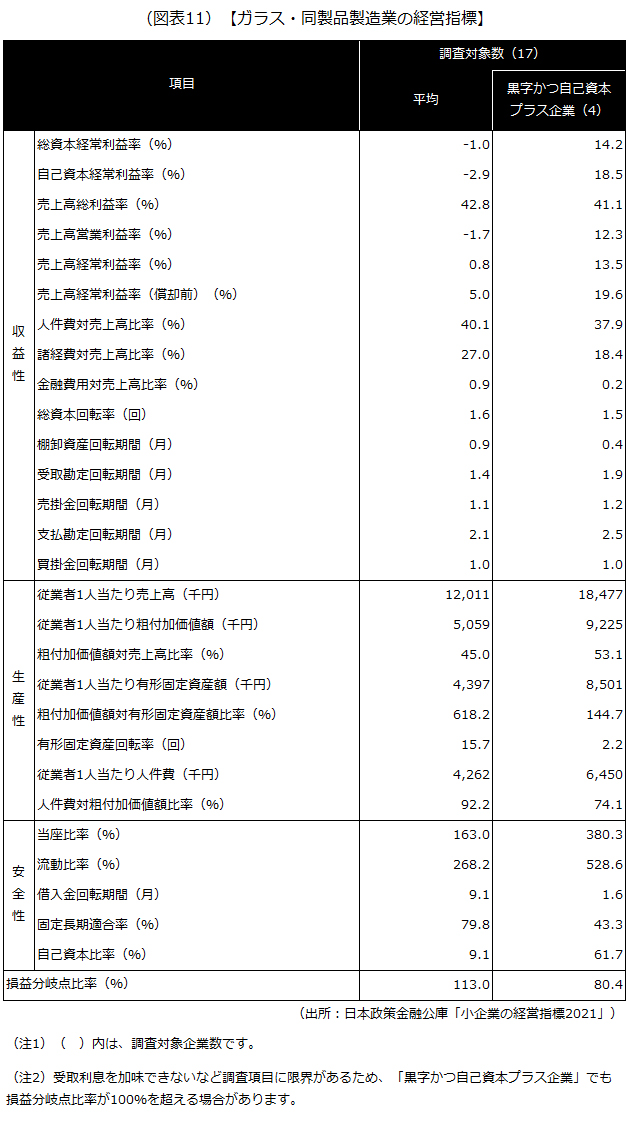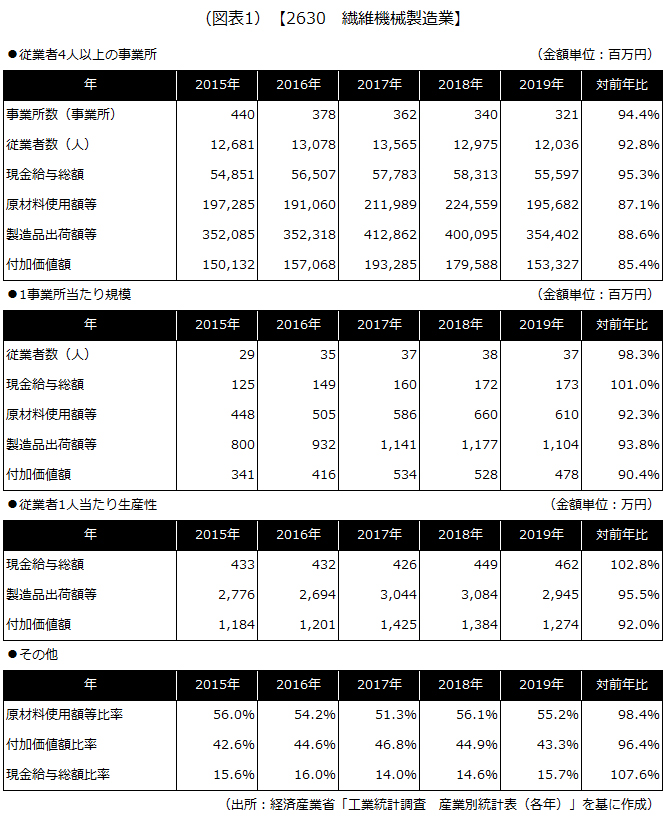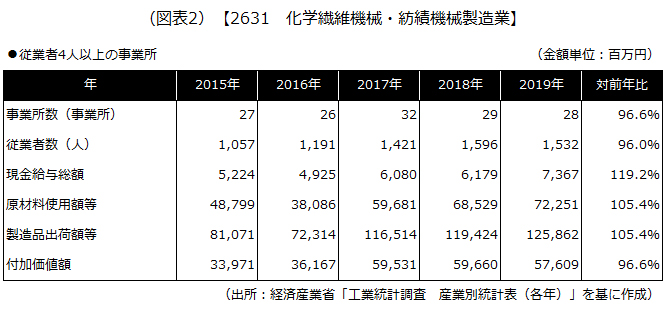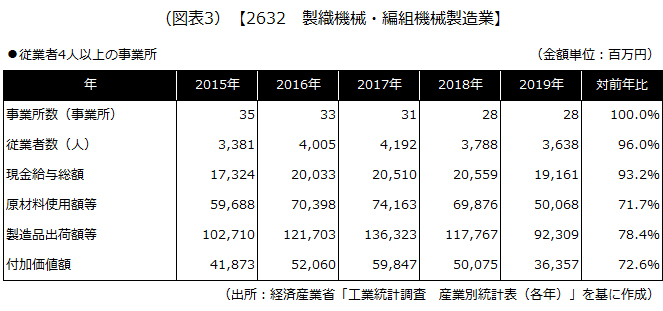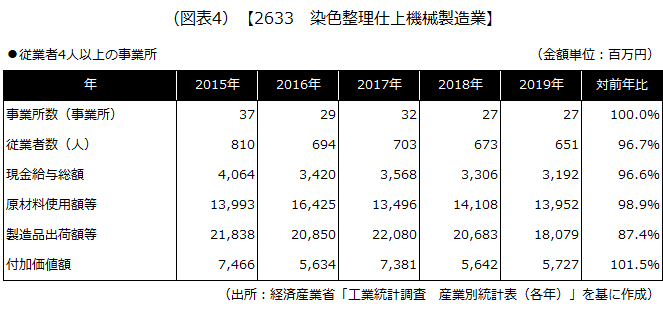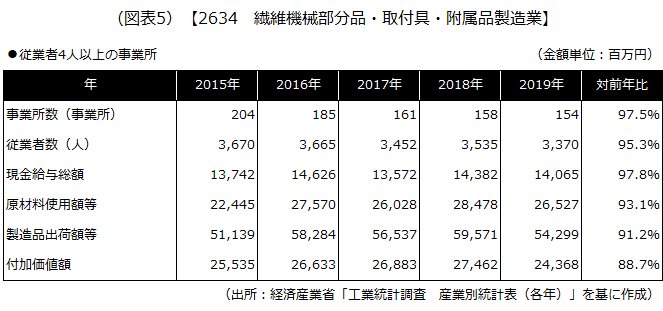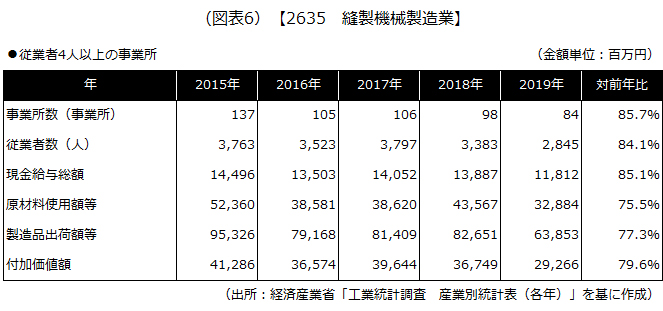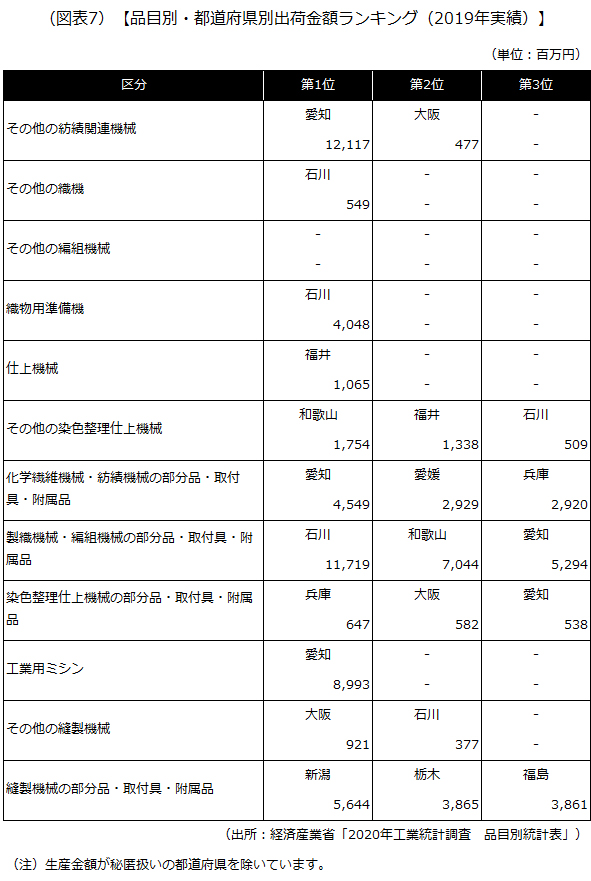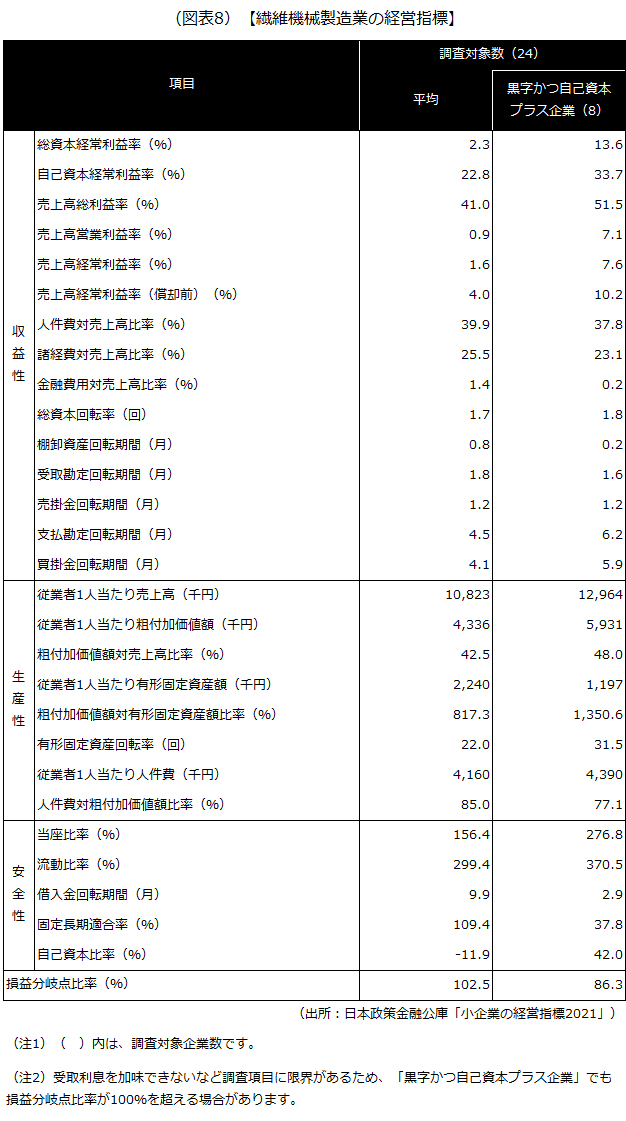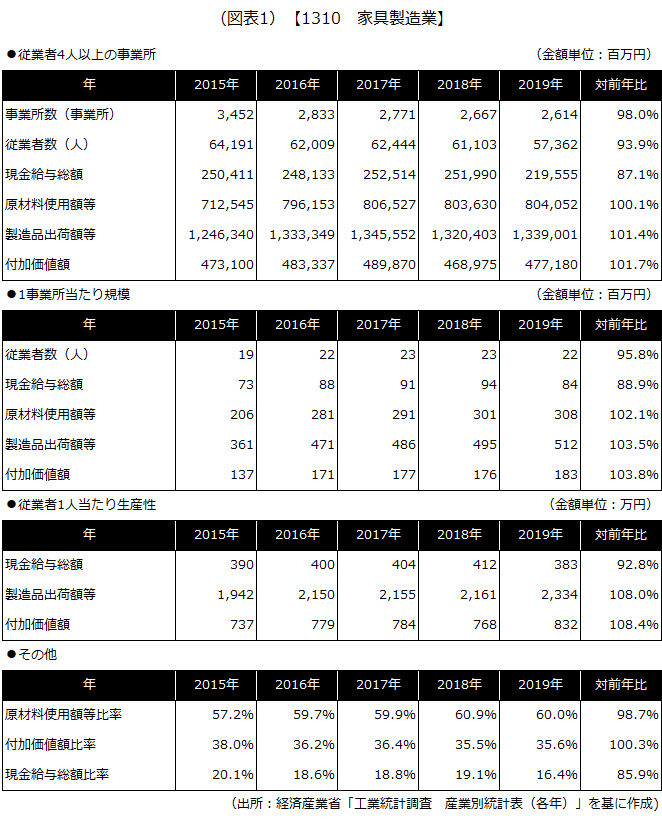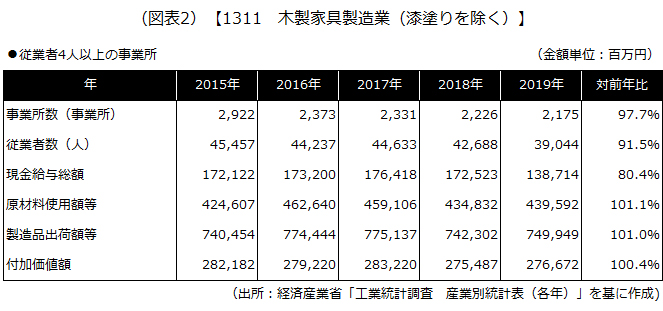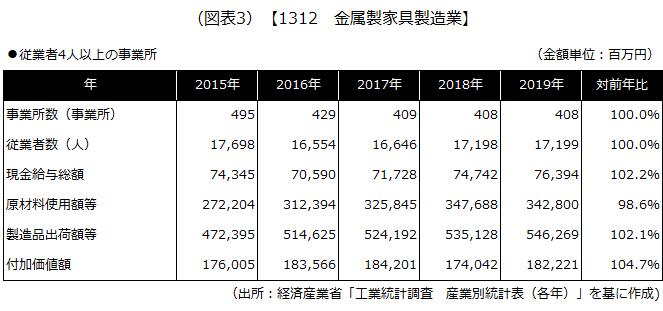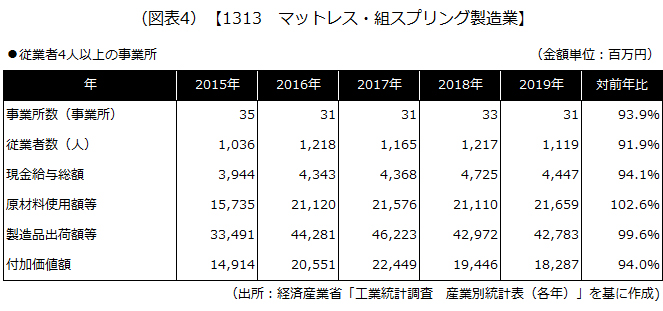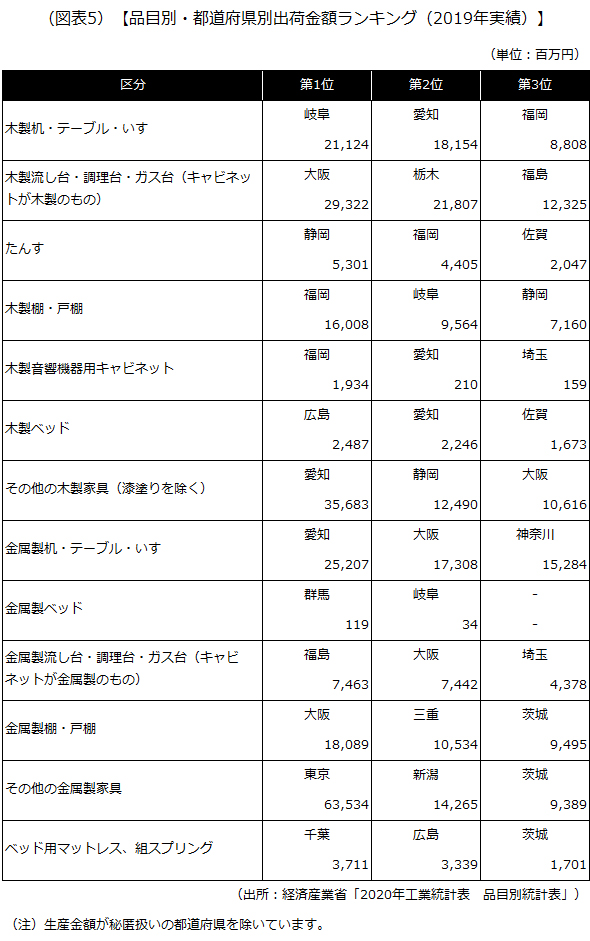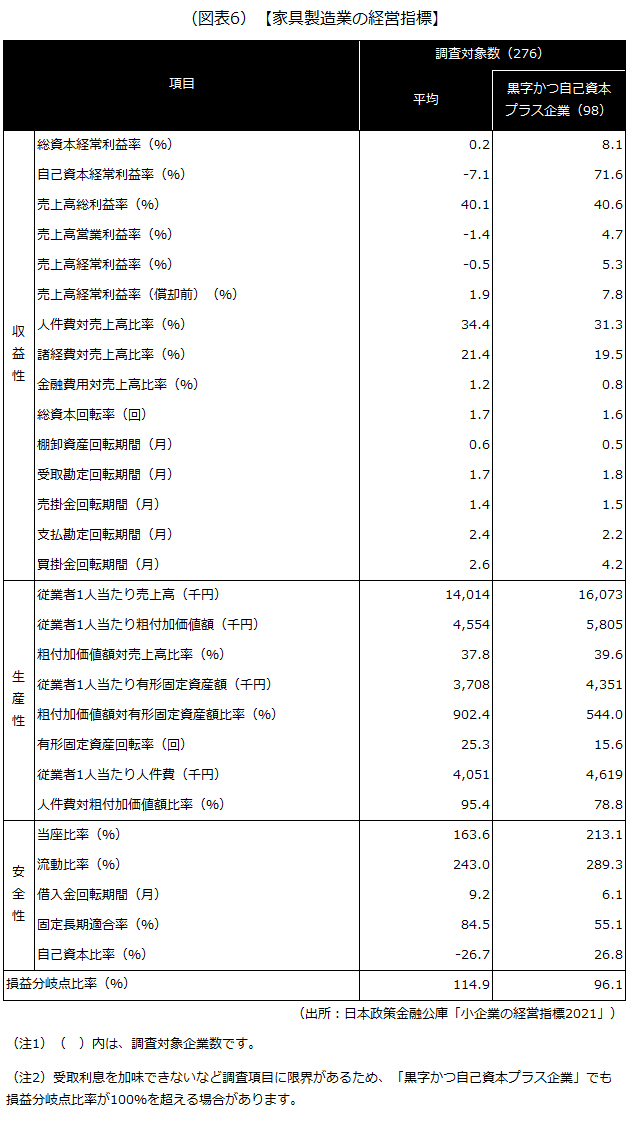書いてあること
- 主な読者:現在・将来の自社のビジネスガバナンスを考えるためのヒントがほしい経営者
- 課題:変化が激しい時代であり、既存のガバナンス論を学ぶだけでは、不十分
- 解決策:古代ローマ史を時系列で追い、その長い歴史との対話を通じて、現代に生かせるヒントを学ぶ
1 同じなのか、違うのか
インターネットが広く一般に利用されるようになって二十余年がたち、情報技術革命という言葉も今や古びた印象さえ持つようになりました。技術の発展はますます加速化しており、AI、IoT、VR/ARなど、かつては未来の物語と思われていたようなことが現実化・実用化され、私たち一般市民の生活や活動も大きく変化しています。
当然、企業のビジネスも大きく変化し、これまでの考え方ややり方ではもはや通用しないとまでいわれるようになっています。かつての経営学、ビジネス理論、メソドロジーなどは、現在、急成長を続ける企業のビジネスモデルに当てはめづらくなっているのも事実で、20世紀型のビジネスと現代のビジネスとの違いを感じることが私自身も多々あります。一方で、変わらない部分、同じ部分というのも存在します。
同じなのか、違うのか。こうした議論は、日常でもよくあります。「この映画はこれまでの映画とはアプローチが全然違う」「いや、あの映画と系統は同じでしょ」といったような会話もありますし、「あの事件とこの事件は本質的に同じだ」「いや、そんなことはない」といったTVコメンテーターのやり取りも目にします。
多くの場合、こうした議論は平行線をたどることになりますが、その理由は、目線の違いにあります。動物や哺乳類という目線で言えば、犬も猫も同じですが、「犬」と「猫」と言い分けている通り、犬と猫は分類上も異なる科です。片方が哺乳類の目線で議論を展開し、もう片方が科の目線で議論をすれば、当然、同じなのか、違うのかという論争に決着はつきません。
ところで、コンピューターのプログラミング言語、特にオブジェクト指向と呼ばれるプログラミングでは、汎化と特化という考え方があります。よく挙げられる自動車の例を用いますが、救急車と消防車は、自動車として共通的な機能を持っています。この共通的な機能をまとめてスーパークラスという上位のものとして定義します。これを汎化といいます。そして、このスーパークラスの定義を継承し、救急車と消防車がそれぞれ持つ特殊な機能を下位のサブクラスで分けて定義します。これを特化といいます。
こうすることで、例えば、新たにパトカー(警邏(ら)車)を定義しなければならない場合に、すでにスーパークラスで定義している自動車として共通的な機能は、もう一度プログラミングする必要はなくなります。パトカーが持つ特殊な機能だけをサブクラスとして定義すればいいので、開発の生産性が上がることになります。
ここで私が申し上げたいのは、同じなのか、違うのか、ということは重要ではなく、何が同じで、何が違うのかを見極めることこそが重要なのだということです。これまで12回にわたって連載させていただいたローマ史の人々と現代の私たちとでは、多くの点で違いがあります。
しかし、何が同じで、何が違うのかを見極めながら歴史を眺めてみると、同じところからは先人たちの知恵が見つけられ、違うところからはその「差分」の気付きを得ることができます。そうすることで、現在の自分へのヒントをつかむことになるのです。ローマ史に限らず、歴史は、そういった教材になります。
2 滅亡までの道のり
ローマ帝国は、五賢帝時代の後、混乱と迷走が続き、衰弱していきます。マルクス・アウレリウスの息子コモドゥスがその悪政から暗殺され、その後、セプティウス・セヴェルスが内戦を制して皇帝に就きますが、「三世紀の危機」と呼ばれる時代に突入していきます。蛮族の大侵入、軍事力強化による財政悪化、内戦の同時多発などがあり、211年からの73年間に多くの皇帝が登場しては消えていきました。
235年から約50年間は、軍隊を支持母体とする軍人が皇帝となる軍人皇帝時代となり、ローマ帝国の性質も大きく変化します。3世紀末のディオクレティアヌスが皇帝になってからは、共和政の伝統をなくした専制君主制を敷くとともに、帝国の分担統治を実施し、広大な領土の効率的な防衛によって秩序回復を図っていきます。
4世紀には、皇帝コンスタンティヌスが「ミラノ勅令」によりキリスト教を公認し、ローマを離れてコンスタンティノープルに首都を遷(うつ)し、新たなローマ帝国の再建を図ろうとします。しかしこれは、ローマ帝国の特質を失わせ、全く異なる帝国に変えることで、ローマ帝国を存続させるようなものでした。
その後、皇帝ユリアヌスのときにキリスト教が否定され、ローマの伝統的な多神教を擁護するなどの政策を取りますが、キリスト教信徒は増え続け、皇帝テオドシウスがキリスト教を国教と定めるに至り、キリスト教の覇権が決定的になりました。テオドシウスの死後、395年には東西に分裂し、西ローマ帝国と東ローマ帝国が成立します。西ローマ帝国はゲルマン人の侵攻を受け続けて衰えていき、476年に滅亡します。
東ローマ帝国は、ローマから離れた領土で実質的にギリシャ化が進み、7世紀にはビザンチン帝国と呼ばれるようになりますが、イスラム勢に次々と領土を奪われていきます。それでも度重なる危機に耐え、1453年にオスマン帝国によって滅亡させられるまで1000年にわたって命脈を保ちました。
なお、ローマ帝国がいつ滅びたのかについてはいろいろな考え方がありますが、一般的には、西ローマ帝国の滅亡をもってローマ帝国の滅亡とされています。東ローマ帝国の滅亡は、中世の終わりを象徴する出来事として捉えられているようです。
3 終わりに
今回は全12回連載の最後ということで、かなりの駆け足でローマ帝国の滅亡までを振り返ってみました。建国以来、数多くの危機に直面しながらも、それを乗り越えて強大化していったローマ帝国でしたが、そうした国家も衰亡していくということを改めて思い知らされます。
現代の情勢を考えると、例えば、宗教や文化における方向性が大きく変化し、国家運営が左右されるのは考えにくいですし、日本が他民族の侵入によって滅亡を迎えるということも想像しがたいところです。ですが、人々の集合体である社会的な組織という観点で見ると、私たちは大企業が滅びていく姿を数多く見てきていますし、政治の紆余曲折も見てきています。
これまで見てきたローマ史の輝かしい場面、苦難を乗り越える場面、愚かな過ちが重なる場面など、全て身近なところで似たようなことを見たり聞いたりしているはずです。自分自身でも、程度の差こそあれ、照らし合わせて考えたくなるような場面があるのではないでしょうか。
当然のことながら、全く同じではありませんが、全く違うわけでもないのです。何が同じで、何が違うのかという目を持って、歴史を眺めてみると、単なる過去のことではなく、豊かな示唆を与えてくれるお話として、親近感を持って捉えることができるかと思います。ローマ史に限らず、歴史に興味をお持ちいただき、自身の生き方、考え方、働き方などに生かしていただければと思います。私自身も、そのように努めてまいりたいと思います。
以上(2021年11月)
(執筆 辻大志)
op90061
画像:unsplash