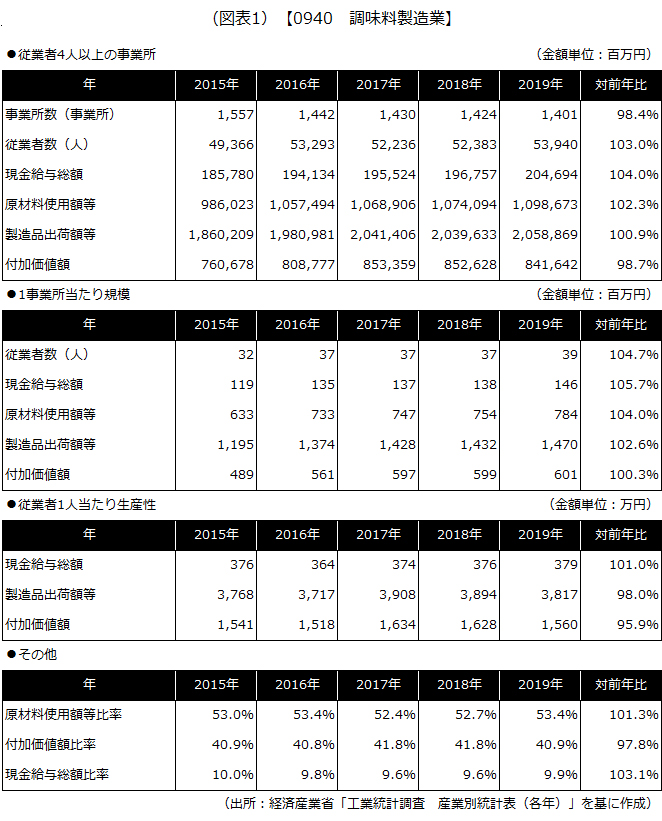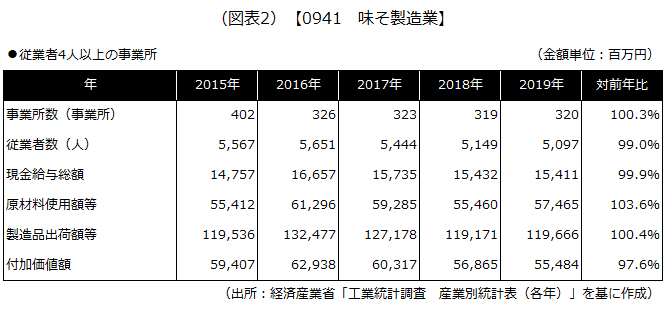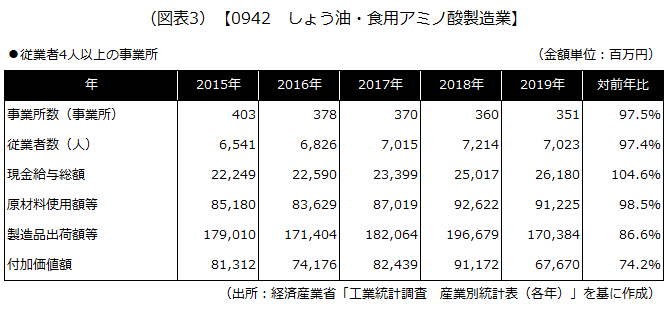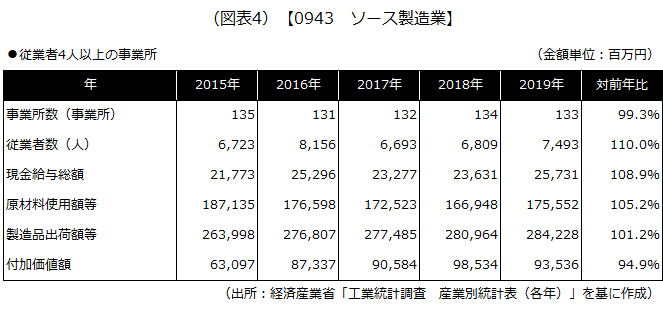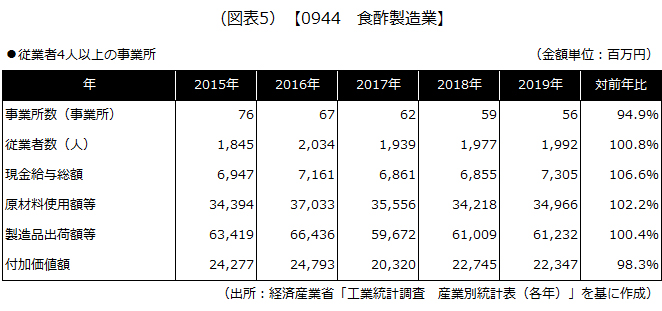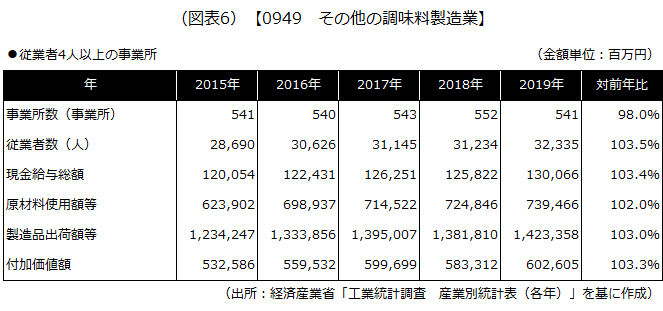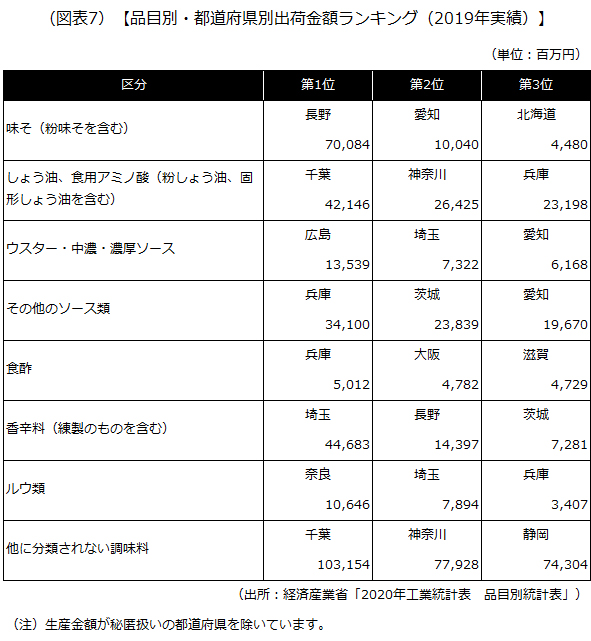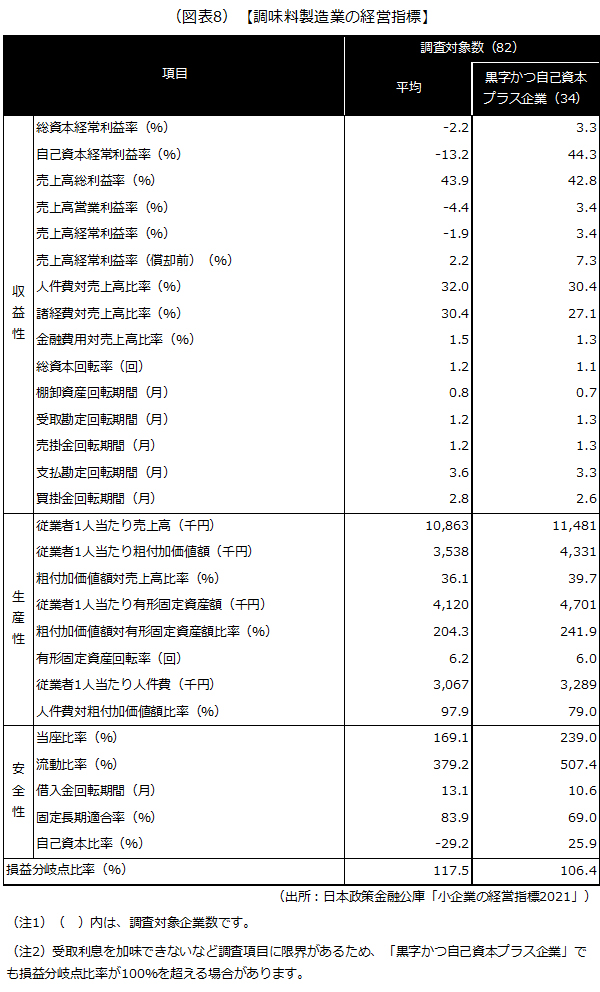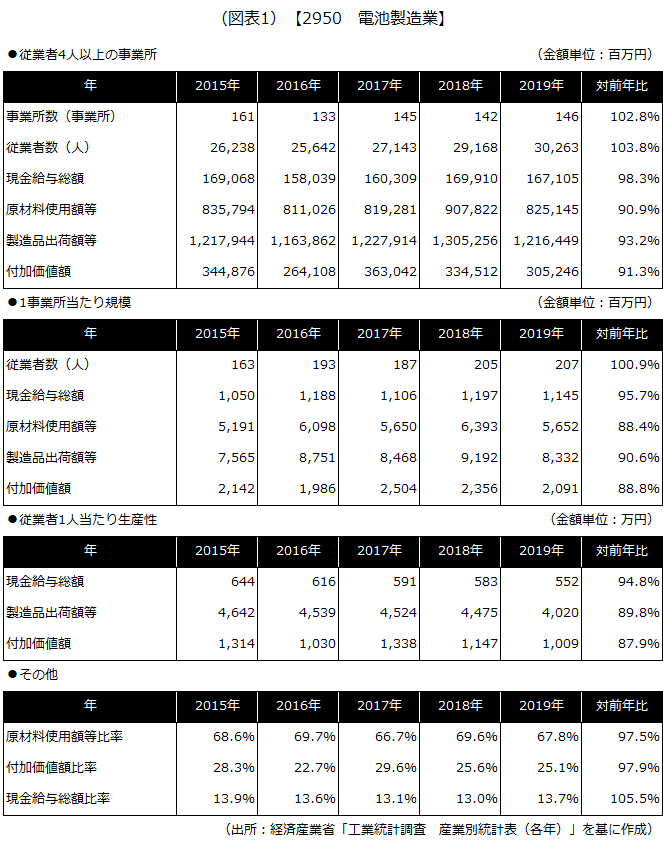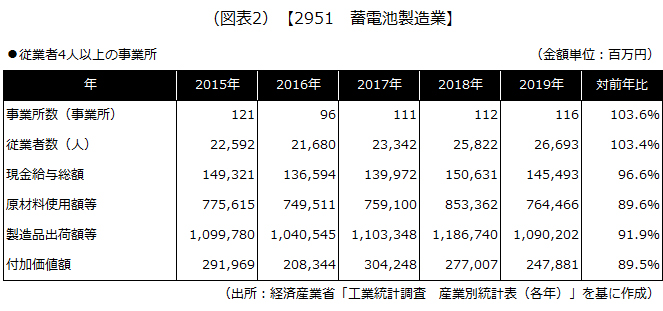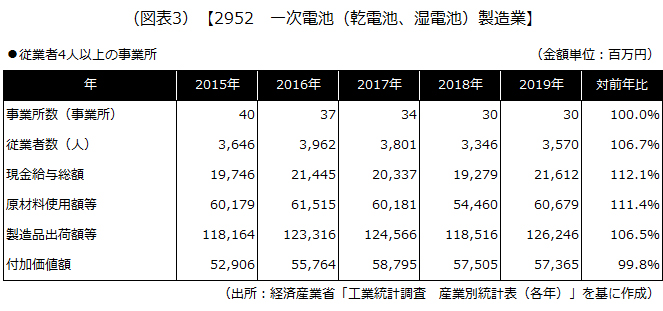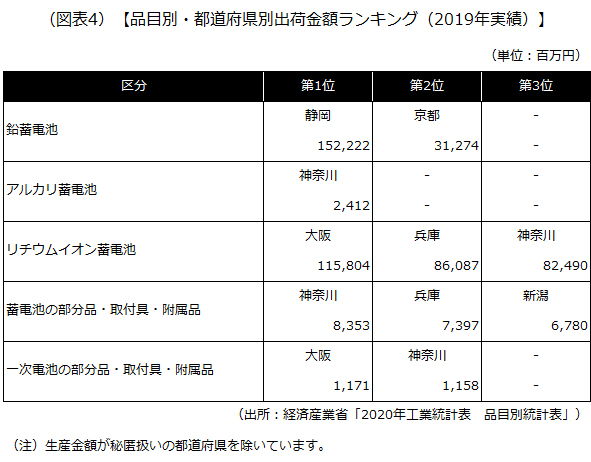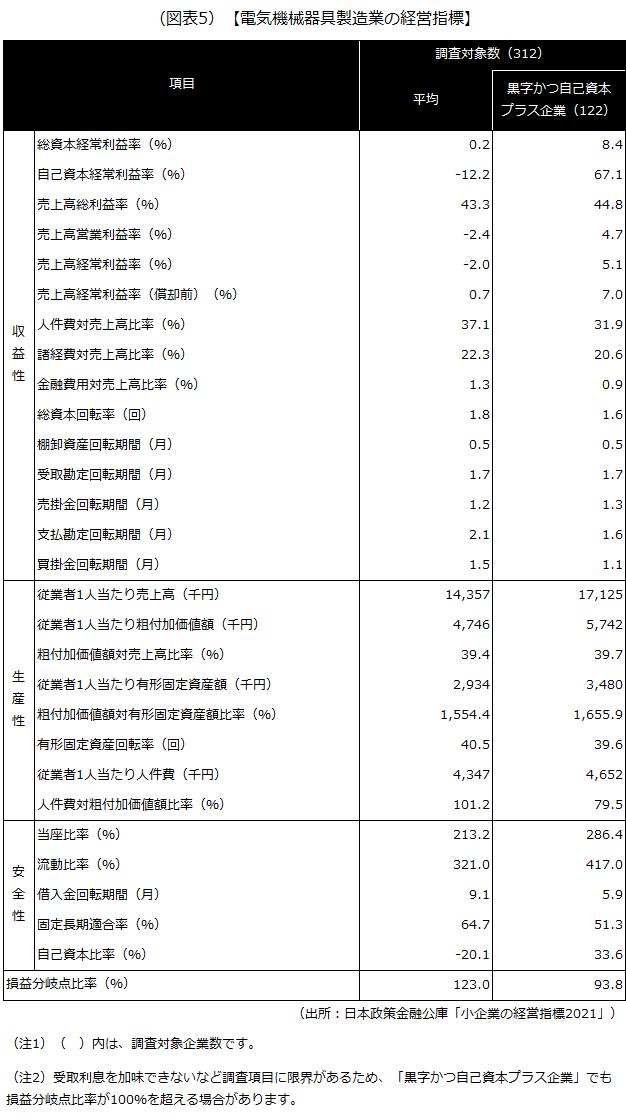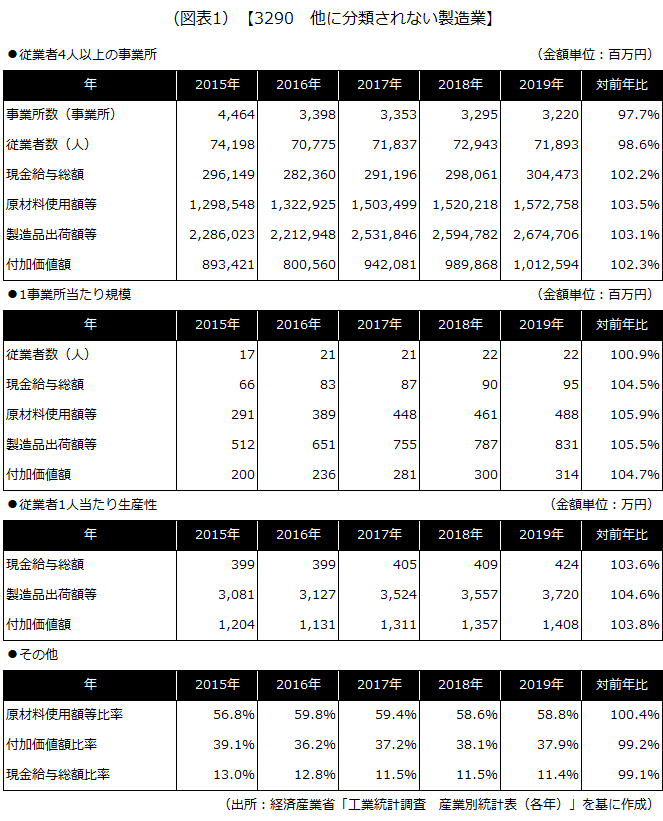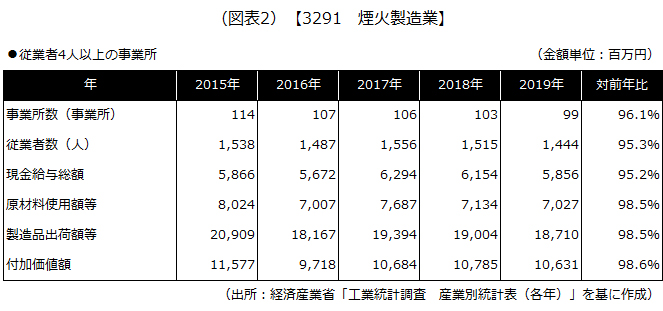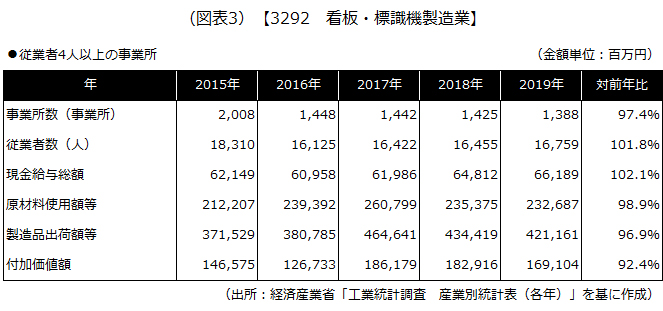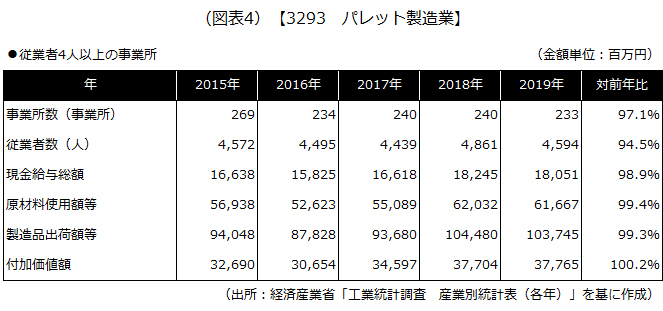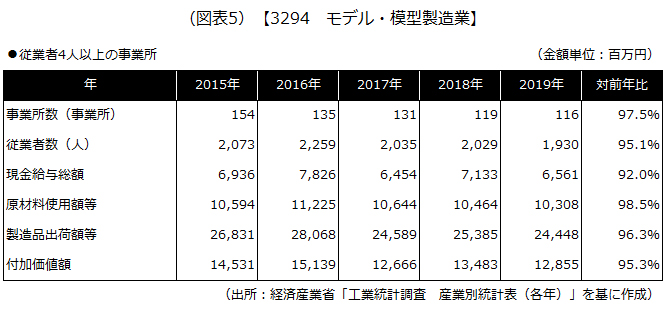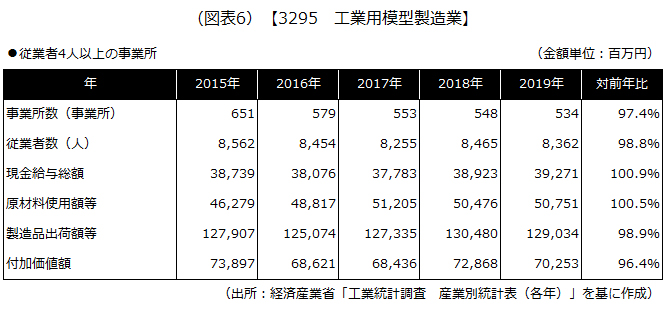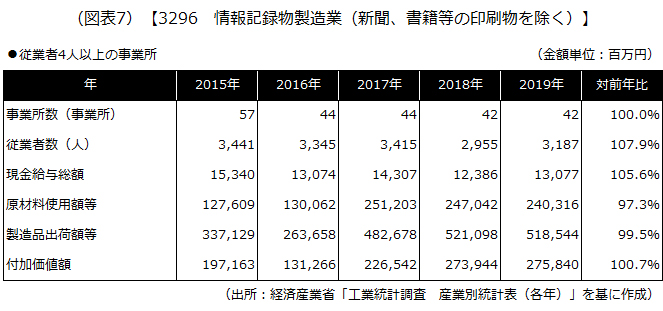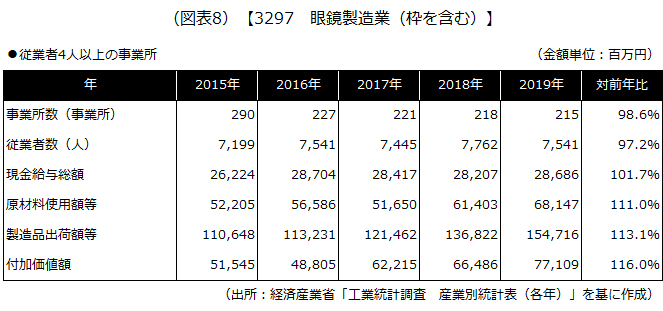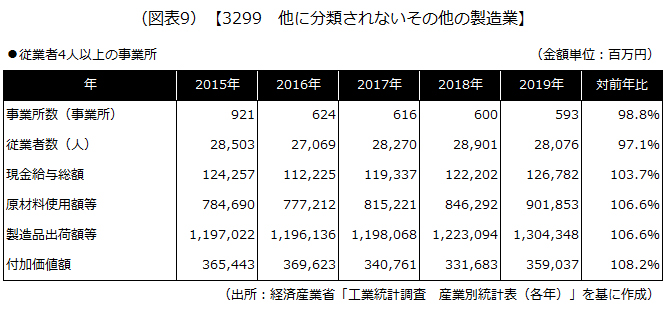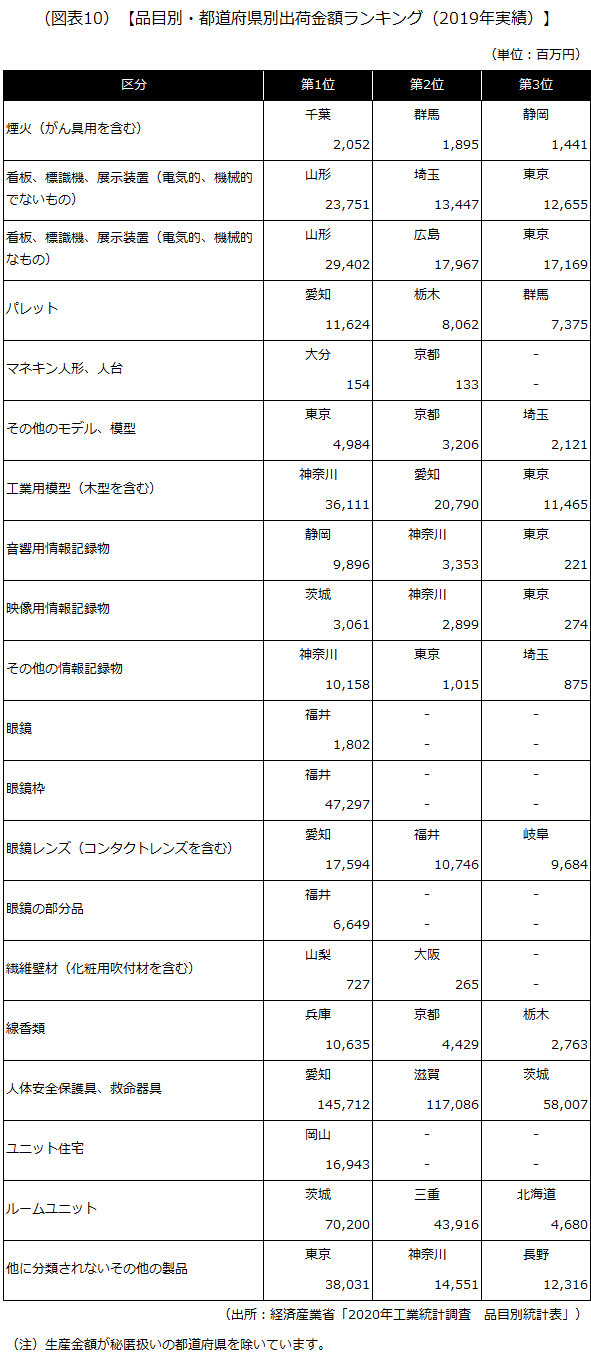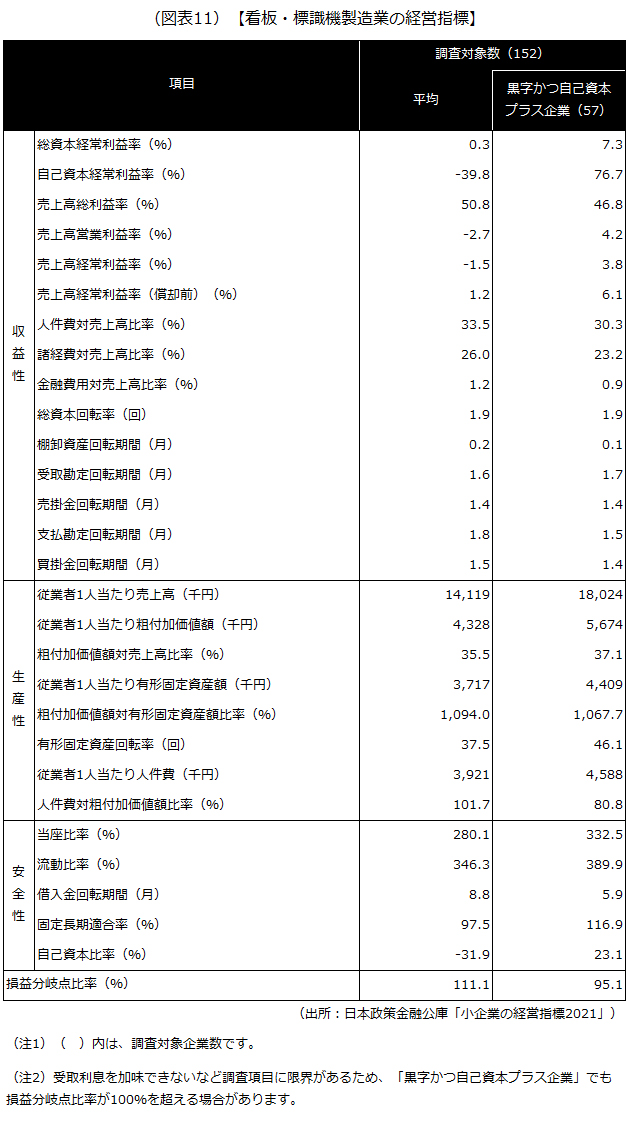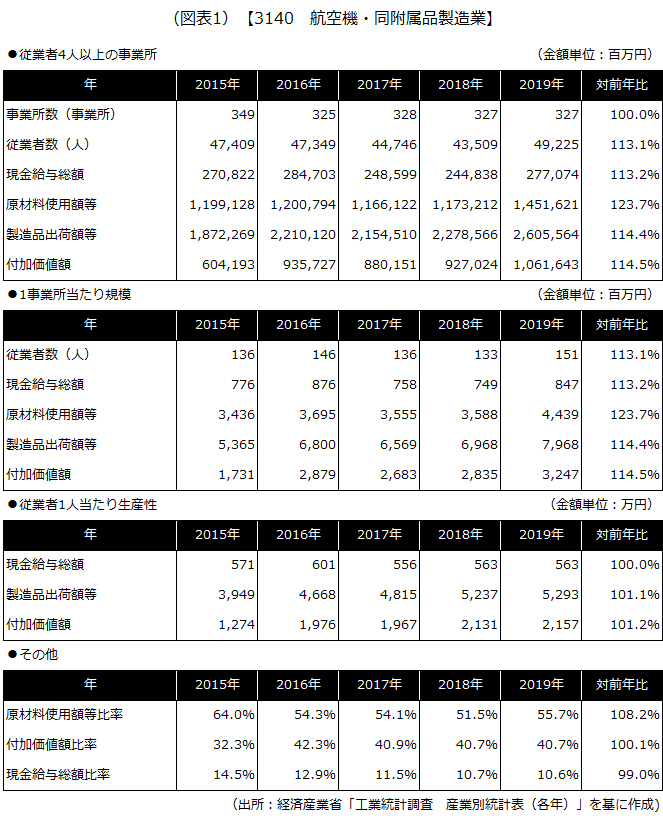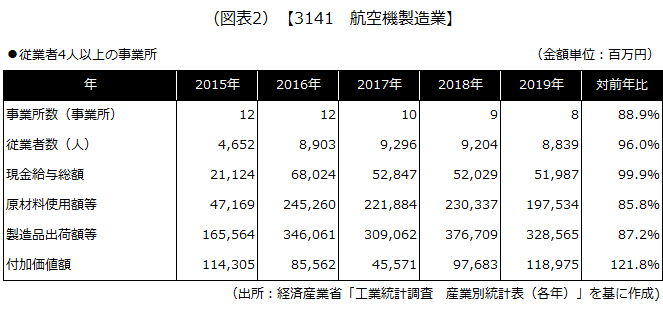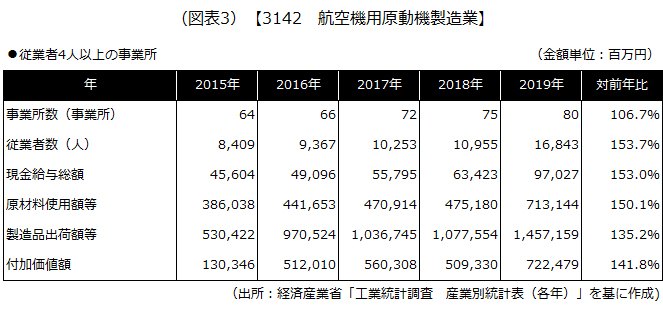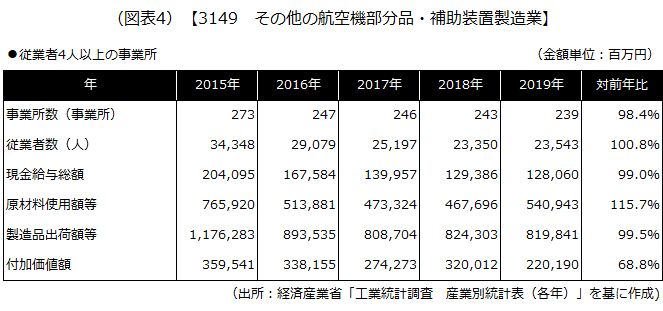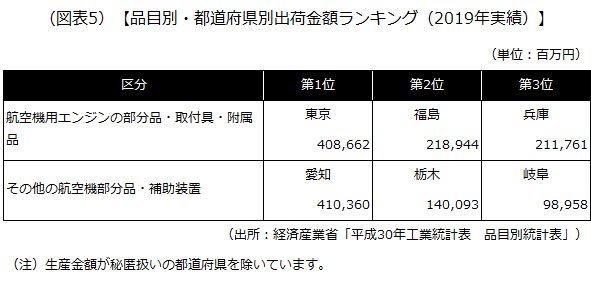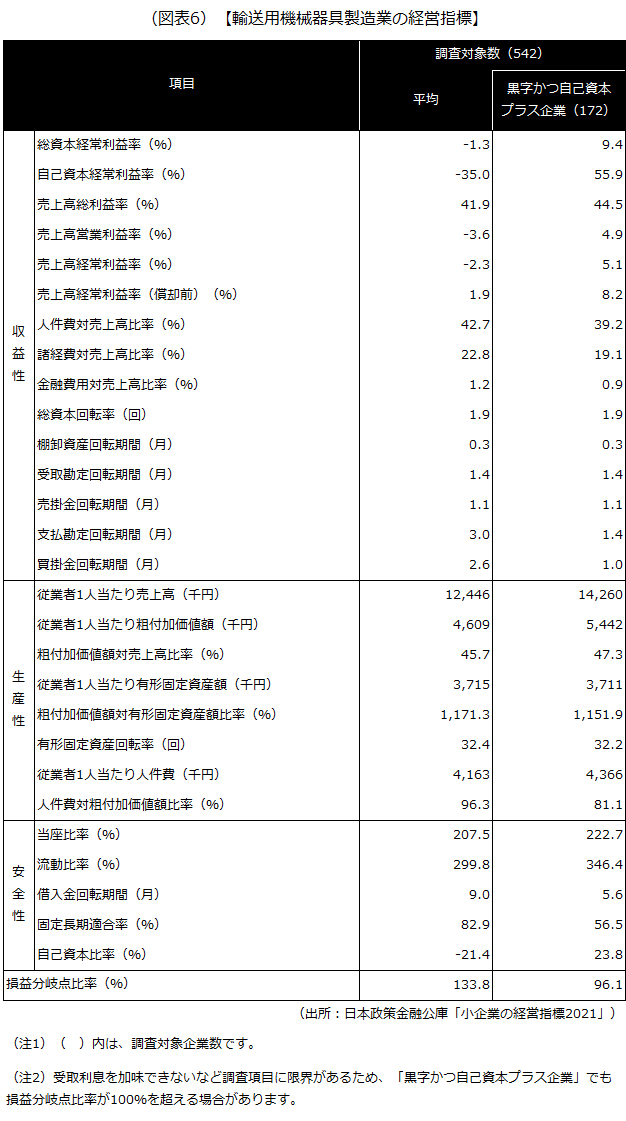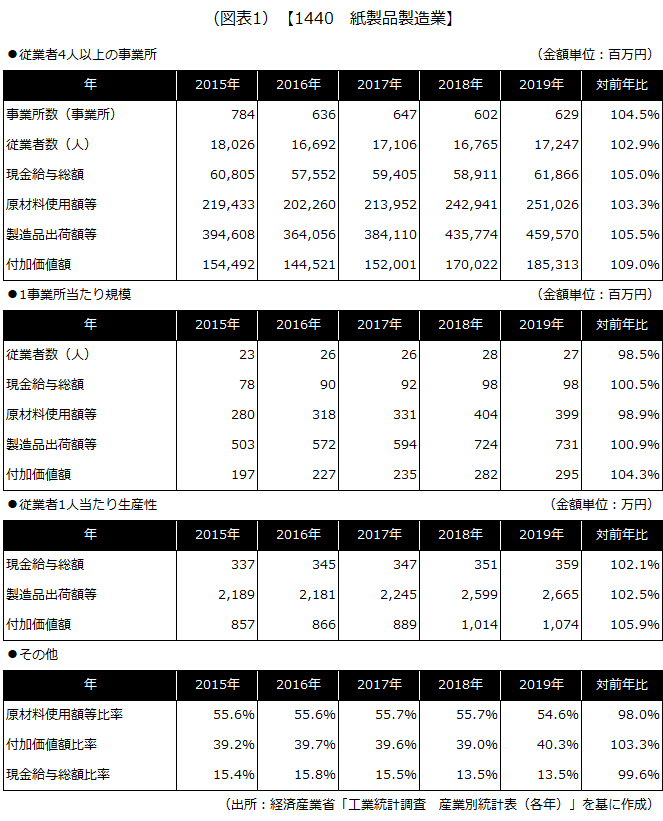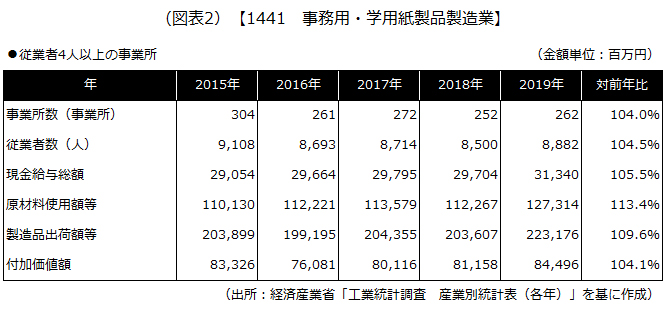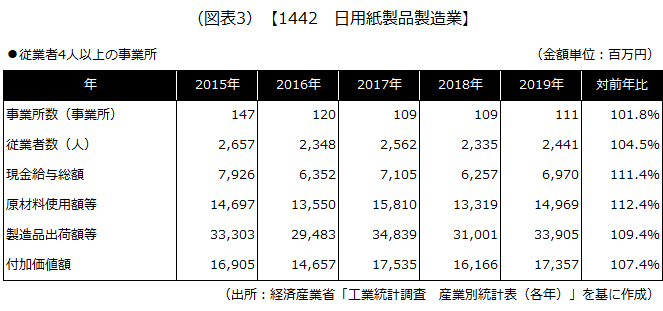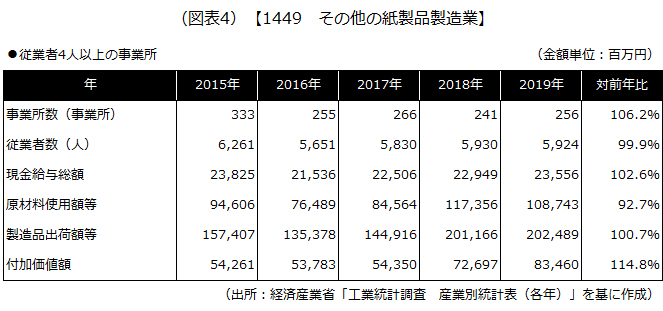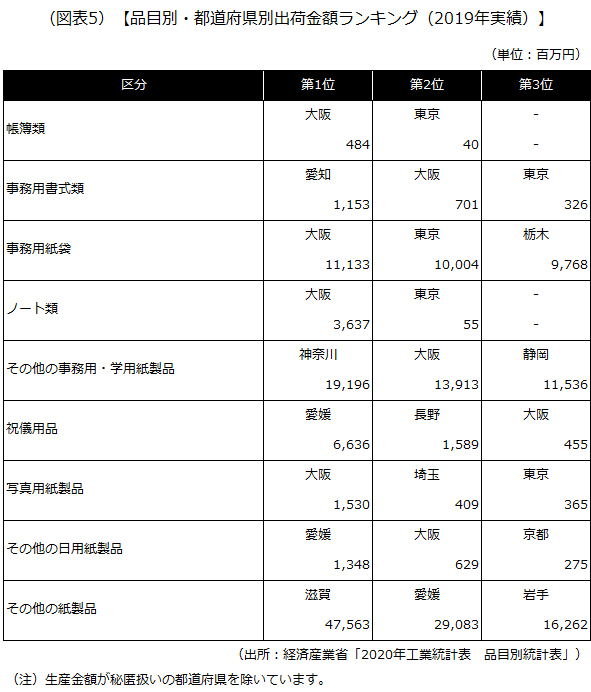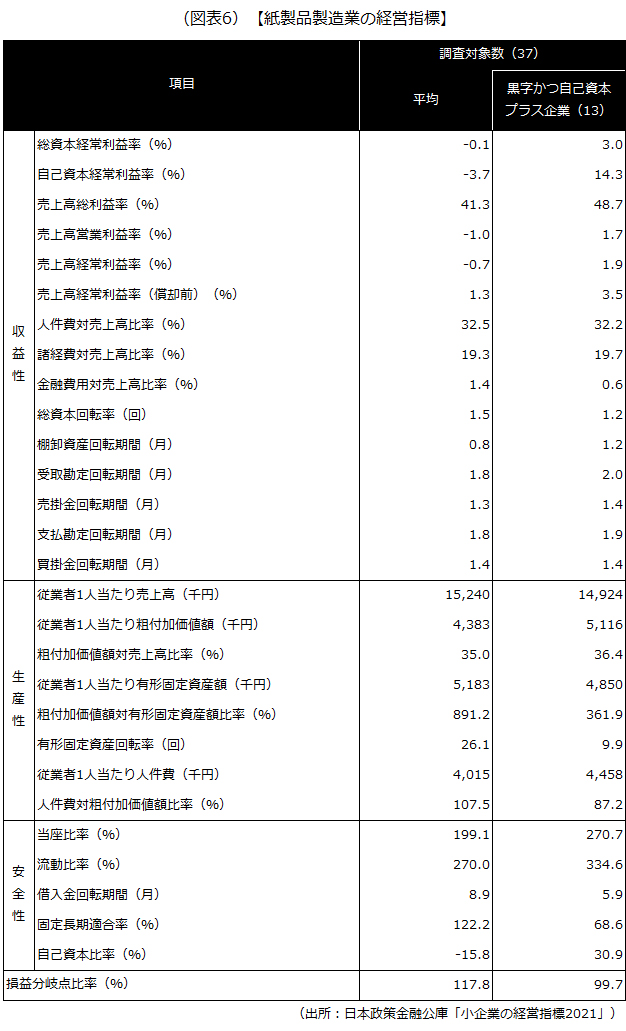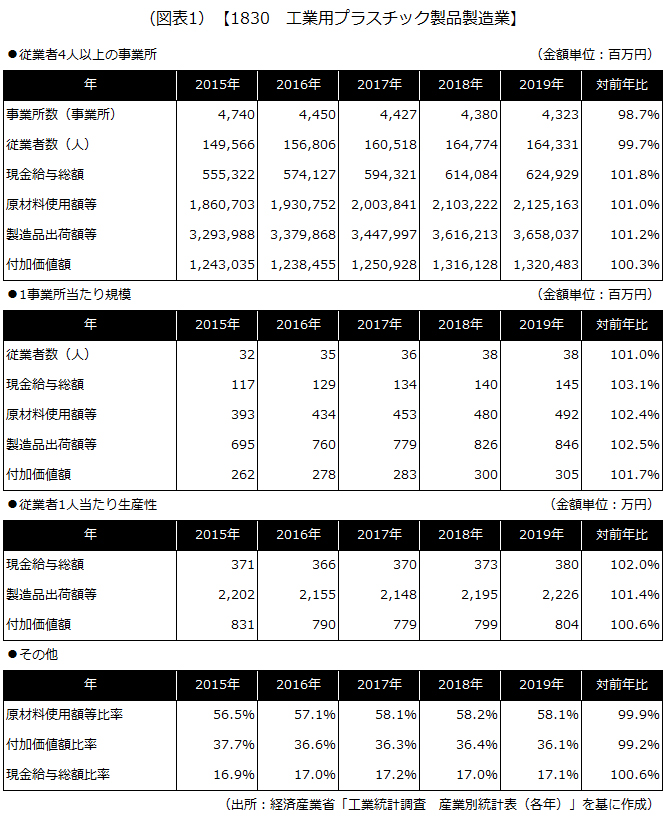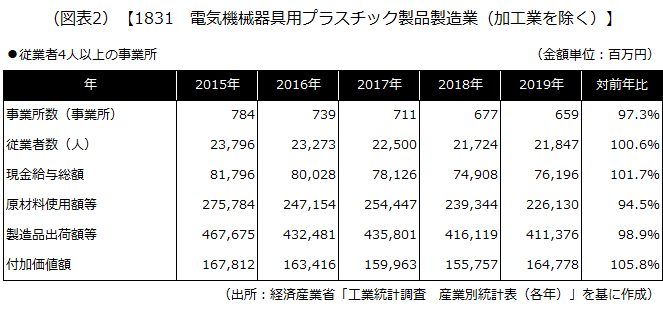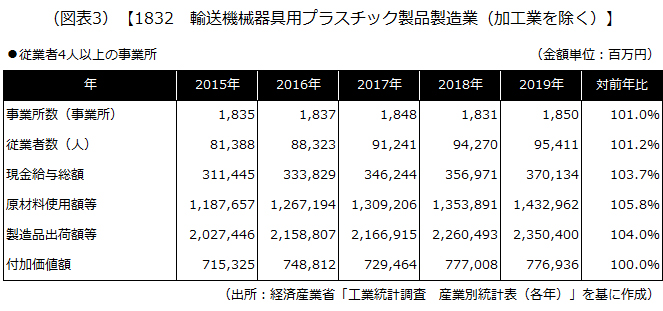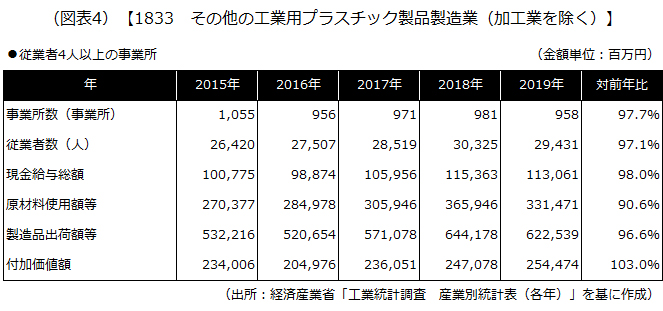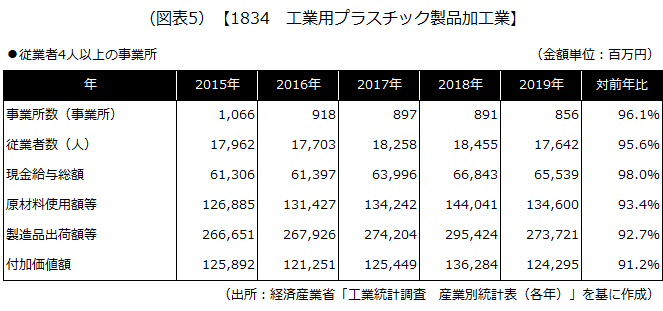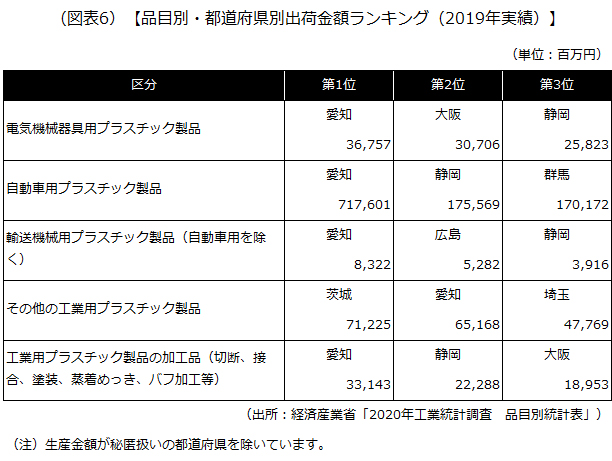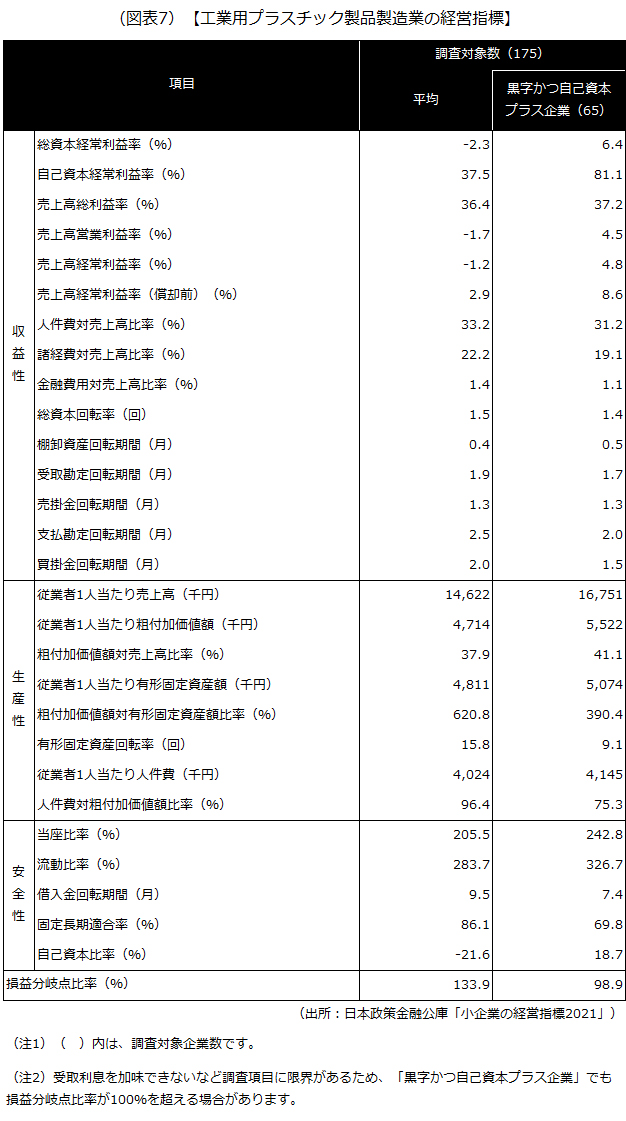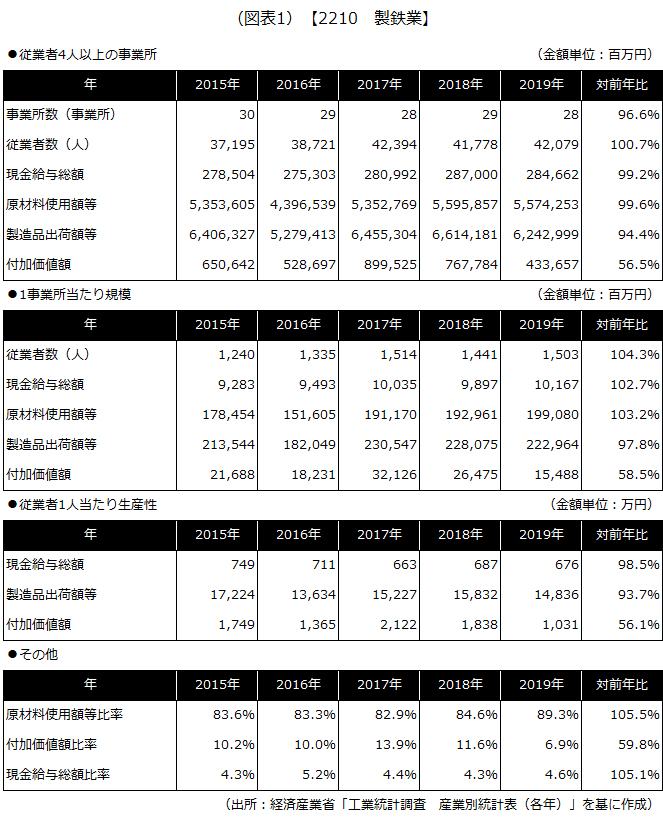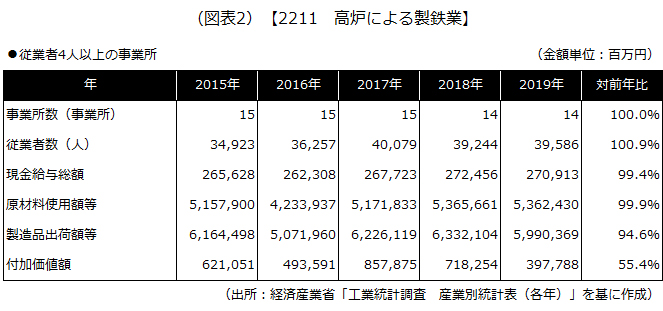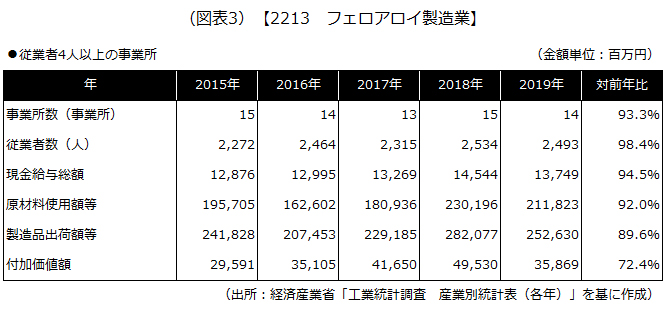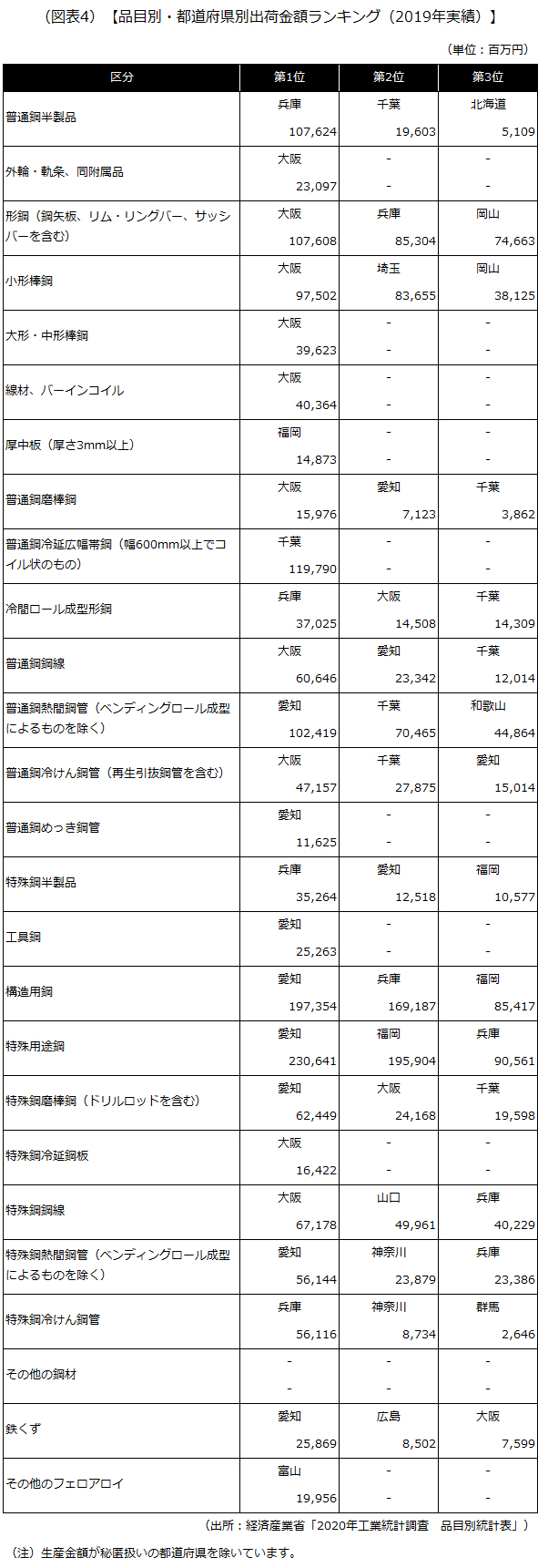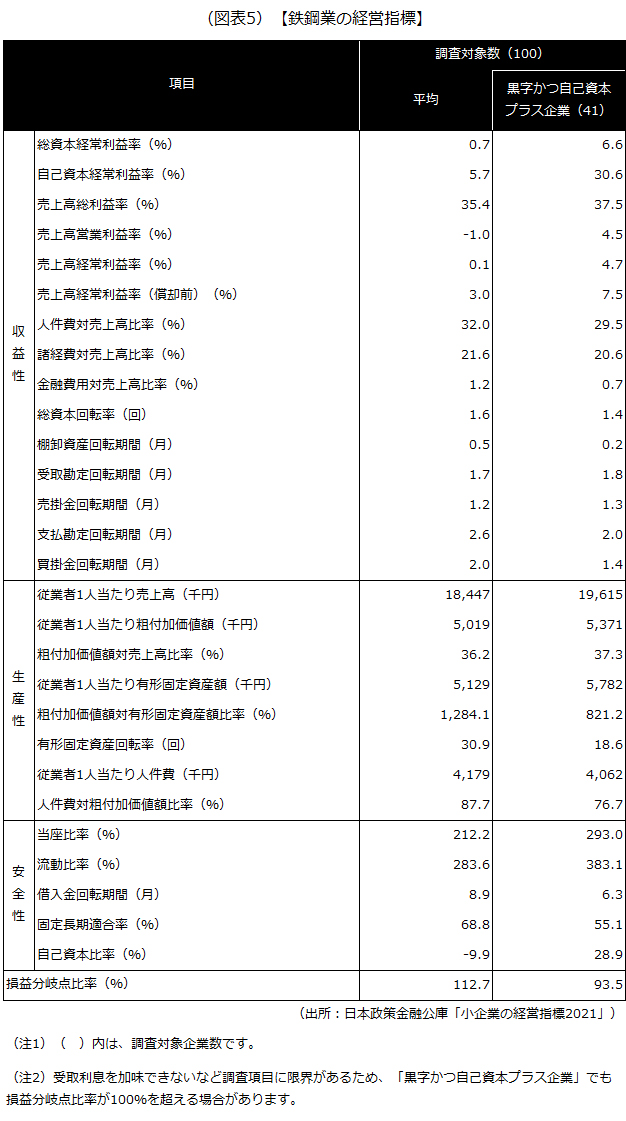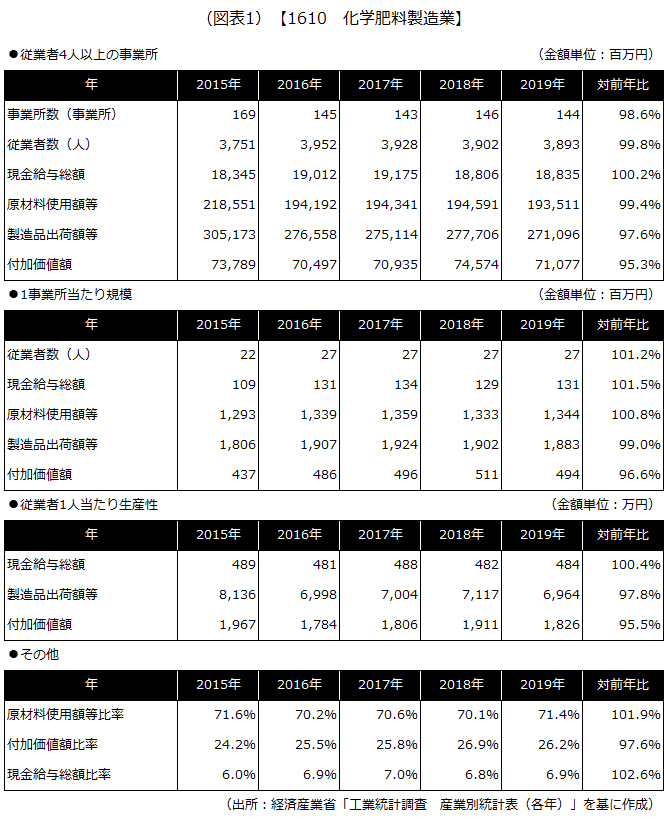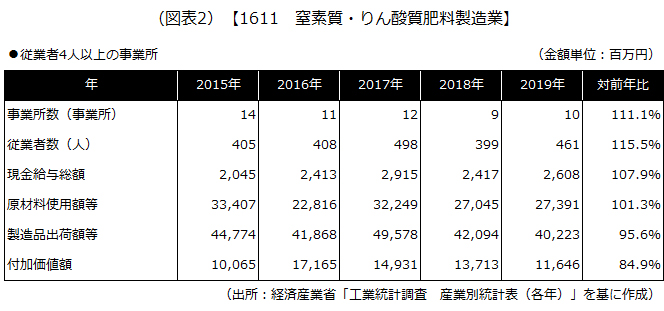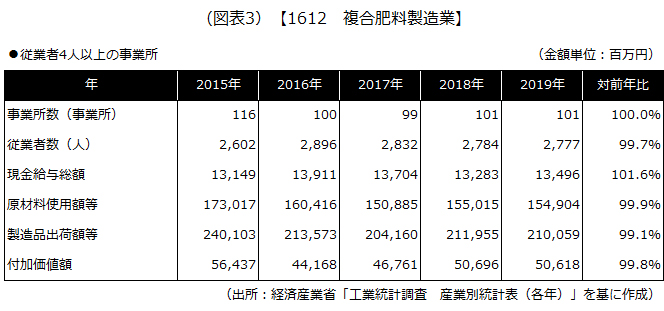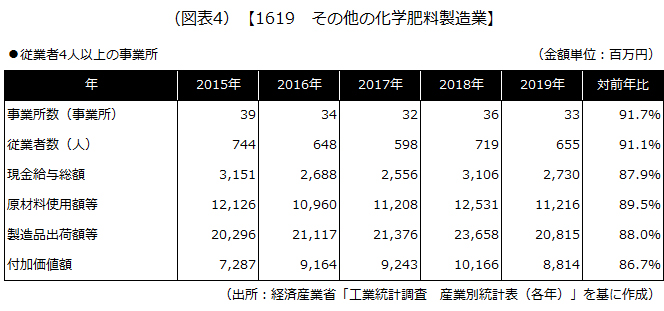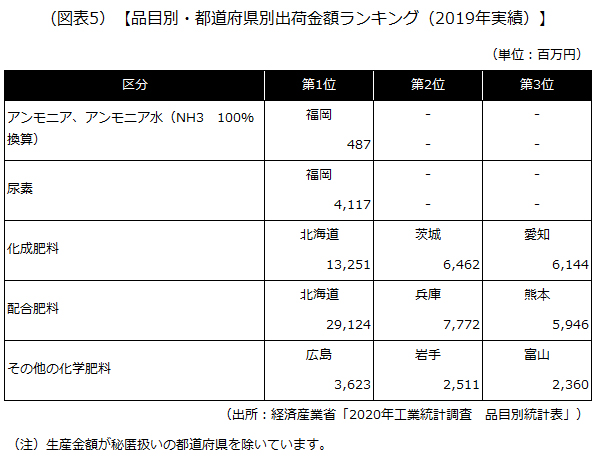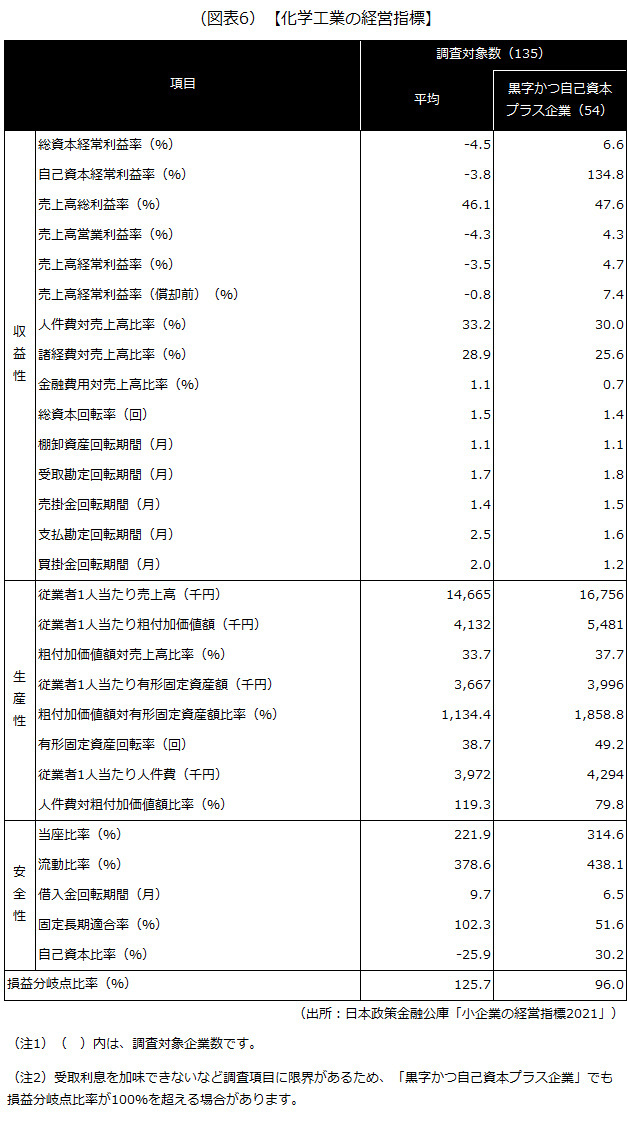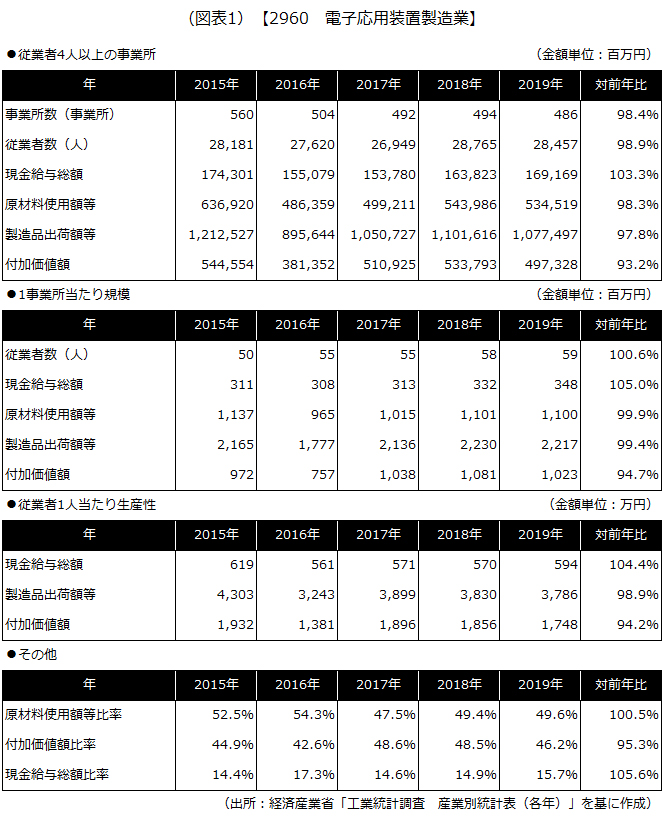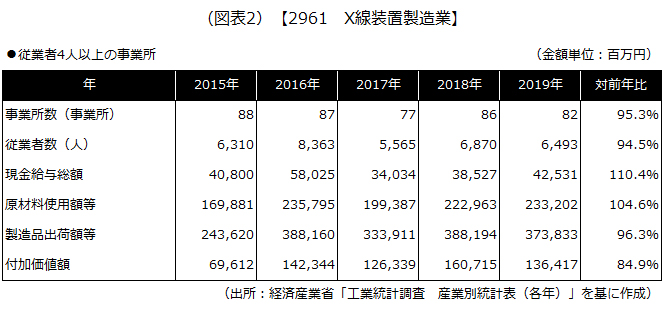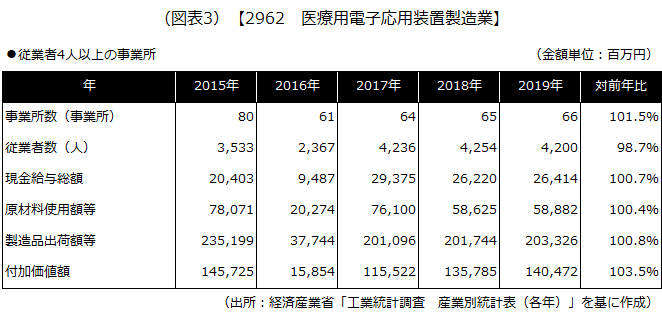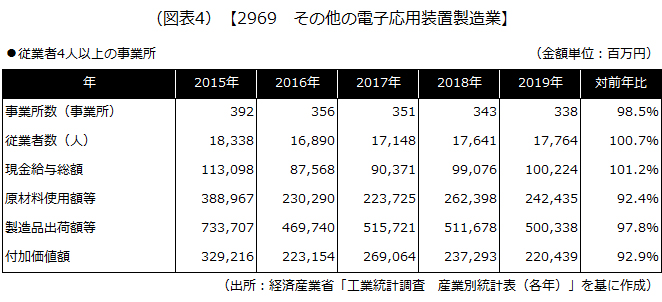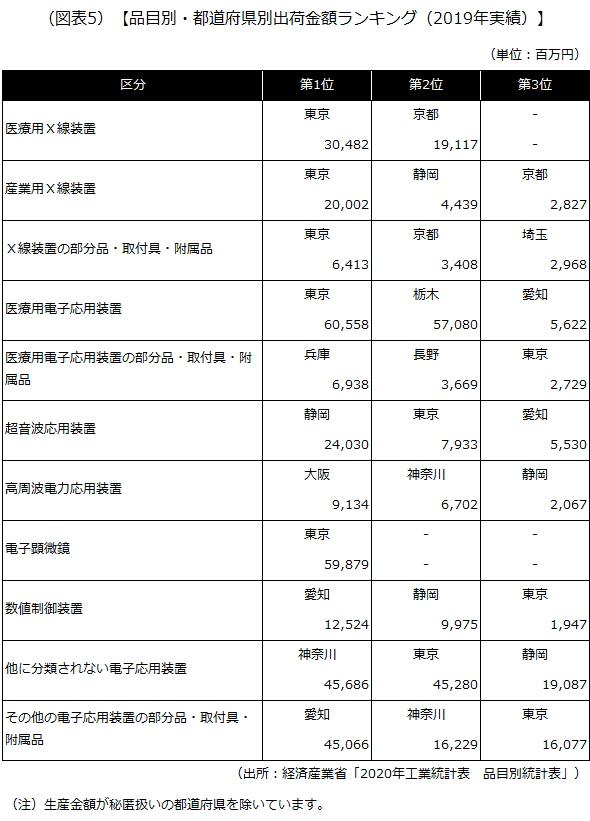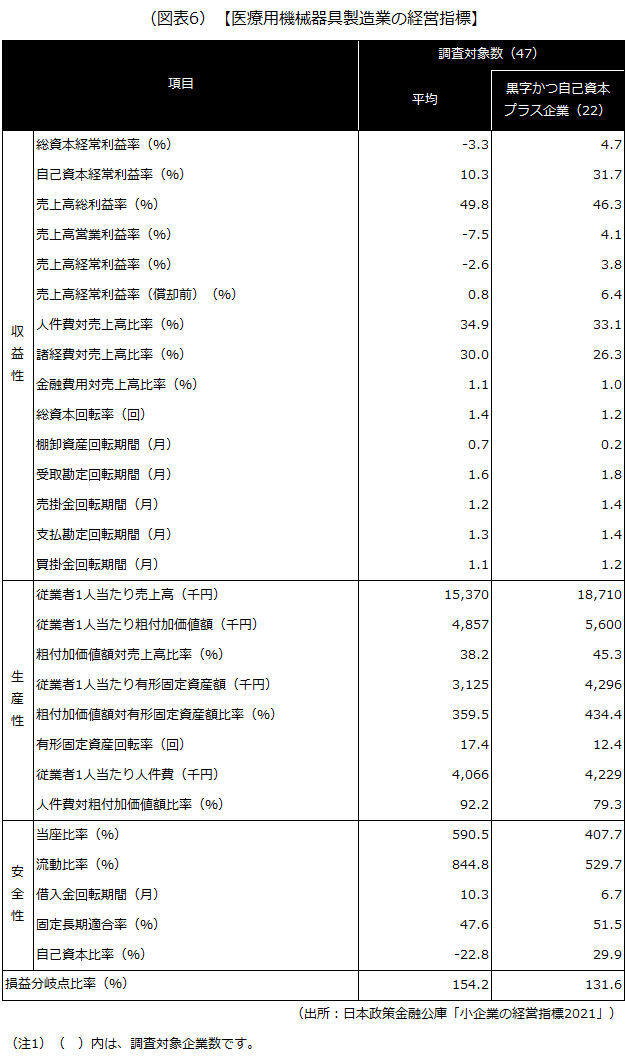書いてあること
- 主な読者:現在・将来の自社のビジネスガバナンスを考えるためのヒントがほしい経営者
- 課題:変化が激しい時代であり、既存のガバナンス論を学ぶだけでは、不十分
- 解決策:古代ローマ史を時系列で追い、その長い歴史との対話を通じて、現代に生かせるヒントを学ぶ
1 古典的なリーダーシップ論
リーダー、あるいはリーダーシップは、古くから研究されてきました。人類が集団を形成し、社会生活を営むようになってから今日に至るまで、私たちはずっとその答えを探しているようです。絶対的な答えは存在しませんが、先人たちが考察してきたリーダーシップ論は、私たちに豊かな示唆を与えてくれます。ごく簡単にですが、リーダーシップ論の変遷をたどってみます。
いわゆるリーダーシップ論は、1900年代頃から活発に議論されるようになりました。近代産業の発展、軍隊の強大化などが背景にあります。最も古典的な考え方は「特性理論」で、リーダーは生まれながらの特性(性格や資質)によってリーダーシップを発揮していると捉えます。この理論は、優秀なリーダーを分析しても同じ特性ではないため、理論として不十分とされましたが、実際に、優れた経営者などを見ると、生まれながらの何かがあるようにも感じられます。
これに続き、1940~60年代に注目されたのは「行動理論」です。これは、リーダーシップは行動によって発揮されると考え、優れたリーダーの行動を類型化し、それを模倣することでリーダーを育成する理論です。「行動理論」に属する代表的な考え方としては、“人への関心”と“生産への関心”という2軸で捉える「マネジリアル・グリッド」や、“課題達成機能(Performance)”と“人間関係・集団維持機能(Maintenance)”という2軸で捉える「PM理論」などがあり、汎用的であるため、現在でも使われています。ただし、行動を模倣するだけでリーダーシップが身に付くわけではないという批判もありました。確かに、行動の模倣だけでは不十分ですが、優れたリーダーの行動軸を捉え、自分に取り入れることは有益でしょう。
2 現在のリーダーシップ論
1960~80年代には「条件適合理論」が提唱されました。これは、外部・内部環境などの条件によって有効なリーダーシップは異なると考え、それらの諸条件に適したリーダーシップに変化させるという理論です。代表的な考え方としては、リーダーの行動を分類し、“環境要因”と“部下の要因”によって、適したリーダーシップは変化すると説いた「パス・ゴール理論」、“リーダーとメンバーとの関係”“仕事の構造化度合い”“自分の地位とパワー”という業務の特徴とリーダーのタイプを組み合わせてリーダーシップを見極める「LPC理論」などがあります。
この「条件適合理論」が発展し、80年代以降、「コンセプト理論」という形で整理されています。「コンセプト理論」は、集団組織やビジネス環境に応じて起こるさまざまなパターンに対して取るべきリーダーシップを整理します。「変革型リーダーシップ」「サーバント・リーダーシップ」などのように、パターンごとにリーダーシップを描いた考え方になっています。
このように、どの時代のリーダーシップ論も、リーダー像を考える上での示唆を含んでいます。そして、「条件適合理論」や「コンセプト理論」に見られるように、結局のところ、リーダーシップとそれを取り巻くさまざまな歯車がうまくかみ合うことが重要であり、それによって、良い結果が生まれ、良い状態が維持されるのです。
3 五賢帝時代の始まり
さて、ローマ史においては、平和と繁栄を謳歌した最盛期といえる時代がありました。5人の皇帝による治世下であったため、「五賢帝時代」と呼ばれています。
前回、カリグラ以降の混乱期をご紹介しましたが、その混乱は、ヴェスパシアヌスが皇帝に就き、一時的に回復されました。しかし、その後を継いだ長男ティトゥスは2年で病死し、経験に乏しい次男ドミティアヌスが皇帝に就きます。ドミティアヌスは、ゲルマニア防壁の建設着手などの功績もありますが、元老院の反皇帝派を強硬に排除したことから元老院との激しい対立を生みました。最後は、執事の解放奴隷に暗殺され、元老院によって「記録抹殺刑」に処されます。これは、存在しなかったものとして、すべての痕跡を抹消するという処罰です。こうしたことにより、元老院派階級の歴史家が残した否定的評価のみが現在まで伝えられています。
ドミティアヌス暗殺後、元老院は早々にネルヴァを皇帝とします。このネルヴァから始まる5人の皇帝の時代が「五賢帝時代」といわれるわけですが、皇帝に即位したとき、ネルヴァはすでに高齢で、15カ月で病没します。高齢で子供もいなかったため、当初から臨時的につなぐための皇帝と考えられており、本人もそれを自覚していたのでしょう。皇帝というよりも調整役といった形で、元老院、市民、軍からの支持を集めるべく奔走し、早々にトラヤヌスを養子にして後継者に指名しました。ネルヴァは、皇帝としては不適格と評価され、五賢帝とされる理由は「トラヤヌスを後継者に選んだ一事のみ」などといわれていますが、ドミティアヌスが暗殺され、一呼吸が必要であった状況下において、ネルヴァのような穏健な調整役のリーダーがうまくかみ合い、安定した状況を次につないだのではないか、と思います。
4 五賢帝時代の全盛期
ネルヴァ没後、トラヤヌスが皇帝に即位します。それまでイタリア本土出身者の最上流貴族しか皇帝に選ばれたことがなかったのですが、トラヤヌスは、初めての属州出身皇帝でした。トラヤヌスは、ダキア戦争とパルティア戦争で功績を上げ、ローマ帝国の版図を史上最大にした他、内政にも努め、帝国全域で公共施設の強化・整備を図りました。真面目に皇帝という役割を務め、演じ、後世に残る功績を数多く打ち立てました。
通常、皇帝というものは、必ず批判的な意見や論評がありますが、トラヤヌスについては、同時代においても後世においても、また、能力も実績も人柄も称賛されており、非の打ちどころがありません。これは、トラヤヌスが優れた特性を持ち、リーダーとしてバランスよく行動したことに加え、元老院、市民、軍を含む国内外のあらゆる状況とそれらを構成する要素が、トラヤヌスというリーダーを中心に、見事にかみ合った結果です。これは意図して成せるものではないと思いますが、リーダーとしての理想的な形といえるでしょう。
トラヤヌスの施政で惜しまれることといえば、パルティアを完全に併呑できぬまま、病没したことでしょう。トラヤヌスには子供がなく、ハドリアヌスを後継者に指名したことになっています。歴史上、疑わしいとされていますが、円滑に皇位は継承されました。ハドリアヌスは、トラヤヌスがパルティア戦争によって属州としたメソポタミア、アッシリア、アルメニアを放棄して戦争を収束させ、東方の国境の安定化を図りました。そして、トラヤヌスの重臣たちを粛清しました。
こうしたことから、元老院とは緊張関係となり、市民からも信頼を失うのですが、税制の公正な実施、社会福祉への取り組みなどを大胆に実行し、市民からの人気を回復させます。そして、皇帝が不在でも完璧に機能するよう内閣組織を固めた上で、ハドリアヌスは、長期の視察巡行の旅に出ます。当時、皇帝が首都を離れる旅は軍事目的が多く、具体的な実務目的を持たない旅など、元老院や市民から反発を招くことでしたが、ハドリアヌスは、二度にわたって長期の視察巡行の旅に出かけ、在位21年中7年しか本国に滞在していません。それが許されるだけの市民からの人気と盤石な内閣組織を備えていました。そうまでしてハドリアヌスが望んだ旅の目的は、各地の巡察、防衛の再整備、行政の調整、統合の象徴としての皇帝の周知にあり、建設分野の一団も引き連れ、各地で公共工事も行いました。こうした長期の旅がありながらも、官僚制度の確立、法制度の整備、ユダヤ反乱の鎮圧など数多くの実績を残しています。
ハドリアヌスは、複雑な性格だったようですが、極めて現実的で、実績重視のリーダーでした。市民への人気取り政策もありましたが、それは手段に過ぎず、なすべきことを確実に遂行しました。長期の視察巡行の旅や文化面での功績などは、この時代の情勢なればこそですが、それも含め、ハドリアヌスのリーダーシップがうまくハマっていたのでしょう。
ハドリアヌスが亡くなると、養子のアントニヌスが即位したのですが、ハドリアヌスと緊張関係が続いた元老院は、「記録抹殺刑」の前段階ともいうべき、先帝ハドリアヌスの神格化を拒否する動議を提出しました。これに対し、アントニヌスは、元老院議員たちに先帝の神格化を粘り強く求め、元老院側が根負けした形で認められました。こうしたアントニヌスの行為から「敬虔なる者」を意味するピウスという称号がつけられ、「アントニヌス・ピウス」と呼ばれています。
アントニヌス・ピウスは「歴史のない皇帝」といわれていますが、これは23年間という長い治世の中で、目立った出来事がないためです。無策や怠慢のように思われがちですが、目立った事件や戦争などが起きていないということは、安定的に運営していたともいえます。アントニヌス・ピウスは何もしなかったわけではなく、新しいことはしなかった。それこそが自分の責務であると考えて行動したのです。
人事や安全保障などは先帝の方向性を継承し、紛争は外交で解決、大規模な公共事業は行わず、自費を投じて財政の立て直しを図り、健全な治世で国家資産を増やしました。アントニヌス・ピウスが亡くなるときには、帝国の国庫は、初代アウグストゥス以来の最高額になったといわれています。
5 リーダーの条件
平和と繁栄が続いた五賢帝時代の中でも、全盛期といえるトラヤヌス、ハドリアヌス、アントニヌス・ピウスの3人をごく簡単にご紹介しましたが、いかがでしたか。私の個人的な見解ですが、トラヤヌスからは「成長」「けん引」、ハドリアヌスからは「転換」「改革」、アントニヌス・ピウスからは「静観」「定着」といった言葉が連想されます。それぞれ全盛期を支えた優れたリーダーですが、性格や考え方も、行動や振る舞いも異なります。この全盛期を眺めてみると、3人の順序も含め、あらゆる要素がうまくかみ合っていたということがよく分かります。現在、「条件適合理論」や「コンセプト理論」を軸にリーダーシップ論が議論されていることもうなずけます。
ご紹介したリーダーシップ論から遡ること400年ほど、ルネサンス期の政治思想家マキャヴェッリは、リーダーにとって不可欠な3条件として、「力量」「好運」「時代への適合性」を掲げています。これもまた納得できます。マキャヴェッリは、古典から学んだ歴史上の人物をもとに思考したわけですが、ローマ史のみならず、歴史には多くのリーダー像のサンプルがあります。それらから学び、自分なりの形を見つけ、追究していくことがリーダーシップの第一歩かもしれません。
以上(2021年10月)
(執筆 辻大志)
op90059
画像:unsplash